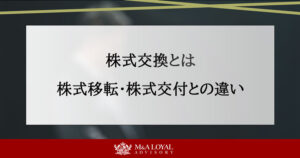株式交換で株価は上がる?下がる?影響をM&Aの専門家が詳しく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
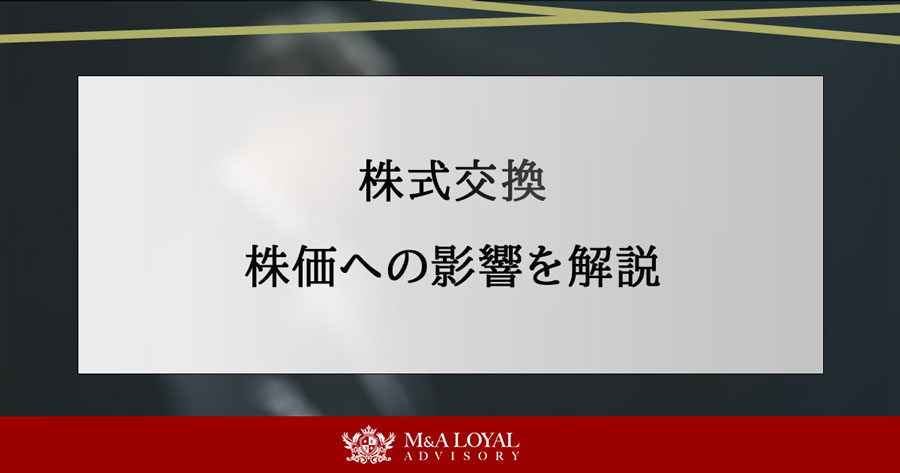
株式交換は、M&Aの手法として広く用いられており、親会社・子会社双方の株価に大きな影響を及ぼす場合があります。 特に株式交換比率や上場廃止の有無、業績連動型の評価などは、投資家や既存株主にとって重要な関心事です。
本記事では、株式交換が株価に与える影響を詳しく解説し、その変動理由やリスク回避の方法、株主が取るべき対応策、さらに株価変動が注目された国内M&A事例までを網羅的に紹介します。
目次
株式交換と株価の関係
まず、株式交換と株価に関する基本的な知識について解説します。
株式交換が行われたM&Aへの評価で株価が変動する
株式交換は、親会社が子会社の全株式を取得し、代わりに自社株式を交付するM&Aの手法の一つです。株式交換の実施が発表されると、親会社と子会社それぞれの株価に影響が生じます。
市場はこの株式交換を「どのような企業戦略か」「どの程度の相乗効果があるか」といった観点から評価し、将来の業績への期待や不安を織り込んで株価が変動します。
特に、発表直後から効力発生日にかけては、投資家の思惑により株価が上下する場面が多く見られます。
株価が上がる場合
株式交換の発表に伴う株価の上昇は、投資家が「将来の業績改善」や「企業価値の向上」に期待することに起因します。株価の上昇は投資家の将来期待に支えられており、その期待の大きさに比例して上昇幅も広がる傾向にあります。
特に、親会社が業界内で高いブランド力や財務安定性を持つ企業であれば、その子会社となる企業の株価は上昇しやすい傾向にあります。これは、グループ内での資源共有や経営効率の向上が見込まれ、事業の成長が加速すると予想されるためです。
なお、株式交換の際には交換比率も重要な評価軸となり、子会社の株主にとって有利な条件であれば株価はさらに上昇する可能性があります。親会社と子会社が共に優良企業であれば、市場全体の期待感が高まり、両社の株価が上昇するケースも見られます。
株価が下がる場合
株価が株式交換によって下落する背景には、将来の業績悪化やシナジー効果への疑念があります。市場全体の評価が否定的であるほど、下落幅も大きくなりやすいです。
特に、親会社が財務的に不安定な企業や赤字企業を子会社化するようなケースでは、買収リスクが意識され、親会社の株価が下落しやすいです。
また、株式交換の条件が株主にとって不利だと判断された場合も、売りが先行して株価が下がる傾向にあります。実務的には、株式交換の発表直後に株価が一時的に下がり、効力発生日が近づくにつれて落ち着くという動きも一般的です。
とりわけ子会社側では、親会社との統合によって独自性が失われるとの見方や、業績への不安が強まることにより、株価の下落が見られることもあります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式交換とは
株式交換に関する基本的な知識について解説します。
株式の交換による子会社化のこと
株式交換とは、ある企業が他の企業を完全子会社化する際に、その対価として自社株式を割り当てるM&A手法の一つです。持株会社体制の構築や事業承継、資本関係の明確化などを目的に実施されるケースが多いです。
1999年の商法改正で導入され、M&Aにおける柔軟な統合手段として活用されています。
親会社となる企業は、対象会社の株主に対して一定の交換比率で自社株式を交付し、対象会社の全株式を取得することで100%支配を実現します。このとき、現金ではなく株式を用いるため、資金を用意せずに再編が可能です。
加えて、三角株式交換という形式では、直接の親会社ではなくその上位企業の株式を対価として用いることも認められています。
株式交換のメリット
株式交換の主なメリットとして以下が挙げられます。
買収資金が不要で実行しやすい
株式交換では、現金ではなく自社の新株や自己株式を対価として用いるため、買収資金を別途用意する必要がありません。
資金に制約がある企業でも、財務負担を増やさずにM&Aを実施できる点は大きな利点です。特に、借り入れによる買収を避けたい企業にとって、有効な選択肢といえます。
法人格を維持したまま統合できる
株式交換では子会社側の法人格が消滅せず存続するため、急激な組織再編を避け、段階的かつ柔軟な経営統合が可能です。
従業員や取引先の反発も起きにくく、統合による混乱を抑えながらシナジーを追求できます。統合プロセスを円滑に進めたい場合に適しています。
少数株主の反対があっても実施できる
株式交換は、譲渡企業の株主総会において特別決議(出席株主の3分の2以上の賛成)を得れば実行できます。そのため、一定数の反対株主がいても、法定要件を満たせば手続きは進行可能です。
反対株主には株式買取請求権が認められますが、これによって実施自体を妨げることはできません。
譲渡企業が親会社経営に参画できる
株式交換により、譲渡企業の株主は親会社の株式を受け取り、そのまま親会社の株主となります。これにより、譲渡企業側も親会社の経営に一定の影響を有し、統合後の成長や配当などの恩恵を受けやすいとされています。
株式交換のデメリット・リスク
株式交換にはデメリットも存在します。デメリットとリスクを解説します。
株式の希薄化が生じる可能性がある
株式交換で新株を発行する場合、親会社の発行済株式数が増加し、既存株主の持株比率が下がる「株式の希薄化」が生じます。
これにより、1株当たりの利益や資産価値が下がり、株価の下落を招く恐れがあります。そのため、株式の希薄化による経済的損失を懸念する既存株主への配慮が必要です。
株価変動のリスクに直面する可能性がある
親会社が上場企業である場合、株式交換によってその株式を保有することになる子会社側の株主は、市場変動の影響を直接受けやすいです。
株価が下落した場合、保有資産の評価額も下がるため、リスク耐性の低い投資家にとっては不安要素となり得ます。
株主構成の変化による影響を受ける
株式交換により、親会社の株式を子会社の株主が新たに保有することになるため、親会社の株主構成が変化します。新たな株主が議決権を持つことになれば、経営方針に影響を及ぼす可能性があります。
経営の安定性を保つためには、発行株数や議決権割合の調整が重要です。
他の株式取得の手法との違い
株式交換と他の手法の違いを解説します。
株式譲渡
株式譲渡とは、既存の株主が保有する株式を第三者に売却することで、経営権を移転させるM&A手法です。会社の法人格を維持したまま事業を承継できる点が特徴で、手続きも比較的簡便なため、中小企業のM&Aで広く用いられています。
従業員や取引先への影響が比較的小さいことから、後継者がいない企業にとって円滑な事業承継の手段といえます。対価として現金が支払われるケースが多く、引退する経営者にとっては老後資金の確保にもつながります。
ただし、買収後は簿外債務や偶発債務といったリスクを買い手が引き継ぐ可能性があるため、事前の調査(デューデリジェンス)が重要です。
株式移転
株式移転は、新設する持株会社に自己株式を取得させ、親子関係を形成する再編手法です。1社による単独株式移転と、2社以上による共同株式移転に分かれ、グループ再編や統合に活用されます。
株式交換と似ていますが、親会社が新設会社か既存会社かが異なります。株式移転は親会社が新設される点が特徴で、組織再編やグループ体制構築に適しています。
株式交付
株式交付は、自社株を対価として他社株式を取得し、子会社化を図る手法です。2021年の法改正で導入され、柔軟な資本参加を可能とするM&A手段として注目されています。
株式交換と異なり、100%子会社化を前提とせず、少数持分の取得にも対応します。そのため、段階的な支配権取得に適しています。なお、国内の株式会社が対象で、合同会社や清算中の会社、既存子会社は対象外です。
株式交換が株価に影響を与える理由
株式交換が株価に影響を与える理由として、次の点が挙げられます。
- 株式交換によって上場廃止が起きるため
- 親会社となる買収企業の業績が影響するため
- プレミアムを反映した株式交換比率が設定されるため
それぞれを詳しく解説します。
株式交換によって上場廃止が起きるため
株式交換によって完全子会社化が行われると、対象会社(売り手企業)は上場廃止となります。これにより、その株主は自社株を手放し、対価として買収企業(買い手企業)の株式を受け取ります。
この交換比率である「株式交換比率」が市場での評価と大きく乖離(かいり)していると、株価に影響を与える一因となり得ます。
例えば、買い手企業が高すぎる株式交換比率を設定して自社株を多く交付すれば、希薄化懸念から買い手企業の株価が下落する可能性があります。一方、売り手企業の株主にとっては、受け取る株式の価値が高まることになり、交換比率の公表後に株価が上昇する動きが見られることもあります。
親会社となる買収企業の業績が影響するため
株式交換においては、買収側である親会社の業績や企業イメージが、直接的に市場の評価へ影響を与えます。特に、親会社が上場企業である場合、子会社となる企業の株主は親会社の株式を保有することになり、その業績が株主価値に直結します。
親会社の収益性や成長性に対する期待が高ければ、株式交換によってポジティブな相乗効果が見込まれ、株価は上昇しやすいです。一方で、親会社の業績が低迷していたり、過去に赤字を出していたりする場合は、統合後の経営リスクを懸念して株価が下落する可能性があります。
また、ブランド力や業界内のポジションも市場の評価に影響を与える重要な要素です。
プレミアムを反映した株式交換比率が設定されるため
株式交換に際しては、譲渡企業の株主に対し、市場価格よりも高い価値を認めた「プレミアム」を加味した株式交換比率が設定されることが一般的です。
このプレミアムは、譲渡企業の既存株主に対して譲渡を促すための経済的誘因であり、企業価値に対する評価を上乗せする形で反映されます。そのため、株式交換の発表後は、売り手企業の株価がプレミアムを反映して上昇する傾向があります。
一方で、買い手企業は多くの新株を発行することで株式の希薄化が進み、既存株主の持分価値が低下する可能性があるため、株価が一時的に下落する場合もあります。
株式交換比率と株価の関係
株式交換比率と株価の関係について解説します。
株式交換比率と株価との関連性
株式交換比率とは、売り手企業の株式1株に対して、買い手企業が何株の自社株を交付するかを示す比率です。この比率は、株式交換における対価の公平性や、親会社・子会社双方の株価に直接影響を与える重要な指標です。
例えば、1:0.6という交換比率であれば、売り手企業の株主は1株に対し0.6株の買い手企業の株式を受け取ります。比率が高く設定されれば、買い手企業の新株発行数が増加し、株式の希薄化を通じて株価が下落する可能性があります。
一方で、比率が低ければ、売り手側の株主にとって対価が少ないと受け止められ、株価が下がることもあります。
株式交換比率を算出する方法
株式交換比率の算定には、両社の株価や企業価値の正確な評価が不可欠です。
上場企業同士であれば、市場株価を基に買い手企業の株価を売り手企業の株価で割ることで、交換比率の目安を算出できます。一方、非上場企業が含まれる場合は、第三者機関による株価算定が必要です。
主な評価手法には、コストアプローチとインカムアプローチ、マーケットアプローチの三つがあります。多くの場合、これら複数の手法を併用して企業価値を客観的に評価し、算定結果に基づいて当事会社間で交渉を行い、最終的な比率が決定されます。
コストアプローチ
コストアプローチは、企業の帳簿上の資産と負債に基づいて純資産価値を算出し、それを株式価値とみなす評価手法です。
将来の収益力を評価に反映しないため、安定企業や清算価値の把握を目的とする場面に適していますが、成長性を評価しにくいという限界もあります。
代表的な方法に簿価純資産法があり、貸借対照表上の資産から負債を差し引いた金額をそのまま株式価値とします。また、時価純資産法では、資産・負債を市場価値に評価替えし、より実態に近い数値を算出します。
インカムアプローチ
インカムアプローチは、企業が将来にわたって生み出すキャッシュフローに着目し、それを現在価値に割り引いて企業価値を算出する方法です。
ただし、キャッシュフロー予測や割引率の設定に不確実性があるため、前提条件次第で結果が大きく変わるリスクもあります。そのため、精緻な事業計画が求められる手法です。
代表的な方法はDCF(Discounted Cash Flow)法で、将来のフリーキャッシュフローを予測し、一定の割引率を使って現在の価値を算出します。この手法は企業の将来性を反映できるため、成長企業の評価に適しています。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、株式市場やM&A市場における取引事例を基に企業価値を評価する手法です。客観的で市場実勢を反映できる点が長所ですが、非上場企業や類似対象が少ない場合には適用が難しいという短所があります。
上場企業の場合は市場株価法を用いることが一般的で、過去1〜3カ月の終値平均などを活用して株価を算定します。また、類似企業比較法では、業種や規模の近い上場企業のPERやPBRといった財務指標を基に株価を推定します。さらに、過去のM&A取引における価格情報を参考にする類似取引比較法も用いられることがあります。
株式交換契約締結後の株価変動リスクを抑える方法
株式交換では、契約締結から効力発生までに一定の期間があり、その間に株価が変動するリスクがあります。
これを抑えるため、「固定比率方式」と「変動比率方式」という二つの交換比率の設定方法が活用されています。
固定比率方式
固定比率方式とは、株式交換契約の締結時点で交換比率を確定させ、その後の株価変動にかかわらず同じ比率を維持する方式です。比較的価格変動リスクの低い局面で採用される傾向にあります。
この方式を用いることで、買収企業は株式の交付数を事前に把握できるため、発行済株式の希薄化割合を計算しやすいです。また、株式交換による資本構成の変動リスクを一定に保てる点がメリットです。
一方で、契約締結後に親会社の株価が大きく変動した場合には、経済的損失や不均衡が生じる可能性があります。例えば、親会社の株価が急騰した場合、売り手企業の株主に対して高価な株式を交付することとなり、親会社側に不利となる恐れがあります。
変動比率方式
変動比率方式は、株式交換契約締結時に売り手企業(完全子会社)の株価を固定し、と買い手企業(完全親会社)の株価変動に応じて交換比率を調整する方式です。株価の変動幅が大きい局面で選択されることが多いです。
この方式では、売り手企業の株主が受け取る対価の経済的価値が一定に保たれるため、株価変動による不利益を回避できる点が大きなメリットです。特に、契約締結から株式交換の効力発生日までに期間が空く場合には、株価の変動リスクが高まるため、売り手企業にとって有効な選択肢です。
また、買い手企業にとっても、株価が上昇すれば交付株数が減少し、株式の希薄化抑制が可能です。ただし、実行時まで交換比率が確定しないため、将来の資本構成やのれんの計上額が見通しにくいというデメリットもあります。
株式交換発表後における個人株主の注意点
株式交換発表後における個人株主の注意点として、次の点が挙げられます。
- 単元未満株式や端数株式が生じる可能性がある
- 株価の変動リスクに備える
- 新しい株式への交換時期を確認する
それぞれを分かりやすく解説します。
単元未満株式や端数株式が生じる可能性がある
株式交換が行われる際、設定された交換比率によっては、個人株主が保有する株式が「単元未満株式」になる可能性があります。
単元未満株式とは、証券取引所が定める最低売買単位(通常は100株)に満たない株式のことで、市場での自由な売却ができず、株主総会での議決権も制限されるという特徴があります。
これに対しては、会社に株式の買い取りを請求する「買取請求」や、不足分を購入して単元化する「買増制度」によって対応することが一般的です。
また、「端数株式(1株にも満たない端数)」については、会社がまとめて売却・換金し、相当額を株主に交付する対応が行われます。
株価の変動リスクに備える
株式交換が発表されると、当事会社の株価は短期間で大きく変動するリスクがあります。特に発表直後や、子会社の上場廃止日が近づくタイミングでは、相場の思惑や期待・懸念が交錯し、売買が活発化する傾向があります。
例えば、統合による相乗効果が期待される場合には買いが集中し株価が上昇する一方、経営リスクや交換比率の不公平感があれば売りが先行して株価が下落する可能性もあります。
こうした変動を見越して、適切な売却や保有判断を下す必要があります。特に短期的な値動きに対して敏感な投資戦略を取っている個人株主は、交換実効日や上場廃止日、企業発表などのスケジュールを把握し、株価の急変に備えておくことが重要です。
新しい株式への交換時期を確認する
株式交換が発表された後、実際に株式が交換されるタイミングには注意が必要です。
株式交換には「契約締結日」「株式の最終売買日」「効力発生日」など複数の重要な日程が存在しますが、株主の保有株は、効力発生日以降に親会社株式へと置き換わります。
場合によっては、株式交換の実施によって株価が不利に動くと予測されることもあるため、最終売買日前に売却を検討する判断も求められます。
特に非上場化により上場廃止が予定されている場合には、売買機会を逃すと換金性が著しく低下する恐れがあります。
個人株主が株式交換に反対して株価を守る方法
個人株主が株式交換に反対して株価を守る方法は次のとおりです。
- 株主総会の特別決議において株式交換を否決する
- 株式交換無効の訴えを起こす
- 株式交換の差止請求をする
- 簡易株式交換による親会社側での株主総会の承認を省略させない
それぞれについて解説します。
株主総会の特別決議において株式交換を否決する
株式交換には、株主総会における特別決議が必要です。議決権を行使できる株主の過半数が出席し、そのうち3分の2以上の賛成がなければ承認されません。
反対株主が一定の議決権を持っていれば、賛成票が要件を満たさず、株式交換を否決できます。
株式交換無効の訴えを起こす
株式交換に重大な違法や手続き上の瑕疵がある場合、効力発生日から6カ月以内に株主などが「株式交換無効の訴え」を提起できます。対象者には、当該契約時の株主や承認を拒んだ債権者などが含まれます。
なお、無効が認められた場合、その判決は第三者にも効力を持つこともあり、広範囲に影響を及ぼします。
株式交換の差止請求をする
完全親会社が特別支配会社である場合、株式交換が法令や定款に違反していたり、条件が著しく不当で株主に不利益が生じる恐れがあるときは、少数株主が差止請求できます。
ただし、差止めの対象は通常、手続き前の段階に限られ、特定の行為を停止させるためには裁判所による判断が必要です。この手段は、不当な行為や損害を未然に防ぐために用いられます。
簡易株式交換による親会社側での株主総会の承認を省略させない
株式交換においては、子会社への対価が親会社の純資産の5分の1以下である場合、「簡易株式交換」として親会社側の株主総会を省略できます。
しかし、この省略には例外があります。親会社の株主のうち、議決権の6分の1以上を保有する者が異議を申し立てた場合、株主総会を開催する必要が生じます。
この制度により、一定数の反対株主がいれば、株主総会の省略を阻止し、株主総会の場で議案に対して意見を表明できます。
株式交換を用いた株価引き下げによる事業承継対策
事業承継においては、自社株の相続や贈与により、相続税や贈与税といった大きな税負担が発生する可能性があります。特に、株価の高い優良企業では、その税額が多額になるため税務戦略において株価の変動を考慮することが大切です。
株価の引き下げ方法には複数ありますが、その一つが株式交換を活用する方法です。株式交換を適切に設計すれば、課税対象となる自社株の評価額を低く抑えられ、円滑かつ負担の少ない事業承継が可能です。
株式交換を用いた株価引き下げにおける主なポイントは次のとおりです。
- 新株の発行
- 規模の大きい会社を親会社にする
それぞれについて解説します。
新株の発行
株式交換では、親会社が子会社の株主に対して株式を交付する必要があるため、新たに株式を発行することが一般的です。
新株の発行によって親会社の発行済株式総数は増加し、既存株主の持分割合が下がる「株式の希薄化」が生じます。これによって1株当たりの利益や純資産価値が薄まり、株価が下落することが多いです。
特に、株価の低い企業が株価の高い企業を株式交換で取得する場合、発行する株式数が多くなるため、親会社の株式評価額が下がると考えられがちです。ただし、株式交換後は親会社と子会社が経済的に一体とみなされるため、単純に自己株評価が下がるとは限りません。
実際の評価にあたっては、資産内容や将来収益性など複数の要素が加味されるため、事前に税理士やM&Aの専門家に相談することが重要です。
規模の大きい会社を親会社にする
非上場企業の株価評価では、会社の規模に応じて評価方法が異なります。中小企業では「純資産価額方式」が基本ですが、企業規模が大きくなるほど「類似業種比準方式」の比重が高いです。
類似業種比準方式では、業界平均の指標を基に評価が行われるため、一般的に株価が抑えられる傾向にあります。そのため、事業承継においては、評価額を引き下げやすい大規模企業を親会社とする株式交換が有効な対策です。
会社区分ごとに評価方法の配分率が異なるため、より大きな会社を親会社とするほど、低めの株価評価につながりやすいです。
株式交換によって株価が変動した国内事例5選
株式交換によって株価が変動した国内事例をいくつか紹介します。
出光興産と昭和シェル石油
2019年4月、出光興産は昭和シェル石油を完全子会社化するため、株式交換を実施しました。交換比率は出光興産:昭和シェル石油=1:0.41と定められ、昭和シェルの株主に対して出光興産株が交付されました。これにより、出光興産は昭和シェルの全株式を取得しています。
出光興産の株価は、2018年10月の株式交換実施の発表当日には5,740円をつけたものの、その後は下落傾向が続き、2019年4月の効力発生日は3,795円にまで下がりました。
一方、昭和シェル石油は、発表当日に2,378円、翌日は2,390円とやや上昇しましたが、その後は下落に転じ、最低で1,413円を記録し、取引最終日には1,682円で取引を終えました。
メルカリとマイケル
2018年、メルカリは自動車関連SNSサービスを運営するマイケル株式会社を完全子会社化するため、簡易株式交換を実施しました。
交換比率はメルカリ:マイケル = 1:194.83と設定されており、メルカリはマイケルの全発行株式を取得し、マイケル株主に対して1株当たり194.83株のメルカリ株を交付しました。なお、マイケルは非上場企業であったため、上場廃止の手続きは不要でした。
メルカリの株価は、株式交換を発表した当日に3,150円をつけましたが、翌日には3,115円へ下落しました。その後も下げ基調が続き、一時は2,685円まで下がりました。株式交換の効力発生日には2,996円となり、発表時よりも低い水準での推移となりました。
一方、マイケルは非上場であったため、株価の推移は確認されていません。
参考:メルカリ、自動車関連SNS「CARTUNE」を運営するマイケルを11月8日付で完全子会社化へ
日清紡HDと新日本無線
2018年、日清紡ホールディングスは新日本無線を完全子会社化するため、簡易株式交換を実施しました。
交換比率は日清紡:新日本無線 = 1:0.65と定められ、新日本無線の株主には、この比率に基づいて日清紡の株式が交付されました。新日本無線は交換の効力発生日に先立ち、上場を廃止しています。また、単元未満株式が生じることが予想されたため、新日本無線の株主には、買取や1単元までの買増制度が用意されました。
株価の動きとしては、日清紡は発表前に1,595円でしたが、発表当日には1,478円に下落し、その後1,100円台まで落ち込んだものの、効力発生日が近づくと1,200円台に回復しています。
一方、新日本無線は発表前に904円、当日に950円と上昇しましたが、その後は徐々に下落し、最終売買日は765円となりました。
参考:日清紡ホールディングス株式会社による新日本無線株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約の締結のお知らせ
セブン&アイ・ホールディングスとニッセン
2016年、セブン&アイ・ホールディングスは、ニッセンを完全子会社とする株式交換を実施しました。
この株式交換は、セブン&アイHD傘下のネットメディア会社「アイ・ネットメディア」を介して行う三角交換方式で、ニッセンの株主にはセブン&アイHDの普通株式が交付されました。ニッセンは事前に上場廃止の手続きを行い、単元未満株の買取や買増制度も用意されるなど、株主への一定の配慮も見られました。
株価の動きとしては、セブン&アイHDは発表前後に4,200円台を維持しながらも上昇傾向を示し、一時は4,840円まで上昇しましたが、効力発生日には4,441円に下落しました。
一方、ニッセンは発表前日の97円から発表当日には126円に上昇しましたが、翌日には76円に下落し、最終取引日は67円となりました。
参考:株式会社セブン&アイ・ホールディングスの完全子会社である株式会社セブン&アイ・ネットメディアの株式交換による株式会社ニッセンホールディングスの完全子会社化に関するお知らせ
トヨタ自動車とダイハツ工業
2016年、トヨタ自動車はダイハツ工業を完全子会社化するため、簡易株式交換を実施しました。交換比率はトヨタ:ダイハツ = 1:0.26とされ、トヨタはダイハツの全株式を取得し、ダイハツの株主に対して自社株54,035,654株を交付しました。これにより、ダイハツ工業は上場を廃止しています。
株価の動きとしては、トヨタ自動車は発表日に7,200円、翌日には7,339円と上昇傾向を示しましたが、その後は5,000円台前半に下落し、交換実施日が近づくと5,000円台後半に回復しています。
一方、ダイハツ工業は発表時に1,860円、翌日には1,977円へと上昇しましたが、その後は1,300円台まで下落し、最終的には1,500円前後まで回復して取引を終えました。
参考:トヨタ自動車株式会社によるダイハツ工業株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
株式交換と株価に関するQ&A
最後に、株式交換と株価に関するよくある質問とその回答を紹介します。
株式交換と株価に関する相談先はどこか
株式交換に関する相談先には、金融機関や公的機関、士業、M&A仲介会社などがあります。証券会社や投資銀行は、企業価値の算定やスキーム設計に強く、特に資金力のある企業にとって有力な助言先です。
一方、中小企業には、商工会議所など公的機関による無料相談や支援制度の活用が現実的です。また、弁護士・税理士・公認会計士といった専門家は、法務・税務・財務の視点からスキームの妥当性やリスクを精査します。
なお、M&A仲介会社は、候補先の探索から条件交渉、株式交換比率の調整までを支援し、実務を一括で任せられます。自社の規模や課題に応じて、適切な相談先を選定することが重要です。
株式交換後に確定申告は必要か
株式交換によって株式を取得した場合、通常は確定申告を行う必要はありません。
国税庁が定める「株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例」が適用され、交換で取得した株式は譲渡益が繰り延べられるため、課税対象とはならないとされています。そのため、株主にとっては確定申告を要しないケースが大半を占めます。
ただし、株式交換の結果として1株未満の端数が生じ、端数に相当する金銭が交付された場合は例外です。この場合、交付された現金部分は譲渡とみなされ、譲渡所得として申告対象となる可能性があります。
株式交換以外の事業承継対策はあるか
株式交換以外にも、株価引き下げを通じて事業承継を円滑に進める手法はいくつか存在します。
代表的な方法が、生命保険の活用と役員退職金の支給です。企業が生命保険に加入すると、その契約直後の保険評価額はゼロまたは極めて低額となることが多く、企業の純資産額が一時的に減少します。これにより株価が下がり、贈与や相続の際の税負担を軽減できます。
また、経営者に対して退職金を支払うことで、会社の利益を圧縮し、同様に株価を下げる効果も得られます。
いずれも自社株の移転を計画的に行う上で有効ですが、節税目的が過度とみなされれば税務否認リスクがあるため、税理士など専門家の助言を受けながら慎重に進める必要があります。
株式交換以外の子会社化の手段はあるか
株式交換以外にも、企業が他社を子会社化する手段はいくつか存在します。
最も一般的な手法は株式譲渡であり、既存株主から発行済株式を直接取得することで支配権を得ます。比較的簡易な手続きで実行でき、柔軟性が高いため、経営者が全株式を保有していることの多い中小企業のM&Aでよく用いられています。
もう一つの手法として第三者割当増資の引き受けがあります。対象企業が新株を発行し、買収企業がそれを引き受けることで資本参加を果たし、結果的に過半数の議決権を取得する方法です。この手法は資金調達と支配権の取得を同時に達成できる利点があります。
さらに、事業譲渡や会社分割を経て段階的に支配権を強化するケースも見られます。これらの手法は、企業の財務状況や事業承継の目的に応じて適切に選択すべきであり、実施に当たっては法務・税務の観点から十分な検討が求められます。
本記事では、株式交換と株価の関係について解説しました。M&Aや経営に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。