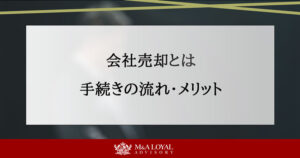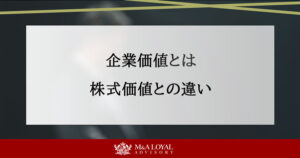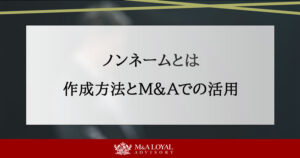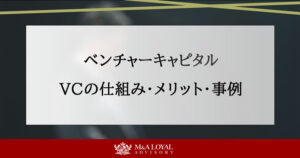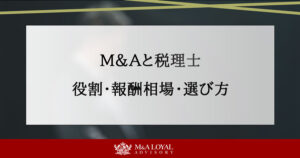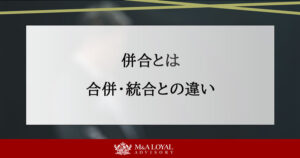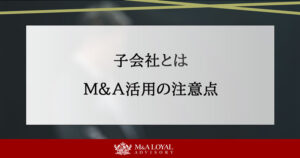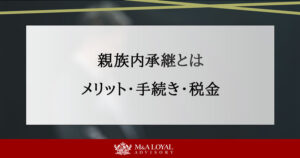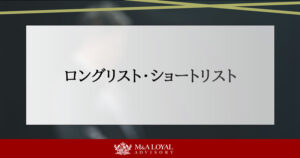株式譲渡とは?手続き・契約・税金・M&Aとの違いまでまとめて解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
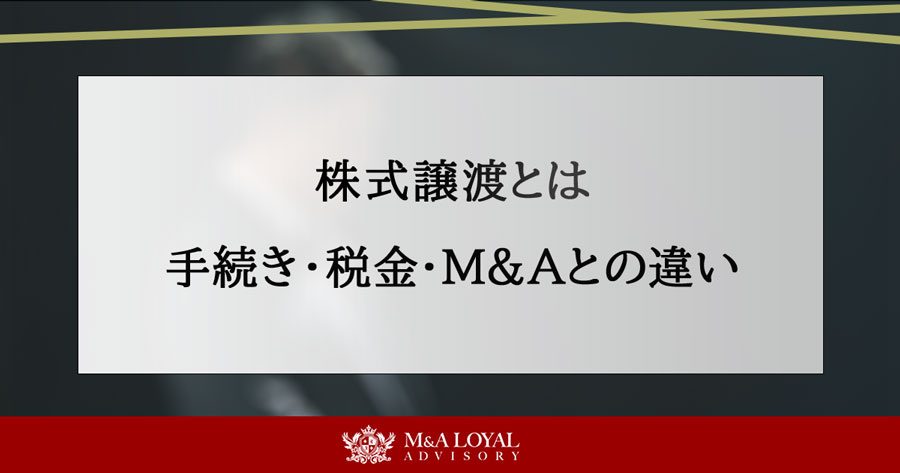
「株式譲渡」とは、会社の株式を他人に売却または譲ることで、その株主としての地位や権利を移転する行為です。特に、中小企業のM&Aや事業承継の場面では、経営権の移転手段として活用されることが多く、株式譲渡の正しい理解は経営者・後継者・投資家のいずれにとっても欠かせません。
一方で、「譲渡と売買の違いは?」「親族に渡す場合の手続きは?」「税金はどうなるのか?」など、複雑な法律・税務・手続きが絡むのも事実です。
この記事では、株式譲渡の基本から手続き、税金、契約書の注意点、M&Aや事業譲渡との違いまでを、専門的かつわかりやすく解説します。実務にも役立つ情報として、ぜひ最後までご覧ください。
目次
株式譲渡とは?
株式譲渡とは、株式会社の株主が自ら保有する株式を、他の人に移転する行為を指します。
この移転は「売買」である場合もあれば、「贈与」や「相続」などの場合もあります。いずれも、譲渡を受けた相手は新たに株主となり、議決権や配当を受け取る権利を取得します。
譲渡が成立すると、会社の支配権や経営権も含めて引き継がれることが多く、特にオーナー企業では、株式の所有によって経営権を握ることが一般的です。ただし、会社によっては株式の種類や役員の構成、契約や法律の影響で、株式を持っていても経営権を完全に確保できない場合もあります。
株式譲渡と売買の違い
「株式譲渡」と「株式売買」は混同されがちですが、厳密には意味が異なります。
株式売買は株式譲渡の一形態であり、譲渡には売買だけでなく、贈与・相続・交換なども含まれます。
- 株式譲渡:株式を他人に移すこと全般
- 株式売買:お金を対価として株式を移すこと(譲渡の一部)
ビジネスの場面では売買が多いですが、親族内承継などでは贈与や相続も関係するため、「譲渡」という広い概念を理解しておくことが重要です。
譲渡制限株式とは?
中小企業に多く見られる「譲渡制限株式」とは、会社の承認なしには自由に第三者へ譲渡できない株式のことです。
定款で譲渡制限を設けている場合、株主が誰になるかを会社がコントロールできるため、経営の安定性が確保されます。
- 取締役会の承認が必要(または株主総会の承認)
- 非公開会社では約9割が譲渡制限を設定していると言われる
譲渡制限株式を売却する場合、買い手が見つかっても「会社が承認しない限り取引が成立しない」点に注意が必要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式譲渡の手続きと流れ
株式譲渡は、「株主が変わる」という会社にとって非常に重要な出来事です。そのため、単に契約書を交わせばよいというものではなく、法律や会社の定款に基づいた適切な手続きが必要です。
特に、譲渡制限株式を扱う場合には、会社の承認が不可欠であり、段取りを誤るとトラブルや法的な無効につながる可能性もあります。
以下では、一般的な株式譲渡の手続きの流れを4つのステップで解説します。
(1)譲渡契約書の作成
最初に必要なのが、譲渡人(売主)と譲受人(買主)の間での株式譲渡契約の締結です。
この契約書には、株式の種類・株数・譲渡価格・支払方法・譲渡日などの基本事項を明記します。
さらに、トラブルを未然に防ぐために、以下のような条項も盛り込むのが一般的です。
- 表明保証(株式譲渡においては、株式が正当に譲渡可能なものであることの宣言)
- クロージング条件(支払い完了をもって譲渡成立とする等)
- 紛争時の管轄裁判所や協議条項 など
契約内容は後述の「株式譲渡契約書のポイントと注意点」で詳しく解説します。
(2)取締役会の承認(譲渡制限がある場合)
会社の定款で株式に譲渡制限が付されている場合には、株主が自由に第三者へ株式を譲渡することができません。
この場合、譲渡人は会社に対して譲渡の承認請求を行い、取締役会(もしくは株主総会)による承認を得る必要があります。
- 譲渡承認請求書を提出
- 承認された場合は手続き進行、拒否された場合は会社が自ら買い取るか、指定買取者を立てる必要がある
非上場会社の多くがこの制度を採用しており、承認プロセスが株式譲渡の成否を左右するポイントとなります。
(3)株主名簿・株券の書き換え
株式譲渡が正式に成立したら、会社に通知し、株主名簿の名義変更を行います。
名義変更が完了しなければ、法律上の株主とは認められないため、議決権の行使や配当の受け取りにも影響します。
また、株券を発行している会社であれば、株券そのものの書き換えまたは返却・再発行の手続きも必要です。
株券発行会社は減少傾向にあるものの、旧来の制度を踏襲している企業では注意が必要です。
登記の必要性はある?
株式譲渡に関しては、原則として法務局での登記手続きは不要です。登記が必要なのは、役員の変更や本店移転など会社情報が変わる場合であり、株主の変更自体は登記の対象外です。
ただし、株式譲渡が原因で代表取締役が変更になる場合などは、会社として登記変更が必要になる可能性があります。
株式譲渡とM&Aの関係
株式譲渡は、M&A(企業の合併・買収)において最も一般的に用いられる手法のひとつです。
特に、中小企業のM&Aでは「事業譲渡」よりも「株式譲渡」が選ばれるケースが多く、その理由や特徴を理解することで、適切な戦略設計が可能になります。
ここでは、M&Aにおける株式譲渡の基本的な位置づけと、よく比較される「事業譲渡」との違いについて整理します。
M&Aで株式譲渡が使われる理由
株式譲渡は、買い手側にとって会社の“権利義務をそのまま引き継ぐ”ことができる手法です。
許認可、契約、従業員、資産、負債などを個別に移す必要がなく、株主が変わるだけで企業全体をスムーズに取得できる点が最大のメリットとされています。
一方、売り手側にとっても、経営権と所有権を一括で移転できるため、リタイアや事業承継の出口戦略として有効な手段となります。
- 手続きが比較的簡易で、スピーディーなクロージングが可能
- 売買価格は企業全体の価値を基準に決まることが多い(100%譲渡だけでなく部分譲渡もある)
このように、株式譲渡は会社の所有権を売るという性質が強く、M&Aでよく使われる手法のひとつです。
事業譲渡との違い
株式譲渡と混同されやすいのが「事業譲渡」です。
事業譲渡では、会社の一部事業(資産・負債・契約など)を切り出して売却します。一方、株式譲渡は会社全体を譲る行為であり、法的にも手続き的にも大きく異なります。
| 比較項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
| 対象 | 会社そのもの | 特定の事業単位 |
| 手続き | 株主変更 | 資産・契約の個別移転が必要 |
| 従業員の地位 | 自動承継される | 同意が必要(再雇用) |
| 許認可 | 原則引き継がれる | 再取得が必要なケースあり |
| 主な活用場面 | 経営権の移転、事業承継 | 不採算事業の切り離し、新規事業獲得など |
株式譲渡は“包括承継”、事業譲渡は“個別承継”とイメージするとわかりやすいでしょう。このように、株式譲渡はM&Aの主要スキームとして、経営権を一括で移すダイナミックな方法として位置づけられています。
株式譲渡における税金と評価の考え方
株式譲渡は、会社や経営権が移るという大きなイベントである一方、税務上の取り扱いや株価評価の考え方も非常に重要なポイントになります。
特に、中小企業や親族間での譲渡では、譲渡所得税・贈与税・企業価値評価(バリュエーション)のいずれも、正しく理解しなければ後から大きな税負担やトラブルを招くリスクがあります。
以下では、株式譲渡に伴う代表的な税金と、評価額の考え方について解説します。
譲渡所得税の仕組み
株式を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税(キャピタルゲイン課税)が課されます。
これは、譲渡価格から取得費と譲渡にかかった費用を差し引いた利益に対して、原則として20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)が課税される仕組みです。
■例:
- 株式の取得価格:1,000万円
- 譲渡価格:3,000万円
- 譲渡益:2,000万円 → 課税額:約406万円
売却益が大きいほど課税額も大きくなるため、事前に売却価格と税額シミュレーションをしておくことが重要です。
親族間の株式譲渡と贈与税の注意点
親子・親族間での株式譲渡は、形式上は「売買」であっても、市場価格より著しく安い価格で譲渡した場合、“みなし贈与”とされる可能性があります。
例えば、適正な株式評価額が1株1万円であるにもかかわらず、1株100円で譲渡した場合、その差額が贈与と見なされ、贈与税の課税対象になります。
税務調査では、適正価格での取引が行われたかどうかを厳しくチェックされるため、親族間でも評価を軽視せず、適切な価格設定を心がけることが重要です。
企業価値評価(バリュエーション)との関係
株式譲渡では、企業の株式がいくらであるべきか=評価額(企業価値)を明確にしておくことが必要です。この評価は、税務対策のみならず、買い手・売り手双方にとっての納得感や交渉材料にもなります。
評価方法には以下のようなものがあります。
- DCF法(ディスカウントキャッシュフロー):将来の収益予測に基づく評価
- 類似会社比準法:上場企業との比較による相対的評価
- 純資産法:資産・負債ベースでの評価(特に小規模企業に多い)
M&Aロイヤルアドバイザリーのような専門家に依頼することで、客観的かつ実務的なバリュエーションが可能になります。
株式譲渡に伴う税金と評価は、一見すると専門的で難解に感じられますが、トラブルや過剰課税を防ぐうえで極めて重要な要素です。
株式譲渡契約書のポイントと注意点
株式譲渡を行う際には、口頭の合意ではなく、株式譲渡契約書という正式な書面を作成することが一般的です。これは、売主と買主の間で取り決めた内容を明文化することで、後日のトラブルや解釈の違いを防ぐためです。
ここでは、実務で押さえておきたい株式譲渡契約書の基本構成と、特に注意すべき項目について解説します。
基本構成と記載事項
株式譲渡契約書には、少なくとも以下の基本的な内容を含めるのが一般的です。
- 譲渡する株式の種類・数・譲渡価格
- 譲渡日および代金の支払日・支払方法
- 譲渡の条件(承認・登記・クロージング)
- 表明保証(株式の正当性、負債・債権の有無など)
- 秘密保持条項・競業避止条項(M&Aの場合など)
- 紛争解決方法(裁判所の合意管轄など)
特に、未上場株式の場合は譲渡制限や会社の承認が必要になるため、「会社承認取得済みであること」を条件にすることもあります。
表明保証条項・クロージング条件など
M&Aにおける株式譲渡契約では、「表明保証条項」や「クロージング条件」が非常に重要です。
表明保証条項とは?
売主が、「この株式は正当に取得したものであり、差押えや紛争はありません」などと表明し、違反があれば責任を負うというものです。これにより、買主はリスクを最小限に抑えられます。
クロージング条件とは?
契約締結後、株式の名義変更・代金の支払い・会社の承認取得など、一定の条件がすべて満たされたときに譲渡が正式に成立する仕組みです。これらの条件は、株式譲渡の安全性と信頼性を担保するために重要です。
弁護士や専門家に依頼すべき理由
株式譲渡契約書は一見シンプルに見えても、条文の書き方ひとつで売主・買主どちらかに大きな不利益が生じる可能性があります。
特に以下のようなケースでは、専門家への相談が推奨されます。
- 初めてのM&Aで契約リスクを理解しきれない
- 親族間や複数人で譲渡が行われる
- 譲渡後も売主が会社に関わる可能性がある
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、契約書の作成や弁護士との連携を通じて、円滑かつ安全な株式譲渡を支援しています。
このように、株式譲渡契約書は「形式上の文書」ではなく、取引の信頼性と法的安全性を支える“中核的な証拠”です。
株式譲渡のメリット・デメリット
株式譲渡は、経営権をまるごと移す強力な手段であると同時に、売主・買主それぞれにとって利点とリスクの両面を持ち合わせています。
ここでは、それぞれの立場から見たメリットとデメリットを分けて整理します。
譲渡する側(売主)にとってのメリット
■まとまった資金(キャピタルゲイン)を得られる
株式譲渡は、企業オーナーにとって資産の現金化ができる数少ない手段のひとつです。
長年経営してきた会社の価値を売却という形で実現できるため、老後の生活資金や新たな投資資金の確保にもつながります。
特にM&Aによる第三者への譲渡では、数千万円〜数億円という規模の資金が手元に残るケースも多く、“経営の出口戦略”として極めて有効です。
■経営権をスムーズに引き継げる
株式の譲渡によって、株主=経営権の移転が一括で行われるため、会社全体をスムーズに次の経営者へバトンタッチできるという点も大きな利点です。
親族内の事業承継でも、第三者M&Aでも、会社のブランドや従業員・取引先との関係性を維持したまま引き継げるため、“会社の価値そのもの”を後世に残す手段として重宝されます。
譲渡する側(売主)にとってのデメリット
■適正価格での売却が難しい場合がある
中小企業の株式は上場されていないため、市場価格という指標が存在しません。
そのため、売却価格の妥当性を自ら証明するのが難しく、安く売りすぎたり、買い手が見つからなかったりするリスクがあります。
専門家の評価なしに独断で価格を決めてしまうと、不公平な取引やトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
■譲渡所得税・贈与税などの税務リスクがある
売却で得た利益には譲渡所得税が発生しますし、特に親族間での譲渡の場合、“みなし贈与”として贈与税の対象になる可能性があります。
これらの税務判断は非常に複雑であり、事前の税理士やM&Aアドバイザーへの相談が不可欠です。
譲受け側(買主)にとってのメリット
■会社を“まるごと”取得できる
株式譲渡は、会社の経営権を一括して取得できる手法であり、資産・負債・契約・従業員・許認可などを原則そのまま引き継ぐことができます。
例えば、重要な契約や設備、人材、ノウハウが整っている企業をそのまま取得できれば、自社の成長戦略に即座に組み込むことが可能になります。
また、会社自体が維持され、許認可や契約は基本的にそのまま引き継がれるため、手続きの手間や時間が大幅に削減されるという利点もあります(ただし、業種や契約内容によっては再申請や確認が必要な場合もあり)。
■成長投資・事業拡大の即戦力となる
M&Aにおける株式譲渡は、新たな市場への進出や競合排除、既存事業とのシナジー創出といった目的において、非常に効果的な手段です。
すでに収益が上がっている企業を取得することで、ゼロから立ち上げる場合と比べてリスクも低く、スピード感のある事業成長を実現しやすくなります。
特に中小企業の承継型M&Aでは、買い手が“会社をそのまま引き受けて育てる”という意味で、長期的な経営視点が求められます。
譲受け側(買主)にとってのデメリット
■潜在的なリスクや債務も引き継ぐ
株式譲渡では、表面上は企業の状態が良好に見えていても、内部に隠れた債務や法的リスク、過去の契約トラブルなどを買主がそのまま背負うことになります。
例えば以下のようなリスクが想定されます。
- 未払い残業代や過去の労務問題
- 租税債務や訴訟リスク
- 財務諸表に記載されていない簿外債務
これらを見落とさないためには、事前のデューデリジェンス(DD)で徹底した調査を行うことが不可欠です。
■経営交代による社内外の不安
オーナー経営者からの株式譲渡によって新たな経営者が就任する場合、従業員や取引先が不安を抱き、離職や契約解消につながるリスクもあります。
特に、中小企業では創業者の存在感が強いため、「経営者が変わる=会社が変わる」と受け止められることも珍しくありません。
株式譲渡後には、従業員との信頼関係構築や、企業文化の理解を踏まえたPMI(経営統合)の設計が不可欠です。
このように、株式譲渡は買い手にとっても大きな可能性を持つ一方、見えづらいリスクも孕んでいます。
トラブルを避けるための事前準備
最も基本でありながら軽視されがちなのが、譲渡前の情報整理とステークホルダーとの調整です。
例えば、以下のような事前準備が欠かせません。
- 自社の株主構成や定款上の譲渡制限の確認
- 株主総会・取締役会での承認手続きの見通し
- 従業員・取引先・金融機関など関係者への説明タイミングの設計
譲渡のプロセスで多いトラブルのひとつが「関係者への根回し不足」です。法的手続きだけでなく、信頼関係の構築も準備の一部と考えましょう。
企業価値評価・デューデリジェンスの実施
適正な譲渡価格を設定し、買い手・売り手双方が納得して契約を結ぶためには、企業価値の正確な把握と事前調査(デューデリジェンス)が不可欠です。
- 【売り手】自社の価値を第三者の評価で裏付け、信頼性を高める
- 【買い手】リスクや債務の有無を事前に洗い出し、判断材料とする
売却益の最大化・買収後のトラブル防止、いずれにおいても、専門家による第三者評価は“交渉力”と“安全性”の両面で効果があると言われています。
専門家に相談するメリット
株式譲渡には、法務・税務・財務・契約設計といった複数分野の専門知識が求められます。
中小企業や未経験者にとっては、見えないリスクや思わぬ落とし穴が存在するため、M&Aアドバイザーや弁護士・税理士といったプロフェッショナルのサポートが不可欠です。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、以下のような支援を一貫して提供しています。
- 株式譲渡の初期診断・スキーム設計
- 株価評価レポートの作成
- 契約書作成・専門家連携・クロージング支援
「誰に・いつ・どのように譲るか」こそ、事業の未来を左右する判断です。専門家の力を借りることで、その判断をより安全で確実なものにできます。
株式譲渡の基本を理解し、戦略的に活用しよう
株式譲渡は、単に「株を売る・買う」というだけの行為ではなく、企業のオーナーシップ・経営権・将来そのものを移転する、極めて重要な意思決定です。
この記事では、株式譲渡の定義から手続き、M&Aとの関係、税金・契約の注意点、そして成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。最後に、押さえておきたい要点を振り返ります。
■本記事のまとめポイント
- 株式譲渡とは:株式会社の株主が保有する株式を他者に移転すること。支配権の移転も伴う。
- 手続きの基本:契約書の作成 → 会社の承認(必要な場合)→ 名義変更 → 登記(必要に応じて)
- M&Aでの活用:包括承継がしやすく、スピーディーな経営権移転を実現しやすい。事業譲渡との違いに注意。
- 税金と評価:譲渡所得税や贈与税のリスクあり。企業価値評価と税務対応がカギを握る。
- 契約のポイント:表明保証やクロージング条件など、リスク回避の条項を適切に設計する。
- 成功のカギ:事前準備・適正評価・専門家との連携。感情だけでなく、戦略とロジックで進めることが重要。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、オーナー経営者の想いを汲み取りながら、法務・財務・戦略面を一貫してサポートしています。
「株式譲渡を検討しているが、何から手をつけてよいかわからない」「将来の事業承継に備えて今のうちに準備を進めたい」――そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
“会社を誰に託すか”という判断は、事業の未来を決める最も大切な一歩です。専門家とともに、安心かつ戦略的な株式譲渡を実現しましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。