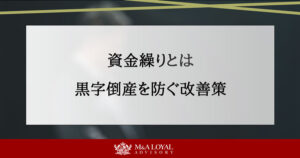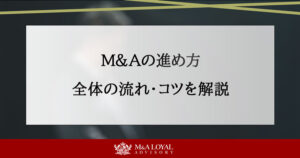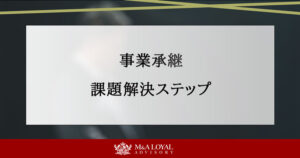スクイーズアウトとは?手法や手続きの流れ、M&Aでの活用法を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
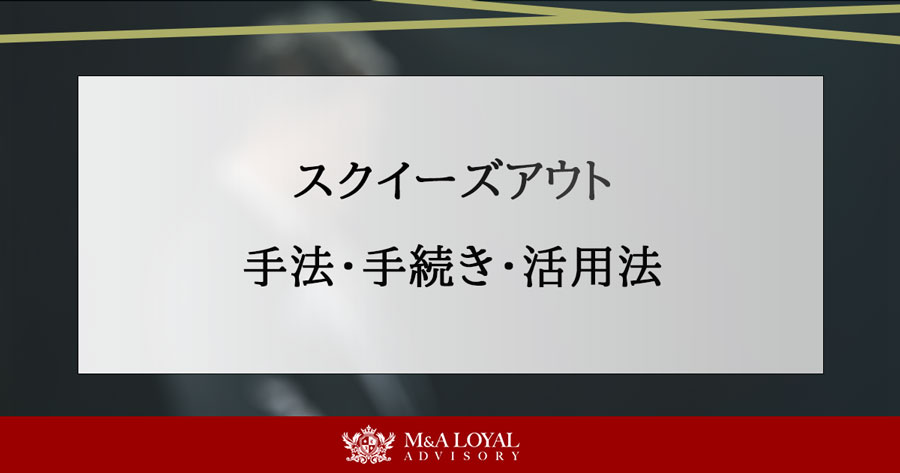
スクイーズアウトとは、支配株主が少数株主を「法的に締め出す」ことによって、株式を集中させる強力な手段です。
特に、M&Aの完全子会社化や事業承継、株主構成の再編などでその手続きが活用されています。また、近年は法制度の整備も進み、複数のスキームが利用可能となりました。
本記事では、スクイーズアウトの基本的な仕組みから、具体的な手法・手続きの流れ、活用される場面、メリット・デメリット、国内事例までを網羅的に解説します。スクイーズアウトの手続きについて、ぜひご理解ください。
目次
スクイーズアウトとは
スクイーズアウトとは、支配株主が少数株主から強制的に株式を取得し、会社から退出させる手法を指します。金銭などを対価として全株式を取得し、経営権を完全に掌握することが目的です。対象株主の同意を要しない手法も存在するため、効率的な企業再編や組織統合の場面で有効です。
M&Aや事業承継、上場廃止の準備などで用いられ、意思決定の迅速化や株主対応コストの削減といった効果が見込まれます。
また、少数株主が所在不明であったり、経営方針に反対していたりする場合でも、法律に基づいて手続きを進められます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



スクイーズアウトが実行されるケース
スクイーズアウトは、経営上のさまざまな障害を取り除く手法として活用されています。代表的なケースは次のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
M&Aによる完全子会社化や事業承継に伴う株式の整理
M&Aによって事業承継や完全子会社化を進める際、買収企業は通常100%の株式取得を目指します。少数株主の存在によって、株主総会での承認が得られない場合、取引の停滞や中止につながるリスクがあるためです。
特に、経営統合や戦略的な再編を迅速に実行したい場面では、株主構成の整理が不可欠です。こうした場面において、スクイーズアウトを通じて少数株主に現金を交付し、強制的に株式を取得することで、経営の一本化が図られます。
相続によって株主が分散しているケース
オーナー社長の死去などによって株式が複数の相続人に分散されると、経営に関与しない人物が株主となり、会社の意思決定を妨げる要因になることがあります。中には経営方針に口出しする相続人や、株主総会への出席に非協力的な相続人もおり、会社の安定運営に悪影響を及ぼす場合があります。
また、相続後に株式の所在が不明になったり、連絡が取れなくなったりすることもあるため、実務上の対応が複雑になることも少なくありません。
こうした分散した株主構成を整理し、株式を経営陣に集中させるための手段として、スクイーズアウトが活用されます。
所在不明株主が存在するケース
かつて会社設立時に発起人7名が必要とされた制度の影響で、経営に関与しない名義株主が形式的に株式を保有しているケースが今も残っています。
これらの名義人は実質的に株主としての関与をしておらず、その所在が不明になることも珍しくありません。所在不明株主の存在は、株主総会の開催や重要な意思決定を妨げる要因となる恐れがあります。
本来であれば除権決定などの法的手続きを通じて整理できますが、実務上は時間や手間がかかり、交渉が成立しないまま停滞するケースも少なくありません。こうした背景から、近年ではスクイーズアウトを用いて、株主の同意を得ることなく株式を取得し、対価を供託によって処理する手法が広く活用されています。
従業員や取引先が株主となっているケース
旧経営陣が従業員の士気向上や取引先との関係強化を目的として株式を持たせていた場合、当事者が退職・取引終了後も株式を保有し続けることがあります。
このような少数株主であっても、経営への関与や反対行動によって意思決定に支障を来す可能性があり、特に経営体制の刷新や事業承継の局面では問題が生じます。
また、株主が外部関係者のままであると、経営方針に対する意見の食い違いや協力拒否といったリスクが生じる恐れがあります。そのため、こうした株主の排除や整理を目的として、スクイーズアウトの手法が用いられることがあります。
上場廃止を目指すケース
スクイーズアウトは、上場廃止を目的とする際にも活用されます。経営資源の集中や迅速な意思決定を実現するために、株式の非公開化を選ぶ企業が増加傾向にあります。
特に、前述の完全子会社化やMBO(経営陣による自社の買収)といった手法では、株式併合や株式等売渡請求といったスクイーズアウトの仕組みが用いられます。
スクイーズアウトの手法・手続きの流れ
スクイーズアウト実行の際に用いられる主な株式取得手法は、次のとおりです。
- 全部取得条項付種類株式
- 株式併合
- 株式交換
- 株式等売渡請求
それぞれの制度的な仕組みや特徴、手続きの流れについて解説します。また、これらを円滑に実行するための事前措置として活用される株式公開買い付け(TOB)についても併せて解説します。
全部取得条項付種類株式
全部取得条項付種類株式 制度の仕組みと特徴
全部取得条項付種類株式とは、会社が定款に基づき、対象となる種類株式をすべて取得できる仕組みを指します。この制度は、会社法の規定に基づき、株主総会で議決権の3分の2以上の特別決議を経た上で、会社が該当する株式を強制的に取得することを認めています。
スクイーズアウトを目的とする場合、まず定款を変更して「種類株式発行会社」とした上で、既存の普通株式を全部取得条項付種類株式に変更します。その後、株主総会の特別決議に基づき、対象となる株式をすべて取得し、対価として現金または他の株式を交付する手続きが行われます。
少数株主を整理する目的では、取得対価の設計が重要です。すべての株主に株式を割り当てる形式としつつ、少数株主の割り当て部分が端数となるよう調整し、その端数を会社が買い取ることで、実質的に現金交付を実現します。この仕組みにより、法律に基づいた手続きで少数株主を整理することが可能です。
手続きの流れ
全部取得条項付種類株式を用いたスクイーズアウトの手続きは、以下の流れで進められます。
- 開示書面の備え置き 株主総会の開催日の2週間前(または通知日の早い日)から、取得後6カ月間、本店で関連書類を備え置きます。この書類には、取得対価やその算定根拠が記載されており、株主が閲覧できるようにする必要があります。
- 株主総会での特別決議 株主総会で、議決権の3分の2以上の賛成による特別決議を行い、全部取得条項付種類株式の取得が承認されます。
- 株主への通知 特別決議が成立した後、会社は取得予定日の20日前までに、株主へ取得内容を通知します。通知には、取得対価や取得手続きの詳細が含まれます。
- 株式の取得と対価の交付 会社が株式を取得し、対価として現金または株式を交付します。この際、少数株主には端数株式が割り当てられるよう取得比率を調整し、その端数部分を会社が買い取ることで、実質的に現金交付を行い、株式の集中を実現します。
少数株主の権利保護
全部取得条項付種類株式を用いたスクイーズアウトでは、少数株主の権利保護が重要です。取得対価の公正性を確保するため、独立した第三者機関による株式評価を行い、価格の妥当性を担保する必要があります。少数株主が取得対価に納得できない場合、裁判所に対して価格決定の申立てを行う権利が認められています。この仕組みにより、少数株主の財産権を適切に保護することができます。
メリットと注意点
- メリット: 全部取得条項付種類株式は、株主総会の特別決議を経ることで、迅速かつ合法的に少数株主を整理し、経営権の集中や意思決定の迅速化を図ることができます。また、取得対価として現金や株式を柔軟に利用できる点も特徴です。
- 注意点: 取得対価の設定や手続きの透明性が不十分な場合、少数株主から異議申し立てや訴訟が提起されるリスクがあります。さらに、手続きが適法であることを担保するため、事前に専門家(弁護士、公認会計士など)の助言を受けることが推奨されます。
補足情報
全部取得条項付種類株式は、株式併合や株式等売渡請求と並ぶスクイーズアウト手法の一つです。特に、グループ再編やM&A後の完全子会社化の場面で多く利用されており、企業の経営効率化や株主構成の整理を実現する有効な手段となっています。
株式併合
制度の仕組みと特徴
株式併合とは、複数の株式を一定の割合で一つにまとめる手法です。例えば、10株を1株に併合する場合、10株未満しか保有していない株主は1株未満の端株となり、株主としての権利を失います。この際、株式を失った少数株主に現金を支払うことで、スクイーズアウトが実現します。
この方法では、端株を合算して市場で売却し、その売却代金を元の持ち株数に応じて各株主に案分します。例えば、0.3株、0.5株、0.2株を集約して100円で売却した場合、それぞれ30円、50円、20円と配分されます。
株式併合の実施には、株主総会における議決権の3分の2以上の特別決議が必要です。比較的簡便な手続きで実施可能なことから、過去にはスクイーズアウトの主な手法として多く活用されてきました。
株式買取請求権・価格決定申立権とは
株式併合によるスクイーズアウトでは、保有株式が1株未満となる少数株主が排除されます。これに対し、少数株主は株式併合に反対し、会社に対して保有株式を公正な価格で買い取るよう請求する権利があります。これが「株式買取請求権」です。
さらに、会社と株主の間で価格が合意に至らない場合、株主は効力発生日から60日以内に限り、裁判所に価格の決定を申し立てることが認められています。これが「価格決定申立権」です。裁判所は非訟手続によって価格を判断し、最終的には、その価格に利息を加算した金額で株式の買取が行われます。
価格が著しく不当な場合には、株主総会決議の取消訴訟を提起できる可能性もあります。
手続きの流れ
株式併合を用いたスクイーズアウトは、次の手順で進められます。
- 取締役会で株主総会の開催を決議
- 書面等の事前備え置き
- 株主総会の開催と特別決議
- 株主への通知等の実施
- 株式併合の効力発生と対価の支払い
まず、取締役会で株式併合を議案とする株主総会の開催を決議します。その後、開示書面を作成し、株主総会開催日の2週間前(または株主への通知日のどちらか早い日)から、効力発生日後6カ月の間、本店に備え置く必要があります。
続いて、株主総会を開催し、株式併合に関する特別決議を行います。併合の効力発生日の2週間前までには、決定内容を株主へ通知しなければなりません。
株式併合の効力が発生した後、1株未満の端株を保有する株主に対しては、会社がその端株を買い取り、現金を対価として支払います。
なお、買取価格は裁判所の審査対象となり、公正かつ妥当な水準である必要があります。
株式等売渡請求
制度の仕組みと特徴
株式等売渡請求とは、議決権の90%以上を保有する特別支配株主が、他の全株主に対して株式の売り渡しを請求できる制度です。2014年の会社法改正で導入され、迅速かつ強制力のあるスクイーズアウト手法として広く注目されています。
手続きは、特別支配株主が対象会社に売渡請求の通知を行い、会社側がこれを承認することで効力が発生します。株主総会の決議を経る必要はなく、取締役会設置会社であれば取締役会の承認のみで進行できる点が大きな特徴です。
少数株主に拒否権はなく、裁判所の関与も不要なため、従来のスキームと比べて手続きの簡素化とスピードの両立が図られます。M&Aや完全子会社化における株主構成の整理を目的としたスクイーズアウトにおいて、実務上の標準的な選択肢となっています。
手続きの流れ
株式等売渡請求によるスクイーズアウトは、次の手順に従って進められます。
- 会社に対して売渡請求を通知する
- 会社が請求を承認し、特別支配株主へ通知する
- 会社から少数株主へ通知を行う
まず、特別支配株主は、対象会社に対して株式売渡請求の通知を行います。この際、株式の取得日や取得価格、算定方法などもあらかじめ決定し、通知内容に含めます。
通知を受けた対象会社は、売渡請求を承認するかどうかを決定し、特別支配株主に対して結果を通知します。取締役会設置会社であれば、取締役会の決議が必要です。
その後、対象会社は、株式取得日の20日前までに、売渡対象となる少数株主に対して売渡請求の内容を通知します。なお、売渡株主以外の新株予約権者などには、公告による通知も認められています。
株式交換
制度の仕組みと特徴
株式交換とは、親会社が子会社の株式を取得する代わりに、自社の株式または現金を対価として交付し、子会社を完全子会社化する手法です。
スクイーズアウトに応用する際は、まず親会社が株式交換によって子会社の全株式を取得し、子会社の少数株主を親会社株主へと移行させます。その上で、株式併合や端株処理によって保有割合を調整し、最終的に少数株主を排除します。
また、2017年度の税制改正以降は、対価を現金とする「現金対価株式交換」も選択肢となっています。この方法では、親会社が子会社の少数株主に現金を支払い、株式を取得します。
2段階の手続きが必要でやや複雑ではあるものの、柔軟性が高く、グループ再編や経営統合を進める際の実務で多用される手法です。
手続きの流れ
株式交換によるスクイーズアウトは、次の手順で進められます。
- 取締役会での決議と契約の締結
- 書面等の事前備え置き
- 株主総会での特別決議
- 効力発生と対価の交付・変更登記
まず、親会社および子会社の取締役会において株式交換契約の締結を決議し、両社間で契約書を取り交わします。
その後、株主総会開催日の2週間前(または通知日のうち早い日)から、効力発生後6カ月まで、株式交換に関する書類を本店に備え置きます。
次に、親会社および子会社の株主総会を開催し、株式交換契約に関する特別決議を行います。株主総会の承認を得て契約が成立すると、定められた効力発生日に親会社が子会社の全株式を取得し、あらかじめ定めた対価を交付します。
最後に、効力発生日から2週間以内に、株式交換に関する変更登記を行います。
株式公開買い付け(TOB)
株式公開買い付け(TOB)とは、上場企業の株式を対象に、一定の価格と期間を提示して、不特定多数の株主から株式を買い取る手法です。
スクイーズアウトの場面では、議決権の取得割合を引き上げ、その後に実施する株式併合や株式等売渡請求などの手続きを円滑に進めるために活用されることが一般的です。
なお、TOBの実施に際しては、情報開示義務をはじめとする厳格なルールが定められており、違反があった場合には課徴金などの制裁が科される可能性があります。そのため、戦略立案を含む事前準備が非常に重要であり、法令や実務に精通した対応が求められます。
スクイーズアウトのメリット
スクイーズアウトには次のようなさまざまなメリットがあります。
- 意思決定の迅速化が図れる
- 事業承継・再編の円滑化が図れる
- 税務上の優遇が受けられる
- 訴訟リスクの回避ができる
- 上場廃止による経営コストの削減ができる
- 長期的視点での経営戦略が取りやすくなる
それぞれについて解説します。
意思決定の迅速化が図れる
スクイーズアウトによって少数株主を排除し、株式を特定の主体に集中させることで、株主間の利害対立や調整負担が大幅に削減されます。
その結果、取締役会や株主総会における意思決定が迅速になり、経営方針の転換や新規事業の開始、大規模な投資などもスピーディに実行できます。
特に、変化の激しい経営環境が続く中では、判断と行動の遅れが企業価値に影響を与えるため、柔軟で迅速な意思決定体制の確立は、持続的成長を支える上でも重要な要素です。
事業承継・再編の円滑化が図れる
企業が継続的に成長するためには、経営権の移譲やグループ再編などの場面において、株主構成の適切な整理が不可欠です。
特に創業者の高齢化による事業承継や、M&Aを前提とした組織再編においては、少数株主の存在が障害となるケースがあります。
スクイーズアウトを通じて株式を特定の株主に集中させることで、意思決定の明確化と手続きの迅速化が実現し、後継者や新経営陣への円滑な移行を可能にします。
税務上の優遇が受けられる
親会社が子会社の全株式を取得して完全子会社化すれば、グループ通算制度の適用対象とみなされます。この制度では、赤字企業と黒字企業間で損益を通算できるため、法人税の負担を抑える効果が期待されます。
また、グループ内再編や資産移転に際しても、税務手続きの簡略化措置を活用できるため、グループ全体の税務効率が向上します。経理業務の負担軽減やキャッシュフローの安定にも寄与する効果があります。
訴訟リスクの回避ができる
少数株主が存在することで、株主代表訴訟などの法的リスクが生じることがあります。経営方針への反対や経営陣への不信感が訴訟に発展すれば、企業は金銭的損失にとどまらず、社会的信用も毀損(きそん)する恐れがあります。
スクイーズアウトを通じて支配株主以外の株主を排除すれば、このような法的リスクを大幅に軽減できます。経営陣は不要な訴訟への対応に煩わされることなく、事業運営に集中できます。
上場廃止によってコストの削減ができる
スクイーズアウトは、上場を廃止することで経営上の負担を軽減できます。
上場を維持するには、四半期ごとの情報開示やIR活動、コンプライアンス対応などに多くの費用と人材を要します。非上場化することで、こうした義務から解放され、限られた経営資源を本業に集中させられます。
さらに、株主構成が整理されることで、株主総会の通知送付や議決権の管理、配当処理といった煩雑な手続きも削減できます。特に少数株主が多い企業では、対応コストが高くなりやすいため、スクイーズアウトによる株主整理は中小企業にとって有効な手段といえます。
長期的視点での経営戦略が取りやすくなる
上場廃止のメリットはコスト削減にとどまりません。上場企業は、株価変動や短期的な業績に対する投資家からの圧力にさらされやすく、長期戦略の遂行が難しい局面があります。
スクイーズアウトによって企業が非公開化されれば、経営陣は短期的な利益目標から自由になり、中長期的なビジョンに基づく戦略を着実に実行しやすい体制を築けます。
研究開発投資やブランドの構築、サステナビリティ経営の推進など、将来に向けた施策を腰を据えて進められる体制が整います。
スクイーズアウトのデメリット
スクイーズアウトには、次のようなデメリットも存在します。
- 実行に時間と手間を要する
- 法的制約によって柔軟性が乏しい
- 対価支払いに伴う財務負担が増える
- 少数株主との対立・訴訟リスクがある
- 社内外の理解とガバナンス対応が必要になる
それぞれについて解説します。
実行に時間と手間を要する
スクイーズアウトの実施には、会社法に基づく厳格な手続きが求められます。基準日公告や株主総会の特別決議、招集通知、開示書類の整備など、多くの段階を慎重に踏まなければなりません。
株式等売渡請求のような比較的迅速な手法でも、最短で20日はかかります。その他の手法では2カ月近く要する場合もあり、少数株主対応や対価算定、社内調整など、実務上の準備負担は多大です。
M&Aのスケジュールと並行する場面では、時間的余裕を持った計画が不可欠です。
法的制約によって柔軟性が乏しい
スクイーズアウトを進めるには、会社法上の厳格な要件を満たす必要があります。
例えば、株式等売渡請求は議決権の90%以上を保有する「特別支配株主」でなければ実行できません。90%未満の持株比率であれば、まず株式公開買い付け(TOB)などでの事前取得が必要となり、時間や資金がかかります。
また、全部取得条項付種類株式や株式併合なども、定款変更や特別決議といった法的手続きを要し、柔軟な運用は難しいです。法務や実務の両面で、専門家による支援体制が欠かせません。
対価支払いに伴う財務負担が増える
スクイーズアウトでは、少数株主の保有株式を適正な価格で買い取る必要があります。企業価値が高く、株主数が多い場合には、その総額は膨大なものとなり得ます。
評価額は通常、第三者による算定を伴い、適正性を欠くと訴訟リスクに直結するため、慎重な対応が求められます。
未上場企業であっても、帳簿上の資産や利益水準を基に企業価値が高いと判断される場合があり、想定外の資金負担が生じることがあります。あらかじめ資金計画を綿密に立てておくことが重要です。
少数株主との対立・訴訟リスクがある
スクイーズアウトは、少数株主の同意を得ずに株式を取得する手法であるため、不満を持つ株主との間でトラブルが発生する可能性があります。
典型的には、価格が不当だと主張されて「価格決定の申立て」や「株主総会決議の取消し請求」などの訴訟に発展することがあります。さらに、手続きに不備があった場合には、差止請求や役員責任の追及といった法的リスクも生じ得ます。
こうしたリスクを避けるには、対価の適正性を担保しつつ、丁寧な説明や文書による合意形成、外部専門家の関与などが必要です。
社内外の理解とガバナンス対応が必要になる
スクイーズアウトの実行は、社内の従業員だけでなく、顧客・取引先・金融機関といった社外関係者にも影響を及ぼす可能性があります。
特に、上場廃止を伴う場合には社会的関心も高まり、説明責任や透明性の確保が一層求められます。
手続きや対価算定の不透明さは、企業イメージの低下を招く恐れがあります。コンプライアンス体制や情報開示の整備が不十分な状態で進めると、企業価値の毀損(きそん)やその後の施策への支障となるため、慎重な対応が欠かせません。
スクイーズアウトの国内事例10選
スクイーズアウトが実施された事例を背景や目的とともに紹介します。また、買付価格を巡って裁判となったケースも併せて紹介します。
ローソン
2024年2月、KDDIと三菱商事はローソンと資本業務提携を締結し、共同で株式公開買い付け(TOB)を実施しました。同年4月に買付けが成立し、7月の臨時株主総会で株式併合と定款変更が可決されました。これにより、発行済株式は2株のみ(KDDIと三菱商事がそれぞれ保有)となり、スクイーズアウトが実行されました。
その後、8月にはKDDIと三菱商事がそれぞれ50%ずつを出資する体制が整い、上場廃止が完了しました。両社はローソンを活用してリアルとデジタルの連携を強化し、経済圏の拡大と生活インフラの高度化を目指しています。
永谷園ホールディングス
2024年6月、永谷園ホールディングスは創業家と丸の内キャピタルによるマネジメント・バイアウト(MBO)を実施し、同年9月にTOBおよび株式併合を経て上場を廃止しました。
スクイーズアウトの目的は、長期的な視点に基づく経営体制の構築と意思決定の迅速化にあります。非公開化後は、ブランド強化や新規事業の展開が進められています。
佐渡汽船
2022年、新潟県本土と佐渡島を結ぶ定期航路を運航する佐渡汽船は、みちのりホールディングス傘下に入り、上場を廃止しました。株式併合により27万株を1株に統合し、端株は1株30円で買い取る形式でスクイーズアウトが実施されました。
当時の株価202円に対し大幅なディスカウントであったものの、債務超過や経営再建の必要性が背景にありました。公共交通再編の一環として実行されたこの事例では、支配権移行の迅速化と株主保護の両立に課題が残りました。
オンリー
2021年、紳士服を手掛けるオンリーは、創業者で筆頭株主の中西浩一氏らが設立した紳士服中西によるMBO(経営陣による買収)を通じて非公開化されました。市場縮小やコロナ禍の影響によるテレワーク拡大を背景に、柔軟で機動的な意思決定体制の構築が急務となったためです。
紳士服中西はTOB(株式公開買い付け)を実施し、約37億円でオンリーの株式を取得しました。買付価格は1株765円とされ、公表前終値に約39%のプレミアムが付されました。その後、株式併合を用いたスクイーズアウトが実行され、完全子会社化が完了しました。
本件のMBOは、衣料品事業の強化や不動産・周辺事業への展開、デジタル投資などを進めるため、中長期的視点に基づく経営改革を目的として行われたものであり、アパレル業界における戦略的非公開化の一例といえます。
LINE
LINEはZホールディングスとの経営統合に向け、2020年にソフトバンクと韓国ネイバーの共同出資会社によって非公開化が進められました。
当初、TOB(株式公開買い付け)により全株取得を目指しましたが、一部の少数株主の応募が得られず、完全子会社化は未達となりました。そこで同年9月、LINEは臨時株主総会で約2,900万株を1株に併合する株式併合を決議し、少数株主をスクイーズアウトしました。
これにより、株式数は32株にまで減少し、2020年12月に上場廃止が実施されました。最終的にLINEはZホールディングスの完全子会社となり、2021年3月に統合が完了しました。
パイオニア
パイオニアは、カーエレクトロニクス事業の不振や構造改革費用の増加により財務が悪化しました。資金調達の必要性から、2018年に香港の再生ファンド・ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア(BPEA)から出資を受け入れ、再建体制に移行しました。
2019年にはBPEAが支配株主となり、株式併合を通じてスクイーズアウトを実施しました。同年3月には上場廃止が完了し、パイオニアは完全子会社となりました。
エナリス
新電力事業を展開していたエナリスは、過去の不適切会計により経営不安が続いていました。KDDIは2016年、「auでんき」の展開にあたり電力需給管理を担うパートナーとしてエナリスと提携しました。
経営安定化を図るため、2018年にKDDIは電源開発(Jパワー)と共同でTOBを実施し、議決権の三分の二を取得した上で株式併合を実行し、スクイーズアウトを行いました。KDDIは本件を「au経済圏」強化の中核戦略と位置付けています。
雪国まいたけ
2015年、米国の投資ファンドであるベインキャピタルは、買収目的会社BCJ-22を通じて雪国まいたけに対しTOB(株式公開買付)を実施し、全株式を取得した上でスクイーズアウトを行いました。
背景には、2013年に発覚した不適切会計や、創業者の退任後も続いた経営陣の対立があり、これらの混乱を収束させ、非公開化によって経営再建を進める狙いがありました。
買収後は、財務体質の改善と事業の選択と集中が推進され、2020年には再上場を果たしました。この再上場は、ベインキャピタルによるバイアウト案件としても注目され、マイタケ事業に特化した戦略の下、西日本や海外市場への展開も進められています。
ジュピターテレコム
ケーブルテレビ事業を手がけるジュピターテレコム(現:J:COM)は、2013年に住友商事とKDDIによる共同買収が行われ、2014年には全部取得条項付種類株式を用いた完全子会社化が実施されました。
当初は経営主導権を巡る対立がありましたが、最終的には折半出資による共同経営に合意し、スクイーズアウトが実行されました。
一部の海外株主は買付価格の不当性を主張して提訴しましたが、最高裁は価格の適正性を認め、買収の適法性を確定しました。価格を巡る紛争が最高裁で決着した事例として注目されました。
カネボウ
カネボウは、業績悪化と粉飾決算により経営危機に直面し、2004年に産業再生機構の支援を受け、2005年に上場を廃止しました。再生ファンドは1株162円でTOBを実施し、これに応じなかった少数株主は2006年に株式併合によるスクイーズアウトで排除されました。
その後、買収価格の妥当性を巡って裁判が起こされ、東京地裁は1株360円が適正と判断しました。しかし、最終的に最高裁は東京高裁の判断を支持し、1株162円が適正と確定しました。
その後、化粧品事業は花王に売却されましたが、企業文化の違いや製品トラブルにより、花王の業績に影響を及ぼしました。
スクイーズアウトに関するQ&A
最後に、スクイーズアウトに関するよくある質問とその回答を紹介します。
少数株主の排除方法は他にあるか
少数株主を排除する方法として、スクイーズアウトの手法以外では、任意の株式買取交渉があります。これは、個別に交渉を行い、株主の同意を得た上で株式を買い取る方法です。トラブルが起こりにくい反面、全ての株主が応じるとは限らず、手続きに時間とコストがかかる点が課題とされます。
このような事情から、より円滑かつ確実に少数株主を整理できる手法として、スクイーズアウトの制度が広く活用されています。
非上場企業でのスクイーズアウトはどのように行うべきか
非上場企業においてスクイーズアウトを行う場合、まずは任意交渉によって株式を買い取る方法が検討されます。しかし、感情的な対立や価格面で合意できないケースでは、強制的な手続きを講じる必要があります。
取得対価を金銭とする手法としては、特別支配株主による株式等売渡請求と株式併合、全部取得条項付種類株式の三つが挙げられます。特に株式併合は、平成26年の会社法改正により、反対株主に対する買取請求制度が整備されたことから、実務上の利用が増えています。
ただし、特別支配株主制度は、原則として議決権の90%以上を単独で保有する必要があるなど、活用が難しい面もあります。
スクイーズアウトで金銭交付を受けた場合、税金はどうなるか
スクイーズアウトによる上場廃止後に金銭交付を受けた場合、その株式は非上場株式とみなされ、譲渡益は申告分離課税(税率20.315%)の対象です。ただし、上場株式の扱いとは異なり、他の上場株式の損益や配当との損益通算はできず、損失の繰越控除も認められません。
また、特定口座やNISA口座で保有していた株式も、上場廃止によって口座外に払い出されるため、税優遇の対象外です。NISA口座の場合、払い出し時の終値が取得価額とされ、交付金額との差額が譲渡益となるため、確定申告が必要になるケースがあります。
なお、具体的な税務処理については、税務署または税理士への確認が推奨されます。
キャッシュアウト・マージャーとは何か
キャッシュアウト・マージャーとは、吸収合併の一形態で、消滅会社の株主に株式ではなく現金のみを対価として交付する手法です。2006年の会社法改正により合法化され、「交付金合併」とも呼ばれます。
この手法を用いれば、存続会社の株主構成を変えることなく、消滅会社の少数株主を排除可能です。ただし、税務上は「適格合併」に該当しないため、法人税などの課税負担が生じるケースがあります。
なお、スクイーズアウトのことを「キャッシュアウト」と呼ぶこともあります。
スクイーズアウトに関する近年の法改正はどのようなものか
近年の会社法改正では、企業が少数株主を整理しやすくなるよう制度の整備が進められています。具体的には、2014年に「特別支配株主による株式等売渡請求制度」が創設されました。この制度では、議決権の90%以上を保有する特別支配株主が他の株主に対して株式の売却を請求できる仕組みが導入され、株主総会の特別決議を経ずに迅速な手続きが可能となりました。
さらに、2017年には税制改正が行われ、株式併合や株式交換などのスクイーズアウト手法に関する課税関係が整理されました。この改正により、課税のばらつきが是正され、スクイーズアウトの実務における使いやすさが向上しています。
加えて、2025年には経済産業省の研究会が制度の迅速化・簡易化を提言しており、企業統治や組織再編の円滑化に資する制度として、今後も注目を集める見込みです。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
本記事では、スクイーズアウトの基本的な仕組みから、具体的な手法・手続きの流れ、活用される場面、メリット・デメリット、国内事例までを解説しました。M&Aや事業承継において、ひとつの方法として理解しておくことで、将来にその知識が活かされることがあるかもしれません。
M&Aや経営課題に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。