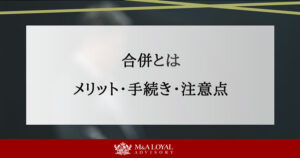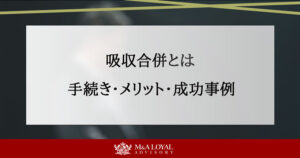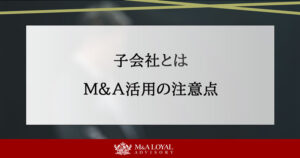「合併」の英語・発音は?使い方を例文付きで解説。M&Aは何の略?
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
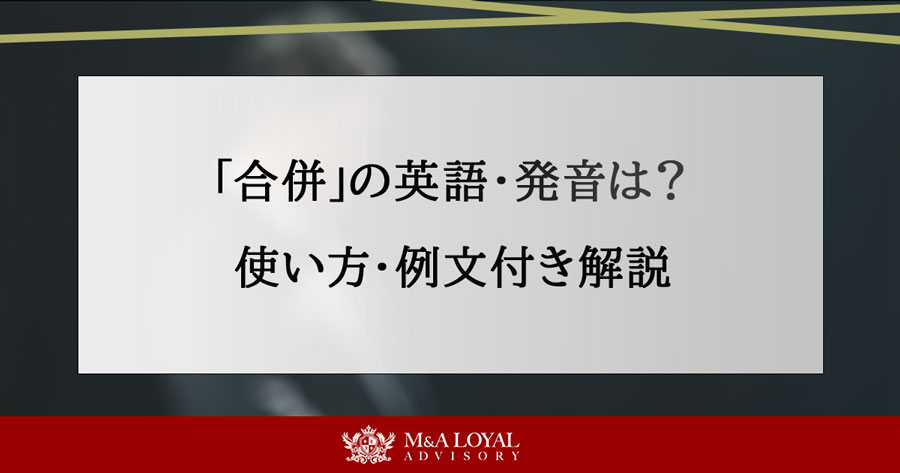
「合併」はビジネスやニュースでよく耳にする言葉ですが、英語ではどのように表現し、どう発音するのでしょうか?
本記事では、「合併」の基本的な英訳から発音、使い方まで、例文を交えて分かりやすく解説します。さらに、「M&A」は何の略なのか、言葉の背景やビジネスでの実際の使われ方についても詳しくご紹介します。
英語初心者の方でも安心して読める内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
そもそも「合併」とは
「合併」の英訳を解説する前に、ビジネスや金融業界で使われる「合併」の意味をおさらいします。
「合併」の意味
ビジネスにおける「合併」とは、複数の企業が法人格を統合し、一つの会社として再編成されることを指します。経営資源の集約やシナジー効果の創出、競争力の強化などを目的に行われることが多く、企業の成長戦略や事業再編の一環として用いられます。
特にグローバル化が進む現代においては、国境を越えた合併も一般的となり、企業の競争環境に大きな影響を与えています。
「合併」の種類
「合併」は大別すると「吸収合併」と「新設合併」の2種類があります。
吸収合併は、一方の会社が存続し、もう一方の会社が消滅する形式の合併です。存続会社が全ての資産・負債・契約などを引き継ぎ、合併後も法人格を維持します。 一方、新設合併は、両方の会社が消滅し、新たに設立される会社がその権利義務を承継する形式の合併です。両社が対等な立場で統合し、新しい法人として再スタートします。
「合併」のメリット
合併のメリットとしては、まず経営資源を統合することにより、重複した業務や人員の整理が可能となり、業務効率の向上やコスト削減が期待されます。
また、営業基盤や技術力、ブランド力などを補完し合うことで、製品やサービスの競争力が強化され、市場での優位性を高められます。さらに、財務面においても資本力や資金調達力が強化され、経営の安定性が向上する点も大きな利点といえるでしょう。
「合併」と「買収」の違い
合併と買収はどちらも企業の統合手法ですが、法人格の消滅の有無という違いがあります。合併では複数の会社が1つに統合され法人格が消滅する会社が発生するのに対し、買収では一方の企業が他方の企業の経営権を取得するのみで法人格は消滅しません。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



「合併」の英語①Absorption merger(吸収合併)
「吸収合併」を意味する英語「Absorption merger」の意味や語源、使い方を例文とともに解説します。
意味と語源
「吸収合併」は「Absorption merger」または「Absorption-type merger」と表現されますが、アメリカ英語では吸収合併を「merger」、新設合併を「consolidation」と表し、二つを区別しています。
「merger」の発音は「マージャ―」ですが、日本でそのままカタカナ語として使われることはほとんどありません。ちなみに「M&A」の「M」は「merger(s)」の頭文字です。
「merger」は、「合併する」という意味の動詞「merge」の名詞形です。「merge」は「沈める」「浸す」を意味するラテン語「mergere」が語源です。また、「merger」の対義語には「division」「separation」「split」などがあります。
名詞「merger」の使い方と例文
名詞「merger」を使った例文は次のとおりです。
The two companies are planning a merger to strengthen their market position.
2社は市場での地位を強化するために吸収合併を計画しています。
The merger between Company A and Company B was completed last month.
A社とB社の吸収合併は先月完了しました。
The merger talks have been ongoing for several months, but no agreement has been reached.
吸収合併交渉は数カ月にわたって続いていますが、合意には至っていません。
Some employees are concerned about potential layoffs following the merger.
吸収合併後の人員削減を懸念している社員もいます。
動詞「merge」の使い方と例文
「合併される」「合併された」など受け身の英語表現は「be merged」です。「〜に合併された」とする場合は「be merged into」「be merged with」などと表現します。「into」の方がより大きな会社に飲み込まれる、というニュアンスが強くなります。
例文は次のとおりです。
The smaller company may be merged into a larger one by the end of the year.
その小規模な会社は年末までに大手企業に吸収合併される可能性があります。
Our company was merged with a competitor after months of negotiation.
数カ月にわたる交渉の末、当社は競合他社と吸収合併しました。
In 2021, the two regional banks were merged to form a new financial group.
2021年に、2つの地方銀行が吸収合併されて新しい金融グループが誕生しました。
「absorption」「absorb」という表現
「吸収」は英語で「absorption」、「〜を吸収する」は英語で「absorb」です。
日本では「吸収合併」の英訳として「absorption-type merger」という表現を使う場合がありますが、英語圏では一般的ではありません。前述したとおり「merger」は単体で「吸収合併」を表します。
しかし、「新設合併」との違いを強調するために「absorption merger」「merger through absorption」「merger by absorption」と表現する場合がまれにあります。
また、「absorb…through a merger(合併を通して…を吸収する)」「absorb…in the merger plan(合併計画の元…を吸収する)」といった表現はしばしば見られます。
例文は次のとおりです。
Company A will absorb Company B through a merger, resulting in the dissolution of Company B.
A社は合併を通じてB社を吸収し、B社は解散となります。
The merger allows Company A to absorb Company B’s customer base and expand into new markets.
この合併により、A社はB社の顧客基盤を吸収し、新たな市場への展開が可能になります。
「合併」の英語②consolidation(新設合併)
次に「新設合併」を意味する「consolidation」の意味や語源、使い方を例文とともに解説します。
意味と語源
「新設合併」は英語で「consolidation」または「consolidation-type merger」といいます。
「consolidation」の発音は「コンソリデーション」で、日本語ではビジネス用語としてあまり一般的ではありませんが、企業統合や財務再編に関する専門的な文脈では使われることがあります。「consolidation」は、「〜を強化する」「〜を統合する」という意味を持つ動詞「consolidate」の名詞形です。
この単語の語源は、ラテン語の「solidus(堅固な、しっかりした)」に由来しており、「共に(con)+堅固にする(solidare)」という意味から、「複数のものを一つの堅固なものにまとめる」というニュアンスが生まれました。
名詞「consolidation」の使い方と例文
名詞「consolidation」を使った例文は次のとおりです。
The consolidation of the two companies resulted in the creation of a new market leader.
2社の新設合併により、新たな市場のリーダーが誕生しました。
The consolidation of multiple subsidiaries into a single entity improved group-wide governance.
複数の子会社を一つの法人に統合することで、グループ全体のガバナンスが向上しました。
Unlike a merger, a consolidation forms an entirely new company from the combining entities.
吸収合併とは異なり、新設合併では統合する事業からまったく新しい会社が設立されます。
動詞「consolidate」の使い方と例文
動詞「consolidate」を使った例文は次のとおりです。
The two companies agreed to consolidate into a new legal entity to strengthen their market presence.
両社は市場での存在感を高めるため、新設合併することに合意しました。
The board approved the plan to consolidate the two businesses into a new corporation by the end of the fiscal year.
取締役会は、当会計年度末までに両事業を新設合併する計画を承認しました。
The two firms decided to consolidate their operations under a new brand.
両社は業務を新しいブランドのもとで統合することを決定しました。
「合併」の英語③amalgamation(イギリス英語)
意味と語源
「amalgamation」という英語も、企業の統合を意味する英語表現の一つです。イギリスやインドなどで使われる用語で、アメリカではほとんど使用されません。
「amalgamation」は「合併」を包括的に表す言葉で、「吸収合併」と「新設合併」のどちらに対しても使われるため、日本語の「合併」に意味的には最も近いといえます。
「amalgamation」の発音は「アマルガメイション」です。 この言葉は「混ぜ合わせる」「融合させる」という意味の動詞「amalgamate」の名詞形です。
使い方と例文
「amalgamation」を使った例文は次のとおりです。
The amalgamation of Company A and Company B resulted in the formation of a stronger, more competitive organization.
A社とB社の合併により、より強力で競争力のある組織が誕生しました。
Under the scheme of amalgamation, both companies will dissolve and transfer their assets to a newly incorporated entity.
合併計画に基づき、両社は解散し、新たに設立される法人に資産を移転します。
The tax implications of the amalgamation were carefully reviewed by both parties before proceeding.
合併による税務上の影響は、実行前に両当事者によって慎重に検討されました。
「合併」に関連するその他の英語表現
合併の際に使用される言葉を英語でどう表現するのかもご紹介します。
「存続会社」の英語
存続会社(合併先)は、英語では「surviving entity」または「surviving company」と表現されます。
ここで使われる「surviving」は「生き残る」「存続する」という意味の形容詞で、合併の結果として法人格を維持し続ける会社を指します。「entity」は「法人」や「組織体」を意味するフォーマルな単語で、法律やビジネス文書で広く使われます。
「surviving entity」は法的・文書的にやや固い表現ですが、実務や口語では「surviving company」と言い換えられることもよくあります。
「surviving entity」を使った例文は次のとおりです。
Company A will act as the surviving entity in the proposed merger with Company B.
A社は、B社との予定されている合併において存続会社として機能します。
The surviving entity will continue operations under the same name and management structure.
存続会社は、同じ社名と経営体制のもとで事業を継続します。
「消滅会社」の英語
消滅会社(被合併会社)は、英語では一般的に「absorbed entity」 や 「dissolved entity」と表現されます。
「absorbed」は「吸収された」という意味で、合併によって他の法人に統合されることを表します。また「dissolved」は「解散した」「消滅した」という意味で、法人格が正式に消滅したことを強調したい場合に使われます。
また、「merged entity」という表現も用いられることがありますが、「合併に関わった法人」という広い意味を持ちます。そのため、「merged entity」が吸収した側なのか、吸収された側なのかは文脈から判断する必要があります。明確に伝えたい場合には、文章中で補足説明を加えることが一般的です。
「absorbed entity」 と「dissolved entity」を使った例文は次のとおりです。
All employees of the absorbed entity will be integrated into the surviving entity’s organizational structure.
消滅会社の全ての従業員は、存続会社の組織構造に統合されます。
Under the merger agreement, Company B will be the dissolved entity and will transfer all of its rights and obligations to Company A.
合併契約に基づき、B社は吸収され解散し、そのすべての権利義務をA社に移転します。
「対等合併」の英語
「対等合併」は「merger of equals」と表現されます。
「equal(イコール)」は形容詞として使われることが多いですが、「対等な存在」という意味の名詞としても使われます。「merger of equals」の「equals」は「equal」の複数形で、「対等な企業同士」という意味で使われています。
「merger of equals」を使った例文は次のとおりです。
The deal was structured as a merger of equals, with both entities contributing similar assets and leadership roles.
この取引は対等合併として構成され、両法人が同等の資産と経営陣を提供しました。
Unlike a typical acquisition, this is a merger of equals, with no single dominant party.
通常の買収とは異なり、これは対等合併であり、主導権を持つ一方的な当事者はいません。
「合併比率」の英語
合併比率とは、合併において消滅会社の株主に対して、存続会社の株式がどのような割合で割り当てられるかを示す比率のことを指します。株式同士の交換となる場合、この比率は経済的な公平性や支配権のバランスに直結する、極めて重要な要素です。
英語では、この「合併比率」を表す言葉として一般的に使用される表現が「exchange ratio」です。「exchange」は「交換する」「引き換える」という意味で、株式の交換(share-for-share exchange)を示しています。
また、同じ意味で「swap ratio」という表現が使われることもあります。「swap」も「交換」を意味しますが、「exchange」よりもややテクニカルな印象があります。意味としては「exchange ratio」と同じです。「merger ratio」という表現は一般的でないので注意してください。
「exchange ratio」「swap ratio」を使った例文は次のとおりです。
The merger exchange ratio was calculated based on the relative valuations of both companies.
合併比率は、両社の相対的な企業価値評価に基づいて算定されました。
In this share swap transaction, the swap ratio favors the acquiring entity slightly.
この株式交換取引では、合併比率がやや買収側に有利に設定されています。
「合併対価」の英語
合併対価とは、合併において消滅会社の株主が、保有株式と引き換えに受け取る見返りのことを指します。この対価は、存続会社の株式、現金、またはその組み合わせなど、さまざまな形態で支払われます。
合併対価の内容は、合併契約書に明記され、株主や規制当局の承認対象となることもあります。 「合併対価」は英語で「merger consideration」です。「consideration」は「考慮」以外にも、法律・ビジネスの文脈で「対価」や「報酬」という意味を持ちます。
「merger consideration」を使った例文は次のとおりです。
The merger consideration will be paid in the form of Company A’s common stock.
合併対価は、A社の普通株式として支払われます。
The type and amount of merger consideration must be approved by the shareholders of both entities.
合併対価の種類と金額は、両法人の株主による承認が必要です。
「略式合併」「簡易合併」の英語
略式合併とは、特別支配関係にある会社との吸収合併において、被支配会社(消滅会社)の株主総会の承認を省略できる制度です。手続きの簡素化を目的としており、企業グループ内での再編や完全子会社化といった場面で活用されます。
この略式合併が認められるのは、存続会社が消滅会社の議決権の90%以上を保有している場合、または消滅会社が存続会社の議決権の90%以上を保有している場合に限られます。いずれの場合も、会社間に強い支配関係があることを前提として、手続きの一部を省略することが可能になります。
「略式合併」は英語で、「short-form merger」 「parent-subsidiary merger」と表現されます。 ただし、 「parent-subsidiary merger」は一般的には親会社が子会社を吸収合併するなど親子関係に基づいた合併を指すため、完全に合致するわけではありません。誤解を避けるために補足説明が必要なこともあります。
ちなみに略式合併と要件が異なる「簡易合併」は米国には存在しないため、それに該当する英語はありません。ただし、州によっては簡易合併と似た制度も存在します。簡易合併を表現する場合は「simplified merger(簡略化された合併)」 や 「merger without shareholder approval(株主の承認が不要な合併)」などと説明されます。
「short-form merger」「parent-subsidiary merger」を使った例文は次のとおりです。
We plan to complete the restructuring through a short-form merger by the end of Q3.
第3四半期末までに、略式合併によって再編を完了する予定です。
The deal will proceed as a parent-subsidiary merger, requiring minimal internal approvals.
この取引は親子会社間の略式合併として進められ、社内承認は最小限で済みます。
「三角合併」の英語
三角合併とは、親会社の子会社(存続会社)が他の会社(消滅会社)を吸収合併する際、消滅会社の株主に対して、子会社ではなく親会社の株式を対価として交付する形です。
米国では「三角合併」は次の2種類に分かれています。
- forward triangular merger:親会社の子会社が被買収会社を吸収し、被買収会社は消滅
- reverse triangular merger:親会社の子会社が被買収会社に吸収されるが、親会社が実質的な支配権を得る(法的には被買収会社が存続)
reverse triangular mergerは「逆三角合併」と呼ばれており、アメリカの買収スキームの一つです。日本の「三角合併」は基本的に forward triangular merger に近いといえます。
例文は次のとおりです。
The acquisition was structured as a triangular merger, with the parent company issuing shares as consideration.
この買収は三角合併の形式で行われ、親会社が対価として株式を発行しました。
Many cross-border acquisitions use a triangular merger structure to provide tax or legal advantages.
多くのクロスボーダーM&Aでは、税務上または法的な利点を得るために三角合併の構造が採用されています。
M&Aは何の略?「買収」の英語表現
M&Aとは、「Mergers and Acquisitions」の頭文字をとった略語で、日本語では「合併と買収」と訳されます。日本では「M&A」という表現で広く使われており、ビジネスシーンやメディアでも一般的な用語として定着しています。
「買収」を意味する英語は「acquisitions」以外にも存在します。 「買収」を意味する英語は次のとおりです。
- acquisition
- takeover
- buyout
- buy up
- purchase
それぞれを詳しく解説します。
acquisition
「acquisition」は、企業や資産を取得することを意味し、最も一般的かつ中立的な「買収」の表現です。動詞は「acquire」です。
主に買い手側の立場で使われ、合意のうえで行われる友好的な買収を指すことが多く、企業の公式発表やビジネスニュースなどで頻繁に使われます。 株や持分の一度を買収する場合は「stake acquisition」という表現を使います。
例文は次のとおりです。
The company announced the acquisition of a smaller competitor.
その企業は、より小規模な競合会社の買収を発表した。
The tech giant announced a stake acquisition in the startup to strengthen their partnership.
その大手テック企業は、提携強化のためにスタートアップ企業の株式を取得したと発表した。
takeover
「takeover」も「買収」を意味しますが、「acquisition」よりやや支配的なニュアンスを持ち、買収される側や第三者の視点で語られることが多い表現です。 「敵対的買収」は「hostile takeover」と表現します。
例文は次のとおりです。
The takeover of the company sparked concerns among employees.
その企業の買収により従業員の間に不安が広がった。
The investor attempted a hostile takeover of the tech giant.
その投資家は、その大手テック企業に対して敵対的買収を試みた。
buyout
「buyout」も「買収」を意味する言葉の一つですが、特に経営権を完全に取得するタイプの買収を指す点が特徴です。単なる株式取得とは異なり、企業全体の支配権を買い取るニュアンスが強く、特に経営陣やオーナーの持分を買い取って完全に掌握するケースでよく使われます。
ビジネスの現場では「マネジメント・バイアウト(MBO)」や「レバレッジド・バイアウト(LBO)」といった専門用語とともに用いられることが多く、ファンドによる企業買収のニュースや投資家の動きを報じる記事などで目にする表現です。
例文は次のとおりです。
The private equity firm completed a buyout of the company, gaining full control.
そのプライベート・エクイティ企業はその会社の買収を完了し、完全な支配権を得た。
buy up
「buy up」はより口語的な表現で、「買収」というよりも「買い占める」「すべて買い取る」といった意味合いが強く、企業そのものよりも株式や資産を大量に購入する行為を表す際に使われます。会話やカジュアルな記事などで登場しやすい表現です。
例文は次のとおりです。
A foreign investor started to buy up shares of the company.
外国人投資家がその企業の株式を買い占め始めた。
purchase
「purchase」も「買収」や「取得」を表す英単語ですが、より一般的・広義の「購入」という意味合いが強く、M&Aの文脈では株式や資産など具体的な対象の取得を表現する際に使われます。「acquisition」に比べてややカジュアルな印象があり、公式な契約書やニュースリリースなどでも、「資産の購入」「株式の購入」といった具体的な行為を明示する場面で使用されます。
企業買収の一環としての株式取得や設備・ブランドなどの資産譲渡を説明する際にも用いられ、「purchase price(購入価格)」や「share purchase agreement(株式譲渡契約)」などの表現と組み合わせて登場することが多いです。
例文は次のとおりです。
The company completed the purchase of 100% of the target’s shares.
その企業は、対象企業の株式100%の購入を完了した。
他の業種で使う「合併」の英語表現
「合併」という言葉は他の業種でも使われます。ここでは、ビジネスシーン以外の「合併」の意味とその英語表現について詳しく解説します。
医療
医療の分野では、「合併症」という形で「合併」という言葉が使われます。これは、ある病気に関連して二次的に発生する別の病気や症状を指します。「合併症」を意味する英語表現は「complication」が一般的です。
例文は次のとおりです。
Pneumonia is a common complication of influenza.
肺炎はインフルエンザの一般的な合併症です。
地方自治体(政治)
地方自治体でも「合併」という言葉が使われます。複数の市町村が一つの行政体として統合されることを意味し、行政効率の向上や財政健全化などを目的として行われます。ここでの「合併」を意味する英語表現には「municipal merger」や「municipal consolidation」 があります。
例文は次のとおりです。
The municipal merger resulted in the creation of a new city administration.
その自治体の合併により、新たな市政が誕生した。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
合併を英語で表現する際には、「merger」や「consolidation」など、文脈に応じた適切な言葉を選ぶことが重要です。これらの用語を正しく理解し使いこなすことは、国際的なM&A交渉や経営戦略の成功につながります。
M&Aや経営課題に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。