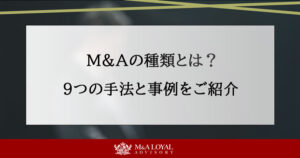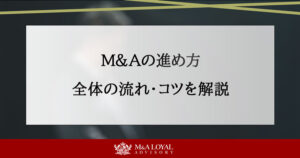M&A相談先の選び方|各機関の特徴や無料相談先を紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
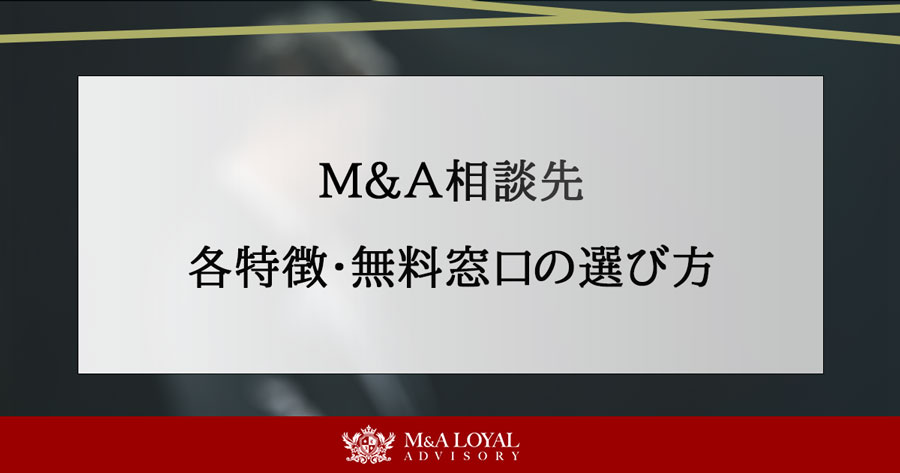
M&Aの相談先と言えば、M&A仲介会社や金融機関、弁護士、税理士など様々な選択肢が挙げられます。M&Aに初期的な関心がある、M&Aを検討したい、といった需要がある一方で、「どこに相談すれば良いのか」「無料相談はどこでできるのか」などが分からず、踏み出せない経営者の方も多いといいます。特にM&Aを検討しようにも、費用や手続きの流れ、相談先の信頼性など判断すべき要素が多く、不安を感じるのは当然のことです。
本記事では、M&Aの相談内容を売り手・買い手の立場別に整理し、相談先の種類ごとに特徴・費用・選定ポイントを丁寧に解説しています。さらに、実際に依頼する際に相談相手に伝えるべき情報や、スムーズな交渉・契約・統合に向けた準備の進め方まで、実践的な視点で紹介しています。
目次
M&Aの相談先・支援機関を一覧で解説
M&Aの相談先や窓口となる主な支援機関は次の通りです。
- M&A仲介会社
- 金融機関
- 税理士・公認会計士
- 弁護士
- ファイナンシャル・アドバイザー(FA)
- 商工会議所・商工会
これらの相談先について、それぞれのメリット・デメリットと費用の観点から解説します。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、M&Aを専門とする民間企業であり、売り手企業と買い手企業の間に立ち、両者の条件調整やマッチングを支援する役割を担います。初期相談から契約、クロージングまでの一連の流れをワンストップで対応する体制が整っています。
仲介会社を利用する最大のメリットは、案件情報の豊富さと専門性の高さです。売却希望企業の条件に合致する買収候補を、幅広いネットワークから提案できるため、短期間で効率的な交渉が期待できます。また、税務・法務の専門家との連携により、契約手続きや企業価値算定などの実務支援も充実しています。
さらに、料金体系は成功報酬型を導入しているケースが多く、初期コストを抑えて相談を始めやすい点も魅力です。例えば、M&Aロイヤルアドバイザリーの場合は、着手金・中間報酬・月額報酬など一切かかりません。オーナーには最後までM&Aを中止することができる権利がありますので、リスクなくM&Aを選択肢のひとつとして検討できます。
初期相談は無料のケースが多いですが、会社によっては着手金・中間報酬・成功報酬の全てが発生します。令和6年度以降、登録支援機関には報酬体系の開示が義務付けられており、手数料の透明性は以前より高まっています。相談先の選定時には、信頼性や担当者の実績を重視することが重要です。
金融機関
金融機関は、資金調達や財務に関する専門知識を有しており、M&Aにおいても重要な相談先の一つです。特に大手銀行や証券会社では、M&A専用の窓口や専門部署を設置し、買収資金の融資やM&A全体のアドバイザリーサービスを提供しています。また、地方銀行や信用金庫でも、中小企業向けのM&A支援を行う例が増えています。
金融機関に相談するメリットは、資金面のアドバイスが的確である点に加え、自社の財務状況を日常的に把握しているため、スムーズなコミュニケーションが期待できる点です。大手金融機関であれば、全国規模・グローバル規模のネットワークを活用したマッチング力にも優れています。
一方、対応する案件は一定以上の規模を前提とする場合が多く、小規模M&Aでは相談自体を受け付けないケースもあります。また、顧客の借入先であるがゆえに、M&A戦略をオープンにしづらい心理的ハードルも無視できません。加えて、手数料水準は高額で、機動的な対応にも限界があります。
相談料は初回無料としている金融機関が多いものの、実務に入るとアドバイザリー契約に基づく高額な報酬が発生します。メガバンクや外資系投資銀行では、成功報酬が数千万円から数億円規模となることもあります。
税理士・公認会計士
税理士や公認会計士は、企業の会計・税務に精通した国家資格者であり、M&Aにおける財務・税務デューデリジェンスや企業価値評価などの重要業務を担います。顧問契約を締結している場合は、既に自社の状況を深く理解しており、初動から専門的な支援が可能です。
これらの専門家に相談するメリットは、財務や税務の観点からリスク分析や適切なスキーム設計を行える点にあります。顧問先であれば、資料準備や対応が円滑に進む上、税制優遇措置の適用可否やM&A後の節税戦略などの助言も受けられます。
一方、M&Aに関する知見や実績が十分でないケースも存在します。特に、相手先の探索や契約交渉など、M&Aプロセス全般に対応できるとは限らず、サポート内容が限定的となる可能性があります。専門外の業務には他の支援機関と併用することが前提とされています。
初回相談は無料のケースが多く、顧問契約中であれば別途費用を要しない場合もあります。ただし、時間単位や業務内容に応じて料金が発生することもあるため、事前に契約条件を確認しておく必要があります。
弁護士
弁護士は、M&Aにおける契約書の作成・確認や法的リスクの把握といったリーガル面を担う重要な専門家です。近年では、中小企業向けM&Aにも対応する弁護士が増えており、顧問弁護士がいる場合には、事情を理解した上で法的支援を受けやすいです。
最大のメリットは、契約関係における適正性を担保し、トラブルの予防や発生時の対応が可能である点です。秘密保持契約書や株式譲渡契約書など、M&Aに不可欠な法的文書のチェックを任せることで、安心して交渉を進められます。また、弁護士は利益相反の観点から、売り手・買い手いずれか一方の利益に専属して行動します。
ただし、弁護士によってはM&A実務の経験が少なく、税務や財務面には対応できないこともあります。また、相手先の探索やスケジューリングなど、交渉以外の業務を含めたトータル支援は提供していない場合が大半です。
費用は30分〜1時間単位で、1時間あたり5,000円~5万円程度と幅広く、初回相談を無料としている事務所もあります。顧問契約がある場合には、定額の顧問料に含まれることもありますが、業務単位で追加費用が発生するケースもあるため契約内容の確認が不可欠です。
ファイナンシャル・アドバイザー(FA)
ファイナンシャル・アドバイザー(FA)は、資産運用や保険、相続などに関する相談に対応し、最適な解決策を提案する専門家です。中立的な立場から顧客の利益を最優先に考え、長期的な視点で資産形成を支援します。
M&AにおけるFAは、売り手または買い手のいずれかと専属契約を結び、利益の最大化を目的とした助言や交渉を担います。M&A仲介会社のように中立性を重視する立場とは異なり、特定のクライアントの利益に特化してサポートを提供することが特徴です。
FAに依頼する主なメリットは、自社の利益を最優先とした戦略的な交渉を進められる点にあります。また、スキーム設計や企業価値評価(バリュエーション)、条件交渉などにおいて高い専門性を有しています。
一方で、中立的でないがゆえに売り手と買い手の主張が対立し、合意までに時間を要する可能性がある点には注意が必要です。相談は無料で受けられるケースもあります。FAの費用や料金体系は依頼先によって異なるため、M&A仲介会社と比較して高いか低いかは一概にはいえません。
商工会議所・商工会
商工会議所や商工会は、地域経済の発展を目的とした公的機関であり、中小企業向けのM&Aや事業承継の相談窓口として機能しています。各都道府県には「事業承継・引継ぎ支援センター」が設置されており、これらの機関と連携しながら、マッチング支援などを提供しています。支援センターの設置主体は地域により異なり、商工会議所内に設置されている場合もあれば、産業振興財団などの外郭団体に置かれているケースもあります。
メリットは、地域密着型であり、地元企業の情報に精通していることです。助成金や補助金に関する知見が豊富で、M&Aに要する費用の軽減策についても相談可能です。中小企業に寄り添ったサポートを提供するため、安心して相談を始められる環境が整っています。
一方で、M&A実務に精通した担当者が常駐しているわけではなく、専門性の高い手続きや契約の対応には限界があります。また、支援センターを通じたマッチングは、地元中心のネットワークにとどまる傾向があり、条件に合致した企業を広範囲に探すには不十分なこともあります。
相談料は原則無料ですが、商工会・商工会議所の会員であることが前提となる場合もあり、その

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



M&Aに関するよくある相談内容【売り手企業】
M&Aを検討する際、どこに相談すべきかは売り手・買い手企業ともに大きな悩みの一つでしょう。特に初めてM&Aを検討する経営者にとっては、不安や疑問が多く、慎重な対応が求められます。
譲渡企業からよくある相談内容は次のとおりです。
- M&Aの実施可否と相談タイミング
- M&Aの進め方と専門家の必要性
- 買い手企業の探索とマッチングの可能性
- 売却価格・企業価値とデューデリジェンス
- 機密保持とM&A全体のスケジュール・コスト
それぞれの相談内容の詳細を解説します。
M&Aの実施可否と相談タイミング
「今すぐM&Aを進める予定はないが相談だけでも可能か」「後継者不在だが本当にM&Aという選択肢が現実的なのか」といった初期段階の相談が多く寄せられます。
実際には、M&Aを行うかどうか決めていない段階でも、情報収集や将来的な選択肢の整理のために専門家へ相談することは非常に有効です。相談を通じて自社の状況に合った選択肢を把握することが、後悔のない意思決定につながります。
M&Aの進め方と専門家の必要性
「M&Aアドバイザーや仲介業者は必ず必要なのか」「どのように交渉や手続きを進めるべきか」といった、進行プロセスに関する相談も多く見られます。中小企業では社内にM&A経験者がいないことがほとんどであるため、第三者のサポートは実務上不可欠です。
加えて、「契約書は誰が作成するのか」「行政手続きはどの段階で必要なのか」といった実務面の支援についても、専門家に依頼することで円滑に進められます。
買い手企業の探索とマッチングの可能性
「自社の希望に合う買い手が現れるのか」「従業員の雇用や取引先との関係を維持できるか」といった、譲渡先企業に関する不安や要望も、よくある相談の一つです。
信頼して事業を託せる相手企業を見つけるには、M&A仲介会社やアドバイザーの持つネットワークと経験が大きく貢献します。
特に地域密着型や業種特化型のマッチングにおいては、第三者の視点で客観的に判断してもらうことが重要です。
売却価格・企業価値とデューデリジェンス
「自社はいくらで売れるのか」「企業価値はどうやって決まるのか」といった価格面の相談は非常に関心が高い分野です。
M&Aでは営業利益や純資産を基に算定することが一般的ですが、実際には買い手との交渉によって価格が決まります。
また、買い手によるデューデリジェンス(詳細調査)を通じてリスクや価値が見直されるため、その準備方法や内容についても事前に理解しておくことが求められます。
機密保持とM&A全体のスケジュール・コスト
「従業員や取引先に知られずに進めたい」「どのタイミングで何を開示すべきか」といった機密情報の管理に関する懸念は多く、秘密保持契約(NDA)や初期段階での匿名交渉が推奨されます。
また、「M&Aにはどのくらいの期間がかかるのか」「総額でどの程度の費用が発生するのか」といった全体の見通しに関する質問も頻出です。
一般的には半年から1年程度が目安で、仲介手数料・専門家報酬・税務関連費用などを含めた資金計画も必要です。
M&Aに関するよくある相談内容【買い手企業】
M&Aの相談内容は売り手と買い手にとって異なります。買い手企業にとってのM&Aは、戦略的成長の一手として重要な意思決定を伴います。初めてのM&Aに臨む企業からは、計画段階から実行・統合まで幅広い相談が寄せられています。
譲受企業からよくある相談内容は次のとおりです。
- M&Aの目的と戦略の妥当性
- 対象企業の選定とマッチング
- 買収資金・費用と調達方法
- 買収プロセス・必要準備・期間
- PMI(経営統合)とM&A後の運営
それぞれの相談内容の詳細を解説します。
M&Aの目的と戦略の妥当性
「自社の成長戦略としてM&Aは適切か」「新規事業進出の手段として有効か」など、M&Aを行う意義や方針についての相談が初期段階でよく見られます。
特に初めてM&Aを検討する企業では、自社にとっての最適なM&A活用法を理解するために、専門家の意見を求めるケースが多いです。
対象企業の選定とマッチング
「どのような企業を買収すべきか」「条件に合う売却企業を紹介してほしい」といった相談も多く、買い手企業にとっては、戦略と合致する譲渡先をいかに見つけるかが重要な課題です。
業種・地域・規模・シナジーなど多面的な観点から、候補企業を絞り込むサポートが求められます。
買収資金・費用と調達方法
「どの程度の買収資金が必要なのか」「M&Aの支援費用や成功報酬はどれくらいかかるのか」といった費用面の相談も非常に多く見られます。
M&Aには企業価値に応じた買収資金の他、M&A仲介会社への報酬や専門家費用などの付帯コストが発生します。資金調達方法としては、自己資金・金融機関からの借り入れ・ファンドの活用などがあり、それぞれのスキームに適した調整が必要です。
買収プロセス・必要準備・期間
「M&A完了までにどれくらいの期間がかかるのか」「どんな書類を準備すべきか」など、進行全体に関する相談も頻出です。
通常、M&Aは数カ月から1年程度の期間を要し、基本合意・デューデリジェンス・最終契約など多段階のプロセスを経て進みます。初めてM&Aに取り組む企業では、専門家の支援を受けながらスケジュールを可視化し、段階的に準備を進めていくことが不可欠です。
PMI(経営統合)とM&A後の運営
「買収後の統合作業をどう進めれば良いか」「従業員やシステムの統合はどうするか」といった、M&A成約後のPMI(Post Merger Integration)に関する相談も多く寄せられます。
PMIでは業務プロセス・ITシステム・組織構造・人事制度などの統合に加え、従業員のモチベーション管理やブランド価値の維持といったソフト面の対応も求められます。M&Aを成功させるには、事後の体制整備を見据えた準備が不可欠です。
M&Aの相談先を選ぶ際のポイント
M&Aの相談先の選定が、取引を成功に導くために極めて重要です。専門性や対応力、費用の妥当性など、複数の観点から総合的に判断する必要があります。
M&Aの相談先を選ぶ際に押さえておくべき五つの主要なポイントは次のとおりです。
- 実績と専門性の有無
- サービス内容と対応範囲
- 費用体系と報酬の妥当性
- 信頼関係と相談体制
- スピード感と情報管理の適切さ
それぞれを詳しく解説します。
実績と専門性の有無
相談先の実務経験と専門性は、M&Aを的確かつ円滑に進めるための基盤です。過去の成約件数や支援実績、同業種・同規模の案件での成功事例の有無を確認しましょう。
また、財務・法務・税務など各分野における専門性も重要です。特にデューデリジェンスや契約書の作成など、プロセスごとに必要な知見が異なるため、対象分野に強みを持つ専門家が関与しているかを見極めることが不可欠です。
サービス内容と対応範囲
相談先が提供する支援内容が、自社のニーズと一致しているかを確認しましょう。初期相談から交渉、契約締結、統合後のPMIまで一貫してサポートしているかは重要な判断材料です。
また、M&Aに従事する会社の中には特定業種や企業規模に特化した支援を行っているケースもあり、自社との親和性を重視することでより効果的なサポートが期待できます。
サービスの範囲が曖昧な場合は、契約前に支援対象の工程や内容を明確に確認する必要があります。
費用体系と報酬の妥当性
M&Aにおける報酬体系は相談先によって異なり、内容が不明確なまま進めると後のトラブルにつながります。各費用項目の有無や金額、発生のタイミング、算出根拠についても事前に明示されているかを確認しましょう。
M&Aの主な費用体系は次のとおりです。
- 相談料:初回相談は無料のケースが多いですが、一部では数万円の費用が発生する場合もあります。
- 着手金:業務開始時に支払う手数料で、相場は50万〜200万円です。成約の有無にかかわらず返金されないことが一般的です。
- 中間報酬:基本合意締結時に支払う費用で、成功報酬の10〜20%程度が目安です。不成立でも原則として返金されません。
- 調査費用:財務・法務・税務に関するデューデリジェンスの実施費用で、200万〜300万円が標準的な相場です。
- 成功報酬:M&A成約時に支払う成果報酬で、一般的にはレーマン方式に基づいて算出されます。
- リテイナーフィー:月額で支払う固定報酬です。導入していない仲介会社もあります。
レーマン方式とは、取引金額を段階的に区分し、それぞれの金額帯に応じた料率を掛けて報酬を算出する仕組みです。例えば、5億円以下は5%、5億円超〜10億円以下は4%、10億円超〜50億円以下は3%といった形で、金額が大きくなるほど料率が下がる点が特徴です。
報酬額は、単に安さで比較するのではなく、提供される支援の質や成果とのバランスが取れているかを基準に判断するべきです。複数の相談先から見積もりを取得し、条件や実績を比較検討することが望まれます。
信頼関係と相談体制
法人としての信頼性だけでなく、実際に対応する担当者の資質もM&Aの成否に大きく影響します。M&Aでは長期にわたり密な連携が必要となり、財務や経営に関する機微な情報も共有します。初回相談の段階で、親身な対応があるか、質問に対して明確で実務的な回答が得られるかなどを見極めておきましょう。
また、内容によっては相談先を複数に分ける選択も考えられますが、安易に多くの機関へ同時に相談することは避けるべきです。同じ内容でも立場によって見解が異なることがあり、判断がぶれる原因となる他、複数の外部に機密情報を開示することで、情報漏えいのリスクが高まります。
信頼できる相手を見極めた上で、相談先を適切に絞り、情報の取り扱いも含めて慎重に進めましょう。
スピード感と情報管理の適切さ
M&Aにはタイミングが重要であり、相談先の対応スピードは成否に直結します。連絡のレスポンスや進捗(しんちょく)報告が遅れると、交渉相手との信頼関係にも悪影響を及ぼします。初期の段階から、相談対応の迅速さや段取り力を確認しておきましょう。
同時に、M&Aの相談では自社の重要な経営情報を扱うため、情報漏えいへの配慮も不可欠です。信頼性の低い相手に安易に情報を渡すのではなく、正式な依頼の際は必ず秘密保持契約(NDA)を締結し、その上で必要な情報を段階的に開示していくことが基本です。
M&Aを相談する際に必ず伝えるべきこと【売り手】
M&Aに関する相談をする際に相談相手に伝えるべき内容をお伝えします。まず、売却を検討する際に伝えるべき主な五つのポイントは次のとおりです。
- 事業内容と強みの明示
- 組織体制と従業員構成
- 財務状況と希望条件
- 株主構成と意思決定の可否
- 過去のトラブルやリスク要因
それぞれのポイントについて解説します。
事業内容と強みの明示
まず、事業の内容やビジネスモデルを具体的に説明することが重要です。業界の成長性や競争環境、主要な収益源、製品・サービスの独自性といった要素は、企業価値を判断する上で重要な判断材料とされます。
取引先や技術が特定の個人に依存している場合は、買い手にとってリスクとなるため、属人性の有無や、これに対する組織的な対応状況も共有しておくべきです。
組織体制と従業員構成
次に、組織構造や人員体制について正確に伝えましょう。経営幹部やキーパーソンの役割、従業員数、年齢構成、スキルセットなどは、買い手がポストM&Aを見据える上での判断材料です。
特に、経営者が引退を予定している場合は、後継体制や権限移譲の準備状況も併せて伝える必要があります。
財務状況と希望条件
売却希望額や譲渡に際しての条件(雇用の維持や社名の継続など)がある場合は、明確に伝えておく必要があります。
さらに、直近数期分の決算書や財務諸表を提出することで、アドバイザーが企業価値を概算し、希望条件との整合性を評価できます。財務面の透明性は、買い手からの信頼獲得にもつながります。
株主構成と意思決定の可否
株主の構成や議決権の集中状況もM&Aの可否を左右する要素です。
例えば、株主が多数存在し意見が分かれている場合、スムーズな譲渡が困難になる可能性があります。相続や持株会の存在など、特殊な株式保有状況がある場合も含め、あらかじめ詳細を共有しておきましょう。
過去のトラブルやリスク要因
相談先は、将来の買い手が懸念を持ちうるリスク要因も把握しておく必要があります。過去の訴訟や行政指導、財務上の不正、顧客との契約トラブルなど、ネガティブな情報も含めて正確に開示しましょう。
事前にリスクを整理し、対応策を講じておくことは、交渉の信頼性を高める上で重要な要素と位置付けられます。
M&Aを相談する際に必ず伝えるべきこと【買い手】
買収を検討する企業にとっても、初期段階で適切な情報を共有することは、M&Aの成功確率を高める上で重要です。
買い手側が相談時に伝えるべき五つのポイントは次のとおりです。
- 買収対象の条件とニーズ
- 資金力と取引スキームの希望
- M&A後の運営方針
- マネジメント体制と受け入れ準備
- 買収判断における重視点と懸念点
それぞれのポイントを解説します。
買収対象の条件とニーズ
まず、どのような企業を買収したいのかを明確にしましょう。具体的には対象業種やエリア、企業規模、事業内容などです。
M&Aの目的(新規市場参入や既存事業とのシナジー創出、人材獲得など)とともに伝えることで、候補企業の選定精度が高まります。
資金力と取引スキームの希望
買収にあたって用意している資金規模や自己資金・借入金の構成、予算上限などの情報も重要です。
加えて、株式譲渡や、事業譲渡、合併といった希望するスキームがある場合は、それも明示してください。資金面の透明性が高いほど、交渉の信頼性も高まります。
M&A後の運営方針
買収後の経営スタンスについても明確に伝える必要があります。例えば、現経営陣を継続させる方針か、自社の経営陣を派遣する予定かによって、売り手側の受け入れ姿勢が変わります。
従業員の処遇や企業文化の統合方針なども含めて説明することで、売却先との相互理解が深まります。
マネジメント体制と受け入れ準備
買収後の経営体制をどのように構築するかも重要な情報です。
誰を経営に関与させ、どのようなマネジメントを行うのか、また社内でのPMI(統合プロセス)をどのように進めるのかを具体的に共有することで、売り手の不安を和らげる効果があります。
買収判断における重視点と懸念点
買収判断において重視している要素(技術や人材、顧客基盤、ブランドなど)や、過去のM&Aで懸念された事項があれば、率直に伝えておくことが望まれます。
これにより、候補先の選定および情報開示に際して、的確な調整を講じやすくなります。
M&Aを円滑に進めるコツ
M&Aは相談した後がスタートです。M&Aは事前準備から交渉、契約、統合に至るまで多岐にわたる工程を含むプロジェクトのため、スムーズに進行させるためには、各フェーズで適切な対策を講じることが重要です。
M&Aを円滑に進めるために売り手・買い手の両者にとって押さえるべきポイントは次のとおりです。
- 目的と希望条件を明確にする
- 自社の現状を客観的に把握しておく
- 信頼できる相談先を選定する
- 情報の開示と整備を怠らない
- 長期的な視点で進行計画を立てる
それぞれを分かりやすく解説します。
目的と希望条件を明確にする
M&Aの検討を始める段階では、自社がM&Aに何を求めているのかを明確にすることが出発点です。
譲渡対価の最大化や、事業拡大、経営資源の獲得、従業員の雇用維持など、目的によって最適な手法や相手先が異なります。特に、譲れない条件については、優先順位をつけて整理しておくことで、交渉段階でもブレずに対応できます。
さらに、M&Aの目的は単一ではなく、複数の目標が複雑に絡み合っている場合が多いため、あらかじめ短期的な成果と長期的な経営ビジョンの両面から整理しておくことが重要です。
目的と条件が曖昧なままでは、交渉の方向性が定まらず、かえって意思決定を遅らせる要因となり得ます。
自社の現状を客観的に把握しておく
M&Aの交渉では、相手企業に対して自社の状況を正確かつ客観的に説明する必要があります。事業内容や組織構成、財務状況、経営課題などを整理し、資料として準備しておきましょう。
特に財務面については、直近数期分の決算書や資産負債の内訳など、根拠となる数値情報を把握しておくことが求められます。加えて、営業実績や収益構造の変化、重要顧客との取引継続性など、定量・定性の両面から全体像を明らかにする必要があります。
将来的な成長可能性や事業リスクを含めて可視化しておくことで、買い手からの信頼性が大きく高まります。
信頼できる相談先を選定する
M&Aには財務・法務・税務など多分野にわたる専門知識が必要です。これらを的確にカバーできる専門家や仲介会社を選ぶことが、プロセス全体の質に直結します。
単に知見を有しているだけでなく、企業ごとの状況に応じた提案や助言ができることや、親身かつ誠実な対応が期待できることも重視すべき要素です。複数の相談先を比較検討し、相性も含めて総合的に判断しましょう。
加えて、報酬体系の透明性や契約形態(成功報酬型・固定報酬型など)も事前に確認しておくことで、費用面でのトラブルを防止できます。M&Aの進行は長期にわたるため、単発的なアドバイスだけでなく継続的な支援体制が整っているかも見極めるべき重要なポイントです。
情報の開示と整備を怠らない
交渉やデューデリジェンスの段階では、情報開示の正確性とタイミングが成否を左右します。重要な財務・法務情報を事前に整理し、第三者から見ても一貫性のある形で提供できる状態を整えておくことが大切です。
開示にあたっては、情報漏えいのリスクに配慮し、NDA(秘密保持契約)を締結した上で進めると良いでしょう。また、情報提供においては資料の信頼性と網羅性が求められるため、抜けや誤解のない説明を行うための事前準備が不可欠です。
特に、買い手が懸念しやすい契約関係・債務状況・訴訟履歴などの情報は、初期段階から整理しておくことで、後のリスク評価において有利に働く可能性があります。
長期的な視点で進行計画を立てる
M&Aは、検討から成約まで数カ月から1年以上を要することが一般的です。短期的な成果を焦るのではなく、中長期的な企業価値の最大化を視野に入れて計画を立てましょう。
必要に応じて社内体制を整えたり、関係者の理解を得たりするための時間も考慮して、余裕を持ったスケジューリングを行うことが重要です。
また、想定外の事態や交渉の停滞に備え、複数のシナリオを描いた上で柔軟に対応できる体制を構築しておくことが望まれます。M&A後の統合プロセス(PMI)までを見据えたロードマップを描いておくことで、買い手からの評価向上にもつながります。
M&Aの相談に関するQ&A
最後に、M&Aに関するよくある質問とその回答を紹介します。
M&Aの相談はどのタイミングで始めるべきか
明確な売却・買収の意思が固まっていなくても、将来的な選択肢として検討している段階から相談することがおすすめです。早期に相談することで、自社の状況整理や準備が進めやすくなり、希望条件に沿った相手先とマッチングできる可能性も高まります。
M&A無料相談ではどのような支援・サポートを受けられるか
相談先によって内容は異なりますが、M&Aの無料相談では、自社が売却や買収に適しているか、またそのタイミングが妥当かといった初期的な判断材料を得られます。加えて、企業価値の目安や希望条件に合う相手の有無、M&Aの進め方や全体の流れ、必要な準備事項、費用体系の概要なども確認可能です。
無料相談はあくまで情報収集や方向性確認を目的としたものであり、実務フェーズは原則として有料です。そのため、まずはリスクなく専門家に相談し、今後の判断材料とすることが効果的です。
会社の規模が小さい場合はどこに相談するべきか
小規模事業者の場合は、地域の商工会議所や「事業承継・引継ぎ支援センター」などの公的機関が適した相談先です。費用負担が少なく、M&Aの初期段階から専門家による支援が受けられます。
また、事業規模に合ったマッチング支援を行っているM&A仲介会社も有効です。
M&Aで売却を検討しているが負債があっても問題ないか
負債がある企業でも、事業に将来性や独自の強みがあれば、買い手が見つかる可能性は十分にあります。負債の有無だけで判断せず、まずは自社の価値を客観的に評価してもらうために相談してみることをおすすめします。
M&A相談をすると、必ず譲渡・売却をしなくてはいけないのか
相談段階では方針の確認や選択肢の整理が主目的です。内容を聞いた上で、M&A以外の選択肢を採る判断もできますので、気軽に相談して問題ありません。
商工会議所と事業引継ぎ支援センターの違いは何か
商工会議所は地域の中小企業を幅広く支援する機関で、M&Aは主に初期相談や他機関の紹介を担当します。
一方、事業引継ぎ支援センターは事業承継・M&A支援に特化しており、専門家による実務的なアドバイスやマッチング支援を行います。具体的な支援を受けたい場合は、引継ぎ支援センターが適しています。
M&Aのデメリットは何か
M&Aは事業成長や承継の手段として有効ですが、売り手・買い手それぞれに特有のリスクがあります。
具体例は次のとおりです。
売り手
- 買い手が見つからない可能性がある
- 希望条件で売却できない場合がある
- 情報漏えいや社内混乱が発生するリスクがある
買い手
- 統合後の組織運営がうまくいかないリスクがある
- 簿外債務や偶発債務を引き継ぐ可能性がある
- 許認可や契約の承継が困難な場合がある
売り手企業にとって、M&Aのプロセスは慎重に進める必要がありますが、買い手企業にも多くの課題が待ち受けています。売り手と買い手、両者がM&Aのメリットとデメリットを理解することが大切です。
まとめ
M&Aのよくある質問の一つに「どのようにして信頼できるアドバイザーを見つけるか」というものがあります。信頼できるアドバイザーを選ぶ際には、実績や専門性、そして過去のクライアントからの評価を確認することが大切です。また、アドバイザーがあなたの業界やビジネスモデルに精通しているかどうかも重要なポイントです。最終的には、アドバイザーとのコミュニケーションが円滑に行えるか、信頼関係を築けるかどうかが成功の鍵となります。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは着手金無料で初期の相談にも対応しています。M&Aや経営課題に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。