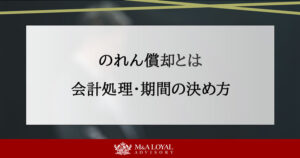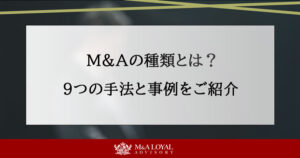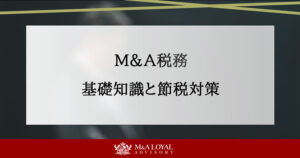のれん代とは?償却期間や会計処理、M&A成功の実務ポイントを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
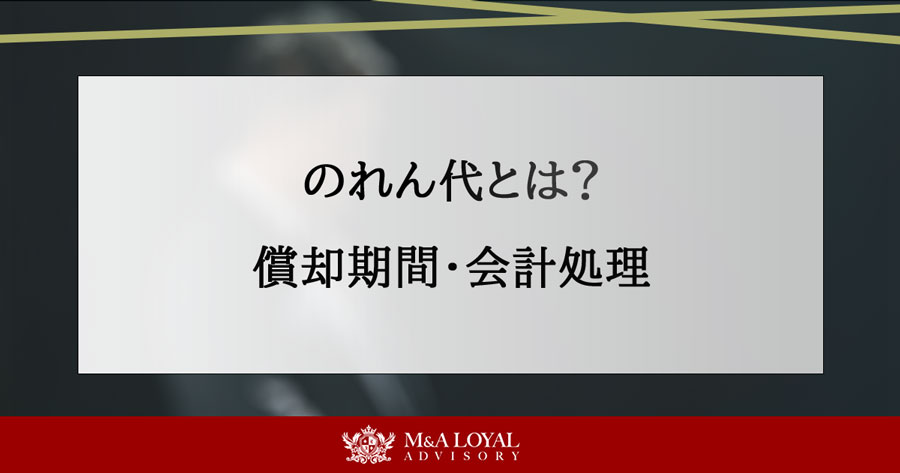
M&Aを検討する企業にとって、「のれん代」の理解は欠かせません。のれん代は単なる会計上の数字ではなく、M&A価格の決定、税務戦略、買収後の財務状況に大きな影響を与える重要な要素です。しかし、「なんとなく理解しているつもりだが、詳細はよくわからない」という経営者も少なくありません。
本記事では、M&Aにおけるのれん代の基礎知識から実務的な活用法まで、体系的に解説します。のれん代の定義や発生メカニズム、計算方法、そして日本基準とIFRSの会計処理の違いや税務上の取り扱いなど、M&Aにおいて特に重要なポイントを中心に詳しく説明します。
適切なスキーム選択による節税効果や、のれん代を活用したM&A交渉術など、実践的な内容も網羅しています。経営者やM&A実務担当者に役立つ情報を、わかりやすくお届けします。
目次
のれん代とは
M&Aを検討する際に必ず理解しておきたい「のれん代」は、M&Aの成否を左右する重要な要素です。
のれん代の定義
のれん代とは、「M&A価格とその事業に係る時価純資産との差額」を指します。のれん代とは、「M&A価格(取得対価)とその事業に係る識別可能な純資産の公正価値(時価)との差額」を指します 。会計などで用いられる「のれん」は、企業のブランド力、顧客との良好な関係、保有する特許やノウハウ、従業員の技術力、組織風土など、個別に識別して分離して認識することができない将来の経済的便益をもたらす無形資産の集合体であり、「超過収益力」の源泉とも言えます 。
例えば、時価純資産が1億円の企業を1億5千万円で買収した場合、その差額の5千万円がのれん代となります。これは貸借対照表上に明示されていない価値であり、企業の持つ無形の資産価値です。
のれんという言葉の由来は、お店の軒先に掲げられる暖簾(のれん)からきており、その店の象徴や信用力を表すものです。
のれん代が発生する仕組み
企業の事業価値は、個々の資産が独立して生み出す価値の単純合計ではありません。有形資産だけでなく、ブランド力、技術力、顧客関係、従業員のスキルなど、目に見えない無形資産が一体となって収益を生み出しています。
例えば、老舗飲食店の真の価値は、不動産や設備だけでなく、長年培ってきたレシピ、常連客との関係、地域での評判、従業員の技術など無形の要素から大きく生まれています。M&Aでは、これらの無形資産を含む経営資源の全体を一度に取得できる点が魅力です。
重要なのは、のれん代は買い手の主観で決まるという点です。同じ企業でも、買い手によって評価額が大きく異なる場合があります。
中小企業M&Aにおけるのれん代の特徴と重要性
中小企業M&Aにおけるのれん代は、企業が長年かけて築き上げてきた収益力やブランド価値、顧客基盤などの無形資産を表す重要な指標です。具体的には、買収価格が対象企業の純資産額を超えた部分として計上されます。大企業のM&Aと比較した特徴としては、評価手法として「コストアプローチ」が多く用いられること、オーナー個人の能力や人脈に依存する部分が大きいため評価が難しい場合があることなどが挙げられます。
のれん代が重要な理由:
- 適正な企業価値評価のカギとなる
- M&A価格交渉の重要な材料となる
- 税務上のメリットを得られる可能性がある
- スキーム選択に影響する
中小企業のM&Aでは、税務上のメリットを享受できるスキームとして「事業譲渡」や「非適格分社型分割」が選択されることがあります。これらのスキームでは、税務上の「のれん」に相当する「資産調整勘定」が認識され、原則として5年間で均等償却することにより損金算入が可能となり、節税効果が期待できます 。
負ののれん代とは
通常、M&A価格は対象企業の時価純資産を上回りますが、逆に下回る場合もあります。このとき発生するのが「負ののれん代」です。
負ののれん代が発生する主な理由には、業績不振や将来的な収益性の低下、訴訟リスクや偶発債務の存在、不動産や設備の含み損などがあります。
中小企業M&Aでは、雇用維持や取引先との関係を重視するためにあえて純資産以下の価格でM&Aを行うケースも見られます。例えば、後継者不在で廃業を検討している企業が、従業員の雇用や取引先との関係を守るために、純資産よりも低い価格で売却することがあります。
日本の会計基準では、負ののれん代は特別利益として一括利益計上します。税務上、負ののれんに相当するものは「差額負債調整勘定」として扱われ、会計上の即時利益認識とは異なり、原則として5年間で均等に益金として算入されます 。なお、会計上の負ののれんの額と税務上の差額負債調整勘定の額は、評価方法の違いなどから必ずしも一致するわけではない点に留意が必要です 。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



のれん代の計算方法
のれん代の計算方法を理解することは、M&Aにおいて適正な企業価値を把握するために不可欠です。
基本の計算式
のれん代の基本的な計算式は以下の通りです。
のれん代 = M&A価格(買収価額)- 対象企業の時価純資産額
時価純資産額とは、資産の時価評価額から負債の時価評価額を差し引いた金額です。簿価と時価には差があることが多く、例えば不動産では含み益や含み損が発生していることもあります。
具体例:
- 買収価額:1億円
- 簿価純資産額:5,000万円
- 土地の含み益:2,000万円
- 時価純資産額:7,000万円
- のれん代:1億円 – 7,000万円 = 3,000万円
この3,000万円が企業のブランド力、技術力、顧客基盤などの無形資産に対して支払われた金額となります。
主要アプローチであるインカム法とコスト法の違い
企業価値を評価する主な方法には「インカムアプローチ」「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」があります。
| 評価アプローチ | 特徴 | 主な手法 | 適した企業 | メリット | デメリット |
| インカムアプローチ | 将来の収益性に基づく評価 | DCF法、マルチプル法 | 成長企業、安定収益企業 | 将来性を反映、企業固有の価値を評価可能 | 予測に依存し主観的になりやすい |
| コストアプローチ | 純資産価値に着目した評価 | 簿価純資産法、時価純資産法 | 資産型企業、中小企業 | 客観的評価が可能、理解しやすい | 将来性を反映しにくい |
| マーケットアプローチ | 市場での取引事例や類似企業との比較に基づく評価 | 類似会社比較法(マルチプル法など) | 上場企業、類似取引事例がある企業 | 市場評価を反映、比較的客観的で理解しやすい | 適切な類似企業や取引事例がない場合適用困難 |
インカムアプローチ(収益アプローチ)
DCF法では、将来の事業計画に基づいてキャッシュフローを予測し、適切な割引率で現在価値に割り引いて企業価値を算出します。将来性や成長性を反映できる一方、予測に依存するため評価が主観的になりやすい点が特徴です。
コストアプローチ
純資産価値に着目した評価手法で、貸借対照表の数字をベースにするため客観的な評価が得られやすく、経営者にも理解されやすいという特徴があります。中小企業のM&Aではコストアプローチがベースとなることが多いですが、将来の収益性を十分に反映できない点が課題です。
マーケットアプローチ
市場での取引事例や類似企業との比較に基づく評価手法で、類似会社比較法(マルチプル法)や類似取引比較法などが代表的な手法です。株価や財務指標など公開データを使用するため客観性が高く、市場評価を反映できる一方、適切な類似企業や取引事例がない場合には適用が困難となります。また市場の変動に左右されやすく、企業固有の特性を十分に反映しにくい点が課題です。
具体的なシミュレーション
超過収益法によるのれん代の計算例
- 対象会社の正常利益を算出:2,000万円
- 一般的な期待利益を算出:純資産5億円 × 業界平均ROE2% = 1,000万円
- 超過利益 = 正常利益 – 一般的な期待利益 = 1,000万円
- のれん代 = 超過利益 × 3年 = 3,000万円
年買法によるのれん代の計算例
のれん代 = 税引後の正常利益 × 年数 例:税引後正常利益1,500万円 × 3年 = 4,500万円
DCF法による企業価値算定例
- 将来5年間のフリーキャッシュフロー予測と現在価値への割引
- 継続価値(ターミナルバリュー)の計算
- 企業価値の算出:フリーキャッシュフローの現在価値 + 継続価値
- のれん代 = 企業価値 – 時価純資産額
これらの方法はあくまで目安であり、実際のM&Aでは複数の手法を用いて総合的に評価することが重要です。
・のれん代評価の考慮要素:
- 財務デューデリジェンスの結果
- 時価評価による含み損益
- 業界動向や競合状況
- 買い手にとっての戦略的価値(シナジー効果)
- オーナー経営者への依存度
のれん代の会計処理と税務上の取り扱い
のれん代の会計処理と税務上の取り扱いは、M&Aにおける重要な検討要素です。
会計処理|日本基準とIFRSの違い
のれん代の会計処理は、適用する会計基準によって大きく異なります。
| 項目 | 日本基準 | IFRS(国際会計基準) |
| のれんの償却 | 20年以内の定額法償却が必要 | 償却なし |
| 減損テスト | 減損の兆候がある場合に実施 | 毎年必ず実施 |
| 減損の検討方法 | 2段階アプローチ | 1段階アプローチ |
| 負ののれんの処理 | 一括で特別利益計上 | 発生時に利得として一括認識(IFRSには営業利益と特別利益の明確な区分なし) |
| 利益への影響 | 毎期安定的な償却費計上 | 減損時に大きな損失計上の可能性 |
日本基準での会計処理
日本の会計基準では、のれんは無形固定資産として計上され、20年以内の期間で定額法による償却が必要です。実務上は投資回収期間を考慮して5〜10年程度の期間で償却するケースが多いです。
のれん償却費は販売費及び一般管理費に計上され、営業利益に影響します。減損の兆候がある場合には減損テストを実施します。
IFRS(国際会計基準)での会計処理
IFRSでは、のれんの規則的な償却は行わず、毎年一度の減損テストが義務付けられています。のれんの価値が低下した場合にのみ減損処理を行う点が日本基準との大きな違いです。
税務処理|資産調整勘定としての実務対応
税務上、会計上の「のれん」に直接対応する資産分類は存在しません。M&Aのスキームによっては、買収対価が被買収企業の純資産の税務上の評価額を上回る場合に「資産調整勘定」が認識され、これが税務上の正ののれんに相当します 。逆に下回る場合には「差額負債調整勘定」が認識され、これが税務上の負ののれんに相当します 。
資産調整勘定(税務上の正ののれん)
税務上の「のれん」(資産調整勘定)は、原則として5年で均等償却を行い、損金算入されます。この償却は法人税法上の強制償却であり、会計上の処理の有無に関わらず、税金計算上の費用として認められます。
負債調整勘定(税務上の負ののれん)
負債調整勘定は以下の3つに分類されます。
- 退職給与負債調整勘定
- 短期重要負債調整勘定
- 差額負債調整勘定
このうち、差額負債調整勘定は5年間で均等に益金の額に算入されます。
具体的な仕訳例
事業譲渡の場合
(事業譲渡対象資産:1,000、負債:700、のれん:200、譲渡対価:500)
| 仕訳(譲渡企業側) | 借方 | 貸方 |
| 負債 700 現預金 500 | 資産 1,000 譲渡益 200 |
| 仕訳(譲受企業側) | 借方 | 貸方 |
| 資産 1,000 のれん 200 | 負債 700 現預金 500 |
非適格分社型分割の場合
(分割対象資産:1,000、負債:700、のれん:200、譲渡対価:500)
| 仕訳(譲渡企業側 – 分割時) | 借方 | 貸方 |
| 負債 700 子会社株式 500 | 資産 1,000 譲渡益 200 |
| 仕訳(譲渡企業の子会社側) | 借方 | 貸方 |
| 資産 1,000 のれん 200 | 負債 700 資本金等の額 500 |
のれん償却の仕訳
日本基準での償却(例:10年で償却、のれん200の場合):
・(借方)のれん償却費 20 (貸方)のれん 20
・税務上の償却(5年均等償却、のれん200の場合):年間償却額は40
のれん代償却の節税効果
税務上の「のれん」(資産調整勘定)は5年間で損金算入できるため、重要な節税効果をもたらします。
節税効果の計算
・節税効果 = のれん代 × 法人税等の実効税率(約34%)
・例えば、のれん代200万円の場合、節税効果は約68万円となります。
この節税メリットはM&A価格の交渉において活用できます。例えば、M&A価格を節税効果分だけ上げても、買い手側の実質負担額を抑えられる可能性があります。
ただし、この節税効果を得るためには、適切なM&Aスキーム(事業譲渡や非適格分社型分割)を選択する必要があります。株式譲渡では税務上ののれんは発生せず、節税効果も得られません。
のれん代と国際会計基準(IFRS)
グローバル化が進む現代のビジネス環境において、国際会計基準(IFRS)ののれん代処理に関する知識は、海外企業とのM&Aや国際的な事業展開を検討している企業にとって重要です。日本基準とIFRSではのれん代の処理方法に大きな違いがあり、これがM&A戦略や財務報告に影響を与えます。
国際会計基準ののれん代処理|日本基準との重要な違い
IFRS(国際財務報告基準)と日本基準ののれん代処理には重要な違いがあります。最も大きな違いは、IFRSではのれんの規則的な償却を行わない点です。
IFRSでは、のれんは経済的便益が企業に流入すると考えられるため、毎期の償却は行わず、減損が認められた場合にのみ減損処理を行います。減損テストは毎年必ず実施する必要があり、減損の兆候があれば追加で実施します。
減損テストの方法も異なります。日本基準が2段階アプローチなのに対し、IFRSは1段階アプローチを採用しています。これにより、IFRSでは減損損失がより早期に認識される傾向があります。
IFRSを採用すると、のれんの非償却により短期的には利益が増加しますが、減損リスクも高まります。減損が発生すると一度に大きな損失を計上することになるため、業績の変動が大きくなる可能性があります。
IFRS採用企業の最新動向
日本でIFRSを採用する企業は増加傾向にあり、特に国際的な事業展開をしている大企業で採用が進んでいます。IFRS採用のメリットとしては、グローバルな比較可能性の向上、海外投資家からの評価向上、海外企業との合併・買収の容易化などが挙げられます。
特にM&Aを積極的に行う企業はIFRSを採用する傾向があります。のれんの非償却により短期的な利益増加効果がありますが、将来的な減損リスクにも注意が必要です。
クロスボーダーM&Aにおけるのれん代の取り扱い
クロスボーダーM&A(国境を越えたM&A)では、会計基準の違いが重要な課題となります。海外企業を買収する場合、対象企業がどの会計基準を採用しているかを事前に把握することが重要です。
日本基準を採用している企業がIFRS採用企業を買収する場合、のれんの償却方法の調整、公正価値評価の範囲の違い、減損テストの方法の違いなどが主な論点となります。
クロスボーダーM&Aでは、会計・税務面の複雑さから専門家との緊密な連携が不可欠です。のれん代の処理方法の違いを理解し、適切に対応することで、クロスボーダーM&Aの成功確率を高めることができます。
のれん代とM&Aスキーム
M&Aスキーム(手法)の選択によって、のれん代の会計・税務上の取り扱いが大きく異なります。
株式譲渡とのれん代|会計・税務上の影響と特徴
株式譲渡は中小企業M&Aで最も多く採用されるスキームです。会社自体の所有権(株式)を譲渡する方法で、資産・負債をまとめて移転できます。
株式譲渡の場合、個別財務諸表上ではのれんは発生せず、買収対価の全額が「子会社株式」として資産計上されます。連結財務諸表作成企業(主に上場企業)では、連結上でのれんが計上されます。
税務上ののれん(資産調整勘定)は発生しないため、税務上の償却による節税効果も得られません。
- メリット:契約関係や許認可の維持、手続きの簡便さ
- デメリット:簿外債務等のリスクをすべて引き継ぐ、税務上の償却メリットなし
事業譲渡とのれん代|税務メリットと消費税の注意点
事業譲渡は、事業に関連する資産・負債を個別に譲渡する方法です。譲渡対象を選択できるため、特定の事業や資産のみの取得に適しています。
事業譲渡では、買収価格が譲渡された資産の純資産額を超えた場合にのれんが発生します。こののれんは譲受企業の貸借対照表に計上されます。ただし、計上されるのれんの処理方法は、会計基準や取引形態によって異なる場合があります。税務上ののれん(資産調整勘定)も発生し、5年間で均等償却(損金算入可能)されるため節税効果があります。
重要な注意点として、のれん代に消費税が課税される点があります。のれん代が多額の場合、消費税負担(10%)も大きくなるため、初期投資額に影響します。
- メリット:譲渡対象の選択性、税務上の償却メリット
- デメリット:個別の移転手続きの手間、契約関係の移転に第三者の同意が必要、のれん代への消費税課税
会社分割とのれん代|非適格分割を活用した節税戦略
会社分割は、会社の事業の一部または全部を別会社に移転する方法です。税務上、「適格分割」と「非適格分割」に区分されます。
M&Aで注目される「非適格分社型分割」では、税務上ののれん(資産調整勘定)が発生し、5年間で均等償却(損金算入可能)されます。事業譲渡と異なり、のれんは分割承継会社(子会社)に計上される点が特徴です。
また、会社分割(適格・非適格を問わず)は、消費税の課税対象外取引であり、のれん代にも消費税は課税されません。多額ののれん代が発生する場合は有利なスキームとなります。
- メリット:税務上の償却メリット、のれん代の消費税免除、契約関係の維持
- デメリット:手続きの複雑さ、時間とコストがかかる、分割会社側で譲渡益課税の可能性
M&A手法選択の判断基準
主要なM&Aスキームののれん代関連の特徴を比較表でまとめます。
| 比較項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 | 非適格分割 |
| 会計上のれん | 個別上なし(連結上あり) | 個別上で発生 | 個別上で発生 |
| 税務上のれん | 発生しない | 発生する(譲受企業) | 発生する(承継会社) |
| のれん償却 | 連結上のみ(税務上なし) | 会計:20年以内 税務:5年 | 会計:20年以内 税務:5年 |
| 消費税 | 非課税 | 課税あり(10%) | 課税対象外 |
| 手続き | 比較的シンプル | やや複雑 | 最も複雑 |
| リスク引継 | 全て引継 | 選択的に引継 | 対象事業のみ引継 |
最適なスキーム選択のポイント:
- のれん代の大きさ(大きいほど税務メリットも大きい)
- 譲渡対象の範囲(全部か一部か)
- リスク許容度
- 税務メリットの重要性
- 時間的制約と手続きの複雑さ
- 消費税負担の影響
中小企業M&Aでは、これらの要素を総合的に判断し、専門家のアドバイスを得ながら最適なスキームを選択することが重要です。
支払った消費税は「課税仕入れ」となり、条件を満たせば仕入税額控除の対象となりますが、キャッシュフロー上はいったん支払いが必要です。
会社分割における消費税の免除
会社分割(適格・非適格を問わず)は、消費税法上の「資産の譲渡等」に該当せず、「包括承継」とみなされるため消費税の課税対象外となります。非適格分割でも税務上ののれんが計上されますが、消費税は課税されません。
例えば、のれん代1億円の場合:
- 事業譲渡:消費税1,000万円の負担が生じる
- 会社分割:消費税負担が生じない
スキーム選択と消費税の影響
M&Aスキーム選択において、消費税の影響は重要な検討要素です。のれん代が大きいほど、消費税の影響も大きくなります。
消費税の観点からは、株式譲渡または会社分割(消費税負担なし)が事業譲渡(消費税負担あり)より有利です。のれん代が小さい場合は、手続きの簡便さから事業譲渡を選択することもありますが、のれん代が大きい場合は、消費税負担を避けるために株式譲渡や会社分割が選ばれることが多いです。
のれん代を高く評価してもらうためのアプローチ
のれん代は買い手の主観で決まるため、自社を高く評価してくれる企業を見つけることが重要です。自社の強みが買い手のニーズと合致する企業を探すことで、のれん代を高く評価してもらえる可能性が高まります。
・高評価が期待できる買い手候補:
- 自社が強みを持つ市場に参入したい企業
- 自社の技術やノウハウを必要としている企業
- 自社の顧客基盤を獲得したい企業
- シナジー効果が大きく期待できる企業
買い手候補の絞り込みには、ロングリスト→ショートリストという段階的アプローチが効果的です。業界内の競合企業、取引先、新規参入を計画している企業などから最適な候補を見つけることが重要です。
また、のれん代の税務メリットを活用した交渉も有効です。税務上ののれん(資産調整勘定)の5年償却による節税効果を説明し、適切なM&Aスキームを提案することで、より高い買収価格での合意を引き出せる可能性があります。
事前準備の実践ステップ
のれん代を高く評価してもらうためには、M&A交渉前の事前準備が重要です。
- 自社の強みと弱みの客観的分析
SWOT分析などで自社の競争優位性や独自の経営資源を明確化する
- 財務データの整備と透明性の確保
過去3〜5年分の財務諸表の整備、適正な会計処理、将来の収益予測とその根拠資料の作成など
- 無形資産の価値の明確化
知的財産権、顧客基盤、従業員のスキル、ブランド価値などを具体的に示す
- 魅力的な事業計画の策定
市場分析と競合分析に基づいた現実的かつ魅力的な計画を作成する
- M&A仲介会社やアドバイザーの活用
専門知識と経験を持つ専門家のサポートを受ける
これらの準備を通じて自社の価値を最大限に引き出し、のれん代を高く評価してもらうことが可能になります。
のれん代のリスクマネジメント|買い手企業の視点
買い手企業にとって、のれん代は投資回収の対象であると同時にリスク要因でもあります。ここでは買い手企業の視点からのリスクマネジメントについて解説します。
デューデリジェンスのポイント
のれん代のリスクを最小化するためには、M&A前のデューデリジェンス(買収監査)が極めて重要です。
財務デューデリジェンス(FDD)のポイント
- 財務諸表の信頼性検証
- 簿外債務や偶発債務の洗い出し
- 収益と費用の詳細分析(一時的/経常的要素の区別)
- キャッシュフローの質の検証
- 関連当事者取引の妥当性
事業デューデリジェンス(BDD)のポイント
- 市場環境と競合状況の分析
- 事業モデルの持続可能性の検証
- 顧客基盤の安定性と集中リスク
- 人的資源の依存度(特定の従業員への依存リスク)
- 技術やノウハウの陳腐化リスク
特に中小企業M&Aでは、オーナー経営者個人のスキルや人脈に依存している部分が大きい場合が多いため、買収後にそれらの価値が失われるリスクを評価することが重要です。
減損リスク対策|M&A後の企業価値維持の方法
買収後に期待したシナジーや収益が実現できなかった場合、のれん代の減損処理が必要になるリスクがあります。このリスクを最小化するための対策を紹介します。
買収後統合計画(PMI)の重要性
M&A成功の鍵は買収後の統合プロセス(Post-Merger Integration: PMI)にあります。
- 統合計画の早期策定と実行
- 統合チームの編成と責任者の明確化
- 具体的なマイルストーンとKPIの設定
- 重要人材の維持戦略
文化的統合の重要性
M&A失敗の大きな原因の一つが企業文化の不統合です。
- 企業文化の差異分析と相互理解
- 頻繁かつオープンなコミュニケーション
- 共通の価値観と目標の設定
- 早期の懸念事項への対応
シナジー効果実現のための具体的施策
- シナジー効果の具体的な数値目標設定
- 実現のためのロードマップ作成
- 責任者とリソースの明確な割り当て
- 定期的な進捗確認と課題解決
税務リスクの予防と対応策
のれん代(資産調整勘定)に関連する税務リスクを管理することも重要な課題です。
税務リスクの主な種類
- 取引構造(スキーム選択)に関するリスク
- 税務申告の適正性に関するリスク
- 税制改正に伴うリスク
- 資産調整勘定の計上額の妥当性に関するリスク
税務リスク予防のための事前対策
- 税務専門家によるスキーム検討
- 税務当局への事前相談(事前照会)の活用
- 文書化と根拠資料の整備
- 資産・負債の適正な時価評価
特に中小企業のM&Aでは、税務処理の専門知識が不足していることが多いため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
まとめ│中小企業M&Aにおいてのれん代活用は重要
のれん代は企業の無形価値を表す重要指標です。中小企業M&Aでは、バランスシートに表れない価値が大きいため、のれん代の適正評価が特に重要となります。
M&Aスキーム選択時には、のれん代の会計・税務処理や消費税影響を考慮することで取引後の財務リスクを軽減し、効率的な取引が可能です。売り手は自社の強みを評価してくれる買い手を見つけ、買い手は適切なデューデリジェンスとPMIでリスクを最小化しましょう。のれん代を深く理解することが、M&A成功の鍵となります。 M&Aや経営課題のお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。