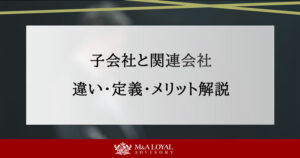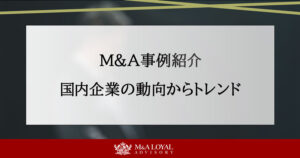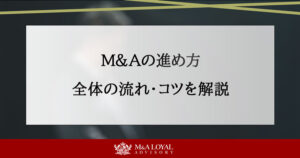持分法適用会社とは?子会社との違いやメリットをわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
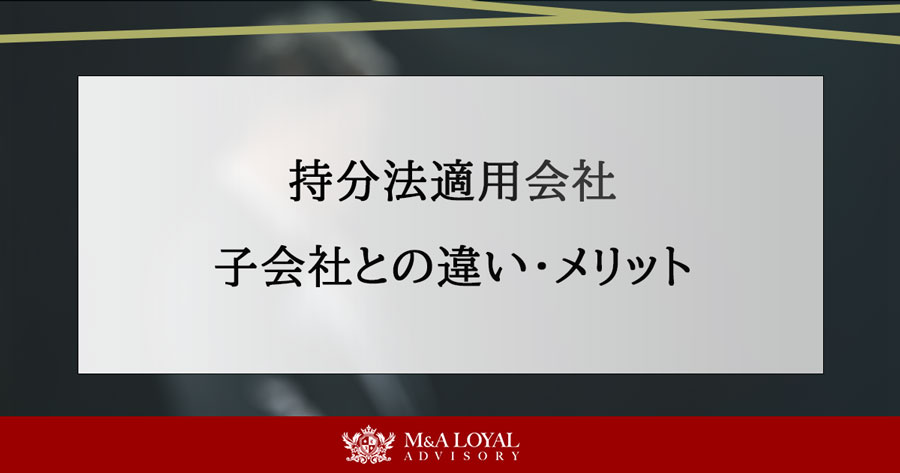
企業のM&Aや投資戦略を検討する際、「持分法適用会社」という用語を耳にすることがあります。しかし、その具体的な意味や連結子会社との違い、実務上の取り扱いについて正確に理解している方は多くないのではないでしょうか。
持分法適用会社は、中小企業の成長戦略において重要な選択肢の一つです。完全な子会社化よりも少ない投資で他社との協力関係を築くことができ、段階的な事業展開や新規市場への参入が可能となります。また、適切に活用することで財務諸表の改善効果も期待できます。
本記事では、持分法適用会社の基本概念から適用要件、具体的な会計処理方法、メリット・デメリット、実務上の注意点まで、経営者や経理担当者が知っておくべきポイントを体系的に解説します。
目次
持分法適用会社とは?基本概念をわかりやすく解説
持分法適用会社とは、親会社が一定の影響力を持ちながらも完全な支配権を有しない会社に対して、持分法という会計処理方法を適用する会社のことです。具体的には、親会社が議決権の20%以上50%以下を保有する関連会社や、持分法適用会社に該当する非連結子会社が含まれます。
持分法の定義と目的
持分法とは、投資先企業の純資産や損益のうち、投資企業の持分に相当する部分を投資企業の財務諸表に反映させる会計方法です。この方法により、投資先企業の業績変動が投資企業の財務状況に適切に反映されます。持分法の主な目的は、企業グループ全体の財務状況をより正確に表示することにあります。
連結財務諸表における役割
連結財務諸表において、持分法適用会社は「投資有価証券」として貸借対照表に計上され、その損益は「持分法による投資損益」として損益計算書に反映されます。例えば、親会社が30%の株式を保有する会社が100万円の利益を計上した場合、親会社は30万円を自社の利益として認識できます。このように、子会社化せずとも投資先の業績を取り込める点が持分法の特徴です。
中小企業にとっての重要性
中小企業にとって持分法は、M&A戦略や事業展開において重要な選択肢となります。完全買収に比べて少ない投資額で他社との協力関係を築けるため、資金力に限りがある中小企業でも成長戦略を実現しやすくなります。また、持分法適用により財務諸表の収益性が向上することで、金融機関からの融資や投資家からの評価向上も期待できます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



持分法適用会社の適用範囲と5つの要件
持分法の適用範囲は、日本の会計基準において明確に定められています。親会社が財務および事業方針の決定に対して重要な影響を与えるかどうかが判断の基準となり、以下の5つの要件によって決定されます。
議決権比率による基本要件(20%以上50%以下)
持分法適用の最も基本的な要件は、親会社が保有する議決権比率です。原則として、議決権の20%以上50%以下を保有する会社が対象となります。この範囲であれば、親会社は投資先企業の経営に重要な影響を与えることができるものの、完全な支配権は持たないとみなされます。ただし、議決権比率だけでなく、実質的な影響力も考慮される点が重要です。
関連会社としての適用要件
関連会社として持分法が適用される要件は、議決権保有比率に加えて実質的な影響力が考慮されます。議決権が15%以上20%未満でも、以下のいずれかに該当すれば関連会社となります。
・役員派遣:親会社の社員等が投資先の役員に就任している
・重要な融資:事業運営に必要な資金の融資を実施している
・技術提供:事業に不可欠な技術やノウハウを提供している
・重要な取引:売上や仕入の相当部分を占める取引がある
・実質的影響:財務・事業方針決定に重要な影響を与えている
非連結子会社としての適用要件
非連結子会社が持分法適用となる要件は、子会社でありながら連結対象から除外される場合です。具体的には、親会社にとって重要性が乏しい場合や支配が一時的である場合が該当します。ただし、議決権所有比率が20%以上50%以下の範囲にある非連結子会社については、持分法の適用が必要となります。
重要性の原則による除外規定
持分法の適用においては、重要性の原則が適用されます。投資先企業の規模や業績が親会社の連結財務諸表に与える影響が軽微である場合、持分法の適用を省略することが可能です。一般的に、投資先企業の総資産、売上高、純損益が連結ベースの1%未満の場合は重要性が低いとみなされることが多いです。
実質的な影響力の判断基準
議決権比率に加えて、実質的な影響力の有無も重要な判断基準となります。契約上の取り決めや事実上の支配関係、技術的依存関係などを総合的に勘案して判断されます。例えば、議決権は20%未満でも、重要な技術供与契約や独占的な取引契約により実質的な影響力を行使できる場合は、持分法適用の対象となる可能性があります。
持分法適用会社と連結子会社の違い
持分法適用会社と連結子会社は、親会社の議決権保有比率や支配力の程度によって区分されます。この違いを理解することは、適切な会計処理や経営戦略の策定において極めて重要です。
支配力の程度による区分
連結子会社は、親会社が議決権の50%超を保有し、完全な経営支配権を持つ会社です。一方、持分法適用会社は議決権の20%以上50%以下を保有し、重要な影響力は持つものの完全な支配権は有しない会社を指します。連結子会社では親会社が経営方針を決定できますが、持分法適用会社では経営方針への影響力は限定的です。
会計処理方法の相違点
連結子会社の場合、子会社のすべての勘定科目を親会社の財務諸表に合算し、連結修正仕訳を行う必要があります。これに対して持分法適用会社では、「投資有価証券」と「持分法による投資損益」の2つの勘定科目のみで処理が完結します。このため、持分法の方が会計処理の負担が大幅に軽減されます。
財務諸表への反映方法の違い
財務諸表への反映方法において、連結子会社と持分法適用会社には明確な違いがあります。連結子会社は、親会社の貸借対照表や損益計算書において、すべての項目が詳細に反映されます。つまり、連結子会社の資産、負債、収益、費用が親会社の財務諸表に統合されます。
一方、持分法適用会社では、投資企業の持分に応じて純資産と損益のみが反映されます。例えば、持分法適用会社が1億円の売上を計上した場合、持分比率が30%であれば、親会社の財務諸表にはその純利益の30%分(つまり、持分法による投資損益)が「持分法による投資損益」として計上されます。このため、持分法適用会社の業績が親会社の売上に直接加算されることはありません。
このように、連結子会社と持分法適用会社では財務諸表への反映方法が異なるため、企業の財務状況を正確に理解するためには、それぞれの会計処理の違いを把握しておくことが重要です。
持分法適用会社と関係会社の関係性
関係会社と持分法適用会社の関係性を正しく理解することは、企業の財務報告や経営戦略において重要な意味を持ちます。両者の概念には重複する部分と異なる部分があります。
関係会社の定義と範囲
関係会社とは、子会社、関連会社、その他の関係会社を総称した広義の概念です。会社法では、親会社が財務および事業の方針の決定を支配している場合や重要な影響を与えることができる場合に関係会社と定義されます。具体的には、議決権の過半数を保有する子会社、20%以上の議決権を保有する関連会社、重要な取引関係にあるその他の関係会社が含まれます。
持分法適用会社の位置づけ
持分法適用会社は、関係会社の一部を構成する概念です。この持分法が適用される関係会社には、主に関連会社と非連結子会社が含まれます。つまり、すべての持分法適用会社は関係会社ですが、すべての関係会社が持分法適用会社となるわけではありません。
具体的には、連結子会社は、持分法の適用対象外となります。また、重要性の低い関係会社(通常、親会社の持分が少ない企業)についても、持分法を適用する必要がない場合があります。これにより、持分法適用会社は、財務諸表において特定の会計処理を受けることになります。
このように、持分法適用会社は関係会社の中でも特別な位置づけを持っており、その会計処理や財務報告において異なる取り扱いがされることがあります。
会計上の概念と法律上の定義の違い
重要な違いとして、関係会社は主に「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(財務諸表等規則)で定義される会計上の広範な概念であるのに対し、持分法適用会社はその中で持分法が適用される会社を指す、より具体的な会計上の概念である点があります。
関係会社の判定では実質的な影響力が重視され、議決権比率は必ずしも決定的な要因ではありません。一方、持分法適用会社の判定では、明確な会計基準に基づいた客観的な要件が適用されます。このため、同じ投資関係でも、法律上と会計上で異なる分類がなされる場合があります。
持分法適用会社の確認方法と判断手順
持分法適用会社であるかどうかを確認するためには、企業の開示資料を体系的に調査する必要があります。主な確認方法は以下の3つです。
・連結財務諸表の注記事項の確認
・有価証券報告書の関係会社情報の調査
・非上場企業への直接問い合わせ
上場企業と非上場企業では確認方法が異なるため、それぞれに適した手順を理解することが重要です。
連結財務諸表の注記事項を確認する
最も確実な確認方法は、連結財務諸表の注記事項を調べることです。連結財務諸表規則により、持分法を適用した関連会社や非連結子会社の数と主要な会社名の記載が義務付けられています。具体的には「持分法適用の関連会社」「持分法適用の非連結子会社」という項目で、対象会社数と主要企業名が明記されています。また、持分法を適用しない理由がある場合は、その理由も併せて記載されます。
有価証券報告書の関係会社情報を調べる
連結財務諸表に記載がない場合は、有価証券報告書の「関係会社の状況」を確認します。この項目では、関係会社の一覧とともに、議決権所有割合、主要な事業内容、資本金額などが記載されています。議決権所有割合が20%以上50%以下の会社については、備考欄に持分法適用の有無が記載されることが一般的です。さらに、有価証券報告書の注記事項でも持分法に関する詳細な情報が開示されています。
非上場企業に直接問い合わせる
非上場企業の場合、財務情報が公開されていないため、直接的な確認が必要となります。M&Aの検討段階であれば、デューデリジェンスの過程で関係会社の状況や持分法適用の有無を調査します。また、取引先や投資先企業について知りたい場合は、企業に直接問い合わせるか、信用調査会社のレポートを活用する方法もあります。ただし、機密性の高い情報のため、適切な守秘義務契約の締結が前提となります。
持分法適用会社の仕訳処理と実務例
持分法適用会社の会計処理では、投資先企業の業績変動や取引内容に応じて適切な仕訳を行う必要があります。ここでは、親会社A社が持分法適用会社B社の株式30%を保有するケースを例に、主要な仕訳パターンを解説します。
損益確定時の仕訳方法
持分法適用会社が損益を計上した場合、親会社は持分比率に応じた損益を自社の業績として認識します。B社が当期純利益200万円を計上した場合、A社は30%に相当する60万円を持分法による投資損益として計上します。
仕訳例(利益の場合):
(借方)投資有価証券 600,000円 (貸方)持分法による投資損益 600,000円
逆に、B社が100万円の損失を計上した場合は、A社も30万円の損失を認識します。
仕訳例(損失の場合):
(借方)持分法による投資損失 300,000円 (貸方)関係会社株式 300,000円
配当受取時の会計処理
持分法適用会社から配当を受領した際は、特殊な会計処理が必要です。B社から配当金50万円を受け取った場合、配当の受領を記録します。
配当受領時の仕訳:
(借方)現金預金 500,000円 (貸方)投資有価証券 500,000円
関係会社間取引の仕訳処理
A社がB社に商品200万円(利益40万円含む)を販売した場合、通常の売上計上に加えて、未実現利益の消去処理が必要となります。
売上計上時の仕訳:
(借方)売掛金 2,000,000円 (貸方)売上高 2,000,000円
未実現利益消去の仕訳:
(借方)持分法による投資損益 120,000円 (貸方)投資有価証券 120,000円
消去する金額は、利益40万円に持分比率30%を乗じた12万円となります。この処理により、グループ外への最終的な販売まで利益の実現を繰り延べます。
持分変動時の処理手順
A社がB社の株式を追加取得し、持分が30%から40%に増加した場合の処理です。追加投資額100万円を支払った場合の仕訳は以下のとおりです。
株式追加取得時の仕訳:
(借方)関係会社株式 1,000,000円 (貸方)現金預金 1,000,000円
持分比率の変更に伴い、過去の投資損益の取り込み比率も遡及的に調整する場合があります。また、持分比率が50%を超えて連結子会社になった場合は、持分法適用が終了し、連結会計への移行処理が必要となります。このような重要な変更がある場合は、会計監査人や税理士と十分に協議して適切な処理方法を確認することが重要です。
持分法適用会社のメリット・デメリットと活用戦略
持分法適用会社の活用は、中小企業の成長戦略において重要な選択肢となります。そのメリットとデメリットを正しく理解し、戦略的に活用することで企業価値の向上が期待できます。
メリット①:会計処理の簡素化による業務効率化
持分法の最大のメリットは、会計処理の大幅な簡素化です。連結子会社の場合、子会社のすべての勘定科目を詳細に合算し、複雑な連結修正仕訳を行う必要があります。一方、持分法では「投資有価証券」と「持分法による投資損益」の2つの勘定科目だけで処理が完結するため、経理部門の負担が大幅に軽減されます。これにより、月次決算の早期化や決算業務の効率化が実現でき、人件費の削減効果も期待できます。
メリット②:財務諸表の見栄え向上効果
持分法適用により、投資先企業の好業績を自社の財務諸表に反映できます。例えば、成長性の高いベンチャー企業に30%出資した場合、その企業の利益成長に応じて自社の営業外収益も増加します。これにより、売上高や営業利益が横ばいでも、経常利益や当期純利益の向上が図れます。金融機関からの融資審査や投資家への説明において、この効果は企業の成長性をアピールする重要な要素となります。
メリット③:中小企業M&Aでの戦略的活用
資金力に限りがある中小企業にとって、持分法は効率的な成長戦略の実現手段となります。完全買収に比べて少ない投資額で他社との協力関係を構築でき、段階的な関係強化も可能です。例えば、まず20%の出資で持分法適用会社とし、事業シナジーの効果を確認した後に追加投資で子会社化するといった戦略が取れます。また、異業種への参入や新規市場開拓において、現地企業との合弁会社設立にも活用できます。
デメリット:持分法適用に伴う制約と対策
持分法適用には注意すべき制約もあります。最も重要なのは、一度適用が始まると企業の判断だけでは終了できない点です。連結財務諸表規則に従った適切な開示義務も発生し、記載漏れがあれば法的な問題となる可能性があります。また、投資先企業の損失も自社の業績に影響するため、投資先の業績悪化リスクを常に監視する必要があります。
これらの対策として、投資前の十分なデューデリジェンス実施、投資後の定期的なモニタリング体制の構築、適切な会計処理のための専門家との連携が重要です。特に中小企業では、税理士や公認会計士との密接な協力により、適切な会計処理と開示の確保が不可欠となります。
持分法適用会社の実務上の注意点
持分法適用会社の会計処理や管理において、実務上注意すべき重要なポイントがあります。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることで、法的リスクの回避と円滑な業務運営が可能となります。
連結財務諸表規則の記載漏れに注意する
連結財務諸表規則では、持分法適用に関する詳細な記載義務が定められています。主な記載事項は以下のとおりです。
・持分法適用会社の数と主要な会社名の明記
・持分法を適用しない関連会社がある場合の理由記載
・持分法適用範囲の変更があった場合の内容と理由の開示
・重要な関連会社の名称と投資損益算出根拠の記載
・持分法適用会社の重大な後発事象の内容開示
記載漏れや不正確な記載は、有価証券報告書虚偽記載等の法的問題につながる可能性があるため、会計監査人や税理士との密接な連携による確認作業が不可欠です。
自社都合での適用終了ができない制約がある
持分法の適用は、企業の財務報告の一貫性確保のため厳格に規定されています。一度適用要件を満たして持分法適用会社となった場合、企業の判断だけで適用を終了することはできません。適用終了となるのは、議決権比率が50%を超えて連結子会社になった場合、議決権比率が20%を下回った場合、または投資先企業の重要性が著しく低下した場合に限られます。このため、投資戦略を検討する際は、将来的な持分法適用の継続可能性も考慮した慎重な判断が必要となります。
税務リスクを事前に把握しておく
持分法適用には、会計上の処理と税務上の処理に差異が生じる場合があります。特に、持分法による投資損益の計上タイミングと税務上の益金・損金算入時期にズレが生じることがあり、適切な税効果会計の適用が必要となります。また、国外の持分法適用会社については、外国子会社合算税制(CFC税制)の適用可能性も検討が必要です。さらに、持分法適用会社からの配当については、益金不算入制度の適用要件を満たすかどうかの確認も重要となります。これらの税務リスクを適切に管理するため、税理士との定期的な相談体制を整備し、税務上の取り扱いを事前に明確化しておくことが推奨されます。
まとめ|持分法適用会社を活用した企業成長戦略
持分法適用会社は、議決権の20%以上50%以下を保有する関連会社や非連結子会社に適用される会計処理方法であり、中小企業の成長戦略において極めて有効な手段です。会計処理の簡素化による業務効率向上、財務諸表の収益性改善、限られた資金での戦略的投資実現といったメリットを活用することで、企業価値の向上が期待できます。
ただし、連結財務諸表規則の遵守、適用終了の制約、税務リスクの管理など、注意すべき点も多く存在します。これらのリスクを適切に管理するためには、投資前の十分なデューデリジェンス、投資後の継続的なモニタリング体制の構築、専門家との密接な連携が不可欠です。
持分法を戦略的に活用することで、中小企業でも段階的なM&Aや異業種参入、新規市場開拓が可能となります。自社の成長戦略と照らし合わせて持分法の活用を検討し、適切な専門家のサポートを得ながら実行することで、持続的な企業成長の実現につなげていきましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。