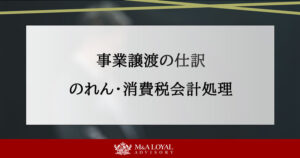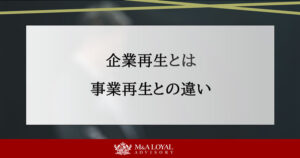経営戦略と税制の交差点:組織再編税制の仕組みと活用法を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
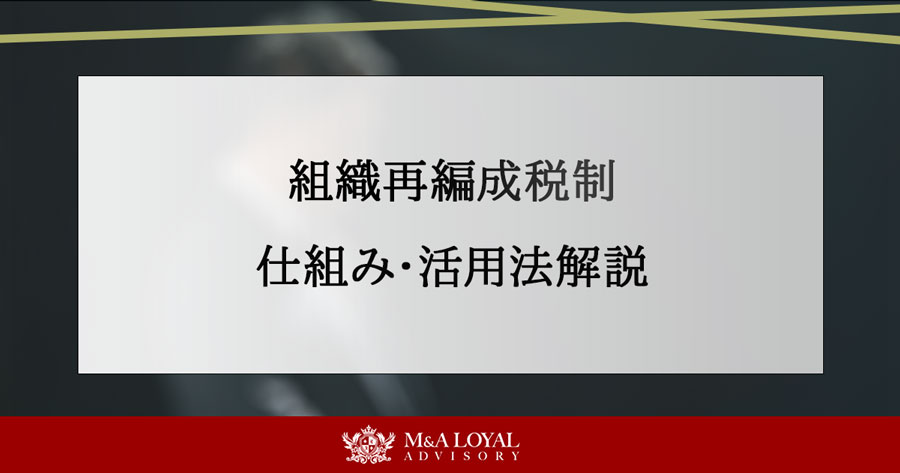
企業のM&Aや事業再編がますます活発化する現代、単なる経営判断だけでなく「税制の活用」が企業成長を左右する重要な鍵となっています。その中でも特に注目されているのが「組織再編税制」です。
組織再編税制とは、会社の合併や分割、株式交換・移転など、企業グループの再編に伴う取引において、税負担を一定の条件下で繰延べられる制度のこと。組織再編税制を適切に活用すれば、税コストを抑えつつスピーディーな組織統合や事業再編を実現することが可能です。
しかしその一方で、制度の内容は複雑で専門的な理解が求められるうえ、適用要件を満たさない場合には多額の課税が発生するリスクもあります。
本記事では、組織再編税制の基本構造から適格・非適格の違い、実際のM&Aや持株会社化などにどう活かされているかまで、経営戦略と税制の“交差点”に立つ視点で徹底的に解説していきます。
目次
組織再編税制とは何か?─目的・概要・重要性
組織再編税制の定義と導入背景
組織再編税制とは、企業が合併・会社分割・株式交換・株式移転などの再編行為を行う際、税務上の課税関係を一定の要件を満たす場合に限り繰延べできる仕組みを指します。これは、2001年の税制改正によって導入された制度で、日本企業の再編促進と国際競争力の強化を目的に整備されました。
もともと、組織再編行為には譲渡損益や資産の時価評価による法人税課税が発生していましたが、経済合理性に基づく再編を妨げる要因とされていたため、適格要件を満たす再編に対しては課税を繰り延べることで、企業の柔軟な事業再編を後押しすることが意図されました。
この税制は、経営統合や企業グループ内の再編、事業承継といった経営課題に対し、税負担の最適化を図りながら対応するための有効な選択肢となっています。
企業が注目する理由:節税と経営統合の戦略性
企業が組織再編税制に注目する最大の理由は、税務上の“繰延効果”によって、短期的な税負担を回避しながら再編をスムーズに行える点にあります。たとえば、グループ内の会社を合併する場合、本来であれば資産の時価評価益に課税されますが、適格要件を満たすことで簿価引継ぎが認められ、課税を繰延べることが可能です。
また、経営統合や再編においては、企業価値を維持・最大化しながら、持株会社体制の構築やスピンオフの実行など、将来の成長戦略を見据えた再編が必要となります。そうした戦略的再編において、税制上のメリットを最大化することは、財務戦略上も極めて重要です。
加えて、近年では中小企業でも持株会社化やグループ再編によって、経営の効率化や事業承継対策を行う動きが加速しており、組織再編税制は中堅・中小企業においても現実的なツールとなっています。
対象となる組織再編の種類(合併・会社分割・株式交換など)
組織再編税制の対象となる行為には、大きく以下の6類型があります。これらは、いずれも法人税法上で明確に定義されており、税務上の取扱いが整理されています。
- 合併(吸収合併・新設合併)
法人が他の法人と合体し、一方の法人が存続または新設される再編方法。 - 会社分割(吸収分割・新設分割)
事業の一部または全部を分割し、別の法人に承継させる再編。承継法人が既存企業か新設企業かで分類されます。 - 株式交換
一方の法人が他方の法人のすべての株式を取得し、完全子会社化するスキーム。 - 株式移転
複数の法人が新設法人の完全子会社となり、持株会社を設立するスキーム。 - 現物分配(現物出資)
企業が保有する株式等の資産を別法人に出資または分配する取引。 - 事業譲渡と事業譲受け(厳密には“再編税制外”だが実務上密接に関連)
これらの手法は、M&A、グループ再編、事業承継、ホールディングス化といった様々な目的に応じて使い分けられており、それぞれに対する組織再編税制の適用可否が再編成功の分かれ目になります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



適格組織再編と非適格組織再編の違い
適格組織再編の定義と要件
組織再編税制における「適格組織再編」とは、一定の要件を満たす再編について、税務上の課税を繰り延べることが認められる制度です。具体的には、再編によって移転された資産や負債を時価ではなく簿価で引き継ぐことができ、法人税などの課税が発生しません。すなわち、再編取引が“なかったもの”として取り扱われる特例であり、企業にとって非常に有利な制度です。
適格と認められるには、主に以下のような要件を満たす必要があります。
- 事業継続性要件
再編後も移転された事業が、譲受法人によって引き続き継続されている必要があります。たとえば、吸収合併によって引き継いだ工場や営業所が、すぐに閉鎖されるようなケースはこの要件を満たさないと判断されることがあります。事業の内容や従業員の継続性も重要です。 - 株式継続保有要件
再編の対価として株式が交付された場合、その株式が一定期間(通常は2年間)継続して保有されることが求められます。これは、再編の実質的な継続性と持続的な支配を担保するための要件です。短期的な売却や転売が行われた場合は、課税繰延が否認されるリスクがあります。 - 支配関係または従業員・資産等の継続要件
完全支配関係(90%以上の出資)にある企業間での再編は、比較的緩やかな要件で適格とされます。一方、支配関係がない場合は、従業員・事業用資産の承継割合など、より厳格な条件が適用されます。
※上記は適格要件の一部です。
このように、適格再編の判断は単なる形式だけでなく、「事業が本当に継続しているか」「支配関係は維持されているか」といった実態の整合性が重要視されるのが特徴です。
非適格となった場合の税務リスク
適格要件を満たさない組織再編は、「非適格組織再編」として課税対象になります。この場合、再編時点で譲渡された資産や株式が時価で評価され、その含み益に対して法人税などの課税が行われます。
たとえば、譲渡資産に不動産や株式などの含み益がある場合、それらが時価評価され、帳簿価額との差額に対して課税されることになります。これにより、一時的に多額の税負担が発生し、キャッシュフローに深刻な影響を及ぼす可能性があります。
また、非適格再編では以下のようなリスクも同時に生じます。
- 繰越欠損金の引継ぎ不可:適格再編と異なり、税務上の損失繰越の恩恵が受けられない。
- 減価償却資産の再評価:簿価引継ぎができず、新たな耐用年数・評価額で計上し直す必要がある。
- のれんの計上と償却負担:のれんが大きくなると、減価償却の影響で利益圧縮を招く可能性がある。
非適格再編は、意図的な節税回避やスキームの失敗、法解釈の誤認により発生するケースが多く、事前の入念な検討と専門家の助言が不可欠です。
判断基準となる「事業継続性」「持株割合」など
適格・非適格の判断は、以下のような複数の観点から行われます。単一の要素だけでなく、全体として合理的かつ継続的な再編であるかどうかが重要です。
- 事業継続性の有無:営業活動が形式的でなく、従業員や取引先も含めて維持されているか。
- 持株割合(支配関係):完全支配(90%以上)であれば、要件が緩和される。
- 対価の性質:対価として株式ではなく現金が使われた場合は、非適格とされる可能性が高い。
- スキームの実質性:節税目的だけの名目的再編は、税務当局により否認される可能性がある。
- 資産・負債の移転比率:事業用資産や従業員の一定割合以上が引き継がれているか。
これらの要素をふまえ、再編前に実態を精査・整理し、法令・通達に基づいた「適格性の論拠」を明文化しておくことが肝要です。
再編スキーム別の活用方法と税務ポイント
合併(吸収合併・新設合併)の活用と留意点
組織再編の中でもっともポピュラーなスキームが「合併」です。合併には、存続会社が他の会社を吸収する「吸収合併」と、既存の複数会社が解散し新たな法人を設立する「新設合併」の2種類があります。
吸収合併は、迅速な再編や意思決定の一元化が目的で用いられやすく、手続きも比較的簡便です。一方、新設合併は、対等合併やブランド刷新、新体制の構築などを意図するケースに多く活用されます。
税務上のポイントとしては、合併により譲渡される資産の評価方法と、損益通算や繰越欠損金の取扱いが挙げられます。適格合併であれば、資産は帳簿価額で承継され、課税が繰り延べられます。非適格となると含み益への課税や、損金算入の制限が生じるため、制度の理解が欠かせません。
また、合併比率やのれんの扱い、合併差損益の会計処理も税務リスクに直結するため、事前のスキーム設計と税務当局とのすり合わせが重要です。
会社分割(吸収分割・新設分割)の活用と論点
会社分割は、企業が事業部門を切り出し、他の法人に承継させる形で行われます。スピンオフや事業の選択と集中、グループ再編において広く利用されており、「吸収分割」と「新設分割」の2形態があります。
吸収分割では、既存の他社が対象事業を引き継ぎ、新設分割では新会社を設立して承継させます。どちらも、事業そのものを移転するため、資産・負債・人材・契約関係などが包括的に移動します。
組織再編税制では、適格要件を満たす会社分割について、譲渡益が課税されない仕組みとなっています。ただし、事業の実態、承継範囲、対価の内容などに応じて、適格・非適格の分かれ目が変わるため注意が必要です。
また、会計上のスピンオフ税制や分社化に関する開示対応、役員報酬・人事制度の再設計など、税務以外の観点からの準備も不可欠です。
株式交換・株式移転の活用と課税繰延の注意点
持株会社体制の構築やグループ経営の効率化に際して用いられるのが、「株式交換」および「株式移転」です。
- 株式交換:既存会社の株主が、他社(主に親会社)に株式を交換して支配を委ねるスキーム。
- 株式移転:複数の会社が、新設の持株会社の子会社となる形で支配構造を再構成する手法。
これらは、持株会社の設立や子会社再編、親子間の資本関係見直しに多用されており、資本政策と連動して活用されることが多いです。
組織再編税制では、これらの取引についても適格要件を満たせば、株式移転・交換による株式評価益に対して課税が繰り延べられます。ただし、現金等が対価に含まれていたり、持株比率が適格範囲を外れる場合は、課税対象となるため注意が必要です。
また、株主の側でも課税が発生することがあるため(譲渡所得課税等)、法人・個人双方の影響を事前に確認する必要があります。
組織再編税制を活用する際のリスクと対策
税務否認リスクと「実質基準」への対応
組織再編税制は、適格要件を満たせば大きな節税効果をもたらす制度です。しかし、その一方で、要件を形式的に満たしているだけでは認められず、税務当局から否認されるリスクがあります。とくに問題となるのが「実質基準」です。
例えば、会社分割や株式移転を用いたグループ内再編において、単に形式上の再編にとどまり、実態として事業が伴っていない、あるいは節税目的が主と判断されると、課税繰延が否認される可能性が高まります。このような事例は過去の税務裁判でも数多く報告されており、実質的な事業継続性や経営統合の合理性が求められます。
実質基準をクリアするためには、次のような対策が重要です。
- 事業の継続性を示す書類(事業計画書・業務委託契約など)の整備
- 雇用の継続や従業員の転籍など人的リソースの実質的移動
- 税務顧問や第三者専門家による意見書の取得
- 会計・税務上の整合性を説明する内部文書の作成
また、国税庁は「形式的な適格要件の充足にとどまらず、取引の実質を重視する」姿勢を強めています。特に、事業再編の直後に組織解散や事業廃止が予定されているようなケースでは、実質要件が満たされていないと判断される可能性が極めて高いため、慎重な検討が必要です。
会計・開示面での落とし穴
税務面での適格性に加えて、組織再編は財務会計・開示においても多くの影響を及ぼします。たとえば、のれんの処理や連結財務諸表における支配の判定、税効果会計における繰延税金資産の取り扱いなど、多岐にわたる論点があります。
また、上場企業にとっては、投資家に対する情報開示や証券取引所の報告義務を伴うため、IR(投資家向け広報)との連携も不可欠です。特に再編の目的が戦略的成長や効率化である場合、その効果や見通しを適切に市場へ説明できなければ、株価下落や投資家離れを招く可能性があります。
これらを回避するためには、以下の体制構築が重要です。
- 経理部門と税務顧問による会計処理フローの明確化
- 法務部門と連携したディスクロージャー文書の準備
- 開示資料における再編スキームの正確な記述と説明責任の履行
- 経営陣の関与によるガバナンス強化
組織再編をめぐる税務調査の現状
組織再編税制の適用件数が増加する中で、税務調査における重点的な審査対象にもなりつつあります。特にM&Aを伴う大規模再編では、取引の背景や動機、グループ全体の再編方針までが詳細にチェックされます。
よくある指摘事例としては以下のとおりです。
- 「名目的な再編であり、事業の実体が伴っていない」
- 「一部株主の意向により形式的に適格性を装った」
- 「分割型分割を装いながら、実質は事業譲渡に該当する」
などが挙げられます。これらは結果として、再編効果を失うどころか、過大な税負担と追徴課税、場合によっては重加算税の対象にもなりかねません。
税務調査に備えるためには、スキーム設計段階から税理士・弁護士・会計士と連携し、実質的な再編目的や経済合理性を裏付ける資料を整備しておくことが不可欠です。
リスク回避のための専門家連携と事前対策
組織再編税制を円滑かつ安全に活用するためには、税理士、会計士、弁護士、M&Aアドバイザーなど、各専門家との連携が欠かせません。特に、複雑なスキームを伴う場合や、複数の法人・部門をまたぐ統合・分割では、法務・税務・会計・労務といった幅広い分野の知見が必要です。
実務上のポイントは以下のとおりです。
- 税理士による適格要件の詳細なチェックと税務意見書の取得
- 会計士によるのれん・資本取引の処理確認
- 弁護士による契約書・社内議事録の法的有効性の検証
- M&Aアドバイザーによる統合後の企業価値評価と相乗効果の算定
また、社内でも再編プロジェクトチームを設置し、総務・経理・法務・人事といった関連部署が横断的に連携してプロジェクトを推進することが成功の鍵となります。
最後に、再編実行後も「事後モニタリング」を継続し、税務調査や開示対応に備える体制を維持することが重要です。たとえば、再編後の財務報告書においてスキームの結果を説明する記載を用意し、関係者間で情報共有を行うことで、想定外のリスクに備えることができます。
成功事例と失敗事例に学ぶ実務ポイント
成功事例①:持株会社化によるグループ再編で税負担ゼロ
ある中堅製造業A社は、複数の事業子会社を抱える中で、「経営資源の集中」と「事業ポートフォリオの最適化」を図るため、持株会社体制への移行を決断しました。具体的には、A社が100%出資する新設のホールディングカンパニー(持株会社)を設立し、既存子会社の株式をすべて移転。その際に「株式移転」を活用し、組織再編税制における適格要件を満たすスキームとして設計されました。
適格性を確保するために以下の対策を講じたことが成功の鍵でした。
- 株式移転に係る「適格要件チェックリスト」を税理士と作成
- 子会社の事業内容、取引関係、雇用状況を全て開示・説明
- 株主との事前合意形成(特に少数株主対応)
- 株式継続保有の意向書を取得
その結果、課税繰延が認められ、持株会社化による資産評価益への課税は発生せず、数億円単位の税コスト削減に成功しました。さらに、財務の一元管理と経営の意思決定スピードも大幅に向上し、再編後3年で連結売上は20%以上成長する成果に結びついています。
成功事例②:事業承継を見据えた吸収分割による再構成
別のケースとして、関東で複数の医療法人を展開していたB社グループは、後継者への事業承継を機に、グループ内再編を検討しました。
旧体制では、個別法人ごとに人材・設備・財務体制が分断されており、将来的な承継や統合に支障がある状態でした。そこで、「吸収分割」によって、主要な診療部門を1つの医療法人へ集約。不要資産や非中核部門は別法人に切り出す再編スキームを採用しました。
税務上の適格性を維持するため、以下の手順を丁寧に実行。
- 分割対象事業の継続性を示す事業計画書を整備
- 給与体系・雇用条件の変更なし(転籍による不安回避)
- 医療法・法人税法の両面で適格判定を専門家がWチェック
これにより、事業承継時の資産再評価課税を回避しつつ、組織の合理化と人材流動性の確保に成功しました。承継後も経営のスムーズな引継ぎが可能となり、外部の医療グループとの業務提携にも道を開く結果となりました。
失敗事例①:適格要件を見誤り数千万円の追徴課税
あるIT企業C社は、グループ内の機能を統合する目的で、新設合併を実施しました。税理士の助言のもと、組織再編税制の適格合併を前提として実行されましたが、事前に要件の詳細を十分に検証していなかったため、想定外の課税リスクに直面することになりました。
問題となったのは以下の点です。
- 合併対象の一方が「休眠会社」であり、事業実態が認められず
- 合併後にすぐ休業状態へ移行したことにより、継続性が否定
- 税務調査により「形式的な再編」と見なされ、否認処理
結果として、帳簿価額を超える資産評価益が課税対象となり、法人税と地方税を合わせて3,000万円以上の追徴課税を受ける事態となりました。この事例は、「節税スキーム」として表面的に制度を利用することのリスクを如実に示しています。
失敗事例②:株式交換での対価設計ミス
関西の卸売業D社は、親会社へのグループ化を目的に株式交換を実行。対価としてD社株主に現金と株式を交付する設計でした。しかし、この設計が組織再編税制の「適格株式交換」の要件を逸脱しており、非適格取引として取り扱われる結果となりました。
問題点は以下のとおりです。
- 現金部分が全体対価の20%超となっていた(要件違反)
- 株主説明資料に対価構成の明確な記載がなく、透明性不足
- 結果的に、株式評価益に対して所得税課税が発生
この件では、株主側にも思わぬ課税が発生したことで、株主からの反発や信頼失墜を招き、再編プロジェクト全体の正当性まで問われる事態に発展しました。
成功・失敗から学ぶ実務上の教訓
これらの事例が示す通り、組織再編税制の活用には「設計段階の精密さ」と「制度への深い理解」が不可欠です。とくに以下の3点は、すべての再編実務に通底する成功の鍵と言えるでしょう。
- 税務と経営戦略の整合性を担保すること
- 事前の専門家連携による多角的なシミュレーション
- 文書による裏付け(継続性、実質性、関係性)を怠らないこと
成功企業は、「税制を使う」のではなく「税制に沿って再編を最適化している」点が共通しています。つまり、税制はあくまで補助線であり、再編の主目的が経営的合理性と整合しているかが最重要ということです。
組織再編税制の今後の展望と企業への示唆
税制改正の動向と政策的意図
組織再編税制は、2001年の導入以降、企業再編の活性化と国際競争力の強化を目的として改正が繰り返されてきました。近年では、単なるグループ内再編だけでなく、スタートアップ支援やオープンイノベーションの推進といった、経済成長戦略の一環としての位置づけが強まっています。
たとえば、2021年税制改正では、「事業ポートフォリオの最適化」や「人的資本の有効活用」といった政策目的に基づき、より柔軟なスキーム適用が認められるようになりました。今後も、経済・社会の構造変化(デジタル化・グローバル化・人的資源の流動性)に対応するかたちで、制度の進化が求められるでしょう。
今後の主な論点としては以下が想定されます。
- 中小企業再編への税制支援拡大
- 海外子会社とのクロスボーダー再編への適格性見直し
- 企業グループの支配構造の明確化と租税回避規制の強化
- ESG・サステナビリティ再編(脱炭素や人権経営)との整合性
企業は、制度変更の「事後対応」ではなく、「事前予測」と「スキーム適合力」の強化が求められます。
企業が取り組むべき戦略的アプローチ
これからの組織再編は、「節税目的」ではなく、企業価値の最大化を主眼とした経営判断の一環であることが強く求められます。再編そのものが目的ではなく、その先にある事業成長、効率化、資本コストの最適化、人的資源の再配置といった課題解決に繋がっている必要があります。
そのために、企業が講じるべき戦略的アプローチは以下の通りです。
- 【経営戦略と整合した再編目的の明文化】
事業ドメインの統合・分離、子会社整理、海外展開など、経営レベルでの意思決定と制度適用の一体化が重要です。 - 【再編後のオペレーション計画・人事制度の見直し】
制度上の適格性よりも、実態としての統合効果・PMI(統合後の経営)が評価される時代です。 - 【外部ステークホルダーとのコミュニケーション設計】
株主、投資家、従業員、取引先など利害関係者への丁寧な説明と合意形成が不可欠です。 - 【自社内における「再編の型」の蓄積】
同様の手法を繰り返すことで、内部ノウハウを体系化し、再編を機動的に実行できる体制を構築することが、競争優位に繋がります。
専門家との連携による価値創出
再編の成功は、適切なスキーム選定と税務対応だけでなく、専門家との継続的な連携によってもたらされます。
特に以下のような場面では、外部知見の活用が大きな成果を生みます。
- 組織再編に精通したM&AアドバイザーによるPMI支援
- 会計士による買収後の統合財務システム設計
- 弁護士による株主間契約、労務対応などの法的整理
- 税理士による制度改正へのタイムリーな対応とリスク最小化
また、近年ではAIやクラウドシステムを活用した再編支援も進んでおり、組織再編を一過性のイベントではなく、継続的な「事業変革プロセス」として捉えることが求められています。
組織再編税制の将来展望と戦略的活用
制度改正の動向と今後の注目点
組織再編税制は、企業のM&Aやグループ再編の活性化を促す目的で2001年に導入され、その後も幾度となく法改正が行われてきました。とくに近年は、スタートアップ支援やグローバル対応を意識した制度整備が進められており、今後も「柔軟性」と「透明性」を両立した制度へと進化していくと見られます。
たとえば、直近の改正では、適格要件の見直しや、企業グループ内での資産移転に係る繰延制度の簡素化が図られており、今後は次のような点が議論の焦点になると予測されます。
- 事業再編における“実質判定”基準の明確化
- 税務コンプライアンスのデジタル化対応(電子帳簿保存・e-Tax連携)
- 国際的なM&Aにおける再編スキームへの対応強化
- 無形資産移転(知財・データ)の組織再編税制上の取扱い
企業としては、これらの動向を継続的にウォッチし、柔軟な制度適応力を持つことが求められます。
中堅・中小企業における実務上の可能性
従来は大企業・上場企業を中心に活用されてきた組織再編税制ですが、最近では中堅・中小企業でも積極的に導入する事例が増えています。たとえば、親族内承継や役員間での事業承継を円滑に行う手段として、会社分割や株式交換を活用するケースが代表的です。
また、地域密着型の中小企業がホールディングス化を進めることにより、次のようなメリットを享受できるようになっています。
- 事業部門ごとの経営責任の明確化
- 事業承継時の株式移転による税負担軽減
- グループガバナンスの強化
一方で、税務・法務・会計の各分野における実務対応が不十分なまま実行されることも多く、リスク管理やスキーム設計において専門家の関与が不可欠です。
税務戦略としての活用法と注意点
組織再編税制を「節税手法」としてのみ捉えるのではなく、「経営戦略の一部」として位置づけることが、長期的に見て最も効果的な活用方法です。事業ポートフォリオの再構築、新規事業への参入、事業撤退など、経営判断と連動した再編こそが、税制の本質的なメリットを引き出す手段となります。
そのためには、以下のような姿勢が重要です。
- 初期段階から税務顧問やM&Aアドバイザーと戦略を擦り合わせる
- 再編後の組織像を見据えた経営計画の立案
- 社内外のステークホルダーとの情報共有と合意形成
- 「形式」より「実質」を重視した文書・根拠の整備
制度上のメリットを確実に享受するためには、単なる書類整備や形式要件の充足ではなく、「このスキームが自社にとってどのような合理性を持つか」という問いへの明確な答えが求められます。
組織再編に強いパートナーの選び方
組織再編を成功に導くためには、経験豊富で信頼できる外部パートナーの存在が欠かせません。とくに、税務のみならず、会計・法務・M&A・人事制度まで総合的に支援できる体制を持つ専門家チームとの連携が理想です。
選定の際には、以下のポイントを重視しましょう。
- 組織再編に関する実績と事例の豊富さ
- スキーム設計だけでなく、実行・PMIまで一貫支援が可能か
- 法人税・消費税・所得税など多角的な税務視点でのアドバイス
- 業種特化型の知見(製造業、医療福祉、ITなど)
また、再編後の持続的な成長を支えるためには、単発のコンサルではなく、継続的な顧問契約や経営支援まで見据えたパートナーシップ構築が望まれます。
まとめ
組織再編税制は単なる節税の道具ではなく、企業成長のための「戦略的ツール」であるという視点が重要です。制度の複雑さや形式的な要件に目を奪われるのではなく、経営課題を解決し、企業価値を最大化する手段として活用していく姿勢が求められます。
制度適用の判断や実務の遂行においては、会計・税務・法務の視点を統合しながら、「実態に即した再編」を設計することが肝要です。特に、PMI(統合後の運営)や人的リソースの最適化といった観点を再編前から組み込むことが、成功の鍵を握ります。
企業単独で再編を進めるには、制度知識・スキーム設計・税務対応・社内調整など、数多くの専門的課題を乗り越える必要があります。そのため、実務経験豊富な専門家との連携が不可欠です。たとえば、M&Aの実行支援から再編後の管理体制構築まで一気通貫でサポートできるパートナーと連携することで、スキームの精度が高まり、税務否認リスクを最小限に抑えることができますので、組織再編の予定がある場合はぜひ検討ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。