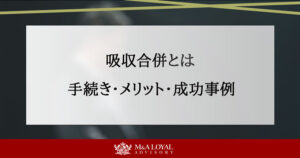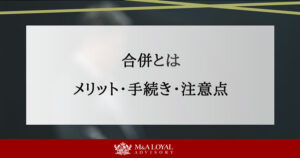合併企業の一覧30選!成功事例から失敗事例【2025年最新】
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
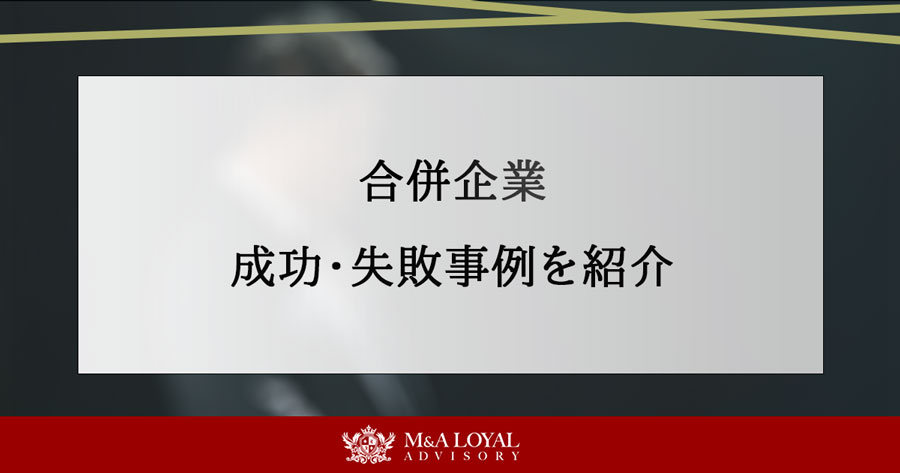
企業の合併は、経営資源の再編や競争力の強化を目的に行われる重要な経営戦略です。しかし、全ての合併が成功するわけではなく、明暗が分かれるケースも少なくありません。
本記事では、企業合併の事例30選を、成功事例・失敗事例に分類して紹介し、それぞれの背景や結果から学ぶべき教訓を探ります。
また、合併の種類や経営統合との違い、国内外のM&A動向、株価算定の仕組みなど、実務に役立つ基礎知識も併せて解説します。
目次
企業合併とは
まず、企業合併に関する基本的な知識について解説します。
企業同士が結合すること
企業合併とは、複数の企業が法的に一つの会社へ統合されることを指します。これはM&A(Mergers and Acquisitions)のうち「Mergers(合併)」に該当する手法です。合併によって一方または全ての企業が消滅し、権利義務が統合されます。
企業合併は、単に経営権が移転するだけの買収とは異なり、法的にも経済的にもより深い統合を伴います。事業規模の拡大や資源の最適化、経営効率の向上などを目的に用いられ、グループ再編や業界再編の局面でよく活用されます。
企業合併の種類
企業合併には大きく分けて「吸収合併」と「新設合併」の2種類があります。どちらも複数企業が一つに統合される点は共通していますが、統合後の存続形式や法的手続きに違いがあります。
吸収合併
吸収合併とは、一方の会社(存続会社)が他方の会社(消滅会社)を取り込む形で合併し、消滅会社の全権利義務を引き継ぐ手法です。比較的手続きが簡便であることから、実務では最も一般的に用いられます。
特に子会社の整理統合や経営不振企業の救済において利用される場面が多く、存続会社の許認可・契約・上場資格などを維持できる点が大きな利点です。
ただし、企業間に優劣や上下関係の印象を与えるという懸念もあります。
新設合併
新設合併は、複数の企業が同時に解散し、新たに設立された会社へ全権利義務を承継させる合併手法です。
統合される企業同士が対等の立場で合意することが多く、公平性が重視されます。新設会社が新たに全てを引き継ぐため、ブランドや社名の刷新などを伴いやすい点が特徴です。
ただし、許認可の再取得や上場手続きのやり直しなど、行政的・実務的な負担が大きい点がデメリットとされます。
合併と経営統合の違い
合併と経営統合はいずれも複数の企業をまとめる手法ですが、法人格の扱いや統合の実態に明確な違いがあります。
合併は会社法上の手続きに基づき、存続会社以外の企業の法人格が消滅し、全ての権利義務が存続会社に承継されます。吸収合併や新設合併の形をとることで、最終的に一つの会社に集約される点が特徴です。
一方、経営統合は、持株会社の設立や株式の移転・交換を通じて、各企業の法人格を存続させたままグループ化し、意思決定機能のみを一元化する仕組みです。各社は完全子会社として存続しながら、親会社の方針に従って事業運営を行います。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



企業合併の近年の成功事例12選
近年に行われた企業合併の中から、業績の向上や事業基盤の強化につながった事例を取り上げ、それぞれの背景や成果を解説します。
JR東海リテイリング・プラス
JR東海リテイリング・プラスは、2023年10月に東海キヨスク株式会社と株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズが合併して誕生した企業です。なお、合併は東海キヨスクを存続会社とする吸収合併の形式で実施されました。
東海キヨスクは駅構内で土産品や飲料を販売する小売業を、ジェイアール東海パッセンジャーズは新幹線の車内販売や駅弁製造を担っていました。
合併の目的は、駅構内の店舗を集約・大型化し、土産品・弁当・飲料を一体的に提供することで利便性を高めることにあります。さらに、ご当地商品の強化や作り立て食品の提供、フランチャイズ事業の拡充など、多様な利用者ニーズに対応した店舗展開を推進する方針が示されています。
ベクトル
2023年10月、企業PRやコンサルティング事業を展開するベクトルは、完全子会社である株式会社スマートメディアを吸収合併すると発表しました。これにより、スマートメディアは2024年1月1日付で解散し、法人格が消滅しました。
スマートメディアは、2018年にベクトル傘下のLAUGHTECHとOPENERS、JIONの3社が合併して誕生した企業です。3社が手がけていたウェブメディアの運営実績や制作ノウハウを統合し、オウンドメディア制作やSNS運用支援など、デジタルコンテンツ領域で事業を展開してきました。合併による相乗効果を生かし、多様なクライアントのマーケティング活動を支える体制を築いてきた点が特徴です。
今回の合併は、ベクトルが進めるマーケティングの全工程を一貫して支援する体制をより強固にするための一手です。主力であるPR事業のサービス領域が広がる中で、スマートメディアの機能をグループ本体に取り込み、PRとの連携を深めることで、経営の合理化と事業間のシナジーを高める狙いがあります。
大阪公立大学
大阪公立大学は、大阪府立大学と大阪市立大学の統合により、2022年4月に新設された公立大学です。両大学の再編構想は2011年に始まり、2019年には運営法人が合併して統合の基盤が整いました。教育・研究資源を集約し、組織のスケールメリットを生かすことで、国際的にも競争力のある大学を目指しています。
新大学は、従来の両大学の特色を生かしつつ、11学部1学域の体制へと再編され、分野横断的な学びを可能にしました。学生数は約1万6千人にのぼり、国公立大学の中でも上位に位置する大規模な大学です。
統合により経営の効率化が進むだけでなく、グローバル展開や研究力の強化にも注力しており、世界大学ランキング200位以内を将来的な目標に掲げています。
ソフトバンクとLINEモバイル
ソフトバンク株式会社は、通信事業を展開する企業で、2022年3月に完全子会社であるLINEモバイル株式会社を吸収合併しました。合併はソフトバンクを存続会社とする簡易吸収合併の形式で行われ、LINEモバイルは解散しました。
合併の目的は、ソフトバンクが展開するオンライン専用ブランド「LINEMO」と、LINEプラットフォームとの連携を強化することにありました。
LINEモバイルが持つMVNOサービスのノウハウを生かしながら、契約や利用手続きの完全オンライン化を進めることが狙いです。また、LINEの通信をデータ容量の消費なしで利用できる「LINEギガフリー」といった独自機能の提供体制を整えることも重要な目的でした。
現在は、LINEモバイルの新規受付は終了しており、LINEMOブランドの下でサービス提供が継続されています。
三菱UFJリースと日立キャピタル
三菱UFJリースと日立キャピタルは、いずれもリース事業を主力とする企業で、2021年4月に合併しました。なお、合併は吸収合併の形で行われ、三菱UFJリースを存続会社とし、日立キャピタルの法人格は消滅しました。
合併の目的は、長引く低金利や新型コロナウイルスの影響で厳しさを増す事業環境の中、経営基盤を強化し、両社の得意分野を補完して収益機会を広げることにありました。合併によって誕生した三菱HCキャピタルは、総資産約10兆円となり、リース業界ではオリックスに次ぐ規模となりました。
航空機や太陽光発電に強みを持つ三菱UFJリースと、販売金融や風力発電に実績のある日立キャピタルの統合によって、再生可能エネルギー分野などの成長市場でシナジーを発揮しています。
はごろもフーズ
はごろもフーズ株式会社は、2021年3月にギフト製品の製造・販売を行う100%子会社のはごろも商事株式会社を吸収合併しました。合併は、はごろもフーズを存続会社とする吸収合併の形式で実施され、はごろも商事は法人格を消滅しました。
合併の目的は、経営資源の集中と効率化を通じて事業価値を向上させることにあります。なお、今回の合併は、会社法上の簡易合併・略式合併に該当し、株主総会の承認を経ることなく実施されました。
日本調剤
日本調剤は、2021年1月1日付で100%子会社の株式会社ライムを吸収合併することを決定しました。合併は、日本調剤を存続会社、ライムを消滅会社とする吸収合併方式で実施され、これによりライムの法人格は消滅しました。
ライムはこれまで、日本調剤グループの一員として全国各地で薬局を運営し、地域の患者に身近な医療サービスを提供してきました。今回の合併は、同社の機能を本体に統合することで、調剤薬局事業の一元管理体制を構築し、グループ全体としてのオペレーションの均質化と管理の効率化を推進する狙いがあります。
また、経営資源の集中と意思決定の迅速化を図ることで、激変する医療・薬局業界の環境変化に柔軟に対応し、地域医療への貢献を一層高める体制を整えることも目的としています。
日本製鉄
日本製鉄は、2019年10月に完全子会社である日鉄日新製鋼株式会社を、2020年4月1日付で吸収合併することを発表しました。合併は、日本製鉄を存続会社、日鉄日新製鋼を消滅会社とする吸収合併方式で実施され、これにより日新製鋼の法人格は消滅しました。
2017年に子会社化し、2019年に完全子会社化していた日新製鋼ですが、経営環境の急速な悪化や度重なる災害・事故への対応を背景として、本格的な一体運営体制の構築が決断されました。
経営資源の最適配分や間接部門の統合を通じてコスト削減を図り、グループの競争力を高めるとともに、将来的な設備削減も見据えた柔軟かつ機動的な事業運営体制の確立を目指しました。
なお、日本製鉄株式会社は、2012年に新日本製鐵と住友金属工業が合併して誕生した「新日鐵住金株式会社」を前身としています。両社の技術力と事業基盤を統合することで国内外での競争力強化を図り、2019年には社名を「日本製鉄株式会社」へと変更しました。
さらに、2025年には米国の老舗鉄鋼大手であるUSスチールの完全子会社化を成功させ、国内外から大きな注目を集めています。
ロッテ
ロッテは2018年4月、グループ再編の一環として傘下のロッテとロッテ商事、ロッテアイスの3社を合併しました。製造から販売までを一社に集約することで、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図り、新体制での成長を目指しました。
これにより、従来は分断されていた菓子とアイスの企画・製造・販売が一体化され、業務効率と投資効果が向上しています。また、ブランドの一貫した戦略展開が可能となり、「ガーナ」「チョコパイ」「雪見だいふく」などの主力商品の強化と新商品開発を並行して推進しています。
オイシックス・ラ・大地
有機野菜宅配のオイシックスと大地を守る会が2017年に経営統合して「オイシックスドット大地」誕生しました。両社の統合により、宅配業界で一躍最大手となり、翌2018年には業界2位のらでぃっしゅぼーやを吸収合併し、社名も同年7月に「オイシックス・ラ・大地」へと変更され、三つのブランドを統合する新体制が整えられました。
これにより、調達から物流、デジタルマーケティングに至るまでグループ全体のシナジーを高め、高付加価値な食品宅配市場をけん引する基盤が築かれました。
統合効果で売り上げ規模は600億円を超え、ミールキット事業や移動販売など多様なサービス展開も進んでいます。
U-NEXT
2017年12月、動画配信サービスを展開するU-NEXTと、有線放送を手がけるUSENが経営統合を実施しました。U-NEXTを存続会社とする吸収合併の形式で、USENは上場を廃止し、「USEN-NEXT HOLDINGS(現:U-NEXT HOLDINGS)」へと組織体制を移行しました。この統合は、規模の小さいU-NEXTが存続会社となる珍しいパターンとして注目されました。
統合の背景には、成長市場にあるU-NEXTの拡大戦略と、安定した基盤を持つUSENの事業資源を掛け合わせ、両社の強みを補完する狙いがありました。U-NEXTは、当時赤字を抱えつつも映像配信でシェアを伸ばしており、法人向け営業力を持つUSENと統合することで新たな市場開拓を目指しました。
ENEOS
ENEOSは、2017年4月にJXエネルギーが東燃ゼネラル石油を吸収合併し、JXTGエネルギーとして新たに発足しました。
この合併は、両社の親会社であるJXホールディングスと東燃ゼネラルの株式交換を経た後、エネルギー事業を一体化する形で実施されました。少子高齢化や省エネ技術の進展で国内の石油需要が減少する中、事業基盤の強化と国際競争力の向上を目的として行われたものです。
さらに2020年には、社名をENEOSに変更し、ブランドの統一と認知度向上を図りました。ENEOSは国内最大のガソリンスタンド網を有し、ガソリン販売量でトップシェアを誇ります。
著名な企業合併の成功事例10選
過去に実施された企業合併の中から、特に知名度が高く、経営面でも一定の成果を収めた成功事例を厳選し、各企業の動向や合併の影響を紹介します。
三菱UFJ銀行
2006年に東京三菱銀行とUFJ銀行が合併して「三菱東京UFJ銀行」が誕生しました。東京三菱銀行は、三菱銀行と東京銀行の合併により発足し、UFJ銀行も三和銀行と東海銀行の合併によって形成された背景があります。
この合併は、金融持株会社制度の導入後に進んだ都市銀行再編の集大成であり、合併当時の総資産は約190兆円に達しました。経営統合の狙いは、国際的な競争力の強化と業務効率の向上にありました。
その後、2018年にはブランドの統一とグループ一体経営を明確にするため、「三菱東京UFJ銀行」から「三菱UFJ銀行」へと行名を変更しました。現在では日本最大級のメガバンクとして、国内外で広範な金融サービスを展開しています。
イオングループ
イオングループは、合併を中核としたM&A戦略によって急成長を遂げてきた代表的な企業です。その始まりは1969年、現名誉会長・岡田卓也氏がフタギに合併を提案し、「岡田屋」「フタギ」「シロ」の三社統合でジャスコが誕生したことにあります。
その後も合併・買収を軸に流通網を拡大し、ダイエーやマイカルなどの大手を傘下に収めるなど、規模の経済を追求してきました。2022年には100円ショップ大手キャンドゥをTOBにより子会社化し、成長の手を緩めていません。
また、国内にとどまらず、マレーシアや中国をはじめとするアジア各国にも進出し、グローバル展開も進めています。
大丸と松坂屋
百貨店大手の大丸と松坂屋は、2007年に共同持株会社「J.フロント リテイリング」を設立し、経営統合を実現しました。その後、2010年に松坂屋を存続会社とする形で吸収合併し、新会社「大丸松坂屋百貨店」として一本化されました。
統合の背景には、少子高齢化や消費者ニーズの多様化により百貨店事業の競争力が低下していたことがあります。特に松坂屋は名古屋店での競争激化や銀座店の再開発問題などを抱えていたため、経営体制の強化が急務となっていました。
合併後は、大丸の社長が新会社の代表に就任し、持株会社はグループ戦略の立案や経営資源の配分などに特化する体制へと移行しました。
三越と伊勢丹
2008年、三越と伊勢丹は経営統合し、「三越伊勢丹ホールディングス」が発足しました。形式上は対等合併でしたが、業績好調だった伊勢丹が実質的に主導し、経営や商品戦略は伊勢丹色が強まりました。
合併は、百貨店業界の構造不況やEC拡大への対応として「選択と集中」を進める狙いがありました。地方店舗の整理と基幹店への資源集中が奏功し、収益体質が改善しました。2025年3月期には伊勢丹新宿本店の売り上げが4212億円と過去最高を記録し、グループ純利益も528億円を達成しました。
2026年3月期は純利益600億円と、14年ぶりの最高益更新を見込んでいます。訪日客需要はやや鈍化するものの、国内富裕層の高額品需要と構造改革が業績を支えています。
マルハニチロ
マルハニチロは、マルハとニチロの経営統合によって2007年に誕生しました。さらに、2014年には完全子会社5社とともにマルハニチロ水産を存続会社として6社合併を行いました。これにより純粋持株会社制から事業持株会社制へ移行し、経営の合理化と効率化を図りました。
なお、合併前には、グループ会社アクリフーズで冷凍食品への農薬混入事件が発生し信用を損ねましたが、体質改善により信頼と業績を回復させています。その後もマリンアクセスとリテールサービスの合併を実施し、マグロ事業の統合運営を推進しています。
2026年には社名を「Umios」へ変更し、高輪ゲートウェイシティへの本社移転を予定しています。新社名には海を起点に食で社会課題を解決する決意が込められ、海外経常利益比率70%以上と世界トップ10入りを目標とした長期ビジョンの下、新たな成長戦略に取り組んでいます。
ワイモバイル
2014年6月、ソフトバンクグループ傘下のイー・アクセスとウィルコムが合併し、新たにワイモバイル株式会社として事業を開始しました。イー・アクセスの携帯電話事業とウィルコムのPHS事業を統合し、低価格かつ定額制の通信サービスをさらに強化する狙いがありました。
新ブランド「Y!mobile」も立ち上げられ、スマートフォン市場への本格参入が始まりました。この合併により、店舗網や契約数の拡大、端末開発の効率化が進められ、格安スマホ市場での競争力が高まりました。
2015年4月には、ワイモバイル株式会社がソフトバンクBBやソフトバンクテレコムとともにソフトバンクモバイルに吸収合併され、現在はソフトバンク株式会社の一部門として運営されています。
幻冬舎
2010年、幻冬舎の見城徹社長は、出版不況や株価低迷を背景に、MBO(経営陣による企業の株式や事業部門の買い取り)による上場廃止を決断しました。
特別目的会社TKホールディングスを設立し、自身が借り入れた約60億円超の資金で幻冬舎株の買収を進めましたが、外部ファンド「イザベル・リミテッド」が株式の3分の1以上を取得したことで、上場廃止の可決が困難となりました。その後、TOB価格を引き上げるなど対応を講じた結果、イザベルが議決権を行使しなかったことから、株主総会では上場廃止が可決されました。
2011年にはTKホールディングスを消滅会社とし、幻冬舎を存続会社とする吸収合併が実施され、MBOが成立しました。
アステラス製薬
2005年に山之内製薬と藤沢薬品工業が合併し、アステラス製薬が誕生しました。両社は泌尿器・免疫といった得意分野や技術を補完し合い、経営資源をがん領域に集中させる戦略を採用しました。
合併翌年には大衆薬事業を売却し、新薬開発に特化した結果、前立腺がん治療薬「イクスタンジ」が年商1000億円を超えるなど成果を上げました。パイプラインの充実や再生医療分野への参入、共同研究の強化など、内外の資源を柔軟に取り込みながら競争力を高めています。
エディオン
エディオンは2002年にデオデオとエイデンが設立した共同持株会社として発足しました。
2005年にミドリ電化を子会社化、2009年にデオデオとミドリ電化を合併しました。2010年にはエディオンEASTとエディオンWESTを吸収合併し、本体に一本化するなど、効率的な経営体制を確立しています。
さらに、2012年には「イシマル」「エイデン」「ミドリ」「デオデオ」の店舗ブランドを「エディオン」に統一し、情報システムや物流機能も再編することで、競争力の強化を実現しています。
その後も、リユースや物流、通販、不動産、スポーツ、運輸など多様な分野で合併や子会社化を重ね、現在まで事業領域を拡大しています。
スクウェア・エニックス
スクウェアとエニックスは、ゲーム産業の環境変化に対応する経営戦略として、2003年4月に吸収合併の形式で経営統合しました。形式上はエニックスが存続会社となりましたが、商号は「スクウェア・エニックス」となり、スクウェアの社長が新会社のトップに就任しています。
経営危機に直面していたスクウェアと、収益の不安定さを抱えていたエニックスが、ネットワークやモバイルといった新領域への展開を見据えて手を結んだ形です。
欧米市場に強いスクウェアと、アジアでの展開に注力していたエニックスの戦略が補完し合い、合併後はタイトーの完全子会社化や海外子会社の統合を進めるなど、積極的なグローバル展開を図っています。
企業合併の失敗事例8選
企業合併が必ずしも成功するとは限らず、実際に大きな損失や混乱を招いた失敗事例もあります。合併の目的や背景、失敗に至った要因とその後の影響について紹介します。
RIZAP
RIZAPグループは、本業とは異なる業種の企業を次々に合併・買収する戦略を展開し、成長を急ぎました。買収価格が純資産を下回る企業を中心に取得した結果、負ののれんを利益に計上して業績を一時的に押し上げましたが、再建に時間を要し、立て直しが追いつかなくなりました。
特に2019年3月期には、構造改革費用の増加と買収先の不振によって営業損益が93億円の赤字に転落し、過去最大の最終赤字を記録しています。さらに、海外展開の欠如や利幅の小さい業態の買収、シナジーの薄い異業種M&Aも影響し、成長戦略は頓挫しました。
経営改善を図るため、同社は一部子会社の売却などの再建体制の整備に取り組んでいます。また、2022年以降はchocoZAP事業の急拡大により業績が回復傾向にあります。
AOLとタイムワーナー
2000年、アメリカの大手インターネット企業AOLは、通信・メディア大手のタイムワーナーと合併しました。この合併は「世紀の合併」とも呼ばれ、ネットと旧メディアの融合を目指す試みでした。
しかし、直後にITバブルが崩壊し、広告収入の急減や企業文化の乖離が深刻化したことにより、2002年には約1,000億ドルの最終赤字を計上します。社員は出身企業の利害に固執し、新会社としての一体感を築けませんでした。
2009年にはAOLの分離が決定され、合併は正式に解消されました。CEOのレビン氏は、失敗の要因として人的要素への配慮不足を悔やみ、どれほど優れたビジョンがあっても社員の共感なくして成功は難しいと振り返っています。
ダイムラー・ベンツとクライスラー
1998年、ダイムラー・ベンツとクライスラーは「対等合併」を発表し、ダイムラー・クライスラーが誕生しました。しかし実態はダイムラー主導で、ドイツ流の支配的な姿勢がクライスラー側に受け入れられず、幹部の対立や人材流出が相次ぎました。
また、ベンツブランドのイメージ維持を優先し、クライスラーに対する技術供与は限定的でした。その結果、両社の強みを生かした協業は進まず、統合によるシナジーは実現しませんでした。
加えて、アジアでの三菱自動車や現代自動車との資本提携でも同様に高圧的な姿勢が反発を招き、いずれも関係解消に至りました。現地の市場特性を十分に考慮しないマーケティングも裏目に出て、世界戦略全体が失速し、業績悪化に拍車をかけました。
2007年、ダイムラーはクライスラーをファンドに売却し、約9年で合併は解消されました。
LIXIL
2011年、大手製陶企業INAXと建材大手トステムは、新日軽とサンウエーブ工業、東洋エクステリアと合併し、住宅設備の総合企業LIXILを設立しました。
旧来の事業会社の機能を再編し、住宅市場の変化に対応するため、機能別のカンパニー制に移行しました。社名はLIXILに統一されましたが、各社のブランドは継続して使用されています。
しかし、合併後の経営ではトステム創業家の潮田氏とINAX創業家出身の伊奈氏との対立が表面化し、2019年3月期には約150億円の営業損失を計上しました。その後、経営は立て直されて市場からの信頼も復活しましたが、創業家間のあつれきは合併の負の側面も浮き彫りにしました。
みずほ銀行
2002年、第一勧業銀行・富士銀行・日本興業銀行が合併し、みずほ銀行が発足しました。
統合時には「世界最大の銀行」として注目を集めましたが、実態は経営危機に直面していた銀行同士が生き残りを図った防衛的措置でした。持ち株会社方式で権力構造が温存されたことから、意思決定の遅れが常態化しました。
発足初日には大規模なシステム障害が発生し、三菱UFJ銀行と三井住友銀行、みずほ銀行からなる三大メガバンクの中で、みずほが後れを取る要因となりました。
日本航空と日本エアシステム
2002年、日本航空(JAL)と日本エアシステム(JAS)は、段階的な経営統合を開始しました。そして2006年にJASが吸収合併される形で完全統合を果たしました。
合併はネットワークの拡充や国際競争力の強化を目的として進められましたが、公正取引委員会は競争制限の恐れを指摘しており、実際に運賃の上昇といった不利益が表面化しました。
さらに、不採算路線の整理が進まず、大型機材の非効率な運用や非中核事業への過剰投資、複雑な労働体制などの構造的課題が重なった結果、2010年にJALは経営破綻に至りました。JASとの合併も破綻の要因の一つと指摘されています。
その後、JALは企業再生支援機構の支援の下、大規模な人員整理や年金削減を実施し、2012年には再上場を果たしています。
ファミリーマートとサークルKサンクス
2016年、ファミリーマートはユニーグループ・ホールディングスを吸収合併し、サークルKサンクスと経営統合を進めました。ブランド転換は2016年9月に開始され、2018年11月に全国約5,000店の統合を完了しました。
商品や物流拠点の統合によって売り上げや客数は一定の伸びを見せましたが、当初の想定以上に不採算店舗の閉鎖が発生し、業界シェアは減少しました。また、ロイヤルティ増加や経営方針の変化に対する不満が加盟店オーナーの間で広がり、ベンダー企業にも混乱が生じました。
ファミリーマートは統合完了後も質の高い店舗づくりや伊藤忠商事との連携による成長戦略の推進を行っています。2021年には新型コロナウイルス感染症の影響で、都市部の店舗を中心に売り上げが減少し、統合後初の最終赤字を計上する時期もありましたが、現在は安定して黒字経営を続けています。
そごうと西武百貨店
「そごう」と「西武百貨店」は、2009年にセブン&アイ・ホールディングス傘下のミレニアムリテイリングを通じて合併しました。株式会社そごうを存続会社とし、「株式会社そごう・西武」として新たに発足しました。本部機能の統合や運営効率の向上を目的とした再編でした。
しかし、百貨店業界の構造不況や消費低迷の影響で、業績は低迷を続け、2023年2月期には、4期連続の最終赤字に陥りました。
セブン&アイは成長分野に経営資源を集中させる方針の下、そごう・西武の売却を決定しました。労働組合はこれに反発し、ストライキを実施しましたが、最終的に雇用維持などに配慮した形で調整が進められました。
2023年9月、そごう・西武は米フォートレス・インベストメント・グループの関係会社に全株式が譲渡され、売却が完了しました。今後は全国の10店舗で改装が予定されており、2025年には西武池袋本店の全面改装が行われています。
近年のM&Aの動向
近年のM&Aは、世界と日本国内で異なる動きを見せています。それぞれにおける件数の推移や背景要因、注目される分野や今後の見通しについて解説します。
世界のM&Aの動向
2024年の世界におけるM&A件数は約5万件と、前年より14%減少しました。これは3年連続の減少であり、主な原因は各国の金利高止まりによる資金調達コストの上昇です。加えて、米英仏をはじめとする主要国での選挙や、米中対立を含む地政学的リスクが企業の買収判断に影響を与えました。
ただし産業・サービス分野では、成長戦略の一環として買収を進める動きがあり、特にAI・自動化・エネルギートランジション関連の技術取得を目的としたM&Aが目立ちます。また、企業は事業ポートフォリオの再編やノンコア事業の切り離しに注力しており、カーブアウトや分社化も活発です。
今後、金利の低下やインフレ圧力の緩和が進めば、再びグローバルM&Aが活性化する可能性があります。
国内のM&Aの動向
日本国内では、少子高齢化と中小企業の後継者不在が深刻化する中、M&Aは事業承継手段としての重要性を増しています。
中小企業庁の推計によれば、2025年には70歳を超える経営者が約245万人に達し、その半数以上が後継者未定の状態にあります。黒字廃業のリスクが高まる中、第三者による事業承継、すなわちM&Aの促進が政策的にも求められています。
上場企業においても、2024年には上場廃止を目的としたM&A(MBO・TOB含む)が前年から約32%増加し、新規上場件数を上回りました。市場の圧力や企業価値の再評価を背景に、株式非公開化を選ぶ企業が増加傾向にあります。
今後も、グループ内再編、経営資源の集中、新事業への転換を図るためのM&Aは活発に行われると見込まれます。
企業合併に関するQ&A
最後に、企業合併に関するよくある質問とその回答を紹介します。
企業合併によって株価にどんな影響があるか
企業合併は、株価に大きな影響を与えることがあります。
投資家が合併によって得られるシナジー効果や収益拡大を期待する場合、発表後に株価が上昇することが一般的です。特に、ブランド価値の向上や新規事業の展開が見込まれるケースでは、株価が安定的に上昇する傾向があります。
一方で、合併による資金負担が大きい場合や、相手企業に対する市場の評価が低い場合には、株価が下落する可能性もあります。また、合併交渉の混乱や情報の不透明さが不安材料となり、投資家心理を冷え込ませることもあります。
企業合併における株価算定方法はどんな方法があるか
企業合併では、公正な合併比率を決定するために、いくつかの株価算定方法が用いられます。
代表的な手法の一つが「DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)」で、将来のキャッシュフローを基に現在価値を算出する方法です。企業の将来性を反映しやすい一方で、事業計画に左右されやすく、恣意(しい)的な操作が入りやすいという課題もあります。
次に「市場株価法」は、過去の株価平均を基に客観的に評価する方法で、上場企業の合併に広く使われています。また、「純資産価額法」は、企業の保有資産をベースに評価する方法で、中小企業の合併時に用いられることが多いです。
企業合併は、経営資源の効率化や市場での競争力を高めるための重要な手段ですが、成功には綿密な計画と戦略が必要です。合併の事例を振り返ることで、成功の要因や失敗の原因を理解し、今後の対策に活かすことができます。合併の成功は、企業文化の統合や従業員の適応、顧客への影響など、多くの要素が絡み合っています。
合併を検討している方や興味を持つ方は、まずは成功事例から学び、リスク管理に努めることが重要です。もし、具体的な合併の方法やステップを知りたい場合は、専門家の意見を聞いたり、さらに詳しい資料を参考にすることをお勧めします。M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。