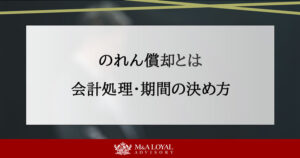減価償却費とは?仕訳や計算方法、耐用年数をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
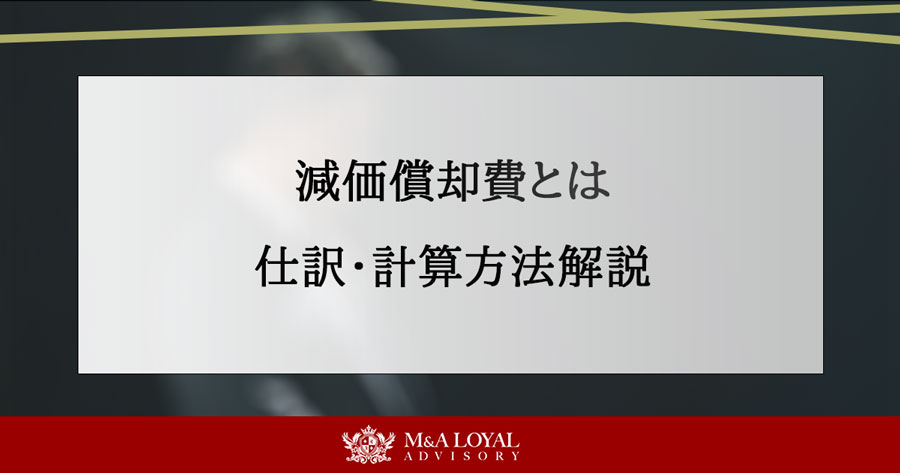
事業で使用する建物や機械、車両などの固定資産を購入した際、その費用を一括で経費計上するのではなく、使用期間に応じて分割して計上する「減価償却費」という会計処理があります。この処理は単なる帳簿上の手続きではなく、企業の正確な損益計算や税務対策、さらには将来のM&Aにおける企業価値評価にまで大きな影響を与える重要な要素です。
しかし、減価償却費の仕組みや計算方法について十分に理解している経営者や経理担当者は意外に少なく、適切な処理ができていないために節税機会を逃したり、税務調査で指摘を受けたりするケースも見受けられます。本記事では、減価償却費の基本的な考え方から実務での活用方法、注意すべきポイントまで、中小企業の実情に合わせてわかりやすく解説していきます。
目次
減価償却費とは何か?会計処理の基本概念
減価償却費とは、建物や機械設備、車両などの固定資産の取得費用を、その資産の使用可能期間(耐用年数)にわたって分割し、各事業年度に費用として計上する会計処理です。
この仕組みにより、資産の購入年度に一括して費用計上するのではなく、実際にその資産から便益を受ける期間に応じて適切に費用配分することができます。中小企業においても、正確な損益計算と適切な税務処理を行うために欠かせない重要な会計処理となっています。
固定資産の価値を期間配分する仕組み
減価償却は、固定資産が持つ経済的価値を時間の経過とともに費用として配分する会計手法です。例えば、1,200万円で購入した製造機械の耐用年数が10年の場合、毎年120万円ずつ減価償却費として計上します。これにより、資産の取得費用を実際に使用する期間に応じて合理的に配分でき、各年度の損益を正確に把握することが可能になります。
この期間配分の考え方は、企業会計原則における費用収益対応の原則に基づいており、事業の実態を適切に反映した財務諸表の作成に不可欠な要素です。
減価償却が必要な理由と会計上の意味
減価償却が必要な理由は、主に会計上の正確性と税務上の適正処理にあります。固定資産の購入費用を取得年度に一括計上すると、その年度の利益が大幅に減少し、翌年度以降の利益が実態以上に大きく表示されてしまいます。これでは各年度の経営成績を正しく判断できません。
減価償却により費用を適切に期間配分することで、毎年の利益が事業の実態を反映し、経営者や投資家、金融機関が正確な経営判断を行えるようになります。また、税務上も減価償却費は損金算入が認められているため、適切な節税効果も期待できます。
耐用年数の決まり方と確認方法
耐用年数は、法人税法の下位法令である「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に添付された別表(別表第一から第六)において、資産の種類、構造、用途に応じて詳細に定められています。例えば、普通自動車は6年、パソコンは4年、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の「事務所用のもの」は50年といった具合です。耐用年数の確認は、国税庁のホームページで公開されている「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を参照することができます。
また、中古資産の耐用年数を簡便的に計算する場合、その計算結果に1年未満の端数があれば切り捨て、年数が2年に満たない場合は2年とするルールがあります。正確な耐用年数の把握は、適切な減価償却計算の前提となる重要な要素です。
中小企業における減価償却の重要性
中小企業にとって減価償却は、特に重要な会計処理となります。まず、30万円未満の減価償却資産については、年間300万円を限度として取得年度に一括償却できる特例があり、これを活用することで大きな節税効果を得ることができます。
また、適切な減価償却処理により正確な損益計算が可能となり、銀行融資の審査や投資家との交渉において信頼性の高い財務諸表を提示できます。さらに、将来的なM&Aを検討している企業にとっては、減価償却の処理状況が企業価値評価に直接影響するため、日頃から正確な処理を心がけることが重要です。税務調査においても減価償却は重点確認項目の一つであり、適切な処理により税務リスクを回避できます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



減価償却費の対象となる資産・ならない資産の見分け方
減価償却の対象となる資産を正しく判断することは、適切な会計処理を行う上で重要なポイントです。基本的な判断基準は、事業の用に供している資産であること、時間の経過により価値が減少すること、使用可能期間が1年以上であること、そして一定額以上の取得価額であることです。これらの条件を満たす資産が減価償却の対象となりますが、実務では判断に迷うケースも多く、正確な理解が必要です。
事業用資産かつ経年劣化する有形資産の見分け方
有形資産のうち減価償却の対象となるのは、実際に事業で使用され、かつ時間の経過とともに価値が減少する資産です。具体的には建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品などが該当します。判断のポイントは以下の通りです。
- 事業目的で実際に使用されている資産
- 物理的または機能的な劣化が生じる資産
- 使用可能期間が1年を超える資産
- 取得価額が10万円以上の資産
一方、建設中の建物や未稼働の機械設備は、事業の用に供していないため減価償却の対象外となります。また、事業用ではなく役員の個人的な用途に使用している資産も対象外です。
特許権・ソフトウェアなど無形資産の判断基準
無形資産についても、一定の条件を満たせば減価償却の対象となります。主な対象資産は特許権、商標権、著作権、ソフトウェア、のれんなどです。無形資産の場合、原則として定額法による償却を行います。
- 特許権や商標権: 法定保護期間または契約期間が耐用年数。
- ソフトウェア: 税法上、利用目的に応じて定められており、「複写して販売するための原本」や「開発研究用のもの」は3年、一般的な社内利用などの「その他のもの」は5年で償却。
- のれん: M&A時に発生。会計上は「20年以内の効果が及ぶ期間」で償却するが、税務上は「資産調整勘定」として特定のM&A(事業譲渡など)の場合に限り5年間で均等償却。両者のルールは大きく異なるため注意が必要。
土地・美術品など価値が下がらない資産の見分け方
減価償却の対象とならない資産は、時間の経過により価値が減少しないと考えられる資産です。代表的なものに土地、美術品、骨董品、金地金などがあります。
- 土地:時間経過による価値減少がないため非償却資産
- 美術品:100万円以上は非償却資産、100万円未満は償却対象
- 骨董品:歴史的価値があり価値減少しないため非償却資産
- 電話加入権:現在は価値がほぼゼロだが制度上は非償却資産
ただし、美術品については平成27年の税制改正により、取得価額が100万円未満のものは減価償却資産として取り扱われることになりました。また、ゴルフ会員権のように価値の変動が大きい資産については、実質的な価値減少が生じた場合に評価損として処理することがあります。
減価償却費の計算方法と実務での活用法
減価償却費の計算方法には主に定額法と定率法の2つがあり、それぞれ異なる特徴とメリットを持っています。定額法は毎年同額を計上する方法で計算が簡単である一方、定率法は初年度に多額を計上できるため節税効果が高いという特徴があります。
中小企業においては、事業の状況や資金繰り、税務戦略に応じて適切な計算方法を選択することが重要です。また、中古資産の取得や少額減価償却資産の特例など、実務上知っておくべきポイントも多く、これらを適切に活用することで経営効率を高めることができます。
定額法による計算手順と具体例
定額法は、減価償却費を毎年同額ずつ計上する計算方法です。計算式は「取得価額×定額法の償却率」となり、償却率は耐用年数に基づいて国税庁の償却率表で定められています。例えば、取得価額600万円、耐用年数10年の機械設備を購入した場合、定額法の償却率は0.1(1÷10年)なので、毎年の減価償却費は600万円×0.1=60万円となります。
計算手順は以下の通りです。
- 取得価額と耐用年数を確認する
- 国税庁の償却率表から定額法の償却率を調べる
- 取得価額に償却率を乗じて年間減価償却費を算出する
- 最終年は残存価額1円を残すため1円少なく計上する
定額法の最大のメリットは、毎年同額のため将来の資金計画が立てやすく、計算も簡単である点です。
定率法による計算手順と具体例
定率法は、未償却残高に一定の償却率を乗じて減価償却費を計算する方法です。同じ600万円、耐用年数10年の機械設備の場合、定率法の償却率は0.2となります。1年目の減価償却費は600万円×0.2=120万円、2年目は(600万円-120万円)×0.2=96万円というように、年々減価償却費が減少していきます。
ただし、定率法で計算した償却費が「取得価額×保証率」で計算される償却保証額を下回った年からは、「改定取得価額×改定償却率」という計算式に切り替わり、毎年同額を償却します。この仕組みにより、最終的に残存価額1円まで確実に償却できるよう設計されています。
定率法は初年度の節税効果が高く、設備投資年度の利益を効果的に圧縮できるため、法人では原則的な計算方法とされています。
中小企業が選ぶべき計算方法の判断基準
中小企業が減価償却の計算方法を選択する際の判断基準は、主に資金繰りと税務戦略の観点から検討します。定率法を選ぶべきケースは、初年度の節税効果を重視したい場合、設備投資年度の利益が大きく税負担を軽減したい場合、キャッシュフローの改善を図りたい場合です。
一方、定額法を選ぶべきケースは、毎年安定した経費計上により予算管理を容易にしたい場合、経理処理の負担を軽減したい場合、長期的な資金計画を重視する場合です。
- 法人の場合:原則定率法、定額法への変更は税務署への届出が必要
- 個人事業主の場合:原則定額法、定率法への変更は税務署への届出が必要
- 建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェア:強制的に定額法
最終的な償却総額は同じであるため、企業の財務戦略や事業計画に最も適した方法を選択することが重要です。
中古資産を取得した場合の耐用年数の算出方法
中古資産の耐用年数は簡便法を用いて計算できますが、重要な例外があります。それは、中古資産の購入後に支出した「資本的支出」の額が、その資産の「再取得価額(新品価格)」の50%を超える場合です。この場合、簡便法は使えず、新品と同じ法定耐用年数を適用しなければなりません。購入価格が新品価格の50%を超えるかどうかは、この判定に一切関係ないため注意が必要です。
購入価格が新品価格の50%以下で、使用可能期間の見積りが困難な場合は、国税庁の簡便法を使用します。計算式は以下の通りです。
- 法定耐用年数の一部経過:(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
- 法定耐用年数が全部経過:法定耐用年数×20%
例えば、法定耐用年数6年の中古車で3年経過している場合は、(6年-3年)+3年×20%=3.6年となり、端数切捨てで3年が耐用年数となります。
少額減価償却資産の特例(30万円未満)の活用
中小企業にとって非常に有利な制度が、30万円未満の少額減価償却資産の一括償却特例です。この特例により、取得価額30万円未満の減価償却資産については、年間300万円を限度として取得年度に全額を経費計上できます。対象となるのは、青色申告を行う中小企業者等(従業員数1,000人以下)です。
活用のポイントは以下の通りです。
- 年間限度額300万円を有効活用して計画的な設備投資を実施
- 年度末の利益調整として30万円未満の備品購入を検討
- パソコン、プリンター、机、椅子などの事務用品が主な対象
- 取得価額には消費税も含む場合があるため注意が必要
この特例と通常の減価償却を使い分けることで、効果的な節税と資金繰り改善を図ることができます。特に年度末の利益が予想以上に出た場合の調整手段として非常に有効です。
減価償却費の仕訳と会計処理の実践方法
減価償却費の仕訳には「直接法」と「間接法」の2つの方法があり、どちらを選択しても税務上の金額は変わりませんが、帳簿の記載方法や財務諸表の表示方法が異なります。また、事業年度の途中で資産を取得・売却した場合は、月割計算による特別な処理が必要になります。適切な仕訳処理を行うことで、正確な財務諸表の作成と税務申告が可能となり、企業の健全な会計管理を実現できます。
直接法による仕訳の記帳方法
直接法は、減価償却費を固定資産勘定から直接差し引く仕訳方法です。この方法では、借方に減価償却費を計上し、貸方に該当する固定資産勘定を記入します。例えば、取得価額300万円の車両の年間減価償却費が50万円の場合、以下のような仕訳となります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却費 | 500,000 | 車両運搬具 | 500,000 |
直接法の最大のメリットは、帳簿上で固定資産の現在価値(未償却残高)が直接確認できる点です。貸借対照表では車両運搬具が250万円(取得価額300万円-減価償却費50万円)と表示され、現在の帳簿価額が一目でわかります。中小企業では資産管理がシンプルになるため、直接法を採用するケースも多く見られます。
ただし、取得価額の情報が見えにくくなるというデメリットもあります。
間接法による仕訳の記帳方法
間接法は、固定資産勘定はそのままにして、減価償却累計額勘定(固定資産のマイナス勘定)を使用する仕訳方法です。同じ車両の例では、以下のような仕訳となります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却費 | 500,000 | 減価償却累計額(車両運搬具) | 500,000 |
間接法では、貸借対照表に取得価額300万円と減価償却累計額50万円が別々に表示されるため、資産の取得価額と累計償却額の両方を確認できます。これにより、資産の取得時期や償却の進行状況を把握しやすくなります。
- 取得価額の情報が保持される
- 償却の進行状況が明確に把握できる
- 監査や税務調査で説明しやすい
- 大企業や上場企業で一般的に採用される
間接法は情報量が多く管理精度が高いため、多くの企業で採用されている標準的な方法です。
期中取得・売却時の処理方法
事業年度の途中で減価償却資産を取得した場合は、事業の用に供した月から月割計算で減価償却費を計上します。例えば、3月決算の会社が10月に車両を取得した場合、10月から3月までの6か月分を計上します。年間減価償却費が60万円なら、60万円×6か月÷12か月=30万円が当期の減価償却費となります。
売却時の処理では、まず売却時点までの減価償却費を計上し、その後売却損益を計算します。帳簿価額200万円の車両を180万円で売却した場合の間接法による仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現金預金 | 1,800,000 | 車両運搬具 | 3,000,000 |
| 減価償却累計額 | 1,000,000 | ||
| 固定資産売却損 | 200,000 |
期中処理では月割計算が基本となるため、正確な取得日・売却日の把握と計算が重要です。売却損益は営業外損益として計上し、税務上も適切に処理する必要があります。
減価償却費の実務における注意点
減価償却費の計上は理論的には単純ですが、実務では様々な注意点があります。特に事業年度の途中で資産を取得した場合の月割計算、減価償却の計上漏れ、税務調査での指摘事項については、多くの企業で問題となりやすい分野です。これらの注意点を事前に理解し、適切な管理体制を構築することで、税務リスクを回避し、正確な会計処理を維持することができます。
事業年度の途中で取得した資産を月割計算する
事業年度の途中で減価償却資産を取得した場合、年間の減価償却費を月割計算して当期分を算出します。重要なポイントは、資産の購入日ではなく「事業の用に供した日」から計算を開始することです。例えば、3月に機械を購入したが実際の稼働開始が5月の場合、5月から減価償却を開始します。
月割計算では、事業供用開始月から事業年度末までの月数を12か月で割って年間減価償却費に乗じます。年間減価償却費120万円の資産を10月に取得した場合(3月決算)、10月から3月までの6か月分となり、120万円×6÷12=60万円が当期の減価償却費となります。
- 事業供用日の正確な把握と記録が重要
- 1か月未満の端数は1か月として計算
- 購入日と事業供用日が異なる場合の注意
- 売却時は売却月まで計算に含める
月割計算のミスは税務調査で指摘されやすいため、事業供用日の記録と計算の正確性を重視する必要があります。
減価償却の計上漏れを防ぐ
減価償却の計上漏れは、中小企業において頻繁に発生する問題です。計上漏れを防ぐためには、まず固定資産台帳の整備が不可欠です。すべての減価償却資産を台帳に記録し、定期的な現物確認を行うことで、管理対象資産の把握漏れを防げます。
特に注意が必要なのは、少額資産や建物附属設備です。エアコン、内装工事、電気設備などは計上を忘れがちですが、これらも立派な減価償却資産です。また、リース資産についても、ファイナンスリースの場合は減価償却が必要になるため、契約内容の確認が重要です。
- 固定資産台帳の継続的な更新と管理
- 年次での現物確認と台帳との照合
- 建物附属設備や構築物の計上忘れに注意
- リース契約の内容確認とファイナンスリースの適切な処理
- 少額資産の特例適用判定の正確性
定期的な棚卸しと台帳管理により、計上漏れのリスクを大幅に軽減できます。
税務調査での指摘を回避する
税務調査において減価償却は重点的に確認される項目の一つです。よくある指摘事項としては、耐用年数の適用誤り、償却方法の変更手続き漏れ、事業供用日の認定誤り、少額減価償却資産特例の適用誤りなどがあります。
耐用年数については、資産の用途や構造を正確に把握し、国税庁の耐用年数表と照合することが重要です。また、定率法から定額法への変更や、その逆の変更を行う場合は、事前に税務署への届出が必要であり、届出漏れは指摘の対象となります。
- 耐用年数表との照合による適用年数の確認
- 償却方法変更時の適切な届出手続き
- 事業供用日を示す客観的な証拠資料の保管
- 少額減価償却資産特例の年間限度額管理
- 償却率の適用確認と計算ミスの防止
税務調査での指摘を避けるためには、日頃から正確な記録管理と定期的な自己点検を行い、疑問点は税理士や税務署に事前確認することが効果的です。証憑書類の適切な保管も、調査時の説明材料として重要な要素となります。
M&A時に重要となる減価償却費の考え方
M&A(企業の合併・買収)において、減価償却費は企業価値評価や取引後の会計処理に大きな影響を与える重要な要素です。特に中小企業のM&Aでは、減価償却の処理状況が企業価値に直接影響するため、売り手企業は事前の整備が重要であり、買い手企業は詳細な確認が必要となります。適切な減価償却処理により企業価値を適正に評価し、M&A後のスムーズな統合を実現することで、取引の成功確率を高めることができます。
企業価値評価における減価償却の影響
企業価値評価において、減価償却費は特にDCF法(割引キャッシュフロー法)とEBITDA倍率法で重要な役割を果たします。DCF法では、フリーキャッシュフローの計算において「税引き後営業利益+減価償却費-設備投資額-運転資本増加額」という式を使用し、減価償却費はキャッシュアウトを伴わない費用のため加算されます。
例えば、年間営業利益5,000万円、減価償却費1,000万円の企業の場合、減価償却費の適切な計上により企業価値が大きく変動します。減価償却の計上漏れがある企業では、実態修正により営業利益が減少し、結果として企業価値が下がる可能性があります。
EBITDA倍率法では、「営業利益+減価償却費」でEBITDAを算出し、業界平均の倍率を乗じて企業価値を算定します。
- 減価償却費の計上状況が企業価値評価に直接影響
- DCF法では減価償却費がキャッシュフロー計算の重要要素
- EBITDA倍率法では減価償却費がEBITDA算出の基礎
- 計上漏れや過不足は企業価値の過大
- 過小評価につながる
正確な減価償却処理により、適正な企業価値評価が可能となります。
デューデリジェンスで確認される減価償却のポイント
M&Aのデューデリジェンス(買収監査)では、減価償却に関する以下の項目が重点的に確認されます。まず、減価償却費の計上漏れや過不足の有無を調査し、必要に応じて実態修正を行います。特に中小企業では、建物附属設備や少額資産の計上漏れが頻繁に発見されます。
耐用年数の適用についても詳細に確認され、資産の用途や構造に応じて適切な年数が適用されているかを検証します。また、定率法と定額法の選択が適切で、税務署への届出が必要な変更について手続きが完了しているかも確認対象となります。
- 固定資産台帳と実際の資産の照合確認
- 減価償却費の計上漏れや償却過不足の調査
- 耐用年数適用の適切性と根拠資料の確認
- 償却方法選択の一貫性と変更手続きの完了状況
- 特別償却や圧縮記帳等の税務上の特例処理の影響を考慮
デューデリジェンスで発見された問題点は、企業価値評価に反映され、最終的な取引価格に影響を与えるため、売り手企業は事前の自己点検が重要です。
M&A後の会計処理と減価償却の引き継ぎ
M&A成立後は、取得した資産を時価で評価し直し、新たな減価償却計算を開始します。この際、買収対価と純資産時価の差額は「のれん」として計上されますが、その償却は会計と税務で扱いが異なります。会計上は「20年以内のその効果が及ぶ期間」で規則的に償却しますが、税務上は「資産調整勘定」として5年間で償却され、しかもこの税務上の償却が認められるのは事業譲渡など特定のM&Aスキームに限られます。のれん償却費は営業利益を圧迫するため、買い手企業の今後の業績に大きく影響します。
既存の固定資産については、時価評価後の金額を新たな取得原価として、残存耐用年数で減価償却を継続します。この処理により、M&A前後で減価償却費の金額が大きく変動する可能性があります。
また、買い手企業と売り手企業で減価償却の会計方針が異なる場合は、統一された方針に合わせて調整を行います。特に償却方法(定額法・定率法)や耐用年数の適用方針について、グループ全体での一貫性を保つことが重要です。
- 取得資産の時価評価と新たな減価償却計算の開始
- のれんの計上と20年以内での償却処理
- 会計方針の統一と減価償却方法の調整
- 固定資産台帳の統合と管理体制の整備
M&A後の適切な会計処理により、統合後企業の財務諸表の信頼性を確保し、将来の経営判断に必要な正確な財務情報を提供できます。
まとめ|減価償却費を正しく理解して企業価値を高めよう
減価償却費は、単なる会計処理ではなく、企業の健全な成長と価値向上を支える重要な仕組みです。固定資産の取得費用を耐用年数に応じて適切に期間配分することで、正確な損益計算が可能となり、経営者は事業の実態を正しく把握できるようになります。定額法と定率法の特徴を理解し、企業の財務戦略に応じて最適な計算方法を選択することで、節税効果と資金繰りの改善を同時に実現できます。
特に中小企業においては、30万円未満の少額減価償却資産の特例活用や、適切な月割計算の実施、計上漏れの防止など、実務面での正確な処理が企業価値に直結します。また、将来的なM&Aを視野に入れている企業にとって、減価償却の適切な処理は企業価値評価において重要な要素となるため、日頃からの正確な会計処理が競争優位性の源泉となります。
今後のアクションとしては、まず固定資産台帳の整備から始め、定期的な現物確認と償却計算の見直しを実施することをお勧めします。税制改正への対応や複雑な判断が必要な場合は、税理士や会計の専門家と連携し、最新の制度を活用した最適な処理方法を検討することが重要です。減価償却費を正しく理解し活用することで、企業の財務基盤を強化し、持続的な成長と企業価値の向上を実現していきましょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。