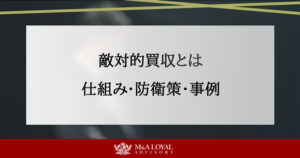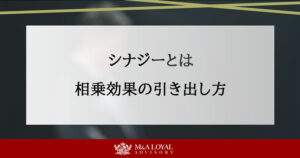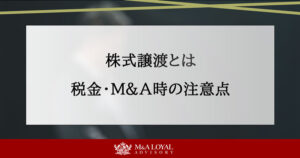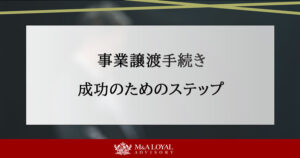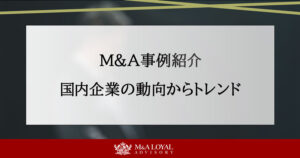買収とは?意味やM&Aとの違い、メリットと注意点を事例と共に解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
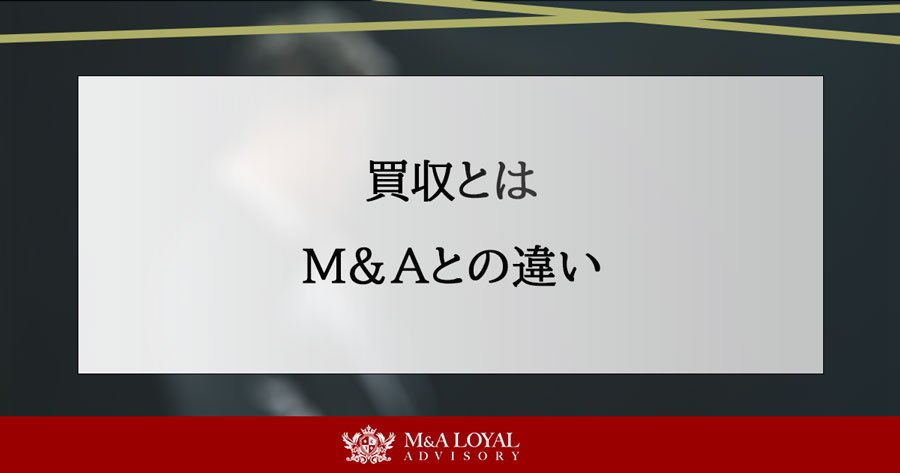
買収とは、他社の事業や経営権を取得し、自社の成長や新たな市場への進出を目指す手法です。近年では、大企業だけでなく中小企業でも、競争力強化や事業拡大を目指し、買収を選択するケースも増加しています。
本記事では、買収とは何かという基本的な意味やM&Aとの違いから、そのメリット・デメリット、手続きの流れ、買収を成功させるポイントまでをわかりやすく解説します。
目次
買収とは?基本概念をわかりやすく解説
買収とは、他社の事業や経営権を取得することで、自社の成長戦略や事業拡大を実現するM&Aの代表的な手法の一つです。近年では、大企業だけでなく中小企業においても、事業承継や競争力強化を目的に買収が注目を集めています。
現代の急速に変化する経営環境では、自社のリソースだけで事業を拡大するのは難しいため、他社の経営資源を活用して効率的かつ迅速に成長を目指す買収は、多くの企業にとって重要な選択肢となっています。
買収の基本的な意味と定義
買収とは、金銭や株式などの対価を支払い、他社の事業や経営権を取得することを指します。買い手企業は、買収を通じて売り手企業が持つ「人材」「技術」「ノウハウ」「販路」「設備」などの経営資源を獲得できることが特徴です。
買収の対象は、大きく分けて「株式」または「事業資産」です。株式を取得する場合、議決権の50%以上を取得することで経営権を掌握することが可能になり、3分の2以上を取得すれば完全な経営支配が実現します。これは議決権を持つ株式を一定数以上取得することにより、株主総会での決議を単独で可決できてしまうためです。
- 議決権の過半数以上:株主総会の普通決議を単独で可決する権限
- 議決権の2/3以上:株主総会の特別決議を単独で可決する権限
中小企業の買収では、経営者が保有する株式の大半を譲渡する形が一般的です。この方法により、事業の継続性を保ちながら新体制へ移行することができます。
企業買収と事業買収の違い
買収は大きく「企業買収」と「事業買収」に分けられ、それぞれ目的や対象範囲が異なります。
企業買収とは
企業買収は、対象企業の株式を取得し、会社全体の経営権を手に入れる手法です。買収後も売り手企業の法人格は存続し、買い手企業の傘下で事業を継続します。この方法では、売り手企業のすべての資産、負債、契約関係、従業員を引き継ぐことになります。
なお、企業買収は狭義では「株式譲渡」「株式交換」「株式移転」「株式公開買付(TOB)」などが挙げられますが、広義では「合併」や「事業譲渡」が含まれます。
事業買収とは
事業買収は、企業内の特定の事業部門や事業資産だけを取得する手法です。この方法では、必要な部分だけを選択的に取得できるため、不要な負債やリスクを引き継がずに済むのが大きなメリットです。売り手企業の法人格はそのまま存続するため、企業全体を買収するわけではありません。
また、事業買収は「事業譲渡」として実施されることが一般的です。事業譲渡とは、売り手企業が保有する特定の事業資産(設備、ノウハウ、契約など)を買い手企業に移転する法律的な手法を指します。事業譲渡の場合、契約の個別移転や許認可の再取得が必要になることが多く、手続きが複雑になることがあります。
| 項目 | 企業買収 | 事業買収 |
|---|---|---|
| 対象 | 企業全体(株式を取得して経営権を掌握) | 特定の事業部門や資産(選択的取得) |
| 法人格 | 売り手企業の法人格は存続 | 売り手企業の法人格は存続 |
| 承継範囲 | 包括承継(資産・負債・契約・従業員) | 個別承継(必要な部分だけ取得) |
| 手続き | 比較的簡単(株式譲渡契約が中心) | 複雑(契約移転や許認可再取得が必要) |
| メリット | 会社全体を迅速に取得可能 | 不要な負債やリスクを避けられる |
| デメリット | 不要な負債やリスクも引き継ぐ可能性がある | 手続きが煩雑で時間がかかる場合がある |
中小企業では、事業承継目的で企業全体の経営権を引き継ぐ「企業買収」が一般的です。一方で、特定分野への参入や事業の選択と集中を目指す場合には「事業買収」が選択されることもあります。
買収とM&Aの違いと関係性
買収とは、M&Aの中核的な手法の一つであり、M&Aの一部として位置づけられます。一方、M&Aは企業再編を目的とした広い概念であり、買収以外にも「合併」や「業務提携」「資本提携」なども含まれます。
買収と合併の違い
買収では、売り手企業の法人格が存続し、買い手企業の傘下で事業が継続されます。これに対し、合併では複数の企業が統合され、一つの法人として新たに運営されるため、消滅する企業が発生します。特に中小企業のM&Aでは、手続きが比較的簡単で事業継続性を保ちやすい「株式譲渡による買収」が広く利用されています。
| 項目 | 買収 | 合併 |
|---|---|---|
| 定義 | 企業が他の企業を購入し、その経営権を取得する行為 | 二つ以上の企業が一つの企業に統合される行為 |
| 目的 | 市場シェアの拡大、新技術の取得 | 経営資源の統合、規模の経済の達成 |
| 結果 | 買収された企業は独立性を失う | 統合後は新しい企業として運営される |

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



買収の種類と中小企業での位置づけ
買収とは、他社の経営権を取得することを指しますが、その方法には「友好的買収」と「敵対的買収」の2種類があります。売り手企業の同意を得ているかどうかが両者を区別するポイントとなり、その違いを理解することは、中小企業が買収を検討する際に非常に重要です。
友好的買収の特徴
友好的買収とは、売り手企業の経営陣から事前に同意を得て実施される買収です。この場合、買い手と売り手が買収条件や価格に合意したうえで進められるため、交渉や経営統合がスムーズに進むのが特徴です。
特に日本では、実施されるM&Aの大半が友好的買収です。中小企業では株式に譲渡制限があるケースが多いため、オーナー経営者の同意なしに株式を取得することは実質的に困難です。友好的買収では、トップ面談や条件交渉を通じて相互理解を深めることで、買収後の経営統合も円滑に進められる点がメリットです。
敵対的買収の特徴
敵対的買収とは、売り手企業の経営陣の同意を得ずに実施される買収を指します。この手法は主に上場企業を対象とし、TOB(株式公開買付)を活用して市場から株式を取得し、経営権の掌握を目指します。
ただし、日本では株式持ち合いなどの企業文化が根強く、敵対的買収の成功率は低いのが現状です。また、中小企業においては株式譲渡制限があるため、敵対的買収が実施されるケースはほとんどありません。
中小企業における買収の現状と背景
近年、買収を含むM&Aは急速に増加しています。レコフデータによると、2024年にはM&Aの実施件数は過去最多の4,700件に達しました。この背景には、経営者の高齢化と後継者不足という深刻な課題が挙げられます。
中小企業庁の過去の推計によれば、2025年までに約127万社の中小企業が「後継者未定」の状態になるとされており、さらに経営者の6割以上が70歳を超えると予測されています。このような状況を受けて、政府は事業承継・引継ぎ支援センターを全国に設置し、M&Aのマッチング支援を強化しています。また、事業承継税制の拡充や補助金制度の充実により、買収を活用した事業承継が注目されています。
事業承継手段としての買収
中小企業の事業承継は従来、親族内承継が主流でしたが、帝国データバンクによると、少子高齢化の影響により親族以外への承継が6割を超えています。(内部昇格・外部招聘・M&Aなど含む)
このような変化の中で、第三者への事業承継手段としてM&Aが注目されています。
事業承継型M&Aは、単なる経営権の移転ではなく、企業の持続的成長を実現する有効な手段として位置づけられています。売り手企業にとっては、後継者問題の解決、従業員の雇用維持、株式売却による利益獲得といったメリットがあります。
買い手企業にとっても、新規事業への参入、既存事業の拡大、優秀な人材の獲得などのメリットを短期間で実現できるため、成長戦略の重要な選択肢となっています。
買収がもたらすメリット
買収は企業の成長戦略において強力な手段であり、自社の力だけでは時間がかかる課題を短期間で解決できます。中小企業にとって買収がもたらす代表的なメリットを4つの観点から詳しく解説します。
買収のメリット
- 既存事業の拡大とスケールアップ:事業規模の拡大、地域展開の迅速化、規模の経済効果
- 新規事業への迅速な参入:経営資源を一括取得し、リスクを軽減。多角化によるリスク分散
- 優秀な人材と技術の獲得:即戦力人材、特許・ノウハウ・技術力の獲得
- シナジー効果による競争力強化:売上・コスト・財務面での相乗効果
それぞれについて解説します。
既存事業の拡大とスケールアップ
買収のメリットの1つ目が既存事業の拡大とスケールアップです。他社を買収することにより、事業を短期間で大幅に拡大し、市場での競争力を強化できます。特に同業他社を買収することで、売上規模の拡大、市場シェアの向上、コスト効率の改善を一度に実現できるのが大きなメリットです。
また、買収による事業規模の拡大により、仕入れや製造における規模の経済効果を享受できます。大量発注による原材料費の削減、生産効率の向上、管理コストの最適化など、単独では実現困難なコスト競争力を獲得できます。また、販売網の統合により営業効率も大幅に向上します。
地域展開の観点でも、買収は極めて有効です。新しい地域に一から拠点を構築するには多額の投資と時間が必要ですが、その地域で既に事業基盤を持つ企業を買収することで、迅速な市場参入と顧客基盤の獲得が可能になります。
新規事業への迅速な参入
買収の2つ目のメリットが新規事業への参入が容易になる点です。新規事業分野への参入しようとした場合、自社で一から新事業を立ち上げようとすると、市場調査、商品開発、販路開拓、人材採用など、多くの時間と資源が必要になります。
既に参入予定の分野で事業を軌道に乗せている企業を買収することで、必要な経営資源が揃った状態からスタートできます。市場での実績、顧客基盤、ノウハウ、許認可などを一括で取得できるため、新規参入のリスクを大幅に軽減できます。
特に中小企業にとって、新規事業の失敗は経営に深刻な影響を与える可能性があります。買収により実績のある事業を取得することで、安定した収益基盤を確保しながら新分野でのチャレンジが可能になります。また、多角化による事業リスクの分散効果も期待できます。
優秀な人材と技術の獲得
買収の3つ目のメリットが優秀な人材や技術の獲得です。新たに社員を採用する場合、教育の時間とコストが必要となります。しかし、買収によってすでに実践経験を積んでいる人材や自社にない専門知識や技術を持つ優秀な人材を獲得することにより、時間やコストを削減することができます。これは特に技術集約型の中小企業にとって重要なメリットです。
また、買収対象企業が保有する特許、ノウハウ、技術力は、自社の競争力向上に直結します。研究開発に数年かかる技術も、買収により短期間で自社のものにできます。また、業界特有の専門知識や顧客との関係性も重要な無形資産として活用できます。
- 即戦力人材の確保:採用・教育コストの削減
- 技術力の向上:研究開発期間の短縮
- 専門ノウハウの取得:業界知識の蓄積
ただし、ここでは人材の定着率向上は重要なポイントとなります。労働環境の変化により、優秀な人材が離職してしまうと、この効果は半減します。そのため、貴重な人的資源の流出を防ぐことが大切です。
シナジー効果による競争力強化
買収の4つ目のメリットはシナジー効果の創出です。買収の魅力は、1+1が2以上の成果を生み出すことです。シナジーには、売上シナジー、コストシナジー、財務シナジーなどがあり、単独では実現できない競争力を獲得できます。
例えば、売上シナジーでは、相互の顧客基盤を活用したクロスセル、商品ラインの拡充による提案力向上、ブランド力の相乗効果などにより売上拡大を実現できます。販売チャネルの共有により、新商品の市場投入も効率化されます。
コストシナジーでは、重複部門の統合、共同購買による調達コストの削減、生産拠点の最適化などにより、大幅なコスト削減が可能です。管理部門の統合により、間接費の効率化も図れます。
財務シナジーでは、信用力の向上による資金調達コストの削減、キャッシュフローの安定化、節税効果の活用などにより、財務基盤の強化を実現できます。これらのシナジー効果により、市場での競争優位性を確立し、持続的な成長基盤を構築できます。
買収のデメリット(リスク)と注意点
買収には多くのメリットがある一方で、重大なリスクも存在します。特に中小企業にとって買収の失敗は経営に深刻な影響を与える可能性があるため、事前にデメリットを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
買収のリスクとして主に以下の点が挙げられます。
- 高額な買収費用:買収価格、関連費用、返済負担が財務を圧迫
- 統合プロセスの複雑さ:組織・制度・システムの統合に時間とコストがかかる
- 人材流出と企業文化の衝突:従業員の離職や価値観の違いによる対立
- 期待効果未達のリスク:のれんの減損、隠れた債務、市場条件の変化
それぞれについて解説します。
高額な買収費用の負担
買収には多額の資金が必要であり、中小企業にとって大きな財務負担となります。買収価格だけでなく、仲介手数料、法務費用、税理士費用、デューデリジェンス費用など、関連する様々なコストが発生します。
買収価格の算定では、対象企業の将来性やシナジー効果を見込んで「のれん代」が上乗せされることが一般的です。しかし、期待した成果が得られない場合、投資回収が困難になるリスクがあります。特に競争の激しい入札では、価格が釣り上がって「高値掴み」となる危険性があります。
また、資金調達の面でも課題があります。自己資金だけでは買収資金を賄えない場合、金融機関からの借入が必要になりますが、買収後の返済負担が経営を圧迫する可能性があります。また、買収後の統合コストや設備投資なども考慮すると、想定以上の資金が必要になることがあります。
中小企業が買収を検討する際は、自社の財務体力を十分に分析し、無理のない資金計画を立てることが不可欠です。買収価格の妥当性を慎重に検証し、複数の専門家から意見を求めることも重要です。
統合プロセスの複雑さ
買収後の統合プロセス(PMI)は、買収の成否を左右する重要なプロセスですが、同時に最も困難で複雑な作業でもあります。異なる企業文化、システム、制度を統合するには、膨大な時間と労力が必要です。
経営システムの統合では、会計システム、人事制度、給与体系、就業規則などを一元化する必要があります。それぞれの企業で異なるルールや慣習があるため、統合作業は想定以上に複雑になることがあります。ITシステムの統合も技術的な困難を伴い、データ移行や新システムの導入には時間とコストがかかります。
組織統合では、役職や責任の再配置、報告系統の整理、意思決定プロセスの統一などが必要です。これらの変更により一時的に業務効率が低下したり、従業員の混乱を招いたりする可能性があります。
- システム統合:会計・人事・ITシステムの一元化
- 組織再編:役職・部門・報告系統の整理
- 制度統一:就業規則・評価制度・福利厚生の調整
PMIの失敗は買収効果を大幅に減じるため、買収前から詳細な統合計画を策定し、専門家のサポートを得ながら進めることが重要です。
人材流出と企業文化の衝突
買収により企業文化や労働環境が変化することで、優秀な人材の流出リスクが高まります。特に、買収対象企業の従業員にとって、新しい経営方針や企業文化への適応は大きなストレスとなる可能性があります。
経営方針の違いから生じる価値観の衝突は、深刻な問題となることがあります。意思決定のスピード、リスクに対する考え方、顧客対応の方針などの違いが、現場レベルでの混乱や対立を招く可能性があります。
待遇や労働条件の変更も人材流出の要因となります。給与体系の見直し、福利厚生の変更、勤務時間の調整などが従業員の不満を招き、転職を考える契機となることがあります。特に、買収対象企業の核となる技術者や営業担当者の離職は、買収効果を大幅に減じる結果となります。
コミュニケーション不足も重要な問題です。買収の理由や今後の方針について十分な説明がないと、従業員の不安や憶測を招き、組織の結束力を損なう可能性があります。定期的な説明会や個別面談を通じて、従業員の理解と協力を得る努力が不可欠です。
期待した効果が得られないリスク
買収において最も深刻なリスクは、期待した効果が得られず、投資回収ができなくなることです。
特にのれんの減損リスクは重要です。買収価格に含まれる「のれん」は、将来の収益力やシナジー効果を見込んだ部分ですが、実際の業績が期待を下回った場合、会計上の減損処理が必要になります。これにより、大幅な損失を計上する事態となる可能性があります。
簿外債務や偶発債務の発覚も重大なリスクです。貸借対照表に記載されていない未払い賃金、退職給付債務、債務保証、訴訟リスクなどが買収後に判明した場合、予想外の財務負担を負うことになります。デューデリジェンスの不備により、これらのリスクを見逃すケースがあります。
市場環境の変化も買収効果に大きな影響を与えます。買収時の前提条件が変化し、想定していた市場成長や収益性が実現しない場合、買収投資の回収が困難になります。
- のれんの減損:期待収益の未達による損失計上
- 隠れた債務:未把握の財務リスクの顕在化
- 市場変化:前提条件の変化による収益性悪化
これらのリスクを最小化するためには、徹底したデューデリジェンス、適正な買収価格の設定、詳細な統合計画の策定が不可欠です。
買収の手法と選択基準
買収には複数のスキームがあり、実行する際は、目的や状況に応じて最適な手法を選択することが重要です。中小企業のM&Aで主に用いられる手法の特徴を理解し、自社に適した方法を選択しましょう。
株式譲渡による買収の特徴
M&Aで最も用いられる買収スキームが株式譲渡です。この方法では、売り手企業の株式を買い手企業が取得することで経営権を獲得します。会社の法人格がそのまま存続するため、事業の継続性を保ちながら経営権の移転を実現できます。
株式譲渡の最大のメリットは手続きの簡便性です。株主総会決議や債権者保護手続きが不要で、株式譲渡契約の締結と株主名簿の書き換えにより買収が完了します。許認可や各種契約も原則として引き継がれるため、事業運営に支障をきたすリスクが少なくなります。
ただし、会社全体を買収するため、不要な資産や負債も含めてすべて引き継ぐことになります。簿外債務や偶発債務のリスクもあるため、事前のデューデリジェンスが極めて重要です。また、売り手の株主が個人の場合、譲渡所得税が課税される点も考慮が必要です。
株式譲渡は、対象企業の事業全体を取得したい場合や、許認可事業の承継を重視する場合に適した手法です。中小企業では、事業承継を目的とする買収の大部分で株式譲渡が選択されています。
その他の株式取得による買収(株式交換・株式移転・第三者割当増資)
株式を取得する買収手法には、他にも「株式交換」「株式移転」「第三者割当増資」といった方法があります。これらの手法は、比較的柔軟で多様な目的に対応できるため、多くの企業に利用されています。
■株式交換
株式交換は、買収対象企業の株主がその株式を買収企業の株式と交換する形で行われます。これにより、買収企業は現金を使わずに買収を実現でき、資金流動性を保つことが可能です。また、株式交換による買収は、両社の株主が新たな企業の成長を共有する機会を持つため、友好的な統合が期待できます。
■株式移転
株式移転は、買収企業が新たに設立する持株会社に、買収対象企業の株式を移転する形で行われます。この手法は、グループ企業の再編成や統合が目的となる場合に適しています。持株会社を設立することで、経営資源の集中や効率的な管理が可能となります。
■第三者割当増資
第三者割当増資は、買収企業が新たな株式を発行し、買収資金を調達する手法です。これは、特定の投資家や企業に対して株式を割り当てることで、資本を増強しつつ、買収を円滑に進めることができます。この方法は、迅速な資金調達が可能であり、買収企業にとっては柔軟な資本戦略を実行できるメリットがあります。
事業譲渡による買収の特徴
事業譲渡は、会社の特定事業や事業資産のみを選択的に取得する手法です。必要な事業だけを買収し、不要な負債や事業を除外できるため、リスクを限定した買収が可能になります。
事業譲渡の大きなメリットは、買収範囲を柔軟に設定できることです。優良事業のみを取得し、不採算部門や簿外債務を回避できるため、買収リスクを大幅に軽減できます。また、買収価格も必要な部分のみとなるため、資金負担を抑えることが可能です。
一方で、手続きが複雑になるデメリットがあります。資産・負債の個別移転、契約の再締結、従業員の個別同意取得など、多くの手続きが必要です。許認可についても、新たに取得が必要になる場合があります。また、消費税の課税対象となる場合もある点にも注意が必要です。
事業譲渡は、多角化企業の特定部門のみを買収したい場合や、新規事業参入で特定のノウハウ・技術のみを取得したい場合に適しています。
会社分割(吸収分割・新設分割)による買収の特徴
会社分割を利用した買収は、企業が特定の事業や資産を分離する際に用いる手法で、「吸収分割」と「新設分割」の2つの形態があります。
吸収分割は、既存の企業が特定の事業部門を他の企業に移転することで、受け取る側はその事業の資産や負債を引き継ぎます。これにより、受け取り企業は迅速に新たな市場や事業を獲得できるという利点があります。新設分割では、企業が新たな法人を設立し、特定の事業をその法人に譲渡します。この方法は、元の企業の組織が大きく変わらず、リスクを限定的にすることが可能です。
会社分割を通じた買収は、特定の事業に集中して投資を行いたい企業にとって魅力的です。特に新しい技術や市場への参入を目指す際、分割された事業の専門性や既存の顧客基盤を活用することができます。また、分割によって企業全体のポートフォリオを最適化し、より戦略的な資源配分が可能になります。さらに、分割を通じて非中核事業を切り離すことで、親会社はコアビジネスに専念でき、経営効率の向上が期待できます。しかし、分割の過程では従業員のモチベーションや企業文化の一体性が損なわれるリスクもあり、慎重な計画とコミュニケーションが重要です。
中小企業に最適な手法の判断基準
買収手法を選択する際には、買収目的、対象企業の状況、税務面、資金面などを総合的に検討する必要があります。以下の基準を参考に、自社に最適な手法を選びましょう。
買収目的による選択
- 株式譲渡:事業承継や企業全体の取得を目的とする場合に適しています。法人格が存続するため、事業の継続性を保ちながら経営権を移転できます。
- 事業譲渡:新規事業参入や特定技術の取得を目的とする場合に有効です。必要な部分だけを選択的に取得でき、負債や不採算部門を除外できます。
- 株式交換・株式移転:グループ内再編や持株会社の設立を目的とする場合に適しています。
対象企業の状況による選択
- 許認可事業を営んでいる場合:許認可の承継が容易な株式譲渡が適しています。法人格が存続するため、許認可がそのまま引き継がれます。
- 負債が多い企業や不採算部門を抱える場合:リスク回避が可能な事業譲渡を検討すべきです。必要な事業や資産だけを選択的に取得でき、不必要な負債や事業を除外できます。
税務面での検討
- 株式譲渡:売り手が個人株主の場合、譲渡所得税(20.315%)が課税されます。
- 事業譲渡:売り手が法人の場合、譲渡所得に法人税(実効税率約30~34%)が課税されます。また、譲渡する資産が課税対象の場合に消費税が課税される点にも注意が必要です。
資金面での検討
- 株式譲渡:会社全体の価値に基づく価格となり、シナジー効果を重視する場合に適しています。
- 事業譲渡:必要な部分だけを取得するため、資金負担を抑えることが可能です。資金制約がある場合に有効です。
買収手法の選択により、買収の成否が大きく左右されます。法務・税務・財務の観点から慎重に検討するため、M&Aアドバイザリーなど専門家と相談しながら進めることが推奨されます。
買収の流れと手続き
買収の成功率を高めるためには、体系的なアプローチが欠かせません。M&Aの失敗事例の多くは、準備不足や戦略の曖昧さが原因となっています。ここでは、中小企業が買収を成功させるための実践的なプロセスを、具体的なステップに沿って解説します。
ステップ1:買収目的と戦略の明確化
買収プロセスを成功させるための第一歩は、買収の目的と戦略を明確にすることです。この段階は、買収プロセス全体の基盤を築く重要なステップであり、後続の意思決定の方向性を定める役割を果たします。
まず、買収の目的を明確にするためには、自社の長期的なビジョンや目標を確認し、買収が本当に必要である理由を具体的に設定することが求められます。例えば、以下のような目的が挙げられます。
- 新たな市場への進出による事業規模の拡大。
- 自社に欠けている技術やノウハウを補強し、競争力を高める。
- 市場シェアを拡大し、規模の経済を活用してコスト効率を改善する。
これらの目的が具体的であるほど、買収後に期待される効果が明確になり、次のステップでの意思決定がスムーズに進みます。また、目的を設定する際には、自社の状況を客観的に分析することが重要です。強みや弱みを正確に把握し、買収によってどの部分を補強するのかを明確にすることで、具体的な成果指標を定めることができます。例えば、売上の〇〇%増加やコストの△△%削減など、測定可能な目標を設定することが成功の基準となります。
さらに、買収によって期待されるシナジー効果を具体的に試算することも欠かせません。例えば、売上シナジーでは、相互の顧客基盤を活用して市場拡大を図ることができます。コストシナジーでは、生産効率の向上や共同購買によるコスト削減が実現可能です。財務シナジーでは、資金調達力の向上やキャッシュフローの安定化といった効果が期待できます。
目的が明確になったら、次はそれを達成するための具体的な戦略を策定します。ターゲット企業の選定基準を設定し、財務的な分析を行い、買収プロセスや統合後に発生する可能性のあるリスクを洗い出します。計画には柔軟性を持たせ、環境の変化や予期しない事態に対応できる体制を整えることが重要です。
M&A仲介会社との連携を活用する
買収プロセスを円滑に進めるためには、M&A仲介会社との連携が効果的です。仲介会社は、複雑な手続きのサポートだけでなく、ターゲット企業の発掘、交渉調整、統合計画の策定など、買収プロセス全体を支援します。特に中小企業においては、リソースが限られているため、専門家の力を借りることで負担を軽減し、成功確率を高めることが可能です。
ステップ2:最適な買収相手を選定する
買収戦略を策定した後は、その戦略に基づいて最適な買収相手を選定する段階に進みます。このプロセスでは、候補企業の発掘から最終的な選定まで、段階的かつ慎重に進めることが求められます。
まず、候補企業の発掘では、幅広い情報収集が重要となります。M&A仲介会社が保有する案件や業界ネットワークからの紹介、公開情報による調査など、複数のチャネルを活用して候補を探します。この段階では、ロングリストを作成し、一定の条件に該当する企業を広範囲にピックアップします。ロングリストを作成する際には、絞り込みすぎることなく、漏れを防ぐことが大切です。
ロングリストが完成したら、次にショートリストを作成します。ショートリストでは、財務内容の詳細な分析や事業の将来性評価、経営陣との相性確認を行い、最終候補を数社に絞り込みます。この段階では、トップ面談を実施して相互の理解を深めることが成功への鍵となります。
買収相手を評価する際には、定量面と定性面の両方を総合的に判断する必要があります。定量面では、売上や利益の成長性、財務の安全性、収益性など、具体的な数字を分析します。一方、定性面では、経営陣の資質や従業員のモチベーション、技術力、ブランド価値など、企業の質的な側面を評価します。このように、数字だけでなく、企業の文化や人材の質も重要な判断材料となります。
最終選定では、買収戦略との適合性やシナジー効果の大きさ、買収が実現可能かどうか、統合プロセスの難易度など、さまざまな要素を慎重に検討します。これにより、最も成功確率の高い企業を選び出すことが可能になります。
買収相手の選定は、買収プロセス全体の成功を左右する重要なステップです。各段階を丁寧に進めることで、戦略に沿った最適な選択を実現できます。
ステップ3:交渉および基本合意書の締結
買収プロセスの次のステップは、交渉と基本合意書の締結です。まず、買収対象企業とのトップ面談を行い、その後、価格や条件、支払い方法などの具体的な項目を取り決めます。この交渉では、双方の利益を考慮しながら、合意点を見つけることが求められます。
交渉が成立した後は、意向表明書または基本合意書を締結します。基本合意書は、正式な契約の前段階として、合意内容を文書化するもので、買収の大枠を確認するための重要な書類です。ここでは、具体的な取引条件や買収後の展望についても触れられることが一般的です。基本合意書を確実に締結することで、次のステップに進むための基盤が形成されます。
この段階では、法的な拘束力は限定的ですが、双方のコミットメントを示す意味合いがあります。そのため、交渉と基本合意書の内容は、慎重に検討し、双方の理解が一致するようにすることが重要です。さらに、この段階で発生する可能性のあるリスクを事前に洗い出し、適切な対策を講じることも、交渉の成功に寄与します。交渉力と効果的なコミュニケーションが求められるこのステップは、買収プロジェクトの方向性を決定づけるため、最善の結果を引き出すためにも専門家の助言を求めることが推奨されます。
ステップ4:デューデリジェンスおよびバリュエーションの実施
基本合意書を締結後は、デューデリジェンスとバリュエーションを実施します。
デューデリジェンスは、対象企業の実態を把握し、潜在的なリスクを評価するプロセスです。財務、法務、税務、業務、環境など多岐にわたる調査を通じて、買収後の統合計画や価格交渉の基礎となる情報を収集します。例えば、財務諸表の分析を通じて収益性や財務安全性を確認し、契約書や許認可の確認を通じて法的リスクを洗い出します。また、従業員や顧客との関係性を評価することで、事業の持続可能性を判断します。
一方、バリュエーションは、対象企業の価値を評価し、適正な買収価格を算定するプロセスです。ディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)、比較会社分析、取引事例法などの手法を活用して、企業の将来収益性や成長可能性を見極めます。これにより、買収の投資効果を最大化する価格を設定することが可能です。
これらのプロセスは専門的な知識と経験が求められるため、公認会計士や弁護士、税理士、M&Aアドバイザーなどの外部専門家を活用することが推奨されます。正確な情報収集と評価を行うことで、買収成功の可能性が大幅に高まります。
デューデリジェンスとバリュエーションは、買収プロセスの中で最も重要なステップであり、買収後の統合計画やリスク管理の策定においても大きな役割を果たします。この段階を丁寧に進めることで、買収プロジェクトを成功へと導く基盤を形成することができます。
ステップ5:最終契約とクロージング
最終契約とクロージングは、買収プロセスの最終段階であり、交渉で合意した内容を法的に確定し、買収を実現する重要なステップです。
まず、最終契約書の作成では、買収価格や支払い条件、移転する資産や負債、雇用契約の引き継ぎなどの条件が詳細に記載されます。さらに、買収後の統合計画やリスクへの対応策も含めることで、スムーズな移行を目指します。この契約書は法的拘束力を持ち、買収の正式な実行を保証するものです。
クロージングでは、買収の法的手続きが完了し、実際に所有権が移転します。この段階では、必要な許認可の取得、資金の送金、資産や負債の移転が行われます。また、関係者全員がクロージングの内容を確認し、承認することが求められるため、慎重に進める必要があります。
クロージング後の統合プロセス(PMI)では、組織やシステムの統合、企業文化の融合を進めるための計画を事前に準備し、実行体制を整えることが重要です。特に、従業員や顧客、取引先への適切なコミュニケーションを行うことで、統合のスムーズな進行が可能になります。
専門家との連携を活用することで、リスクを最小化しながら買収を確実に実行し、期待した成果を最大化することができます。最終契約とクロージングを成功裏に完了することで、企業は次の成長ステージへと進む準備が整います。
買収の成功事例と失敗事例
ここでは、企業買収の成功事例と失敗事例をピックアップしてご紹介します。
日本企業による海外企業の買収成功例
2017年に村田製作所は、アメリカのヘルスケアIT分野のベンチャー企業であるヴァイオス・メディカルを買収しました。村田製作所はヘルスケア・メディカル分野を注力市場のひとつに位置づけ、ヴァイオス・メディカルが保有する海外病院ネットワークを買収後に活用し、海外のヘルスケア・メディカル分野において事業拡大を実現しました。
中小企業の買収による成長事例
2020年に茨城県の小野写真館は、伊豆の人気旅館である「桐のかほり 咲楽」をM&Aで取得しました。売り手企業の「桐のかほり 咲楽」は後継者不足、買い手企業の小野写真館はコロナ禍でブライダル事業の売上が大幅に落ちていました。しかし事業譲渡により、旅館にウエディングフォトスタジオを併設したり、旅館全館を貸し切った挙式を開催したりと、事業拡大に成功しています。
買収後の統合失敗による事例
2012年にソニーが、スウェーデンの通信機器メーカーであるエリクソンの株式を取得して完全子会社化しました。しかし、市場の変化への対応の遅れや経営戦略の相違などからM&Aが失敗し、ソニーは約2,000億円の損失を計上することになりました。
過大な買収金額による失敗事例
2008年にパナソニックは、三洋電機を400億円で買収して子会社化しました。さらに投資が行われ、2011年には完全子会社化を実現、総投資額は8,100億円以上にものぼりました。しかし、リチウム電池事業において予測を誤り、2013年3月期の個別決算で6,000億円以上の評価損が計上されました。
買収の成功ポイント
ここでは、買収を成功させるためのポイントについて触れていきます。
長期的視野に立った戦略立案
企業買収は企業の未来を左右する重大な経営戦略です。買収を成功させるには、長期的視野に立った戦略立案が欠かせません。前述のとおり、適切なターゲット企業の選定、デューデリジェンス、買収後の企業文化の融合と従業員の統合が、成功するか否かを決めます。買収は自社の事業成長を迅速に実現する施策ではありますが、長期的視野に立ってしっかりと戦略を立案し、戦略的に進めることで、成功へと導くことができます。
経営陣のコミットメントとリーダーシップ
買い手企業の経営陣が買収後も責任を持ってコミットメントし、売り手企業のガバナンスと企業文化融合を最優先課題として取り組むことも、企業買収の成功に寄与します。
買収は、異なる企業文化を持つ組織同士の統合でもあります。買い手企業と売り手企業の両社従業員は、新たな環境や価値観に適応しなければなりません。そこで大きな力となるのが、経営陣の強いコミットメントとリーダーシップです。企業買収の目的や戦略、統合プロセスについてのビジョンを明確にして、統合後の全従業員に共有することで、組織全体がまとまります。
企業文化の理解と融合
企業文化の融合は、異なる組織をひとつにまとめるうえで大変重要です。買い手企業と売り手企業、双方の文化の違いを互いが理解し合い、共通の価値観を構築することで、企業統合後の一体感が生まれます。
従業員とのコミュニケーションとエンゲージメント
異なる企業が統合されることで、買い手企業と売り手企業のどちらも従業員は、新しい環境や文化への不安、将来への不透明感から、モチベーションやエンゲージメントが下がりやすくなります。特に、売り手企業の従業員はより変化が大きいため、モチベーションやエンゲージメントが低下しやすく、離職が進みがちです。そのため、それぞれの企業文化を両社バランスよく融合させ、新たに統一された文化を築き上げていくことが重要です。
専門家の活用と適切なアドバイザーの選定
企業が買収を行ううえで心強い存在となるのがM&Aの専門家、いわゆる「M&Aアドバイザー」です。
M&Aの一連の流れをサポートするM&Aアドバイザーは、M&Aの交渉前の段階からM&A後の統合作業まで全般のアドバイスを行います。
具体的には、M&Aに関するアドバイスや交渉、契約書の作成、デューディリジェンスなどです。依頼者である企業の利益最大化を目指すのがM&Aアドバイザーの役割であり、買い手企業と売り手企業のどちらの立場にとっても有益であるように働きかけます。
適切なアドバイザー選びのポイント
M&Aアドバイザーの選定は、M&Aの成否を決める重要なポイントとなります。参考となるのが実績と経験です。過去のM&Aの成約件数や、手掛けてきたM&Aの業種や規模、PMIの経験値も確認するのが望ましいでしょう。M&Aアドバイザーはそれぞれ得意とする業種や規模があり、PMIの経験値も異なります。買い手企業は、自社の業種やシェア拡大を目指す市場などを踏まえたうえで、M&Aアドバイザーを選定するのが望ましいでしょう。
まとめ|買収で企業の持続的成長を実現しよう
買収は、中小企業が経営課題を解決し、持続的成長を実現する有効な戦略的手段です。他社の事業や経営権を取得することで、既存事業の拡大、新規事業への参入、優秀な人材の獲得、シナジー効果による競争力強化を短期間で実現できます。
一方で、高額な費用負担、統合の複雑さ、人材流出リスクなどのデメリットも存在するため、適切な準備と専門家のサポートが不可欠です。買収成功の鍵は、明確な目的設定、最適な相手選定、専門家との連携にあります。変化の激しい経営環境において、買収は中小企業の競争力維持と発展のための重要な選択肢となるでしょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。