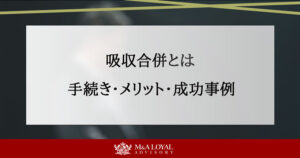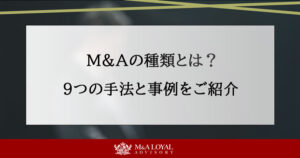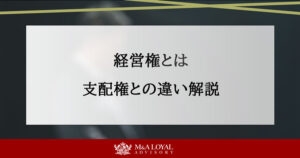三角合併とは?手法や活用場面、メリット・注意点、事例を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
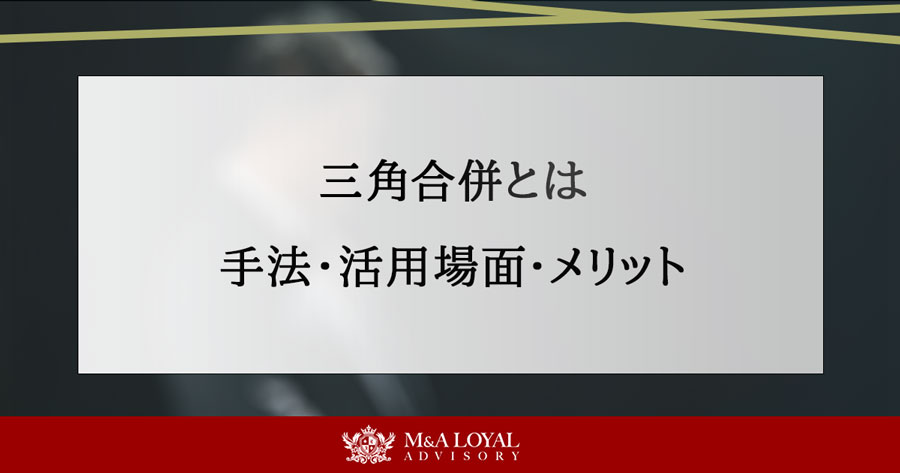
三角合併は、2007年に解禁された比較的新しいM&A手法です。従来の合併とは異なり、消滅会社の株主が存続会社の親会社株式を受け取る仕組みで、外国企業による日本企業の買収や事業承継において選択肢の一つとなっています。現金を使わない資金効率の良いM&Aが可能になることから、近年注目を集めています。
本記事では、三角合併の基本的な仕組みから具体的な活用場面、メリット・デメリット、実際の事例まで、中小企業の経営者が知っておくべきポイントを詳しく解説します。M&Aや事業承継を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
三角合併とは何かをわかりやすく解説
三角合併は、2007年に解禁された比較的新しいM&A手法です。中小企業経営者の方にとって、将来的な選択肢として理解しておくべき重要なスキームといえるでしょう。ここでは、三角合併の基本的な仕組みから解禁された背景まで、わかりやすく解説していきます。
三角合併の基本的な仕組み
三角合併とは、合併により消滅する会社の株主に対して、存続会社の親会社の株式を交付して行われる合併のことです。「三角」と呼ばれる理由は、通常の合併が消滅会社と存続会社の2社間で行われるのに対し、存続会社の親会社も含めた3社が関与するためです。
具体的な仕組みを見てみましょう。A社(消滅会社)とB社(存続会社)が合併する際、通常であればA社の株主はB社の株式を受け取ります。しかし三角合併では、B社の親会社であるC社の株式をA社の株主が受け取ることになります。この結果、A社の元株主はC社の株主となり、A社の事業はB社に引き継がれます。
会社法では原則として子会社による親会社株式の取得は禁止されていますが、三角合併においては例外的に認められており、このスキームが実現可能となっています。
通常の吸収合併との決定的な違い
通常の吸収合併と三角合併の最も大きな違いは、消滅会社の株主が受け取る対価にあります。一般的な吸収合併では、消滅会社の株主は存続会社の株式を受け取りますが、三角合併では存続会社の親会社の株式を受け取ります。
この違いにより、親会社は子会社の支配権を維持したまま、他社を傘下に収めることが可能になります。例えば、上場している親会社C社が100%子会社のB社を通じてA社を買収する場合、通常の合併では一時的にB社の株主構成が変わってしまいますが、三角合併ならC社がB社を完全にコントロールしたまま取引を完了できます。
また、外国企業による日本企業の買収においても、現行法では外国企業が直接日本企業と合併することができないため、三角合併が重要な手法として活用されています。外国企業が日本に子会社を設立し、その子会社を通じて日本企業を買収する際に威力を発揮します。
三角合併が2007年に解禁された背景
三角合併は、2006年5月に施行された会社法から1年後の2007年5月1日に解禁されました。この解禁には、経済のグローバル化とクロスボーダーM&Aの加速という時代背景があります。
旧商法時代には、消滅会社の株主に交付できる対価は「存続会社の株式」のみに限定されていました。しかし、この制限により海外企業による日本企業の買収が困難となり、国際的なM&A市場での日本の競争力低下が懸念されていました。特にアメリカからは、日本市場への参入障壁として三角合併解禁の強い要請がありました。
新会社法では対価の柔軟化が図られ、現金や親会社株式での支払いも可能となりました。ただし、外国企業による敵対的買収への懸念から、防衛策整備のための期間として1年間の猶予が設けられ、2007年の解禁となったのです。現在の三角合併は友好的な提携を前提とした制度として運用されており、中小企業にとっても事業拡大や国際展開の新たな選択肢となっています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



三角合併と他のM&A手法との比較
M&Aには様々な手法があり、それぞれに異なる特徴とメリット・デメリットがあります。中小企業経営者が最適な手法を選択するためには、三角合併と他の主要なM&A手法との違いを理解することが重要です。ここでは、三角合併と類似手法との比較を通じて、適切な選択基準を解説します。
三角合併と逆三角合併の使い分け
三角合併と逆三角合併は名前は似ていますが、実際の仕組みは大きく異なります。三角合併では対象会社が消滅会社となり、買収側の子会社が存続会社となります。一方、逆三角合併では買収用に設立された特別目的会社(SPC)が消滅会社となり、対象会社が存続会社として残ります。
使い分けの基準は、対象会社の許認可や契約関係の維持にあります。対象会社が重要な許認可を保有している場合や、取引先との長期契約が法人格と密接に結びついている場合は、逆三角合併が適しています。許認可の引き継ぎが困難である医療機関、建設業、金融業などでは、法人格を維持できる逆三角合併のメリットが大きくなります。一方、許認可の制約が少なく、買収側の経営方針を迅速に反映させたい場合は、三角合併が効果的です。
株式交換・事業譲渡との違いと選択基準
株式交換は、完全親会社が完全子会社の全株式を取得し、100%の支配関係を築く手法です。三角合併との大きな違いは、株式交換では対象会社の法人格が残ることです。また、株式交換では通常、買収する側の会社の株式(親会社株式)を対価とします。一方、三角合併では、存続会社(買収を実行する子会社)の親会社の株式を対価として交付するのが基本的な仕組みです。
より複雑なケースでは、存続会社の親会社のさらに親会社(祖父会社など)の株式が対価として用いられることもありますが、これは一般的な三角合併の定義ではありません。主な違いは、合併では対象会社が消滅するのに対し、株式交換では対象会社が子会社として存続する点です。
事業譲渡は、会社の事業の一部または全てを譲渡する手法で、必要な事業のみを選択的に取得できる点が特徴です。しかし、従業員の個別同意や取引先との契約更新が必要となり、手続きが煩雑になります。
選択基準として、対象会社の法人格を維持したまま完全子会社化を目指す場合は株式交換(または三角株式交換)が適しています。特定の事業のみを取得したい場合は事業譲渡が考えられます。外国企業による日本企業の買収や、買収の対価として親会社の株式を利用したい場合には、三角合併が有効な選択肢となります。ただし、複雑な資本関係での統合や具体的な状況に応じて最適な手法は異なるため、専門家との相談が不可欠です。
中小企業に適したM&A手法の判断フローチャート
中小企業がM&A手法を選択する際の判断基準をフローチャート形式で整理すると、まず「買収資金の準備状況」を確認します。現金での買収が困難な場合は、株式交換や三角合併が有力な選択肢となります。次に「対象会社の特性」を検討します。許認可や契約関係の維持が重要な場合は株式交換や逆三角合併、特定事業のみの取得が目的なら事業譲渡を選択します。
- 資金制約がある場合:株式交換または三角合併を検討
- 許認可維持が重要:株式交換または逆三角合併を選択
- 特定事業の取得:事業譲渡が最適
- 外国企業との取引:三角合併が有効
- 完全子会社化が目標:株式交換または三角合併を採用
最終的な判断では、税務上の取り扱い、手続きの複雑さ、株主や債権者への影響を総合的に評価し、自社の戦略目標に最も適した手法を選択することが重要です。
三角合併の5つの活用場面を中小企業向けに解説
三角合併は大企業だけのものではありません。中小企業においても、適切な場面で活用することで事業の成長や発展につながる可能性があります。ここでは、中小企業が三角合併を活用できる5つの具体的な場面について、実際のメリットと留意点を含めて詳しく解説します。
外国企業による中小企業の完全子会社化
日本の中小企業が持つ高い技術力や独自のノウハウは、海外企業からも強く注目されています。外国企業が中小企業を完全子会社化したい場合、個別の株主から株式を買い取る方法では時間とコストがかかりすぎるため、三角合併が有効な手段となります。
例えば、精密機器製造を手がける中小企業が、アメリカの大手技術企業に買収される場合を考えてみましょう。外国企業は日本に子会社を設立し、その子会社を通じて中小企業を吸収合併します。中小企業の株主は、アメリカ企業の株式を受け取ることになります。
この場合のメリットは、中小企業の株主が流動性の高い外国企業の株式を取得できることです。また、外国企業側も現金を用意せずに買収を実現できます。ただし、言語の壁や文化の違い、外国企業の株式保有に伴うリスクについては事前に十分な検討が必要です。
上場企業グループ内での中小企業統合
上場企業のグループ内に複数の中小企業がある場合、効率的な統合を図るために三角合併が活用されることがあります。特に、非上場の中小企業を存続会社とし、他のグループ会社を統合する際に威力を発揮します。
具体的なケースとして、上場企業の傘下にある地域密着型の中小サービス業が、同じグループ内の他の事業会社を統合する場面が挙げられます。通常の合併では非上場企業の株式を対価とするため流動性に問題が生じますが、三角合併なら上場企業である親会社の株式を対価とできるため、統合される企業の株主にとってもメリットがあります。
この統合により、グループ内での重複業務の削減、経営資源の効率的配分、シナジー効果の創出が期待できます。
事業承継における親族外への事業移転
中小企業の事業承継では、後継者不足により親族外への事業移転を検討するケースが増えています。このような場面で、買い手企業が上場企業の子会社である場合、三角合併が有効な選択肢となります。
地方の老舗製造業の経営者が引退を考えており、後継者がいない状況を想定してみましょう。買い手となる企業が上場企業の子会社である場合、三角合併により現在の株主(創業者家族など)は上場企業の株式を取得できます。これにより、事業の継続と同時に、創業者家族にとっても流動性の高い資産を確保できることになります。
事業承継における三角合併のメリットは、売却代金を現金ではなく株式で受け取ることで、将来的な企業価値向上の恩恵も受けられる点です。
技術力のある中小企業の海外展開支援
優れた技術を持つ中小企業が海外展開を目指す際、資金力や現地でのネットワークが不足することが課題となります。このような場面で、海外に拠点を持つ企業との三角合併により、効率的な国際展開を実現できる場合があります。
例えば、環境技術に強みを持つ中小企業が、海外で事業展開している日本企業の現地子会社と三角合併することで、現地での販売網や顧客基盤を一気に獲得できます。親会社の株式を取得することで、より大きな企業グループの一員として事業展開が可能になります。
このスキームでは、中小企業の技術力と大企業の資本力・ネットワークが組み合わさり、双方にとってメリットのある関係を構築できます。
グループ会社間でのM&A効率化
企業グループ内でのM&Aにおいても、三角合併は効率的な手段となります。特に、親会社が子会社の支配権を維持しながら、新たな企業を傘下に加えたい場合に有効です。
持株会社制を採用している企業グループにおいて、既存の子会社を通じて新たな企業を買収する場合を考えてみましょう。通常の合併では一時的に子会社の株主構成が変わってしまいますが、三角合併なら親会社の株式を対価とすることで、子会社の完全支配を維持したまま買収を完了できます。
この手法により、グループ戦略に基づいた柔軟な企業再編が可能となり、中小企業であってもより大きな企業グループの戦略の中で成長機会を見出すことができます。
三角合併のメリットと中小企業への影響
三角合併は中小企業にとって新たな成長機会をもたらす可能性があります。従来のM&A手法では実現困難だった取引が可能になることで、中小企業の戦略的選択肢が大幅に拡大しています。ここでは、三角合併がもたらす具体的なメリットと中小企業経営に与える影響について詳しく解説します。
株式の流動性を確保できる
三角合併の最大のメリットの一つは、消滅会社の株主が存続会社の親会社の株式を取得できることです。中小企業のオーナー経営者にとって、これは非常に重要な要素となります。
通常の合併では、消滅会社の株主は存続会社の株式を受け取ることになります。しかし、存続会社が非上場の中小企業である場合、取得した株式の現金化は困難を極めます。一方、三角合併では存続会社の親会社の株式を受け取るため、親会社が上場企業であれば株式市場での売却が可能になります。
例えば、地方の製造業が上場企業グループの子会社と合併する場合、通常の合併では非上場企業の株式しか取得できませんが、三角合併なら上場企業の株式を取得できます。これにより、創業者や株主は必要に応じて株式を現金化でき、事業承継や資産の流動化が円滑に進みます。
現金を使わない資金効率の良いM&A
中小企業にとって大きな負担となる買収資金の問題に対しても三角合併は有効な手段となります。特に外国企業による中小企業買収において、この資金効率の良さは顕著に現れます。
外国企業が日本の中小企業を現金で買収する場合、巨額の資金調達が必要となることもあり、為替リスクも伴います。しかし、三角合併なら外国企業は自社株式を対価とできるため、現金を一切使わずに買収を実現できます。価値のある株式さえあれば、大規模な案件でも実行可能になります。
この仕組みは、中小企業側にもメリットをもたらします。買い手企業の資金調達能力に左右されることなく、より多くの潜在的な買い手候補から最適なパートナーを選択できるようになります。結果として、中小企業の企業価値向上と最適な事業承継先の確保が期待できます。
税制上の優遇措置を受けられる可能性
三角合併では、一定の要件を満たすことで適格合併として認められ、税制上の優遇措置を受けることができます。これは中小企業のM&Aにおいて、非常に重要な経済的メリットとなります。
適格合併の要件を満たした場合、合併により移転される資産は簿価で評価され、譲渡損益に対する課税は繰り延べられます。これにより、合併時に巨額の税負担が発生することを避けることができます。2019年の税制改正により、間接完全親法人が交付する株式についても、譲渡損益の繰延が可能になりました。
中小企業の場合、含み益のある不動産や設備を保有していることが多く、通常の合併では多額の税金が発生する可能性があります。しかし、三角合併で適格要件を満たせば、この税負担を大幅に軽減できるため、より有利な条件での事業承継が実現できます。
経営支配権を維持できる
三角合併では、親会社が子会社に対する100%の支配権を維持したまま、新たな企業をグループに加えることができます。これは企業グループの経営戦略において非常に重要な特徴です。
通常の吸収合併では、消滅会社の株主に存続会社の株式を交付するため、一時的に親会社の子会社に対する支配権が希薄化する可能性があります。その後、株式交換などにより完全支配を回復する必要があり、複雑な手続きと追加コストが発生します。
三角合併なら、親会社の株式を対価とするため、親会社は一貫して子会社を完全にコントロールでき、迅速な意思決定と効率的な経営統合が可能になります。中小企業が大企業グループに参加する際も、明確な支配関係の下で安定した事業運営が期待できます。
三角合併で中小企業が注意すべきポイント
三角合併には多くのメリットがある一方で、中小企業が実施する際に注意すべき重要なポイントが存在します。これらの注意点を事前に理解し、適切な対策を講じることが、三角合併の成功につながります。ここでは、中小企業経営者が特に留意すべき4つの重要なポイントについて詳しく解説します。
敵対的買収リスクを事前に確認する
三角合併は、その手続き上、合併契約の締結や株主総会の承認が必要となるため、基本的には友好的な提携を前提とした制度として設計・運用されています。そのため、一般的に敵対的買収の手段として用いられることは困難と考えられています。
しかし、理論上、対象会社の取締役会が株主からの強い圧力等により合意に至るケースなど、敵対的と見なされうる状況での利用可能性が完全に否定されるわけではありません。中小企業にとっては、相手方との信頼関係に基づき、合意の上で進めるM&A手法と理解しておくことが重要です。これは中小企業にとって重要な保護要素となりますが、同時に注意すべき点でもあります。
三角合併を成立させるためには、存続会社と消滅会社の経営陣が事前に合併契約を締結し、株主総会での特別決議による承認を得る必要があります。特別決議は議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が要件となっています。
中小企業が三角合併を検討する際は、相手企業との信頼関係の構築が不可欠です。単に買収提案を受けるだけでなく、買収後の事業方針、従業員の処遇、企業文化の継承など、重要事項について十分な協議を行う必要があります。特に外国企業との三角合併では、言語や商慣習の違いにより誤解が生じやすいため、専門家を交えた慎重な検討が求められます。
端数株式処理の複雑さに備える
三角合併では、消滅会社の株主に交付する親会社株式に端数が生じる場合、処理が通常の合併よりも複雑になります。この問題は中小企業のM&Aにおいて実務上の大きな課題となる可能性があります。
通常の合併であれば、端数株式は存続会社による買取や競売により現金化し、株主に交付することができます。しかし、三角合併では合併対価が親会社株式であるため、従来の端数処理手続きを適用できません。そのため、存続会社は親会社株式と端数相当の現金を組み合わせて対価を支払う必要があります。
この処理には買取や競売を行わずに株式の端数部分相当の金額を算出する必要があり、専門的な評価作業が必要となります。中小企業では、このような複雑な評価作業に対応できる体制が整っていない場合が多いため、事前に専門家との連携体制を構築しておくことが重要です。
親会社株式取得時の法的要件を満たす
三角合併の実行には、子会社である存続会社が親会社の株式を事前に取得する必要があります。通常、会社法では子会社による親会社株式の取得は禁止されていますが、三角合併の場合は例外的に認められています。
しかし、この株式取得には実務上の困難が伴います。親会社の株式を市場で大量購入する場合、市場価格への影響を考慮する必要があり、実際の大量購入が可能かどうかの検討が必要です。また、親会社への増資による株式取得も考えられますが、資金の出所が親会社からの貸付である場合、「見せ金」と見なされるリスクがあります。
- 市場での大量購入:市場価格への影響を慎重に評価
- 増資による取得:見せ金規制への抵触を回避
- 安価な取得:有利発行該当性の検討が必要
- 適正価格評価:第三者機関による客観的な評価を実施
中小企業では、これらの法的要件を満たすための専門知識や実務経験が不足している場合が多いため、弁護士や公認会計士などの専門家の助言を受けることが不可欠です。
株主・債権者との事前合意を取り付ける
三角合併の成功には、株主や債権者との十分な事前協議と合意形成が欠かせません。特に中小企業では、経営者と株主の関係が密接であることが多く、丁寧な説明と合意形成が重要になります。
株主に対しては、三角合併により受け取る親会社株式の価値、将来性、リスクについて詳細に説明する必要があります。特に外国企業の株式を受け取る場合、配当方針、株主優待制度、IR情報の入手方法など、実務的な事項についても説明が求められます。一部の株主が外国株式の保有を望まない場合、合併前に株式を売却する可能性もあり、株価への影響を考慮する必要があります。
債権者保護についても重要な検討事項です。三角合併により企業の資本構成や信用力が変化する可能性があるため、主要な債権者には事前に合併計画を説明し、理解を得ることが大切です。必要に応じて、債権者保護手続きを適切に実施し、法的な要件を満たすとともに、継続的な取引関係の維持を図る必要があります。
三角合併の事例と中小企業への示唆
実際の三角合併事例を分析することで、中小企業経営者は貴重な学びを得ることができます。ここでは、日本の三角合併の初期の事例であるシティグループのケースと、国内企業同士の三角合併事例であるオリックス証券のケースを取り上げ、中小企業が学ぶべき成功のポイントを詳しく解説します。
シティグループによる日興コーディアル買収事例
2007年に実行されたシティグループによる日興コーディアルグループの完全子会社化は、日本において外国企業の親会社株式を対価とするM&A(いわゆる「三角スキーム」)が解禁されて以降の象徴的な案件の一つです。
この取引は、シティグループの日本子会社を通じて行われ、日興コーディアルグループの株主は対価としてシティグループ(親会社)の株式を受け取りました。この事例はしばしば「三角合併第1号」として言及されますが、法形式としては日興コーディアルグループが存続しシティグループの子会社となったため、正確には「三角株式交換」の手法が用いられたと解釈するのが適切です。このスキームにより、シティグループは現金を使わずに完全子会社化を実現できました。
この事例が成功した重要な要因は、シティグループが日本市場への真剣な取り組み姿勢を示したことです。シティグループは2007年7月に外資系として初めて銀行免許を取得し、東京証券取引所への上場も申請しました。これにより、日興コーディアルの株主にとって受け取るシティグループ株式の流動性が確保され、株式交換への抵抗感が軽減されました。
中小企業への示唆として、買収提案を受ける際は相手企業の日本市場に対する長期的なコミットメントを慎重に評価することが重要です。単なる財務的な魅力だけでなく、事業の継続性や従業員の雇用維持について具体的な保証を求めることが必要です。
参照:
・シティグループ・インク、株式会社日興コーディアルグループ『シティグループ及び日興コーディアルグループ、包括的戦略提携に合意』
・大和総研『経営戦略研究情報 2007 年のM&A動向レビュー②三角合併』
オリックス証券によるジェット証券買収事例
2009年3月、オリックス証券はジェット証券を三角合併方式で吸収合併しました。この事例は、国内企業間における(順)三角合併の活用例として参考になります。
合併のスキームとしては、オリックス証券(存続会社)が、その親会社であるオリックス株式会社の株式をジェット証券(消滅会社)の株主に交付する形で行われました。ジェット証券は、オンライン取引を主体とし、アイドルファンドやグリーンシート銘柄、新型投資信託といったユニークな金融商品を取り扱うなど、特徴的な企画力を持っていました。
この合併の主な目的は、オリックス証券の持つ安定した経営基盤に、ジェット証券の持つ企画力を融合させることで、さらなる経営基盤の強化と顧客満足度の向上を実現することにありました。
この事例から中小企業が学べる点は、自社の強みを活かしつつ、特定の機能やノウハウを持つ企業を三角合併によって取り込むことで、事業の多角化やサービス向上を効率的に図れる可能性があるということです。特に、買収対価として親会社株式を利用できるため、買収資金を抑えつつ戦略的な統合を進める選択肢となり得ます。
参照:オリックス証券株式会社『ジェット証券株式会社との合併に関するお知らせ』
中小企業が学ぶべき成功のポイント
これらの事例から、中小企業が三角合併を成功させるために学ぶべき重要なポイントが明らかになります。
第一に、明確な戦略目的を持つことの重要性です。シティグループは日本市場での事業統合強化、オリックス証券はジェット証券の企画力を取り込むことによる経営基盤強化と顧客満足度向上という、それぞれ明確な目的がありました。中小企業も、なぜ三角合併を選択するのか、どのような価値創造を目指すのかを具体的に定める必要があります。
第二に、自社と相手企業の強みを理解し、シナジーを追求することです。オリックス証券の事例では、安定した経営基盤と特徴的な企画力という、両社の異なる強みを組み合わせることで相乗効果を狙いました。自社の経営資源と相手企業の持つ技術、ノウハウ、顧客基盤などを客観的に評価し、統合によってどのような付加価値が生まれるのかを具体的に描くことが重要です。
第三に、株主への丁寧な説明と合意形成です。三角合併は、消滅会社の株主にとっては、存続会社ではなくその親会社の株式を受け取ることになるため、その価値や流動性、将来性について十分な情報開示と説明を行い、理解と合意を得ることが不可欠です。シティグループの事例では、シティグループ株式の流動性確保がポイントとなりました。中小企業では株主との距離が近いため、より丁寧なコミュニケーションが求められます。
第四に、事前の関係構築も、円滑な交渉と統合のためには有効です。シティグループの事例では、既に日興コーディアルの株式を一定割合保有しており、一定の関係性がありました。相手企業との信頼関係を事前に築いておくことは、M&Aの成功確率を高める要素となり得ます。
- 戦略的な目的の明確化:単なる財務的メリットを超えた価値創造
- 段階的なアプローチ:リスクを抑えながら関係を深化
- 専門家の活用:法務・税務・評価の各分野での適切な助言
- 長期的な視点:短期的な利益よりも持続可能な成長を重視
最後に、専門家との連携が成功の鍵となります。三角合併は複雑な手続きを伴うため、法務、税務、企業評価の各分野で専門家の助言を得ることが不可欠です。中小企業であっても、この点は妥協すべきではありません。適切な専門家チームを組成し、綿密な準備と実行管理を行うことで、三角合併の成功確率を大幅に向上させることができます。
まとめ|三角合併を中小企業M&Aの選択肢として活用しよう
三角合併は、2007年の解禁以来、国内のM&Aにおいて新たな可能性を提供してきました。現金を使わない資金効率の良い買収、税制上の優遇措置など、企業にとって魅力的なメリットがあり、三角合併は外国企業による買収、事業承継、グループ内統合など、様々な場面で活用できる戦略的な選択肢といえるでしょう。
ただし、端数処理の複雑さや法的要件への対応など、注意すべきポイントも存在します。成功事例から学べるように、事前の関係構築と専門家との連携が重要です。中小企業経営者の皆様も、三角合併という選択肢を理解し、自社の成長戦略に活用することで、新たなステージへの飛躍を実現していただきたいと思います。 M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。