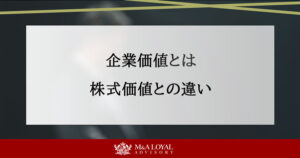譲渡制限付株式とは?報酬制度としてのメリット・注意点、事例を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
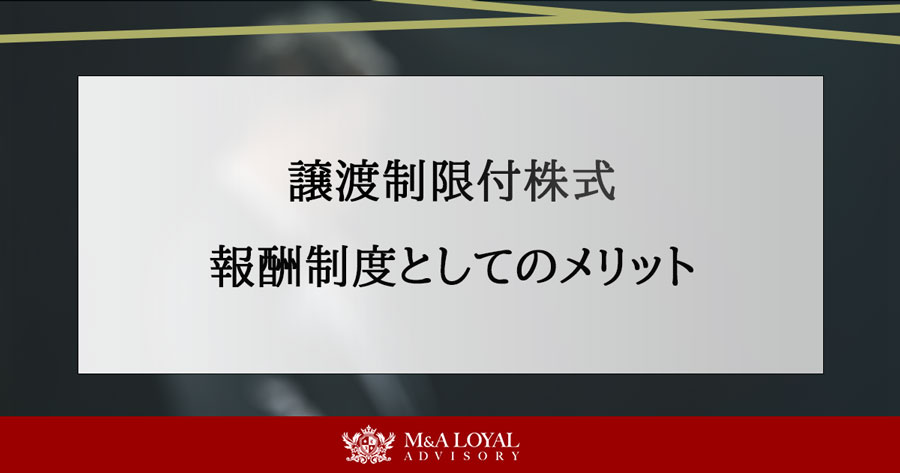
譲渡制限付株式は、一定期間や条件が満たされるまで自由に売却できない株式であり、近年は役員や従業員への報酬制度として活用が広がっています。 譲渡制限付株式は、優秀な人材の定着やモチベーション向上、さらには敵対的買収の防衛策としても有効である一方、制度設計や運用コスト、株価下落リスクなど注意すべき点も存在します。
本記事では、譲渡制限付株式報酬制度の仕組みやメリット・デメリット、ストックオプションなど他制度との違い、導入手順や設計のポイント、実際の導入事例に至るまでを分かりやすく解説します。
目次
譲渡制限付株式報酬制度とは
まず、譲渡制限付株式報酬制度について紹介します。
譲渡制限付株式報酬制度の概要
譲渡制限付株式報酬制度とは、会社が役員や従業員に対してあらかじめ自社株式を報酬として交付し、その株式に一定期間の譲渡制限を設ける仕組みです。交付された株式は制限期間が終了するまでは売却や譲渡ができず、継続して勤務することによって初めて制限が解除されます。もし、所定の勤務期間を満たさなかった場合には、その株式は基本的に会社に無償で取得されます。
パフォーマンスシェアとの違い
パフォーマンスシェア(PS:業績連動株式報酬制度)は、同じく株式を事前交付する点では共通していますが、解除や最終的な付与数が「業績目標の達成度」によって決まる点が大きな特徴です。売上高や利益、株価指標などの業績条件があらかじめ設定され、成果が高ければ株式数が増え、逆に基準を下回れば減少、場合によってはゼロとなることもあります。
譲渡制限付株式報酬制度が「一定期間の勤務」を条件としているのに対し、パフォーマンスシェアは「業績達成」を条件としている点で性格が異なります。
ストックオプションとの違い
ストックオプション(SO)とは、企業が役員・従業員などの人材に対して、あらかじめ決められた価格で自社の株式を取得できる権利を付与する制度です。株価が上昇すれば、権利を行使して安価に株式を購入し、それを市場で売却することで利益を得られます。「将来の株価上昇を前提に利益を得る可能性があるが、報酬がゼロになるリスクもある」という仕組みです。
譲渡制限付株式ユニットとの違い
譲渡制限付株式ユニット(RSU)は、株式そのものではなく「将来株式を受け取る権利(ユニット)」を最初に付与する制度です。ユニットは株式と同じ価値を表しますが、付与時点ではまだ実際の株式は交付されません。そのため、株主としての権利(配当や議決権)も原則として持たないことが通常です。従業員が所定の勤続年数を満たした時点で、ユニットが株式に転換され、初めて株式が交付されます。もし条件を満たせなければ株式は交付されず、権利も消滅します。
両者に共通しているのは、原則として「勤続年数」を条件とする点です。ただし、RSは株式を先に交付してから制限を付ける「事前交付型」であるのに対し、RSUは将来の株式交付を約束する「事後交付型」であるという違いがあります。この仕組みの差によって、従業員の心理的な受け取り方や会社側の設計自由度にも違いが生まれます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



譲渡制限付株式報酬制度のメリット
譲渡制限付株式報酬制度を導入する主なメリットは次のとおりです。
優秀な従業員の流出を防ぐ
譲渡制限付株式は、一定期間を経過しないと自由に処分できない仕組みになっており、従業員はその間会社に在籍して初めて報酬としての株式を完全に取得できます。この仕組みによって、従業員は「株式が完全に自分のものになるまでは会社に残ろう」というインセンティブを持ちやすくなり、結果として優秀な人材の定着につながります。特に競争の激しい業界では、リテンション(人材流出防止)の観点から非常に有効な制度です。
役員のモチベーション向上
役員が株式を持つことで、株価や企業価値の上昇が自分自身の利益に直結します。そのため、株主と同じ目線で企業価値の向上を考えるようになり、経営判断に対する責任感や積極性が高まります。
また、短期的な成果だけでなく、中長期的な成長戦略や持続的な企業価値の向上を意識する動機付けにもつながり、経営陣のモチベーションを全体的に底上げする効果が期待できます。
管理機能の向上
譲渡制限付株式を付与された役員や従業員は、株式を自由に売却できないため、一定期間は会社と運命を共にする立場になります。これにより、経営陣や従業員は株主としての意識を持ち、会社の成果やガバナンスに主体的に関与するようになります。結果として、業績や経営の透明性を意識した行動が増え、企業全体としての管理機能や内部統制の質が高まることにつながります。
このように、譲渡制限付株式の制度は、従業員のモチベーション向上や企業文化の醸成にも寄与するため、企業の長期的な成長戦略において重要な役割を果たします。
現金が不要
この制度では、報酬を株式で交付するため、会社が現金を支出する必要がありません。特に資金に余裕がないベンチャー企業やスタートアップにとっては、現金を温存しながら優秀な人材に魅力的な処遇を提供できる点が大きな強みです。
また、現金報酬と株式報酬を組み合わせることで、資金繰りと人材確保の両立を図ることも可能です。
敵対的買収の防衛
役員や従業員に譲渡制限付株式を広く付与しておくと、会社に深く関わる人々が株主として一定の株式を持つことになります。これにより、外部の第三者が大量の株式を買い集めて経営権を奪おうとする「敵対的買収」を仕掛けても、社内株主の結束が強固であるため、簡単に支配権を握ることが難しくなります。この仕組みは、防衛策としての側面も持っているのです。
譲渡制限付株式報酬制度のデメリット
譲渡制限付株式報酬制度を導入する主なデメリットは次のとおりです。
社内の株主間での権力闘争のリスク
譲渡制限付株式は、役員や従業員に幅広く付与されるため、退職者や不満を抱える社員が株式を保有し続けるケースが発生します。その株式が第三者に売却されたり、まとめて外部に流出したりすると、会社の支配権に影響を及ぼす可能性があります。結果として、経営の安定性が損なわれたり、敵対的買収や経営への不当な干渉といったリスクが高まる要因となります。
設立後の導入が難しい場合がある
譲渡制限付株式報酬制度を導入するためには、定款の変更や株主総会での特別決議が必要です。このため、既存株主の理解と合意を得ることが欠かせず、特に株主数が多い会社や利害関係者が複雑な会社では調整が困難になります。設立時に制度を設けておけばスムーズに運用を開始できますが、会社設立後に新たに導入しようとすると、時間やコストがかかりやすい点がデメリットとして挙げられます。
株価が下落するリスク
譲渡制限付株式報酬制度を導入する際には、新株を発行して役員や従業員に付与することが一般的です。新株発行は市場に出回る株式の総数を増加させるため、既存株主の持分比率が下がる「希薄化リスク」が生じます。その結果、EPS(Earnings Per Share=1株当たり利益)が低下し、投資家から見た株式価値が下がる可能性があります。特に市場からの評価が敏感な上場企業では、株価下落につながるリスク要因となり得ます。
株価下落によるインセンティブの低下
譲渡制限付株式の魅力は、株価の上昇によって大きな報酬価値を得られる点にあります。しかし、会社の業績不振や市場環境の悪化により株価が下落すると、株式報酬としての価値が低下し、役員や従業員にとってのインセンティブ効果が薄れてしまいます。現金報酬と異なり価値が保証されないため、外部環境の影響を強く受けやすく、報酬制度としての安定性に欠ける面があります。
制度設計や運用にかかるコスト
この制度を導入するには、定款の整備や株主総会での承認など複雑な法的手続きが必要です。また、譲渡制限期間や解除条件、没収の仕組みなどを慎重に設計し、付与後も継続的に管理する体制を整えなければなりません。専門家への依頼や内部での管理体制の構築が必要となるため、制度の設計段階から運用まで相応のコストと労力が発生します。特にリソースの限られた中小企業にとっては、その負担が大きく感じられる場合があります。
従業員に課税義務が発生する
譲渡制限がかかっている株式が交付される時点では、通常は課税対象になりません。しかし、譲渡制限が解除され、従業員が株式を自由に処分できる状態になった段階で、その時点の時価が給与所得として課税されます。これにより、従業員にとっては税負担が生じる可能性があります。
しかし、譲渡制限が解除され、従業員が株式を自由に処分できる状態になった段階で、その時点の時価が給与所得として課税されます。 さらに、従業員が株式を実際に売却した際には、譲渡所得として課税されます。
譲渡制限付株式報酬制度の導入手順
譲渡制限付株式報酬制度を導入する手順は次のとおりです。
- 金銭報酬債権の付与
- 現物出資としての払込み
- 株式の交付と譲渡制限の設定
- 譲渡制限の解除条件
それぞれの工程を分かりやすく解説します。
金銭報酬債権の付与
譲渡制限付株式を役員や従業員に付与する場合、会社法上の手続きに沿って株式を発行する必要があります。
通常の方法として、会社が役員や従業員に対して「金銭報酬債権」を報酬の一部として支給し、その債権を株式取得のための出資に充てる仕組みを取ります。こうすることで、株式交付に必要な「対価」が存在することになり、法的に適正な株式発行が可能となります。この手法は、株主に対する義務を果たすためにも重要です。
現物出資としての払込み
役員や従業員は、受け取った金銭報酬債権を「現物出資」として会社に払い込みます。この手続きは帳簿上で処理されるものであり、役員や従業員が実際に現金を会社に支払う必要はありません。つまり、従業員にとっては追加的な資金負担を伴わずに株式を取得できる点が大きな特徴です。この仕組みは、株式報酬制度を通じて、従業員が企業の成長に直接参加できる機会を提供するものとなります。
また、現物出資としての払込みは、株主としての権利を持つことができるため、従業員のモチベーション向上にも寄与します。
株式の交付と譲渡制限の設定
会社は現物出資としての払込みを受けた上で、その対価として譲渡制限付株式を役員や従業員に交付します。ただし、付与された株式は一定の条件を満たすまで譲渡が制限されており、受け取った時点では売却や譲渡による利益を得ることはできません。その後、対象者は契約で定められた期間、会社において役務を提供し続けることを前提としています。
譲渡制限の解除条件
譲渡制限の解除条件として最も一般的なのは「一定期間の勤務継続」です。例えば、3年間在籍すれば、その時点で譲渡制限が解除され、株式を自由に売却できるようになります。
また、勤務年数に加えて「業績条件」を課す設計も可能です。具体的には、売上高や利益率の改善といった目標を達成した場合に制限が解除される仕組みを導入することがあり、これを「業績連動型譲渡制限付株式」と呼びます。混乱を避けるために、これらの条件を「勤務継続型」と「業績連動型」と区別して呼ぶことが一般的です。
条件を満たさなかった場合の取り扱い
もし役員や従業員が在任期間を満たさなかったり、業績条件を達成できなかった場合、会社はその株式を無償で取得し、没収することが一般的です。ただし、任期途中で退任した場合には、在籍していた期間に応じて一部の株式について譲渡制限を解除するなど、柔軟な運用を行うことも可能です。
譲渡制限付株式報酬制度の設計ポイント
譲渡制限付株式報酬制度を設計する際は、次の項目に注意する必要があります。
● 交付対象
● 交付時期
● 勤務期間
それぞれを詳しく解説します。
交付対象
制度を導入する際にまず検討すべきは、株式を交付する対象者を誰にするかという点です。多くの企業では、経営判断に直接関与する取締役や執行役員を中心に付与されますが、優秀な人材の定着を目的として、従業員や特定部門の管理職などに対象を広げるケースもあります。
対象範囲を広げることで従業員全体のモチベーション向上を期待できますが、一方で株主構成や希薄化への影響も考慮し、慎重な設計が求められます。
交付時期
株式の交付時期をいつにするかも重要な設計ポイントです。新任役員就任時や年度の期首に付与する方法のほか、業績評価のタイミングに合わせて付与することもあります。交付のタイミングを戦略的に設定することで、経営計画や業績目標との一体感を持たせやすくなります。
また、期首に付与して中長期的な貢献を促すのか、成果評価後に付与して短期的な努力を報いるのかによって、インセンティブの性格が変わる点にも留意が必要です。
勤務期間
譲渡制限付株式の最も大きな特徴は、一定の勤務期間を条件として譲渡制限が解除される点です。一般的には3年程度の勤務継続を条件とするケースが多く見られますが、5年や10年といった長期設定を行う企業もあります。
勤務期間が長ければ人材の定着効果は高まりますが、従業員の流動性や報酬の魅力度を考慮すると、過度に長期の設定は逆効果となる場合もあります。業界の慣行や企業の成長段階を踏まえ、現実的でバランスの取れた期間を設計することが重要です。
譲渡制限付株式報酬制度の事例
譲渡制限付株式報酬制度を導入している有名企業を紹介します。
ユニ・チャーム
ユニ・チャームは、社員一人一人が中長期的な視点を持ち、企業価値向上に「ONE TEAM」で取り組むことを目的として、役員および全社員を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。対象はユニ・チャーム本体および国内の100%出資グループ会社に所属する正社員・シニアエキスパートの合計3,190名であり、社内資格に応じて株式が付与されます。付与された株式には2020年9月30日から2025年7月1日までの約5年間の譲渡制限が設けられており、その間に新たに入社した社員についても、譲渡制限解除年度を基準に株式が付与される仕組みです。
この制度の目的は、社員にとって成長を加速させるインセンティブを提供し、経済的豊かさを実現することです。また、会社にとっては持続的な企業価値の向上と株主価値の共有を中長期的に実現することにあります。
WOWOW
WOWOWは、2020年5月15日に開催された取締役会において、取締役の報酬制度を見直し、取締役の報酬限度額を年額49億円から60億円に改定するとともに、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。新制度の対象は社外取締役を除く取締役、取締役を兼務しない執行役員および理事であり、企業価値の持続的な成長に向けたインセンティブ付与と株主との価値共有の推進を目的としています。
制度の枠組みとして、金銭報酬債権の総額は年額12億円以内、交付株式数は年100,000株以内とされ、具体的な配分は独立社外取締役が多数を占める指名・報酬諮問委員会の助言を経て取締役会が決定します。株式には3年から30年の間で定められた譲渡制限期間が設けられ、在任継続を条件に期間満了時に制限が解除されます。
SUBARU
SUBARUは、2017年4月28日に開催された取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しました。本制度は、社外取締役を除く取締役および執行役員を対象とし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を強化することを目的としています。また、2016年度の税制改正によって役員への株式報酬に関する税務上の取り扱いが明確化されたことも、導入の背景にあります。
制度の概要として、対象者に割り当てられるのは当社の普通株式で、その総数は年10万株以内とされます。1株当たりの払込金額は、直近1カ月間の終値の平均値を基準とし、特に有利とならない範囲で取締役会が決定します。会社は対象者に株式払込金額相当の金銭債権を報酬として支給し、対象者はこれを現物出資として払い込み株式を取得する仕組みです。また、株式の発行に際しては譲渡制限付株式割当契約を締結し、3年間の譲渡制限や一定事由発生時の会社による無償取得といった条件が設けられます。
JR東日本
JR東日本は、2026年度から非管理職を含む一般社員を対象とした新たな株式報酬制度を導入します。導入するのは「譲渡制限付き株式報酬(RS)」で、社員に自社株式を職制に応じて付与し、売却は取得から10年経過または定年退職時に可能となります。10年未満で退職した場合は株式を返却する仕組みです。
株式の割当規模は株価や業績目標の達成度を踏まえて決定され、詳細な給付数や時期は今後詰められます。会社は既に社員への説明を開始しており、制度の導入に備えて2024年8月には約77億円の自社株買いを実施しました。なお、役員は対象外で、現行のグループ持株会制度も引き続き維持されます。
新制度の目的は、社員に経営参画意識を持たせ、株価上昇による資産形成を通じて人材確保にもつなげることです。JR東は7月に発表した新グループ経営ビジョンで「社員一人ひとりが10年後の当社グループを自ら創る」という起業家精神を掲げており、今回の制度もその一環です。少子高齢化で人口減が続く沿線地域において鉄道事業の持続性を高めるとともに、AIを活用した新サービス創出を進め、社員一人ひとりの活躍を促す狙いがあります。こうした取り組みは、2025年5月に実施した人事・賃金制度改革(定期昇給に成果を反映)とも連動しています。
パーソルグループ
パーソルグループは譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
本制度は、部長や課長などのミドルマネジメント層を対象に、3年間の保有を条件として株式を交付する仕組みです。2021年度に導入され、2024年度の対象者は約3,000名に達し、一人当たりの付与額は100万円相当となっています。これは、管理職社員の貢献に応えるとともに、経営と同じ目線で事業に参画してほしいというCEOの思いを背景に、人事部門と財務部門が協力して制度を整備した結果です。
加えて、グループ各社の取締役や幹部社員を対象とした信託型株式報酬制度も運用しています。この制度では、株式取得のための資金をあらかじめ信託に拠出し、退職時に株式として給付します。2017年度に導入されて以来、対象者や給付額を段階的に拡大しており、2024年度には約250名が対象となり、一人当たり300万円相当の給付規模にまで成長しています。
そもそも株式の譲渡制限とは
次に、株式の譲渡制限について解説します。
譲渡制限株式の概要
株式会社を設立する際には、商号や本店所在地、資本金などを決める他に、株式に譲渡制限を付けるかどうかを定款で定める必要があります。実際には、新しく設立される株式会社のほとんどが譲渡制限付き株式を採用しています。
会社法により、株式会社は「株式を譲渡によって取得するには会社の承認が必要」と定められています。この承認機関は通常、取締役会または株主総会です。
非公開会社と公開会社
株式の全てに譲渡制限を設けている会社を「非公開会社」と呼びます。ここでいう「非公開」とは、上場していないという意味ではなく、「株式を譲渡・取得する際に会社の承認が必要な会社」という意味です。「株式譲渡制限会社」とも呼ばれます。多くの中小企業はこの形態です。
一方、定款で株式譲渡制限を設けていない会社を「公開会社」といい、証券取引所に上場している会社は原則全て公開会社に該当します。
株式に譲渡制限を設けるメリット
株式会社設立時に多くの企業が株式に譲渡制限を設ける目的は次のとおりです。
● 外部の人が株主になるのを防げる
株式譲渡制限会社では、株式の譲渡には会社の承認が必要になるため、経営に関わりのない第三者が株主になることを防げます。また、定款で定めれば、相続によって譲渡制限株式が移転した場合に、会社が相続人に対して株式の売渡しを請求することが可能です。これにより、相続をきっかけに株式が細かく分散したり、会社にとって望ましくない人物が株主になることを防止し、安定した株主構成を維持できます。
● 役員任期を最長10年にできる
非公開会社は、取締役・監査役の任期を最長10年まで延長できます。登記や重任決議の頻度を下げられるため、手続きコスト・事務負担を軽減でき、長期の事業計画に沿った体制維持もしやすくなります。人材流動が少ない同族会社や中小企業では特に有効です。
● 取締役会を置かなくても良い
非公開会社は「取締役会非設置」という選択ができ、取締役1名体制も可能です。議案審議や議事録作成などの手続きが簡素になり、日々の意思決定を速く回せます。創業初期や小規模事業で、機動力や事務負担の軽さを重視する場合に適します。
● 監査役を設置する義務がない
原則として、非公開かつ一定の規模以下であれば監査役の設置は任意です。その分、役員数・機関設計・報酬などの固定コストを抑えられます。実務では、会計士・税理士等の外部専門家によるチェックや内部けん制で代替するケースも多いです。
● 株主総会の招集期間を短縮できる
公開会社の原則が「2週間前通知」であるのに対し、非公開会社は「1週間前通知」で招集できます。全株主の同意が得られる場合はさらに柔軟な運用(招集手続きの省略等)も可能です。
● 発行可能株式総数を自由に設定できる
非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合、法律上は発行可能株式総数に倍率制限がなく、会社の資本政策に応じて自由に設計できます。一方で公開会社(譲渡制限のない会社)の場合は、会社法により発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍以内と制限されています。
株式に譲渡制限を設けるデメリット
株式に譲渡制限を設けることには次のようなデメリットも存在します。
● 外部からの出資を受けにくい
株式に譲渡制限を設けると、新しい株主を迎えるためには会社の承認が必要になります。これは会社の安定性を守る一方で、外部の投資家やベンチャーキャピタルが自由に株式を取得できないため、資金調達の機会が制約される側面があります。特に、急速な成長を目指すベンチャー企業やスタートアップにとっては、投資家が参入しにくくなることで資金調達の選択肢が限られてしまう可能性があります。その結果、銀行融資や内部留保など、株式発行以外の手段に依存することになりやすいのです。
● 経営の透明性が損なわれることがある
譲渡制限付き株式を採用している会社では、株主構成が限られ、株主のほとんどが経営陣やその身内、親しい関係者で固められることが一般的です。そのため、株主によるチェック機能が働きにくくなり、外部の監視が不足することで経営判断が閉鎖的になりがちです。外部の意見や異なる視点が入らないため、意思決定の透明性や健全性が損なわれ、場合によってはガバナンスが弱まるリスクもあります。経営陣にとっては自由度が高い反面、内部の少数者の意見に偏った運営にならないよう、バランスを意識する必要があります。
● 株式買取請求権が行使される場合がある
譲渡制限株式では、株主が株式を譲渡しようとしても会社が承認しないケースがあります。この場合、株主は「株式買取請求権」を行使し、会社に対して自らの株式を買い取るよう求めることができます。これは、株主が株式を自由に処分できないという不利益を受ける代わりに、適正な価格で現金化できるようにするための権利です。一方で、会社にとってはこの制度が大きな負担になることがあります。特に、会社の業績が好調で株価が高く算定される場合や、複数の株主から同時に請求が行われる場合には、多額の資金を短期間で準備しなければならず、資金繰りに深刻な影響を与える可能性があります。さらに、買取価格について会社と株主の間で意見が対立すれば、裁判所に価格決定を申し立てる必要が生じ、手続きやコストの負担も増えます。
譲渡制限付株式を売却する方法
譲渡制限株式の譲渡の基本的な流れは次のとおりです。会社によって承認される場合を紹介します。
- 請求者の譲渡承認請求
- 取締役会または株主総会での承認
- 決定内容の請求者への通知
- 株式譲渡契約書の締結
- 株主名簿の書換請求
- 株主名簿記載事項証明書の交付
それぞれの工程を分かりやすく解説します。
請求者の譲渡承認請求
譲渡制限株式を持つ株主が自分の株式を第三者に譲渡しようとする場合、まず会社に対して承認を求める「譲渡承認請求」を行わなければなりません。譲渡制限株式は、定款で会社の承認を条件としているため、承認請求を行わずに譲渡しても効力を持ちません。請求には譲渡の相手方、株数、譲渡条件などを記載し、会社に提出することが一般的です。
取締役会または株主総会での承認
会社は請求を受けると、定款で定められた承認機関によって審議が行われます。取締役会を設置している会社では取締役会が承認権限を持ち、取締役会がない会社では株主総会が承認機関です。
ここで承認が得られなければ、株式を自由に譲渡できません。ただし会社は単に承認を拒否するだけではなく、不承認とする場合には会社自身や他の株主に株式を買い取らせる義務を負います。これは株主の財産権を保護するための仕組みです。
決定内容の請求者への通知
承認または不承認の決定がなされたら、会社は速やかにその内容を請求者へ通知します。承認された場合は通常どおり譲渡に進みますが、不承認の場合には、会社が定められた期間内に株式の買い受け人を指定しなければなりません。
もし、買い受け人を指定できなければ、最終的に譲渡は承認されたものとみなされる場合もあります。この「承認みなし」の規定は、会社の定款や株主総会の決議に基づいて設定されることが一般的です。
株式譲渡契約書の締結
承認が得られた場合、譲渡人と譲受人との間で株式譲渡契約書を作成します。この契約書には譲渡する株式の種類や数、譲渡価格、支払条件、譲渡日などを明確に記載します。契約書を交わすことで、譲渡の条件に関する誤解やトラブルを防止し、譲渡を法的に有効なものとする役割を果たします。
株主名簿の書換請求
契約が成立しても、それだけでは新しい株主が会社に認められるわけではありません。会社に対して株主名簿の書換請求を行い、正式に名義を変更する必要があります。
株主名簿に記載されて初めて、株主としての権利(議決権や配当請求権など)が認められます。これは会社法上の重要な要件です。このため、株主名簿の書換は、株主としての地位を確立するための重要な手続きとなります。
株主名簿記載事項証明書の交付
株主名簿の書換が行われると、会社は「株主名簿記載事項証明書」を交付します。これは新株主の名義変更が完了し、会社がその事実を公式に証明する書類です。
この証明書が交付された時点で、株式譲渡の手続きは全て完了です。新株主はこれをもって正式に会社法上の株主として認められ、株主としての権利行使が可能となります。
譲渡制限付株式会社を公開会社にする方法
譲渡制限付株式会社を公開会社にする方法は次のとおりです。
- 株主総会の特別決議
- 取締役・監査役の選任
- 登記申請
それぞれの工程を解説します。
株主総会の特別決議
まず、会社を公開会社にするためには、株主総会において定款変更の特別決議を行う必要があります。
具体的には、定款に定められている「株式を譲渡するには会社の承認を要する」という条項を削除し、株式を自由に譲渡できるようにします。特別決議には出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要であり、通常の決議よりも厳格な要件が求められます。
また、この定款変更が効力を生じると、会社法の規定により現在の取締役や監査役の任期が自動的に終了する点にも注意が必要です。つまり、この決議をもって新たな役員体制を選任する準備も同時に進めておかなければなりません。
取締役・監査役の選任
公開会社となる以上、ガバナンス体制の強化が必須です。会社法では公開会社には取締役会の設置が義務付けられており、最低でも3名以上の取締役を選任する必要があります。
また、監査役が設置されていない場合には、少なくとも1名以上の監査役を新たに選任する必要があります。監査役は会社の業務や会計を監査する役割を担い、取締役の監視機能を果たすため、公開会社化の過程で必須のポジションです。ここで選任された取締役・監査役は、株主総会での承認を経て正式に就任します。
登記申請
定款変更と新たな役員体制の決定が整ったら、最後に登記手続きを行います。本店所在地を管轄する法務局に対して登記申請を行い、公開会社である旨と役員体制の変更を記録します。
登記の申請は変更決議の日から2週間以内に行うことが法律で義務付けられており、これを怠ると過料の対象となる場合があります。登記が完了すると、会社は正式に「公開会社」として扱われるようになります。
まとめ
譲渡制限付株式は、企業にとって魅力的な人材を引き留めたり、モチベーションを向上させるための有力な報酬制度です。しかし、その導入には慎重な制度設計が必要で、運用コストや税務上の注意点にも配慮しなければなりません。また、株価の変動によってはインセンティブが弱まるリスクもあるため、導入を検討する際はこれらの要素をしっかりと考慮することが重要です。もし、譲渡制限付株式の導入を考えているのであれば、まずは自社のニーズに合った制度設計を行い、専門家に相談することをお勧めします。これにより、企業の長期的な成長と安定を図ることが可能となります。ぜひ、この記事を参考にして、次のステップへと進んでください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。