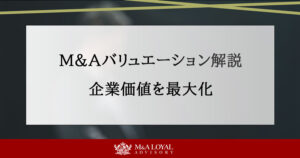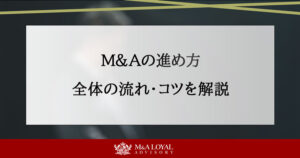製造業のM&A最前線|成功事例で読み解く戦略と実務ポイント
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
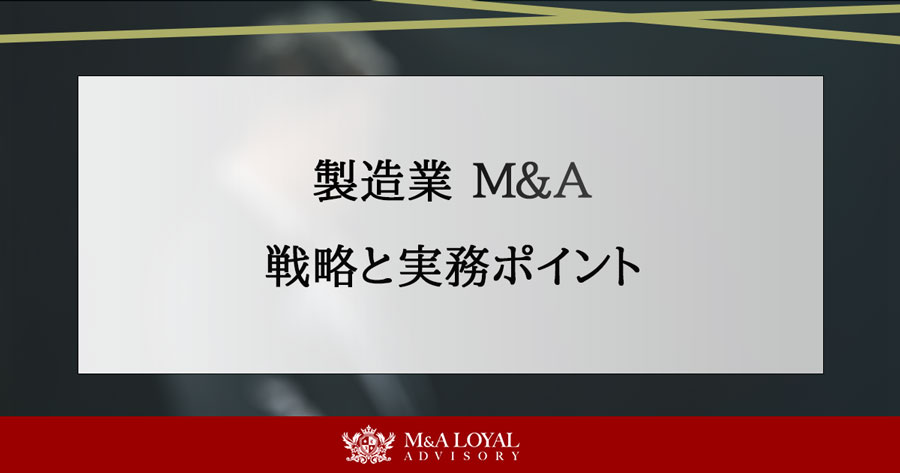
製造業におけるM&A(合併・買収)は、いまや単なる事業承継の手段にとどまらず、技術革新の加速、海外展開、業界再編といった経営課題を解決する“成長戦略”として注目されています。
2025年現在、国内では鉄鋼・化学・電子部品・自動車部品など製造業分野で大規模な再編が相次ぎ、規模の枠を超えて多くの企業が、M&Aを活用して次のステージに進もうとしています。
一方で、製造業特有のノウハウ・設備・人材の継承、製造現場の統合(PMI)、知財や取引契約の扱いなど、他業界にはない実務上の難しさもあります。M&Aは成功すればチャンスとなりますが、失敗すれば経営の混乱を招く恐れもあるため、正しい知識と戦略が不可欠です。
本記事では、製造業M&Aの最新動向と、実際の成功事例をもとに「何が成否を分けるのか」「どう進めるべきか」を解説します。M&Aを検討している製造業の企業の経営者や実務担当の皆さんは、ぜひご参照ください。
目次
製造業におけるM&Aの現況とトレンド(2025年版)
製造業全体の件数と業種別傾向
2025年上半期、日本におけるM&A総件数は前年比10%以上の伸びを示し、製造業関連の案件も例年を上回る活況を呈しています。特に、下記の業種において取引数の増加が見られます。
- 鉄鋼・金属加工業:大手による海外企業の買収や、素材供給の安定化を目的とした垂直統合が進行中。
- 電子部品・半導体関連:台湾・韓国の競合を意識した技術統合や、外資系とのアライアンスが加速。
- 化学・素材系メーカー:脱炭素を目的とした異業種連携型のM&Aが増加。
- 自動車部品・機械加工系:EV対応やグローバルサプライチェーン再構築を視野に入れた買収が進む。
特に、東証プライム上場企業においては、非中核事業の切り離し(カーブアウト)と新技術獲得を両立する「攻めと守りのM&A」が活発化しており、業界横断的な取引が目立っています。
活発化の背景:グローバル化、人材不足、技術継承
製造業M&Aの背景には、以下のような構造的要因が複合的に絡んでいます。
- グローバル競争の激化:アジアや北米、欧州の製造業プレイヤーと対抗するためには、規模拡大・コスト最適化が不可欠であり、M&Aはその手段となっています。たとえば、日本製鉄のUSスチール買収も「調達から製造・販売までの北米拠点強化」が目的のひとつでした。
- 国内の人材不足と後継者難:特に中小製造業では、熟練技能者の高齢化と若手技術者の確保が難航しており、事業の維持に限界を感じた経営者による売却相談が増えています。M&Aは「後継者不在問題」の具体的解決策として実務に定着しつつあります。
- 技術継承・研究資源の共有:研究開発型企業では、設備投資・技術開発費の高騰が続き、単独では競争が困難な分野も増加。M&Aを通じた「補完関係の技術融合」が、製品の高付加価値化に繋がっています。
製造業M&Aの特徴と他業界との違い
製造業におけるM&Aは、業務の性質上、以下のような特徴が存在し、他業界とは異なる慎重な検討が求められます。
- 固定資産・減損リスクの精査:土地・工場・特殊設備など高額な資産を保有する企業が多く、その価値評価と将来収益の見通しが取引条件に強く影響します。
- 知的財産・技術ノウハウの把握困難性:製造技術が暗黙知化していることも多く、「人に依存するノウハウ」が移転できないリスクがあります。トレーニング制度や標準化マニュアルの整備度も重要な評価要素となります。
- 製造現場の統合リスク(PMI):設備や人材の統合がスムーズに進まなければ、品質管理や生産性が大きく低下します。多拠点間のERP統合、製造工程の調整、労務管理の統一など、統合フェーズの難易度が非常に高い点も特筆すべきです。
- 取引先との関係性の維持が不可欠:サプライヤーや元請けとの長期取引に支えられる企業も多く、M&A後に「会社が変わったから解約」といった事態を避けるため、事前の合意形成や信頼関係維持が極めて重要です。
これらをふまえ、製造業M&Aでは「法務・財務・技術・現場」のすべてに目配りした総合的な戦略と実行体制が求められます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



製造業での成功事例
日本製鉄×U.S.Steel:国家を巻き込んだ大型買収
2023年12月、日本製鉄が米国の老舗鋼鉄メーカー「U.S.Steel」を141億ドル(約2兆円)で買収すると発表し、2025年6月に正式に買収を完了しました。このM&Aは、グローバル鉄鋼業界における日米連携の象徴であり、政治的・経済的に極めて大きなインパクトをもたらしました。
最大の障壁となったのは、米国政府および労働組合からの反発でした。バイデン政権は国家安全保障や雇用の観点から慎重姿勢を崩さず、長期にわたる審査と交渉が続きました。
その中で日本製鉄は、「ゴールデンシェア」と呼ばれる特別株制度を導入。米政府に対して重要事項の拒否権を与え、安全保障上の懸念に配慮した設計を行いました。また、買収後には現地への大規模投資、雇用維持、U.S.Steelブランドの継続、米国人CEOの任命など、地域社会との信頼構築にも注力しました。
この事例は、製造業M&Aにおいて「政治対応力」「ガバナンス配慮」「地元合意の形成」がいかに重要かを物語っています。
大日本印刷×光金属工業所:異業種技術の融合による成長戦略
2025年1月、大日本印刷(DNP)は自動車内装部品などを手がける光金属工業所の持株会社「HKホールディングス」を完全子会社化しました。これは印刷業界の大手が製造業のなかでも金属・加飾分野へ進出するという大胆なM&Aであり、注目を集めました。
この買収の背景には、DNPの印刷技術をベースにした高機能素材事業と、光金属の金属成型技術の融合によって、次世代モビリティ(EV・自動運転)向け製品の開発力を強化する狙いがあります。
また、脱炭素としてプラスチックから金属へのシフトが求められるなかで、環境配慮型素材の開発という点でもシナジーが高いM&Aとなりました。買収後も光金属工業所の経営体制や顧客対応は維持され、技術・営業両面での統合がスムーズに進行中です。
第一工業製薬×ゲンブ:グループ内M&Aで効率化
第一工業製薬は、2025年4月に同社グループ企業であるゲンブの脱臭剤関連事業を吸収分割により統合しました。これはいわゆる「グループ内M&A」であり、事業整理・経営資源の集中を目的とした戦略的な再編と位置づけられます。
ゲンブは特殊素材や機能性化学品に強みを持つ企業で、これまで一定の独立性を保ってきました。しかし、グループ内での事業重複や業務効率の課題が顕在化し、より機動的な研究・製造体制の構築が求められていました。
この吸収分割では、技術者の移籍、製造拠点の統合、知財の一括管理が行われ、PMIは極めてスムーズに進行。収益構造の安定化と研究開発の集中が実現し、グループ全体としての競争力が高まる結果となっています。
これらの事例はいずれも、目的の明確化・買収後統合の計画性・現場との信頼構築といった要素を備えており、2025年の製造業M&Aにおける「成功モデル」として広く参照されるに値します。
成功のカギは?
戦略的マッチングの重要性
製造業におけるM&Aの成否を分ける最大の要素は、買収先企業と自社との「戦略的マッチング」が取れているかどうかにあります。単に財務指標が良好だから、あるいは安価だからといった理由でM&Aを行った場合、統合後に事業シナジーが生まれず、却って統合コストや摩擦が増すリスクがあります。
成功するM&Aでは、以下のような戦略的な整合性が確認されています。
- 技術的補完関係がある(例:DNPと光金属の素材技術融合)
- 顧客層や市場が一致している
- サプライチェーン上の統合メリットが見込める
- 中長期の成長戦略と合致している
また、業界内におけるポジショニングの最適化という観点も重要です。競合他社との差別化要素を明確化し、M&Aによって市場での強みをどのように拡張できるかを可視化することが、M&A成功の起点となります。
このように、「なぜこの企業を買収するのか」「何を一体化させるのか」が明確であればあるほど、M&A後の統合プロセスにおいても迷いが生じず、現場レベルでの実行力が高まります。
PMI(統合プロセス)の実務ポイント
Post Merger Integration(PMI)は、M&A成功の可否を決める最大の山場です。特に製造業では、現場の生産体制、品質管理、システム統合など「実働の調整」が不可欠であり、一般的なサービス業M&Aよりも格段にハードルが高いのが実情です。
PMIで重視すべき点は以下のとおりです。
- 組織文化の違いに対するケア(例:日米企業統合時の価値観調整)
- 生産ラインや在庫管理システムの統合
- 現場リーダー層の巻き込みと早期対話
- 中核人材の流出防止施策
- 物流拠点やサプライヤーとの連携強化
- 製品仕様や品質基準の統合・標準化
- ERPやPLMなどの主要システム統合
特に、買収先企業のキーパーソンが離職した場合、暗黙知や顧客関係など重要な無形資産が失われる可能性があります。PMI開始前から関係構築を始め、M&A完了後も継続的にフォローを行う「長期型の人材戦略」が必要です。
さらに、統合後に起こりやすい課題として「現場オペレーションの混乱」や「責任範囲の曖昧化」があります。これを防ぐには、M&A前の段階で統合後の業務プロセス設計(TO-BE設計)を明確にしておくことが重要です。
成功企業に学ぶ「人・技術・資本」の融合戦略
成功事例に共通して見られるのは、「人材の引継ぎ」「技術の統合」「資本効率の最適化」という3つの軸を有機的に融合させる設計力です。以下、一例をあげましょう。
- 日本製鉄はU.S.Steelの幹部と現場人材を活かしつつ、米国内での経営自立性を保証。地域雇用を維持することで政治リスクにも対応し、グローバル統合のロールモデルとなった。
- 第一工業製薬は自社研究とグループ事業を統合し、研究リソースの集中と成果最大化を実現。グループ内M&Aで効率性と革新性を両立させた。
また、人材については、単なる雇用維持にとどまらず、育成・評価制度の再構築や、統合後のキャリアパス明示も含めた「組織設計の再構築」が効果的であることがわかっています。
このように、M&Aは「買ったら終わり」ではなく、買収後にどのように企業資源を結びつけ、どんな成果を出すかが問われる時代です。机上の数値ではなく、現場・経営・市場の3層を繋ぐ戦略眼が、成功の鍵となります。
製造業M&Aの実務と注意点
製造業特有のデューデリジェンスと契約留意点
製造業M&Aでは、一般的な財務・法務調査に加え、設備資産や生産工程、人材スキルに関する実態把握が欠かせません。これにより、表面的な財務情報では読み取れない「現場の実力」「将来の競争力」を見極めることが可能になります。特に、以下の観点でのチェックが求められます。
- 設備の償却状況と更新投資計画:老朽化設備のリスク評価、再投資必要性の確認。特に、生産に不可欠なライン設備の耐用年数や稼働率は、投資判断に大きく影響します。
- 工場稼働率と生産能力:需要に対して供給余力があるか、設備移転の柔軟性はあるか。閑散期・繁忙期の生産変動と生産ラインの可変性も考慮されるべきです。
- 環境規制・労働基準法順守状況:コンプライアンス違反の有無、是正指導履歴など。特に、化学・金属加工などは環境負荷の観点で行政リスクが高く、過去の行政指導履歴や訴訟リスクも評価に含める必要があります。
- 技術者の年齢構成と継承難易度:ノウハウ継承の見通しと、教育・訓練体制の有無。60代以上が中核を担っている企業では、M&Aによる技術喪失リスクが高く、マニュアル整備や教育制度の確認が重要です。
契約面では、買収後の設備不良・不適合による損害を想定し、「表明保証条項」の明記が必要です。さらに、取引先とのサプライ契約の継続条件や、経営者や幹部社員の退任タイミングの調整条項なども、M&A契約における実務的な論点として見落とせません。
PMI前提の統合スケジュール設計
PMI(Post Merger Integration)を成功させるには、M&A締結前から統合計画を設計しておく必要があります。製造業では以下の要素を事前に明確化しておくことがポイントです。
- 工程別の統合スケジュール(製造、物流、販売、情報):月単位の詳細工程表に落とし込み、部門責任者に役割と期限を明示する。
- ERPや生産管理システムの共通化スキーム:導入済みのITシステムの互換性と統一方針、データ移行計画などを確認。
- 品質管理基準(ISOなど)の一元化手順:既存と買収先の品質基準の差異を調査し、共通ルールの策定が必須。
- 中核人材の業務・職責再設計と配置転換計画:PMI直後に現場の混乱が生じないよう、リーダー層の早期関与と役割明確化が必要です。
さらに、統合後3か月、6か月、1年といったマイルストーンにおける成果指標(KPI)を設定し、実績を定期的に評価・修正するPDCA体制の構築も重要です。
製造業ならではの法務・知財の論点
製造業M&Aでは、商標や特許といった知的財産権の移転だけでなく、設計図や製造工程に関わるノウハウ・技術文書の取扱いが重要です。形式知として文書化されていない「現場の知見」が事業価値の大半を占めるケースも多いため、以下のような法務リスクに配慮が必要です。
- 共同開発契約の有効性確認:旧取引先との知財共有条項、競業避止義務の確認。競合他社との過去契約に基づく知財使用制限がある場合は、シナジー実現に支障をきたす可能性があります。
- 退職者によるノウハウ持出し防止条項の整備:機密保持・競業避止条項の再構築。特に、設計者や製造責任者などの退職者からの知財流出を防ぐため、事前の誓約書締結が有効です。
- 第三者ライセンス契約の移転合意:特許ライセンスや技術供与契約の譲渡承諾の取り付け。特定顧客とのOEM契約や、外部ベンダー技術の共同使用契約の再確認が求められます。
これらの論点を放置すると、買収後に「使えない技術」「使えない特許」だけが残り、想定シナジーが消失するリスクもあります。法務チームと現場が連携し、実態に即した契約・制度設計を徹底する必要があります。
業界別に見る製造業M&Aの動向と戦略
自動車部品業界:EVシフトに伴う再編加速
世界的な電動化(EV)への転換を背景に、自動車部品業界では大規模なM&Aが相次いでいます。既存のエンジン系部品メーカーが事業縮小を迫られる一方、電動モーターや電池冷却システム、軽量素材といった新領域への参入が課題となっています。
この流れを受けて、異業種からの新規参入や、技術獲得型のM&Aが活発化しています。買収の目的は「EV特化技術の確保」や「サプライヤー構造の再編」が主であり、部品モジュール単位での系列再編も進行中です。
中堅部品メーカーにとっては、大手完成車メーカーの調達方針の変化が死活問題となるため、M&Aによって新たな販路や技術基盤を確保する動きが顕著です。
化学・素材業界:脱炭素対応と高機能化ニーズがドライバー
化学・素材分野では、環境規制強化に対応するための「クリーン技術」や、半導体・電池材料といった高付加価値領域への事業転換を背景に、M&Aが加速しています。特に以下の2点が主要なドライバーとなっています。
- 脱炭素対応のための製造プロセス改革
- 高純度素材や特殊材料の需要急増
大手化学メーカーによるベンチャー買収や、同業統合によるスケールメリット確保が目立ち、環境認証やLCA(ライフサイクルアセスメント)への対応力もM&A評価に大きな影響を与えています。
また、海外市場への展開を視野に入れたクロスボーダーM&Aも増加傾向にあり、欧州環境基準(REACH等)を意識した統合戦略が進められています。
電子部品業界:技術進化に伴う垂直統合の流れ
半導体・センサー・回路基板などを含む電子部品業界では、IoT・5G・自動運転といった成長領域の拡大により、供給網の強化と垂直統合を目的としたM&Aが急増しています。
特に、サブコン・EMS(電子製造サービス)企業による材料・設計工程への進出や、ファブレスメーカーによる開発資源獲得が進んでおり、「開発〜製造〜品質保証」を内製化する動きが顕著です。
中堅・中小企業にとっては、部品単価の下落や競争激化のなかで「研究開発機能の共同化」や「販路の共同確保」を目指す戦略的統合が不可欠となってきています。
機械・装置業界:設備更新需要と省力化ニーズへの対応
工作機械、食品機械、物流機器などを含む機械・装置業界では、人手不足や老朽設備の更新需要に対応するため、省力化技術・自動化ソリューションの獲得を狙ったM&Aが進んでいます。
特に、AI・画像認識・ロボティクスを活用したスマートファクトリー関連の機器メーカーを中心に、異分野からの技術統合型M&Aが増加中です。
また、ユーザー企業の“製造ラインの一括請負ニーズ”に対応するために、機械設計、据付、保守まで一貫提供可能な企業を形成するためのグループ内統合も盛んです。
製造業M&Aを取り巻く政策・外部環境の変化
政府による中小企業支援策とM&A促進施策
日本政府は、中小企業の事業承継や再編促進のため、さまざまな支援制度を整備しています。代表的なものに「事業承継・引継ぎ補助金」や「中小M&Aガイドライン」などがあり、M&A実施時の税制優遇や専門家の無料相談窓口が用意されています。
経済産業省の「中小企業の経営資源引継ぎ支援事業」では、地域金融機関やM&A仲介会社と連携し、第三者承継を推進。これにより、後継者難に悩む製造業者の出口戦略としてM&Aを現実的な選択肢とする動きが進んでいます。
また、2024年に施行された改正産業競争力強化法では、地域経済活性化に資する中堅製造業の統合・連携に対して規制緩和や支援措置が講じられており、クロスボーダーM&Aにも弾みがついています。
グローバルリスクとサプライチェーン再構築の潮流
新型コロナウイルスやウクライナ危機など、地政学的リスクが顕在化したことで、製造業のグローバルサプライチェーンに大きな見直しが求められています。とくに中国依存の高い部品・素材の調達については、「脱中国」「サプライヤー多元化」が世界的な潮流です。
この状況下で、海外工場や原材料供給網を持つ企業の買収が増加。たとえば日本企業がASEAN地域の現地メーカーをM&Aすることで、調達多様化・コスト最適化・リスク分散を同時に図るケースが多く見られます。
また、欧米でもサプライチェーン強靱化政策に基づき、自国生産回帰を促進する「産業回帰」支援策が打ち出されており、これに伴う日系企業の再編や海外撤退・売却も進行中です。
ESG経営・カーボンニュートラルとM&A戦略の融合
企業のESG(環境・社会・ガバナンス)対応が評価基準となる中で、製造業においてもカーボンニュートラル対応のためのM&Aが活発化しています。特に以下のような動きが顕著です。
- 二酸化炭素排出量削減につながる製造技術を持つ企業の買収
- 再生可能エネルギー設備を保有する企業の統合
- ESG格付けの高い企業との統合で評価向上を狙う戦略
投資家からの圧力やサプライチェーン全体での脱炭素要求が高まるなか、単なる生産効率だけでなく「持続可能性のある供給体制の構築」が製造業M&Aの新たなトレンドとなっています。
製造業M&Aの今後と経営戦略の展望
M&Aを経営の中核戦略と捉える視点
製造業におけるM&Aは「単なる財務的手段」から、「企業価値の再定義」を可能にする戦略的な施策へと進化しています。とくに日本の中堅〜大企業においては、以下の理由からM&Aが経営の中核に位置付けられるようになっています。
① 技術革新と市場構造の変化
AI、IoT、脱炭素、電動化といった技術トレンドの急速な進展により、自社単独で全ての技術をカバーすることは困難になっています。そこでM&Aによって即戦力の技術や人材、ブランドを獲得し、市場変化に迅速に対応するという経営戦略が定着し始めました。
② 海外展開の再構築
日本製造業の多くが依存してきた中国市場の地政学的リスクや、ローカル志向の高まりにより、「グローバル展開」=「現地企業とのM&A」にシフトする傾向が強まっています。特にASEANやインド、東欧などでは現地パートナーの買収を通じた現地化が鍵を握ります。
③ 株主・市場からの圧力
ROE(株主資本利益率)やPBR(株価純資産倍率)などの改善が求められる中、資本効率を高めるための「事業再編M&A」や「非中核事業の切り離し」が投資家から強く要請されています。
次世代経営に必要な3つのM&A視点
今後の製造業経営者がM&Aを活用する上で不可欠となる戦略視点は以下の3つです。
①「垂直統合」から「価値軸の選択と集中」へ
かつての製造業では、原材料の調達から製造・販売まで一気通貫で行う「垂直統合」が重視されていました。しかし、今日では自社の強みに特化し、周辺領域はM&Aや提携によって効率化する“選択と集中”の戦略が主流です。
例として、完成品メーカーが高機能部材やソフトウェアの設計機能を買収し、周辺工程は外注または提携で補完する動きが挙げられます。
②「買収そのもの」よりも「統合後の価値創造」が重要
M&Aの成否を決めるのは、買収金額の大小ではなく、「統合後に何を実現するか」です。製品の共通化、拠点統合、人材育成、顧客ネットワークの共有など、シナジーの創出ができなければ、むしろ企業価値を毀損するリスクがあります。
統合後に混乱が生じやすい“工場現場”や“設計部門”にこそ、綿密なPMI(Post Merger Integration)計画と社内合意形成プロセスが求められます。
③「技術ドリブン」+「人材・文化ドリブン」型M&A
M&Aでは、目に見える技術や顧客基盤に目が行きがちですが、実は企業の「暗黙知」や「現場の空気感」、「従業員エンゲージメント」こそが価値の源泉であることも少なくありません。
成功するM&Aでは、被買収企業の経営者や従業員との“人間的な信頼関係”を土台に、理念やカルチャーの統合を重視しています。逆に、ここを怠ると、優秀な人材が退職し、技術もノウハウも流出するという結果になりかねません。
M&Aを「差別化戦略」として活用する条件
M&Aは今や、規模の経済やコスト削減の手段ではなく、企業の差別化を実現するためのツールとなっています。以下は、その成功に必要な3つの条件です。
① データドリブンな意思決定体制の構築
市場調査、バリュエーション、技術・人材評価などを定量的に把握し、感覚ではなく「データに基づく意思決定」を行う体制が求められます。特に製造業では、設備寿命・原価率・生産性指標などの正確な把握が必須です。
② ステークホルダーとの長期的関係構築
買収後、従業員・顧客・取引先といった既存の関係性を尊重しつつ、段階的に統合を進める“持続可能なPMI”が重要です。「すぐに変えよう」とせず、時間をかけて信頼を積み上げるアプローチが、結果的に統合効果を最大化します。
③ M&A後のブランドマネジメントと発信力
ブランドの統合や継承方針を明確にし、外部への情報発信も怠らないことが信頼維持の鍵です。特にBtoB製造業では、長年の取引関係が買収によって崩れることを懸念されやすく、早期のコミュニケーションが欠かせません。
このように、製造業におけるM&Aの成功には、経営戦略の一部としての設計・準備・実行が不可欠です。そしてそれを可能にするのは、社内だけでなく、専門家や外部支援パートナーとの協働です。
まとめ:製造業M&Aの現在地と、次に進むための視点
2025年の日本製造業は、地政学的リスク、脱炭素社会への移行、技術革新の加速といった複雑な環境変化の中で、M&Aを重要な成長戦略のひとつとして位置づけています。
この記事では、日本製鉄や大日本印刷などの最新M&A成功事例を通じて、製造業M&Aの実態と成功要因を明らかにしました。特に以下の3点は、どの企業にとっても普遍的な教訓と言えるでしょう。
- 戦略の明確化
「なぜこの企業を買うのか?」「買収後に何を目指すのか?」という目的と成果の可視化が不可欠です。 - 統合プロセス(PMI)の丁寧な設計
現場・人材・文化を無視した統合は、せっかくの買収価値を毀損しかねません。逆に、現場重視の統合戦略が成否を分けます。 - 外部環境の変化への対応力
カーボンニュートラル、サプライチェーン再構築、知財保護など、M&Aは単なる手段ではなく「変化に柔軟に応じるための仕組み」である必要があります。
特に、中小~中堅製造業にとって、後継者不在や販路課題、設備更新といった問題に直面するなかで、M&Aは単なる売却や買収にとどまらず、「未来を切り開く手段」として再評価されつつあります。
買収する側にとっては成長投資のチャンスであり、売却する側にとっては技術・人材・企業文化を次世代に承継する責任ある出口戦略にもなり得ます。
ぜひ、自社の成長・発展を実現するひとつの道として、M&Aをご検討してみてはいかがでしょうか?
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。