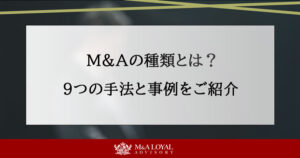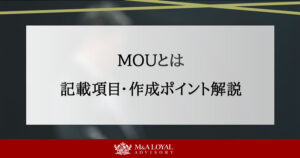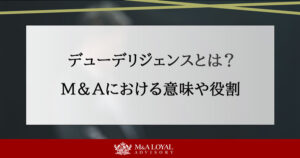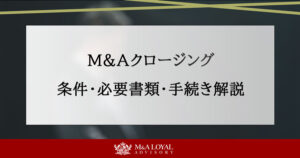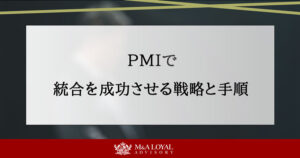M&Aの期間とスケジュールは?平均目安や必要な準備を詳しく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
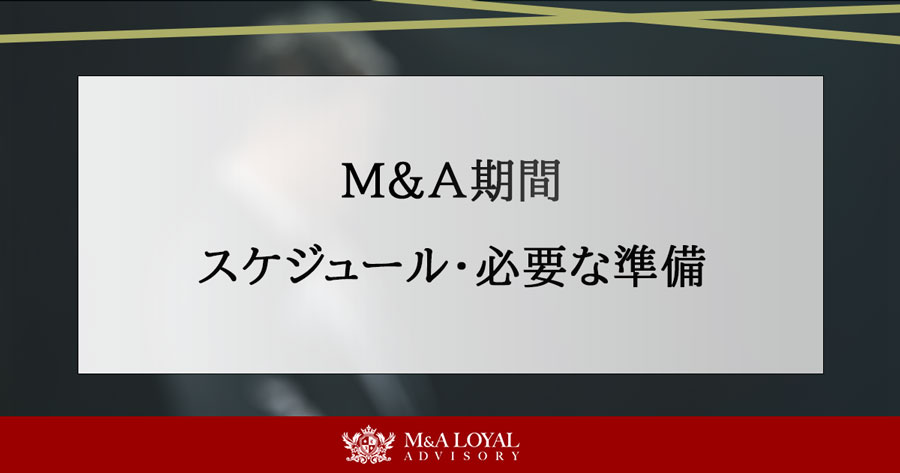
M&Aに必要な期間をご存じでしょうか。一般的にM&Aの期間は半年から1年程度とされていますが、案件の複雑さや交渉の進行状況によって大きく変動します。適切なスケジュール管理を行わないと、時間がかかりすぎて経営判断が迷走したり、思わぬトラブルが発生するリスクもあります。
本記事では、M&Aの各フェーズに必要な期間とスケジュール、スムーズに進めるための準備について詳しく解説いたします。
目次
M&Aに必要な期間と全体の流れ
M&Aにかかる期間は案件によって大きく異なりますが、一般的には半年から1年程度が標準的な期間とされています。早い場合は1ヶ月程度で完了することもありますが、複雑な案件では2〜3年かかることもあります。
M&Aの期間に影響を与える要因
M&Aの期間を正確に把握することは、成功への第一歩となります。適切な期間設定により、関係者全員が同じ認識で進めることができ、無駄な時間を削減できます。期間の見通しが立たないと、経営判断が遅れたり、従業員の不安が高まったりするリスクがあります。
M&Aの期間に影響を与える主な要因として、買収対象企業の規模、業界の特性、デューデリジェンスの複雑さ、交渉の難易度などが挙げられます。これらの要因を事前に把握し、適切なスケジュール管理を行うことが重要です。
全体の流れとタイムライン
M&Aは大きく5つのフェーズに分かれており、各フェーズには一定の期間が必要です。以下の表は、標準的なM&Aスケジュールの概要を示しています。
| フェーズ | 期間 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 事前準備〜買収相手の確定 | 1ヶ月目 | 目的設定、業界選定、仲介契約、候補選定 |
| 秘密保持契約〜基本合意契約 | 2ヶ月目 | NDA締結、トップ面談、意向表明、基本合意 |
| デューデリジェンス(監査) | 3ヶ月目 | 財務・法務・ビジネス調査 |
| 最終条件交渉〜クロージング | 4ヶ月目 | 契約書作成、最終契約、対価支払い |
| PMI(統合作業) | 5ヶ月目〜 | 業務・文化統合 |
この表は標準的なスケジュールを示していますが、実際の期間は案件の複雑さや交渉の進捗によって変動します。特に、買収相手の選定や条件交渉の段階で時間がかかることが多く、全体のスケジュールに大きな影響を与えることがあります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



事前準備から買収相手確定までの期間
M&Aの成功は適切な事前準備にかかっています。このフェーズでは、M&Aの目的を明確にし、買収戦略を策定し、適切な買収相手を見つけるまでの期間が含まれます。通常1~3ヶ月程度の期間が必要ですが、条件が厳しい場合は半年から1年以上かかることもあります。
目的・戦略立案に必要な期間
M&Aの目的と戦略を明確にすることは、全体のスケジュールに大きな影響を与える重要なプロセスです。シナジーの明確化、M&A予算の設定、その他の条件設定などを行います。同業他社の買収による事業拡大を目指すのか、多角化による新規事業参入を目指すのかによって、必要な期間や検討すべき要素が変わります。
この段階では、社内での合意形成も重要な要素となります。経営陣や主要株主との調整、取締役会での承認取得など、内部の意思決定プロセスにも十分な時間を確保する必要があります。
仲介会社選定とマッチング期間
M&A仲介会社やファイナンシャルアドバイザーとの契約締結から、実際の買収候補企業の選定までの期間です。中小企業の場合はM&A仲介会社、大手企業の場合はファイナンシャルアドバイザーを選ぶことが一般的です。
買収相手の探索では、設定した条件に合致する企業を見つける必要があります。条件が厳しすぎると、マッチする企業が見つからず、期間が大幅に延びる可能性があります。柔軟性を持った条件設定が、スムーズな進行のカギとなります。
買収スキーム策定の期間
買収スキームの策定は、M&Aの成功に直結する重要な要素です。主な選択肢として、株式取得による企業全体の買収、事業譲受による特定事業のみの取得、経営統合による合併などがあります。
各スキームにはメリット・デメリットがあり、税務面、法務面、事業面での影響を総合的に検討する必要があります。この検討には専門家のアドバイスが不可欠であり、適切なスキーム選択により後のプロセスをスムーズに進めることができます。
秘密保持契約(NDA)から基本合意までの期間
買収候補企業が決まった後、具体的な交渉に入る前に必要な各種契約の締結と、基本的な合意に至るまでの期間です。このフェーズでは、秘密保持契約の締結から始まり、トップ面談、意向表明、基本合意契約まで、通常1ヶ月程度の期間が必要となります。
秘密保持契約と情報開示の期間
秘密保持契約(NDA)の締結は、M&Aの期間における重要な第一歩となります。情報漏洩による従業員の離職や風評被害を防ぐため、双方の企業が注意すべき点を明確に定める必要があります。
NDA締結後は、ネームクリア(候補企業名の開示)、IM(企業概要書)の開示という流れで進みます。この段階では、M&Aの概要、期待されるメリット、買収後の経営方針などの情報を段階的に開示していきます。
トップ面談と意向表明の期間
トップ面談は、両社の経営者が直接会って交渉する重要な機会です。この面談では、シナジーの確認、雇用の継続、買収額の概算、今後の進め方などについて話し合います。経営者同士の相性や信頼関係の構築も、M&Aの成功に大きく影響します。
トップ面談の結果を受けて、買収意思と条件を明確にした意向表明書を提出します。この書類には、買収方法、買収価格、条件などが記載され、次の段階への移行の基準となります。
基本合意契約の締結期間
基本合意契約は、両社の意向が合致したことを明文化する重要な契約です。通常は法的拘束力を持たない条件付きの合意となりますが、M&Aを進める上での重要な節目となります。
基本合意契約では、買収価格の概算、買収スキーム、スケジュール、デューデリジェンスの実施方法などが定められます。この契約により、次のフェーズであるデューデリジェンスに進む準備が整います。
デューデリジェンス実施期間
デューデリジェンス(DD)は、買収対象企業の実態を詳細に調査する重要なプロセスです。通常1ヶ月程度の期間が必要ですが、企業の規模や複雑さによって期間は変動します。この段階では、買収リスクの洗い出しと買収額の精査が行われ、M&Aの成功に直結する重要な情報が収集されます。
財務デューデリジェンスの期間
財務デューデリジェンスは、対象企業の財務状況を正確に把握するために重要な調査です。公認会計士や税理士が中心となって、過去数年間の決算書、税務申告書、管理会計資料などを詳細に分析します。
この調査では、売上や利益の実態、資産・負債の正確性、税務リスクの有無、キャッシュフローの状況などが確認されます。隠れた債務や簿外負債の発見、利益の質の評価なども重要なポイントとなります。
法務デューデリジェンスの期間
法務デューデリジェンスでは、弁護士が中心となって、対象企業の法的リスクを調査します。重要な契約書の内容、労務関係の問題、株主構成、知的財産権、係争中の案件などが詳細に調べられます。
特に中小企業の場合、労務関係の問題や契約書の不備が見つかることが多く、これらの問題が買収価格や条件に大きな影響を与えることがあります。法務DDの結果は、最終的な買収判断の重要な材料となります。
ビジネスデューデリジェンスの期間
ビジネスデューデリジェンスは、経営コンサルタントが中心となって、対象企業の事業内容や経営状況を調査します。市場環境の分析、競合他社との比較、経営陣の評価、事業計画の妥当性などが検証されます。
この調査では、実際の事業所視察も行われ、現場の状況を直接確認します。従業員へのインタビューや業務プロセスの確認により、財務諸表だけでは分からない企業の実態を把握することができます。
最終条件交渉からクロージングまでの期間
デューデリジェンスの結果を受けて、最終的な買収条件を決定し、契約を締結するまでの期間です。通常1ヶ月程度の期間が必要ですが、交渉が難航した場合は数ヶ月かかることもあります。この段階では、法的拘束力のある最終契約の締結とクロージング手続きが行われます。
最終条件交渉の期間
最終条件交渉は、デューデリジェンスで発見された問題点を踏まえ、買収価格の調整、表明保証の内容、クロージング条件などについて詳細な交渉が行われます。
この段階では、双方の利害が対立し、交渉が長期化する可能性があります。特に、簿外債務の処理、従業員の雇用条件、経営陣の処遇などについて、慎重な検討が必要となります。
最終契約書の作成と締結期間
最終契約書は、M&Aの全ての条件を明確に定めた法的拘束力のある契約です。この契約書の作成には、弁護士による詳細な検討が必要であり、通常数週間の期間が必要となります。
契約書には、買収価格、支払い条件、表明保証、補償条項、クロージング条件などが詳細に記載されます。一度締結されると解除が困難になるため、内容については十分な検討が必要です。
クロージング手続きの期間
クロージングは、M&Aの最終段階であり、実際に対価の支払い、株式の移転、関連書類の引き渡しなどが行われます。また、社内外への正式発表も行われ、必要に応じて株主総会での承認も取得されます。
クロージング手続きには、通常1ヶ月以上の期間がかかります。この期間中に、銀行での送金手続き、法務局での登記手続き、従業員への説明などが並行して進められます。
PMI(統合作業)の期間
PMI(Post Merger Integration)は、M&Aの成功を左右する重要なフェーズです。クロージング後から本格的に開始され、通常半年から1年程度の期間が必要となります。この期間では、ハード面の統合とソフト面の統合を並行して進め、M&Aの効果を最大化することが目標となります。
ハード面統合の期間
ハード面の統合は、業務システムの統合を中心とした具体的な作業であり、通常半年程度の期間が必要です。経理システム、人事システム、ITシステムなどの統合が主な作業となり、実務部門との綿密な調整が求められます。
この作業では、以下のような統合が行われます。
- 会計システムの統合と会計基準の統一
- 人事制度の統合と給与システムの統一
- ITインフラの統合とセキュリティ対策
- 業務プロセスの標準化と効率化
- 報告体制の整備と管理体制の構築
ソフト面統合の期間
ソフト面の統合は、企業文化や従業員の意識の融合を目指すものであり、ハード面の統合よりも時間がかかることが一般的です。企業文化、価値観、職場の雰囲気などの調整が必要であり、経営者主導でPDCAサイクルを回しながら進めることが重要です。
ソフト面の統合では、従業員の不安解消とモチベーション向上が重要な課題となります。定期的な説明会の開催、人事交流の促進、新しい企業理念の浸透などを通じて、組織の一体感を醸成する必要があります。
統合効果の測定と改善期間
PMIの効果を測定し、必要に応じて改善を行うことも重要です。売上シナジー、コストシナジーの実現状況を定期的に検証し、計画との乖離がある場合は迅速に対策を講じる必要があります。
この期間では、統合後の業績評価、従業員満足度調査、顧客満足度調査などを通じて、M&Aの効果を定量的に測定します。問題が発見された場合は、速やかに改善計画を策定し、実行することが重要です。
M&A期間を短縮するための方法
M&Aの期間を短縮することは、コスト削減や機会損失の防止につながる重要な要素です。適切な準備と効率的な進行により、標準的な期間を短縮することが可能です。ここでは、実際にM&Aの期間を短縮するための具体的な方法について解説します。
事前準備の充実による期間短縮
M&Aの流れを事前にシミュレーションし、手続き全体を見通すことで、方向性のブレを防ぎ、期間を短縮することができます。事前に必要書類を準備し、社内の意思決定プロセスを明確にしておくことで、各段階での遅延を防ぐことができます。
事前準備では、以下の項目を重点的に検討することが重要です。
- M&Aの目的と期待効果の明確化
- 買収予算と資金調達方法の検討
- 社内の意思決定フローの整備
- 必要書類の事前準備
- 専門家チームの早期選定
交渉条件の柔軟性による期間短縮
交渉条件について、譲れる部分と譲れない部分を明確にし、柔軟な姿勢を示すことで交渉の長期化を回避できます。全ての条件で最大限の要求をするのではなく、優先順位を付けて交渉することが重要です。
条件交渉では、価格だけでなく、支払い条件、表明保証の内容、クロージング条件なども総合的に検討し、全体として最適な条件を目指すことが大切です。小さな条件にこだわりすぎると、全体のスケジュールに悪影響を与える可能性があります。
PMI対策の事前設計による期間短縮
PMI対策を事前に設計し、統合準備を並行して進めることで、統合スピードを大幅に向上させることができます。クロージング前から統合計画を策定し、必要なリソースを確保しておくことが重要です。
PMI対策の事前設計では、統合チームの編成、システム統合の計画、人事制度の統合方針、コミュニケーション計画などを詳細に検討します。また、統合に必要な外部専門家やシステムベンダーとの調整も、早期に開始することが効果的です。
まとめ
M&Aの期間は一般的に半年から1年程度が標準的ですが、事前準備の充実度や交渉の進行状況によって大きく変動します。各フェーズの期間と必要な準備を事前に理解し、適切なスケジュール管理を行うことで、スムーズなM&Aの実現が可能となります。
成功するM&Aのためには、専門家との連携、社内体制の整備、そして統合後のPMIまでを見据えた総合的な計画が不可欠です。期間短縮のためには、事前準備の充実、柔軟な交渉姿勢、そしてPMI対策の事前設計が重要なポイントとなります。
M&Aは複雑なプロセスですが、適切な準備と専門家のサポートにより、期待する成果を得ることができます。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様のM&Aを成功に導くための総合的なサポートを提供しています。M&Aや経営課題に関するお悩みはお気軽にお問合せください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。