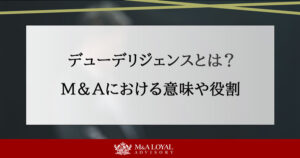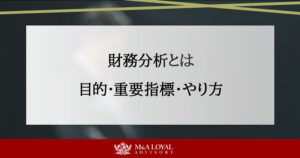財務DDとは?チェックリストから目的、費用相場までやり方を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
財務デューデリジェンス(財務DD)とは、M&Aの場面において対象企業の財務状況を詳細に調査し、潜在的なリスクを洗い出すことを指します。財務に関する問題を見落とすことは、取引の成否に大きく影響を与える可能性があるため、財務DDを実施することでリスクや不正を未然に防ぐことができます。
しかしながら、財務DDでは具体的にどのような調査が行われるのか、どのタイミングで実施するべきなのか、費用はどの程度かかるのかという点については、あまり詳しく知られていません。この記事では、財務DDとは何か、基本的な概要から目的、チェックリスト、さらに調査の流れや費用の相場に至るまでをわかりやすく解説します。これにより、安心してM&Aを進めることができるでしょう。
目次
財務デューデリジェンス(財務DD)とは?意味をわかりやすく解説
財務デューデリジェンス(財務DD)とは、デューデリジェンスの一種で、企業買収時の財務面の精査を指します。デューデリジェンスとは買収監査を意味し、M&Aにおいて取引後のリスクを最小限に抑えるためには対象企業の詳細な調査が欠かせません。ここでは、財務DDの具体的な意味や重要性についてわかりやすく解説します。
財務DDとは
財務DDとは、買い手が売り手企業の財務状況を詳しく調査することを指し、主に企業の買収や合併、新規投資の意思決定時に実施されます。デューデリジェンスは英語で「Due Diligence」と表記し、「適正評価」や「精査」を意味します。対象企業の価値や潜在的なリスクを詳細に分析・評価するプロセスはM&Aや投資において欠かせません。
デューデリジェンスには、財務DD以外にも、法務DD、税務DD、人事DDなど複数の種類があり、さまざまな角度から対象企業を調査してリスクを洗い出します。このプロセスを怠ると、取引後に予想外の問題が発覚し、買い手企業にとって大きな損失となる可能性があります。そのため、デューデリジェンスは慎重かつ徹底的に行うことが大切です。
| デューデリジェンスの種類 | 説明 |
|---|---|
| 財務DD | 財務状況の分析と評価 |
| 税務DD | 税務リスクの評価と最適化 |
| 法務DD | 法的リスクの確認と対応策 |
| 事業DD | 事業運営の効率性と将来性の評価 |
| 人事DD | 人材の質と組織の健全性の評価 |
| 環境DD | 環境への影響と持続可能性の評価 |
財務DDの重要性
財務DDは、買収や投資の意思決定を行う過程で非常に重要な役割を果たします。企業の財務状態を詳細に分析し、潜在的なリスクを特定することで、投資先の健全性を評価し、意思決定の質を向上させることができます。
まず、財務DDを通じて、企業の資産・負債の実態を明確にし、財務諸表の正確性を確認することができます。これにより、買収価格の妥当性を判断し、買収後の統合計画を立案する際の土台を築くことが可能になります。
さらに、財務DDは、隠れたリスクや不正の兆候を見逃さないための予防策としても機能します。企業の過去の財務履歴を精査することで、収益の持続可能性や将来のキャッシュフローの予測に重大な影響を与える要因を特定できます。これにより、投資に伴うリスクを最小限に抑え、より確実なリターンを期待できます。
また、財務DDは買収後のシナジー効果を最大化するための戦略策定にも寄与します。事前に財務状況を把握することで、どの分野で効率化やコスト削減が可能かを具体的に見極めることができます。特に、資本の効率的な再配分や、無駄なコストの削減といった施策を計画する上で、財務DDの結果は非常に役立ちます。
財務DDと税務DDの違い
デューデリジェンスにはいくつかの種類がありますが、混合されがちなのが財務DDと税務DDです。財務DDは主に、企業の財務状況や経営成績を分析し、企業価値の正確な評価を行うことを目的としています。これには、貸借対照表や損益計算書の精査、キャッシュフローの分析、過去の業績のトレンド分析などが含まれます。
一方、税務DDは企業の税務関連のリスクを調査することに重点を置き、対象企業の税務処理が適切に行われているかを調査・検証します。 具体的には、法人税や消費税、源泉所得税などの申告内容と実態の整合性を確認し、過去の税務申告の適性性や未払税金の有無、繰延税金資産の回収可能性といった論点を分析します。税務調査の指摘歴や、タックスプランニングの妥当性も評価対象です。これに加えて、税効果会計の評価や税務戦略の見直しなども含まれることがあります。
このように、財務DDは企業の全体的な財務の健全性を評価するのに対し、税務DDは税務面での潜在的なリスクや負担を明らかにすることを目的としています。ただし、財務DDと税務DDは内容に被る部分があり、財務DDに税務DDが内包されている場合もあります。両者は補完的な関係にあり、どちらもM&Aにおいて欠かせないプロセスです。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



財務DDを行う目的
財務デューデリジェンスは主にM&Aの場面で実施されます。財務DDを行う目的は次のとおりです。
- 財務リスクの把握と回避
- 適切な企業価値の算定
- 事業計画の策定と統合準備
それぞれの目的について解説します。
財務リスクの把握と回避
財務DDの最大の目的は、対象企業に内在する財務リスクを事前に把握し、取引後のトラブルを未然に防ぐことです。財務DDでは、対象企業の財務状況について、簿外債務や偶発債務、不正会計、粉飾決算の兆候を含むリスクを確認します。また、課税逃れや納税漏れなどの税務リスクも検証対象となります。
さらに、収益性やキャッシュフローの安定性、資産の適正価値、負債構造、取引先リスクなど、多角的な観点から調査を行うことで、対象企業の財務の健全性を総合的に把握します。これらのリスクが買収後に顕在化すれば、想定外の損失や訴訟問題に発展する可能性があるため、早期の発見と対策が不可欠です。
適切な企業価値の算定
財務DDは、対象企業の財務情報を基に、企業価値を適切に評価するために実施されます。財務の実態に即した適正なバリュエーション(企業価値評価)は、M&Aの買収価格や出資額の妥当性を判断する材料になります。
特に非上場企業では公開情報が限られるため、財務DDによる独自の評価が意思決定において極めて重要な役割を果たします。
事業計画の策定と統合準備
財務DDによって得られる情報は、買収後の意思決定やPMI(統合準備)を進める際の判断材料としても活用されます。 例えば、正常収益力の把握により将来の収益予測が可能となり、過去の設備投資や運転資本の構造を分析することで、今後必要となる資金計画や投資配分を具体化できます。
また、部門別の収益性やコスト構造も明らかになるため、買収後のシナジー効果を見込んだ経営戦略の策定や、統合スケジュールの設計に大きく貢献します。
財務DDの流れ|実施手順とプロセス
財務デューデリジェンス(財務DD)の一連の流れは次のとおりです。
- 専門家への依頼と秘密保持契約(NDA)の締結
- 調査対象資料のリストアップと開示依頼
- 資料の分析とヒアリングの実施
- リスクの特定と報告書の作成
- 買収条件への反映と意思決定
それぞれの手順を解説します。
1.専門家への依頼と秘密保持契約(NDA)の締結
財務DDの実施にあたっては、まず公認会計士や税理士、M&Aアドバイザーなど、財務・会計の専門知識と実務経験を持つ外部専門家への依頼が一般的です。また、財務DDを開始する前提として、まず買い手と売り手の間で秘密保持契約(NDA)を締結します。これは、財務諸表や税務申告書、契約書といった機密情報が外部に漏えいすることを防ぐための法的措置です。
NDAを結ぶことで、情報の取り扱いや調査の前提条件に関する双方の合意形成がなされ、財務デューデリジェンスを円滑に進めることができます。
2.調査対象資料のリストアップと開示依頼
NDAの締結後、M&Aアドバイザーは財務DDに必要な資料を整理・リストアップし、売り手に対して正式に開示を依頼します。 提出が求められる主な資料は、過去数期分の財務諸表や税務申告書、月次試算表、売掛金・在庫の明細、借入契約書、リース契約書などです。
これらの資料は企業の実態や財務リスクを把握する上で極めて重要な根拠であるため、正確かつ網羅的な情報開示が求められます。
3.資料の分析とヒアリングの実施
売り手から開示された資料を基に、公認会計士や財務アドバイザーが本格的な分析作業を行います。 財務諸表の整合性や収益・費用の傾向を確認するだけでなく、不自然な数値や説明のつかない取引が見つかった場合には、追加資料の提出を求めることがあります。
さらに、関係者へのヒアリングを通じて、その背景や根拠を詳しく確認していきます。ヒアリングの対象は、経理担当者にとどまらず、必要に応じて経営陣にも及びます。 また、在庫の実在性や資産の稼働状況を把握するために、現地訪問による棚卸資産や固定資産の実査が行われることもあります。
これらのプロセスを通じて、表面的な財務数値だけでは見えない、企業の実態を深く掘り下げていきます。
4.リスクの特定と報告書の作成
財務DDの結果は、「財務デューデリジェンス報告書」として取りまとめられ、財務上のリスクや重要な論点が整理されます。 この報告書により、財務状況の全体像とリスクの深刻度が可視化され、経営陣による買収判断や、価格交渉・契約条件の調整などに活用されます。
報告書の内容次第では、追加調査や条件変更の必要性が生じる場合もあり、M&Aの成否を左右する重要な成果物といえます。
5.買収条件への反映と意思決定
財務DDの結果を受けて、買い手は売り手の企業価値の再評価を行い、買収価格や契約条件の見直しを検討します。
調査によって重大なリスクが判明した場合には、最終的に取引自体を中止する判断に至る可能性もあります。 財務デューデリジェンスは、M&Aの成否を左右する極めて重要なプロセスであり、取引の実行に向けた最終的な意思決定を支える根拠として機能します。
財務DDのチェックリストと確認項目
財務デューデリジェンス(財務DD)で実際に確認されるチェックリスト項目や資料は次のとおりです。
- 財務諸表
- 売掛金・受取手形
- 棚卸資産
- 有形固定資産
- 事業外資産
- 買掛金・支払手形
- 借入金
- その他負債(簿外債務)
それぞれを詳しく解説します。
財務諸表
財務DDでは、対象企業の財務諸表が経営実態を正確に反映しているかどうかが確認されます。使用される主な資料は、直近2〜5期分の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書です。これらを通じて、業績の推移や財務構造の変化が把握されます。
また、月次あるいは四半期の試算表と年次財務諸表との間に大きな乖離(かいり)がないか、整合性が保たれているかも評価の対象です。
財務諸表上には、適用されている会計方針や会計基準が記載されており、それが適切かつ継続的に運用されているかが確認されます。加えて、売り上げの前倒し計上や費用の繰延といった特異な会計処理の有無も、財務諸表の記載内容から読み取られるべき重要な論点とされています。
売掛金・受取手形
売掛金および受取手形は、対象企業の資産の健全性や資金回収能力を評価する上で欠かせない項目です。 これらの債権に関しては、残高の推移と売り上げとの整合性を通じて、売上計上の妥当性や債権管理の実態が確認されます。
得意先別の回収サイトや回転期間を確認することで、滞留債権や長期の未回収債権の有無が把握可能です。回収期間が他社平均に比べて著しく長い場合や、特定の得意先への債権集中が見られる場合は、将来的な貸倒リスクが示唆されます。
また、過去の貸倒実績や、貸倒引当金の計上状況も財務資料に明示されており、債権の評価が実態を反映しているかどうかを判断する上で重要な手がかりです。これらの情報から、帳簿上の資産が実際にどの程度回収可能であるかが明らかになります。
棚卸資産
棚卸資産は、在庫の適正性や資産性を評価するための重要な項目とされ、財務DDにおいて重点的に確認されます。資料には在庫の種類や評価方法(先入先出法、総平均法など)が明記されており、会計方針が実態に即しているかどうかの判断材料として用いられます。
また、棚卸資産の月次残高の推移や回転期間のデータからは、過剰在庫や滞留在庫の有無、在庫管理の効率性が読み取れます。長期間動きのない在庫が存在している場合は、評価減の対象となる可能性があり、資産性の見直しが求められます。
さらに、在庫の年齢表や実地棚卸の実施状況を通じて、帳簿残高と現物との整合性も確認されます。棚卸資産は資金を多く拘束する性質を持つため、過大な在庫水準が見られる場合には、資金効率やキャッシュフローへの影響も含めた総合的な評価が必要です。
有形固定資産
有形固定資産は、過去の設備投資の実績や減価償却の妥当性を把握し、将来の資本的支出を見通す上で重要な資料のひとつです。
固定資産台帳などの資料には、資産ごとの取得時期や耐用年数、償却累計額が記載されており、それらの情報から適正な減価償却が実施されているかどうかが判断されます。償却が不十分な場合、帳簿上の利益が実態より過大に計上されている可能性があるため、注意が必要です。
また、稼働していない遊休資産や、著しく老朽化した設備が計上されている場合には、資産性の見直しや今後の廃棄予定に関する情報も含めて評価の対象です。設備の更新計画や新たな投資予定の有無は、関連資料や補足情報を通じて把握され、M&A後に発生し得るキャッシュアウトリスクとして整理されます。
事業外資産
事業外資産は、本業の収益獲得に直接関与しない資産であり、財務DDにおいては事業価値から切り離して評価される対象とされています。遊休不動産、余剰な現預金、投資有価証券、役員の私的利用が想定される資産などが該当し、財務諸表上では他の資産項目と混在して計上されているケースが多く見られます。
これらの資産は企業の本来的な事業価値には寄与しないため、別途評価され、買収価格の調整対象として取り扱われることが一般的です。なお、事業外資産の評価には市場価格や公正価値が用いられ、売却後の税務リスクも考慮される必要があります。
事業外資産の保有が多い場合には、時価評価の実施とともに、買収スキームや資金計画への反映が求められます。財務資料上に明示されていない場合でも、経営者の個人的な事情により保有されているケースがあるため、補足資料や関連情報を通じて資産の性質を明確にする必要があります。
買掛金・支払手形
買掛金および支払手形は、対象企業の債務管理状況や資金繰りの実態を把握する上で重要な分析対象です。 財務資料には支払サイトや債務残高の推移が記載されており、これらの数値から債務水準の妥当性やキャッシュフローへの影響度が読み取れます。
仕入先別の支払条件や月次ベースの債務残高の増減推移に着目することで、支払遅延のリスクや不自然な債務増減の兆候を検出できます。 支払条件の変更履歴や債権者との交渉経緯なども関連資料に含まれている場合があり、今後の資金負担や取引条件の見通しを立てる上での判断材料です。
借入金
借入金に関する資料は、資金調達の構造や財務リスクの評価に直結する重要な情報源です。
契約書類や借入金一覧表には、金融機関ごとの借入残高や金利、返済条件、担保設定の有無といった基本情報が記載されています。これらの情報を基に、元本返済スケジュールや利払い負担を明確にします。併せて、借り入れに付随する財務制限条項(コベナンツ)が設定されている場合は、その具体的な内容および順守状況の確認が必要です。
資料上で財務指標の悪化がコベナンツ違反に直結する可能性が示唆される場合には、追加の資金調達制限や契約解除といったリスクも想定されます。さらに、金融機関との取引履歴や借換え実績などの情報からは、将来的な資金調達の柔軟性や、買収後の財務運営への影響度を評価する上での判断材料が得られます。
その他負債(簿外債務)
財務DDでは、財務諸表に計上されていない負債や、将来的に発生する可能性のある偶発債務についても確認が行われます。
代表的な対象としては、役員退職慰労金、債務保証、訴訟・損害賠償に関するリスク、未記載のリース契約などがあります。これらの情報は契約書や覚書、社内資料などに記載されているケースが多く見られます。これらの負債は表面上の財務数値には反映されないものの、M&A後に実際の支払義務が発生する可能性があるため、買収価格の調整項目として極めて重要です。
資料に記載された支払い根拠や金額の算定基準を基に、妥当性の評価や、必要に応じた引当金の追加計上も検討されます。訴訟案件に関する資料では、係争中の事案の内容、争点、請求金額などが確認され、これらの情報は買収判断への影響を見極めるための重要な評価材料です。
財務DDにかかる費用の相場と目安
財務デューデリジェンス(財務DD)の実施には、一定の調査費用が発生します。 財務DDは公認会計士に依頼することが一般的で、1時間あたり2万~5万円の作業単価×作業時間で計算されることが多いです。費用の水準は、対象企業の規模や業種、調査範囲、依頼先の専門家(監査法人、FAS系コンサル、会計事務所など)によって異なりますが、中小企業のM&Aでは100万〜500万円程度となるケースが多く、上場企業や大規模案件では500万円を超えるケースもあります。
費用には、資料分析・ヒアリング・現地調査・報告書作成などにかかる工数が含まれています。さらに、税務・法務・人事など他分野のデューデリジェンスも同時に行う場合は、その分の費用も必要となるため総額がさらに高額になる点に留意しましょう。
調査コストを適正に管理するためには、調査項目に優先順位を設け、リスクが高い領域に絞って実施することが推奨されます。
財務DDを行う際の買い手のポイントと注意点
財務デューデリジェンス(財務DD)を実施する際に意識する点は次のとおりです。
- 情報漏えい対策を徹底する
- 調査時期に注意する
- 専門家と連携する
それぞれの項目について解説します。
情報漏えい対策を徹底する
財務DDでは、対象企業の経営実態や財務状況に関する機密性の高い情報を数多く取り扱います。そのため、情報漏えいを防ぐための管理体制が極めて重要です。 調査開始前には、秘密保持契約(NDA)を締結し、調査関係者の範囲や情報の取扱ルールを明確に定めましょう。加えて、アクセス権限の制御やデータの保存・送信方法の厳格化、閲覧履歴の管理など、運用面での対策も講じなければなりません。
仮に情報が外部に流出すれば、契約の破棄や損害賠償といった重大なリスクを招く可能性があるため、組織全体で慎重かつ厳格な対応が重要です。
調査時期に注意する
財務DDを実施する際には、調査時期の選択も大切です。特に、売り手の繁忙期を避けることが望ましいでしょう。繁忙期に調査を行うと、対象企業の担当者が他の業務で手一杯になっている可能性が高く、必要な情報やデータの提供が遅れる、または不完全になりがちです。これにより、調査の効率が悪化し、結果としてプロジェクト全体のスケジュールが遅れるリスクがあります。
調査時期の選定にあたっては、企業の業種や特性を考慮に入れることも不可欠です。例えば、製造業では年度末が繁忙期になることが多いですが、小売業では年末年始が特に忙しい時期となることがあります。これらの業種特有の繁忙期を理解し、適切な時期に調査を実施することで、より効率的で成果の高い財務DDを実現することが可能になります。
専門家と連携する
財務DDを成功させるためには、専門家との連携が非常に重要です。財務DDは多岐にわたる複雑な分析を必要とするため、財務、法務、税務などの各分野の専門家と協力することで、より正確で詳細な評価を行うことが可能となります。例えば、会計士や税理士は財務諸表の分析や税務に関するリスクの評価を行い、弁護士は契約書や法的リスクの検討を行います。これにより、買収対象企業の潜在的な問題やリスクを事前に発見することができ、買収後の不測の事態を未然に防ぐ助けとなります。
また、専門家との連携は、買収交渉の際にも強力なサポートとなります。専門家の意見を基にした交渉戦略を立てることで、買収価格や契約条件の交渉を有利に進めることができます。さらに、企業の文化やビジョンに合った専門家を選ぶことで、スムーズなコミュニケーションが可能となり、プロジェクト全体の進行を円滑にします。
財務DDを受ける際の売り手のポイントと注意点
財務デューデリジェンス(財務DD)を受ける際のポイントや注意点は次のとおりです。
- 調査に備えた体制を整える
- 提出資料は網羅的かつ正確に整備する
- 誠実で透明性のある対応を心がける
それぞれの項目について解説します。
調査に備えた体制を整える
財務DDを受ける際には、事前に社内での対応体制を整えておくことが重要です。特に経理・財務部門は資料提出やヒアリング対応の中心となるため、専任の窓口担当を置き、関係部署との連携が取りやすい体制を構築しておく必要があります。
また、経営陣は調査の概要や目的を把握し、必要に応じて説明できる準備をしておきましょう。調査中に情報の行き違いや確認作業で混乱が生じることを防ぐために、あらかじめ社内の役割分担やスケジュール管理を明確にし、円滑な対応ができる体制を整えておくことが大切です。
提出資料は網羅的かつ正確に整備する
財務DDでは、財務諸表や月次試算表、借入明細、売掛・買掛金管理表、在庫リスト、固定資産台帳、契約書類など、多岐にわたる資料の提出が求められます。調査を円滑に進めるためには、これらの資料を事前に最新版でそろえ、数値の整合性や記載内容の正確性を確認しておくことが重要です。
数字の不一致や説明の不備があると、追加の調査を招くだけでなく、買い手側に不信感を与え、交渉全体に悪影響を及ぼす可能性があります。資料は可能な限り体系的に整理し、問い合わせに対して迅速に対応できる体制を整備しておくことで、調査はスムーズに進行します。
誠実で透明性のある対応を心がける
財務DDの対応において、リスクや問題点を意図的に隠すことは、後々大きな信頼の失墜につながる恐れがあります。多少の課題がある場合でも、それを正直に開示し、その背景や今後の対応方針を明確に説明することが重要です。
透明性のある対応は、買い手に「信頼できる相手」という印象を与え、結果として取引条件の柔軟性や交渉の円滑化に良い影響をもたらします。不都合な情報であっても誠実に説明する姿勢こそが、合意に至る上で欠かせない姿勢といえます。
財務DDに関するQ&A
財務デューデリジェンス(財務DD)に関するよくある質問とその回答を紹介します。
財務DDは必ず実施すべきか
財務DDは法的に義務付けられているわけではありません。しかし、M&Aや出資における意思決定においては、極めて重要なプロセスとされています。特に非上場企業の場合、公的な開示資料が限られているため、財務内容や潜在的なリスクを第三者が独自に確認する手段として、財務DDの実施が強く推奨されます。
実施を省略した場合、簿外債務や粉飾決算などの重大な問題を見落とし、取引後に深刻なトラブルへ発展する可能性もあります。取引規模や対象企業の状況に応じて、調査範囲や深度を柔軟に設計しつつも、原則として実施を前提に検討すべきです。
財務DDにかかる時間や期間はどのくらいか
財務DDの実施期間は、一般的に2週間〜2か月程度が目安です。ただし、実際の所要期間は、対象企業の規模や業種、開示資料の準備状況、調査の深度によって大きく左右されます。例えば、資料の開示が滞る場合や関係者とのヒアリング日程が調整困難な場合には、さらに時間を要することもあります。
財務DDを行うタイミングはいつか
財務DDは、M&Aプロセスの中で基本合意締結後から最終契約締結までの期間に実施されることが一般的です。具体的には、意向表明書(LOI)や基本合意書(MOU)が交わされ、取引の大枠が合意された段階で、買い手が売り手のリスク評価や価格妥当性の確認を目的に着手します。
このタイミングであれば、取引条件の方向性がある程度固まっている一方で、まだ契約義務が発生していません。そのため、万一重大なリスクが判明した場合でも、条件の見直しや取引中止といった柔軟な対応が可能です。
財務DDの結果でM&Aが中止になることはあるか
財務DDの結果によって、M&Aが中止に至るケースも存在します。簿外債務や偶発債務の存在、不適切な会計処理、粉飾決算の兆候、過剰な借り入れ、著しい収益性の悪化などが確認された場合です。
こうした問題が判明し、当初の想定と大きく乖離(かいり)していると判断された場合には、買い手は取引リスクを回避するため、M&Aの中止を決断することがあります。
財務DDを簡易的に済ませる方法はあるか
取引規模が小さい場合や、事前に十分な情報収集がなされている場合には、フルスコープ(詳細型)デューデリジェンスではなく、限定的またはライト(簡易型)デューデリジェンスで対応できます。例えば、主要な財務指標やリスク項目に絞ったレビューや、税務・法務デューデリジェンスと連携して最低限のポイントに限定した確認を行う形式などが挙げられます。
ただし、調査範囲を狭めることで見逃すリスクもあるため、省略する項目と残す項目の取捨選択は、経験豊富な専門家と相談の上で慎重に判断する必要があります。
まとめ
財務デューデリジェンス(財務DD)は、企業買収や合併における重要なプロセスであり、企業の財務状況を詳しく分析することで、潜在的なリスクや課題を特定し、買収後の不測の事態を防ぐための役割を果たします。このプロセスを通じて、投資判断の根拠を強化し、適切な意思決定を行うための重要な情報を取得することが可能です。
本記事を通じて、財務DDの基本的な知識からその具体的な流れ、費用、注意点について理解を深めていただけたかと思います。M&Aや経営課題に関するご相談がございましたら、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーまでお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。