減価償却の定率法とは?計算式や償却率、定額法との違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
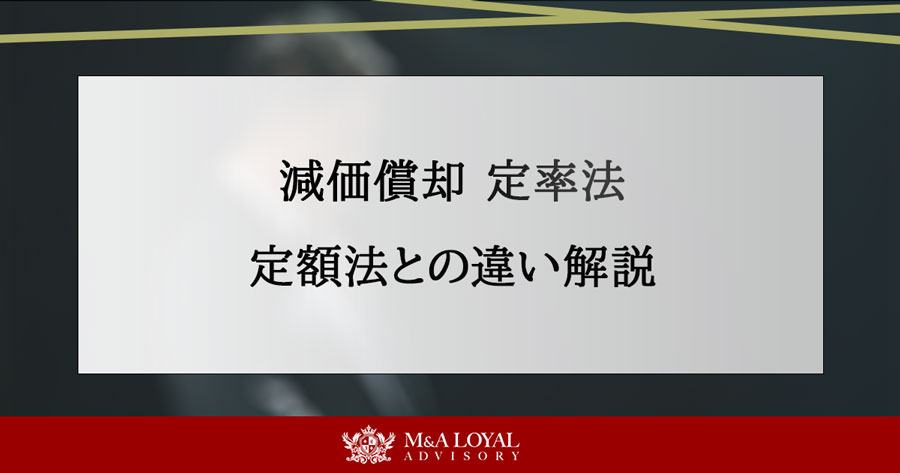
中小企業の経営者や経理担当者の皆様は、減価償却の計算方法について悩んだことはありませんか?特に定率法は、その複雑な仕組みから敬遠されがちですが、実は大きなメリットを持つ償却方法です。
減価償却の定率法は、資産の未償却残高に一定の償却率を乗じて計算する方法で、2012年4月以降は「200%定率法」が適用されています。この方法を選択することで、設備投資の初期段階で多額の費用計上が可能となり、税務上の優遇を受けられます。
本記事では、定率法の基本的な仕組みから具体的な計算方法、定額法との比較、そしてM&Aを視野に入れた戦略的な活用方法まで、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。償却保証額や改定償却率といった専門用語も分かりやすく説明し、計算ミスを防ぐポイントもお伝えします。 本記事を通じて、定率法を味方につけ、強固な財務基盤を構築していきましょう。
目次
減価償却の定率法における基本知識
減価償却の定率法は、中小企業の財務戦略において重要な役割を果たす計算方法です。設備投資を行った初期段階で多額の費用計上が可能となるため、資金繰りの改善や節税効果を期待できます。特にM&Aを視野に入れた経営を行う中小企業にとって、定率法の仕組みを正しく理解することは、企業価値の最適化につながる重要な要素となります。
減価償却の定率法の仕組みと計算の基本原理
定率法とは、固定資産の未償却残高に一定の償却率を乗じて減価償却費を計算する方法です。2012年4月1日以降に取得した資産には「200%定率法」が適用されます。これは、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2倍するという考え方に基づきつつも、実務上は国税庁が耐用年数ごとに定めた「減価償却資産の償却率等表」の率を必ず使用する必要があります。
定率法の基本的な計算式は「期首未償却残高×定率法償却率」となります。未償却残高は年々減少していくため、減価償却費も徐々に少なくなっていく特徴があります。ただし、減価償却費が償却保証額を下回った場合は、改定償却率を用いた計算に切り替わる仕組みとなっています。
例えば、100万円の機械装置(耐用年数5年)を購入した場合、定率法償却率は0.400(定額法の0.200の2倍)となり、初年度は40万円の減価償却費を計上できます。この金額は定額法の20万円と比較して2倍となり、初期の費用計上額が大きくなることがわかります。
中小企業における活用のメリット
中小企業が定率法を活用する最大のメリットは、税金の支払いを将来に繰り延べることによる早期のキャッシュフロー改善効果です。耐用年数全体で支払う税額の総額は変わりませんが、投資初期の税負担を軽減できます。設備投資を行った初年度から数年間は、定額法と比較して多額の減価償却費を計上できるため、課税所得を圧縮し、法人税の負担を軽減できます。
・初期投資回収の加速:投資初期に多額の費用計上により、実質的な投資回収が早まる
・資金繰りの改善:節税により手元資金が増加し、次の投資機会に備えられる
・設備更新の促進:早期償却により、技術革新に対応した設備更新が容易になる
また、定率法は実際の資産価値の減少パターンに近いという利点もあります。新品の機械設備は使い始めの数年間で急速に価値が下がることが多く、定率法はこの実態を会計上でも反映できます。中小企業の経営者にとって、実態に即した財務諸表の作成は、経営判断の精度向上にもつながります。
M&A時に定率法が企業価値に与える影響
M&Aにおいて、減価償却方法の選択は企業価値評価に大きな影響を与えます。定率法を採用している企業は、初期に多額の減価償却費を計上しているため、簿価純資産は定額法採用企業より低くなる傾向があります。しかし、これは必ずしも企業価値が低いことを意味しません。
買い手企業の視点では、定率法採用企業は既に多くの減価償却を済ませているため、買収後の減価償却負担が軽くなるメリットがあります。一方、売り手企業にとっては、EBITDAベースでの評価を求めることで、減価償却方法の違いによる影響を排除した適正な企業価値評価を受けることができます。
M&Aのデューデリジェンスでは、減価償却方法の妥当性や将来の設備投資計画も重要な検討項目となります。定率法を採用している場合、その選択理由と今後の償却スケジュールを明確に説明できることが、買い手の信頼を得るポイントとなります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



減価償却における定率法と定額法の違いを徹底比較
減価償却の方法として代表的な定率法と定額法は、それぞれ異なる特徴を持ち、企業の財務戦略に大きな影響を与えます。中小企業がM&Aを視野に入れた経営を行う場合、両者の違いを正確に理解し、自社の状況に応じた最適な選択をすることが重要です。ここでは、実務的な観点から両者の違いを詳しく比較していきます。
償却費の推移が資金繰りに与える影響
定率法と定額法の最も大きな違いは、償却費の推移パターンにあります。定率法では初年度に多額の償却費を計上し、その後年々減少していきます。一方、定額法では耐用年数にわたって毎年同額の償却費を計上します。
例えば、500万円の製造設備(耐用年数10年)を導入した場合、定額法では毎年50万円の償却費となりますが、定率法(償却率0.200)では初年度100万円、2年目80万円と、初期に多額の費用を計上できます。この違いが資金繰りに与える影響は次のとおりです。
定率法を選択した場合、初期の税負担が軽減されるため、投資直後の資金繰りが改善します。特に設備投資に多額の資金を投じた直後は、運転資金の確保が課題となることが多いため、この効果は中小企業にとって大きなメリットとなります。
一方で、償却費が年々減少することから、将来的には税負担が増加し、資金繰りへの圧迫要因となる可能性があります。このため、定率法を選択する企業は、将来の収益計画と資金計画を慎重に立てる必要があります。
節税効果の違いと適切な選択基準
定率法と定額法の節税効果の違いは、主に課税の繰り延べ効果として現れます。定率法は初期に多額の費用を計上できるため、早期の節税効果が高くなります。
- 定率法の節税メリット: 初期数年間(通常は3-5年)の税負担を大幅に軽減できる
- 定額法の特徴: 安定的な費用計上により、利益計画が立てやすい
- 選択のポイント: 事業の成長段階と将来の収益見通しを考慮
適切な選択基準として、以下の要素を検討することが重要です。まず、事業が成長期にある企業や、設備投資直後で資金需要が高い企業は定率法が有利です。初期の節税効果により、成長投資に回せる資金を確保できるためです。
一方、安定期に入った企業や、毎期の利益を平準化したい企業には定額法が適しています。また、金融機関からの評価を重視する場合も、利益の安定性を示せる定額法が有利になることがあります。
M&Aを見据えた償却方法の選び方
M&Aを将来的に検討している中小企業にとって、減価償却方法の選択は戦略的な意思決定となります。買い手・売り手双方の視点から、それぞれの方法がもたらす影響を理解することが重要です。
売り手企業の立場では、定率法を採用している場合、簿価純資産が低くなりがちです。簿価純資産とは、企業の資産から負債を差し引いたもので、企業の実質的な価値を示します。この影響を軽減するためには、EBITDA(利払い・税・減価償却前利益)を基準にした評価を求めることが有効です。さらに、定率法によって早期に償却を進めていることは、設備の実態価値を適切に反映している証拠とも言え、買い手に好印象を与える可能性があります。
買い手企業の視点では、対象企業が採用している償却方法によって、買収後のキャッシュフローが大きく変わることを認識する必要があります。具体的には、定率法を採用している企業を買収した場合、既に多くの減価償却が済んでいるため、買収後の減価償却費の負担が軽減されます。これにより、買収後の統合効果を早期に実現することができ、資金繰りの改善にもつながります。
M&Aの準備段階では、償却方法の変更も検討事項となりますが、安易な変更は避けるべきです。継続性の原則(過去の会計処理を尊重する原則)から逸脱した変更は、かえって買い手の不信を招く可能性があるためです。重要なのは、選択した償却方法の合理性を明確に説明できることです。たとえば、なぜ定率法を選択したのか、その利点について具体的なデータや事例を用いて説明することで、信頼性を高めることができます。
減価償却の定率法による具体的な計算方法と実務ポイント
定率法による減価償却計算は、償却率・改定償却率・保証率という3つの要素を正しく理解し、適切に運用することが重要です。中小企業の経理担当者にとって、これらの仕組みは複雑に感じられるかもしれませんが、基本的な考え方を押さえれば確実に計算できるようになります。ここでは、実務で必要となる具体的な計算方法と、ミスを防ぐためのチェックポイントを詳しく解説します。
償却率・改定償却率・保証率の正しい使い方
定率法で使用する3つの率は、それぞれ異なる役割を持っています。償却率は通常の減価償却計算で使用する基本的な率で、200%定率法では定額法の償却率の2倍に設定されています。改定償却率は、償却保証額を下回った後に使用する率で、残りの期間で均等償却するための率です。保証率は、償却保証額を算出するための率で、最低限の償却額を確保する役割があります。
具体例として、耐用年数5年の機械装置(取得価額300万円)の場合を見てみましょう。償却率は0.400、改定償却率は0.500、保証率は0.10800となります。まず償却保証額を計算すると、300万円×0.10800=32万4,000円となります。
・1年目:300万円×0.400=120万円(償却保証額を上回るため、そのまま計上)
・2年目:180万円×0.400=72万円(償却保証額を上回るため、そのまま計上)
・3年目:108万円×0.400=43万2,000円(償却保証額を上回るため、そのまま計上)
このように、各年度で償却保証額との比較を行いながら計算を進めていきます。
償却保証額を下回った場合の処理方法
償却保証額を下回った場合の処理は、定率法の計算で最も注意が必要な部分です。通常の計算で減価償却費が償却保証額を下回った年度から、改定償却率を使用した計算に切り替わります。重要なのは、改定取得価額として、償却保証額を下回った年度の期首未償却残高を使用する点です。
先ほどの例の続きを見てみましょう。4年目の計算では、期首未償却残高64万8,000円に償却率0.400を乗じた25万9,200円が、償却保証額32万4,000円を初めて下回ります。この4年目から計算方法が切り替わります。
4年目の減価償却費は、4年目の期首未償却残高(改定取得価額)648,000円に、改定償却率0.500を乗じて計算します。
4年目の減価償却費:648,000円 × 0.500 = 324,000円
5年目も同様に、固定された改定取得価額648,000円に改定償却率0.500を乗じて計算し、最後に備忘価額1円を残す調整をします。
5年目の減価償却費:324,000円 – 1円 = 323,999円
5年目は備忘価額1円を残すため、32万3,999円となります。改定償却率を使用した後は、実質的に定額法と同じ計算になることがポイントです。
減価償却の定率法の計算ミスを防ぐためのわかりやすいポイント
定率法の計算でよくあるミスを防ぐために、以下のチェックポイントを確認することが重要です。まず、償却率の適用年度を間違えないことです。2012年4月1日以降取得分は200%定率法、それ以前は250%定率法となるため、取得時期の確認が必須です。
次に、償却保証額との比較を毎年必ず行うことです。エクセル等で計算する際は、IF関数を使って自動判定する仕組みを作ると効果的です。また、改定取得価額の固定を忘れないことも重要です。改定償却率を使用する際は、最初に下回った年の期首残高で固定し、それ以降は変更しません。
・取得時期と適用される償却率の確認
・償却保証額の正確な計算と毎年の比較
・改定取得価額の固定と正しい適用
・最終年度の備忘価額1円の処理(資産が除却されずに現存していることを示すため、帳簿価額として1円を残す必要があります)
年度途中取得や中古資産購入時の特殊な計算方法
年度途中で資産を取得した場合、初年度の減価償却費は月割計算が必要です。計算式は「取得価額×償却率×使用月数÷12」となります。例えば、9月に600万円の設備(耐用年数6年、償却率0.333)を取得した場合、初年度は600万円×0.333×4÷12=66万6,000円となります。
中古資産の場合は、簡便法を用いて耐用年数を見積もることができます。法定耐用年数を既に経過している場合は、法定耐用年数の20%を使用します。一部経過している場合は「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で計算します。計算結果が2年未満の場合は2年とし、1年未満の端数は切り捨てます。
例えば、法定耐用年数10年の機械を5年経過後に取得した場合、(10年-5年)+5年×20%=6年となります。この場合、耐用年数6年に対応する償却率を使用して計算を行います。中古資産の取得は節税効果が高いため、M&A実務でも重要な検討事項となります。
ただし、この簡便法には重要な例外規定があります。中古資産を取得して事業に使うために支出した資本的支出の金額が、その資産の再取得価額(同じ新品を取得する場合の価額)の50%を超える場合は、簡便法は適用できず、法定耐用年数で償却しなければなりません。
M&A実務における減価償却の定率法に関する注意点
M&A実務において、減価償却方法の違いは企業価値評価や買収後の統合計画に大きな影響を与えます。特に定率法を採用している中小企業の場合、その特性を正しく理解し、デューデリジェンスで適切に評価することが重要です。ここでは、M&Aの各段階で注意すべき定率法に関するポイントを、実務的な観点から解説します。
デューデリジェンスで減価償却の妥当性を検証する
デューデリジェンスにおける減価償却の検証は、単に計算の正確性を確認するだけでなく、経営判断の妥当性を評価する重要なプロセスです。定率法を採用している企業の場合、以下の観点から詳細な検証が必要です。
まず、償却方法の選択理由と継続性を確認します。定率法を選択した背景には、節税目的だけでなく、資産の実態に即した償却を行うという経営判断があるはずです。この選択が事業の特性に合致しているか、過去から一貫して適用されているかを検証します。
次に、償却計算の正確性と税務リスクを評価します。特に償却保証額を下回った後の改定償却率の適用や、年度途中取得資産の月割計算など、複雑な処理が正しく行われているかを確認します。計算ミスは将来の税務調査リスクにもつながるため、慎重な検証が必要です。
・過去3-5年間の固定資産台帳と減価償却明細の照合
・償却方法変更の有無と変更理由の妥当性評価
・税務申告書との整合性確認
・将来の設備投資計画と償却負担の見通し
また、EBITDAの正常化調整においても、定率法特有の考慮が必要です。初期に多額の償却費を計上している場合、過去のEBITDAが過小評価されている可能性があるため、償却方法の違いを調整した分析が求められます。
企業価値算定で償却方法の影響を正確に反映する
企業価値算定において、減価償却方法の違いは複数の側面から影響を与えます。定率法採用企業の評価では、以下の点を正確に反映させることが重要です。
DCF法による評価では、将来キャッシュフローの予測に償却方法の影響を適切に織り込む必要があります。定率法の場合、既存資産の償却費は年々減少していきますが、新規投資分は再び高い償却費から始まります。この循環を考慮した予測モデルの構築が必要です。
類似企業比較法を用いる場合は、償却方法の違いによる影響を調整します。定額法採用企業と比較する際は、EV/EBITDA倍率などの指標において、償却方法の違いが与える影響を考慮した調整が必要となります。
純資産法では、簿価純資産と時価純資産のギャップに注意が必要です。定率法により早期に償却が進んでいる資産は、簿価が実態価値より低い可能性があり、時価評価による調整額が大きくなる傾向があります。
買い手・売り手の立場で償却方法を戦略的に評価する
M&Aにおいて、買い手と売り手では減価償却方法に対する評価視点が異なります。それぞれの立場から戦略的な評価を行うことが、交渉を有利に進める鍵となります。
買い手の立場では、定率法採用企業の買収により、買収後の減価償却負担が軽減されるメリットがあります。既に多くの償却が済んでいるため、買収後の利益への圧迫が少なく、投資回収が早まる可能性があります。一方で、設備の更新時期が近い場合は、新規投資による償却負担増加のリスクも評価する必要があります。
売り手の立場では、定率法による早期償却が企業価値評価に与える影響を正しく説明することが重要です。簿価純資産の低さは必ずしも企業価値の低さを意味しないこと、むしろ税務上のメリットを享受してきた証左であることを、買い手に理解してもらう必要があります。
・買い手のメリット:買収後の償却負担軽減、早期の投資回収
・売り手の対応:EBITDA基準での評価要求、税務メリットの説明
・交渉ポイント:将来の設備投資計画、償却方法の統一
最終的には、両者が納得できる評価方法と価格設定を見出すことが重要です。減価償却方法の違いを単なる会計処理の差異として捉えるのではなく、経営戦略の一環として評価し、M&Aの成功につなげることが求められます。
減価償却の定率法を活用した節税と財務戦略
定率法による減価償却は、単なる会計処理ではなく、中小企業の成長戦略を支える重要な財務ツールです。適切に活用することで、節税効果の最大化、キャッシュフローの改善、そしてM&Aに向けた財務体質の強化を実現できます。ここでは、定率法を戦略的に活用するための具体的な方法を解説します。
設備投資タイミングによる節税効果の最大化
設備投資のタイミングは、節税効果に大きな影響を与えます。定率法の特性を活かした戦略的な投資計画により、税負担を最適化できます。
まず重要なのは、利益が大きく出る年度での設備投資です。定率法では初年度に多額の減価償却費を計上できるため、高収益年度に設備投資を行うことで、課税所得を効果的に圧縮できます。
例えば、1,000万円の製造設備(耐用年数5年)を導入した場合、定率法を適用すると、初年度には400万円の減価償却費を計上することができます(これは20%の減価償却率を仮定した場合の例です)。実効税率30%として計算すると、400万円 × 30% = 120万円の節税効果が得られます。
このように、高収益年度に設備投資を行うことは、税負担を軽減し、企業のキャッシュフローを改善するための有効な戦略となります。
また、期首近くでの設備投資も重要です。年度途中での取得は月割計算となるため、4月に取得すれば12ヶ月分の償却費を計上できますが、12月取得では1ヶ月分しか計上できません。この差は初年度の節税効果に直結します。
・高収益年度での集中投資:利益圧縮効果を最大化
・期首投資の徹底:年間償却費を最大限計上
・複数年投資の分散:毎年の節税効果を平準化
・中古資産の活用:短い耐用年数で早期償却
さらに、中古資産の戦略的活用も検討すべきです。中古資産は耐用年数が短く設定できるため、より早期の償却が可能となり、節税効果が高まります。
キャッシュフロー改善への効果的な活用方法
定率法の最大の特徴である「自己金融効果」を活用することで、企業のキャッシュフローを大幅に改善できます。減価償却費は現金支出を伴わない費用であるため、計上した金額分だけ手元資金が増加します。
具体的な活用方法として、まず設備投資直後の資金繰り改善があります。多額の投資を行った直後は運転資金が逼迫しがちですが、定率法による高額な減価償却費の計上により税負担が軽減され、実質的な資金回収が早まります。
次に、計画的な設備更新サイクルの構築です。定率法により早期に償却が進むことで、設備更新のための内部留保が蓄積されやすくなります。これにより、外部資金に頼らない自己資金での設備更新が可能となり、財務の健全性が向上します。
また、償却費の減少を見越した資金計画も重要です。定率法では償却費が年々減少するため、将来の税負担増加に備えた資金計画が必要です。初期の節税効果で得られた資金を将来の投資や運転資金として計画的に留保することが求められます。
M&A前の財務体質強化への戦略的応用
M&Aを将来的に検討している中小企業にとって、定率法は財務体質強化の有力なツールとなります。買い手にとって魅力的な財務構造を構築するための戦略的な活用方法を解説します。
まず、EBITDAの改善戦略です。M&Aの企業価値評価ではEBITDAが重視されるため、減価償却費の影響を受けない指標での評価向上が重要です。定率法により既に多くの償却を済ませている企業は、将来のEBITDAが改善する見通しを示すことができます。
・既存設備の償却進捗による将来利益の改善見通し
・新規投資の抑制によるフリーキャッシュフローの増加
・税務メリットを享受した健全な財務体質のアピール
次に、買い手にとっての投資回収見通しの改善です。定率法により償却が進んだ設備を保有する企業は、買収後の減価償却負担が少ないため、買い手の投資回収が早まります。この点を戦略的にアピールすることで、より高い企業価値評価を得られる可能性があります。
最後に、財務の透明性確保も重要です。定率法の採用理由や計算の妥当性を明確に説明できる体制を整えることで、デューデリジェンスでの信頼性が向上します。過去の償却実績と将来の償却計画を明確に示すことで、買い手の不安を解消し、スムーズなM&A実現につながります。
まとめ|減価償却の定率法を理解してM&Aに備える財務基盤を構築しよう
減価償却の定率法は、初期に多額の費用計上が可能な償却方法であり、中小企業の節税戦略とキャッシュフロー改善に大きく貢献します。特に、定率法では初年度に多くの減価償却費を計上できるため、税負担を軽減し、資金繰りを改善する効果があります。
また、償却保証額や改定償却率の仕組みを正確に理解し、適切な計算を行うことが重要です。これらの概念は、企業の減価償却の戦略的な運用に必要不可欠です。
M&Aにおいては、定率法の採用が企業価値評価に与える影響を理解することが不可欠です。買い手にとっては買収後の償却負担が軽く、売り手にとってはEBITDAベースでの適正評価を求める根拠となります。
今後は、現在の償却状況を正確に把握し、設備投資計画と連動した財務戦略を立案することが求められます。定率法を戦略的に活用し、M&Aに備えた強固な財務基盤を構築していきましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。













