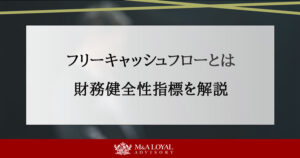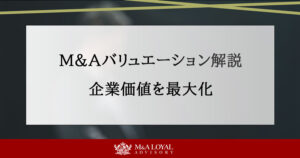減価償却費の計算をわかりやすく解説!ケース別や定額法・定率法の計算例も紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
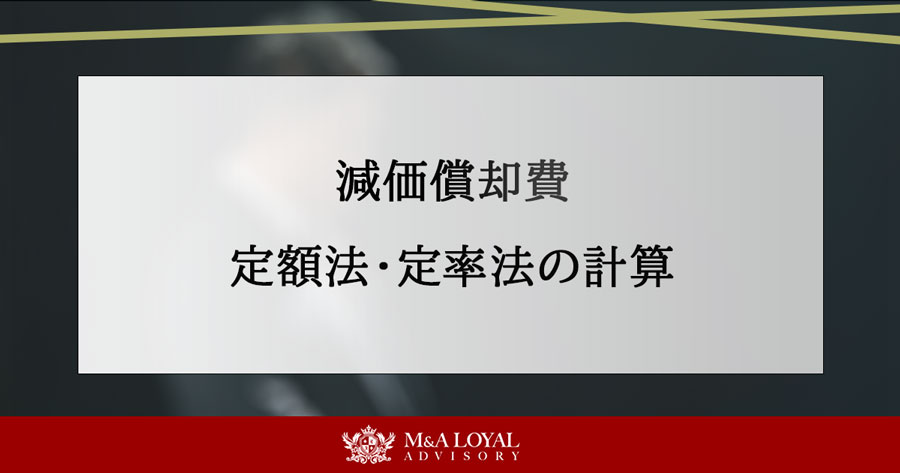
中小企業の経営者や経理担当者にとって、減価償却費の計算は避けて通れない重要な業務です。しかし、「計算方法が複雑で理解しにくい」「定額法と定率法の使い分けが分からない」「実際の計算例を見ながら学びたい」といった悩みを抱える方も少なくありません。
本記事では、減価償却費の計算に必要な基礎知識から、定額法・定率法の具体的な計算手順、建物・設備・車両などのケース別計算例まで、初心者でも理解できるよう分かりやすく解説します。さらに、M&A時における減価償却の重要性や企業価値評価への影響についても詳しく説明します。適切な減価償却費の計算をマスターし、財務管理の精度向上と将来のM&A成功につなげましょう。
目次
減価償却費の計算前に知っておくべき基礎知識
減価償却は、中小企業の経営において単なる会計処理を超えた重要な経営戦略ツールです。適切な減価償却の理解と実践により、税負担の軽減、資金繰りの改善、そして将来のM&Aにおける企業価値の向上を実現できます。ここでは、減価償却費の計算を始める前に必ず押さえておくべき基礎知識について解説します。
中小企業における減価償却の重要性
中小企業にとって減価償却は、経営の根幹に関わる重要な要素です。まず、減価償却費の計上により課税所得を適切に減額でき、法人税や所得税の負担軽減につながります。例えば、1,000万円の製造設備を取得した場合、耐用年数10年の定額法では毎年100万円の減価償却費を計上でき、その分だけ税負担を抑制できます。
さらに、減価償却は現金支出を伴わない費用であるため、減価償却費相当額を内部に留保できる自己金融効果があります。これにより、将来の設備更新や事業拡大のための資金確保が可能となり、財務体質の強化に寄与します。また、中小企業者等の特別償却制度を活用すれば、機械設備の取得価額の30%まで特別償却が認められ、投資初期の節税効果を最大化できます。
M&A時に減価償却が与える影響
M&Aにおいて減価償却は、企業価値評価と取引条件の決定に直接的な影響を与えます。企業価値評価の主要手法であるコストアプローチでは、企業の貸借対照表(バランスシート)の純資産を基準とした評価方法であり、減価償却費が帳簿価額に影響を与えます。適切な減価償却が行われていない場合、資産価値が過大または過小に評価され、適正な取引価格の算定が困難になります。
インカムアプローチにおいても、減価償却費は将来キャッシュフローの計算に影響し、企業価値の算定結果を左右します。特に設備集約型の中小企業では、減価償却方法の選択が企業価値に大きな差をもたらす可能性があります。
さらに、デューデリジェンスでは減価償却の適正性が重要なチェックポイントとなります。償却方法の適切性、耐用年数の妥当性、実際の資産状況との整合性などが詳細に検証され、これらの問題が発見されれば取引価格の減額要因となります。したがって、M&Aを視野に入れる中小企業は、日頃から適切な減価償却を行い、財務の透明性を確保することが重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



減価償却費の計算に必要な3つの要素をわかりやすく解説
減価償却費の正確な計算には、取得価額、耐用年数、償却率という3つの基本要素を正しく把握することが不可欠です。これらの要素を適切に理解し活用することで、税務申告での計算ミスを防ぎ、M&A時の企業価値評価においても信頼性の高い財務情報を提供できます。ここでは、それぞれの要素について具体的な確認方法と実践的なポイントを解説します。
取得価額の正しい把握方法
取得価額は、減価償却の基礎となる最も重要な要素です。単純な購入代金だけでなく、資産を使用可能な状態にするまでに要したすべての費用を含める必要があります。
具体的には、本体価格に加えて運送費、据付工事費、試運転費、購入手数料、登録費用なども取得価額に含まれます。例えば、製造設備を500万円で購入し、運送費30万円、据付費用70万円がかかった場合、取得価額は600万円となります。
また、消費税の扱いにも注意が必要です。税込経理方式を採用している企業は消費税込みの金額を、税抜経理方式を採用している企業は消費税抜きの金額を取得価額とします。建物と土地を一括で購入した場合は、固定資産税評価額の比率や消費税額から建物部分の取得価額を適切に按分する必要があります。
耐用年数の調べ方と一覧表
耐用年数は、国税庁が定める「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認できます。資産の種類、構造、用途によって細かく設定されており、正確な分類が重要です。
主要な資産の耐用年数例は以下の通りです。
- 建物(事務所用):鉄筋コンクリート造50年、木造24年
- 機械装置:設備の種類により細分化されているため、国税庁の耐用年数表で個別の確認が必要
- 車両:普通自動車6年、軽自動車4年
- 工具器具備品:パソコン(電子計算機)4年、事務机(主として金属製のもの)8年
中古資産を取得した場合、簡便法を用いて耐用年数を計算できます。法定耐用年数の一部を経過した資産は「(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)」で算出します。この計算結果に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨て、計算結果が2年に満たない場合は2年とします。耐用年数表に該当項目がない場合や判断に迷う場合は、税務署への確認が必要です。
償却率の確認方法
償却率は、耐用年数に応じて国税庁の「減価償却資産の償却率等表」で定められています。定額法と定率法でそれぞれ異なる償却率が設定されており、選択した償却方法に対応する率を使用します。
定額法では、耐用年数に応じた一定の償却率を適用します。例えば、耐用年数4年の場合は0.250、5年の場合は0.200となります。計算式は「取得価額×定額法償却率」となり、毎年同額の減価償却費が算出されます。
定率法では、より複雑な計算が必要です。基本的な定率法償却率に加えて、改定償却率と保証率も確認する必要があります。耐用年数5年の場合、定率法償却率0.400、改定償却率0.500、保証率0.10800が設定されています。計算した減価償却費が償却保証額を下回った場合は、改定償却率を使用した方法に切り替わるため、両方の数値を把握しておくことが重要です。
減価償却費の計算方法|定額法をわかりやすく解説
定額法は、減価償却の計算方法の中でもシンプルで分かりやすい方法です。多くの中小企業が採用しており、特に建物や設備投資の減価償却で用いられる計算方法となります。毎年一定額を減価償却費として計上するシンプルな仕組みにより、財務計画の予測が立てやすく、経営の安定性に寄与します。
定額法の計算式と特徴
定額法の基本計算式は非常にシンプルです。「減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率」で算出され、耐用年数期間中は毎年同じ金額を減価償却費として計上します。
定額法の償却率は耐用年数に応じて決められており、例えば耐用年数4年の場合は0.250、5年の場合は0.200となります。この償却率は国税庁の「減価償却資産の償却率等表」で確認できます。
定額法の最大の特徴は、計算の簡便性と予測可能性です。毎年の減価償却費が一定であるため、年間の費用計画や資金繰り計画を立てやすく、財務管理の安定性に貢献します。また、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアについては、法令により定額法の適用が義務付けられています。
なお、耐用年数の最終年には、資産が帳簿上に残っていることを示すため、減価償却費から1円を差し引いた金額を計上し、備忘価額として1円を残します。これにより、償却完了後も資産の存在を帳簿で確認できます。
定額法の具体的な計算例(建物・設備)
実際の計算例を通じて、定額法の理解を深めましょう。
事例1:事務所建物の場合
鉄筋コンクリート造の事務所建物を5,000万円で取得した場合を考えます。鉄筋コンクリート造事務所の耐用年数は50年、定額法償却率は0.020です。
年間減価償却費 = 5,000万円 × 0.020 = 100万円
毎年100万円ずつ、50年間にわたって減価償却を行います。最終年(50年目)のみ、99万9,999円を計上し、1円を備忘価額として残します。
事例2:製造設備の場合
製造業で使用する機械装置を1,200万円で取得した場合を見てみます。製造業用機械の耐用年数は10年、定額法償却率は0.100です。
年間減価償却費 = 1,200万円 × 0.100 = 120万円
毎年120万円ずつ、10年間にわたって減価償却を行います。10年間の総減価償却費は1,199万9,999円となり、最終的に1円が帳簿に残ります。
定額法は計算が簡単で理解しやすいため、中小企業の経理担当者にとって扱いやすい方法です。また、毎年の費用が一定であることから、設備投資の影響を平準化でき、安定した財務運営に寄与します。特に不動産賃貸業や製造業など、長期的な設備投資を行う業種では、定額法による計画的な費用配分が経営の安定性向上に重要な役割を果たします。
減価償却費の計算方法|定率法をわかりやすく解説
定率法は、資産の価値減少の実態により近い減価償却方法として、多くの企業が採用しています。初年度に大きな減価償却費を計上できるため、設備投資直後の節税効果が高く、特に機械装置や車両などの資産に適用されます。ただし、計算が複雑になるため、正確な理解が重要です。
定率法の計算式と特徴
定率法の基本計算式は「減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率」です。未償却残高とは、取得価額から過去の減価償却費累計額を差し引いた金額で、毎年変動します。
定率法では、一定の償却率を未償却残高に乗じて計算するため、初年度の減価償却費が最も大きく、その後は年々減少していきます。この特徴により、資産価値の実際の減少パターンをより適切に反映できます。
ただし、定率法には特別な仕組みがあります。計算した減価償却費が「償却保証額(取得価額×保証率)」を下回った場合、その年度から「改定取得価額×改定償却率」による定額法に切り替わります。これにより、耐用年数内での完全な償却を保証しています。
定率法が適用できる資産は、機械装置、車両運搬具、工具器具備品などです。建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアには適用できません。(特に、平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以降に取得した「建物附属設備」および「構築物」の償却方法は、定額法に一本化されました。)また、法人は原則として定率法を使用しますが、届出により定額法を選択できます。
定率法の具体的な計算例(機械・車両)
実際の計算例で定率法の仕組みを確認しましょう。
事例:営業車両の場合
普通自動車(営業車)を500万円で取得した場合を考えます。耐用年数6年、定率法償却率0.333、改定償却率0.334、保証率0.09911とします。
まず償却保証額を計算します:500万円 × 0.09911 = 49万5,550円
各年の計算は以下の通りです。
1年目
減価償却費:500万円 × 0.333 = 166万5,000円
未償却残高:500万円 – 166万5,000円 = 333万5,000円
2年目
減価償却費:333万5,000円 × 0.333 = 111万555円
未償却残高:333万5,000円 – 111万555円 = 222万4,445円
3年目
減価償却費:222万4,445円 × 0.333 = 74万740円
未償却残高:222万4,445円 – 74万740円 = 148万3,705円
4年目
通常計算:148万3,705円 × 0.333 = 49万4,113円
この金額が償却保証額49万5,550円を下回るため、改定償却率に切り替えます。
減価償却費:148万3,705円 × 0.334 = 49万5,557円
5年目以降
同様に改定償却率0.334を適用し、最終年は備忘価額1円を残して完了します。
定率法は初期の節税効果が高く、キャッシュフローの改善に寄与しますが、後年の減価償却費が少なくなるため、長期的な資金計画に注意が必要です。また、計算が複雑になるため、経理システムの活用や専門家への相談が重要になります。
中小企業が使える減価償却の強力な税制優遇措置
通常の減価償却に加えて、中小企業者等(資本金1億円以下の法人など)が設備投資を行う際には、税負担を大幅に軽減できる強力な優遇税制が用意されています。これらを活用することで、投資初年度のキャッシュフローを劇的に改善し、企業の成長を加速させることが可能です。代表的な2つの制度をご紹介します。
中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制は、特定の新品設備を取得した場合に、通常の減価償却費とは別に、以下のいずれかの優遇措置を選択できるものです。
- 取得価額の30%の特別償却
初年度に、通常の減価償却費に加えて取得価額の30%を追加で経費(損金)にできます。これにより、投資初年度の課税所得を大きく圧縮できます。
- 取得価額の7%の税額控除
算出した法人税額から、取得価額の7%を直接差し引くことができます。
ただし、この税額控除を選択できるのは、資本金3,000万円以下の法人および個人事業主に限られます。資本金3,000万円超1億円以下の法人は特別償却のみ適用可能です。
【対象設備の例】
- 機械及び装置:1台160万円以上
- ソフトウェア:合計取得価額70万円以上
- 貨物運送用の普通自動車(車両総重量3.5トン以上)
この制度は、後述する経営力向上計画の認定がなくても利用できるため、比較的活用しやすいのが特徴です。
中小企業経営強化税制(即時償却)
中小企業経営強化税制は、中小企業投資促進税制よりもさらに強力な優遇措置です。最大のメリットは、設備投資額の全額をその年度の費用として一括で計上できる「即時償却」が可能な点です。
- 即時償却(取得価額の100%償却)
取得した設備の価額の全額を、事業で使い始めた年度に一括で経費(損金)にできます。例えば、2,000万円の機械を導入した場合、その2,000万円全額をその期の費用として計上できるため、利益が大きく出た年度の税負担を劇的に軽減できます。
- 取得価額の最大10%の税額控除
即時償却の代わりに、税額控除を選択することも可能です。資本金3,000万円以下の法人は10%、資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%の税額控除が適用されます。
【極めて重要な適用要件】
この強力な制度を利用するためには、単に設備を購入するだけでなく、事前に自社の経営力を向上させるための「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受ける必要があります。
【対象設備の例】
- 機械及び装置:1台160万円以上
- 工具・器具備品:1台30万円以上
- ソフトウェア:合計取得価額70万円以上
どちらの制度を選ぶべきか?
2つの制度の違いを下の表にまとめました。設備投資を計画する際は、どちらの制度が自社にとって有利か、専門家である税理士にも相談しながら検討することが重要です。
| 項目 | 中小企業投資促進税制 | 中小企業経営強化税制 |
| 主な優遇措置 | 30%特別償却 または7%税額控除 | 即時償却(100%)または最大10%税額控除 |
| 税額控除の 対象法人 | 資本金3,000万円以下の法人等 | 資本金3,000万円以下の法人等は10% 資本金3,000万円超1億円以下の法人は7% |
| 主要な要件 | 特定の新品設備を導入すること | 「経営力向上計画」の認定を受けること |
| 手続き | 確定申告書への明細書添付 | 計画の認定後、確定申告書に認定書等を添付 |
これらの制度を戦略的に活用することで、通常の減価償却だけでは得られない大きな節税メリットを享受し、企業の財務体質を強化することができます。
減価償却費の計算を実践!5つのケース別計算例
実際の業務で遭遇する様々なシチュエーションにおける減価償却費の計算を、具体的な数値を用いて解説します。これらの計算例をマスターすることで、日常の経理業務からM&A時の資産評価まで、幅広い場面で正確な減価償却費の算出が可能になります。
事務所建物を取得した場合
木造の事務所建物を3,000万円で取得したケースです。木造事務所の耐用年数は24年、定額法償却率は0.042となります。
年間減価償却費 = 3,000万円 × 0.042 = 126万円
毎年126万円ずつ24年間計上し、最終年は125万9,999円を計上して1円を残します。木造建物は鉄筋コンクリート造(50年)に比べて耐用年数が短いため、年間の減価償却費が大きくなり、早期の費用計上が可能です。
製造設備を導入した場合
製造業で使用する専用機械を2,500万円で導入した場合を考えます。製造業用機械の耐用年数は10年、定額法償却率は0.100です。
年間減価償却費 = 2,500万円 × 0.100 = 250万円
10年間にわたって毎年250万円を計上します。製造設備は事業の中核となる資産であり、適切な減価償却により投資効果を長期的に反映できます。また、設備の更新計画も立てやすくなります。
営業車両を購入した場合
普通自動車(営業車)を400万円で購入した場合の定率法計算例です。耐用年数6年、定率法償却率0.333、改定償却率0.334、保証率0.09911とします。
償却保証額:400万円 × 0.09911 = 39万6,440円
1年目:400万円 × 0.333 = 133万2,000円
2年目:(400万円 – 133万2,000円) × 0.333 = 88万8,444円
3年目:(266万7,556円 – 88万8,444円) × 0.333 = 59万2,592円
4年目は計算結果が償却保証額を下回るため、改定償却率を使用します。このように定率法では初期の節税効果が高く、資金繰りの改善に寄与します。
中古資産を取得した場合
3年経過した中古の普通自動車を250万円で取得した場合です。まず中古資産の耐用年数を計算します。
新車の耐用年数6年から経過年数3年を考慮した計算: (6年 – 3年) + (3年 × 20%) = 3年 + 0.6年 = 3.6年
1年未満は切り捨てるため、耐用年数は3年となります。定額法償却率は0.334です。
年間減価償却費 = 250万円 × 0.334 = 83万5,000円
中古資産は新品より耐用年数が短くなるため、年間の減価償却費が大きくなり、早期の費用計上による節税効果が期待できます。
年度途中で取得した場合の月割計算
4月から3月が事業年度の会社が、10月1日にパソコンを60万円で購入し、同日から使用開始した場合です。パソコンの耐用年数は4年、定額法償却率は0.250です。
通常の年間減価償却費:60万円 × 0.250 = 15万円
10月から3月までの6ヶ月間の月割計算: 初年度の減価償却費 = 15万円 × (6ヶ月 ÷ 12ヶ月) = 7万5,000円
翌年度以降は通常通り年間15万円を計上し、最終年度は残りの期間に応じて月割計算を行います。年度途中での取得は月割計算が必要であり、使用開始月から計算を開始する点に注意が必要です。
これらの計算例を参考に、自社の資産取得時には適切な減価償却費の計算を行い、正確な財務管理を実現してください。
減価償却費の計算後の会計処理をわかりやすく解説
減価償却費を計算した後は、適切な会計処理により帳簿に記録する必要があります。会計処理の方法には直接法と間接法の2つがあり、それぞれ異なる特徴とメリットを持ちます。中小企業では管理の複雑さや監査対応を考慮して処理方法を選択することが重要です。
直接法と間接法の違いと仕訳例
直接法は、固定資産の帳簿価額から減価償却費を直接差し引く方法です。取得価額100万円、年間減価償却費25万円の備品の場合、仕訳は以下のようになります。
(借方) 減価償却費 250,000円 / (貸方) 備品 250,000円
直接法では、貸借対照表上の固定資産に未償却残高(75万円)が表示され、現在の資産価値が一目で分かります。計算が簡潔で理解しやすい一方、固定資産の取得価額や減価償却の累計額を帳簿上で確認できないという欠点があります。
間接法は、「減価償却累計額」という別勘定を設けて間接的に処理する方法です。同じ条件での仕訳は以下のとおりです。
(借方) 減価償却費 250,000円 / (貸方) 減価償却累計額 250,000円
間接法では、貸借対照表に「備品 1,000,000円」「減価償却累計額 △250,000円」と表示され、取得価額と減価償却の進捗状況を明確に把握できます。固定資産の管理や分析により適しており、多くの企業で採用されています。
中小企業におすすめの処理方法
中小企業には間接法の採用を推奨します。主な理由として、資産の履歴管理、M&A時の透明性確保、税務調査への対応力向上が挙げられます。
間接法では固定資産の取得価額が明確であり、設備投資の意思決定や資産の更新計画立案に有用です。また、M&Aにおけるデューデリジェンスでは、資産の取得時期、減価償却の適正性、実際の資産状況などが詳細に検証されるため、間接法による透明性の高い記録が評価向上につながります。
さらに、税務調査においても、減価償却の計算根拠や資産の使用状況を明確に説明できるため、調査対応が円滑になります。固定資産台帳との整合性確認も容易で、経理業務の効率化にも寄与します。
ただし、固定資産の数が少なく管理が簡単な小規模事業者の場合は、直接法でも十分対応可能です。事業規模や管理体制に応じて最適な方法を選択し、一度決定した方法は継続して適用することが重要です。
M&A実務で押さえておくべき減価償却費計算のポイント
M&Aにおいて減価償却は、企業価値評価と取引条件の決定に重大な影響を与える要素です。買い手側は対象企業の減価償却の適正性を詳細に検証し、売り手側は自社の減価償却処理の透明性と正確性を証明する必要があります。適切な準備により、M&A交渉を有利に進め、適正な企業価値の実現が可能になります。
デューデリジェンスで減価償却の適正性を証明する
M&Aのデューデリジェンスでは、減価償却に関する以下のポイントが重点的に検証されます。まず償却方法の適切性として、業種や資産の使用状況に対して定額法・定率法の選択が合理的かが確認されます。製造業の機械設備に定額法を適用している場合、その理由と妥当性の説明が求められます。
耐用年数の妥当性も重要な検証項目です。法定耐用年数の適用が適切か、業界標準と比較して異常な設定がないか、実際の使用期間と乖離がないかが詳細に調査されます。特に中小企業では、税務上有利な耐用年数を恣意的に選択していないかが厳しくチェックされます。
実際の資産状況との整合性確認では、帳簿上の資産と現物の一致、稼働状況の実態、老朽化の程度などが現地調査により検証されます。帳簿に計上されているが実際には使用していない遊休資産の存在は、企業価値評価に大きな影響を与えるため、事前の整理が重要です。
売り手企業は、これらの検証に対応するため、固定資産台帳の整備、減価償却計算の根拠資料準備、税務申告との整合性確認を事前に行う必要があります。
企業価値評価への影響を把握し対策を講じる
減価償却は企業価値評価の各アプローチに直接的な影響を与えます。コストアプローチでは、減価償却により算定された帳簿価額が純資産価値の基礎となるため、適切な減価償却により実態に即した資産価値を示すことが重要です。過度に保守的な減価償却は企業価値を低く見積もる要因となります。
インカムアプローチでは、減価償却費が将来キャッシュフローの計算に影響し、企業価値算定の重要な要素となります。定額法と定率法の選択により短期的なキャッシュフローパターンが変わるため、評価への影響を事前に分析し、最適な選択を行うことが重要です。
特に設備集約型の中小企業では、減価償却政策が企業価値に与える影響が大きくなります。売り手企業は、減価償却の会計方針を明確に文書化し、その合理性を説明できる体制を整備すべきです。また、設備の更新計画や将来の設備投資予定についても整理し、持続的な事業運営能力を示すことが企業価値向上につながります。
買い手企業は、対象企業の減価償却政策を詳細に分析し、買収後の減価償却方針との整合性を検討する必要があります。償却方法の変更が必要な場合は、その影響をキャッシュフロー予測に反映し、適切な買収価格の算定を行うことが重要です。
まとめ|減価償却費の正確な計算でM&Aを有利に進めよう
減価償却費の正確な計算は、中小企業の健全な財務管理とM&A成功の基盤となります。取得価額、耐用年数、償却率の3要素を正しく把握し、定額法と定率法を適切に使い分けることで、節税効果と企業価値向上の両立が実現できます。
特にM&Aを検討する中小企業にとって、減価償却の適正な処理は企業価値評価の信頼性確保と交渉力強化に直結します。デューデリジェンスでの適正性証明、企業価値算定への影響分析、将来キャッシュフローの正確な予測など、あらゆる局面で減価償却の専門知識が重要な役割を果たします。
今後は、学んだ知識を自社の固定資産管理に活用し、適切な会計処理体制の構築を進めてください。また、M&Aを視野に入れる場合は、早期の段階から減価償却政策の見直しと文書化を行い、透明性の高い財務体制を整備することが重要です。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、中小企業のM&Aをサポートしています。M&Aや経営課題に関するご相談は、ぜひ当社の専門アドバイザーにお任せください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。