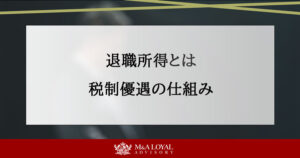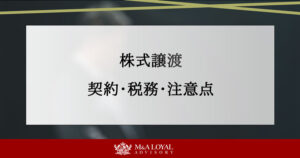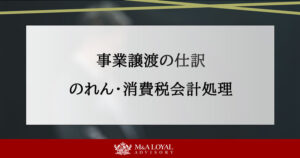譲渡所得とは?基本的な仕組みから税務処理・確定申告まで簡単に解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
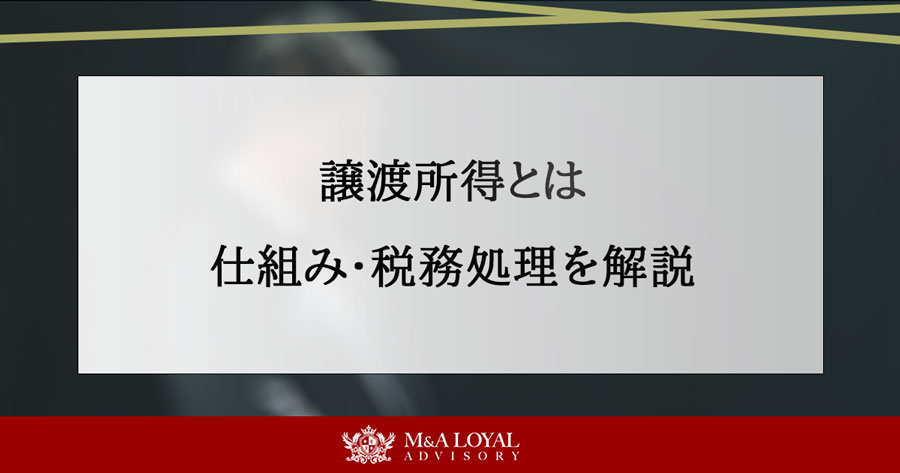
不動産や株式などの資産を譲渡することによって生ずる所得「譲渡所得」について、正しく理解していますか?不動産の売却や中小企業のM&A取引では、譲渡所得の税務処理が重要な要素となります。適切な知識がないまま取引を進めると、本来受けられるはずの特例制度を見逃したり、予想以上の税負担を抱える可能性があります。
本記事では、譲渡所得の基本的な概念から実際の計算方法、M&A取引での特殊な取り扱い、活用できる特例制度、そして確定申告の具体的な手続きまで、実務で必要となる知識を分かりやすく解説します。正しい税務処理により手取り額を最大化し、安心して資産譲渡を実現するための実践的な情報をお届けします。
目次
譲渡所得とは何か?
譲渡所得とは、個人が所有する資産を譲渡(売却)することによって生じる所得のことです。所得税法では所得を10種類に分類しており、譲渡所得はその中の一つとして位置づけられています。給与所得や事業所得のような継続的な所得とは異なり、一時的な性質を持つ所得として特別な取り扱いが行われます。
中小企業M&Aにおいても、株式譲渡や事業譲渡の際にこの譲渡所得として課税されることになるため、適切な理解が重要です。譲渡所得の基本的な計算式は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」となり、純粋な利益部分に対して課税される仕組みです。
譲渡所得の基本的な定義と仕組み
譲渡所得は英語では「Capital Gain」と表現され、資本利得として位置づけられています。この所得の特徴は、資産の保有期間中に蓄積された価値の増加分を、譲渡時点で一括して認識することにあります。
基本的な計算方法は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。取得費には購入代金のほか、購入時の仲介手数料や登録免許税なども含まれます。譲渡費用には売却時の仲介手数料や印紙税などが該当します。
譲渡所得は一時的な大きな所得となることが多いため、税負担の軽減を図る各種特例制度が設けられています。特に居住用財産の譲渡では3,000万円の特別控除など、手厚い優遇措置が用意されています。
譲渡所得の対象となる資産の種類
譲渡所得の対象となる資産は幅広く定められており、主要なものとして以下があります。
・不動産関連:土地、建物、借地権
・有価証券:株式、特定の公社債
・動産:金地金、宝石、書画、骨董品
・権利:特許権、著作権、鉱業権、漁業権
・その他:ゴルフ会員権、船舶、機械器具
ただし、すべての資産譲渡が譲渡所得になるわけではありません。事業用の商品や棚卸資産、山林の譲渡(ただし土地部分は譲渡所得)、日常生活で使用する家具や衣類などの生活用動産は対象外です。また、貸付金や売掛金などの金銭債権も除外されます。
中小企業M&Aにおいては、株式譲渡や事業譲渡が主な対象となります。株式譲渡では株式そのものが譲渡資産となり、事業譲渡では事業に使用している各種資産が個別に譲渡資産として扱われることになります。
総合課税と分離課税による分類方法
譲渡所得の課税方法は、譲渡する資産の種類によって「総合課税」と「分離課税」の2つに分類されます。この違いを理解することは、税負担を正確に把握する上で極めて重要です。
総合課税は、譲渡所得を給与所得や事業所得などの他の所得と合算して、累進税率(所得税5%~45%)で課税する方法です。ただし、所有期間が5年を超える長期譲渡所得に該当する場合、税負担を軽減する重要な優遇措置があります。具体的には、譲渡所得の金額を2分の1にしてから他の所得と合算して税額を計算します。金地金、宝石、書画、骨董品、機械器具、特許権、著作権などの譲渡が総合課税の対象となります。
一方、分離課税は他の所得とは分離して独立して税額を計算する方法です。土地・建物・借地権、株式等の譲渡が分離課税の対象となります。分離課税では所有期間によって税率が異なります。例えば、土地・建物の譲渡では、所得税・住民税・復興特別所得税を合わせた合計税率が、短期(所有期間5年以下)で39.63%(所得税30%、住民税9%)、長期(所有期間5年超)で20.315%(所得税15%、住民税5%)となります。また、株式等の譲渡は所有期間にかかわらず一律20.315%です。
なお、この所有期間の判定基準は資産の種類によって異なります。土地・建物や株式などの分離課税では「譲渡した年の1月1日時点」で所有期間が5年を超えるかどうかで長期・短期を判定します。一方、総合課税の対象となる資産(ゴルフ会員権など)では「実際の取得日から譲渡日までの期間」で判定します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



譲渡所得の課税方法と税率の仕組み
譲渡所得にかかる税金は、資産の所有期間と種類によって大きく異なります。これは国が短期的な投機的取引を抑制し、長期的な資産保有を促進するための政策的な配慮が反映されているためです。中小企業のM&Aにおいても、この仕組みを理解することで適切な売却タイミングを判断できるようになります。
税率の違いは単純に数パーセントの差ではなく、場合によっては税負担が倍近く変わることもあります。そのため、譲渡所得の課税方法と税率の仕組みを正確に把握しておくことは、資産譲渡において極めて重要な要素となります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の判定基準
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分は、資産の種類と所有期間によって決まります。土地・建物や株式といった分離課税の対象となる資産の場合、判定基準は「譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうか」です。具体的には、1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得となります。注意すべき点は、実際の所有期間ではなく、売却年の1月1日を基準として判定することです。
一方で、ゴルフ会員権など総合課税の対象となる資産の場合は、実際の取得日から譲渡日までの期間で判定され、所有期間が5年を超えれば長期譲渡所得となります。こちらの場合は、譲渡日が近づくにつれて所有期間が変動するため、売却のタイミングに注意が必要です。
例えば、2018年2月1日に取得した資産を2023年2月2日に売却する場合、実際の所有期間は5年を超えていますが、2023年1月1日時点では4年11ヶ月となるため、短期譲渡所得として扱われます。この約1ヶ月の違いで税負担が大きく変わるため、売却時期の検討は慎重に行う必要があります。
中小企業M&Aでは、株式を長期保有している経営者が多いため、多くの場合は長期譲渡所得に該当します。しかし、事業承継のタイミングや資産の種類によっては短期譲渡所得となる可能性もあるため、事前に所有期間を確認し、適切な計画を立てることが重要です。特に、事業承継を考える際には、税負担を最小限に抑えるための戦略を検討することが求められます。
資産の種類別による税率の違い
譲渡所得の税率は、分離課税の対象となる資産において特に明確な差があります。土地・建物の譲渡では、短期譲渡所得に対して所得税30%・住民税9%(合計39%)、長期譲渡所得に対して所得税15%・住民税5%(合計20%)の税率が適用されます。
株式等の譲渡については、短期・長期の区分に関係なく一律で所得税15%・住民税5%(合計20%)の税率となります。これは株式投資を促進する政策的配慮によるものです。
- 土地・建物: 短期39%、長期20%
- 株式等: 短期・長期とも20%
- 総合課税資産: 他の所得と合算し累進税率(5%~45%)を適用
※ただし、所有期間が5年を超える長期譲渡所得に該当する場合、その所得金額の2分の1の額を課税対象とする優遇措置があります。これにより、税負担が軽減されることになります。
さらに、平成25年から令和19年までは復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が上乗せされます。そのため、実際の税率は土地・建物の短期譲渡では39.63%、長期譲渡では20.315%となります。この復興特別所得税の適用は、特定の期間に限られていますので、今後の税制改正にも注意が必要です。
土地・建物と株式等での計算方法の差異
土地・建物と株式等では、譲渡所得の計算方法にも違いがあります。土地・建物の場合、取得費には購入代金のほか、購入時の登録免許税や不動産取得税、仲介手数料なども含めることができ、建物については減価償却費相当額を控除します。
株式等の場合は、取得費として購入代金と委託手数料等を計上し、譲渡費用として売却時の委託手数料を差し引きます。土地・建物のような特別控除制度は基本的にありませんが、計算がより単純になっています。
中小企業M&Aでは、株式譲渡が分離課税20.315%(長期の場合)で比較的有利な税率となる一方、事業譲渡では個別資産ごとに総合課税と分離課税が混在するため、税務上の取り扱いが複雑になります。そのため、M&Aのスキーム選択においては税務影響を十分に検討することが重要です。
譲渡所得金額の正しい計算方法
譲渡所得金額の計算は、税務申告において最も重要な部分の一つです。計算を間違えると、本来支払う必要のない税金を払うことになったり、逆に申告漏れとして後から追徴課税を受けるリスクもあります。中小企業M&Aにおいても、株式譲渡価格から正確な譲渡所得を算出することで、適切な税務処理が可能になります。
基本的な計算式は「譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」となります。この式の各要素を正確に把握し、適切に計算することが節税につながる重要なポイントです。
収入金額に含まれる項目と注意点
収入金額は譲渡の対価として受け取る金額ですが、単純な売却価格だけではありません。売却価格に加えて、固定資産税や都市計画税の精算金も収入金額に含まれます。
例えば、不動産を3,000万円で売却し、固定資産税の精算金として5万円を受け取った場合、収入金額は3,005万円となります。また、金銭以外に物や権利を受け取った場合は、その時価を収入金額として計算します。
中小企業M&Aの株式譲渡では、譲渡価格以外にも役員退職金や顧問契約などの付帯的な収入がある場合、それらの性質を慎重に検討する必要があります。一定の条件下では、著しく低い価額での譲渡は時価での譲渡とみなされる場合もあるため、特に親族間でのM&Aでは注意が必要です。
取得費として計上できる費用の詳細
取得費は資産を取得する際に要した費用であり、購入代金や建築代金が基本となります。しかし、それ以外にも多くの費用を取得費として計上できます。
主な取得費には以下があります。購入時の仲介手数料、登録免許税や不動産取得税などの税金、測量費や整地費、設備費や改良費、さらには借入金の利子(使用開始日まで)も含まれます。
・購入代金・建築代金
・購入時仲介手数料
・登録免許税
・不動産取得税
・印紙税
・設備費
・改良費
・借主立退料(取得時)
建物の取得費については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。また、相続によって取得した資産の場合、被相続人の取得費を引き継ぐため、時価ではなく当初の取得費となる点に注意が必要です。
譲渡費用の範囲と具体的な計算例
譲渡費用は、資産を売却するために直接かかった費用のことです。資産の維持管理費用とは区別され、売却のために特別に支出した費用のみが対象となります。
具体的には、売却時の仲介手数料、売買契約書の印紙税、借家人への立退料、建物の取壊し費用、測量費などが譲渡費用に該当します。一方、固定資産税や修繕費など、資産の維持管理のための費用は譲渡費用には含まれません。
計算例として、4,000万円で売却した物件で、売却時の仲介手数料が120万円、印紙税が2万円、測量費が30万円かかった場合、譲渡費用の合計は152万円となります。これらの費用を適切に計上することで、譲渡所得を圧縮し、税負担を軽減することが可能です。
さらに、譲渡費用を正しく計上することは、税務署に対する説明責任を果たす上でも重要です。万が一、税務調査が行われた際に、適切な書類や証拠を用意しておくことが求められます。
取得費が不明な場合の概算取得費の活用方法
先祖代々の土地や、購入時の書類が紛失してしまった場合など、取得費が不明なケースでは「概算取得費」を活用できます。これは売却額の5%を取得費とみなす制度です。
例えば、4,000万円で売却した土地の取得費が不明な場合、200万円(4,000万円×5%)を取得費として計算できます。また、実際の取得費が判明している場合でも、概算取得費の方が有利であれば、概算取得費を選択することも可能です。
ただし、概算取得費を選択した場合、実際にかかった改良費やその他の取得に関連する費用を別途加算することはできません。概算取得費は取得費全体を包括する概念として扱われるため、実額と概算のどちらが有利かを総合的に判断する必要があります。
中小企業M&Aでは、創業時からの株式保有により取得費が明確な場合が多いですが、増資履歴やその他の関連書類の整理が重要になります。また、株式の譲渡においても、取得費の扱いを正確に理解しておくことが、税負担の軽減につながります。
M&Aにおける譲渡所得の特殊な取り扱い
中小企業M&Aでは、一般的な資産譲渡とは異なる特殊な税務処理が必要になります。特に株式譲渡と事業譲渡では、譲渡所得の計算方法や適用される税率が大きく異なるため、どちらのスキームを選択するかによって最終的な手取り額に大きな差が生じます。
M&A取引では、単純な譲渡所得の計算だけでなく、のれんの取り扱い、役員退職金の活用、消費税の課税関係など、複合的な税務論点を検討する必要があります。これらの要素を適切に組み合わせることで、大幅な節税効果を実現できる可能性があります。
株式譲渡と事業譲渡での譲渡所得の違い
株式譲渡では、譲渡対価から株式の取得費と譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得となり、20.315%の分離課税が適用されます。中小企業の場合、会社設立時からの株式保有で取得費が非常に低いケースが多く、譲渡益のほぼ全額が課税対象となることが一般的です。
一方、事業譲渡では譲渡企業(法人)に譲渡益が発生し、まず法人税等(実効税率約31~35%)が課税されます。その後、税引き後の利益を株主個人が配当などで受け取る際に、さらに配当所得として所得税・住民税(最高税率約55%)が課税されます。この「法人税」と「所得税」の二重課税により、株主の最終的な手取り額は、同額の対価であっても株式譲渡(個人の譲渡所得税約20.315%の単一課税)に比べて大幅に少なくなるのが一般的です。
具体的な計算例として、2億円で会社を売却する場合を考えてみましょう。株式譲渡では、取得費1,000万円、譲渡費用500万円とすると、譲渡所得は以下のように計算されます。
- 譲渡所得 = 譲渡対価 – 取得費 – 譲渡費用 = 2億円 – 1,000万円 – 500万円 = 1億8,500万円
この譲渡所得1億8,500万円に対して約3,760万円(1億8,500万円 × 20.315%)の税金がかかります。
これに対して、事業譲渡では、法人の譲渡益に対する法人税が課税され、その後、株主への配当や退職金に対する税金がかかります。例えば、法人税が33%だと仮定すると、譲渡益に対する法人税は以下のように計算されます。
- 法人の譲渡益 = 2億円 – 取得費(例:1,000万円) = 1億9,000万円
- 法人税 = 1億9,000万円 × 33% = 約6,270万円
その後、税引き後の利益は以下のようになります。
- 税引き後の利益 = 2億円 – 6,270万円 = 約1億3,730万円
この金額を株主が配当として受け取ると、さらに高い税率(最大55%)がかかるため、最終的な手取り額は大幅に減少します。
このように、株式譲渡と事業譲渡では税負担が異なり、特に事業譲渡の場合は二重課税が発生するため、株主の最終的な手取り額が少なくなることが一般的です。
中小企業M&Aでの譲渡価格算定のポイント
中小企業M&Aにおける譲渡価格の算定では、純資産価格にのれん(営業権)を加えた金額で評価されることが一般的です。この「のれん」の税務上の取り扱いは、M&Aスキーム選択における極めて重要な論点です。
事業譲渡の場合、買い手は支払ったのれん代を税務上「資産調整勘定」として資産計上し、5年間で均等に償却して損金に算入できます。これは買い手にとって将来の法人税を軽減する「タックス・シールド」となり、より高い買収価格を提示できる要因になります。一方、株式譲渡の場合、買い手が支払った対価は「子会社株式」となるため、のれんの損金算入は認められません。つまり、株式譲渡ではのれんの会計上の扱いが異なり、税務上のメリットを享受できないことになります。
のれんは企業の収益力、顧客基盤、技術力、ブランド価値などの無形資産を反映したものであり、EBITDA(営業利益+減価償却費)の3~5倍程度で算定されることが多く、業界や企業の成長性によって大きく変動します。したがって、のれんの評価は慎重に行う必要があります。
税務上重要なのは、のれんの計算根拠を明確にしておくことです。税務調査で不当に高額な評価と判断されると、贈与税や法人税の追加課税を受けるリスクがあります。そのため、適切な評価方法に基づく算定資料の整備が不可欠です。
また、株式譲渡では株式の取得費が重要な論点となります。中小企業では増資履歴が複雑な場合もあるため、設立時から現在までの出資状況を正確に整理し、適切な取得費を算定することが節税につながります。特に、株式の取得費に関する情報が不明確な場合、将来的な税務上のトラブルを避けるためにも、しっかりとした記録の維持が重要です。
M&A取引特有の税務上の注意点と対策
M&A取引では、著しく低い価額での譲渡に注意が必要です。特に個人から法人へ資産を譲渡する場合、その譲渡価格が時価の2分の1未満であると、売り手は実際に受け取った金額にかかわらず、時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得税が課される可能性があります(みなし譲渡所得課税)。さらに、買い手側も時価との差額が受贈益として法人税の対象となるため、特に親族や関連会社間での取引では、専門家とともに時価を慎重に評価することが不可欠です。
また、役員退職金を活用した節税スキームも重要な検討事項です。譲渡所得には20.315%の税率が適用されますが、退職所得は退職所得控除と2分の1課税により実効税率を下げることができます。ただし、過大な退職金は累進課税により逆に税負担が重くなるため、適正な金額設定が必要です。
- 退職所得控除の計算: 退職金の額に応じた控除が適用されます。これにより、一定額までは課税対象から外れます。
- 2分の1課税による税負担軽減: 退職所得の半分のみが課税対象となるため、実効税率が下がります。
- 累進税率との比較検討: 退職所得と譲渡所得の税率を比較し、最も有利な方法を検討します。
- 適正額の算定: 過大にならないよう、退職金の設定には慎重を期す必要があります。
さらに、M&A後の税務申告タイミングも重要です。株式譲渡による所得税は翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)に申告・納税する必要があり、住民税は翌年6月から納付が始まります。大きな譲渡益が発生する場合は、予定納税の検討も含めて資金繰りを計画的に準備することが重要です。特に、譲渡益が大きい場合は、事前に税金を見越した資金の準備を行うことで、納税時の資金繰りの負担を軽減できます。
譲渡所得で活用できる特例制度と節税対策
譲渡所得には多くの特例制度が用意されており、これらを適切に活用することで大幅な節税効果を実現できます。特に居住用財産の譲渡では、3,000万円の特別控除をはじめとする強力な優遇措置があり、場合によっては譲渡所得税を完全に回避することも可能です。この特別控除は、居住用財産を譲渡した際に、その譲渡所得から3,000万円を控除できる制度で、特に自宅を売却する場合に有効です。
これらの特例制度は、国が個人の住居確保や適切な資産移転を支援するために設けられたものです。中小企業M&Aにおいても、経営者の自宅売却や事業用不動産の処分において、これらの特例を活用することで手取り額を最大化できる場合があります。ただし、各特例には厳格な要件があるため、例えば居住期間や譲渡する不動産の種類など、事前の確認と計画的な実行が重要です。
また、居住用財産に関する特例以外にも、事業用資産に関連する特例や譲渡所得に関するその他の優遇措置についても知識を深めることが、M&Aにおける資産の最適化につながります。特に、税理士などの専門家と相談しながら進めることが推奨されます。
マイホーム売却時の3,000万円特別控除を適用する
居住用財産の3,000万円特別控除は、マイホームを売却した際に譲渡所得から最高3,000万円を控除できる強力な特例制度です。この特例の最大の特徴は、所有期間の長短を問わず適用できることです。
適用要件は比較的明確で、現在住んでいる家屋または住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する家屋が対象となります。また、家屋とともに売却する敷地や、家屋を取り壊した場合のその敷地も適用対象です。
具体的な節税効果を計算してみましょう。譲渡所得が2,000万円の場合、通常であれば長期譲渡所得として20.315%の税率で約406万円の税金がかかります。しかし、3,000万円特別控除を適用すれば、譲渡所得が完全に相殺されて税金はゼロになります。
注意すべき点として、親子や夫婦など特別な関係がある人への売却では適用できません。また、前年・前々年に同じ特例の適用を受けていないことや、他の特例制度との重複適用制限もあります。特例の適用を受けるためには、譲渡所得がゼロになる場合でも確定申告が必須です。
軽減税率の特例と買換えの特例を活用する
10年超所有軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用できる非常に有利な制度です。売却したマイホームの所有期間が10年を超える場合、3,000万円控除後の譲渡所得6,000万円以下の部分に対して14.21%の軽減税率が適用されます。
計算例として、譲渡所得4,000万円のケースを考えてみます。3,000万円控除後の1,000万円に対して、通常税率20.315%なら約203万円の税金ですが、軽減税率14.21%なら約142万円となり、約61万円の節税効果があります。
買換えの特例は、一定要件を満たすマイホームの買換えにおいて、譲渡益への課税を将来に繰り延べる制度です。現在の売却時点では課税されず、将来買換え後の物件を売却する際にまとめて課税される仕組みです。
・居住期間10年以上かつ所有期間10年超
・譲渡対価1億円以下
・買換え物件の床面積50㎡以上
・新耐震基準への適合
この特例は税負担の軽減ではなく繰り延べですが、当面の納税資金が不要になるため、資金繰りの面で大きなメリットがあります。
また、「居住用財産の3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」とは選択適用となり、同時に利用することはできません。前者は税額を確定的に減少させる制度、後者は課税を将来に繰り延べる制度であり、どちらが有利かは個々の状況によるため、慎重な判断が必要です。
その他の特別控除制度の適用要件を確認する
居住用財産以外にも、譲渡所得には様々な特別控除制度があります。最も控除額が大きいのは、公共事業等による土地・建物の売却時の5,000万円特別控除です。道路拡張や公共施設建設のための土地収用等が対象となります。
その他の主要な特別控除制度は以下の通りです。特定土地区画整理事業等による土地売却では2,000万円、特定住宅地造成事業等では1,500万円、農地保有合理化等による土地売却では800万円の控除が受けられます。
・公共事業等:5,000万円控除
・土地区画整理事業:2,000万円控除
・住宅地造成事業:1,500万円控除
・農地保有合理化:800万円控除
・低未利用土地等:100万円控除
複数の特例制度に該当する場合、合計で5,000万円が上限となり、控除額の大きい順に適用されます。中小企業M&Aでは、事業用不動産が公共事業の対象となるケースもあるため、売却タイミングを検討する際は公的な開発計画も確認することが重要です。
これらの特例制度を最大限活用するためには、売却時期の調整、必要書類の準備、確定申告の適切な実行が不可欠です。特に複数の特例制度が適用可能な場合は、どの組み合わせが最も有利かを慎重に検討する必要があります。
譲渡所得の確定申告と手続きの流れ
譲渡所得の確定申告は、多くの方にとって馴染みのない手続きですが、適切に行うことで大幅な節税効果を得ることができます。申告期限は原則、毎年2月16日から3月15日までと決まっており、この期間内に正確な申告を完了させることが重要です。
中小企業M&Aにおいて株式譲渡を行った場合、多額の譲渡所得が発生することが多いため、申告漏れや計算ミスがあると大きな追徴課税のリスクを抱えることになります。そのため、事前に手続きの流れを理解し、必要書類を整備しておくことが成功の鍵となります。
確定申告が必要となるケースを正しく判定する
譲渡所得がある場合、基本的に確定申告が必要です。ただし、一定のケースでは申告不要となる場合もあるため、正確な判定が重要です。確定申告が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 譲渡所得がプラスの場合: 売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた結果がプラスであれば、原則として申告が必要です。これは課税対象となるためです。
- 譲渡所得がゼロまたはマイナスの場合: この場合でも、特例制度の適用を受ける場合は申告が必須となります。特に、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合、譲渡所得が特別控除額以下で実質的に税金がかからない場合でも、確定申告をしなければ特例の適用を受けることができません。つまり、確定申告が特例適用の手続きそのものとなるのです。
- 株式譲渡の場合: 特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、他の株式との損益通算を行う場合や、翌年以降への損失繰越を行う場合は確定申告が必要です。中小企業M&Aでは通常、相対取引となるため特定口座の利用はできず、必然的に確定申告が必要となります。
また、申告が不要となるケースとしては、譲渡所得が20万円以下の場合(給与所得者の場合)が挙げられますが、この点についても注意が必要です。自営業者などの場合、譲渡所得が20万円以下でも申告が必要な場合がありますので、個々の状況に応じた判断が求められます。
必要書類を準備し申告書を作成する
譲渡所得の確定申告では、多くの書類が必要となります。基本的な書類として、確定申告書第一表・第二表に加えて、分離課税用の第三表が必要です。さらに、譲渡所得の内訳書(土地・建物用または総合譲渡用)の作成も必須となります。
添付書類として、売買契約書の写し、取得時・譲渡時の領収書、登記事項証明書などが必要です。特例制度を適用する場合は、戸籍の附票の写し、住民票の写し、耐震基準適合証明書など、特例ごとに指定された書類も準備する必要があります。
・確定申告書(第一表・第二表・第三表)
・譲渡所得の内訳書
・売買契約書の写し
・取得費や譲渡費用の領収書
・登記事項証明書
書類作成の順序としては、まず譲渡所得の内訳書で所得金額を正確に計算し、その後第三表(分離課税用)に転記、最後に第一表・第二表で全体の税額を計算する流れが効率的です。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の指示に従って入力するだけで必要な書類を作成できます。
申告時の注意点を押さえて節税を実現する
確定申告書の作成では、取得費の計上漏れが最も多いミスです。購入代金だけでなく、仲介手数料、登録免許税、改良費なども取得費に含められるため、関連する領収書はすべて確認しましょう。また、建物については減価償却費の計算も必要となりますが、減価償却費はその年ごとの取得費とは別に考慮する必要があります。
特例制度の適用要件を正確に確認することも重要です。居住用財産の3,000万円特別控除では、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限があります。また、軽減税率の特例では、所有期間10年超の判定が売却年の1月1日時点で行われるため、タイミングに注意が必要です。
複数の特例制度が適用可能な場合は、どの組み合わせが最も有利かを慎重に検討します。例えば、居住用財産の買換え特例と3,000万円特別控除は選択適用となるため、将来的な税負担も含めて比較検討する必要があります。特に、特例の選択によって、短期的な利益と長期的な税負担にどのような影響があるかを考慮することが重要です。
申告後の納税についても計画的に準備することが重要です。譲渡所得税は申告期限までに現金で納付する必要があり、多額の場合は延納制度の利用も可能です。住民税は翌年6月から納付が始まるため、資金繰りを考慮した計画が必要です。
確定申告書の提出方法は、税務署への持参、郵送、e-Taxの3つがあります。e-Taxを利用すれば24時間いつでも提出でき、添付書類の省略も可能となるため、積極的な活用をお勧めします。さらに、e-Taxを利用する際には、事前に利用者識別番号や暗証番号の取得が必要となるため、早めの準備を心掛けると良いでしょう。
まとめ|譲渡所得を正しく理解してM&Aを成功に導こう
譲渡所得の正しい理解は、中小企業M&Aを成功に導く重要な要素です。本記事で解説した内容を振り返ると、譲渡所得の基本的な仕組みから特例制度の活用、確定申告の手続きまで、多岐にわたる知識が必要であることがわかります。
特に重要なポイントは、株式譲渡では20.315%の分離課税が適用される一方、事業譲渡では法人税等約34%に加えて個人への配当・退職金にも課税される点です。また、居住用財産の売却では3,000万円特別控除や軽減税率の特例により、大幅な節税効果を期待できます。
中小企業M&Aにおいては、単なる税務知識だけでなく、適切なタイミングでの実行と専門家との連携が成功の鍵となります。譲渡所得の計算、特例制度の適用判定、確定申告の手続きなど、複雑な税務処理を適切に行うことで、手取り額を最大化し、安心してM&Aを完了させることができるのです。
M&Aを検討されている経営者の皆様には、早めに税務面での検討を開始し、必要に応じて税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。なお、私どもM&Aロイヤルアドバイザリー株式会社では、税務面も含めた総合的なM&Aサポートを提供しており、お客様の成功を全力で支援いたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。