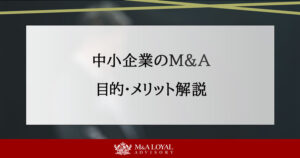個人でも会社を買う方法!個人M&Aのメリットと成功への5ステップ
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
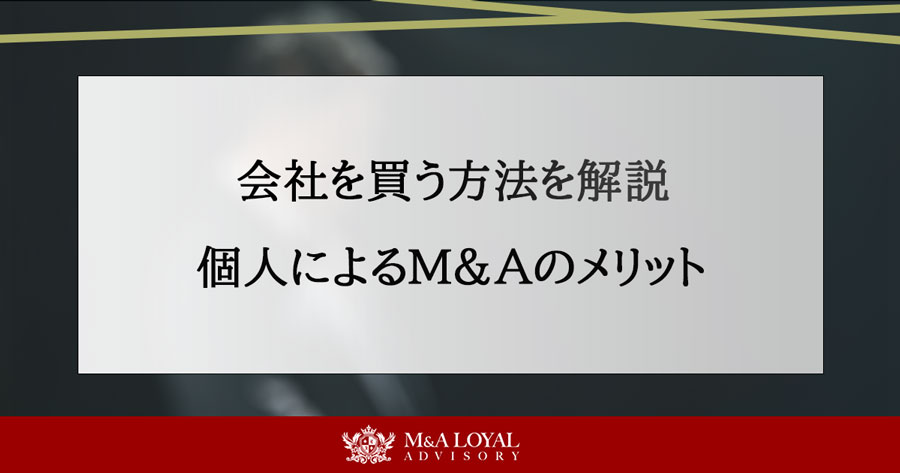
「会社を買う」と聞くと、大企業や投資ファンドが行うイメージがありますが、実は個人でも会社を買うことが可能なのをご存知ですか?近年、経営者の高齢化や後継者不足を背景に、個人による企業買収(個人M&A)が増加しています。
個人M&Aのメリットは、ゼロから起業する苦労を避け、すでに軌道に乗った事業をすぐに手に入れられる点。特に許認可が必要なビジネスでは、大きな時間短縮になります。
一方で、簿外債務の引継ぎや人材流出などのリスクも存在するため、適切な知識と準備が必要です。本記事では、個人でも会社を買うための具体的な手順から、資金調達方法、成功のポイントまで徹底解説します。あなたも新たなビジネスチャンスを掴むため、「会社を買う」第一歩を踏み出してみませんか?
目次
会社を買うことは個人でも可能?近年増加する個人M&A
かつては大企業や中堅企業だけが行うものと思われていたM&A(企業の合併・買収)ですが、近年では個人が会社を買収する「個人M&A」が増加しています。「本当に個人でも会社を買うことができるの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。結論からいえば、個人でも適切な手続きを踏むことで企業買収は十分に可能です。ここでは個人M&Aの基本と最新動向について解説します。
個人M&Aとは?その背景と現状
個人M&Aとは、文字通り個人が会社や事業を買収することを指します。従来は企業間で行われるものというイメージが強かったM&Aですが、この数年で個人による買収が活発化しています。その背景には主に次の要因があります。
まず、経営者の高齢化や後継者不足の深刻化が挙げられます。2024年版中小企業白書によると、多くの中小企業経営者が高齢化し、後継者が見つからない状況が続いています。こうした企業の受け皿として個人買収者の存在感が増しています。
また、新型コロナウイルスの影響で事業環境が変化し、事業売却を検討する経営者が増加したことも要因の一つです。さらに、M&Aマッチングサイトの普及により、個人でも手軽に企業買収の機会にアクセスできるようになりました。
2024年のM&A市場では、日本企業が関与したM&A件数が大幅に増加しています。例えば、MARR株式会社の集計によると、2024年の日本企業関連のM&A件数は4,700件に達し、前年の4,015件から17.1%増加して過去最多を更新しました。
このうち個人M&Aも、案件の小型化や事業承継型M&Aの増加といった市場全体の傾向から増加していると考えられ、市場の裾野が広がっています。
個人が狙いやすい買収対象の特徴
個人がM&Aで狙いやすい企業には、いくつかの特徴があります。まず規模としては、従業員数が少ない小規模企業や個人経営の会社が中心です。価格帯としては、300万円~1,000万円程度の案件が一つの目安となりますが、M&Aマッチングサイトなどでは、より小規模な500万円以下の案件も多数見受けられ、個人でも資金調達が可能な範囲の選択肢は多様です。
業種としては、以下のような特徴を持つ企業が狙い目です。
・飲食店、小売店、サービス業など個人でも運営しやすい業種
・安定した顧客基盤を持ち、すぐに収益が見込める企業
・許認可が必要だが、一度取得すれば強みになるビジネス
・特定の専門スキルや資格を活かせる分野
特に美容室や理容室などの美容業界では、経営者の高齢化と後継者不足が進んでおり、個人M&Aの対象として人気があります。厚生労働省の令和5年度衛生行政報告例(2024年3月末時点のデータ)によると、美容所は27万4,070軒と過去最高を更新する一方、理容所は減少しており、業界再編の動きが顕著です。
必要資金の相場と調達方法
個人M&Aに必要な資金は案件によって大きく異なりますが、小規模な案件では500万円前後から、中規模でも数千万円程度で参入可能なケースが多くあります。ただし、買収資金だけでなく、M&A手続きにかかる諸費用も考慮する必要があります。
M&A仲介会社に依頼する場合、一般的に以下のような費用が発生します。
・相談料:多くの場合は無料だが、有料の場合は5,000円~1万円程度
・着手金:50万円~200万円程度(発生しない場合もある)
・中間金:50万円~200万円程度(発生しない場合もある)
・成功報酬:買収額に応じて変動(レーマン方式で計算されることが多い)
資金調達方法としては、自己資金のほか、日本政策金融公庫の「事業承継・集約・活性化支援資金」などの公的融資制度を活用することができます。また、一部の民間金融機関ではM&A向けの融資商品も提供されています。資金面での不安がある場合は、事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的支援機関に相談することも有効です。
なお、デューデリジェンス(買収監査)のための専門家への依頼費用などの付随コストも考慮する必要があります。一般的に、デューデリジェンス費用は案件の規模や調査範囲に応じて数十万円から数百万円程度かかることが多いですが、M&A仲介会社の手数料に含まれる場合もあります。事前に資金計画を立てておくことが重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



会社を買う5つの主要なメリット
個人が会社を買うということは、決して特別なことではなくなりつつあります。しかも、新規で起業するよりも多くのメリットがあることが注目されています。ここでは、個人M&Aの主要な5つのメリットについて詳しく解説します。これらのメリットを理解することで、自分に合った形での会社経営への道が見えてくるでしょう。
ゼロから立ち上げる苦労を回避できる
新規事業を立ち上げる場合、ビジネスモデルの構築から顧客開拓、設備投資、人材採用まで、あらゆることをゼロから始める必要があります。これには膨大な時間、労力、そして多額の資金が必要です。
一方、既存の会社を買収すれば、すでに事業基盤が整っている状態からスタートできます。具体的には、以下のような苦労を回避できます。
・立ち上げ期の赤字期間を短縮できる
・事業の仕組み化や効率化がすでに進んでいる
・初期投資額を抑えられる場合が多い
・営業許可や各種登録などの手続きがすでに完了している
こうした点から、個人M&Aは起業の「ショートカット」とも言える方法です。すでに走り出している事業をバトンタッチで受け取ることで、経営者としての道のりをスムーズに始められます。
既存の顧客基盤やブランド力をすぐに獲得できる
会社を買うことの大きなメリットの一つが、既存の顧客基盤とブランド力を即座に獲得できる点です。新規事業では、顧客獲得のために多大な時間とマーケティングコストがかかりますが、買収ではその過程を省略できます。
すでに顧客やファンがついている商品・サービスを引き継ぐことで、以下のような利点があります。
・安定した収益基盤がすぐに手に入る
・既存顧客のニーズをすでに把握している状態で事業展開できる
・市場での認知度や信頼性をゼロから構築する必要がない
・マーケティング活動の効率化が図れる
特に長年にわたって築かれた信頼やブランド力は、一朝一夕では構築できない貴重な資産です。買収を通じてこれらを獲得することは、ビジネスを加速させる大きな推進力となります。
許認可が必要なビジネスにも迅速に参入できる
許認可が必要な業種においては、個人M&Aのメリットが特に顕著です。例えば、運送業や旅行業、建設業、医療関連事業などでは、事業開始にあたって様々な許認可が必要となります。これらの取得には数ヶ月から場合によっては数年の時間と、複雑な手続きが必要です。
しかし、すでに許認可を持っている会社を買収すれば、以下のようなメリットがあります。
・許認可取得のための時間的ロスがなく、すぐにビジネスを開始できる
・取得が難しい許認可でも、そのまま引き継げる場合が多い
・許認可申請のための複雑な手続きや要件確認の手間を省ける
・業界特有の規制や制約に対するノウハウもそのまま獲得できる
これらの許認可は参入障壁として機能しているため、逆に言えば競争を制限する効果もあります。そのため、許認可を持つ企業を買収することは、競争の少ない市場へ効率的に参入する戦略ともなります。
短期間での事業規模拡大が期待できる
個人で一から事業を始めた場合、規模の拡大には通常長い時間が必要です。しかし、会社買収を通じて、短期間での事業規模拡大が可能になります。
買収により、以下のような資産やリソースをすぐに手に入れることができます。
・設備や店舗などの物理的資産
・仕入れ先や協力会社などのビジネスネットワーク
・業界ノウハウや専門知識を持った人材
・規模の経済によるコスト削減効果
すでに複数の事業を展開している場合は、買収した企業とのシナジー効果によって、既存ビジネスの拡大や効率化も期待できます。こうした相乗効果を最大化するためには、買収前にシナジーポイントを明確に特定し、買収後の統合計画をしっかりと立てておくことが重要です。
成長後の高額売却や不労所得も視野に入る
会社を買って経営するメリットは、単に事業を運営することだけではありません。将来的な高額売却や継続的な収入源の確保という観点も重要です。
企業価値を高めることで、以下のような中長期的メリットが期待できます。
・買収時よりも高い価格での売却(いわゆる「企業の再販」)が可能になる
・役員報酬や配当による安定的な収入源を確保できる
・事業の仕組み化を進めることで、オーナーとしての不労所得的な要素も生まれる
・資産価値の増大により、さらなる投資や事業展開の資金が得られる
特に事業が軌道に乗り、適切な人材を配置して経営を委託できるようになれば、オーナーとしての立場を維持しながらも、日常的な業務から解放される可能性も広がります。経営者としての経験を積みながら、資産形成の道も開けるのが個人M&Aの魅力と言えるでしょう。
会社を買う際に注意すべきデメリットとリスク
個人M&Aには多くのメリットがある一方で、見落としがちなデメリットやリスクも存在します。会社を買う決断をする前に、これらのリスク要因を十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、個人M&Aの主要なデメリットとリスクについて解説します。
簿外債務など隠れたリスクを引き継ぐ可能性
会社を買収する際に最も注意すべきリスクの一つが「簿外債務」です。これは貸借対照表に計上されていない隠れた債務のことで、買収後に思わぬ負担となる可能性があります。
具体的な簿外債務としては、以下のようなものが挙げられます。
・未払いの残業代や社会保険料
・税務当局とのトラブルや追徴課税のリスク
・公害問題や環境汚染に関する責任
・顕在化していない訴訟リスク
・保証債務や連帯保証
これらのリスクを回避するためには、専門家によるデューデリジェンス(買収監査)を徹底して実施することが不可欠です。また、最終契約書には「表明保証条項」を盛り込み、万が一隠れた問題が発覚した場合の補償を売り手に約束してもらうことも重要な対策です。
買収後の人材流出リスク
会社の買収後、思わぬ形で従業員が離職してしまうリスクがあります。特に企業の価値は人材に大きく依存するケースが多いため、核となる従業員の流出は事業継続に大きな影響を与えかねません。
人材流出が起こる主な理由としては、以下のようなものがあります。
・経営者交代による不安や将来への懸念
・新たな経営方針への不満や適応困難
・買収によるモチベーション低下
・競合他社からの引き抜きなど
このリスクを軽減するためには、買収前から従業員とのコミュニケーションを重視し、将来ビジョンを明確に伝えることが大切です。また、重要な人材については、雇用条件の維持や改善を約束することも検討すべきでしょう。場合によっては、旧経営者に一定期間アドバイザーとして残ってもらうことで、移行期間をスムーズに進める方法もあります。
取引先や顧客からの理解を得ることの難しさ
会社を買収した後、既存の取引先や顧客との関係を維持することは、想像以上に難しい課題となる場合があります。特に中小企業では、取引関係が旧経営者との個人的な信頼関係に基づいていることが多いためです。
取引先や顧客の離反が起こりやすいケースとしては、以下のような状況が考えられます。
・経営者の人柄や専門性を重視していた取引関係
・長年の付き合いによる暗黙の了解や慣習がある場合
・新経営者の経営方針やビジョンに対する不安
・競合他社からの働きかけ
このリスクに対応するためには、買収後すぐに主要取引先への挨拶回りを行い、事業継続の意思と将来ビジョンを丁寧に説明することが重要です。また、可能であれば旧経営者からの紹介や同席をお願いし、信頼関係の橋渡しをしてもらうことも効果的です。顧客基盤を維持することは、買収後の事業成功にとって欠かせない要素なので、十分な配慮と計画が必要です。
事業内容の制限と方向転換の難しさ
会社を買う際には、その会社が行ってきた事業を基本的に継続する必要があります。全く異なる事業への転換は、許認可や既存リソースの面から難しい場合が多いのです。
事業の制限や方向転換の難しさには、以下のような要因があります。
・業界特有の許認可やライセンスの制約
・既存従業員のスキルセットや専門性
・取引先との契約や取引条件の継続性
・設備投資やシステムの既存環境
もし買収後に大幅な事業転換を考えているなら、それが実現可能かどうかを買収前に十分検討することが重要です。場合によっては「事業譲渡」の形で必要な資産や許認可だけを取得する方法も検討すべきでしょう。買収後の自由度をどこまで確保できるかについて、事前に明確なイメージを持つことがトラブル防止につながります。
これらのデメリットやリスクを認識していれば、適切な対策を講じることで多くの問題は回避できます。重要なのは、事前の調査と準備を徹底し、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことです。リスクを理解した上で慎重に進めれば、個人M&Aは依然として魅力的な選択肢となるでしょう。
会社を買う5ステップの具体的手順
個人M&Aを成功させるためには、適切なプロセスを踏むことが重要です。ここでは、会社を買う際の5つの主要ステップについて、具体的な手順とポイントを解説します。これらのステップを理解することで、効率的かつ効果的に買収プロセスを進めることができるでしょう。
買収の目的と戦略を明確に定める
会社買収の第一歩は、自分がなぜ会社を買いたいのか、その目的と戦略を明確にすることです。この段階では以下のポイントを検討しましょう。
・事業目的:新規事業への参入、既存事業の拡大、収益源の多様化など
・予算設定:投資可能な金額と期待するリターン
・業種や規模:自分のスキルや経験を活かせる分野かどうか
・地域:自分が関与しやすい地理的条件
・時間的制約:どのくらいの期間で買収を完了させたいか
目的と戦略を明確にしておくことで、その後の意思決定がスムーズになります。特に買収プロセスの途中で問題が発生した場合、初めに定めた目的に立ち返ることで、冷静な判断ができるようになります。また、効率的なM&Aプロセスを進めるためにも、目標を明確にしておくことが不可欠です。
候補企業を探す
買収の目的と戦略が決まったら、次は条件に合った候補企業を探します。候補企業の探し方には、主に以下の方法があります。
・M&A仲介会社の利用:専門的な知識と豊富な案件情報を持つM&A仲介会社に依頼する
・M&Aマッチングサイトの活用:インターネット上で売却希望企業を検索できるサービス・事業承継・引継ぎ支援センターの活用:公的機関による無料相談サービス
・金融機関や会計士からの紹介:取引のある専門家に相談する
・業界団体や商工会議所のネットワーク:業界内の情報網を活用する
特に個人M&Aの場合は、M&Aマッチングサイトが使いやすい選択肢となるでしょう。これらのサイトでは、自分の希望条件に合った企業を効率的に探すことができます。候補企業を見つけたら、企業の基本情報や財務状況などの初期情報を収集します。この段階では表面的な情報だけでも構いませんが、自分の条件に合っているかどうかの判断材料として整理しておきましょう。
交渉から基本合意書締結までの流れ
候補企業が見つかったら、交渉のプロセスに入ります。この段階では以下の流れで進みます。
- 初期接触:候補企業との最初のコンタクトを取り、興味を伝える
- 秘密保持契約(NDA)の締結:情報交換を行うための守秘義務契約
- 初期情報交換:企業概要や財務情報など基本的な情報の提供を受ける
- トップ面談:売り手企業の経営者と直接会い、互いの考えや理念を確認する
- 基本合意書の締結:基本的な取引条件に合意し、文書化する
基本合意書には、M&Aのスキーム、譲渡価格の目安、今後のスケジュールなどの基本条件が記載されます。特に重要なのは「独占交渉権」と「秘密保持義務」の部分で、これらには法的拘束力を持たせるのが一般的です。基本合意書の締結により、売り手は他の候補者と交渉できなくなり、買い手は安心してデューデリジェンスなどの次のステップに進むことができます。
基本合意書の作成では、M&A専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。特に個人M&Aでは、交渉力や契約書の作成経験に差があることが多いため、専門家のサポートがあると安心です。
デューデリジェンスによる企業価値評価
基本合意書を締結した後は、対象企業の詳細な調査(デューデリジェンス)を行います。デューデリジェンスとは、買収対象企業の資産、負債、契約関係などを詳細に調査し、リスクや企業価値を評価するプロセスです。
デューデリジェンスでは、以下の項目を中心に調査します。
・財務デューデリジェンス:財務諸表の分析、収益性、キャッシュフローの確認
・税務デューデリジェンス:税務申告の適正性、税務リスクの確認
・法務デューデリジェンス:契約関係、訴訟リスク、知的財産権の確認
・事業デューデリジェンス:事業モデル、市場環境、競合状況の分析
・人事デューデリジェンス:人材の質、労務問題、組織体制の確認
デューデリジェンスには専門的な知識が必要なため、公認会計士や弁護士などの専門家に依頼することが一般的です。調査の結果、簿外債務や隠れたリスクが発見された場合は、買収価格の再交渉や条件の変更を検討することもあります。
また、デューデリジェンスと並行して、バリュエーション(企業価値評価)も行います。DCF法やマルチプル法など複数の手法を用いて、適正な買収価格を算出します。
最終契約とクロージング手続きの実施
デューデリジェンスの結果に基づいて最終的な条件を調整し、最終契約書を締結します。最終契約書には以下のような内容が含まれます。
・取引の詳細(株式譲渡、事業譲渡などのスキーム)
・譲渡価格と支払条件
・表明保証(売り手による情報の正確性の保証)
・誓約事項(クロージングまでの行動制限)
・クロージング条件(取引完了のための前提条件)
・補償条項(表明保証違反の際の補償)
最終契約書の締結後、クロージング(決済)の手続きに移ります。クロージングでは、株式の移転や代金の支払いなど、実際の取引を完了させるための手続きを行います。
クロージング後は、実際に会社の経営を引き継ぐことになります。この段階では、従業員への説明や取引先への挨拶、業務の引継ぎなど、スムーズな経営移行のための準備が必要です。また、買収後の統合計画(PMI:Post Merger Integration)を事前に検討しておくことで、経営の一貫性を保ちながら円滑な移行が可能になります。
会社買収の5ステップは、一見複雑に見えるかもしれませんが、各段階で適切に計画を立て、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、個人でも十分に実現可能なプロセスです。特に初めてM&Aを行う場合は、早い段階からM&A仲介会社や専門家に相談することをおすすめします。
会社を買って成功するための3つの重要ポイント
個人M&Aで会社を買う決断をしたなら、次に考えるべきは「買った後にどう成功させるか」です。せっかく買収した会社を成長させ、期待通りの成果を上げるために、特に重要な3つのポイントを押さえておきましょう。
専門家の協力を得て徹底したリスク調査を行う
会社買収の最大のリスクは、表面上は見えない問題を引き継いでしまうことです。このリスクを最小化するには、専門家による徹底したデューデリジェンス(買収監査)が不可欠です。
個人M&Aの場合、特に以下の点に注意した調査が重要です。
・簿外債務の有無(未払い残業代、社会保険料など)
・訴訟リスクや係争中の案件
・税務上の問題(追徴課税のリスクなど)
・重要顧客や取引先との契約状況
・従業員の雇用条件や労務管理状況
これらの調査には、公認会計士や税理士、弁護士など各分野の専門家の協力が必要です。特に個人で初めてM&Aを行う場合は、経験豊富なM&Aアドバイザーに相談し、適切な専門家を紹介してもらうのが効果的です。調査費用は、案件の規模や調査範囲によって異なり、一般的に数十万円から数百万円程度が目安となりますが、M&A仲介会社によっては着手金や成功報酬に含まれる場合もあります。具体的な費用は専門家に見積もりを依頼することが不可欠です。この投資は将来の大きなトラブルを防ぐための保険と考えるべきでしょう。
また、最終契約書には必ず「表明保証条項」を盛り込み、調査で発見できなかった問題が後に発覚した場合の補償について明記することも重要です。専門家の力を借りて、リスクをしっかりと把握した上で買収を進めることが、成功への第一歩となります。
自分の経験とリソースに見合った規模の会社を選ぶ
会社買収で失敗するケースの多くは、買い手の能力やリソースを超えた規模や業種の会社を買ってしまうことに起因します。自分の強みを活かせる分野で、管理可能な規模の会社を選ぶことが極めて重要です。
自分に合った会社を選ぶための主なチェックポイント
・自分の経験やスキルを活かせる業種か
・従業員数や事業拠点の数が管理可能な規模か
・財務的な余裕度(買収後の運転資金や追加投資を含む)
・自分の時間的コミットメントと経営に必要な時間のバランス
・既存事業や本業との両立が可能か(副業として買収する場合)
例えば、飲食業の経験がまったくない方が、いきなり複数店舗を持つレストランチェーンを買収するのはリスクが高いでしょう。まずは自分の経験を活かせる分野で、小規模な会社から始めることをおすすめします。
個人M&Aでは、自分のキャパシティを正直に評価し、無理のない範囲で挑戦することが長期的な成功につながります。
買収後の統合計画と経営戦略を事前に準備する
M&Aの成否を分けるのは、買収後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)です。買収前から具体的な統合計画と経営戦略を準備しておくことで、買収後の混乱を最小限に抑え、スムーズに新体制へ移行することができます。
買収前に準備しておくべき主な計画
・従業員への説明と不安解消のためのコミュニケーション計画
・主要顧客や取引先への挨拶と関係維持の方針
・組織体制や意思決定プロセスの見直し
・短期(100日)・中期(1年)・長期(3年)の経営戦略
・旧経営者からの引継ぎスケジュールと範囲
・業務プロセスや社内システムの統合方針
特に重要なのは人材の維持です。買収後に優秀な人材が流出してしまうと、買収の価値が大きく損なわれる可能性があります。前経営者に一定期間はアドバイザーとして残ってもらう、主要社員との面談を行い不安を取り除くなどの対策を講じることが効果的です。
これら3つのポイントを押さえることで、個人M&Aの成功確率は大きく高まります。専門家の力を借りてリスクを最小化し、自分に合った会社を選び、買収後の道筋を明確に描いておくことが、会社買収で成功するための鍵となるのです。
まとめ|会社を買って新たなビジネスチャンスを掴もう
個人でも会社を買う「個人M&A」は、近年の選択肢として注目されています。ゼロからの起業と比べ、既存の顧客基盤や許認可をすぐに獲得できるメリットがあります。もちろん簿外債務や人材流出などのリスクはありますが、専門家の協力を得ることで最小化可能です。
資金面でも日本政策金融公庫などの融資制度が整備されつつあり、自己資金が少なくても挑戦できる環境が整ってきました。経営者の高齢化や後継者不足による売却案件は今後も増加が予想され、個人M&Aのチャンスは広がっています。
自分のスキルを活かせる事業を選び、適切な準備を整えれば、個人M&Aは新たなビジネスキャリアの扉を開く鍵となるでしょう。この機会に、あなたも会社買収という選択肢を検討してみませんか。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。