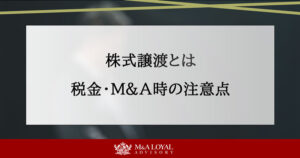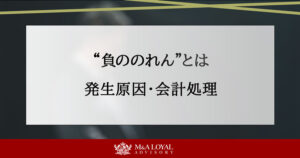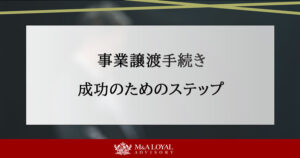事業譲渡の仕訳|のれんや消費税の会計処理も買い手売り手別に解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
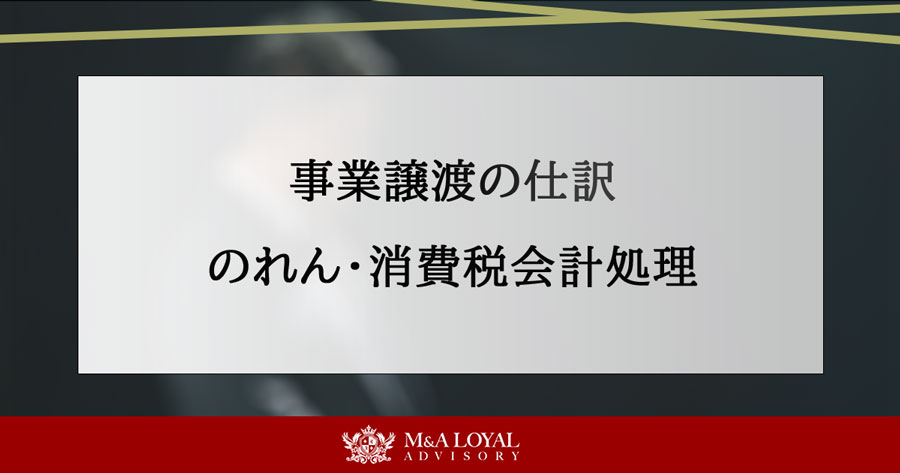
事業譲渡は、企業の資産や負債の移転を伴う複雑なプロセスであり、正確な仕訳を行うことが重要です。しかし、多くの経営者や会計担当者は、これらの詳細な手続きや税務処理に戸惑うことが多いのが現実です。
この課題を解決するために、本記事では、事業譲渡の仕訳と税務処理に関する知識をわかりやすく解説します。ぜひ、この機会に事業譲渡の仕訳と税務処理の基本を学び、よりスムーズな企業運営を実現してください。
目次
事業譲渡とは?基本概念を解説
事業譲渡とは、企業が特定の事業またはその一部を他の企業に譲り渡す行為を指します。この手法はM&Aのスキームの一つであり、企業の再編成や戦略的な方向転換において重要な選択肢となります。
事業譲渡は、譲渡対象が事業単位であることが特徴で、譲渡対象となる事業の資産や負債、契約、従業員などの個別承継が基本となります。この手法は企業の成長戦略やリスク管理の一環として積極的に活用されることが多く、成功させるためには、法的・財務的な側面に加え、人的資源や市場環境への配慮も欠かせません。
事業譲渡と株式譲渡の違い
事業譲渡と株式譲渡は、どちらもM&A(合併・買収)など事業承継に利用される手法ですが、その性質と影響はそれぞれ異なります。両者の違いについて見ていきましょう。
- 事業譲渡:
事業譲渡とは、企業が保有する事業の一部または全体を他の企業や個人に譲渡することを指します。このプロセスでは、譲渡対象となる事業の資産や負債が個別に選定され、売り手から買い手へと移転します。事業譲渡は、特定の事業単位を切り離し、新たな経営者の下で運営を継続することが目的であり、企業全体を譲渡するわけではない点が特徴です。これにより、売り手側は不要な事業を整理し、経営資源を効率的に再配置することが可能になります。
- 株式譲渡:
株式譲渡は企業の所有権を移転する手続きであり、特定の事業ではなく、企業そのものの株式を売買することを指します。株式譲渡では、企業のすべての資産と負債が一括して移転するため、企業全体の支配権が変更されることになります。
株式譲渡に対して、事業譲渡では譲渡する事業の範囲や内容を柔軟に設定できるため、買い手にとっては特定の事業機能や資産を選択的に取得できるメリットがあります。
事業譲渡を選択する理由として、売り手企業が資金調達を目的とする場合や、特定の事業の成長が見込めないために戦略的に撤退を考える場合などが考えられます。また、買い手企業にとっては、既存事業とのシナジー効果を追求したり、市場参入を迅速に図るための手段として用いられることがあります。事業譲渡は、企業の経営戦略において重要な選択肢として位置付けられており、その実行には法的手続きや会計処理の知識が不可欠です。
事業譲渡の対象となる資産と負債の扱い
事業譲渡では、譲渡対象となる資産と負債を適切に評価し、明確に特定することが重要です。
- 資産:土地、建物、設備、在庫といった物的資産だけでなく、ブランド価値や特許、ライセンスなどの無形資産も含まれます。これらの資産の評価は譲渡価格を決定する上で重要な要素です。
- 負債:未払金や借入金、引当金などが含まれます。ただし、負債の移転は契約内容に依存するため、事前に明確な取り決めが必要です。これにより、譲受側が想定外の負債を引き継がないようにすることができます。
さらに、譲渡契約では、どの資産や負債を移転するのかを明確にし、双方が合意することが求められます。契約や許認可が譲渡対象に含まれる場合、これらの引き継ぎや再取得が必要となることもあります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



事業譲渡のメリットとデメリット
事業譲渡には、多くの利点がある一方で、注意すべき課題も存在します。
事業譲渡のメリット
- 事業の選択と集中:非中核事業を譲渡することで、経営資源を中核事業に集中させることができます。
- 新たな市場や技術へのアクセス:譲受側にとっては、新たな事業分野への迅速な参入が可能です。
- 資金調達手段:譲渡側にとっては、得た資金を事業拡大や債務返済に活用できます。
事業譲渡のデメリット
- 評価の難しさ:資産や負債の適切な評価が難しい場合があり、不適切な評価は譲渡価格に悪影響を与える可能性があります。
- 統合リスク:異なる企業文化や組織構造の統合が課題となり、混乱を招くことがあります。
- 法的・税務的手続き:複雑な法的・税務的手続きが必要であり、これに伴うコストや時間の負担があります。
このように、事業譲渡は多くの利点を提供する一方で、慎重な計画と管理が求められる複雑なプロセスであるため、企業はそのメリットとデメリットを十分に理解し、戦略的に判断する必要があります。
事業譲渡時の基本的な仕訳処理
事業譲渡を行う際の仕訳処理は、売り手企業と買い手企業の双方において正確かつ適切に行うことが重要です。仕訳処理が適切でないと、後々の会計監査や税務調査において問題が生じる可能性があります。そのため、各取引の仕訳を慎重に行うことが求められます。
第三者間取引における基本的な仕訳の流れ
事業譲渡における第三者間取引では、売り手企業と買い手企業の間で資産と負債が移転するため、双方の正確な仕訳が必要です。
まず、売り手企業は譲渡する資産と負債を帳簿から除去し、その結果として生じる譲渡益や譲渡損を記録します。譲渡益は、資産の売却価格が帳簿価額を上回る場合に計上され、逆に譲渡損は売却価格が帳簿価額を下回る場合に発生します。譲渡益(譲渡損)の計算には公正価値の評価が欠かせません。
一方、買い手企業は取得した資産と負債を新たに帳簿に計上します。取得する資産の取得価額を決定し、負債についても同様に評価を行います。これにより、買い手企業は譲受資産を適切に記録し、将来の償却計画を立てることができます。また、のれんが発生する場合には、その計上と償却処理が必要となります。
さらに、事業譲渡に関連する仕訳には、消費税の取り扱いも含まれることが多く、資産が消費税の課税対象となる場合には、適切な税務処理が求められます。これにより、税務申告の際に正確な情報を提供し、法令遵守を確保することができます。
このように、第三者間取引における仕訳は、企業の財務状態を正確に反映し、監査や税務調査においても透明性を保つために重要です。企業は、専門家の助言を受けながら、会計基準や税務法令に基づいた正確な仕訳を行うことが求められます。
売り手企業の仕訳と勘定科目の選定
事業譲渡を行った売り手企業は、譲渡取引を財務諸表に正確に反映することが求められます。譲渡される資産の帳簿価額と売却価格を比較し、譲渡益が発生する場合は『譲渡益』を利益として計上します。逆に、譲渡損が発生する場合は『譲渡損』として損失を計上します。
これらの勘定科目の選定にあたっては、公正価値の評価が重要であり、適正な市場価格を基に計算を行う必要があります。公正価値は資産や負債の市場価値を反映するものであり、譲渡価格を決定する際の基準となります。この評価には専門的な知識が必要であり、第三者の評価機関を活用することが推奨されます。
また、資産と負債の除去に際しては、売却対象となる各資産の勘定科目を明確にし、それぞれの帳簿価額を適切に減少させることが必要です。例えば、固定資産を譲渡する場合には、「固定資産売却損益」勘定を利用し、売却損益を計上します。これにより、資産の移動が正確に反映され、後の会計監査においても透明性が確保されます。
買い手企業の仕訳と取得価額の決定
事業譲渡を行った買い手企業は、取得した資産と引き受けた負債を新たに帳簿に計上することが求められます。取得価額の決定にあたっては、各資産の種類や性質に応じた評価方法を適用し、適正な市場価格を反映します。
例えば、土地や建物などの固定資産は、現行の市場価格や鑑定評価を基に評価し、流動資産はその時点での市場取引価格を参考にします。また、負債についても、引き受ける負債の性質に応じて評価を行い、適切な負債額を認識します。
事業譲渡ののれん発生時の仕訳処理
事業譲渡において「のれん」が発生する場合の仕訳処理について解説します。のれんは、企業が他の企業を買収した際に支払った対価と、譲り受けた純資産との差額として認識されます。こののれんは、買収企業の価値を超える無形の資産として会計処理され、主にブランド力や顧客基盤、将来の成長可能性を反映しています。
この無形資産は貸借対照表において『無形固定資産』として計上され、企業の収益力や競争力を向上させる要因として重要です。
会計処理では、のれんは通常、買収完了時に「のれん」勘定を借方に計上し、支払った現金や株式の額を貸方に記入します。この処理により、買収によって得た無形の価値が資産として認識されます。しかし、のれんは定期的な減損テストの対象となり、価値が減少した場合には減損損失として計上しなければなりません。この減損テストは、企業が期待していた収益を達成できているかを評価し、企業の財務状態を正確に反映するために不可欠です。
さらに、のれんの評価は、企業の将来のキャッシュフローや市場環境の変化に依存するため、慎重な管理が求められます。適切な会計処理と減損テストを行うことで、企業の財務諸表の信頼性を確保し、ステークホルダーに対して透明性の高い情報を提供することが可能となります。したがって、のれんの評価と会計処理は、企業の経営戦略と財務報告において非常に重要な役割を果たします。
売り手企業ののれん仕訳例
売り手企業の場合、通常のれんの仕訳を行う必要はありません。これは、事業譲渡においてのれんが買い手企業側に発生する無形資産であるためです。売り手企業は譲渡対価を受け取る際に、譲渡する資産と負債を帳簿から取り崩すことが主な会計処理となります。
具体的な仕訳としては、譲渡資産の帳簿価額を貸方に、譲渡負債を借方に記入し、得た譲渡対価を借方に計上します。その差額は譲渡益または譲渡損として計上され、当期の損益として反映されます。これにより、売り手企業は事業譲渡に伴う財務影響を正確に反映することができます。
具体的な仕訳例(売り手企業の場合)
譲渡益が発生する場合:
借方:現金預金(譲渡対価)貸方:土地、建物、その他の資産(帳簿価額)貸方:譲渡益(譲渡対価-帳簿価額-負債)
譲渡損が発生する場合:
借方:現金預金(譲渡対価)借方:譲渡損(帳簿価額+負債-譲渡対価)貸方:土地、建物、その他の資産(帳簿価額)
売り手企業は、事業譲渡によって得た利益を再投資や債務の返済に充てることができるため、財務戦略の見直しが必要です。また、譲渡によって残存する事業における効率化や収益性の向上を図ることが求められます。売り手企業は譲渡後のキャッシュフローの管理を徹底し、譲渡による財務的な変化に対応するための計画を立てることが重要です。
買い手企業ののれん仕訳例
買い手企業におけるのれんの仕訳処理は、事業譲渡後の財務報告において重要な役割を果たします。買い手企業は、買収に伴い支払った対価と譲り受けた純資産との差額としてのれんを認識し、これを無形固定資産として貸借対照表に計上します。
具体的な仕訳例としては、買収が完了した時点で「のれん」勘定を借方に計上し、対価として支払った現金や発行した株式の金額を貸方に記入します。この仕訳により、買収によって得られた無形の資産価値が企業の財務状況に反映されます。
具体的な仕訳例(買い手企業の場合)
ケース:
- 譲受資産の公正価値:5,000万円
- 譲受負債の公正価値:2,000万円
- 支払った対価:6,000万円
- のれん:6,000万円 − (5,000万円 − 2,000万円) = 3,000万円
仕訳:
借方:土地、建物、その他の資産(公正価値) 5,000万円借方:のれん 3,000万円貸方:現金預金(支払対価) 6,000万円貸方:負債(公正価値) 2,000万円
のれんの計上後は、定期的な減損テストが不可欠です。減損テストは、のれんの帳簿価額が実際の価値を上回っていないかを確認するためのプロセスであり、価値の下落が確認された場合には減損損失として計上されます。この処理は、企業の財務諸表が市場環境の変化や経営計画の修正を反映し、正確性と透明性を保つために重要です。
買い手企業は、のれんの評価を通じて将来のキャッシュフローや市場環境の変動に対処する必要があります。適切な仕訳と評価を行うことで、企業の財務状況が正確に報告され、ステークホルダーに対して信頼性の高い情報を提供することが可能となります。したがって、買い手企業ののれん仕訳例は、企業の戦略的意思決定や財務健全性に大きな影響を与える重要な要素となります。
事業譲渡の負ののれん発生時の処理
負ののれんとは、買い手企業が取得した事業や資産の公正価値が取得価額を上回る場合に生じる差額を指します。これは、取得価額が純資産価額よりも低い場合に発生し、買い手企業にとっては特別利益として計上されることが一般的です。負ののれんが発生する原因には、売り手側の財務的困難、事業の将来性の低評価、または市場の動向による急激な価値変動などが考えられます。
売り手企業の仕訳例
事業譲渡において負ののれんが発生する場合、売り手企業は譲渡価格が資産の簿価を下回る状況に直面します。この場合、売り手企業はその差額を「譲渡損」として損失計上しなければなりません。具体的な仕訳例としては、まず譲渡された資産の簿価を貸方に計上し、譲渡価格を借方に記録します。差額が生じた場合、その差額は「事業譲渡損失」などの適切な勘定科目を用いて損失として計上されます。
具体的な仕訳例
ケース:
- 資産の簿価:1,000万円
- 譲渡価格:800万円
- 譲渡損:1,000万円 − 800万円 = 200万円
仕訳:
借方:現金預金(譲渡価格) 800万円借方:譲渡損 200万円貸方:土地、建物、その他の資産(帳簿価額) 1,000万円
この仕訳により、譲渡価格と資産の簿価との差額が損失として計上され、財務諸表に反映されます。
買い手企業の仕訳例
買い手企業が事業譲渡において負ののれんを認識する場合、取得した資産と負債を公正価値で計上した後、支払った対価との差額を特別利益として処理します。具体的な仕訳例としては、取得した資産を借方に、取得した負債と支払った対価を貸方に記録し、その差額を負ののれんとして特別利益の項目で計上します。
具体的な仕訳例
ケース:
- 取得資産の公正価値:5,000万円
- 取得負債の公正価値:2,000万円
- 支払った対価:4,500万円
- 負ののれん:5,000万円 − 2,000万円 − 4,500万円 = 500万円
仕訳:
借方:土地、建物、その他の資産(公正価値) 5,000万円貸方:現金預金(支払対価) 4,500万円貸方:負債(公正価値) 2,000万円貸方:特別利益(負ののれん) 500万円
この仕訳により、取得した資産と負債が帳簿に正確に反映され、負ののれんは特別利益として損益計算書に計上されます。
この特別利益は、企業の利益計算に大きく寄与し、資本効率や財務指標を改善する要素となります。ただし、負ののれんが発生する背景には、売り手企業の財務的な問題や市場の変動が関連している場合があるため、買い手企業はこれらの要因を慎重に評価し、将来的なリスク管理に活用することが重要です。
事業譲渡における法人税・消費税
事業譲渡における法人税と消費税の仕訳は、企業の財務処理において重要な要素です。
法人税の取り扱い
売り手企業は、譲渡による利益を損益計算書に計上し、これに対して法人税が課されます。譲渡益は、譲渡価格から資産の帳簿価額を差し引いた金額として計算されます。たとえば、以下の仕訳が行われます。
- 借方:現金預金(譲渡価格)
- 貸方:土地、建物、その他の資産(帳簿価額)
- 貸方:譲渡益
一方、買い手企業は取得した資産を公正価値で認識し、減価償却資産については適切な耐用年数に基づいて償却を行います。
消費税の取り扱い
譲渡対象が消費税の課税対象かどうかを確認することが重要です。課税対象には商品在庫や設備が含まれますが、土地や一部の金融商品は非課税です。
- 売り手企業:課税資産の譲渡に伴い発生する消費税を「仮受消費税」として計上し、申告・納付を行います。
- 買い手企業:仕入れにかかる消費税を「仮払消費税」として計上し、後に仕入税額控除として処理します。
消費税の対象となる資産とそうでない資産
事業譲渡においては、消費税の課税対象となる資産と非課税資産を明確に区分することが重要です。消費税の対象となる資産には、通常、動産やサービスの提供が含まれます。これには、機械設備、在庫商品、営業権など、明確に取引が行われているものが該当します。
一方、土地や一部の金融商品、株式などは消費税の非課税資産として扱われます。これらの区分は、売り手企業と買い手企業の双方にとって、譲渡の際の正確な会計処理と税務申告を行うために不可欠です。売り手企業は、消費税が課される資産を譲渡した際に、売上高と消費税預かり金を正確に計上する必要があります。これにより、税務申告における混乱を避け、適切な税金の納付を確保します。
買い手企業側では、取得した資産に対して支払った消費税を仮払消費税として計上し、後に控除可能な場合は、適切な申告手続きを行います。控除可能な消費税額を正確に把握するためには、取得価額に消費税が含まれているかを確認することが重要です。
また、消費税の控除可能性については、税務上の要件を満たしているかを確認し、専門家の助言を受けることが推奨されます。これにより、誤った税務処理を避けることができ、事業譲渡後の税務リスクを軽減することが可能です。適切な消費税の取り扱いを行うことにより、事業譲渡における会計処理がスムーズに進み、企業運営の安定性を確保します。
売り手企業の消費税仕訳例
売り手企業が事業譲渡を行う際、譲渡する資産が消費税の課税対象となる場合には、消費税の仕訳処理を正確に行うことが求められます。ただし、事業譲渡全体が消費税の課税対象外となる場合もあるため、取引形態に応じた課税対象の確認が重要です。
具体的な仕訳例
ケース:
- 譲渡資産の売上高:1,000万円
- 消費税率:10%
- 消費税額:100万円
仕訳:
借方:現金預金 1,100万円(1,000万円+100万円)
貸方:売上 1,000万円
貸方:仮受消費税 100万円
この仕訳により、譲渡した資産の売上高と消費税の預かり金が明確に記録されます。
消費税の納税プロセス
- 仮受消費税の記録 売り手企業は課税資産の譲渡に伴い消費税を「仮受消費税」として記録します。
- 未払消費税への振替 消費税の納税が必要な場合、譲渡完了後に「仮受消費税」勘定から「未払消費税」勘定へ振替を行い、納税額を確定します。
- 消費税の納付 「未払消費税」勘定を用いて納税処理を行い、財務諸表に反映します。
買い手企業の消費税仕訳例
事業譲渡において、買い手企業は取得した資産に関連する消費税を適切に仕訳処理する必要があります。消費税の正確な会計処理は、税務申告の際に控除を受けるための基盤となります。
1. 仮払消費税の計上
買い手企業は、取得した資産に対する消費税を「仮払消費税」として計上します。これにより、消費税申告時に仕入税額控除が可能になります。
具体例:
- 資産の取得価額:1,000万円
- 消費税率:10%
- 仮払消費税:100万円
仕訳:
借方:土地、建物、その他の資産 1,000万円
借方:仮払消費税 100万円
貸方:現金預金 1,100万円
2. 仮払消費税の管理
「仮払消費税」は、消費税申告時に控除されることを見越して帳簿上で明確に管理されます。これにより、税務申告時に正確な控除を行うことが可能となり、企業のキャッシュフローへの影響を最小限に抑えることができます。
3. 資産取得価額の確認
取得した資産については、消費税が含まれているかどうかを確認し、その内容を会計処理に反映させることが重要です。消費税が含まれていない場合、取得価額は消費税を除いた金額として計上されます。
事業譲渡における税務上の注意点
事業譲渡は、企業が特定の事業またはその一部を他の企業に売却するプロセスで、これには複雑な会計および税務上の手続きが伴います。正確な仕訳は、税務リスクを最小限に抑え、事業譲渡を円滑に進めるために不可欠です。ここでは税務上の注意点について解説します。
法人税の課税ポイント
売り手企業は、譲渡益に対する法人税負担を考慮しなければなりません。譲渡益は売却価格から資産の帳簿価額を差し引いたもので計算されます。買い手企業は、事業資産の取得価額を正確に設定し、将来的な減価償却に影響を与える法人税計算を行います。
のれん・資産/負債調整の税務処理
- のれんは、買い手が支払った価格が純資産価額を上回る場合に発生し、一定期間で償却されます。
- 負ののれんは、支払価格が純資産価額を下回る場合に発生し、即時に収益として計上される場合があります。
不動産取得税やその他の関連税金
- 不動産が含まれる場合、買い手企業は不動産取得税を考慮する必要があります。
- 登録免許税や印紙税などの関連税金も考慮することが不可欠です。
減価償却資産と耐用年数の算出方法
- 買い手企業は、取得した資産の耐用年数を正確に設定し、減価償却を適切に行う必要があります。
非課税売上や消費税の取扱い
- 非課税資産と課税資産を正確に区分し、消費税申告に影響を与えない適切な処理を行います。
まとめ
事業譲渡の仕訳の理解は、企業の資産や負債の移転を適切に処理するために非常に重要です。正確な会計処理を行うことで、税務上の問題を未然に防ぎ、企業の健全な経営を支えることができます。この記事で解説した内容を参考に、のれんや消費税の仕訳をしっかりと理解し、必要な手続きをスムーズに進めてください。
もし、事業譲渡の仕訳についてさらに詳しく知りたい場合や、実際の処理に不安がある場合は、専門の税理士や会計士に相談することをお勧めします。彼らの専門知識を活用することで、より正確で効率的な会計処理を行うことができるでしょう。まずは小さな疑問からでも、積極的に解決していくことが、企業の成長につながります。
事業譲渡を含むM&Aや経営課題関するお悩みはぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。