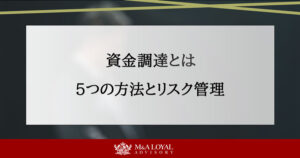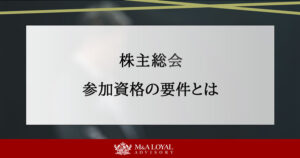割当株式とは?株主割当増資のメリット・デメリットと手続きの流れ
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
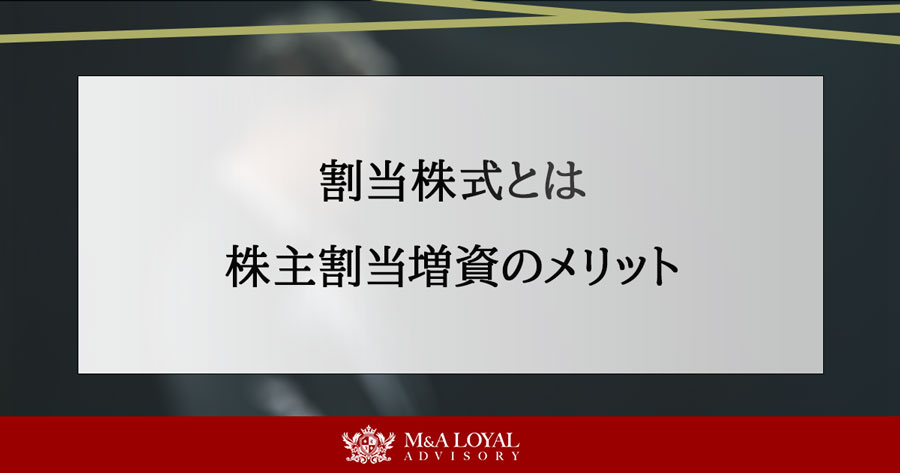
割当株式とは企業が増資を行う際に既存の株主に割り当てる株式のことで、企業は新株発行によって会社の資金調達を効率的に行いながら、既存の株主との関係を維持することができます。
この記事では、割当株式の基本的な理解から株主割当増資の仕組みや手続きの流れ、メリットとデメリット、さらには注意点までを網羅的に解説します。
目次
割当株式とは?概要と基本知識
割当株式とは、企業が新たに株式を発行する際に、既存の株主に対してその株式を優先的に割り当てられる株式を指します。割当株式を用いた資本増強の手法を「株主割当増資」と呼びます。
割当株式の特徴
割当株式の特徴として、まず既存株主の持株比率が維持される点が挙げられます。新株の発行により株式数が増加することから、通常は既存株主の持ち分が希薄化するリスクがありますが、割当株式ではあらかじめ定められた割合で新株を購入できるため、このリスクを緩和することができます。
さらに、割当株式は通常、割引価格で提供されることが多く、既存株主は市場価格よりも低い価格で新株を取得することが可能です。また、企業にとっては、既存株主に対する信頼関係を強化し、資金調達を円滑に進める手段となります。
しかしながら、割当株式の発行には慎重な判断が求められます。新株発行が過度に行われると、株価に悪影響を及ぼす可能性もあるため、企業は株式市場の状況や投資家の反応を考慮する必要があります。
株主割当増資の定義と目的
株主割当増資は企業が新たに発行する株式を既存の株主に優先的に割り当てる増資手法で、企業が成長や新たなプロジェクトを実施するための資金を調達する際に、既存株主の支持を得ることを目的としています。
株主割当増資の最大の特徴は、既存株主の持ち株比率を維持しつつ、企業の資金調達を可能にするという点です。これにより、株主は相対的な影響力を失わずに、企業の成長に貢献することができます。
さらに、株主割当増資は、企業と株主の信頼関係を強化する役割も果たします。既存株主に対して優先的な権利を与えることで、株主の企業に対するコミットメントを高め、長期的な関係の構築を促進します。また、割引価格で新株を提供することが多いため、株主にとっても魅力的な投資機会となります。一方で、企業は資金調達をスムーズに行うことができ、資金調達コストの削減にも寄与します。
しかし、株主割当増資を実施する際には、企業は市場の状況や株主の反応を慎重に見極める必要があります。新株発行による潜在的な株価の変動リスクや、株式の過剰供給による市場の混乱を避けるため、計画的な実施が求められます。この増資手法は、企業の資本政策において重要な選択肢の一つであり、その目的や意義を十分に理解することが成功の鍵となります。
株主割当増資の仕組みと割当株式数
株主割当増資では、既存株主に対してその持ち株数に応じて新株を割り当てる仕組みが採用されます。具体的には、各株主の持ち株数に基づいて割当株式数が決定され、通常は均等に割り当てられることが一般的です。これにより、株主は自身の持ち株比率が大きく変動しないように保護されます。
例)持ち株10株につき新株1株の場合
- 既存株200株持つ株主:新株20株
- 既存株80株持つ株主:新株8株
- 既存株20株を持つ株主:新株2株
割当株式では、この割合を株主ごとに変えることはできない点に注意が必要です。
この仕組みのメリットは、既存株主が企業の成長に伴う利益を引き続き享受できる点です。また、新株を取得することで、株主は企業の戦略的な方向性に対して支持を示し、長期的な利益を見込むことができます。しかし、株主が新株を購入しない場合、持ち株比率の希薄化が発生する可能性があるため、その点は注意が必要です。
企業側にとっても、既存株主の投資意欲を刺激し、資金調達をスムーズに進めることができるため、戦略的な資金運用の一環として重要な役割を果たします。ただし、このプロセスが成功するためには、企業は株主に対して適切な情報提供を行い、透明性を確保することが求められます。
株主割当増資と第三者割当増資との違い
株主割当増資と第三者割当増資の違いは対象が既存株主のみかどうかにあります。株主割当増資が既存株主に新株を優先的に割り当てるのに対し、第三者割当増資は、特定の第三者、つまり既存株主以外の投資家や企業に新株を割り当てることができます。この違いにより、両者は企業の資金調達戦略において異なる役割を果たします。
第三者割当増資の主な特徴は、資金調達と同時に戦略的な提携関係を築ける点です。この手法は、M&A手法の一つとしても活用され、新たなビジネスパートナーを迎え入れたり、特定の技術や市場へのアクセスを得るために採用されることも多くあります。ただし、既存株主にとっては持ち株比率の希薄化が生じやすい点に留意する必要があります。
株主割当増資と第三者割当増資は、それぞれ異なる特徴があるため、企業は自社の状況や市場環境を考慮し、最適な増資方法を選択することが大切です。
株主割当増資と公募増資との違い
公募増資は、一般投資家を対象に新株を広く募集する方法です。第三者割当増資は特定の第三者であるのに対し、公募増資は不特定多数の投資家に新株を募集する方法で、広範囲な資金調達が可能です。市場における株式の流動性が向上しやすく、企業が多くの資金を調達したい場合に有効です。
ただし、市場全体から新たに資金を集めるため、既存の株主は持ち株比率が希薄化するリスクがあります。また、公募増資は株式市場に大きな影響を与えることがあり、株価が変動する要因ともなります。そのため、企業は公募増資を行う際には、タイミングや市場の状況を慎重に考慮する必要があります。
両者を比較すると、株主割当増資は企業と現株主との関係を重視する場合に選ばれます。一方、公募増資は、より広範な資金調達が可能であり、企業の成長戦略や大規模なプロジェクトの実現に向けて有効です。それぞれの増資方法には独自のメリットとデメリットがあり、企業は自社の状況や資金調達の目的に応じて最適な手法を選択することが重要です。
| 増資の種類 | 説明 |
|---|---|
| 株主割当増資 | 既存の株主に対して新しい株式を割り当てる増資方法。 |
| 第三者割当増資 | 特定の第三者に対して新しい株式を割り当てる増資方法。 |
| 公募増資 | 一般の投資家を対象に公募して新しい株式を発行する増資方法。 |

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株主割当増資の手続き・流れ
割当株式の発行および株主割当増資を行う際の一連の流れについて解説します。
- 取締役会または株主総会の決議
- 募集事項の決定と公示
- 募集株式の申込と株主への割当
- 出資の履行と登記変更
取締役会または株主総会の決議
株主割当増資の実施には、まず取締役会および株主総会での決議が必要です。取締役会では、増資の目的や必要性、発行する株式の数や価格、具体的なスケジュールについて詳細に検討されます。この段階で、株主割当増資が会社の戦略目標にどのように寄与するかを明確にし、取締役間での合意を形成することが重要です。
次に、取締役会での決議事項は株主総会に持ち込まれます。株主総会では、株主に対して増資の意図と詳細が説明され、賛否を問う投票が行われます。ここでの決議は特別決議と呼ばれ、通常、出席株主の3分の2以上の賛成が必要です。この手続きは、既存株主に対する公平性を確保し、彼らの持株比率や権利が適切に保護されることを保証するために不可欠です。
取締役会および株主総会での決議が完了した後、会社は増資の具体的な手続きを進めることができます。この段階で、法的な文書の作成や必要な届け出が行われ、正式に増資のプロセスが開始されます。これにより、株主割当増資が法的に適切かつ透明性のある形で進行し、全ての関係者がその目的と影響を理解した上で協力できる体制が整えられます。
なお、公開会社では取締役会、非公開会社は株主総会で募集事項を決定します。ただし、定款で定めがある場合は株主総会での決議は不要となり、取締役会の決議で決めることができます。募集事項の決定と公示
取締役会および株主総会で増資が承認された後、次に行うのは募集事項の詳細な決定とその公示です。募集事項には、新たに発行される株式の数、発行価格、申込期日、払込期日など、増資に関する具体的な条件が含まれます。これらの要素は会社の資本政策に直結するため、慎重に決定される必要があります。特に発行価格は、市場価格との整合性を保ちながら、既存株主の利益を損なわないように設定されます。
募集事項の決定後、これらの情報は法令に基づき公示されます。公示は、株主に対する情報提供の透明性を確保し、投資判断を促すために不可欠です。通常、会社のホームページや電子公告、さらには全国紙などの媒体を通じて公示されます。このプロセスにより、既存株主をはじめとする関係者全員が増資の詳細を把握できるようになります。
さらに、公示された募集事項は、株主や市場の反応を見極める指標にもなります。市場環境や株主の反応に応じて、会社は迅速に対応策を講じることが可能です。これにより、株主割当増資が予定通りに進行するだけでなく、株主や投資家との信頼関係を築く一助ともなります。
なお、既存株主への通知は引受申込の2週間前までに行う必要があります。
募集株式の申込と株主への割当
募集株式の申込と株主への割当フェーズでは、募集事項に基づいて株主が新株の申込を行い、その後、会社が各株主に対して新株を割り当てます。具体的には、まず株主は事前に公示された条件に従って、指定された期間内に申込手続きを完了させる必要があります。申込の際には、通常、申込株数や払込金額の確認が必要であり、これにより株主は自己の持ち株比率を維持しつつ、追加の投資を行うことが可能になります。
申込が完了すると、会社は各株主の申込内容に基づいて、新株をどのように割り当てるかを決定します。株主割当増資の場合、通常、既存の持ち株比率に応じた割当が行われるため、株主の相対的な持ち株比率が大きく変動することはありません。
出資の履行と登記変更
割当の決定後、会社は株主に対して正式な通知を行い、払込金の受領を確認します。出資の履行は、通常、定められた払込期日までに完了しなければならず、この期日を過ぎると増資に参加できなくなります。出資が確認されると、会社は資本金の増加を正式に認識し、これが会社の財務基盤を強化する一助となります。
その後、新株を発行し、登記変更の手続きが行われます。これは、法務局において会社の登記簿に変更を加えることで、増資が法的に有効であることを公的に証明する必要があります。この手続きには、増資の内容を示す詳細な書類や、株主からの払込金を示す証拠書類が必要です。登記変更は、効力が発生してから2週間以内に行うことが会社法で定められています。
登記が完了すると、増資は正式に成立し、会社の資本金が増加します。この過程を通じて、会社は新たな資本を得て、事業拡大や新規プロジェクトへの投資を進めることが可能となります。また、登記変更後は、株主や投資家が会社の新たな資本構成を確認できるようになり、これがさらなる投資の呼び水となることもあります。
株主割当増資のメリットとデメリット
株主割当増資のメリットとデメリットを見ていきましょう。
株主割当増資のメリット
株主割当増資は、企業が資金調達を行う際に既存株主に新たに発行する株式を優先的に割り当てる方法です。この手法にはいくつかのメリットがあります。
- 持株比率の維持が可能
- 割安な価格での新株取得
- 友好的な株主基盤の維持
持株比率の維持が可能
株主割当増資では、既存株主に対して比例的に新株を割り当てるため、持株比率を維持することができます。通常、新株が発行されると持株比率は希薄化するリスクがありますが、この方法を用いることで、株主は自身の持株比率を維持しながら新株を購入できます。これにより、企業の経営に対する影響力を保ちながら成長に貢献することが可能です。
割安な価格での新株取得
株主割当増資で発行される新株は、通常、現在の市場価格よりも低い価格で提供されることが多く、既存株主は割安な価格で新株を取得できます。これにより、長期的な投資価値が高まる可能性があり、株主にとっては魅力的な投資機会となります。
友好的な株主基盤の維持
企業にとって株主割当増資は、友好的な株主基盤を維持するための有効な手段です。既存株主に新たな株式を優先的に提供することで、株主との関係が強化され、安定した経営基盤を築くことができます。これにより、投資家との信頼関係を深め、将来的な資金調達の可能性を広げることが可能となります。
以上のように、株主割当増資は、持株比率の維持や割安な価格での新株取得など、企業と株主双方にとって有利な資金調達手段となり得ます。これらの特性を理解し、戦略的に活用することが企業経営において重要です。
株主割当増資のデメリットとリスク
株主割当増資にはいくつかのデメリットやリスクがあります。
- 株価への影響
- 既存株主の資金準備負担
- 手続きの複雑さと時間
- 市場環境の影響
株価への影響
株主割当増資は既存株主に新株を割り当てる方法であるため、発行株式数が増加します。これにより一株当たりの利益(EPS)が希薄化し、場合によっては株価が下落する可能性があります。株価の下落は投資家の信頼を損なうリスクがあり、企業の資金調達能力や市場での評価に影響を与えることがあります。
既存株主の資金準備負担
株主割当増資を実施する際には、既存株主が新株を引き受けるための資金を準備する必要があります。全ての株主が追加の資金を提供できるとは限らず、その結果として一部の株主が新株を引き受けられない場合、持株比率が変動してしまう可能性があります。これが株主間の不均衡を生み出し、企業のガバナンスに影響を与えるかもしれません。
手続きの複雑さと時間
株主割当増資は通常、発行手続きに時間と手間がかかります。取締役会や株主総会での承認が必要になるため、迅速な資金調達が求められる場合には適していないかもしれません。この手続きの複雑さが、資金調達の機会を逃すリスクを高める可能性があります。
市場環境の影響
市場環境が悪化している時期に株主割当増資を行うと、投資家の関心が低下し、新株が期待通りに引き受けられないリスクもあります。これにより、企業が計画した資金調達額を確保できない場合があり、事業計画に支障をきたす可能性があります。
これらのリスクを十分に考慮し、適切なタイミングと戦略をもって株主割当増資を行うことが重要です。企業は株主とのコミュニケーションを強化し、増資の目的とメリットを明確に伝えることで、株価への悪影響を最小限に抑える努力が求められます。
実施時の注意点と増資方法の比較
株主割当増資を実施する際には、いくつかの注意点があります。
発行可能株式数の確認
発行可能株式数とは、会社が定款で定めた最大の株式発行数のことで、これを超えて新株を発行することはできません。したがって、増資を検討する際は、まず現時点での発行済株式数と発行可能株式数を比較し、余裕があるかどうかを確認する必要があります。この確認を怠ると、増資を進められないばかりか、企業の成長戦略に支障をきたす可能性があります。
株価への影響
さらに、株主割当増資が株価に与える影響も慎重に考慮しなければなりません。新株の発行により発行済株式が増加するため、1株あたりの価値が低下し、一時的に株価が下落するリスクがあります。そのため、増資の内容やタイミングは戦略的に決定する必要があります。
企業は市場の状況や投資家の反応を予測し、株主との適切なコミュニケーションを図ることが求められます。
まとめ
割当株式を活用することで、中小企業は資金調達の柔軟性を高めることができます。この手法は、既存株主の持株比率を維持しつつ、新たな資金を効率的に集めるための有効な手段です。
しかし、実施にあたっては株価への影響や手続きの複雑さに注意が必要です。株主割当増資を活用した資金調達を成功させるためには、基本的な知識をしっかりと理解し、会社の状況に最も適した方法を選ぶことが大切です。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。