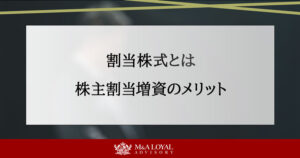新株予約権とは?メリットや種類、ストックオプションとの違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
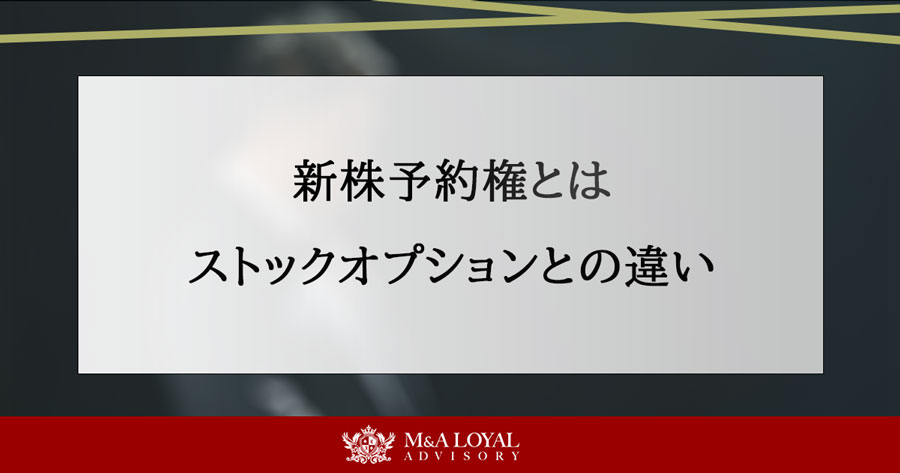
新株予約権とは、企業が資金調達や経営戦略の一環として発行する重要な仕組みであり、従業員や役員へのインセンティブ、M&Aにおける交渉手段、さらには敵対的買収の防衛策としても活用されます。
一方で、株主の持株比率の希薄化や株価下落リスクなどのデメリットも伴うため、新株予約権とはどういうものかという正しい理解が不可欠です。
本記事では、新株予約権とは何か、その基本的な仕組みから種類、メリット・デメリット、ストックオプションとの違い、発行や行使の実務に至るまでを詳しく解説し、実務での活用イメージを明確にしていきます。
目次
新株予約権とは
まず、新株予約権について分かりやすく解説します。
新株予約権の基本
新株予約権とは、将来に特定の条件で会社の株式を購入できる権利のことです。この権利を持っているからといってすぐに株を持っているわけではなく、実際に株を手に入れるには「行使」という手続きを行う必要があります。
例えば、新株予約権を持っていると、株価が上がる前に決まった価格で株を買うことができます。具体的には、1株を100円で買える権利を持っているとします。その後、株価が150円に上がったときにこの権利を行使すれば、100円で株を買って、すぐに150円で売ることができ、その差額である50円が利益になります。これが新株予約権を利用するメリットです。
また、新株予約権の保有者は、その権利を行使するかどうかを自由に選択できます。行使期間内に権利を使わなかったとしても不利益はなく、例えば株価が行使価格の100円を下回った場合には、あえて行使せずに見送ることで損失を回避できます。
ストックオプションとの違い
新株予約権は、従来の転換社債(CB)の転換権部分やワラント、そしてストックオプションなどを含む総称として位置付けられています。
このうちストックオプションは新株予約権の一形態であり、特に役員や従業員に対して報酬やインセンティブとして付与されるものです。したがって、両者は異なる制度ではなく、新株予約権という広い枠組みの中にストックオプションが含まれる関係にあります。
ストックオプションのついては後述します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



新株予約権の目的・メリット
企業が新株予約権を発行する主な目的は次の4つです。
- 従業員・役員のインセンティブ設計
- M&Aでのインセンティブ設計
- 資金調達
- 敵対的買収の防衛
それぞれを詳しく解説します。
従業員・役員のインセンティブ設計
新株予約権の最も代表的な活用方法は、従業員や役員に対するインセンティブとして付与するケースです。
通常の給与や賞与は短期的な成果に基づいて支給されますが、新株予約権は株価の上昇に応じて利益を得られるため、会社の中長期的な成長と密接に結びついています。例えば、株価が上がれば従業員は権利を行使することで大きな利益を得られ、その利益は自らが会社に貢献した結果だと実感できます。こうした仕組みは、従業員に会社の一員である意識やオーナーシップを芽生えさせ、経営陣と従業員が同じ方向を向いて企業価値の向上に取り組む土台になります。
また、優秀な人材を引き留める手段としても効果的であり、競合他社への流出を防ぐ「リテンション策」として機能します。さらに、新しい人材を採用する際にも、将来的なリターンを提示できる点は大きな魅力となり、採用市場での競争力を高められます。
M&Aでのインセンティブ設計
企業の合併や買収の際には、対象企業の経営陣やキーパーソンのモチベーションをどう維持するかが大きな課題です。買収直後は組織文化の違いや将来への不安から、優秀な人材が離職するリスクが高まります。
そこで新株予約権を付与することによって、彼らが統合後の会社に残り、積極的に成果を出すよう動機付けることができます。具体的には、買収後に一定期間会社に残り、業績目標を達成した場合に新株予約権を行使できるといった条件を設けることで、経営陣や従業員がM&A後の成長戦略に一体感を持って取り組むことができます。
M&Aは企業の成長にとって大きなチャンスである一方で、組織内の不安や摩擦が業績悪化につながるリスクも抱えています。そのため、新株予約権を通じてキーパーソンのモチベーションを維持し、人材の定着と統合プロセス(PMI)の円滑化を実現することは非常に重要です。
資金調達
新株予約権は資金調達手段としても重要な役割を果たします。
企業は新株予約権を発行し、投資家に有償で販売することで、即時に資金を調達できます。また、将来的に投資家が新株予約権を行使すれば、その時点で行使価格に応じた資金が会社に流入します。つまり、発行時点と行使時点の二段階で資金調達の機会を確保できる柔軟な仕組みです。
この方法は、銀行融資や社債発行と比べて返済義務がなく、企業の財務負担を軽減できる点が大きなメリットといえます。
新株予約権は条件設定次第で柔軟に設計できるため、成長過程にある企業にとっては有力な資金調達手段です。特にベンチャー企業やスタートアップにとっては、投資家にとってもリスクを抑えつつ将来的なリターンを期待できるため、資金調達を成功させやすい点で有効です。
敵対的買収の防衛
新株予約権は、いわゆる「ポイズンピル」として敵対的買収の防衛策にも利用されます。ポイズンピルとは、企業が敵対的買収から自社を守るための戦略で、買収提案を受けた際に株主に特別な権利を付与することで、買収者の株式取得を困難にする手法です。
敵対的買収者が市場で大量の株式を取得し、会社の支配権を握ろうとする場合に備えて、あらかじめ既存株主に対して新株予約権を割り当てておきます。これにより、買収者が一定の割合を超えて株式を取得した際には既存株主が新たに株式を取得できる仕組みが働き、買収者の持株比率を相対的に下げられます。
結果として、買収者は簡単には経営権を握れなくなり、望まない買収から会社の独立性を守れます。この方法は、株主や従業員、さらには取引先の利益を保護する点でも有効です。
新株予約権の注意点・デメリット
新株予約権の注意点や主なデメリットは次のとおりです。
- 既存株主の持株比率が希薄化する可能性がある
- 株価下落リスク
- 行使されなければ資金調達効果が得られない
- 公平性の問題
- 導入・運用コストの負担
- 経営者の乱用リスク
それぞれを詳しく解説します。
既存株主の持株比率が希薄化する
新株予約権が行使されると新しい株式が発行されるため、既存の株主が保有する株式の割合が相対的に低下します。これを「株式の希薄化」と呼びます。
株主にとっては、会社の利益分配である配当の取り分が減ったり、株主総会での議決権の比重が軽くなったりするなど、具体的な不利益が発生する可能性があります。特に大量の新株予約権を発行した場合、支配権を持つ株主にとっては影響が大きく、自らの経営への関与度が下がることにもつながります。
従って、企業が新株予約権を発行する際には、株主への十分な説明責任を果たすことが強く求められ、透明性を欠く対応をすると株主との信頼関係を損なうリスクがあります。
株価下落リスク
新株予約権が発行されると、市場では「将来的に株式数が増加し、既存株式の価値が薄まるのではないか」という懸念が生じます。その結果、発行が発表された段階で株価が下落するケースも存在します。
さらに、発行条件が市場から見て割安と判断されれば、投資家心理が冷え込み、株価下落が加速する恐れがあります。株価が下がれば、投資家の信頼を失うだけでなく、会社自身が将来の資金調達を行いにくくなる可能性も出てきます。つまり、新株予約権はその設計や発表の仕方によっては短期的に企業価値を損なうリスクを伴います。
行使されなければ資金調達効果が得られない
新株予約権は、保有者が権利を行使することで初めて会社に資金が入る仕組みです。従って、行使価格よりも株価が低い状態が続けば投資家は権利を行使せず、結果として会社は資金調達効果を得られません。
例えば、行使価格を100円に設定していても株価が80円のままであれば、投資家にとって権利を行使するメリットはなく、資金流入はゼロとなります。
このように新株予約権は、必ずしも資金調達が実現するとは限らない不確実性を抱えています。そのため、企業は市場環境や株価の動向を見極めながら慎重に制度を設計する必要があります。
公平性の問題
新株予約権を従業員や役員に付与する場合、その対象や条件設定によっては社内に不公平感を生み出す恐れがあります。
例えば、経営陣や一部の役員だけが大きな利益を得られる仕組みになっていると、一般の従業員は不満を抱き、かえって組織全体の士気を下げてしまうことがあります。本来はモチベーション向上のために導入した仕組みが逆効果になる可能性があります。
そのため、公平性や透明性を意識して付与対象者や条件を決める必要があります。また、付与に関する情報開示が不十分であると、株主や従業員の間で「経営陣が自らの利益のために制度を悪用しているのではないか」という疑念が生まれるリスクも否定できません。
導入・運用コストの負担
新株予約権の発行には、株主総会の特別決議や登記手続き、監査法人・証券会社との調整など、多くの法的・事務的な作業が伴います。これらには相応の時間とコストがかかり、特に中小企業やスタートアップにとっては負担が大きいといえます。
また、発行後も権利行使の管理や株主名簿の更新など、継続的な運用コストが発生します。さらに、ストックオプションとして従業員に付与する場合には、税務面での取り扱いが複雑になることが多く、専門家のサポートが必要になるケースもあります。
これらを総合すると、新株予約権は導入のハードルが低い制度ではなく、適切な設計と継続的な管理体制が欠かせません。
経営者の乱用リスク
新株予約権は経営陣が自己保身のために乱用するリスクがあることです。
例えば、敵対的買収防衛を目的とするポイズンピル型の新株予約権は、本来は企業価値や株主の利益を守るための制度ですが、経営陣が自らの地位を維持するためだけに利用してしまうと、株主に不利益を与える結果となります。このようなケースでは、株主と経営陣の間に対立が生じ、企業のガバナンスに深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、新株予約権を導入する際には、その必要性や合理性を明確に示し、株主や市場からの理解を得ることが重要です。
新株予約権の発行対象
新株予約権の分類にはまず発行対象者が誰なのか、という軸があります。大別すると社内向けと社外向けです。社外向けは社外の誰に発行するかによってさらに三つに分けられます。
社内向け(ストックオプション)
社内向けの新株予約権は、従業員や役員に対して付与されるもので、一般的に「ストックオプション」と呼ばれます。
これは単なる給与や賞与といった短期的な報酬ではなく、会社の成長や株価の上昇によって将来的に利益を得られる仕組みを提供するものです。従業員にとっては、自らの努力が企業価値の向上に結び付き、それが株価の上昇を通じて自分の利益となるため、強いモチベーションにつながります。
特にスタートアップや成長途上の企業では、現金報酬が十分に支払えない場合に、優秀な人材を確保・定着させる手段として活用されます。さらに、従業員が会社の「一員」ではなく「株主の一員」としての意識を持つようになることで、経営陣と従業員の利害が一致し、中長期的な企業価値向上を目指す基盤が整います。
株主割当て
株主割当ては、既存株主全員に対して持株比率に応じた新株予約権を発行する方法です。これにより、特定の株主だけが利益を得るような不公平が生じにくく、既存株主に対して平等に機会を提供できます。
さらに、この方法は敵対的買収への防衛策としても利用されます。既存株主が新たに株式を取得できるようにすることで、買収者の持株比率を相対的に低下させ、経営権の掌握を困難にします。こうした仕組みにより、企業は望まない買収から自社の独立性を守ることができます。
第三者割当て
第三者割当ては、特定の外部関係者に対して新株予約権を発行する方法です。対象は金融機関や取引先、業務提携先、ベンチャーキャピタルなど多岐にわたります。
企業にとっては資金調達の手段となるだけでなく、戦略的な関係を強化する目的でも活用されます。例えば、重要な取引先企業に新株予約権を与えることで、長期的な協力関係を築きやすくなり、取引の安定性や信頼関係を高める効果があります。
また、スタートアップ企業がベンチャーキャピタルに新株予約権を付与することで、資金調達を円滑に進められるケースも一般的です。
ただし、特定の第三者だけに有利な条件で発行すると、既存株主に不公平感を与え、株主との関係悪化を招くリスクもあります。このため、企業は株主とのバランスを考慮し、適切な条件で新株予約権を発行することが重要です。
公募
公募による発行は、不特定多数の投資家を対象に新株予約権を募集する方法です。
証券市場を通じて広く投資家から資金を集められるため、大規模な資金調達に適しています。上場企業が用いるケースが多く、投資家にとっても「将来の株価上昇を見込んで安定的に利益を狙える投資商品」として関心を集めやすい仕組みです。
特に成長戦略を加速させたい企業にとっては、短期間で大量の資金を調達できる点が大きな魅力です。
しかし、手続きには証券会社を介した募集業務や金融商品取引法に基づく厳格な規制が伴い、コストや時間的負担が大きくなります。
また、発行規模が過大であったり条件が投資家にとって不利だと判断された場合には、市場にネガティブな印象を与えて株価下落を招くこともあります。従って、公募は資金調達力が大きい一方で、市場動向や投資家心理に十分配慮しなければならない手段です。
新株予約権の価格
新株予約権は支払いの有無や価格の決め方によっても区分できます。
無償発行(無償割当)
無償割当は、新株予約権を既存株主や従業員に対して無償で付与する形態です。
株主に対して一律に割り当てれば、既存株主の利益を保護でき、敵対的買収への防衛策としても機能します。また、従業員や役員に無償で付与すれば、ストックオプションとしてのインセンティブ効果を発揮し、会社の成長に対するモチベーションを高める手段です。
無償割当の場合、会社に即時の資金流入はありませんが、権利が行使される段階で株式の発行対価が入るため、将来的には資金調達につながります。
有償発行
有償発行とは、文字どおり、新株予約権を取得する際に対価を支払う形態です。
投資家や取引先などの外部関係者に対して発行されるケースが多く、会社はその対価を資金調達に活用できます。
例えば、新株予約権1個につき100円といった金額を設定し、投資家が購入することで会社は即時に現金収入を得られます。さらに、その後権利が行使されれば行使価格に応じて追加の資金が流入するため、二段階の資金調達手段となる点が特徴です。
有償発行の場合は、投資家はリスクを取って権利を購入するため、会社は条件を慎重に設計する必要があり、発行時の株価や将来の成長性が投資家から厳しく評価されます。
有利発行
有利発行とは、新株予約権の発行条件が市場価格や一般的な評価額よりも有利に設定されているケースを指します。
例えば、株価が100円のときに行使価格を80円に設定したり、新株予約権を低価格または無償で発行する場合などが該当します。
有利発行は、特定の株主や従業員、経営陣などに利益を集中させることが可能であり、インセンティブ付与や戦略的パートナーとの関係強化に活用されます。
ただし、不当に特定の者を優遇すれば、他の株主にとって不利益となり株主平等の原則に反する恐れがあります。
公正発行
公正発行とは、新株予約権の発行条件が市場価格や合理的な評価額に基づき、公平で妥当と認められる水準で設定されているケースを指します。
例えば、株価が100円のときに行使価格もおおむね100円程度に設定するような場合です。公正発行は、既存株主に不利益を与えにくく、資金調達やインセンティブ制度の導入にあたって株主からの理解を得やすい方法です。
新株予約権の行使方法
新株予約権の権利行使の方法を解説します。
行使手続き
新株予約権を行使して新株を取得するには、証券会社を通じて所定の手続きを進める必要があります。
一般的な流れとしては、株主確定日に株主へ新株予約権が割り当てられ、その後、発行会社から権利行使に関する案内が送付されます。続いて、株主はインターネット、電話、または書面で行使の申し込みを行います。その後、証券会社で必要な手続きや審査が行われ、承認されれば新株が交付されます。
ただし、行使手続きには行使価格の支払いが必要であり、その支払い方法についても事前に確認しておくことが重要です。また、行使期限や具体的な手続き方法は発行会社によって異なる場合があるため、案内に従い適切な手続きを行う必要があります。
行使期間
行使期間とは、新株予約権を付与されてから実際に行使できるまでの期間を指します。法律上は期間に制限はありませんが、ストックオプションを「適格税制」に対応させるには、行使期間を2年以上10年以内に設定する必要があります。
ちなみに、令和5年度税制改正において、設立から5年未満の非上場会社においては、権利行使期間を「付与決議日後2年を経過した日から付与決議日後15年を経過する日まで」へと延長されました。
適格税制とは、一定の要件を満たした場合に課税が軽減される制度です。通常のストックオプションでは、①付与時には課税されないものの、②行使時には株価上昇分が給与所得として課税され、③さらに株式譲渡時には売却益が譲渡所得として課税されます。つまり、課税のタイミングが2回あることが通常です。
しかし、適格税制に適用されていれば、行使時の課税は免除され、株式を売却したときの譲渡益のみが課税対象となります。結果として、課税のタイミングが1回に減り、税負担を大きく軽減できる点がメリットです。そのため、ストックオプションを導入する際は、できる限り適格税制に対応させることが望ましいといえます。
行使価格
行使価格とは、新株予約権を行使して株式を取得するときに支払う金額のことで、発行時にあらかじめ決められます。一般的には株主にメリットを与えるため、発行時の株価より安く設定されることが多いことが特徴です。
一方で、ストックオプションについては「適格税制」を利用する方が税務上有利となるため、行使価格には一定の制限があります。具体的には、①行使価格はストックオプション発行時の株価以上であること、②年間で1,200万円を超えないこと、という条件を満たす必要があります。
新株予約権の買取請求
新株予約権は原則的に買取請求できませんが、次の条件下では実施可能です。
- 譲渡制限株式化
- 全部取得条項付種類株式化
- 株式の分割・交換・移転
- 会社の合併
それぞれを分かりやすく解説します。
譲渡制限株式化
譲渡制限株式とは、株式を譲渡する際に会社の取締役会や株主総会の承認を必要とする株式を指します。新株予約権を取得した投資家の中には、株式を市場で自由に売却して譲渡益を得ることを目的としている人も少なくありません。
しかし、株式が譲渡制限株式とされてしまうと、承認を得ない限り売却できず、期待していた流動性や譲渡益の機会が大きく制約されます。これは新株予約権者にとって不利益であるため、このような場合には例外的に買取請求が認められ、株主は保有する新株予約権を会社に買い取ってもらえます。
全部取得条項付種類株式化
全部取得条項付種類株式とは、株主総会の特別決議を通して、会社が発行済みの全ての株式を強制的に取得できる種類株式のことです。
株主としては、長期保有や市場での売却によって利益を得る機会を失い、会社に株式を引き取られるリスクを負うことになります。このように株主にとって明確に不利な状況といえるため、全部取得条項付種類株式化が行われた場合、株主は株式を強制的に引き取られる代わりに、通常は事前に定められた対価を受け取ることができます。
ただし、これには会社の定款や株主総会の決議に基づく手続きが必要であり、不利益を被る可能性があるため、株主への十分な説明や手続きが重要です。また、全部取得条項付種類株式化が行われた際に新株予約権の買取請求が可能であるかどうかは、具体的な条件や状況に依存します。
株式の分割・交換・移転
株式分割は、既存の株式を細かく分けることで、通常は株価が下落する傾向にあります。しかし、新株予約権自体は分割されないため、相対的にその価値が下がります。これにより、株主は思い描いていた権利行使後の利益を得にくくなるため、不利益が発生します。
また、株式交換や株式移転の場合、発行済み株式のすべてが別の既存会社や新設会社の株式に置き換えられます。この際、新株予約権者は当初割り当てられた会社の株式ではなく、異なる会社の株式を取得することになり、想定外のリスクや価値変動にさらされます。こうした場合も、新株予約権者の利益を守る観点から、買取請求が認められることがあります。
ただし、新株予約権の取り扱いや買取請求の可否は、具体的な契約内容や企業の方針によって異なるため、事前に確認が必要です。
会社の合併
会社合併は、複数の会社が一つに統合される企業再編行為です。合併によって存続会社や新設会社の株式が発行され、新株予約権の対象株式が当初の発行会社のものから異なる会社の株式へと切り替わります。
新株予約権を保有する株主にとっては、当初期待していた企業の成長性や事業戦略に基づいて投資判断をしていたのに、合併によってその前提が崩れてしまう可能性があります。
結果として、株主が想定していたリターンを得られないリスクが高まり、不利益が生じるため、合併のケースでも新株予約権の買取請求が認められています。
新株予約権の仕訳
社外向けの新株予約権発行と、社内向けであるストックオプションの付与では、新株を発行するという目的は共通していますが、会計上の処理方法には違いがあります。
ここでは代表的なケースとして、発行会社が行う社外向けの新株予約権発行と、従業員などに無償で付与するストックオプションについて、それぞれの仕訳や使用される勘定科目を解説します。
発行側(社外)
発行時
1個1万円(新株予約権1個につき交付株式数100株、発行価額1株1万円、行使価額1株1万円)の新株予約権を100個発行し、当座預金に全額の払い込みを受けた場合は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 当座預金 | 1,000,000円 | 新株予約権 | 1,000,000円 |
新株予約権の払込金を受け取った際は、「新株予約権(純資産)」の勘定科目を用いて仕訳を行います。受け取った時点では資本金に直結させず処理するのは、その権利が将来実際に行使されるかどうか不確定であり、失効する可能性もあるためです。
権利行使時
1個1万円(新株予約権1個につき交付株式数100株、行使価額1株1万円)の新株予約権について、90個分の権利が行使され、当座預金に払い込みを受けた場合は次のとおりです。権利行使分は新株の発行が行われ、全てを資本金としました。
| 借方 | 貸方 | ||
| 当座預金 | 90,000,000円 | 新株予約権 | 90,900,000円 |
| 新株予約権 | 900,000円 | ||
新株予約権が行使されて株式の払込金を受け取った場合、その金額を新株予約権の金額と合わせて資本金に振り替えます。ただし、払込額の2分の1を超えない範囲については、資本準備金へ計上することも可能です。なお、仕訳例では新株発行を前提としていますが、自己株式を保有している場合には、資本金に組み入れる代わりに自己株式を交付する方法も認められています。
権利失効(行使期限到来)時
1個1万円(新株予約権1個につき交付株式数100株、行使価額1株1万円)の新株予約権について、10個分は権利が行使されずに期限を迎えた場合。
| 借方 | 貸方 | ||
| 新株予約権 | 100,000円 | 新株予約権戻入益 | 100,000円 |
行使されずに失効した新株予約権については、その金額を「新株予約権戻入益」として計上し、特別利益に振り替えます。
発行側(無償ストックオプションの場合)
付与時
無償ストックオプションは、権利を付与する際に対価の払い込みを伴わないため、新株予約権のオプション部分に対応する払込金額は発生しません。
しかし、無償ストックオプションの付与時には、オプションの公正価値を会計上で計上する必要があります。従って、発行時点で会計上の仕訳を行うことが求められます。
株式報酬費用計上時
期末にあたり、当期首に執行役含む役員に付与した10個のストックオプション(1個につき交付株式数100株、行使価額1株1万円)について、株式報酬費用を月割り計上する場合は次のとおりです。なお、ストックオプションの公正な評価単価は1個1万円、対象勤務期間は2年とします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 株式報酬費用 | 50,000円 | 新株予約権 | 50,000円 |
ストックオプションは、役員や従業員が追加的に提供するサービスへの対価とみなし、その分を費用として処理します。この際に用いる勘定科目は「株式報酬費用」です。付与の時点では「新株予約権」を直接計上しませんが、株式報酬費用の認識に合わせて、順次「新株予約権」へ振り替えていきます。
株式報酬費用や新株予約権を計上するには、ストックオプションの公正な評価単価と、付与日から権利確定日までの対象勤務期間を考慮する必要があります。例えば、対象勤務期間が2年間で期首に付与されたケースでは、次のように算定します。
(1万円 × 10個) × 12/24 = 50,000円
また、権利確定条件を満たさず失効が見込まれる場合や、公正価値に変動が生じた場合には、計上する株式報酬費用の再計算や修正が必要となることがあります。
権利行使時
公正な評価単価1個1万円(1個につき交付株式数100株、行使価額1株1万円)のストックオプションについて、10個分の権利が行使され、当座預金に払い込みを受け、全てを資本金に組み入れた場合は次のとおりです。対象勤務期間中の公正な評価単価の変動や条件未達成による失効はなかったものとします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 当座預金 | 10,000,000円 | 資本金 | 11,000,000円 |
| 新株予約権 | 100,000円 | ||
権利確定日を迎えるまでに、公正価値の変動などを踏まえて最終的な新株予約権の金額が確定します。権利行使の際には、一般的な新株予約権の行使時と同じ仕訳処理を行います。
権利失効時
公正な評価単価1個1万円(1個につき交付株式数100株、行使価額1株1万円)のストックオプションについて、5個分の権利が行使されずに行使期間満了日を迎えたとします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 新株予約権 | 50,000円 | 新株予約権戻入益 | 50,000円 |
権利が失効した場合の会計処理も、一般的な新株予約権と同じ扱いです。失効した分については、特別利益として「新株予約権戻入益」に振り替えて計上します。
取得側
新株予約権を取得した側では、勘定科目として「新株予約権」を直接使用せず、売買を目的とする場合は「有価証券」、投資目的の場合は「投資有価証券」を用いて処理します。具体的には、新株予約権の取得時、行使時、失効時それぞれに応じた仕訳を行います。
特に失効時には権利が消滅するため、その金額を特別損失として計上します。これは、失効した新株予約権の取得時に計上した金額を損失として扱うことにより、財務諸表に反映されます。
取得時
1個1万円(1個につき交付株式数100株、発行価額1株1万円、行使価額1株1万円)の新株予約権5個を取得し、当座預金より支払いを行った場合は次のとおりです。新株予約権は売買目的の取得ではないとします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 投資有価証券 | 50,000円 | 当座預金 | 50,000円 |
権利行使時
1個1万円(1個につき交付株式数100株、行使価額1株1万円)の新株予約権5個について権利を行使し、取得した株式の対価を当座預金より支払った場合は次のとおりです。新株予約権は売買目的で取得したものではないとします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 投資有価証券 | 5,050,000円 | 投資有価証券 | 50,000円 |
| 当座預金 | 5,000,000円 | ||
権利失効時
1個1万円(1個につき交付株式数100株、行使価額1株1万円)の新株予約権5個について権利を行使しないまま行使期間を経過したため、失効損を計上した場合は次のとおりです。新株予約権は売買目的で取得したものではないとします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 新株予約権失効損 | 50,000円 | 投資有価証券 | 50,000円 |
新株予約権に関するQ&A
最後に、新株予約権に関するよくある質問とその回答を紹介します。
新株予約権付社債とは何か
新株予約権付社債とは、あらかじめ定められた条件の下で株式を取得できる権利(新株予約権)が付与された社債を指します。新株予約権を行使する場合、その払い込みに充てられる金額は社債部分の元本とみなされます。また、どの時期に、どれだけの株式を発行できるかといった条件はあらかじめ決められています。
2002年4月の商法改正では、新株予約権の制度が導入され、これまで別々に扱われていた転換社債(CB)の転換請求権や新株引受権付社債(いわゆるワラント債)の新株引受権、さらにストックオプションまでもが「新株予約権」という名称に一本化されました。これにより、従来CBやワラント債と呼ばれていたものも「新株予約権付社債」と整理され、そのうち従来のCBと同じ仕組みを持つものは「転換社債型新株予約権付社債」と呼ばれるようになりました。
また、この改正ではCBやワラント債に関する規定も整備されました。新株予約権は分離して譲渡できず、従来のCBでは新株予約権を行使するとき、必ず社債の償還額が払い込みに充当される仕組みとされました。さらに、従来の非分離型ワラント債は「分離できない新株予約権付社債」として整理され、一方で、社債と新株予約権を別々に切り離して譲渡できる分離型ワラント債については、新株予約権付社債の枠組みには含まれない扱いとなりました。
新株予約権無償割当とは何か
新株予約権無償割当とは、企業が資金調達を目的として既存株主に新株を取得できる権利を無償で与える仕組みです。株主は付与された新株予約権を行使することで普通株式を手に入れられ、通常は市場価格よりも低い水準で購入できる点が大きな特徴となっています。
この制度には二つの形態があります。一つは「上場型新株予約権の無償割当(ライツ・オファリング)」で、一定期間その権利自体が証券取引所に上場されるため、株主は権利を行使して株式を取得するだけでなく、市場を通じて第三者に売却し利益を得ることも可能です。
もう一つは「非上場型の新株予約権無償割当」で、こちらは市場に上場されないため、株主が利益を得る方法は権利行使による株式取得に限られます。この場合、行使可能期間を過ぎると権利は失効し、無価値となってしまいます。
従って、新株予約権無償割当は株主にとって投資機会を広げると同時に、企業にとっては柔軟な資金調達手段ですが、上場型か非上場型かによって流動性や活用方法に大きな違いが生じます。
自己新株予約権とは何か
自己新株予約権とは、企業が自社で発行した新株予約権を改めて取得し、保有する仕組みを指します。典型的な活用場面としては、従業員が退職した際に付与済みのストックオプションを会社が買い戻す場合や、事業環境の変化によって当初の目的を果たせなくなった新株予約権を消却するといったケースがあります。これにより、不要な新株予約権を整理でき、登記にかかる手間やコストを抑えられる点が利点とされています。
また、自己新株予約権の取得に関しては、会社法上の明確な規定は存在しませんが、権利を持つ者と会社の間で合意が成立すれば自由に取得できます。この柔軟性により、実務上は人事や経営戦略の変化に応じて対応しやすい制度となっています。
新株予約権は配当を受け取れるか
新株予約権を保有しているだけでは、配当を受け取ることはできません。配当はあくまで株主に対して支払われるものであり、株主としての地位を得るのは新株予約権を行使して株式を取得した時点からです。つまり、新株予約権そのものは「将来株式を取得できる権利」にすぎず、株式と同じような権利(議決権や配当請求権)は付与されていません。
そのため、保有者が配当を受けられるのは、行使価格を払い込んで実際に株式を取得した後です。取得の時期によっては、その年度の配当基準日に株主名簿に記載されていない場合、配当を受けられないケースもあります。
従って、新株予約権保有者が配当を得たいと考える場合には、行使のタイミングを基準日までに合わせる必要があります。
新株予約権を行使しなかった場合はどうなるか
新株予約権は、あらかじめ定められた行使期間の中で行使して初めて株式を取得できる権利です。従って、この行使期間を過ぎても行使しなかった場合、新株予約権は効力を失い、単なる紙切れ同然となって価値がゼロになります。
従業員向けのストックオプションとして付与された場合も、株価が上昇しなければ行使して利益を得る動機は生まれません。さらに、退職や在職条件などの要件を満たせないことで行使資格を失ったり、権利行使に必要な資金を準備できなかったりする場合にも、新株予約権は期限切れとなり無価値になります。
まとめ
新株予約権は、会社が資金調達や従業員へのインセンティブとして利用する重要な手段です。しかし、そのメリットを最大限に活かすためには、関連するリスクやデメリットも十分に理解しておくことが大切です。特に、既存株主の持株比率の希薄化や株価への影響など、慎重な判断が求められます。もし、あなたが企業の経営者や従業員であれば、新株予約権の仕組みやその活用方法を具体的に学ぶことで、より良い意思決定ができるでしょう。この記事で紹介した内容が参考になったと感じたら、ぜひ実際に専門家に相談したり、さらに詳しい情報を調べたりしてみてください。具体的なケースに応じた対応策を講じることで、企業の成長に役立てることができるでしょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。