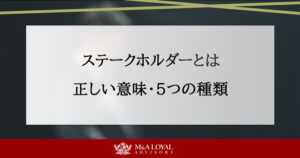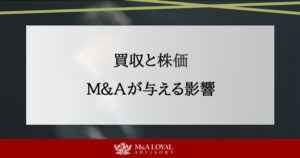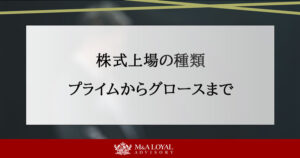従業員持株会とは?仕組みやメリット・デメリットを分かりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
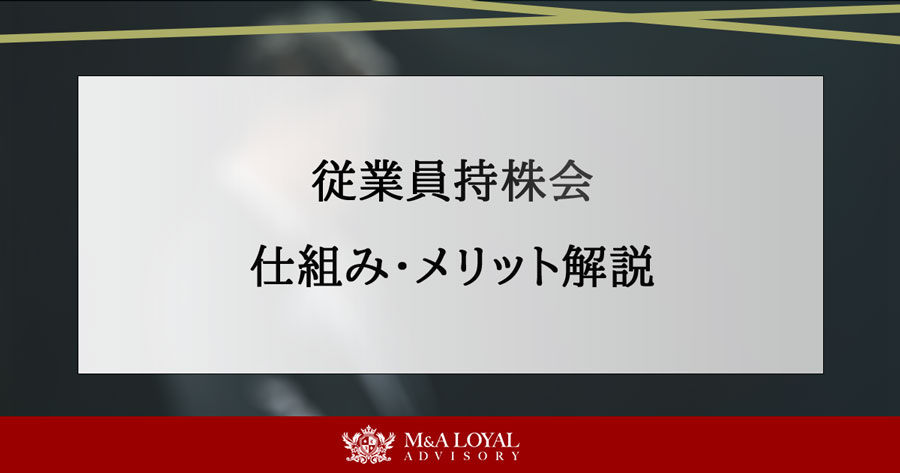
従業員持株会は、企業の従業員が自社の株式を計画的に購入・保有できる制度で、従業員の資産形成と会社への帰属意識の向上を目的としています。
給与天引きで少額から投資できる手軽さや、奨励金の支給といった特典がある一方で、価格変動リスクや転職・退職時の取り扱いなど、注意すべき点もあります。
企業側にも安定株主の確保や従業員の定着促進といったメリットがある反面、制度設計や情報開示に慎重さが求められます。
本記事では、従業員持株会の基本的な仕組みから、加入の流れ、活用時の注意点、企業・従業員双方のメリット・デメリットまで、実務で役立つ情報を分かりやすく解説します。
目次
従業員持株会とは
まず、従業員持株会に関する基本的知識について紹介します。
従業員持株会の概要
従業員持株会とは、従業員が福利厚生の一環として会社の株式を共同で取得することで、経営への関心や参画意識を高め、企業の発展に貢献することを目的とした制度です。加入は義務ではなく従業員の任意です。
株式を所有してもらうにあたって、従業員個人に直接保有してもらうのではなく、従業員持株会という組織を通して間接保有してもらいます。その理由は、退職時の買い戻しを容易にするためです。
従業員持株会は主として上場企業に普及しており、上場企業の9割以上が導入しています。
従業員持株会の仕組み
持株会の基本的な流れは次のとおりです。
- 会員である従業員から、株式購入のための資金を集めます(一般的には毎月の給与や賞与から一定額が天引きされます)。
- 持株会がその資金を基に、自社の株式をまとめて購入します。
- 購入した株式は、従業員それぞれの拠出額に応じて割り当てられます。
このように、持株会では従業員が定期的に拠出した資金を活用して株式を取得し、その出資割合に応じて株式や配当金を受け取れる仕組みです。
従業員持株会の運営
従業員持株会は一般的に民法上の組合による方式が採用されます。民法上の組合は会社設立などとは異なり登記や定款認証は不要です。規約があり二人以上の組合人がいれば組織できます。
持株会の運営方法には、社内で自ら管理するケースと、証券会社などの外部機関に委託するケースの2通りがあり、後者の外部委託が主流です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



従業員持株会のメリット【企業側】
企業にとっての従業員持株会のメリットは次のとおりです。
- 従業員の経営参画意識の向上につながる
- 優秀な人材の獲得に有利に働く
- 安定株主を確保できる
それぞれについて解説します。
従業員の経営参画意識の向上につながる
従業員が持株会を通じて自社株を保有することにより、会社の経営や業績に対する関心が自然と高まります。
自分たちが関わっている業務の成果が株価や配当に反映されることで、「会社の成長=自分の利益」という意識が芽生え、主体的に業務へ取り組む姿勢が醸成されます。
また、経営方針や業績に対する理解が深まることで、組織全体の一体感や連帯感も向上し、結果的に業績や職場環境の改善にもつながる好循環を生み出します。
優秀な人材の獲得に有利に働く
従業員持株会は、給与とは別に将来の資産形成が期待できる制度として、求職者にとって魅力的な福利厚生の一つです。
求職者は給与水準だけでなく、長期的なキャリアや経済的な安定性も重視するため、持株会の存在は企業選びの重要な判断材料となり得ます。
また、入社後も企業の成長とともにリターンが見込めるため、定着率の向上にもつながります。
安定株主を確保できる
従業員を株主とすることで、企業は自社の株式を中長期的に保有してくれる安定株主を確保できます。
特に上場企業は市場での株式の売買によって株主構成が変動しやすく、経営の安定性に影響を及ぼす可能性があります。しかし、従業員が一定割合を保有することで、このリスクを軽減できます。
また、敵対的買収の抑止力としても機能し、企業の自律的な経営体制の維持にも貢献します。
従業員持株会のメリット【従業員側】
従業員持株会は企業ごとに規約が異なりますが、従業員にとっての主なメリットは次のとおりです。
- 中長期的に資産形成できる
- 配当金による再投資がある
- 手間がかからない
- 株式を少額から購入できる
- 奨励金が付与される
- インサイダー取引に当たらない
それぞれについて解説します。
中長期的に資産形成できる
従業員持株会では、毎月一定額を拠出して株式を購入する「定期定額買付」が行われます。
これにより、株価が高いときは少ない株数を、安いときは多くの株数を購入することになり、結果として購入価格が平準化される「ドルコスト平均法」の効果が得られます。
長期的に積み立てを継続することで、価格変動リスクを抑えながら安定的な資産形成が可能となり、将来的な資産づくりにもつながります。
配当金による再投資がある
企業が業績に応じて配当金を支払う場合、一般的に従業員持株会ではその配当金を使って追加の株式を購入する「再投資」が行われます。
これにより、従業員の拠出額に加えて配当金も活用されるため、より効率的に持ち株数を増やせます。
手間がかからない
持株会では、給与天引きによって自動的に拠出金が積み立てられ、株式の購入や管理も全て運営側が行ってくれるため、個人で証券口座を開設したり売買手続きをする必要がありません。
金融知識がない人でも、制度に参加するだけで手軽に投資を始められる点が大きな魅力です。資産運用の第一歩としても最適です。
株式を少額から購入できる
通常、株式を購入するには一定のまとまった資金が必要ですが、持株会では毎月数千円程度からでも始められます。
少額からの積み立てが可能なため、若手社員や投資経験のない人でも安心して参加でき、無理なく資産形成ができます。コツコツと買い増すことで、時間をかけて着実に持ち株数を増やせる点もメリットです。
奨励金が付与される
企業によっては、従業員が拠出した金額に対して一定の割合を上乗せする「奨励金制度」を導入している場合があります。
例えば、拠出額の3〜10%を企業が追加で負担することで、従業員は実際の負担以上の金額で株式を購入でき、持ち株数を効率よく増やせます。
このように、企業からの支援によって、より有利に資産形成ができる点も持株会の大きな魅力です。
インサイダー取引に当たらない
通常、社員が自社株を売買する場合、内部情報を基にした不正な取引(インサイダー取引)とみなされるリスクがありますが、持株会を通じた購入は定期的・継続的に行われる仕組みのため、通常はインサイダー取引には該当しません。ただし、社員は依然として内部情報に基づく取引について注意を払う必要があります。そのため、安心して自社株を保有・積み立てられる点も、大きな安心材料です。
従業員持株会のデメリット【企業側】
企業にとって従業員持株会は次のようなデメリットもあります。
- 運用コストが発生する
- 株価で従業員のモチベーションが左右される
- 株主構成の調整が難しくなる場合がある
- 株主権を行使される場合がある
それぞれについて解説します。
運用コストが発生する
従業員持株会を導入・維持するには、制度の設計や運営に関する事務作業が発生し、社内で対応する場合は人件費、外部の証券会社などに委託する場合は委託費用がかかります。
また、奨励金を導入している企業では、その分の費用負担も必要となり、経済的・人的コストの両面で企業にとって一定の負担が生じます。
株価で従業員のモチベーションが左右される
従業員が自社株を保有していると、株価の変動に一喜一憂しやすくなります。特に株価が下落した場合には、不安や不満が高まり、モチベーションや会社への信頼感が低下する恐れがあります。
経営上の一時的な判断や外部要因による株価下落が、従業員の士気に悪影響を及ぼすリスクがある点は注意が必要です。
株主構成の調整が難しくなる場合がある
持株会が一定割合の自社株を保有することで、株主構成に大きな影響を与える可能性があります。
経営戦略や資本政策上、特定の比率で株主構成を維持したい場合でも、持株会の保有割合が調整できず、将来的な増資や株式移転などの際に支障をきたす恐れがあります。
株主権を行使される場合がある
従業員持株会も他の株主と同様に株主としての権利を持ち、議決権などを行使できる立場にあります。
経営方針や人事に関する重要事項に対して、従業員側から反対意見が出る可能性もあり、経営陣の意思決定に影響を与えるケースも考えられます。株主代表訴訟などに発展する場合もあるため慎重な組織設定が必要とされます。
従業員持株会へ譲渡した株式を議決権のない株式に変更するなどの策を講じることがあります。
従業員持株会のデメリット【従業員側】
従業員にとっての従業員持株会のデメリットは次のとおりです。
- 配当金を受け取れないことが多い(企業や制度によって異なる)
- 好きなタイミングで購入・売却ができない
- 株主優待を受けられない場合がある(企業の方針による)
- 会社の業績で資産が上下する
- 収益性が高いとはいえない
- 職場と財産を同時に失う場合がある
それぞれについて解説します。
配当金を受け取れないことが多い
持株会における配当金は、個人に現金として支払われるのではなく、自動的に株式の再投資に回されることが一般的です。そのため、配当を現金で受け取りたいと考えている従業員にとっては、実感としてのリターンを得づらい制度といえます。再投資によって資産は増加するものの、自由に使えるお金として配当を得ることは難しい場合が多く、制度上の不満につながることがあります。
好きなタイミングで購入・売却ができない
持株会では、株式の購入や売却が個人の判断で随時行えるわけではなく、会社または運営事務局が定める一定のスケジュールに基づいて処理されます。急な資金ニーズが発生した際にすぐに売却できないことや、相場が良い時に売りたいと思っても機会を逃すことがあるなど、流動性の面で不便を感じる場面があります。
株主優待を受けられない
企業によっては、一定数以上の株式を個人で保有する株主に対して優待制度を設けている場合があります。しかし、持株会を通じて株式を保有している従業員は、名義が持株会にあるため原則として株主優待の対象外です。たとえ保有株数が条件を満たしていても、個人名義でないことから優待を受けられず、不公平感を抱くことがあります。
会社の業績で資産が上下する
自社株は、その企業の業績や経営状況によって株価が大きく変動します。業績が悪化すれば株価が下がり、資産価値が目減りするリスクがあります。自分の給与や賞与から拠出している資金が減ってしまうことがあり、会社の状況が個人資産に直接影響を及ぼすという精神的な負担も無視できません。
収益性が高いとはいえない
従業員持株会はリスクを抑えた資産形成には適しているものの、一般的な株式投資や他の金融商品と比べて大きな利益を得られるとはいえません。急成長が見込まれる他社株や高配当銘柄への投資と比較すると、収益性の面では劣ります。
職場と財産を同時に失う場合がある
万が一、勤務先が経営破綻や業績不振により大きなダメージを受けた場合、自身の雇用とともに、持株会で積み立ててきた株式の価値も大幅に下落する可能性があります。
急成長が見込まれる他社株や高配当銘柄への投資と比較すると、収益性の面では劣ります。
職場と財産を同時に失う場合がある
万が一、勤務先が経営破綻や業績不振により大きなダメージを受けた場合、自身の雇用とともに、持株会で積み立ててきた株式の価値も大幅に下落する可能性があります。
このように、職場と資産を同時に失う可能性がある点は、リスクヘッジが重要とされる資産運用において大きなデメリットといえます。
従業員持株会の設計と留意点
従業員持株会を設立する際は次の点に留意する必要があります。
- 加入資格
- 株式の取得原資
- 保有比率と議決権
- 奨励金や配当金の有無
- 退職時の買取価格
- インサイダー取引
- 従業員の税金
それぞれについて解説します。
加入資格
持株会の加入対象は通常は正社員ですが、(取締役ではない)執行役員や転籍者、出向者、派遣社員、子会社の従業員などを含めるかどうかは、制度設計時に明確に定める必要があります。
雇用形態や在籍企業の違いによって待遇に差が生じないよう、加入範囲を慎重に検討し、社内規定に明記することが重要です。企業グループ全体で導入する場合は、制度の共通化や運用ルールの統一も課題です。
株式の取得原資
株式の購入資金は、従業員の給与や賞与からの天引きによる拠出が一般的です。ただし、資金が不足している場合には、会社が一時的に貸し付けを行うこともあります。
また、給与・賞与から天引きする場合には、労働基準法に基づく「賃金控除に関する労使協定」の締結が必要であり、法令順守を前提とした制度運営が求められます。
保有比率と議決権
持株会が保有する株式の比率が高まると、株主総会での議決権にも影響を与える可能性があります。議決権の行使方法や代表者の決定手続きなどは、事前に会則などで定めておく必要があります。
企業側としては、経営への影響度合いを把握し、株式の保有割合や議決権の扱いについて慎重なバランスを取ることが求められます。
持株比率ごとの株主権限は次のとおりです。
- 持株数が1株以上
- 議事録閲覧権
- 株主代表訴訟の提起
- 持株比率が1%以上
- 株主総会での議案請求権
- 持株比率が3%以上
- 株主総会の招集請求権(6カ月以上継続保有が必要)
- 会計帳簿の閲覧および謄写請求権
- 持株比率が33.4%以上(1/3超)
- 特別決議の単独否決権
- 持株比率が50%超(1/2超)
- 株主総会の普通決議の単独可決権
- 持株比率が66.7%以上(2/3超)
- 株主総会の特別決議の単独可決権
- 持株比率が90%以上
- スクイーズアウトの実行権
- 持株比率が100%
- 株主総会の全ての決議の単独可決権
奨励金や配当金の有無
企業によっては、拠出額に対して一定の奨励金を上乗せする制度を設け、従業員の参加促進を図る場合があります。また、配当金については個人に支払われず、自動的に再投資されることが一般的です。
どちらも制度の設計次第でコストや運用方法に影響を与えるため、導入前に企業の財務状況や目的に応じて検討する必要があります。
「株主平等の原則」に触れないように公平な設計が不可欠です。
退職時の買取価格
従業員が退職した際に保有株式をどう扱うかは、従業員持株会の制度設計において非常に重要なポイントです。
特に、退職者の株式を持株会が買い取る場合、その価格をどのように決定するかが明確でないと、従業員との間でトラブルや不信感を招く恐れがあります。
多くの企業では、退職時点における直近の市場価格や、一定期間の平均株価などを基準として買取価格を算出しますが、その方法や時点をあらかじめ会則や運用ルールに明示しておくことが重要です。
インサイダー取引
従業員持株会では一定の条件を満たせばインサイダー取引には該当しません。
しかし、内部情報を基に株式を追加購入したり、新たに持株会へ加入した場合には、インサイダー取引と見なされる可能性があります。
そのため、情報の取り扱いや取引のタイミングには十分な注意が必要です。
従業員の税金
持株会を通じて得た利益(配当や売却益)には税金がかかりますが、その納税義務を負うのは企業や持株会ではなく、利益を得た従業員本人です。持株会はあくまで従業員の代理として株式を保有・運用しているに過ぎず、得られた配当や売却益は最終的に個々の従業員に帰属します。
配当は「配当所得」として、所得税と住民税が源泉徴収されます。また、株式を売却して得た利益は「譲渡所得」として課税対象となり、必要経費(取得費や事務委託料など)を差し引いた額に課税されます。
なお、配当金は現金として手元に入るのではなく、多くの場合は再投資に充てられるため、実際の現金収入は発生しない点にも留意が必要です。税務処理や制度内容をあらかじめ理解しておくことが重要です。
従業員持株会の設立の流れ
従業員持株会を設立するための一般的なフローは次のとおりです。
- 従業員持株会の規約・運営ルールを策定する
- 設立発起人、理事、監事などの役員候補を決定する
- 取締役会にて持株会設立の承認を受ける
- 持株会専用の銀行口座を開設する
- 会社と持株会で覚書を締結する
- 従業員に説明会を開催する
- 入会申込書と拠出金を受け付ける
それぞれの工程を分かりやすく解説します。
従業員持株会の規約・運営ルールを策定する
まずは、持株会の基本的な枠組みとなる規約(会則)や、具体的な運営手順を定めた細則を作成します。
これには、加入資格や拠出方法、株式の割り当て方法、退会時の対応、配当や奨励金の取り扱いなどを明記します。
なお、一度作成した従業員持株会規約を会社側が自由に改正できません。そのため、将来の従業員持株会の不利益変更は困難である点に留意が必要です。
設立発起人、理事、監事などの役員候補を決定する
持株会を円滑に運営するためには、中心となる人材の選任が不可欠です。設立を推進する発起人をはじめ、運営責任者である理事や監査を担う監事を選びます。
従業員持株会であるため、取締役は就任できません。オーナーや代表取締役が人選したり、総務部長や経理部長が就任する場合もあります。
将来のトラブルを防ぐためには、発起人会議事録を残しておくことが賢明です。
取締役会にて持株会設立の承認を受ける
会社として制度を正式に導入するには、社内の意思決定機関である取締役会の承認を得る必要があります。
会則や運営体制、給与の天引き、奨励金の有無など、制度の設計内容を取締役に報告し、承認を受けることで会社としての公式な制度になります。
持株会専用の銀行口座を開設する
制度運営の実務に向けて、理事長印を用意し、資金管理を行うための専用口座を金融機関に開設します。
印鑑の外枠は「◯◯株式会社 従業員持株会」、内枠は「理事長印」とすることが一般的です。
従業員持株会は法人格を有しないため、銀行口座は理事長の個人名で開設します。「◯◯株式会社 従業員持株会 理事長 山田太郎」とすることが一般的です。
会社と持株会で覚書を締結する
会社と持株会の役割や業務の分担、奨励金の支給条件、株式の供給方法などを明文化した「覚書」や「契約書」を締結します。
これは、制度運用中のトラブルや誤解を防ぐための法的根拠となり、双方が合意した条件に基づいて制度が運営されることを保証するものです。
従業員に説明会を開催する
制度の内容やメリット・リスク、加入手続きなどを従業員に分かりやすく説明するための説明会を開催します。
制度の理解を深めた上で、任意で参加を募るため、透明性と納得感が求められます。また、加入手続きや今後のスケジュールについてもこの場で詳しく案内します。
入会申込書と拠出金を受け付ける
説明会を経て加入を希望する従業員から、入会申込書を提出してもらい、給与天引きなどによる拠出金の取り扱いを開始します。
併せて賃金控除に関する労使協定の確認も必要です。申し込み内容に基づいて持株会側で拠出額を管理し、株式購入の手続きへと移行していきます。
非上場企業における従業員持株会
非上場企業における従業員持株会について解説します。
上場予定がなくても導入する企業もある
従業員持株会は上場企業や上場準備企業を中心に普及してきた制度ですが、上場を予定していない非上場企業でも従業員持株会を導入できます。
上場企業では従業員持株会を証券会社が受託管理することが多く、日本証券業協会の持株会ガイドラインに沿った運営がされています。一方、非上場企業はこれに準拠する必要がないため、より自由度の高い独自の制度を構築できます。
また、非上場企業は証券会社には委託できないことから、自社で運営したり、会計事務所に委託することが一般的です。
出典:https://www.jsda.or.jp/shijyo/minasama/mochikabu_mochitoushiguchi/mochikabuGL_250612.pdf
非上場企業の従業員持株会の事例
非上場企業の代表的な従業員持株会を2つ紹介します。
1社目は、YKK株式会社です。YKKおよびその子会社であるYKK APは非上場企業であり、創業者の𠮷田忠雄は株式を単なる資産ではなく「事業への参加証」として捉えていました。その理念の元、現在でも従業員持株会が最大の株主となっており、社員が役職や給与に関係なく均等に株式を保有し、配当を受け取れる制度が維持されています。
2社目は、合同会社DMM.comです。DMMは非上場企業のため市場での株価は存在しませんが、持株会ではDMMグループ全体の「純資産」を基準に株式の価値を決めています。会社が黒字なら純資産が増え、それに応じて株価も上昇します。ただし、この株には議決権や配当金はなく、保有中は利益を得られません。従業員は在職中や退職時に株を売却し、そのときの株価上昇分が利益となる仕組みです。
ストックオプション制度との違い
ストックオプションとは、企業が従業員や役員に対して、あらかじめ定められた価格(行使価格)で自社株を将来購入できる権利を付与する制度です。一般的には、業績向上や株価上昇を目指して働くインセンティブとして活用され、株価が上がればその差額が利益です。
ストックオプションと従業員持株会はいずれも従業員が自社株に関わる制度ですが、目的や仕組みが異なります。
ストックオプションは「将来、一定の価格で買う権利」であり、主に役員や中核人材への報酬インセンティブとして機能します。一方、従業員持株会は、従業員が給与の一部を拠出して自社株を継続的に購入・保有する制度で、長期的な資産形成と経営参画意識の醸成が目的です。
非上場企業の従業員持株会の特徴
非上場企業の従業員持株会のメリットやデメリットを解説します。
親族内継承対策として活用できる
非上場企業が従業員持株会を導入するメリットは前述したもの以外にもあります。
未上場企業において従業員持株会を導入することは、事業承継や相続に備えた有効な対策です。中小企業の株価が高騰すると、経営者が保有する株式の評価額も上がり、事業承継や相続の際に株式取得の対価や相続税の負担が大きくなり、現金での対応が困難になるケースも少なくありません。
このようなリスクに備える手段として、あらかじめ持株会を設立し、経営者が保有する株式の一部(経営権に支障のない範囲)を持株会に譲渡または贈与することで、経営者の株式保有比率を段階的に下げられます。これにより、相続時に対象となる株式の評価額を抑え、相続税負担を軽減可能です。
従業員へ決算情報開示義務が発生する
非上場であっても株式会社であれば決算公告の義務(中小企業は貸借対照表のみ)がありますが、ほとんど企業がその義務を果たしていません。
しかし、従業員持株会は株主であるため、決算書(貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書)の開示義務が発生します。
多くの非上場企業では従業員に決算書の数字を共有していないため、これは非上場企業が従業員持株会を導入するための大きなハードルといえます。
株価の評価方法が難しい
非上場企業では市場での株価が存在しないため、従業員持株会での株式の価値をどう評価するかが課題です。
一般的には会社の純資産や売り上げ、営業利益などを基に算定されますが、明確な指標がなく、算出方法や妥当性について透明性のある仕組みが求められます。
従業員持株会以外の持株会
従業員持株会以外に次のような持株会が存在します。
- 拡大従業員持株会
- 役員持株会
- 取引先持株会
それぞれについて解説します。
拡大従業員持株会
拡大従業員持株会とは、非上場企業の従業員が、関係性の深い上場企業の株式を取得するために組織される持株制度です。
通常の従業員持株会とは、実施会社が非上場企業のみである点と、会員範囲が自社従業員である点、社内で複数の持株会を設立可能である点などで違いがあります。
役員持株会
役員持株会は、取締役や執行役員などの経営層を対象とした株式保有制度です。 役員は通常の従業員持株会には参加できないため、役員持株会が設けられています。
経営陣が株主としての立場を持つことで、企業価値の向上に対する意識が高まり、ガバナンス強化や外部への信頼性向上にも寄与します。
従業員持株会の設立目的は従業員の福利厚生ですが、役員持株会は経営者意識の向上が主な目的です。
取引先持株会
取引先持株会とは、仕入先や販売代理店、業務提携先といった社外の関係企業を対象に設けられる制度です。
取引先に自社株を保有してもらうことで、経済的利害を共有し、長期的かつ安定的な取引関係の構築を図ります。
特にサプライチェーンや販売網の強化を重視する企業においては、関係強化や相互の信頼醸成につながる戦略的な手段として活用されることがあります。
従業員持株会に関するQ&A
最後に、従業員持株会に関するよくある質問とその回答を紹介します。
従業員持株会とESOPの違いとは何か
ESOP(イソップ)とは、「Employee Stock Ownership Plan」の略で、企業が自社株を買い戻し、それを従業員に退職金や年金として分配するアメリカ発の制度です。
企業は信託銀行などに資金を拠出し、その資金で自社株を取得します。信託を通じて従業員に自社株を給付する仕組みとなっており、主に退職時の給付に利用されます。
なお、日本において「ESOP」と称される制度の中には、仕組み上は実質的に従業員持株会とほとんど変わらない運用がなされているケースもあり、導入目的や設計によってその性格は大きく異なります。
従業員持株会とるいとうの違いは何か
るいとうとは、株式累積投資のことを指します。
株式累積投資は、毎月決まった金額で継続的に株式を購入していく積立型の投資方法です。1銘柄当たり1万円以上、1,000円単位で投資額を自由に設定でき、月の上限は通常の金融機関によって異なるため、具体的な条件を確認する必要があります。まとまった資金を用意する必要がなく、少額から無理なく始められる点が魅力です。
従業員持株会とは全く別の投資方法です。
M&Aされた企業の従業員持株会はどうなるか
M&Aにより会社が売却されると、従業員持株会が保有している株式も併せて買収先企業に譲渡されます。その際、持株会の会員である従業員には、売却された株式の対価が分配されます。
ただし、持株会は通常「組合」として運営されているため、株式を売却するには会員全員の同意を得るか、もしくは持株会自体を解散し、清算の手続きを踏む必要があります。
将来的にM&Aの可能性がある場合には、制度設計の段階から持株会の売却や解散に関する対応方針をあらかじめ想定しておくことで、実行時の手続きがスムーズになります。
従業員持株会を退会する際、端数の扱いはどうなるか
1単元に満たない株式を保有している場合は、持株会規約に基づき、退会時に現金で精算するか、臨時入金により1単元まで買い増すかを選択できます。
現金精算では、該当株式が時価で売却され、売却代金から手数料を差し引いた上で、繰越金と合わせて精算金として入金されます。
買い増しを選ぶ場合は、不足分を臨時入金し、1単元まで株式を取得した後、証券口座へ振り替えられます。
休職中はどうなるか・再加入はできるか
給与が発生しない月は拠出できないため、休止する必要があります。しかし、運用自体は続くので従業員持株会を退会する必要はありません。
また、従業員持株会は原則として一度退会すると再加入できないことにも留意しましょう。
従業員持株会における繰越金・口数とは何か
従業員持株会における繰越金とは、持株会への拠出金のうち、当月の株式購入に使われなかった分を、次回以降の株式購入に繰り越して使用するための資金のことです。
口数とは従業員持株会の取引単位のことです。従業員持株会では、株数で取引をするのではなく、1口=1000円などと決め、口数で取引します。
経営課題のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
企業と従業員の双方にメリットがある従業員持株会は、従業員の満足度を高める福利厚生として効果的です。経営課題に関してご相談されたいことがある経営者の方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の発展をサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。