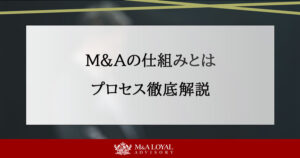セミリタイアとは?必要資金や後悔しないための対策を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
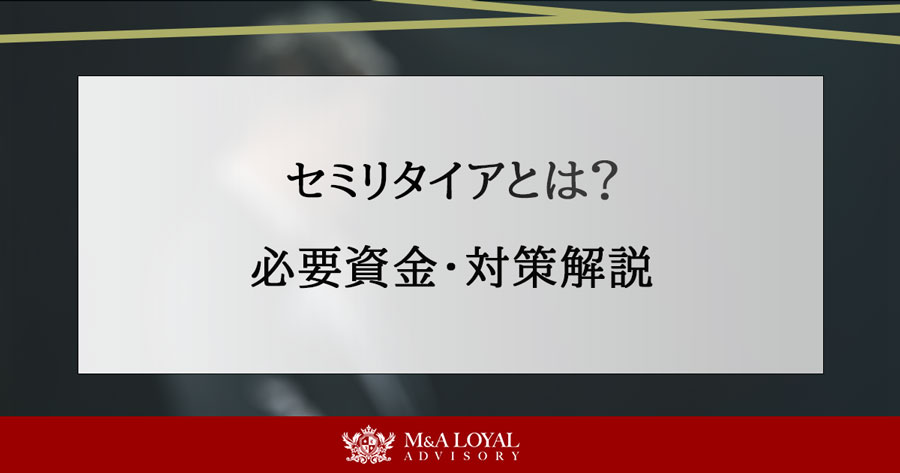
「会社を辞めたいけど、まだ完全に引退するのは不安…」そんな思いを抱く方に注目されているのが「セミリタイア」というライフスタイルです。セミリタイアとは、定年を待たずに会社を早期退職し、時間的自由を手に入れながらも、適度な仕事や収入源を確保する生き方です。アーリーリタイアやFIREとは異なり、セミリタイアとは完全な経済的独立を目指さず、柔軟なバランスを取ることで自分らしい人生を実現できます。本記事では、セミリタイアとは何か、必要な資金や失敗しないための準備、メリット・デメリットまで徹底解説します。人生の選択肢を広げるセミリタイアの可能性を探ってみましょう。
目次
セミリタイアとは?アーリーリタイア・FIREとの違い
セミリタイアという言葉を耳にする機会が増えてきました。ここでは、セミリタイアの基本概念と似た用語との違いについて解説します。
セミリタイアが意味する早期退職と適度な仕事の両立
セミリタイアとは、定年を待たずに会社を早期退職し、自分の時間を多く確保しながらも、負担にならない程度に仕事を続けるライフスタイルです。完全に引退するわけではなく、時短勤務やフリーランス、不動産投資などで適度に収入を得ながら、自分のペースで生活することを指します。
セミリタイアとアーリーリタイアの決定的な違い
アーリーリタイアは、定年前に仕事を完全にやめて働かないことを意味します。自営業や経営者であれば事業を廃業または承継して完全に引退することです。一方、セミリタイアでは仕事と完全に縁を切るわけではなく、適度に働いて収入を得続けるため、アーリーリタイアほど多額の資金を用意する必要はありません。
セミリタイアとFIREの目指す経済的自由の共通点
FIREは「Financial Independence, Retire Early(経済的独立と早期退職)」の略で、投資などの不労所得で生活費をまかない、経済的自由を得ることを目指します。
セミリタイアとFIREは早期に通常の仕事から離れ、自分の時間を大切にするという共通点がありますが、FIREでは投資の運用益だけで生活することを理想とするのに対し、セミリタイアでは軽い仕事からの収入も生活の糧にします。
セミリタイア後に実現できる自由な生活スタイル
セミリタイアにより、週に数日だけ短時間勤務をしたり、フリーランスとして好きな仕事を選んだり、不動産投資で家賃収入を得ながら旅行を楽しんだりできます。自分の能力や経験を活かした活動に集中したり、地方移住して自然の中でゆったり暮らしたりと、ライフスタイルは人それぞれです。
セミリタイアは社会との接点を維持しながら、自分のペースで充実した生活を送る魅力的な選択肢と言えるでしょう。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



セミリタイアの3つのメリット
セミリタイアを検討する方が増えている背景には、従来の働き方では得られない様々なメリットがあります。ここでは、セミリタイアの主な3つのメリットについて解説します。
自由な時間を確保できる生活スタイルの実現
セミリタイアの最大のメリットは、自分自身の時間を大幅に増やせることです。フルタイム勤務では1日の大半を仕事に費やしますが、セミリタイアすれば自分の裁量で使える時間が格段に増えます。
趣味や家族との時間、自己啓発など、これまで後回しにしてきたことに時間を使えるようになります。早朝からの出勤や帰宅後の疲労感から解放され、自分のペースで生活できる点は大きな魅力です。
精神的・身体的な健康状態の向上
フルタイムの仕事環境では、締め切りやノルマ、人間関係などによるストレスが蓄積しがちです。セミリタイアによって仕事の負担が減ると、精神的なストレスが大幅に軽減され、心身の健康状態が改善する可能性が高まります。
仕事のプレッシャーから解放されることで、睡眠の質が向上したり、運動や健康的な食事に時間をかけられるようになります。慢性的な疲労やバーンアウトを防ぎ、長期的に見て健康寿命を延ばすことにもつながるでしょう。
収入源を確保しながら経済的に余裕のあるリタイア
セミリタイアは、完全な引退とは異なり、ある程度の収入を継続して得ながら自由な時間も確保できる選択肢です。アーリーリタイアや完全なFIREでは多額の資金が必要となりますが、セミリタイアであれば比較的少ない資金でスタートできます。
また、複数の収入源を持つことでリスク分散にもなります。メインの仕事からの収入に加えて、不動産投資からの家賃収入や株式投資の配当金など、様々な不労所得を組み合わせることで、経済的な安定性を高めることができます。
セミリタイアの4つのデメリットと対策
セミリタイアには魅力的な側面がある一方で、いくつかの重要なデメリットも存在します。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることが成功への鍵となります。
安定した収入源の確保が不可欠になる
セミリタイアをすると、これまでのフルタイム勤務からの安定収入が減少します。生活水準を維持するためには、新たな収入源を確保することが必要不可欠です。
投資やFXなどの資産運用に過度に依存するリスクに注意が必要です。市場の変動によって損失を被る可能性もあり、経験不足の状態で大きな投資をすると、セミリタイア生活の継続が難しくなることもあります。
対策としては、複数の収入源を確保する、投資は堅実な方法を選び全資産を投資に回さない、セミリタイア前に実際の収入を試算して実現可能性を検証する、予想外の出費に備えた緊急資金を確保するなどが重要です。中小企業経営者であれば、M&Aによる事業売却も選択肢の一つになります。
住宅ローンなど社会的信用の低下に直面する
「定職に就いていない」という理由で社会的信用が低下することがあります。住宅ローンやクレジットカードの審査が通りにくくなり、賃貸物件の契約更新や新規契約においても審査が通らないケースがあります。
対策としては、セミリタイア前に住宅購入やローン契約を済ませる、個人事業主として開業届を提出し事業としての体裁を整える、安定した資産運用の実績を作っておく、保証会社や保証人の活用を検討するなどが考えられます。
健康管理の重要性が格段に高まる
会社員として働いている間は社会保険に加入しており、健康上の問題が発生しても一定の保障があります。セミリタイア後は自分で健康管理をする必要があり、体調不良で仕事ができなくなれば収入が減少します。また、国民健康保険に切り替わることで医療費の自己負担が増えることもあります。
対策としては、十分な医療保険に加入する、規則正しい生活習慣を維持する自己管理能力を磨く、定期的な健康診断を欠かさない、運動習慣を取り入れるなどが重要です。
再就職が難しくなる現実とその対応策
セミリタイア生活が続けられなくなった場合、元のような条件での再就職は非常に難しくなります。特にブランクが長い場合や年齢が高くなっている場合は、就職市場での競争力が低下します。
対策としては、専門的なスキルや資格を維持・更新する、業界とのつながりを保ち最新動向を把握し続ける、セミリタイア中も小規模な仕事を続けキャリアの連続性を保つ、再就職を想定した資金計画を立てるなどが有効です。
これらのデメリットは、事前に認識し対策を講じておくべき課題であり、十分な準備と計画があれば克服できるものです。
セミリタイアに必要な資金
セミリタイアを実現するには、十分な資金が必要です。ただし、完全リタイアやアーリーリタイアと比べると、セミリタイア後も一定の収入を得ることを前提としているため、必要資金は比較的少なくて済みます。ここでは、年代別の必要資金や資金計画について解説します。
30代・40代・50代それぞれに必要な資金
セミリタイアに必要な資金は、リタイアする年齢によって大きく異なります。年齢が若いほど、年金受給までの期間が長くなるため、より多くの資金が必要になります。
30代でセミリタイアする場合
30代という若さでセミリタイアを実現するには、1,500万〜3,000万円程度の貯金が目安とされています。ただし、この金額は最低限の目安であり、生活水準や家族構成、資産運用の状況によって大きく変わります。30代でセミリタイアする場合、年金受給まで30年以上あるため、不労所得の確保や継続的な収入源が必須です。
投資や副業によって月に10万円以上の収入を確保できれば、2,000万円程度の貯金でもセミリタイアが可能です。若さを活かした再就職の可能性が高いことも、30代でのセミリタイアの特徴です。
40代でセミリタイアする場合
40代でセミリタイアを目指す場合は、3,000万〜5,000万円の貯金が目安とされています。この年代は子どもの教育費や住宅ローンなどの固定費が発生している可能性が高く、それらを加味した計画が必要です。
40代のセミリタイアでは、資産運用による不労所得を安定させることがポイントになります。月に10〜15万円の収入を確保できれば、年金受給までの約20年間を乗り切ることができるでしょう。
50代でセミリタイアする場合
50代は年金受給までの期間が比較的短いため、セミリタイアを検討する上で現実的な年代とされています。必要資金は一般的に5,000万〜7,000万円程度と言われていますが、具体的な金額は生活費やライフスタイル、地域、健康状態などによって異なります。また、子どもが独立している場合は生活費も抑えられることが多く、セミリタイアの準備がしやすくなります。
計算式としては「1カ月の生活費×12カ月×(65−セミリタイアの年齢)+1,000万円」という目安もあります。例えば55歳でセミリタイアし、月20万円の生活費を想定する場合、3,400万円程度の貯金があれば実現可能です。ただし、この計算はあくまで目安であり、インフレや医療費、予期せぬ支出などを考慮する必要があります。
セミリタイア後の月々の生活費を正確に算出する方法
セミリタイアに必要な資金を計算するためには、月々の生活費を正確に把握することが重要です。一般的な算出方法は以下のとおりです。
1.固定費の洗い出し:住居費、保険料、通信費、税金などの毎月必ず発生する費用を詳細に列挙します。
2.変動費の見積もり:食費、光熱費、交通費、娯楽費など月によって変動する費用を過去の実績から平均化します。
3.予備費の計上:突発的な出費や物価上昇に備えて、一定の予備費(月々の支出の10〜20%程度)を加えます。
4.年間イベント費用の月割り:旅行や冠婚葬祭など年に数回発生する費用を月割りで計算します。
総務省統計局の家計調査によると、2人以上の世帯の平均消費支出は月に約30万円、単身世帯では約17万円とされています。ただし、これらの数値は年や調査の時期によって変動する可能性があります。また、住宅ローンや家賃の含まれ方は調査によって異なることがあるため、各自の状況に合わせた調整が必要です。
重要なのは、セミリタイア後に社会保険料や税金の負担が変わることを考慮することです。国民健康保険や国民年金への切り替えによって、以前より負担が増える可能性があります。
収入源を複数確保する戦略
セミリタイア生活を長期的に維持するためには、一定の収入源を複数確保することが重要です。収入確保の主な方法は以下のとおりです。
1.資産運用による不労所得
・配当金を重視した株式投資
・インデックス投資やETF投資による長期的な資産形成
・債券やREIT(不動産投資信託)による収入
・iDeCoやNISAなどの税制優遇制度の活用
2.不動産投資による家賃収入
・アパートやマンションの部屋所有による家賃収入
・駐車場や所有空き地の活用
・不動産クラウドファンディングへの投資
3.スキルを活かした副業や短時間労働
・フリーランスとしての専門スキルの提供
・シニア歓迎の職種でのパートタイム勤務
・趣味や特技を活かした小規模ビジネス
4.事業売却によるまとまった資金の確保
・中小企業経営者であれば、M&Aによる会社売却
・事業の一部譲渡による資金化
・のれん分けや技術提供による継続的なロイヤリティ収入
セミリタイアを成功させるポイントは、収入源の多角化です。一つの収入源に頼りすぎると、その収入が途絶えた際にリスクが高まります。複数の収入源を持つことで、安定したキャッシュフローを確保しましょう。
セミリタイアから年金受給までの具体的な資金計画
セミリタイアから年金受給までの期間をどのように乗り切るかが、セミリタイア計画の重要なポイントです。具体的な資金計画を立てる際には、以下の点を考慮しましょう。
1.資金の段階的な取り崩し計画
・定期預金や国債などの安全資産を計画的に取り崩す
・リスク資産(株式など)は長期保有し、市場環境に応じて売却
・緊急時のための流動性の高い資金を常に確保する
2.年金受給までのつなぎ戦略
・60歳からの特別支給の老齢厚生年金(対象者のみ)の活用
・60歳から受け取れる企業年金や個人年金の活用
・65歳から受け取れる老齢基礎年金・老齢厚生年金の見込み額の把握
3.節税・社会保険料対策
・国民健康保険や国民年金の保険料負担軽減制度の活用
・医療費控除や配偶者控除など、各種税制優遇措置の活用
・住民税の計算方法を理解し、前年の所得に基づく負担増を予測
4.リスク対策
・医療保険や介護保険などの保障の見直し
・予想外の出費に備えた予備費の確保
・資産の流動性を確保し、いつでも現金化できる体制の維持
将来的な年金受給額を把握するためには、「ねんきんネット」で自分の年金記録と見込み額を確認しておくことが重要です。また、セミリタイア後も継続的に収入を得るためのスキルを維持・向上させることで、万が一の場合の再就職も視野に入れておくとよいでしょう。
セミリタイアに必要な資金は一人ひとりのライフスタイルや環境によって大きく異なります。自分自身の生活スタイルや価値観に合った資金計画を立て、余裕を持った準備を心がけることが、充実したセミリタイア生活への第一歩となるでしょう。
なお、本項で触れた収入源の確保や具体的な資金計画について、次項で「実現するための方法」として詳しく解説していきます。
セミリタイアを実現するための3つの方法
セミリタイアという選択肢を実現するためには、計画的な準備と行動が必要です。ここでは、セミリタイアを成功させるための3つの主要な方法について解説します。それぞれの方法には特徴やメリット・デメリットがありますので、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
徹底した節約と資産形成でセミリタイア資金を蓄える
セミリタイアへの第一歩は、まず資金を計画的に蓄えることです。多くの人が最初に取り組むのが、支出の見直しと節約による貯蓄の増加です。
固定費の見直し
毎月必ず発生する固定費を削減することは、貯蓄を増やす効果的な方法のひとつです。住居費、通信費、保険料などを見直すことで、年間で大きな金額の節約につながります。
・住居費:可能であれば、より家賃の安い物件への引越しや、早期のマイホーム購入によるローン完済を目指す
・通信費:格安SIMや格安スマホへの切り替え、不要なオプションの解約
・保険料:必要な保障だけを残し、過剰な保険を見直す
・サブスクリプション:使用頻度の低いサービスの解約
変動費の節約
食費、交通費、娯楽費などの変動費も工夫次第で大きく節約できます。ただし、あまりに極端な節約は生活の質を下げてしまうため、自分にとって重要な支出は残すバランスが大切です。
・食費:自炊の頻度を増やす、セール品や特売品を活用する
・交通費:可能な限り徒歩や自転車を利用する、定期券や割引サービスを活用する
・娯楽費:無料や低コストで楽しめる趣味を見つける
効率的な資産形成
節約によって生まれた余剰資金を効率よく増やすには、計画的な投資が不可欠です。長期的な視点で資産形成を行うことが、セミリタイア資金の蓄積には効果的です。
・インデックス投資:低コストで分散投資できる投資信託やETFへの定期的な積立
・税制優遇制度の活用:NISA(特につみたてNISA)やiDeCoを最大限に活用
・複利効果を最大化:長期間にわたる継続的な投資により、複利効果を最大限に活かす
資産形成においては、高いリターンを狙いすぎずに、安定的に資産を増やすことを意識しましょう。特に若い時期からコツコツと積み立てることで、複利効果によって驚くほど資産が増えていきます。
不動産投資で安定した家賃収入を得る仕組み作り
不動産投資は、セミリタイアを実現するための有力な選択肢として多くの人に選ばれています。その理由は、一定収入を継続的に得られることと、レバレッジを効かせた投資が可能なことにあります。
不動産投資のメリット
・安定した家賃収入:定期的な収入が得られる
・インフレヘッジ:物価上昇に伴い家賃も上昇する傾向があり、インフレに強い
・レバレッジ効果:少ない自己資金で大きな投資が可能(金融機関からの融資を活用)
・運用の委託が可能:管理会社に運営を任せることで、手間をかけずに収入を得られる
不動産投資の始め方
不動産投資を始める際は、まず自分のリスク許容度と目標に合った投資方法を選ぶことが重要です。
・区分所有マンション投資:比較的少額から始められ、リスクも分散しやすい
・一棟アパート・マンション投資:まとまった収入が得られる可能性がある反面、資金も多く必要
・REIT(不動産投資信託):不動産の所有権は持たず、証券市場で売買できる金融商品として投資
特に区分所有マンション投資は、セミリタイアを目指す人が選ぶ人気の方法です。マンションを選ぶ際のポイントとしては、立地(駅からの距離、周辺環境)、物件の品質、利回りなどを総合的に判断しましょう。
不動産投資のリスク管理
不動産投資には空室リスクや修繕費用、金利上昇リスクなどがあります。これらのリスクを最小限に抑えるためには以下の対策が有効です。
・複数の物件に分散投資する
・修繕費用や空室対策のための資金を別途準備しておく
・長期固定金利で借入れを行い、金利上昇リスクを回避する
不動産投資でセミリタイアを実現するためには、無理のない範囲で徐々に物件数を増やし、安定した家賃収入の流れを作ることが大切です。セミリタイア前に複数の物件からの家賃収入で毎月の生活費をカバーできる状態を目指しましょう。
M&Aによる事業売却でセミリタイア資金を一気に確保する
中小企業のオーナーや個人事業主の方にとって、M&A(合併・買収)による事業売却は、セミリタイア資金を一気に確保する有効な方法です。特に後継者問題に悩む経営者にとっては、事業価値を現金化しながら会社の存続も図れる魅力的な選択肢となります。
M&Aのメリット
・まとまった資金を一度に確保できる
・従業員の雇用継続や取引先との関係維持が期待できる
・自社の企業文化や理念を引き継いでもらえる可能性がある
・アドバイザーとして関わることで継続的な収入も得られる
M&Aの進め方
事業売却によるセミリタイアを検討する場合、以下のようなステップで進めるとよいでしょう。
1.事業価値の適正評価:財務状況や将来性を踏まえた企業価値の算定
2.売却先の選定:相性の良い買い手企業の探索と交渉
3.デューデリジェンス(資産査定):買い手企業による詳細な調査への対応
4.最終契約締結:条件交渉と契約書の作成
5.クロージング:実際の売買取引の完了
M&Aを成功させるためには、専門家(M&A仲介会社や弁護士、税理士など)のサポートを受けることが重要です。特に中小企業の場合、適切な売却価格の設定や税務上の最適化など、専門的な知識が必要な場面が多くあります。
M&A後のセミリタイア計画
M&Aで得た資金を元に、セミリタイア後の生活設計を行うことが重要です。一般的には以下のような資金配分を検討します。
・安全資産(定期預金、国債など):生活資金の確保
・利回り資産(不動産投資、株式投資など):インフレ対策と収益確保
・事業再投資:小規模な事業やコンサルティング業などへの投資
事業売却後も技術やノウハウを活かし、顧問やアドバイザーとして関わることで、ゆとりある時間を持ちながら収入を確保するというスタイルも、セミリタイアの一つの形です。
これらの3つの方法は、それぞれ単独でも有効ですが、組み合わせることでより確実にセミリタイアを実現できます。自分の状況や目標に合わせて、最適な方法を選び、計画的に実行していくことが成功への鍵となるでしょう。
セミリタイア成功のための3つの重要ポイント
実際にセミリタイア生活を長期にわたって成功させるには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、セミリタイアを持続可能なものにするための3つの重要なポイントについて解説します。
資産運用と節約を組み合わせた資金確保の方法
セミリタイア成功の第一の鍵は、安定した資金確保です。これを実現するためには、効果的な資産運用と賢明な節約の両方を組み合わせることが重要です。
バランスの良いポートフォリオ構築
資産運用において最も重要なのは、リスクを分散させたバランスの良いポートフォリオを構築することです。単一の金融商品や資産クラスに集中投資すると、市場変動の影響を大きく受ける可能性があります。
・株式:成長性を期待できるが価格変動リスクもある
・債券:安定性はあるが利回りは低め
・不動産:定期的な収入と資産価値の保全が期待できる
・現金・預金:緊急時のための流動性を確保
特に、長期的な視点でセミリタイア生活を送るためには、インフレに対応できる資産と安定収入を生み出す資産をバランスよく保有することが大切です。資産のリバランスも定期的に行い、目標に対して最適な配分を維持しましょう。
効率的な節約の継続
資産運用と並行して、無理のない節約を継続することも重要です。ただし、極端な節約は生活の質を下げ、セミリタイア生活の満足度を低下させる恐れがあります。
・固定費の最適化:住居費、通信費、保険料など継続的に見直す
・ムダな支出の削減:衝動買いを避け、必要なものだけを購入する
・電気代や水道代などの光熱費削減:省エネ習慣を身につける
・ポイント活用や特典プログラムの利用:日常の出費で少しでも節約
「節約疲れ」を起こさないように、自分にとって重要な支出は維持しながら、優先度の低い支出から見直していくことがコツです。
複数の収入源を確保する安定性重視の戦略
セミリタイア生活の安定性を高める2つ目のポイントは、複数の収入源を確保することです。ひとつの収入源に頼ると、それが途絶えた場合に生活が立ち行かなくなるリスクがあります。
収入源の多様化
・不労所得:配当収入、家賃収入、著作権収入など
・労働収入:パートタイム、フリーランス、季節労働など
・副業収入:スキルを活かしたオンラインビジネスやコンサルティングなど
・年金や保険:将来的な公的年金、個人年金などの活用
特に、労働収入と不労所得をバランスよく組み合わせることで、時間的自由を確保しながらも安定した収入を得ることができます。経済情勢や自分の状況が変化しても対応できるよう、柔軟性を持たせることが大切です。
収入源ごとのリスク管理
複数の収入源を持つ際には、それぞれの収入源のリスクを把握し、管理することも重要です。例えば、不動産投資では空室リスクや修繕費用、株式投資では市場変動リスクなどがあります。
・収入源ごとのリスク分析:それぞれのリスク要因を洗い出す
・リスク低減策の実施:保険加入、定期的なメンテナンスなど
・収入バランスの調整:高リスク・高リターンと低リスク・安定リターンの組み合わせ
中小企業経営者の場合、M&Aによる事業売却で得た資金を複数の収入源に分散投資することで、リスクを抑えながら安定した収入を確保できます。
明確な目的意識と時間の使い方の計画
セミリタイア成功の3つ目のポイントは、自由な時間をどう使うかという明確な計画を持つことです。ただ仕事から解放されるだけでは、かえって生きがいを失い、精神的な充足感を得られない可能性があります。
セミリタイア後の生活ビジョン
セミリタイア前に、具体的にどんな生活を送りたいのかを明確にしておくことが重要です。「仕事から逃れたい」という消極的な動機だけでなく、「何をしたいか」という前向きな目標を持ちましょう。
・趣味や特技を深める:時間をかけてこれまでできなかったことに挑戦する
・社会貢献活動:ボランティアなど社会とのつながりを持つ活動
・学び直し:新しい知識やスキルの習得に時間を使う
・家族との時間:子育てや親の介護など、大切な人との時間を優先する
具体的な目標があれば、自由な時間を有意義に使うことができ、充実感のあるセミリタイア生活を送ることができます。
精神的・身体的健康の維持
セミリタイア後は生活リズムが変わるため、意識的に健康管理を行うことも大切です。
・定期的な運動:健康維持のために適度な運動を習慣化する
・社会とのつながり:友人や地域との交流を維持する
・知的好奇心の充足:読書や学習などで頭を活性化させる
・食生活の管理:規則正しい食事で健康を維持する
セミリタイア生活を長く続けるには、健康であることが大前提です。充実した時間を過ごすためにも、健康管理は怠らないようにしましょう。
これら3つのポイントを押さえることで、セミリタイア生活をより安定させ、充実したものにすることができます。経済的な安定と精神的な充足のバランスが取れてこそ、真のセミリタイア成功と言えるでしょう。
セミリタイアで後悔しないための4つの準備
セミリタイアは魅力的な選択肢ですが、計画なしに飛び込むと後悔することになりかねません。ここでは、セミリタイア生活を始める前に準備しておくべき4つのポイントを解説します。
綿密な資金計画を立てて経済的な行き詰まりを防ぐ
セミリタイア後に最も後悔する原因の一つが、資金の行き詰まりです。生涯にわたるキャッシュフロー予測を立て、インフレや医療費増加も考慮しましょう。緊急資金として最低でも半年〜1年分の生活費を確保し、投資は市場変動リスクを考慮した計画が重要です。
・10年、20年、30年後の収支計画を立てる
・インフレに対応した資産配分を行う
・医療費の増加を考慮した資金計画を立てる
・緊急資金を別途確保しておく
セミリタイア後の明確な目標と活動計画を設定する
「会社を辞めたい」という消極的理由だけでは、自由時間を得た後に虚無感に襲われることがあります。具体的な目標があれば充実感を得やすくなります。趣味、新スキル習得、ボランティアなど、やりたいことを見つけておきましょう。
・短期、中期、長期の目標をリストアップする
・週間・月間のスケジュールを大まかに計画する
・挑戦したい新しい活動やスキルを考える
・社会との接点を維持する方法を考えておく
保険料や税金など見落としがちな固定費用を算入する
社会保険料や税金などの固定費用は見落としがちです。会社負担だった部分もすべて自己負担になることを忘れないようにしましょう。特に、住民税は前年所得に対して課税されるため、退職翌年も高額になる点に注意が必要です。
・国民健康保険料:市区町村によって金額が異なる
・国民年金保険料:月額約17,510円(2025年度)
・住民税:前年の所得に対して課税される
・固定資産税:不動産所有者は毎年支払いが必要
万が一の場合の復帰プランを事前に考えておく
予期せぬ事態に備えて復帰プランを考えておくことも重要です。年齢が高く就業ブランクが長いほど、条件の良い再就職は難しくなります。スキルや資格の維持・更新、人脈の確保が大切です。
・専門的なスキルや知識を定期的に更新する
・業界の人脈やネットワークを維持する
・フリーランスやパートタイムなど柔軟な働き方の選択肢を持つ
・復帰に備えて小規模な副業を継続する
これら4つの準備を念入りに行うことで、セミリタイア後の生活をより安定させ、後悔のリスクを減らすことができます。
まとめ|セミリタイアは自分らしい生き方のひとつ
セミリタイアは単なる早期退職ではなく、自分らしい生き方を選択するための手段です。十分な準備と計画があれば、若いうちから時間的・経済的な自由を手に入れ、充実した人生を送ることができます。中小企業オーナーの方はM&Aによる事業売却も視野に入れながら、自分に合ったセミリタイアの形を模索してみてはいかがでしょうか。大切なのは、「何から逃れるか」ではなく「何を実現したいか」という前向きな目標を持つことです。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。