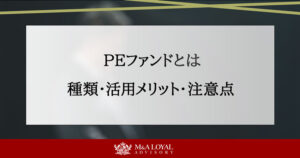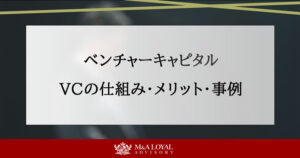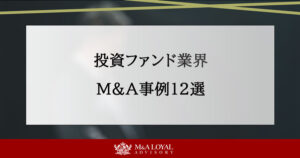プライベートエクイティとは?PE投資のメリットやリスクを徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
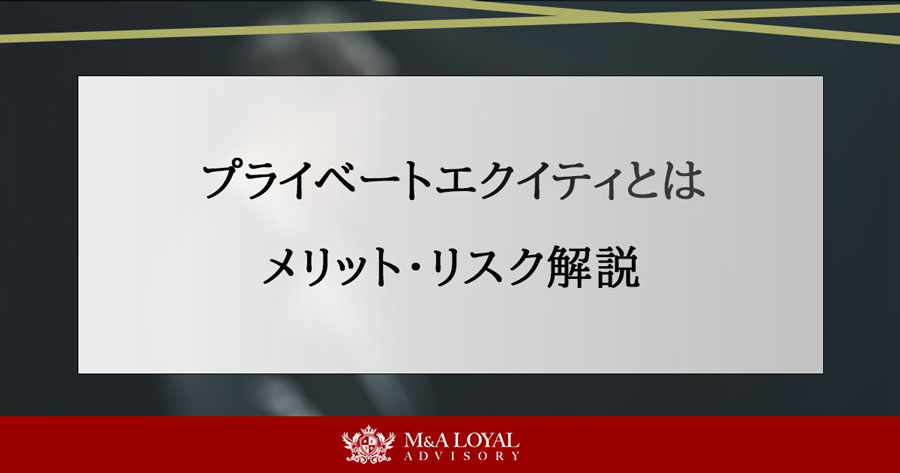
プライベートエクイティ(Private Equity、PE)は、近年、中小企業の事業承継や成長戦略において注目を集めており、PEファンドからの投資を受ける企業が急速に増加しています。特に後継者不足に悩む中小企業のオーナーにとって、プライベートエクイティを活用した投資は事業承継の有力な選択肢の一つです。
PEファンドを活用することにより、企業は資金調達や経営ノウハウの獲得、さらにはIPOやM&Aといった将来的な出口戦略まで幅広い支援を受けることができます。本記事では、プライベートエクイティの基本的な仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説します。
目次
プライベートエクイティ(PE)の基本的な仕組み
プライベートエクイティ(PE)の基本的な仕組みを理解するためには、まず未公開株式と上場株式の違いを把握することが重要です。上場企業の株式はパブリック(公開)株式と呼ばれ、証券取引所で誰でも自由に売買できます。一方、未公開株式は、証券取引所では取引されない非上場企業の株式のことを指します。
プライベートエクイティとは|未公開株式の特徴と価値
プライベートエクイティとは、「Private(非公開・未上場)」と「Equity(株式・株主資本)」が合わさった言葉で、証券取引所に上場していない企業の株式(未公開株式)を意味します。この未公開株式への投資をPE投資と呼びますが、プライベートエクイティ=PE投資を示すケースも多々あります。
未公開株式は一般的に創業者やその親族、取引先などの限られた関係者が保有しており、流動性が低い反面、成長ポテンシャルが高い企業の株式は高値で取引される傾向があります。これは、上場企業と比較して情報開示が限定的であり、投資家にとってリスクが高い一方で、成功した場合のリターンも大きいためです。
プライベートエクイティファンドは、こうした未公開企業に対して資金を提供し、経営に積極的に関与することで企業価値の向上を図ります。多くの場合、過半数の株式を取得して経営権を握り、専門的な知識と豊富な経験を活かして企業の成長を支援します。
プライベートエクイティ投資とは
プライベートエクイティ投資(PE投資)とは、非公開企業に対して資本を提供し、企業価値を高めた上で、株式の売却や上場によって利益を回収する投資活動を指します。
未上場企業は一定の基準を満たさなければ、証券取引所を通じた資金調達ができないため、代替手段としてプライベートエクイティが重要な役割を果たします。
成長・成熟企業や経営再建を要する企業が主な投資対象であり、単なる出資にとどまらず、経営戦略・組織改革・業務改善などの支援まで行うことが多いです。
エグジット(投資回収)の手法としては、新規株式公開(IPO)やM&Aが一般的であり、企業価値の向上によって得られたリターンは投資家へ分配されます。
プライベートエクイティファンドとは
プライベートエクイティファンド(PEファンド)とは、複数の投資家から資金を集め、大規模なPE投資を実行する投資ファンドです。 ファンドとは、投資家からお金を集めて、まとまったお金を運用・分配する仕組みの金融商品で「投資信託」とも呼ばれます。
投資ファンドは、主に機関投資家や年金基金、事業会社、富裕層などから資金を調達し、数年〜十数年の運用期間を設定します。ファンドマネージャーが投資先を選定し、過半数の株式取得や役員派遣などを通じて企業価値を高め、最終的に株式を売却してリターンを得ることを目的とします。
なお、PEファンドを運営する組織はプライベートエクイティファーム(PEファーム)と呼ばれ、少数精鋭の専門家チームによって構成されます。PEファームの収益源は、投資家から受け取るマネジメントフィー(管理報酬)と、キャリードインタレスト(運用益に応じた成功報酬)です。
プライベートエクイティの投資から回収までのプロセス
プライベートエクイティ投資の典型的なプロセスは「資金調達 」「投資」「運用 」「投資回収」「収益分配 」の5つの段階に分けられます。各ステップの詳細については後述しますが、投資判断の段階では、対象企業の事業内容、財務状況、成長性などを詳細に分析し、投資価値を見極めます。投資実行後は、単なる資金提供にとどまらず、経営陣の派遣や戦略立案、業務効率化などの経営支援を通じて企業価値の向上に取り組みます。
最終的には、IPO(株式公開)やM&A(企業買収・合併)、他の投資家への株式売却などの方法で投資を回収し、利益を確定させます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



プライベートエクイティ投資の目的
プライベートエクイティ投資の主な目的は以下の通りです。
- 高いリターンの追求
- 企業の成長促進
- 企業の再構築・再生
- 事業承継の支援
それぞれについて解説します。
高いリターンの追求
PEファンドは、未公開企業に投資することで市場の変動を避けつつ、企業価値を高める戦略を採用します。これにより、投資家に対して優れたリターンを提供することを目的としています。投資先企業の業績向上や効率化は、この目的を達成するための重要な要素です。
企業の成長促進
PEファンドは、資金に加えて経営ノウハウや専門的な支援を提供し、企業が新たな市場に参入したり、製品やサービスのラインアップを拡充できるようサポートします。この支援により企業の競争力が強化され、長期的な成長が可能になります。
企業の再構築・再生
経営難に陥った企業に対して、PEファンドは資本の再編成や組織改革を行います。持続可能なビジネスモデルの構築を支援することで、企業は新たな活力を得て経営を安定化させることができます。
事業承継の支援
特に中小企業では後継者不足が深刻な課題です。PEファンドが経営権を取得することで、円滑な事業承継を実現し、企業の存続を支援します。
プライベートエクイティ投資は、これらの多様な目的を持ち、それぞれの企業のニーズに応じた柔軟なアプローチを提供します。これにより、投資家と企業双方にとっての価値を最大化することを目指しています。
プライベートエクイティの投資対象企業
プライベートエクイティ投資の対象となる企業は多様ですが、主に次の3つが挙げられます。
- ベンチャー企業(スタートアップ)
- 大企業の子会社やノンコア事業
- オーナー経営の中小企業
それぞれの特徴を解説します。
ベンチャー企業(スタートアップ)
PE投資は成熟した企業や成長が見込まれる企業に対して行われることが一般的です。ベンチャー企業やスタートアップは、主にベンチャーキャピタル(VC)の対象となります。
大企業の子会社やノンコア事業
上場企業の傘下にある子会社や、中核でないノンコア事業もPE投資の対象です。 親会社が戦略的に経営資源を集中する中で、採算が合わない・注力対象でない事業が切り離されることがあり、PEファンドがそれらを独立させて再生を支援し、企業価値を高めてエグジットを図るケースが増えています。
オーナー経営の中小企業
少子高齢化や後継者不在に悩むオーナー中小企業にとって、PEファンドは経営支援と事業承継を一体で提供する存在です。 技術力や地域密着型の強みを持ちながら、後継者問題で廃業の危機にある中小企業に対し、資本と人材を提供し、M&Aや持続可能な成長を実現します。
プライベートエクイティ投資の種類と特徴
プライベートエクイティ投資は、投資対象企業の成長段階や状況に応じて、いくつかの異なる種類に分類されます。それぞれの投資手法には独自の特徴があり、企業のニーズに応じて最適な投資形態を選択することが重要です。
ベンチャーキャピタル投資(VC投資)
ベンチャーキャピタル投資は、成長初期段階にあるスタートアップ企業や新興企業を対象とした投資手法です。これらの企業は革新的な技術やビジネスモデルを持つ一方で、事業の不確実性が高く、従来の銀行融資では資金調達が困難な場合が多いのが特徴です。
ベンチャーキャピタル投資では、高いリスクを取る代わりに、成功した場合の高いリターンを期待しており、創業者主導の自由度を保ちながら資金提供とネットワークや知見提供といったアドバイザリー中心の支援スタイルが一般的です。
バイアウト投資
バイアウト投資は、買収後に経営陣の派遣などによって企業価値を高め、買収金額より高値で売却することで利益を得る手法です。プライベートエクイティファンドが対象企業の過半数株式を取得し、経営権を掌握することで、より積極的な経営改革を実行します。
バイアウト投資の対象となる企業には、大企業の子会社やノンコア事業、オーナー経営の中小企業などがあります。これらの企業は安定した収益基盤を持つ一方で、成長性の向上や経営効率化の余地が大きい場合が多く、プライベートエクイティファンドの専門性を活かした改革が期待されます。
借入金を活用して企業を買収し、自己資本を抑えて大規模な投資を実現する「レバレッジド・バイアウト(LBO)」が特に活用されています。 また、「マネジメント・バイアウト(MBO)」では、既存の経営陣が主体となって企業を買収することで、経営の自由度を高めつつ事業承継や上場廃止を目的としたケースが見られます。なお、成長企業に対して経営権を取得せずに少数株主として資金提供を行う方法は「グロースキャピタル」と呼ばれます。
企業再生投資
企業再生投資は、業績不振に陥った企業を対象として、組織改革や事業再構築を通じて再成長を目指す投資手法です。財務的な困難を抱えた企業であっても、優れた技術や市場ポジションを持つ場合には、適切な経営改革により企業価値を回復できる可能性があります。
投資対象は、財務面・事業面に課題を抱える企業が中心で、株式取得やデット・エクイティ・スワップ(DES)などを通じて経営に深く関与します。不採算事業の売却や人員整理、M&A戦略、資本構成の見直しなどを実行し、再生を図る点が特徴です。
投資後は、再生ノウハウを持つ専門家が企業に派遣され、短期的なコスト削減から中長期の成長戦略までを支援します。ターンアラウンド(成長による再生)やワークアウト(リストラによる再生)といったアプローチも状況に応じて採用されます。
再生が成功すれば株式売却やM&Aを通じて大きなリターンが見込める一方で、投資リスクも大きいです。
ディストレス投資
ディストレス投資は、破綻寸前の企業を安価で買収し、大規模なリストラや事業再編を実行することで企業価値の回復を狙う、より高リスク・高リターンの投資手法です。これらの投資には高度な専門知識と豊富な経験が必要とされ、限られた投資家のみが参入している分野です。
再建を目的とする再生ファンドと近い性質を持ちますが、ディストレスファンドはより危機的状況にある企業に対する投資を対象とする点で区別されます。 ディストレスファンドは、景気後退期や金融危機の局面において投資機会が増える傾向がある一方、景気回復局面では対象案件が減少するなど、市況による影響を受けやすい側面があります。
【ステージ別のPE投資例】
| 投資タイプ | ステージ |
|---|---|
| ベンチャーキャピタル | 創業期~成長期 |
| バイアウト | 安定期~成熟期 |
| 企業再生 | 衰退・再成長期 |
| ディストレス | 破綻 |
プライベートエクイティ投資と一言で言っても、どの種類を選択するかは投資家の目標やリスク許容度、そして市場環境によって大きく異なります。最適な投資戦略を選ぶには、投資先企業の状況を的確に評価し、適切なリスク管理を行うことが重要です。PE投資のそれぞれの特徴とリスクを把握し、投資家は自らの目標に合ったものを慎重に選択する必要があります。
プライベートエクイティ投資のメリット
中小企業のオーナーがプライベートエクイティファンドからの投資を検討する際、様々なメリットを享受できる可能性があります。これらのメリットは、単なる資金調達にとどまらず、企業の成長戦略や事業承継にまで幅広く影響を与えます。
PE投資を受ける側のメリット
PEファンドを受ける主なメリットとして以下が挙げられます。
- 資金調達の多様化と柔軟性
- 経営ノウハウと専門知識の獲得
- 事業承継問題の解決
- IPO・M&A実現に向けた支援
それぞれについて解説します。
資金調達の多様化と柔軟性
従来の銀行融資と比較して、プライベートエクイティ投資は返済義務や利息負担がないという大きな利点があります。銀行融資の場合、毎月の返済資金を確保する必要があり、キャッシュフローに制約を受けることがありますが、株式投資の形態であれば、そうした制約から解放されます。
また、プライベートエクイティファンドは、企業の成長に必要な設備投資や研究開発費、人材採用費など、幅広い用途での資金活用を支援してくれるため、経営の自由度が高まります。特に成長投資に積極的な企業にとって、この柔軟性は大きな価値を持ちます。
経営ノウハウと専門知識の獲得
プライベートエクイティファンドは、豊富な投資経験と経営ノウハウを蓄積しており、投資先企業に対して単なる資金提供以上の価値を提供します。具体的には、戦略立案、組織改革、業務効率化、マーケティング強化など、企業経営の各分野において専門的な支援を受けることができます。
特に中小企業のオーナーにとって、大企業での経営経験を持つプロフェッショナルからのアドバイスは貴重な学習機会となります。また、プライベートエクイティファンドのネットワークを活用することで、新たなビジネスパートナーや顧客の開拓、優秀な人材の確保なども期待できます。
事業承継問題の解決
多くの中小企業が直面している後継者不足の問題に対して、プライベートエクイティ投資は有効な解決策の一つとなります。創業者が高齢化し、適切な後継者が見つからない場合でも、プライベートエクイティファンドが経営を引き継ぎ、企業の継続と発展を支援することができます。
この場合、創業者は株式売却により適正な対価を得ることができ、従業員の雇用も維持され、取引先との関係も継続されるため、関係者全員にとってメリットのある解決策となります。また、プライベートエクイティファンドは将来的なIPOやM&Aも視野に入れているため、企業のさらなる成長可能性も期待できます。
IPO・M&A実現に向けた支援
プライベートエクイティファンドは、投資回収の手段として株式公開(IPO)や企業売却(M&A)を検討するため、これらの実現に向けた具体的な支援を提供します。IPOを目指す場合には、財務管理体制の整備、内部統制の強化、情報開示体制の構築などが必要となりますが、これらの準備作業についても専門的なサポートを受けることができます。
M&Aによる企業売却を選択する場合にも、買い手企業の選定、企業価値の最大化、交渉戦略の立案など、高度な専門知識が必要な領域において、プライベートエクイティファンドの経験とネットワークを活用できます。
PE投資をする側のメリット
PEファンドを行う主なメリットとして以下が挙げられます。
- 主体的な経営関与によって高いリターンを狙える
- リスク分散になる
- インパクト投資としての側面がある
それぞれについて解説します。
主体的な経営関与によって高いリターンを狙える
PE投資の最大の魅力は、高いリターンを得られる可能性がある点です。未上場企業の株式を安価な段階で取得し、企業価値が向上した後にIPOやM&Aを通じて売却することで、大きなキャピタルゲインが期待できます。
加えて、PEファンドは単なる資金提供にとどまらず、投資先企業の経営に積極的に関与します。自社のノウハウや人材、ネットワークといったリソースを活用し、経営改革や成長戦略を主導することで、企業価値の向上を自らの手で実現できます。
このように、自社主導でリターンを最大化できる点は、PE投資ならではの大きな強みといえます。特に成長性の高いベンチャー企業や再生可能性のある企業では、短期間で数倍のリターンを実現するケースもあります。
リスク分散になる
PE投資は、伝統的な金融資産(株式・債券など)とは異なる動きをするオルタナティブ投資であり、投資ポートフォリオのリスク分散に有効です。
未上場企業は一般市場の価格変動に左右されにくい側面があるため、経済の不安定な局面でも一定のリターンを期待できることがあります。
また、異なる業種・成長段階の企業に分散して投資することで、一部の投資失敗による損失を他の成功案件で相殺できる可能性があります。
インパクト投資としての側面がある
近年PE投資は、社会的課題の解決と経済的リターンの両立を図る「インパクト投資」としても注目されています。
例えば、中小企業の事業承継支援や地域経済の再生、再生可能エネルギーや医療・福祉分野への投資などは、社会に具体的な変化をもたらしながら、資産価値の向上も期待できる取り組みです。
このような投資は、長期的な資産形成の手段としても優れており、単なる収益追求にとどまらず、実社会へのポジティブな影響を意識した投資戦略を展開できます。
プライベートエクイティ投資のデメリットと注意点
プライベートエクイティ投資には多くのメリットがある一方で、企業オーナーが理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。投資を検討する際には、これらのリスクを十分に検討し、自社の状況に適した判断を行うことが重要です。
PE投資を受ける側のデメリット
PE投資を受ける側のデメリットは以下があります。
- 経営の自由度低下と意思決定プロセスの変化
- イグジット圧力と長期的視点のバランス
- 企業文化や従業員への影響
それぞれについて解説します。
経営の自由度低下と意思決定プロセスの変化
プライベートエクイティファンドが過半数の株式を取得した場合、企業の経営権は実質的にファンド側に移ることになります。これまで創業者や既存オーナーが独断で決定できていた経営判断も、ファンドとの協議や承認が必要となる場合があります。
特に重要な投資判断、人事決定、事業戦略の変更などについては、ファンドの同意なしには実行できなくなる可能性があり、経営の自由度が制限される点は十分に理解しておく必要があります。ただし、これは必ずしもデメリットとは限らず、客観的な視点からの経営判断により、より良い結果をもたらす場合もあります。
イグジット圧力と長期的視点のバランス
プライベートエクイティファンドは、一般的に3年から7年程度の投資期間を設定しており、その期間内に投資を回収することを目指しています。このため、短期的な業績向上や企業価値向上に重点を置く傾向があり、長期的な研究開発投資や人材育成投資が後回しにされる可能性があります。
また、イグジットが前提となっているため、いずれは現在の投資家との関係は終了することになります。企業の将来を考える上で、イグジット後の経営体制や成長戦略についても事前に検討しておくことが重要です。
企業文化や従業員への影響
プライベートエクイティファンドによる経営改革は、しばしば組織の効率化や業務プロセスの見直しを伴います。これらの変化は企業の競争力向上には必要なものですが、従来の企業文化や働き方の変更を要求される場合があります。
従業員にとっては、新しい経営方針への適応や、場合によっては人員整理などの可能性もあるため、変化への不安や抵抗感が生じる可能性があります。こうした問題を最小限に抑えるためには、変更の必要性と将来への展望について、従業員との十分なコミュニケーションが不可欠です。
PE投資をする側のデメリット
PEファンドを行う主なデメリットとして以下が挙げられます。
- 大きなリターンが期待できる反面、リスクが大きい
- 短期的な売却益を期待できない
- 未上場企業は透明性が低い
それぞれについて解説します。
大きなリターンが期待できる反面、リスクが大きい
PE投資は、リターンが大きい一方で、非常に高いリスクを伴います。投資先の多くは、成長初期のベンチャー企業や経営再建中の企業などであり、事業の失敗や環境変化によって企業価値が下がるリスクがあります。
特に収益基盤が未成熟な企業では、経営が破綻するリスクも高く、元本毀損(きそん)の可能性も否定できません。
短期的な売却益を期待できない
PE投資は、基本的に中長期視点での資産運用が前提となるため、短期的な売却益を期待する投資家には向いていません。上場株式のように日々売買できるものではなく、エグジット(IPOやM&A)までに数年単位の投資期間を要します。
また、企業価値が思うように上昇しなければ、エグジットの時期が予想より遅れる可能性もあり、資金の流動性が極めて低い点は大きな制約といえます。そのため、いつ・どれほどのリターンが得られるかが不透明で、資金回収計画が立てにくいです。
未上場企業は透明性が低い
PE投資の対象となる未上場企業は、上場企業と異なり情報開示の義務が限定的であり、財務状況や経営内容に関する情報が不十分なことが多く見られます。そのため、投資判断の根拠となる材料が少なく、精度の高い分析が難しいという課題があります。
また、企業の経営体制やガバナンスの整備が不十分なケースも多く、投資後に予想外のリスクが顕在化することもあり得ます。
プライベートエクイティ投資の流れ
プライベートエクイティ投資が実行される際の流れは次のとおりです。
- 資金調達(ファンドレイズ)
- 投資(ソーシング・エグゼキューション)
- 運用(バリューアップ)
- 投資回収(イグジット)
- 収益分配
それぞれを順番に解説します。
資金調達(ファンドレイズ)
まず、PEファンドの運営主体であるゼネラル・パートナー(GP)は、機関投資家・年金基金・事業会社・富裕層などのリミテッド・パートナー(LP)から出資を募り、投資資金を集めます。
この段階では、ファンドの投資戦略や対象業種、リスク水準、運用期間などを明示し、ファンドの枠組みが形成されます。
投資(ソージング・エグゼキューション)
次に、PEファンドは市場調査や人脈・ネットワークを活用して投資候補企業を探索します。対象企業が見つかれば、詳細なデューデリジェンス(財務・法務・事業調査)を実施し、評価結果を基に投資条件を詰めて契約を締結します。
株式の過半数を取得するケースも多く、MBOやLBOなどの手法が用いられることもあります。
運用(バリューアップ)
出資・買収後は、企業の経営に積極的に関与し、ガバナンス体制の整備や事業ポートフォリオの再構築、人材の強化、コスト削減などに取り組みます。
前述のとおり、単なる資金提供ではなく、PEファンドは経営パートナーとして企業価値を高めることに注力します。
投資回収(イグジット)
企業価値が十分に向上した段階で、PEファンドは投資回収を実施します。
方法としては、IPO、M&Aによる売却、または経営陣への自社株買い戻しなどがあります。これにより、ファンドは投資元本と利益の回収を目指します。
収益分配
最後に、イグジットによって得られた収益は、LPに対して分配されます。キャリードインタレスト(残余利益の一定割合)は、GPの成功報酬として支払われます。
プライベートエクイティ投資における判断材料
プライベートエクイティ投資を実施するかを判断する際、次の要素を持って検討されることが多いです。
- 企業価値
- 財務健全性
- 経営力・成長ポテンシャル
それぞれについて解説します。
企業価値
PE投資において、企業の本質的な価値を適切に見極めることは最も重要なプロセスのひとつです。
企業価値の評価方法としては、将来のキャッシュフローを割り引いて算出するDCF法や、同業他社との指標比較に基づくマルチプル法(EV/EBITDAやPERなど)、そして収益に基づく収益還元法などが用いられます。
財務健全性
企業の財務状況も、PEファンドが投資対象を選定する上で不可欠な判断基準です。特に注目されるのは「EBITDA(利払い・税引前・減価償却前利益)」で、本業の収益力を示す代表的な指標です。
また、負債比率(Debt-to-Equity Ratio)や自己資本比率なども重要であり、資本構成が過度にレバレッジ(借り入れ依存)になっていないかを確認します。
経営力・成長ポテンシャル
PE投資では、財務だけでなく企業の将来性や経営体制も重視されます。市場規模や成長率など、属する業界の将来性を調査した上で、その企業がどのような競争優位性(技術力、ブランド、営業力など)を持つかが分析されます。
また、投資後に成長戦略を実行できるかどうかは、経営陣の実行力や経験にかかっているため、ファンドはリーダーの能力や組織の柔軟性も評価します。
プライベートエクイティ投資における企業価値評価
プライベートエクイティ投資において、適正な投資価格を決定するための企業価値評価は極めて重要なプロセスです。未公開企業の場合、上場企業のような市場価格が存在しないため、様々な評価手法を組み合わせて企業価値を算定する必要があります。
主要な企業価値評価手法
企業価値評価には大きく分けて3つのアプローチがあります。コストアプローチは、企業が保有する資産の価値から負債を差し引いた純資産を基礎として企業価値を算定する評価方法で、簿価純資産法や清算価値法などが代表的です。
マーケットアプローチは、類似する上場企業や取引事例と比較することで企業価値を評価する手法です。インカムアプローチは、企業が将来生み出す利益やキャッシュフローの現在価値に基づいて企業価値を算定する手法です。それぞれの特徴と代表的な手法を以下の表にまとめました。
| 評価アプローチ | 基本的な考え方 | 代表的な手法 |
|---|---|---|
| コストアプローチ | 純資産価値に基づく評価 | 簿価純資産法、清算価値法 |
| マーケットアプローチ | 類似企業との比較による評価 | マルチプル法、取引比較法 |
| インカムアプローチ | 将来利益の現在価値による評価 | DCF法、配当還元法 |
DCF法による将来価値の算定
インカムアプローチの代表格であるDCF(Discounted Cash Flow)法は、企業が将来生み出すキャッシュフローを現在価値に割り戻して企業価値を算定する手法です。この方法は企業の収益力と成長性を直接的に評価に反映できるため、プライベートエクイティ投資では特に重視されます。
DCF法では、3年から5年程度の事業計画に基づいて将来キャッシュフローを予測し、適切な割引率(将来の価値を現在の価値に換算する際に使用する率)を用いて現在価値を算出するため、企業の成長戦略や投資計画の妥当性についても詳細に検討されます。これにより、単純な財務指標だけでは把握できない企業の真の価値を評価することが可能になります。
譲渡先選定におけるプライベートエクイティファンドと一般事業会社の比較
企業の売却を検討する際、プライベートエクイティファンドと一般事業会社のどちらを譲渡先として選択するかは、企業の将来戦略や創業者の意向によって大きく変わります。それぞれに異なる特徴とメリットがあるため、慎重な検討が必要です。
プライベートエクイティファンドへの譲渡メリット
プライベートエクイティファンドは、豊富な資金力と専門的な経営ノウハウ、幅広いネットワークを持っています。これらの経営資源を活用することで、短期間での企業価値向上が期待できます。また、ファンドは投資のプロフェッショナルであるため、企業の成長ポテンシャルを最大限に引き出すための戦略立案と実行に長けています。
特に、将来的なIPOや更なるM&Aを視野に入れている企業にとって、プライベートエクイティファンドの持つ経験とネットワークは極めて価値の高いものとなります。ファンドは過去の投資経験から、成功に導くための具体的な施策を熟知しており、企業の成長を加速させることができます。
一般事業会社への譲渡との違い
一般事業会社への譲渡(戦略的買収)の場合、買い手企業の既存事業との間でシナジー効果を期待できる点が大きな特徴です。販売チャネルの統合、技術の相互活用、調達コストの削減など、事業統合によるメリットを享受できる可能性があります。
| 譲渡先の種類 | 主な提供価値 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| プライベートエクイティファンド | 資金・人材・ネットワーク | 短期間での企業価値向上 |
| 一般事業会社 | 設備・販路・技術シナジー | 事業統合による効率化 |
ただし、一般事業会社への譲渡の場合、買い手企業の経営方針や企業文化の影響を強く受ける可能性があります。組織統合の過程で、従来の事業運営方法や企業文化が大きく変化することもあるため、従業員や取引先への影響も考慮する必要があります。
プライベートエクイティによるM&A成功事例
プライベートエクイティ投資の効果を具体的に理解するために、実際の成功事例を見てみましょう。これらの事例は、プライベートエクイティファンドがどのように企業価値を向上させ、投資回収を実現したかを示す貴重な参考資料となります。
資生堂によるパーソナルケア事業のCVCキャピタルパートナーズへの売却
2021年2月、資生堂は、パーソナルケア事業の国内分を新設会社「ファイントゥデイ資生堂」に承継させ、同社の株式をCVCキャピタルパートナーズが助言するファンド出資先のOBH社へ譲渡すると発表しました。
本件は、資生堂が中長期経営戦略として掲げる「スキンビューティー領域での世界No.1」達成に向けた構造改革の一環であり、高価格帯・高付加価値のスキンケア製品に経営資源を集中する目的がありました。
譲渡対象であるパーソナルケア事業は、企業全体の売上の約9%を占めています。この事業は、化粧品と比較して商品単価が安価であり、競合する大手企業も多数存在しています。こうした状況の中で、資生堂は高単価商品への「選択と集中」を図るために、事業売却を選択したと考えられます。
特に、マスビジネスに特化した柔軟な戦略や迅速な意思決定を行い、価値創造力の高い人材を育成することが求められています。資生堂は、世界23拠点に展開するプライベートエクイティファンドであるCVCの迅速な意思決定や資金調達力を活用し、ブランド育成や研究開発を加速させることを狙っています。
参考:資生堂/パーソナルケア事業1600億円で譲渡、合弁事業化で新会社設立
ニチイ学館のベインキャピタルへの売却
2020年5月、米系PEファンド「ベインキャピタル」は、介護・医療関連事業を展開するニチイ学館に対してTOB(株式公開買い付け)を実施することを発表。同年8月にニチイ学館はMBO(経営陣による買収)により非公開企業となりました。
当時、ニチイ学館では複数のノンコア事業の赤字が経営を圧迫しており、経営資源の再配分が喫緊の課題でした。非公開化を通じて、短期的な株主利益への配慮から解放され、中長期的な視点での構造改革が可能となりました。
PE投資後は、収益性の低いノンコア事業からの撤退・売却を進め、コア事業にリソースを集中。2024年に日本生命保険相互会社がニチイHDを2100億円程度で買収し、ニチイ学館は日本生命グループに仲間入りしました。
参考:MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ/株式会社ニチイホールディングスの株式取得完了について
CLSAキャピタルパートナーズ、タスク・フォースへの資本参加
CLSAキャピタルパートナーズがアドバイザーを務める日本企業特化型投資ファンド「Sunrise Capital IV」は、株式会社タスク・フォースへの資本参加を2022年3月に完了しました。
タスク・フォースは、企業主導型保育園や事業所内保育所を全国で約120施設運営しており、高品質な保育サービスや柔軟な預け方による社会的価値が高く評価されています。今回の資本参加は、経営基盤の強化と持続的な成長支援を目的としており、経営体制やブランド名に変更はなく、現体制のまま運営が継続されます。
リップルウッドによる日本テレコム買収事例
2003年に米国のプライベートエクイティファンドであるリップルウッドが日本テレコムを総額2,613億円で買収した事例は、日本におけるプライベートエクイティ投資の代表的な成功例として知られています。リップルウッドは買収後、経営効率化と事業再編を実施し、わずか1年後の2004年にソフトバンクに3,400億円で売却しました。
この取引では、短期間で約800億円の投資利益を実現し、高いリターンを達成したことで、日本市場におけるプライベートエクイティ投資の可能性を示しました。成功の要因は、通信業界の構造変化を的確に予測し、適切なタイミングでの買収と売却を実現したことにあります。
ベインキャピタルによるすかいらーくHD再生事例
2011年にベインキャピタルが実施したすかいらーくホールディングスの買収事例も、企業再生型投資の成功例として注目されています。当時、すかいらーくは業績低迷に苦しんでいましたが、ベインキャピタルは総合的な経営改革を実施しました。
具体的には、ブランドの再構築、店舗運営の効率化、メニュー開発力の強化、デジタル化の推進などを通じて、企業価値の向上を図りました。これらの取り組みの結果、2014年に東京証券取引所への再上場を果たし、ベインキャピタルは 2017 年までに保有株式の売却を完了しました。
参考:三田証券株式リサーチ
成功事例から学ぶポイント
これらの成功事例に共通するのは、プライベートエクイティファンドが単なる財務投資家ではなく、積極的に経営に関与し、企業価値向上のための具体的な施策を実行していることです。市場環境の変化を的確に捉え、企業の競争力強化のための戦略を立案・実行する能力が成功の鍵となっています。
また、適切なイグジット戦略の立案と実行も重要な成功要因であり、IPOやM&Aのタイミングを見極める能力が投資リターンを大きく左右することが分かります。これらの事例から、プライベートエクイティ投資が企業と投資家の両方にとって価値創造の機会となり得ることが確認できます。
まとめ
プライベートエクイティは、未公開企業への投資を通じて企業価値の向上を目指す投資手法であり、資金調達、経営改善、事業承継支援など多面的なメリットを企業に提供します。特に後継者不足に悩む中小企業オーナーにとって、プライベートエクイティファンドからの投資は事業継続と発展のための有力な選択肢となります。
一方で、経営権の移転やイグジット圧力といったデメリットも存在するため、投資を検討する際には十分な情報収集と専門家への相談が不可欠です。企業価値評価や譲渡先の選定においても、自社の状況と将来戦略に最適な判断を行うことが重要となります。
プライベートエクイティ投資に関するご相談や企業価値評価、M&A戦略の検討をお考えの企業オーナー様は、専門的な知識と豊富な経験を持つアドバイザーにご相談いただくことをお勧めいたします。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。