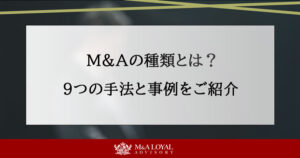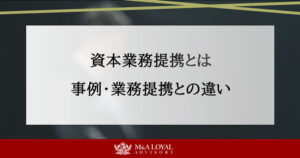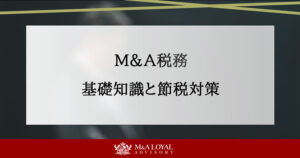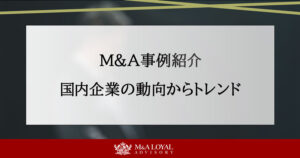ストラクチャーとは?M&Aでの意味と種類、スキームとの違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
ストラクチャーという言葉は、ビジネスのさまざまな場面で使われますが、M&Aの分野では少し異なる意味合いを持ちます。M&Aにおけるストラクチャーとは、取引全体の枠組みや仕組みを指します。具体的には、株式譲渡や事業譲渡、合併といった取引形態の選定から、税務・法務の最適化、資金調達方法、リスク管理など、さまざまな要素を総合的に設計することを意味します。
企業の成長戦略を実現する手段としてM&Aが活用される中で、このストラクチャーをどう設計するかは、取引を効率的かつ円滑に進めるために欠かせないポイントとなります。本記事では、ストラクチャーの基本的な考え方やM&Aにおける役割と種類、さらにはスキームとの違いまで、わかりやすく解説していきます。
目次
ストラクチャーとは|基本的な意味をわかりやすく解説
ストラクチャーとは何か、基本的な意味について解説します。
ストラクチャーの意味と語源
ストラクチャーとは、物事の構造や骨組みを意味する言葉で、ビジネスや金融、建築、さらにはワインの表現など、さまざまな分野で使われます。例えば、建築分野では建物の構造や骨組み、構成要素および建造物全体を指し、ワインの世界では風味の骨格を示す言葉として「しっかりとしたストラクチャーのあるワイン」などと表現されます。
ストラクチャーは英語で「structure」と表記され、「構造」「構成」「組織」などを意味します。日本語では「ストラクチュア」と表記されることもあります。この言葉は、ラテン語の「structura(建てられたもの、構造)」に由来し、さらにその語源は「組み立てる」「築く」という意味の動詞「struere(ストゥルエーレ)」にさかのぼります。
また、金融や投資分野で使われる「ストラクチャードファイナンス」や、医療・介護分野で用いられる「ストラクチャー指標」という言葉もあります。さらに、日常的によく耳にする「インフラ」や「リストラ」も、ストラクチャーから派生した言葉です。
| インフラ:infrastructure(インフラストラクチャー) リストラ:restructuring(リストラクチャリング) |
M&Aにおけるストラクチャーとは
M&Aにおけるストラクチャーは、ビジネスや金融で使われるストラクチャーとは少し異なり、企業の買収・統合を実行する際の具体的な手段や手法を意味します。主なM&A手法には、株式譲渡や事業譲渡、株式交換、会社分割、合併、第三者割当増資などがあり、M&Aの目的や状況に応じて最適な手段が選択されます。
ストラクチャーは、単に取引の手法や枠組みを決めるだけでなく、企業文化や組織の統合にも大きな影響を及ぼします。適切なストラクチャーを選ぶことで、M&Aによって期待されるシナジー効果を最大限に引き出し、統合後のプロセスをスムーズに進めることが可能になります。そのため、ストラクチャーの設計には、法務や財務の専門家だけでなく、戦略的な視点を持つ経営陣の積極的な関与が不可欠です。
また、ストラクチャーを選択する際には、取引に関わるすべてのステークホルダーへの影響を十分に考慮することが求められます。さらに、法規制や税制の変更、市場環境の変化といった外部要因にも注意を払い、状況に応じて柔軟に見直しを行う必要があります。
ストラクチャーとスキームの違い
ストラクチャーとスキームの違いについても触れていきます。M&A業界と金融機関では両者の扱われ方が異なります。
- M&A業界においてはほぼ同義
M&A業界では、ストラクチャーとスキームはほぼ同義で使われることが多いです。どちらも、株式譲渡や事業譲渡など、具体的な実行手段や手法を指します。ただし、実務ではストラクチャーよりもスキームの方が一般的に用いられる傾向があります。
- 金融業界における違い
金融業界では、ストラクチャーは仕組みや構造全体、すなわちファイナンスの設計全体を指すのに対し、スキームは特定の取引や資金調達の枠組みを意味することが多く、やや異なるニュアンスがあります。例えば、「ストラクチャードファイナンス」では、複数の手法を組み合わせた全体的な金融設計全体を指し、「スキーム」はその中の具体的な実行計画や構成要素を指します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



M&Aにおけるストラクチャーの種類
M&Aとは、「Mergers and Acquisitions」の略で、日本語では「合併と買収」と訳されます。一般的には、M&Aというと資本提携のうち経営権(支配権)の移動を伴うものを指しますが、広義のM&Aでは資本提携全般を含むこともあります。一方で、資本の移動を伴わない提携は一般的に「業務提携」と呼ばれます。
狭義のM&Aのストラクチャーは、買収・合併・会社分割に分類できます。合併とは、複数の企業が統合し、1つの会社として再編される手法であり、買収はある企業が他の企業の経営権を取得することを指します。また、会社分割は合併や買収とは異なる企業再編手法ですが、支配権の移動を伴う場合には、M&Aに含まれます。
M&Aのストラクチャーの種類として代表的なものには、株式譲渡・事業譲渡・株式交換・株式移転・会社分割・合併・第三者割当増資があります。
M&Aのストラクチャー①買収
M&Aで特に多く採用されるストラクチャーの一つが買収です。買収ストラクチャーには以下の2つがあります。
- 株式取得
- 事業譲渡
それぞれについて解説します。
株式取得
株式取得とは、売り手企業の株式を取得することで、買い手企業が売り手企業の経営権を得るストラクチャーです。株式取得にはさまざまな手法があり、それぞれに特徴があります。
- 株式譲渡
株式譲渡とは、売り手企業が保有する株式を譲渡代金と引き換えに買い手企業へ譲渡し、経営権(支配権)を移転するストラクチャーです。株式譲渡は、合併や事業譲渡と比べて手続きが比較的簡易で、会社や事業をそのまま承継できる点が特徴です。そのため、M&Aにおいて最も一般的な手法であり、中小企業のM&Aでも広く用いられています。
株式譲渡では、売却後も会社の法人格は消滅せず、会社自体が存続します。このため、売り手企業の従業員や取引先への影響は比較的小さく、後継者問題を解決する手段としても有効です。ただし、売り手と資産と負債はすべて買い手に承継されるため、買い手は簿外債務などのリスクも引き継ぐ点には注意が必要です。
また、株式譲渡の一形態である「TOB(株式公開買付)」は主に上場企業の買収で利用されます。
- 株式交換
株式交換とは、売り手企業の全株式を買い手企業が取得し、対価として自社株を売り手企業に交付するストラクチャーです。買収対価が現金ではなく株式であるため、資金が乏しい場合でも実行可能である点が大きな特徴です。
株式交換も売り手企業が法人格を維持するため、段階的な統合やブランドの保持が可能です。一方で、株式の交換比率の算定には手間とコストがかかり、買い手企業の株主構成にも影響を与えるため、慎重な対応が求められます。
- 株式移転
株式移転は、既存会社の全株式を新会社に移し、既存会社を完全子会社、新会社を完全親会社とする組織再編手法です。株式移転には、1社が単独で行う「単独株式移転」と複数の企業が共同で行う「共同株式移転」があります。単独株式移転はグループ再編、共同株式移転は異業種連携や経営統合に活用されます。
株式移転も法人格を維持したまま組織再編が可能です。株式交換との違いは親会社となるのが既存会社か新会社かという点にあります。株式移転の対価は新会社が発行する株式で支払われます。株価算定や会計処理、持株比率の変動にも留意が求められます。
- 株式交付
株式交付とは、2021年の会社法改正により導入された、比較的新しいM&Aストラクチャーです。買い手企業が自社株式を対価として、売り手企業の株式を取得し、子会社化を行う制度という点では株式交換に似ています。
株式交付と株式交換の違いとしては、株式交換が子会社の株式を100%取得し、完全子会社化を前提としていたのに対し、株式交付は取得する株式が50%超から100%までと柔軟に対応できることです。このため、段階的な子会社化や資本提携にも利用しやすい特徴があります。ただし、株式交付は、売り手企業と買い手企業がともに株式会社である必要があります。
- 第三者割当増資
第三者割当増資は特定の第三者に新株を発行することで、資金調達と経営権取得を同時に行うストラクチャーです。公募増資と異なり、対象を限定して新株を発行する点が特徴です。この仕組みを利用し、買い手は売り手の新株を引き受けることで議決権を取得し、実質的な支配権を得ることができます。
戦略提携や経営支援を目的とする場合に活用されますが、新株発行に伴い株式の希薄化が起こるため、既存株主への説明と合意が不可欠です。また、発行価格の設定には慎重さが求められます。
事業譲渡
事業譲渡とは、企業が営む事業の全部または一部を他の企業に譲渡するストラクチャーです。譲渡対象の範囲を柔軟に設定できることから、売り手企業にとっては不要な部門の切り離しや「選択と集中」の戦略に活用でき、買い手企業にとっても必要な事業だけを取得できるというメリットがあります。
ただし、事業譲渡は会社法上の「組織再編行為」には該当しないため、譲渡対象ごとに個別の契約や移転手続きが必要です。例えば、資産や負債の移転、許認可の再取得、従業員や取引先との契約再締結などが発生するため、手続きが煩雑になりやすい点はデメリットです。
なお、事業譲渡には主に2つの手法があります。
- 一部譲渡
一部譲渡は、企業が特定の事業部門だけを他社に譲渡する手法で、会社自体は存続します。中核事業への集中や不要部門の整理に適しており、売却資金は新規投資や財務改善に活用可能です。買い手にとっても必要な資産や人材を選んで取得でき、効率的な買収が可能です。
- 全部譲渡
全部譲渡は企業が事業の全体を一括して他社に譲渡する手法で、実質的な事業撤退を意味することが大半です。法人は存続しますが、営業活動を失い清算や休眠となるケースもあります。会社法上、売り手側において株主総会での特別決議が必要です。ただし、買い手側については特別決議が不要な場合が一般的です。
M&Aのストラクチャー②合併
合併とは、複数の会社を1つの会社に統合する組織再編の手法であり、形式的にも実質的にも企業を一本化するM&Aストラクチャーです。
合併は、他社と結合することで事業規模の拡大を図ったり、グループ企業間での機能統合を進めたりする際に活用されます。また、業績不振企業の救済や繰越欠損金の引き継ぎといった税務上のメリットを得る目的でも用いられます。さらに、合併対価に株式を用いることで、資金負担を伴わずに実行可能であり、効率的な再編手段として広く利用されています。
合併には「吸収合併」と「新設合併」の2種類があります。
吸収合併
吸収合併とは、1つの会社(存続会社)が他の会社の全ての権利義務(資産・負債・契約など)を包括的に承継し、合併相手の会社は消滅する形式の合併です。新会社の設立を伴わないため、通常は手続きが比較的簡易で、既存の組織体制を生かしやすいというメリットがあります。この形式は、グループ企業の機能統合や、迅速な再編が求められる場合に多く用いられます。
新設合併
新設合併は、関与する全ての会社が解散し、新会社に権利義務を承継させる手法で、対等な統合や新ブランドでの再出発に適しています。許認可の再取得や上場手続きが必要なため、吸収合併より手続きが複雑でコストもかかります。税制適格なら課税繰り延べが可能で、会計面ではパーチェス法や連結処理など専門対応が求められます。
M&Aのストラクチャー③会社分割
会社分割とは、会社が営む事業の全部または一部を、他の会社に承継させる組織再編ストラクチャーです。会社分割は「吸収分割」と「新設分割」の2つの形態があり、事業の切り離しや経営のスリム化、グループ再編など、さまざまな目的で活用されます。
会社分割では、事業に関する権利義務が包括的に承継されるため、事業譲渡のように個別の契約や許認可の移転手続きを行う必要がなく、手続きが簡素化される点がメリットです。ただし、会社法上の組織再編に該当するため、株主総会の特別決議や、場合によっては債権者保護手続きが必要となる点には注意が必要です。
吸収分割
吸収分割は、会社の事業の全部または一部を既存の他社に承継させる手法で、新法人設立が不要なため実行が比較的スムーズです。好調事業への集中や赤字部門の切り離し、戦略提携などに活用され、契約や従業員の権利義務も包括的に承継されます。一方、買い手は負債も引き継ぐリスクがあり、EPSの希薄化などにも注意が必要です。
新設分割
新設分割は、会社の事業の全部または一部を新たに設立する会社に承継させる手法で、事業の独立性を保ちながら柔軟な再編が可能です。将来の上場やグループ内再編を目的に活用されます。「分社型」「分割型」で対価の受け手や税務処理が異なります。なお、業種によっては新会社での許認可再取得が必要な場合もあり、事前確認が重要です。
会社分割に類似する戦略的手法
会社分割と類似する戦略的手法として、次の方法があります。
- スピンオフ
スピンオフは、親会社が保有する子会社株式を既存の株主に分配し、子会社を親会社から独立させる方法です。完全分離型の再編手法として、企業グループの機動性や企業価値の最大化を目的に行われます。
- スピンアウト
スピンアウトとは、企業が自社の一部門や特定の事業を切り離し、独立した新会社として設立するプロセスを指します。スタートアップや技術系ベンチャーに多く見られる形態で、企業内のイノベーション促進にもつながります。
- カーブアウト
カーブアウトは、特定事業を分社化した上で、その株式の一部を外部に売却する手法です。親会社は引き続き支配権を保持しつつ、資金調達やパートナーシップの構築が可能です。
広義のM&Aのストラクチャー
経営権の移動を伴わない資本提携であっても、広義のM&Aとして扱われることがあります。広義のM&Aストラクチャーについて説明します。
株式の持ち合い
株式の持ち合いは、企業同士が互いに株式を保有し合う資本提携の一形態で、長期的で安定した関係を築くのに有効です。取引先との関係強化や買収防衛策としても活用されます。ただし、監視機能の低下やガバナンスの弱体化、資本効率の悪化といったデメリットもあるため注意が必要です。
合弁会社の設立
合弁会社の設立は、複数の企業が資本を出し合い共同経営を行う手法で、ジョイント・ベンチャーとも呼ばれます。互いの強みを活かし、新規事業や異業種進出、多角化を目的に活用されます。資金・人材・技術を共有しながら運営するため、リスク分散にも有効です。特に外国企業が単独進出できない国では、現地パートナーとの合弁設立が有効な進出手段となります。
持株会社設立によるグループ再編
持株会社設立によるグループ再編は、複数の企業が新たに親会社を設立し、その傘下に入る形で経営統合を行う手法です。株式移転を通じて持株会社が設立され、子会社を統制・管理します。
例えば、ZホールディングスはソフトバンクとNAVERの共同出資による企業であり、LINEとヤフーの株式を100%保有しています。ただし、この手法は経営資源の共有や連携が進む一方、シナジー効果は合併より限定的で、不祥事の影響が全体に波及するリスクもあります。
M&A以外(業務提携)のストラクチャー
業務提携のストラクチャーには、次のような形態があります。
- 販売提携
- 技術提携
- 生産提携
それぞれ解説します。
販売提携
販売提携は、自社の製品やサービスの販売・営業活動を他社と協力して行う業務提携の一種であり、株主構成や経営権を変更することなく、収益拡大や市場拡大を目指せるストラクチャーです。主な契約形態としては、商品を仕入れて販売する「販売店契約」、本部のノウハウを活用してロイヤルティーを支払う「フランチャイズ契約」、販売を代行する「代理店契約」などがあります。これらの契約は、販売責任や契約主体、在庫管理の役割分担に違いがあります。
技術提携
技術提携とは、企業同士が技術面で協力する契約です。「共同開発型」は双方の技術力を持ち寄って新たな技術の研究・開発を進めるもので、「ライセンス契約型」は一方の企業が保有する技術を他社に提供し、その技術を用いた製品開発や製造を行います。
技術提携は、開発コストを複数社で分担でき、企業の負担を軽減しながら開発スピードを高める効果が期待されます。また、OEM(他社による製造)やODM(他社による設計・製造)も、技術提供と製品供給を組み合わせた形式として技術提携に含まれることがあります。
生産提携
生産提携とは、自社製品の生産や製造業務を他社に委託する形の業務提携です。自社の生産能力が不足している場合や、需要の増加により既存設備では供給が間に合わない場合に活用されます。ただし、委託先が自社と同等の品質基準を満たす製品を安定的に供給できるかどうかは、提携の成否を左右する重要な要素です。
その他の提携
業務提携には他にもさまざまな形態があり、企業の目的や課題に応じて柔軟に活用されています。
- 調達提携
複数の企業が原材料や部品などを共同で購入する提携です。発注量をまとめることでスケールメリットが生まれ、仕入価格の引き下げや交渉力の強化につながります。コスト削減を目的とした、実用性の高い提携です。
- 物流提携(流通提携)
倉庫や輸送インフラを共有し、物流の効率化を図る提携です。配送コストの削減や物流網の最適化が期待でき、特に中小企業にとっては資源の有効活用が可能です。
- 人材提携
社員の出向や人材交流を通じて、相互に人材を育成し、技術の共有を図る提携です。経営ノウハウの伝達や人材不足の補完策として活用されます。
- マーケティング提携
広告・プロモーション・市場調査などを共同で行う提携です。ブランド価値の向上や販路拡大を目指す企業にとって、相乗効果が期待できます。
- 地域・海外展開提携
特定地域や海外市場への進出に際し、現地企業と連携する提携です。市場開拓のリスクを抑えつつ、現地事情に精通したパートナーと共同で事業を進められる点が特徴です。
M&Aにおけるストラクチャーの選択ポイント
M&Aを検討する際には、どのストラクチャーを選ぶべきか迷うことがあるかもしれません。ここでは、ストラクチャーを選択する際に押さえておきたいポイントについて解説します。
買い手・売り手共通のポイント
売り手企業・買い手企業の双方にとって、M&Aで適切なストラクチャーを選ぶためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 必要な手続きや税負担の違いを理解する
- スケジュール設定
それぞれについて解説します。
必要な手続きや税負担の違いを理解する
M&Aにおいては、選択するストラクチャーによって必要な手続きや課税の仕組みが大きく異なります。そのため、税務や法務の観点から慎重な判断が求められます。株主総会や債権者保護手続きの有無、譲渡により発生する税金の違いを理解する必要があります。
| ストラクチャー | 株主総会 | 債権者保護手続き | 売り手の税金 |
|---|---|---|---|
| 株式譲渡 | 原則不要(譲渡制限株式では必要) | 不要 | 個人:譲渡益に対して、20.315%(所得税・住民税) 法人:譲渡益に対して約30~34%(所得により異なる) 消費税は課税されない |
| 事業譲渡 | 必要(特別決議) | 不要 | 売り手:譲渡益に対して約30%~34% 買い手:課税対象資産に対して消費税や不動産取得税、登録免許税が課される |
| 合併 | 必要(特別決議) | 必要 | 適格合併:売り手・買い手ともに課税なし 非適格合併:売り手に法人税が課税 |
| 会社分割 | 必要(特別決議) | 必要 | 適格分割:売り手・買い手ともに課税なし非適格分割:売り手に法人税が課税 |
スケジュール設定
ストラクチャーの選定にあたっては、取引の実行スケジュールも重要な判断材料です。特に、売り手企業が早期の資金回収や事業再生を目指している場合には、迅速なクロージングが求められます。
例えば、事業譲渡では売却対象の範囲を限定・細分化できるため、買い手企業のリスクを抑えやすいです。一方で、譲渡対象の従業員や取引先との個別契約の再締結が必要となるため、手続きに時間を要する点には留意が必要です。
これに対し、株式譲渡であれば、債権者保護手続きが不要なため、比較的短期間での実行が可能です。
買い手のポイント
買い手企業がM&Aにおいて適切なストラクチャーを選定する際には、次のポイントを押さえることが重要です。
- 取得対象とする事業の範囲
- M&A後の事業の統合形態・支配レベル
- 不確実な要素の縮小
それぞれについて解説します。
取得対象とする事業の範囲
ストラクチャーを検討するにあたっては、まず取得対象となる事業の範囲を明確にすることが出発点です。企業全体を取得するのか、特定の事業部門に限定するのかによって、適切な手法や必要な手続きが大きく異なるためです。
例えば、事業の一部のみを取得する場合は、事業譲渡や会社分割が選択肢となりやすく、企業全体を取得する場合は、株式譲渡や合併といった手法が一般的に用いられます。
M&A後の事業の統合形態・支配レベル
M&A後の事業の統合形態や支配レベルに応じて、選択すべきストラクチャーは異なります。
取得対象の事業が自社と密接に関連している場合は、株式譲渡や合併による完全統合が有効です。この場合、ブランドや組織の統合も比較的スムーズに進めることができます。一方、関連性が低い事業であれば、新会社を設立して分社的に運営する形が望ましく、会社分割や事業譲渡といった手法が適しています。
また、支配権の取得を目的とする場合には、株式譲渡や第三者割当増資、株式交換・移転などの手法を活用することで、関与度に応じた持株比率を柔軟に設定できます。
不確実な要素の縮小
M&Aにおける買い手企業のストラクチャー選定では、訴訟リスクや簿外債務、税務否認リスクなど、不確実な要素をどの程度回避・分離できるかが重要な判断基準です。
これらのリスクを最小限に抑えたい場合には、不要な債務や契約を含まない事業譲渡や会社分割が有効です。一方、株式譲渡は手続きが簡易でスピーディーに実行できる反面、全てのリスクを承継するため、表明保証や補償条項など契約面での十分な保護が必要です。
売り手のポイント
売り手企業において適切なストラクチャーを選ぶポイントは次のとおりです。
- 売却する事業範囲の選択
- 投資回収方法
- 譲渡後における支配のレベル
それぞれについて解説します。
売却する事業範囲の選択
売却する事業の範囲は、ストラクチャー選定における重要な判断基準です。売り手企業の事業戦略やスケジュールに応じて、ノンコア事業の切り離しや迅速な手続きが求められる場合には、対象を絞ったストラクチャーの採用が効果的です。
また、コスト効率の良い手法を選択することが重要です。近年増加している第三者への事業承継においては、会社全体を譲渡する場合には株式譲渡、株式交換、株式交付が、特定の事業単位での譲渡には事業譲渡や会社分割が適しています。
投資回収方法
M&Aにおいて投資回収を目的とする場合、売り手企業にとって最も重要なのは対価の受け取り方法です。対価が現金か株式かによって、最終的な手取り額や税負担が大きく異なります。
例えば、売り手企業の株主が現金による回収を希望する場合は、株式譲渡や事業譲渡が一般的です。一方、売り手企業が対象会社自身である場合には、買い手企業が対象会社に直接出資をする形で第三者割当増資が用いられることがあります。
これらのストラクチャーは、税務・法務・資金面において異なる影響を及ぼすため、投資回収を最大化するには、専門家の助言を得て慎重に選定することが重要です。
譲渡後における支配のレベル
売り手企業が、譲渡後にどの程度経営に関与・支配するかは、ストラクチャー選定の重要な判断軸です。例えば、完全に経営から撤退し、資金を回収したい場合には、株式譲渡や事業譲渡が適しています。基本的に、売却後は経営から完全に離れられます。
一方で、譲渡後も一定の経営関与を残したい場合には、株式の一部譲渡や合弁会社の設立などにより、支配権の一部を保持しつつ、段階的な資金回収や事業成長を図る方法が有効です。さらに、支配権を維持したまま資金を調達したい場合、第三者割当増資を活用すれば経営の主導権を手放さずに外部資本を導入できます。また、株式交付を利用すれば支配権を維持しつつ他の企業や資産を取得することも可能です。
考慮する点(法務・税務・会計)
M&Aのストラクチャーを決定する際には、法務、税務、会計の各側面からの詳細な検討が不可欠です。まず、法務面では契約書の内容や合併・買収に関わる法的な制約を確認し、法令遵守を徹底することが大切です。特に、独占禁止法や労働法などが取引に影響を及ぼす可能性があり、これらの規制に違反すると罰則が科されるだけでなく、取引そのものが無効となるリスクもあります。
次に税務面では、取引に伴う税金の影響を慎重に評価する必要があります。例えば、株式譲渡や資産移転にかかる税負担を最小限に抑えるために、最適なストラクチャーを選ぶことが求められます。また、国際的な取引の場合は各国の税制を把握し、二重課税を回避するための対策を講じることが重要です。
さらに、会計面では、取引を買収後の財務報告にどのように反映させるかが大きな課題となります。特に、のれんの計上や資産の評価方法は、企業の財務状況に直接影響を与えるため、適切な対応が必要です。正しい会計処理を行うことで、投資家や利害関係者に対して透明性の高い財務情報を提供でき、それが企業の信頼性向上にもつながります。
これらの要素を総合的に考慮し、法務・税務・会計それぞれの専門家の意見を取り入れながらストラクチャーを選定することが、M&Aを成功させるための大きな鍵となります。
M&Aのストラクチャー別の成功事例8選
M&Aは目的や状況に応じて多様な手法が選ばれます。
- 株式譲渡
- 株式交換
- 株式移転
- 第三者割当増資
- 事業譲渡
- 合併
- 会社分割
- 資本提携(+合弁会社設立)
ここでは、実際に活用された代表的な8つのストラクチャーごとに、主な成功事例を紹介します。
株式譲渡
2021年、株式会社ベネッセホールディングスは、株式会社プロトコーポレーションから株式会社プロトメディカルケアの全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。教育や介護・保育を主力とするベネッセは、この株式譲渡により介護分野での事業拡大を図りました。
プロトメディカルケアは、介護・福祉・医療分野でのメディア運営や人材派遣、福祉用具の販売・レンタルなどを展開しており、譲渡後も事業は継続しています。社名は「ハートメディカルケア」へ変更されたものの、ブランドや業務体制に大きな変更はなく、円滑な経営引き継ぎが実現しました。
株式交換
2016年、トヨタ株式会社は株式交換によりダイハツ工業株式会社を完全子会社化しました。ダイハツ株1株に対し、トヨタ株0.26株を割り当てる形で実施され、ダイハツ株は上場廃止となりました。
両社は1967年から提携を開始し、小型車分野で協力関係を築いてきました。1998年にトヨタが子会社化し、2016年には小型車事業の強化と連携拡大を目的に完全子会社化へと至りました。
この再編により、トヨタはダイハツをグループに統合しつつ、各ブランドの独自性を維持しながら、グローバル市場での競争力強化を実現しました。
株式移転
2021年、マツモトキヨシホールディングスとココカラファインは、新会社「株式会社マツキヨココカラ&カンパニー」を設立。株式移転によって両社を傘下に置いて経営統合を実施しました。両社は新会社の子会社として法人格を維持しながら、共同事業体制を構築しています。
この手法により、大手企業同士の複雑な組織統合を回避しつつ、実質的な経営統合を実現しました。統合後の店舗数は3,400店を超え、ドラッグストア業界で最大規模となり、売上シェアも国内第3位まで拡大しました。
第三者割当増資
2022年、株式会社アイスタイルは、三井物産および米Amazonとの資本業務提携により、第三者割当増資を実施しました。同社は「@cosme」を運営する国内最大級のコスメ情報企業です。本提携では、Amazonと三井物産からそれぞれ新株予約権付社債および新株予約権を引き受け、アイスタイルは大規模な資金調達を実現しました。
この提携により、Amazon上に公式通販「@cosme SHOPPING」が開設され、三井物産とは国内外のネットワークを活用した新規事業の展開も予定されています。
事業譲渡
2016年10月、ソニー株式会社は電池事業を約175億円で村田製作所に譲渡しました。リチウムイオン電池の商用化で実績を持つソニーでしたが、2009年以降の赤字を受け、経営再建の一環として事業再編を進めていました。
これまでにも、2014年にパソコン事業を日本産業パートナーズ(JIP)へ、2016年にはカメラモジュール製造子会社の株式を中国企業へ譲渡するなどの施策を実施しました。こうした再編を経て、ソニーは経営危機を脱し、2023年にはグループ全体で過去最高の売上高を記録するまでに回復しました。
合併
2005年、三菱東京フィナンシャル・グループ(東京三菱銀行)とUFJホールディングス(UFJ銀行)が合併し、三菱東京UFJ銀行(現・三菱UFJ銀行)が誕生しました。1998年の持株会社制度の解禁を機に、銀行業界では再編が進み、東京三菱銀行は東京銀行と三菱銀行の合併、UFJ銀行は三和銀行と東海銀行の統合により誕生していました。
こうした再編を経て誕生した三菱UFJ銀行は、日本の3大メガバンクの一角を占め、現在では国内最多の企業のメインバンクとして圧倒的な存在感を誇っています。
会社分割
2019年、合同会社DMM.comは、MVNO事業「DMM mobile」とインターネット回線事業「DMM光」を会社分割により楽天モバイル株式会社へ承継しました。この分割によって、DMMは非中核事業を切り離し、コア事業への経営資源集中とともに約23億円の対価を獲得しました。一方、楽天は通信事業の拡大と「楽天エコシステム」の強化に活用し、ID連携によるサービス統合を進めました。
資本提携(+合弁会社設立)
2017年、トヨタ自動車とマツダは資本提携に合意し、互いに約500億円を出資して株式を取得。トヨタはマツダの第2位の株主となり、関係強化を図りました。
この提携は、EV市場の競争激化に対応するもので、技術開発や先進安全技術の連携、製品ラインアップの補完を目的としています。また、米国政府の要請を受けて合弁会社を設立し、米国での新工場建設も進められました。
2024年1月には、車載システムの共通化により、開発コストを7〜8割削減できる見通しが示されるなど、提携によるシナジー効果が顕著に現れています。
M&Aのストラクチャーに関するQ&A
最後に、M&Aのストラクチャーに関するよくある質問とその回答を紹介します。
中小企業のM&Aで最も多く取り入れられる手法は?
中小企業のM&Aでは、株式譲渡が最も多く採用されています。株式譲渡は、売り手企業の株主が保有する株式を買い手に譲渡することで経営権を移転する方法であり、事業の一体性を保ちつつ、従業員や取引先との関係も維持しやすいという特徴があります。
中小企業におけるM&Aは、後継者不在などを背景に年々増加しています。特に、経営者の高齢化が進む中で、親族承継が減少し、第三者への承継ニーズが高まっているのです。2023年には第三者への事業承継が過去最高の成約件数で2,023件に達しました。
事業の一部だけ残すことはできるのか?
事業の一部のみを残してM&Aを実施する場合には、会社分割という手法が有効です。例えば、複数店舗を運営する企業が特定の店舗のみを残し、それ以外を譲渡したい場合などに活用されます。
具体的には、残したい事業を新会社に移して本体を譲渡する方法(いわゆる「ヨコの会社分割」)や、譲渡対象の事業のみを子会社化して売却する方法(「タテの会社分割」)などがあります。これにより、経営者が一部事業を継続したり、親族に承継する余地を残すことが可能です。
どの手法が一番成功しやすい?
成功しやすいとされるストラクチャーは、会社分割や事業譲渡を活用し、事業を切り分けて売却する方法です。買い手のニーズに応じて、必要な事業だけを対象とすることで、より魅力的な条件で提示しやすくなります。
また、不採算部門や経営資源を圧迫している事業を除外し、収益性の高い部分のみを譲渡することで、買い手の関心を高め、成約率を高める効果が期待できます。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
M&Aにおいてストラクチャーの構築は、取引を効率よくスムーズに行ううえで重要です。目的に応じたベストな手法を選定することによって、M&A成功の確率が高まるでしょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。