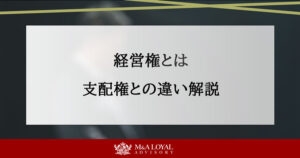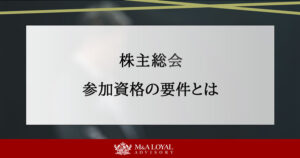株主総会とは?種類から決議事項、開催の流れをわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
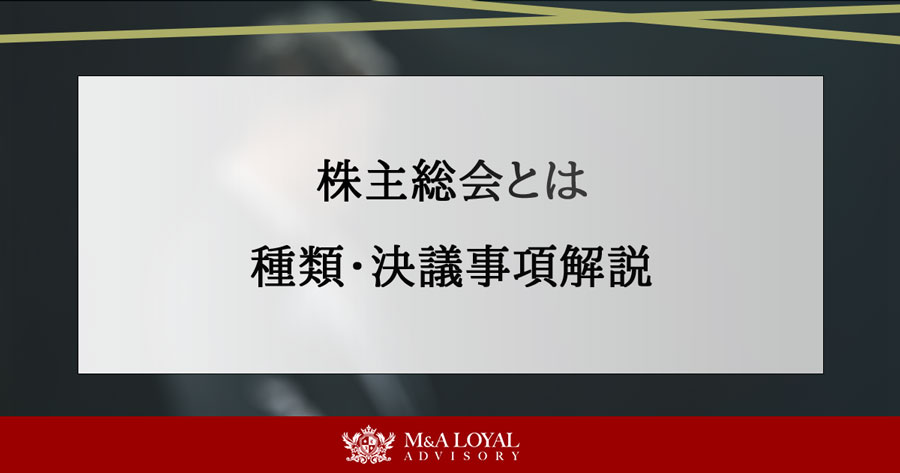
株主総会とは、株式会社における最高意思決定機関であり、会社の重要事項を決議する場です。会社売却やM&A実行には株主総会の承認が原則として必要であるため、経営者が理解しておくべき仕組みです。
近年ではオンライン開催も可能となり、株主が参加しやすい形態へと変化しています。本記事では、株主総会の定義から種類、決議事項、開催の流れまで、中小企業のオーナーが押さえておくべきポイントを解説します。
目次
株主総会とは?会社法上の定義をわかりやすく解説
株主総会とは、会社法第295条に基づいて設けられた株式会社の最高意思決定機関です。会社の組織や経営に関する重要事項を決議し、株主が権利を行使する場として機能します。
株主総会の法的位置づけを理解するには、株主の権利を知る必要があります。株主の権利は「自益権」と「共益権」の2つに分類されます。
- 自益権:個人の利益に影響を与える権利
- 共益権:株主全体の利益に影響を与える権利
株主総会の権限は会社法295条に明記されています。
| 1.株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 2.前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 3.この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。 |
また、会社法105条には株主の権利が規定されています。
| 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 ・剰余金の配当を受ける権利 ・残余財産の分配を受ける権利 ・株主総会における議決権 |
株主が持つ自益権と共益権
自益権とは、株主が会社から直接的な経済的利益を受け取る権利です。具体的には、利益配当請求権や残余財産分配請求権があります。
- 利益配当請求権:会社が解散して負債を利益を上げた際に配当金を受け取る権利。
- 残余財産分配請求権:会社が解散後、負債を返済して残った財産の分配を受け取る権利。
一方、共益権は株主が会社の経営に参加し、経営を監督するための権利です。共益権はさらに「単独株主権」と「少数株主権」に細分化されます。
- 単独株主権:株式1単元株でも保有していれば行使できる権利。議決権の行使や株主総会における質問権などが含まれる。
- 少数株主権:一定割合以上の株式を保有する株主のみが行使できる権利。株主総会の招集請求権や会社解散請求権などがある。
株主総会が果たす2つの目的
株主総会には大きく分けて2つの目的があります。第一に、経営の監視機能です。取締役が適切に経営を行っているかを株主が監督し、経営の透明性を確保する役割を担います。
第二に、情報収集の機会としての役割です。株主は株主総会を通じて会社の経営状況や今後の方針を詳しく把握し、自らの投資判断に活かすことができます。中小企業においても、これらの目的は変わりません。特にM&Aを検討する場合、株主総会での意思決定プロセスが売却の成否を左右することもあるため、その重要性は一層高まります。
株主総会と取締役会の違い
株主総会と混同されやすいのが取締役会ですが、両者は明確に異なる役割を持っています。以下の表で主な違いを整理します。
| 区分 | 株主総会 | 取締役会 |
|---|---|---|
| 法的位置づけ | 最高意思決定機関 | 業務執行の決定機関 |
| 構成メンバー | 株主全員 | 取締役 |
| 主な決議事項 | 定款変更、取締役選任、配当など | 経営計画、予算執行、重要な業務執行など |
| 開催頻度 | 年1回以上の定時総会+必要に応じて臨時総会 | 原則として年4回以上 |
| 収集通知の期間 | 原則開催日の2週間前までに通知 | 原則開催日の1週間前までに通知 |
| 法的根拠 | 会社法第295条 | 会社法第362条 |
株主総会は会社の基本的な方向性を決定する場であり、取締役会はその方向性に基づいて日常的な業務執行を決定する場です。M&Aにおいても、事業譲渡や合併といった重要事項は株主総会での承認が必要となりますが、具体的な交渉や条件調整は取締役会レベルで進められることが一般的です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株主総会の種類
株主総会には大きく分けて「定時株主総会」と「臨時株主総会」があります。それぞれ開催目的や開催時期が異なるため、経営者として両者の違いを正確に理解しておく必要があります。
定時株主総会の特徴と開催時期
定時株主総会とは、会社法第296条第1項に基づき、毎事業年度の終了後に必ず開催しなければならない株主総会です。決算承認や剰余金の処分、取締役や監査役の選任など、会社の年度運営に関する重要事項を決議します。
株主総会の開催時期については、原則として決算期末から3ヶ月以内に開催することが求められます。例えば、3月決算の会社であれば、6月末までに定時株主総会を開催する必要があります。これは会社法第296条第1項において、定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと定められており、実務上は決算日から3ヶ月以内とされているためです。
なお、法人税法第74条では確定申告書の提出期限が決算日から2ヶ月以内とされていますが、株主総会での決算承認を得てから申告する必要があるため、多くの会社は決算日から2ヶ月以内に株主総会を開催しています。ただし、一定の事由がある場合は税務申告期限を1ヶ月延長することができ、その場合は株主総会の開催も決算日から3ヶ月以内の範囲で後ろ倒しにすることが可能です。
臨時株主総会が開催される場面
臨時株主総会は、会社法第296条第2項に基づき、必要が生じたときに随時開催される株主総会です。定時株主総会で扱う事項以外で、株主の決議が必要となる重要事項が発生した場合に招集されます。
臨時株主総会が開催される典型的な場面としては、以下のようなケースがあります。まず、取締役や監査役が任期途中で辞任した場合の後任選任です。次に、M&Aにおける事業譲渡や会社分割、合併などの組織再編を実施する場合です。さらに、重要な事業計画の変更や大規模な資金調達を行う場合なども該当します。
M&Aを検討している経営者にとって、臨時株主総会はスキームによっては特に重要です。事業譲渡や合併などを実行する際には、株主の承認を得るために臨時株主総会を開催し、特別決議による承認を得る必要があるためです。
ただし、株式譲渡による会社売却の場合、原則として売り手側の株主総会決議は不要です(親会社が子会社株式の過半数以上を売却する場合など、例外的に必要となるケースもあります)。臨時株主総会の招集手続きや決議要件を事前に理解しておくことで、該当するM&Aスキームにおいてプロセスをスムーズに進めることができます。
株主総会の開催場所に関する規定
株主総会の開催場所については、会社法第298条第1号により、招集ごとに自由に設定することができます。本店所在地である必要はなく、支店や会議室、ホテルの会場などを選ぶことも可能です。
ただし、著しく不当な場所での開催は、会社法第831条第1項1号に基づき、株主総会決議の取消事由となる可能性があります。たとえば、株主の参加が著しく困難となるような場所は不当と判断される恐れがあります。
開催場所を大幅に変更する場合には、会社法施行規則第63条に基づき、変更理由を株主に開示することが求められます。中小企業においては、株主が限られているため開催場所の選定が問題となることは少ないですが、M&Aによって新たな株主が加わる場合や、将来的な株主構成の変化を見据えて、適切な開催場所を選定する意識を持つことが重要です。
バーチャル株主総会の実務
近年、デジタル技術の発展と新型コロナウイルス感染症の影響により、バーチャル株主総会が急速に普及しています。従来の対面開催だけでなく、オンラインを活用した株主総会の選択肢が広がっています。
株主総会の開催形式の種類
現在、株主総会の開催形式は大きく3つに分類されます。第一に、従来型の「リアル開催」です。これは物理的な会場に株主が集まって開催する形式で、最も伝統的な方法です。
第二に、「ハイブリッド型株主総会」があります。これは会場での開催とオンライン参加を併用する形式で、さらに「参加型」と「出席型」に細分化されます。第三に、「バーチャルオンリー株主総会」があります。これは完全にオンラインのみで開催する形式です。
ハイブリッド型株主総会における参加型と出席型の違い
ハイブリッド型株主総会の「参加型」と「出席型」は、オンライン参加株主の権利の範囲が大きく異なります。参加型は、オンライン参加者が株主総会の様子を視聴できるものの、議決権の行使や質問を行うことはできません。あくまで情報提供を目的とした形式です。
一方、出席型では、オンライン参加者も会場参加者と同等に議決権を行使でき、質問も可能です。出席型の場合、オンライン参加者も正式な出席株主としてカウントされるため、より実質的な参加が保証されます。
| 区分 | 参加型 | 出席型 |
|---|---|---|
| 議決権行使 | 不可 | 可能 |
| 質問権 | 不可 | 可能 |
| 出席株主としてのカウント | されない | される |
| 主な目的 | 情報提供重視 | 意見反映重視 |
中小企業がハイブリッド型を採用する場合、株主構成や経営方針に応じて、参加型と出席型のどちらを選択するか検討する必要があります。M&Aによって投資ファンドなどが株主となった場合、出席型のニーズが高まる可能性があります。
バーチャルオンリー株主総会の制度と実施状況
バーチャルオンリー株主総会は、2021年6月より実現可能となった、オンラインのみで開催する株主総会です。ただし、現時点では産業競争力強化法に基づく会社法の特例制度として位置づけられており、経済産業省と法務省の確認を受けた上場企業のみが実施できます。
2025年6月末時点のデータによると、バーチャルオンリー株主総会を開催した企業は累計74社、開催回数は185回に上ります。導入企業は年々増加傾向にあり、今後さらなる普及が見込まれています。
現状では中小企業が完全バーチャル形式で株主総会を開催することは制度上困難ですが、将来的に規制緩和が進む可能性もあります。M&A後の新体制において、地理的に分散した株主が存在する場合などには、バーチャル開催のニーズが高まることが予想されます。
参考1:場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度
バーチャル株主総会のメリットとデメリット
バーチャル株主総会には、株主側と会社側それぞれにメリットとデメリットがあります。株主側のメリットとしては、遠隔地からでも参加可能になることや、移動コストや時間が不要になることが挙げられます。特に地方在住の株主や海外株主にとっては、大きな利便性向上となります。
一方、デメリットとしては、インターネット操作に不慣れな株主にとってはハードルが高いことや、対面での交流機会がなくなることが指摘されています。会社側のメリットは、会場費や人件費などのコスト削減が可能なこと、感染症対策が不要になること、先進的な企業イメージを醸成できることなどです。
会社側のデメリットとしては、システム導入や保守にかかる費用、通信トラブルや情報漏洩のリスク、株主との直接対話の機会が減少することなどがあります。中小企業がバーチャル株主総会の導入を検討する際には、これらのメリット・デメリットを総合的に判断し、自社の状況に最適な開催形式を選択することが重要です。
株主総会の決議事項
株主総会で決議すべき事項は、会社法や定款によって定められています。決議事項の内容によって、必要な決議要件も異なるため、経営者として正確に理解しておく必要があります。
株主総会の主要な決議事項
株主総会の決議事項は、大きく以下のカテゴリーに分類されます。
- 経営上の基本事項(定款変更、合併、事業譲渡、減資、解散など)
- 役員関係(取締役・監査役の選解任、報酬決定)
- 株主利害関係(配当、自己株式取得、株式併合など)
- 計算関係(計算書類承認、剰余金処分)
- その他法令に基づく特定決議
まず、経営上の基本事項として、定款変更、合併、事業譲渡、減資、会社解散などがあります。これらはいずれも会社の存続や事業の根幹に関わる重要事項です。
次に、役員関係として、取締役や監査役の選任・解任、役員報酬の決定などがあります。役員は会社経営の中核を担う存在であり、その選任は株主の重要な権利です。株主利害関係では、剰余金の配当、自己株式の取得、株式併合などが決議されます。これらは株主の経済的利益に直接影響する事項です。
計算関係では、計算書類の承認や剰余金の処分が含まれます。定時株主総会での主要議題となる事項です。その他、保険業法など他の法令に基づいて特定の決議が求められる場合もあります。
M&Aを検討している経営者にとって特に重要なのが、経営上の基本事項に含まれる事業譲渡や合併です。これらは後述する特別決議が必要となる事項であり、慎重な準備と手続きが求められます。
決議方法の種類と要件
株主総会の決議は、決議事項の重要度に応じて「普通決議」「特別決議」「特殊決議」の3種類に分類され、それぞれ異なる定足数と可決要件が設定されています。
普通決議は、会社法第309条第1項に規定される最も基本的な決議方法です。取締役の選任・解任、監査役の選任、役員報酬の決定などが該当します。定足数は議決権の過半数の出席が必要で、可決要件は出席株主の議決権の過半数の賛成です。
特別決議は、会社法第309条第2項に規定される、より重要な事項について求められる決議です。定款変更、事業譲渡、合併、会社分割、減資などが該当します。定足数は議決権の過半数の出席が必要ですが、定款で3分の1まで引き下げることが可能です。可決要件は出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
特殊決議は、会社法第309条第3項・第4項に規定される、株主の権利に重大な影響を与える事項について求められる最も厳格な決議です。株主ごとに異なる取扱いを定める定款変更などが該当します。定足数は総株主の半数以上の出席が必要で、可決要件は内容により3分の2以上または4分の3以上の賛成が求められます。
普通決議・特別決議・特殊決議の定足数と賛成数
株主総会の普通決議・特別決議・特殊決議の定足数と可決に必要な賛成数は以下の通りです。
| 決議種別 | 主な該当事項 | 定足数 | 可決要件 |
|---|---|---|---|
| 普通決議 | 役員選解任、役員報酬決定など | 議決権の過半数出席 | 出席株主の過半数賛成 |
| 特別決議 | 定款変更、合併、事業譲渡、減資など | 議決権の過半数出席(定款で3分の1まで緩和可) | 出席株主の3分の2以上賛成 |
| 特殊決議 (会社法309条3項) | 譲渡制限株式への変更を伴う定款変更など | 議決権を行使できる株主の半数以上出席 | 出席株主の3分の2以上賛成 |
| 特殊決議 (会社法309条4項) | 株主ごとに異なる取扱いを定める定款変更(非公開会社) | 総株主の半数以上出席 | 出席株主の4分の3以上賛成 |
M&Aにおける事業譲渡や合併は特別決議事項であるため、出席株主の3分の2以上の賛成が必要です。これは単純な多数決ではなく、反対株主が3分の1を超えると否決されることを意味します。売却を検討する際には、事前に主要株主の意向を確認し、賛成を得られる見込みを立てておくことが極めて重要です。
議決権行使の特殊な方法
株主総会における議決権行使には、通常の出席による行使以外にも、いくつかの特殊な方法が認められています。まず、議決権の不統一行使があります。これは会社法第313条第3項に基づき、同一株主が保有する株式について、一部を賛成、一部を反対とする行使方法です。
たとえば、信託銀行などが複数の受益者のために株式を保有している場合、受益者ごとに意見が異なることがあります。このような場合に、株式を分割して異なる議決権を行使できる制度です。ただし、会社は一定の条件下で不統一行使を拒否することも可能です。
また、書面やインターネットによる議決権行使も可能です。株主総会に出席できない株主は、事前に議決権行使書を提出したり、インターネット上で議決権を行使したりすることができます。M&A実行時の臨時株主総会など、重要な決議が予定されている場合には、これらの方法を活用して全株主の意思を確実に反映させることが重要です。
株主総会は省略できる?書面決議と決議の省略
会社法第319条により、全株主の同意があれば、株主総会を実際に開催せずに書面または電磁的方法によって決議を行うことができます。これを書面決議または決議の省略といいます。普通決議だけでなく、特別決議や特殊決議についても書面決議が可能です。
書面決議を行う場合でも、会社法施行規則第72条第4項に基づき、議事録を作成して保存する義務があります。議事録には、決議の内容、決議があったものとみなされた日、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名などを記載する必要があります。
また、会社法第320条により、株主全員が株主総会への報告事項について報告を要しないことに同意した場合、報告を省略することも可能です。中小企業で株主が少数の場合、書面決議の制度を活用することで、株主総会開催の手間やコストを削減できます。ただし、全株主の同意が前提となるため、株主間で意見が対立している場合には利用できません。
株主総会開催の流れと進め方
株主総会を適切に運営するためには、法定の手続きを遵守しつつ、実務上のポイントを押さえる必要があります。特にM&Aを検討している企業では、手続き上の瑕疵が後々のトラブルにつながる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
以下では株主総会の流れとポイントを解説します。
開催日と招集通知期間
定時株主総会は、決算期末から3ヶ月以内に開催することが原則です。実務的には、決算確定後に監査役による監査、取締役会での計算書類の承認、株主への招集通知の発送などのプロセスがあるため、逆算してスケジュールを組む必要があります。
招集通知は、株主総会の日の2週間前までに発送しなければなりません。ただし、取締役会非設置会社で、株主全員の同意がある場合には、短縮や省略も可能です。招集通知には、株主総会の日時・場所、目的事項、議案の内容などを記載する必要があります。
臨時株主総会の招集通知期間は、公開会社では2週間前まで、非公開会社では原則1週間前までです。ただし、非公開会社でも書面または電磁的方法による議決権行使を可能とする場合は2週間前までの通知が必要です。
緊急性の高い案件で期間を短縮する場合、非公開会社かつ取締役会非設置会社に限り、定款で定めることにより株主総会の招集通知期間を1週間より短い期間にすることができます。招集手続きの瑕疵は決議取消事由となる可能性があるため、余裕を持った計画が重要です。
開催場所選定における実務上の配慮
株主総会の開催場所は自由に設定できますが、株主の参加を妨げるような不当な場所は避けなければなりません。実務上は、以下のような配慮が望ましいとされています。まず、交通アクセスが良好で、株主が参加しやすい場所を選定することです。
次に、収容人数が十分で、株主が快適に参加できる環境を確保することです。さらに、従来の開催場所から大幅に変更する場合には、変更理由を明確に説明することです。中小企業では株主が限られているため、本社会議室などで開催するケースも多いですが、株主構成の変化に応じて適切な場所を選ぶ必要があります。
M&A後に新たな投資家が株主となる場合、これまで以上に開催場所の選定に配慮が必要となる可能性があります。特に遠隔地の株主が増える場合には、ハイブリッド型株主総会の導入も検討すべきです。
採決方法と議事進行のポイント
株主総会における採決方法は、議長の裁量によって柔軟に決定することができます。全員賛成が明らかな場合には、拍手や挙手による簡易な採決で済ませることも可能です。一方、意見が分かれる可能性がある重要議案では、投票用紙による記名投票や無記名投票を実施することもあります。
議事進行においては、株主の質問権を適切に保障しつつ、会議を円滑に進めることが求められます。株主は株主総会において、議題について説明を求める権利を有しています。
M&Aに関する議案では、株主から詳細な質問が出ることが予想されます。事前に想定問答を準備し、取締役や監査役が適切に回答できる体制を整えておくことが重要です。また、秘密保持契約により開示できない情報がある場合には、その旨を丁寧に説明する必要があります。
議事録作成と保存義務
株主総会終了後は、速やかに議事録を作成し、本店に備え置く義務があります。議事録には、株主総会の日時・場所、議事の経過の要領およびその結果、出席した取締役・監査役の氏名などを記載します。議事録には議長および出席取締役が署名または記名押印する必要があります。
議事録は10年間保存しなければならず、株主や会社債権者は閲覧や謄写を請求することができます。書面決議の場合でも、前述のとおり議事録の作成義務があります。議事録の記載内容に不備があると、後日、決議の効力が争われる可能性もあるため、正確かつ詳細な記録を心がけるべきです。
M&A実行時の株主総会議事録は、買い手側によるデューデリジェンスの対象となることもあります。適切に作成・保存された議事録は、会社のガバナンス体制が整っていることの証明にもなり、M&Aの成功にも寄与します。
まとめ
株主総会は株式会社における最高意思決定機関であり、経営の重要事項を決定する場として法律上も実務上も極めて重要な位置を占めています。定時株主総会と臨時株主総会の違い、普通決議・特別決議・特殊決議といった決議方法の種類と要件を正確に理解することが、適切な会社運営の基礎となります。
近年はバーチャル株主総会の選択肢も広がっており、株主の利便性向上やコスト削減の観点から導入を検討する企業も増えています。中小企業の経営者がM&Aを検討する際には、事業譲渡や合併には特別決議が必要であること、全株主の意向確認が不可欠であることを念頭に置き、早期から準備を進めることが成功の鍵となります。
株主総会の適切な運営は、企業価値の向上やステークホルダーからの信頼獲得につながります。M&Aを検討されている場合、株主総会のプロセスを含む会社の意思決定体制を整備することで、円滑な事業承継や企業売却を実現できます。M&A実行においては、法的手続きの遵守はもちろん、株主との丁寧なコミュニケーションが何よりも重要です。
M&Aや経営課題についてのご相談は、M&Aロイヤルアドバイザリーにお任せください。経験豊富なアドバイザーが、貴社の状況を丁寧にお伺いし、最適な方向性をご提示いたします。まずはお気軽にご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。