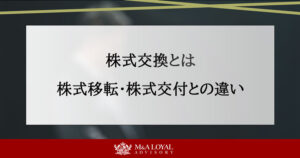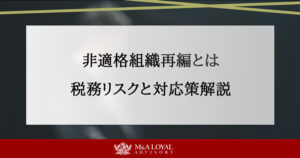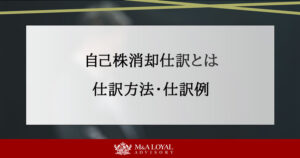株式交換の仕訳と会計処理|親会社・子会社別にわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
株式交換の仕訳は、企業の財務状況を正確に反映し、取引の透明性を確保するための重要なプロセスです。この記事では、株式交換の仕訳や会計処理、税務について、親会社と子会社、そして株主別にわかりやすく説明します。
株式交換には複雑な会計処理が伴いますが、基本的な流れを理解することで、企業の財務状況をよりクリアに把握することができます。この記事を通じて、株式交換の仕訳に対する理解を深め、不安を解消していきましょう。
目次
株式交換の仕訳とは
株式交換の仕訳は親会社と子会社で異なり、それぞれが適切な仕訳処理を行う必要があります。仕訳の前に株式交換の基本について理解しましょう。
株式交換とは
株式交換とは、企業が他の企業の株式を自社の株式と交換して買収する方法で、企業が統合したり、組織を再編成したりする際に使われるM&A手法の一つです。株式交換によって、売り手企業は買い手企業の完全子会社となり、子会社となった企業の株主は買い手企業の株主となります。
例えば、売り手A社と買い手B社の間で株式交換が行われた場合、A社の株主はB社にA社の株式を渡し、B社の株式を受け取ります。なお、株式交換の対価は株式が一般的であるものの、現金や社債等も可能となっています。
完全親会社と完全子会社とは
株式交換では、売り手と買い手は完全親子関係が成立します。他社の全株式を所有し、その経営を支配する側を「完全親会社」、支配される側を「完全子会社」と呼びます。この場合、親会社が子会社の経営方針に対して指導力を持ち、決定権を持つことが特徴です。
親会社は子会社の業績や戦略を統合的に管理し、企業グループ全体の利益の最大化を図ります。一方、子会社となった売り手企業は親会社の戦略や意思決定に基づくため、独立した経営が行われにくくなりますが、親会社から資源やノウハウの提供を受けることで、事業の効率的な成長が期待されます。
株式交換のメリット・デメリット
株式交換のメリットは、対価が自社株式のため、現金を用意せずに企業を買収できる点が挙げられます。これにより、買い手企業は資金繰りに影響を与えずに組織拡大を図ることが可能です。また、株式交換は税務上のメリットもあります。株式交換が適格組織再編に該当する場合、一定の条件下で課税を繰り延べることができ、これにより企業のキャッシュフローを安定させることができます。
一方、デメリットも存在します。株式交換を行うと、発行済み株式数が増加するため、既存株主の持ち株比率が希薄化する可能性があります。これにより、株主の投票権や利益配分が変動するリスクがあります。また、株式交換後の企業価値が適切に評価されない場合、株価が下落するリスクも考慮しなければなりません。
株式交換を実行する際には、このようなメリット・デメリットを理解した上で、総合的に検討することが大切です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式交換の仕訳のルール
株式交換の仕訳にはルールがあり、会計上と税務上で区分が異なります。ここでは株式交換の仕訳のルールと区分について解説します。
会計処理上の株式交換の区分
会計上の処理では、株式交換は以下の4つに区分されます。
- 取得
- 持ち分の結合
- 共同支配企業の形成
- 共通支配下の取引
それぞれについて解説します。
取得による株式交換
取得とは、事業規模や議決権の割合などにより、どちらが株式を取得したかが明確になっている場合の取引です。取得と判断された場合、会計処理には、通常「パーチェス法」が適用されます。パーチェス法では、親会社は子会社の資産や負債を引き継ぎ、時価で財務諸表に計上します。なお、取得価額と時価に差が生じる場合はのれんが発生します。
持ち分の結合
持ち分の結合とは、買い手と売り手の株式の総額がほぼ同額であり、事業規模や議決権の割合でどちらが取得したかが判断できない場合に該当します。この場合、「持分プーリング法」という会計処理方法が適用されていましたが、2008年の企業結合会計基準の改正により持分プーリング法は廃止され、パーチェス法に一本化されています。
共同支配企業の形成
共同支配企業の形成とは、複数の企業が共同で企業の1つの会社を支配する取引です。これには以下の条件を満たす必要があります。
- 出資側となる企業がすべて独立している
- 議決権を持つ株式が対価である
- 出資企業同士で経営を共同支配する契約が結ばれている
この場合、子会社の資産や負債は簿価で評価し、財務諸表に反映します。そのため、のれんは発生しません。
共通支配下の取引
共通支配下の取引とは、同一グループ内での株式交換を指します。この場合も、共同支配企業の形成と同じく簿価で会計処理するため、のれんは発生しません。また、この場合の取引は内部取引として扱われるため、連結時には消去します。
このように、株式交換の仕訳は会計上の区分によって異なるため注意が必要です。
税務処理上の株式交換の区分
税務上のルールでは、株式交換は「適格株式交換」と「非適格株式交換」に区分されます。
適格株式交換
適格株式交換とは、法人税上の適格要件を満たした場合に認められ、税制上の優遇措置が適用されます。適格株式交換では、資産は簿価で処理され、譲渡益に対する課税も発生しません。また、繰越欠損金がある場合、利益と相殺することができます。これにより、売り手は税負担を軽減し、企業の財務負担を抑えることが可能です。
非適格株式交換
適格要件を満たさない株式交換を非適格株式交換と呼びます。この場合は税制上の優遇措置が適用されず、資産は時価で計上され、譲渡益は課税対象になります。また、繰越欠損金と利益を相殺することもできません。さらに親会社、子会社、株主の立場によっても税務処理が異なる点に留意しましょう。
適格株式交換の要件
株式交換の適格要件は支配関係によって異なります。
完全支配関係にある企業間の株式交換の場合
| 要件 | 概要 |
| 金銭等不交付要件 | 株式交換の対価として、「完全親会社の株式」または「完全親会社の完全親会社の株式」のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと |
| 継続保有要件 | 株式交換前に完全支配関係があり、株式交換後も継続が見込まれること |
支配関係にある企業間の株式交換の場合
| 要件 | 概要 |
| 金銭等不交付要件 | 株式交換の対価として、「完全親会社の株式」または「完全親会社の完全親会社の株式」のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと |
| 継続保有要件 | 株式交換前に支配関係があり、株式交換後も継続が見込まれること |
| 事業移転要件 | 完全子会社の従業員の概ね80%以上が株式交換後も引き続き従事することが見込まれること |
| 事業継続要件 | 完全子会社の主要事業が株式交換後も引き続き行われることが見込まれること |
支配関係にない企業間の株式交換の場合
| 要件 | 概要 |
| 金銭等不交付要件 | 株式交換の対価として、「完全親会社の株式」または「完全親会社の完全親会社の株式」のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと |
| 継続保有要件 | 完全子会社の支配株主に交付される完全親会社の株式がすべて継続的に保有されることが見込まれること |
| 継続支配要件 | 完全支配関係の継続が見込まれること |
| 事業関連性要件 | 完全親会社の事業と完全子会社の主要事業に関連性があること |
| 同等規模要件(双方経営参画要件とどちらか一方) | 完全親会社と完全子会社の関連事業の売上高または従業員数の差が概ね5倍を超えないこと |
| 双方経営参画要件(同等規模要件とどちらか一方) | 完全子会社の特定役員が株式交換に伴い退任しないこと |
適格株式交換を選択することで、優遇措置が適用され、キャッシュアウトを抑えながら組織再編を進めることができますが、すべての株式交換が適格と認められるわけではありません。そのため、適格か非適格かを見極め、適切な処理が必要となります。
株式交換の仕訳・会計処理
株式交換の仕訳を親会社と子会社、それぞれの株主の場合で解説します。
親会社の株式交換の仕訳
親会社の株式交換の仕訳を見ていきましょう。株式交換では、親会社が子会社の株式を取得する対価として自社の株式を発行します。そのため、新たに発行する株式の評価額を計上します。
この際、親会社の貸借対照表においては「子会社株式」という勘定科目が増加し、同時に「資本金」や「資本準備金」といった純資産の項目が変動します。なお、自己株式を対価にする場合は、差額を「その他資本剰余金」で処理します。
| 親会社の仕訳の勘定科目 ・子会社株式 ・資本金 ・資本準備金 ・自己株式 ・その他資本剰余金 |
親会社の仕訳例1:新株発行の場合
株式交換の対価新株を発行した場合の仕訳例を解説します。買い手A社の株価が300円、売り手B社の株価が100円、交換比率2:1でB社の発行済株式が10万株とします。2分の1が資本金、残りを資本準備金として仕訳処理します。
- B社取得のためのA社発行株式=10万株×1/2=5万株
- B社取得に支払う対価(時価)=5万株×300円=1,500万円
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| 子会社株式 | 1,500万円 | 資本金 | 750万円 |
| 資本準備金 | 750万円 |
親会社の仕訳例2:自己株式を交付する場合
自己株式を対価にした株式交換の仕訳例を解説します。仕訳例1と同じく、買い手A社の株価が300円、売り手B社の株価が100円、交換比率2:1でB社の発行済株式が10万株とします。この場合、A社に支払う対価は1,500万円で変わりませんが勘定科目が異なります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| 子会社株式 | 1,500万円 | 自己株式 | 1,500万円 |
ただし、上記の仕訳はA社が交付した株式の時価とB社が保有しているA社の自己株式の簿価が同額の場合の処理です。発行株式の時価と自己株式の簿価が異なる場合は差額を「その他資本剰余金」で処理します。A社株式が時価300円、簿価200円の場合は以下の仕訳になります。
- A社自己株式(簿価)=5万株×200円=1,000万円
- A社交付株式(時価)=5万株×300円=1,500万円
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| 子会社株式 | 1,500万円 | 自己株式 | 1,000万円 |
| その他資本剰余金 | 500万円 |
子会社の株式交換の仕訳
子会社は株式交換での仕訳は原則不要です。これは株式交換では、株主が変動するのみで子会社の資産や負債に変動がないためです。ただし、例外的に仕訳が発生することもあります。
| 子会社の仕訳の勘定科目 ・自己株式 ・新株予約権 ・その他資本剰余金 ・免除益 ・譲渡益 ・評価損益 |
子会社の仕訳例1:自己株式を処分する場合
株式交換で子会社に仕訳が発生するケースの1つが自己株式の処分です。子会社が株式交換を行う前から親会社の株式を所有していた場合、株式交換においてこの株式を処分する必要があります。売り手B社が買い手A社の株式(簿価300万円、時価500万円)を保有していた場合の仕訳は以下のとおりです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| A社株式 | 500万円 | 自己株式 | 300万円 |
| その他資本剰余金 | 200万円 |
子会社の仕訳例2:新株予約権が消滅する場合
子会社が株式交換以前に新株予約権を発行していた場合、その予約権は消滅するため減額処理が必要です。減額した金額は「免除益」で計上し、差額を「譲渡益」で処理します。新株予約権が簿価300万円、時価500万円だった場合の仕訳は以下のとおりです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| 新株予約権 | 300万円 | 免除益 | 500万円 |
| 譲渡益 | 200万円 |
子会社の仕訳例3:非適格株式交換の場合
非適格株式交換では、有価証券や固定資産、金融債権を時価で評価するため、簿価との差額が生じることがあります。その場合は、差額を「評価損益」で処理する必要があります。
下記の場合の仕訳を見ていきましょう。
| ・有価証券 簿価300万円/時価500万円 ・固定資産 簿価800万円/時価1,100万円 ・金融債権 簿価150万円/時価200万円 |
この場合の仕訳は以下のとおりです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| 有価証券 | 300万円 | 評価損益 | 550万円 |
| 固定資産 | 200万円 | ||
| 金融債権 | 50万円 |
株主の株式交換の仕訳
親会社と子会社の株主にはどのような仕訳が必要なのかについても解説します。
親会社の株主の仕訳
親会社の株主は株式交換による仕訳は不要です。ただし、親会社が新株を発行することで持株比率が下がり、株価に影響を受ける可能性があります。
子会社の株主の仕訳処理
子会社の株主は親会社の株式を受け取るため、仕訳が必要です。適格株式交換か非適格株式交換かで仕訳の仕方は異なります。
適格株式交換の場合
適格株式交換では、親会社と子会社の株式を簿価で交換した扱いになります。損益は生じないため、税金は発生しません。例えば、買い手A社の株式と売り手B社が株式(簿価1,000万円)を交換した場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| A社株式 | 1,000万円 | B社株式 | 1,000万円 |
非適格株式交換の場合
非適格株式交換の場合、対価が親会社の株式かそれ以外も含まれるかによって仕訳が異なります。例えば、株主Xが売り手B社の株式を簿価500万円(時価800万円)保有しており、A社が対価をすべてA社株式で支払った場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| A社株式 | 800万円 | B社株式 | 500万円 |
| その他資本剰余金 | 300万円 |
現金など株式以外の対価が含まれる場合は、譲渡したものとみなされます。例えば、A社が株主XのB社株式500万円(簿価)を現金と株式合わせて800万円(時価)で取得した場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| 現金 | 800万円 | B社株式 | 500万円 |
| 譲渡益 | 300万円 |
株式交換の税務処理
株式交換の税務処理についても、親会社と子会社、それぞれの株主の場合で見ていきましょう。税務処理では適格か非適格かが課税のポイントとなります。
適格と非適格での課税の有無
| 適格株式交換 | 非適格株式交換 | |
| 親会社 | なし | なし |
| 子会社 | なし | あり |
| 親会社の株主 | なし | なし |
| 子会社の株主 | なし | あり |
親会社の税務処理
株式交換では適格株式交換か非適格株式交換かに関わらず、親会社に税金は発生しません。ただし、取得額の計算方法は適格か非適格かで異なり、適格要件に該当する場合でも株主の数によって計算式が変わります。
適格株式交換の場合
| 子会社の株主が50人未満の場合 取得価額=株式交換直前の子会社株式の帳簿額+取得費用 子会社の株主が50人以上の場合 取得価額=子会社の簿価純資産額+取得費用 |
非適格株式交換の場合
| 取得価額=子会社株式の時価 |
子会社の税務処理
株式交換における子会社の税務処理も適格株式交換か非適格株式交換かで異なります。
適格株式交換の場合
税務処理不要
非適格株式交換の場合
時価の評価額と株式交換直前の帳簿価額の差額に税金が発生
株主の税務処理
株式交換時の親会社と子会社の株主の税務処理についても触れていきます。
親会社の株主の税務処理
親会社の株主は株式交換で税金は発生しません。
子会社の株主の税務処理
子会社の株主は適格株式交換か非適格株式交換かで異なります。
適格株式交換の場合
子会社の株主は親会社に株式を譲渡した扱いになります。帳簿価格を譲渡価格とし、譲渡損益は繰り延べられます。
非適格株式交換の場合
対価が親会社の株式のみの場合は適格株式交換と同様に簿価で扱われ、譲渡損益は繰り延べられます。対価に金銭を含む場合は時価とし、差額を譲渡損益とし、課税対象となります。
株式交換の仕訳の注意点とポイント
株式交換の仕訳を行う際には、企業間の資本構成を大きく変える可能性があるため、慎重な会計処理と税務処理が求められます。以下に、株式交換の仕訳に関する注意点まとめます。
- 適格か非適格かの確認
- 自己株式の処理
- 会計と税務の違い
- のれんの扱い
それぞれについて解説します。
適格か非適格かの確認
適格株式交換と非適格株式交換では、会計および税務上の処理が異なります。適格株式交換の場合、税務上は譲渡益課税が繰り延べられますが、非適格株式交換の場合、株式交換時点で譲渡益課税が発生します。また、会計処理上も、取得原価の算定方法や負債の認識について違いが生じる場合があります。
そのため、取引が適格か非適格かを適切に分類し、関連する税務上および会計上の影響を正しく把握することが重要です。
自己株式の処理
自己株式は会計上、純資産の控除項目として扱われ、資本を減少させる要素となります。そのため、自己株式の取得や処分に際しては、企業の財務状態に与える影響を十分に考慮する必要があります。
自己株式を取得した場合、その対価は純資産を減少させるため、仕訳としては「自己株式」を借方に計上し、現金やその他の支払い手段を貸方に記録します。一方で、自己株式を処分する場合、処分価額が取得原価を上回る場合には資本剰余金を増加させる一方で、下回る場合には資本剰余金を減少させる処理が必要です。
会計と税務のルールの違い
株式交換に伴う会計上のルールと税務上のルールは、目的や基準が異なるため、処理方法に差異が生じる場合があります。例えば、会計上は企業結合基準に基づいてのれんや公正価値を考慮する一方、税務上は譲渡損益の繰延や特定の非課税要件の適用が認められる場合があります。
このため、会計基準に基づく仕訳と、税務申告上の調整を正確に区別して行うことが求められます。特に、税務上の特例(例えば、適格株式交換制度の適用)を利用する場合には、税務調整が必要となることがあります。
のれんの扱い
のれんとは、企業が他の企業を買収する際に支払われる対価のうち、取得した資産や負債の公正価値を超える額を指します。この超過額は、企業のブランド価値や顧客基盤、技術力など、目に見えない無形資産に対する評価として計上されます。
のれんの処理方法は、個別財務諸表と連結財務諸表で異なります。株式交換を通じて企業が他社を取得する際、個別財務諸表ではのれんは計上されません。連結財務諸表を作成する際には、親会社が支払った対価と子会社の純資産額との差額として「のれん」を計上する必要があります。
株式交換の仕訳を正しく行うためには、これらのポイントを押さえる必要があります。これにより、株式交換に伴うリスクを最小限に抑え、財務の健全性を維持しながら、企業の成長を支援する体制を構築することができます。
株式交換の仕訳まとめ
株式交換における仕訳は、企業の財務状況を正確に反映し、税務上適切な処理を行うために非常に大切です。
この記事では、株式交換の基本から実際の会計処理や税務に至るまでをまとめ、さまざまな視点から解説しました。特に、適格株式交換と非適格株式交換の違いや、のれんの処理方法についての理解は、正しい仕訳を行うための基礎となります。
企業の財務戦略を強化し、適切な会計処理を行うためには、これらの知識が不可欠です。
株式交換の基本概念や仕訳のルール、そして適格、非適格の違いについて学びました。特に、仕訳が会計と税務にどのように影響するかを知ることで、誤った処理を避け、企業の財務報告を正確にすることができます。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。