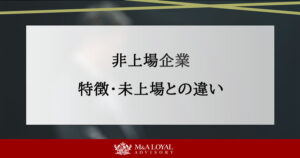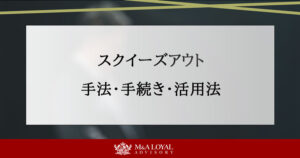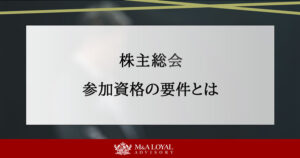株式買取請求権とは?行使の手続きや期限をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
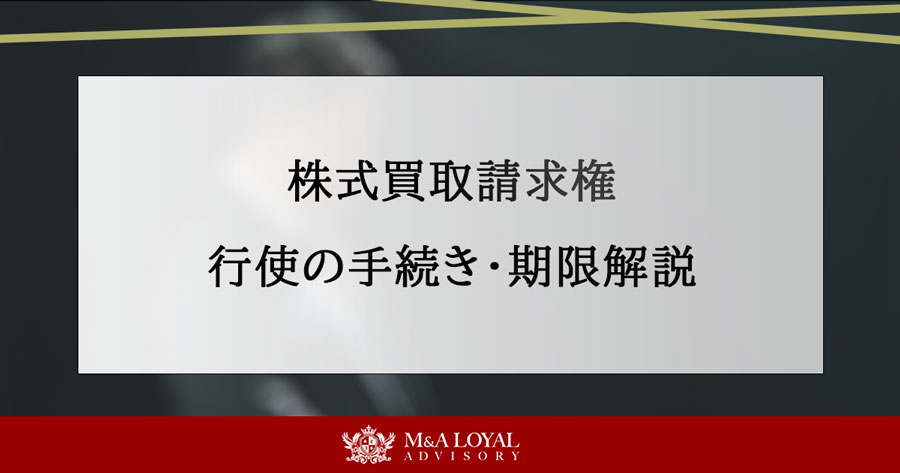
株式買取請求権とは、株主が会社に対して自己の保有する株式を「公正な価格」で買い取るよう請求できる権利です。この制度は、会社の合併や事業譲渡などの重要な決議に反対する少数株主を保護する措置として機能しています。近年のM&A増加に伴い、この権利に注目が集まっていますが、行使方法や手続きの流れ、価格決定の仕組みなど、知っておくべき点は多岐にわたります。
本記事では、株式買取請求権の基本から実務上の注意点まで、オーナー経営者や株主の方々にとって必要な知識をわかりやすく解説します。
目次
株式買取請求権の基本と種類
株式買取請求権は、会社法に基づく株主保護のための重要な制度です。この権利の本質を理解することで、企業経営者も株主も、重要な局面で適切に対応できます。まずは基本的な概念と制度の目的から見ていきましょう。
株式買取請求権とは
株式買取請求権は、株主が一定の条件下で自己の保有する株式を会社に買い取るよう請求できる法的権利です。この制度は、会社の重要な意思決定に反対する少数株主を保護するために設けられています。少数株主の意向に反して進められる会社の大きな変更に対して、株主が経済的な救済を受けられる出口戦略として機能しています。
会社法では、株主と会社との間の利害関係のバランスを図りながら、会社の機動的な経営判断と株主の財産権保護の両立を目指しています。株式買取請求権はその中核的な制度の一つと言えるでしょう。
法的根拠と制度の趣旨
株式買取請求権の法的根拠は会社法に定められています。端数株主の買取請求については会社法第192条、反対株主の買取請求については第116条、第469条、第785条などの条文で規定されています。
この制度の主な趣旨は、多数決原理で決定される会社の重要事項に反対する少数株主に対して、「公正な価格」で投資回収の機会を与えることにあります。特に非上場会社の株主にとっては、市場で株式を売却する選択肢がないため、この権利は非常に重要な意味を持ちます。
株式買取請求権の2つの種類
株式買取請求権には大きく分けて2つの種類があります。それぞれの特徴と適用場面を押さえておくことが重要です。
- 端数株主の買取請求権:単元未満株式を保有する株主が行使できる権利
- 反対株主の買取請求権:会社の重要な意思決定に反対する株主が行使できる権利
この2つは行使場面や要件が大きく異なります。特に中小企業のオーナーや株主にとって重要となるのは「反対株主の買取請求権」であることが多いため、本記事ではこちらに重点を置いて解説します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式買取請求権が行使できる場面
株式買取請求権は、あらゆる状況で行使できるわけではありません。特定の会社の意思決定や状況において、法律で定められた場合にのみ行使可能となります。ここでは、具体的にどのような場面で株式買取請求権が認められるのかを詳しく見ていきましょう。
会社の組織再編時
会社の組織再編は、株式買取請求権が行使される場面の一つです。合併や会社分割など、会社の基本的な構造が変わる決議がなされた際、その決議に反対する株主は買取請求権を行使できます。これは会社の根本的な変更に伴うリスクから株主を保護する手段となっているためです。具体的には以下のような場合が該当します。
- 合併(吸収合併・新設合併)
- 会社分割(吸収分割・新設分割)
- 株式交換・株式移転
- 株式交付
これらの組織再編行為は、会社の基本的な構造や事業内容に大きな変更をもたらすため、株主にとって投資判断の前提が変わることになります。そのため、反対株主に対して株式の買取を請求する権利が法的に定められています。
重要な事業の譲渡・譲受時
会社の事業の全部または重要な一部の譲渡・譲受も、株式買取請求権が認められる場面です。具体的には以下のような場合が含まれます。
- 事業の全部の譲渡
- 事業の重要な一部の譲渡
- 他の会社の事業全部の譲受
「事業の重要な一部」については、会社法467条にて譲渡資産の帳簿価額が総資産の5分の1以上のものと規定されています。
定款変更時
定款の重要な変更が行われる場合にも、株式買取請求権が認められることがあります。特に次のような変更が該当します。
- 株式の譲渡制限の導入
- 株式の内容の変更(種類株式への変更など)
特に株式の譲渡制限を新たに導入する場合は、株主の株式処分の自由が制限されることになるため、反対株主に買取請求権が付与されます。これによって、株主は不本意な制限を受ける前に投資を回収する機会を得ることができます。
スクイーズアウト時
スクイーズアウト(少数株主の締出し)は、支配株主が少数株主の保有する株式を強制的に取得する手続きです。主に以下のような場合に株式買取請求権が認められます。
- 特別支配株主による株式等売渡請求(会社法第179条)
- 全部取得条項付種類株式の取得(会社法第171条)
- 株式併合(会社法第182条の4)
これらの手続きでは、少数株主は会社に留まる選択肢がないため、「公正な価格」で株式を買い取ってもらう権利が特に重要になります。実際、スクイーズアウトの場面では、買取価格を巡って裁判になるケースも少なくありません。
| 場面 | 該当条文(会社法) | 特徴 |
|---|---|---|
| 合併・会社分割・株式交換等 | 第785条、第797条等 | 組織再編に伴う基本構造の変更時 |
| 事業譲渡・譲受 | 第469条、第470条 | 会社の事業基盤に関わる変更時 |
| 株式譲渡制限導入等 | 第116条第1項 | 株主の権利内容の重要な変更時 |
| スクイーズアウト | 第179条、第171条等 | 少数株主の強制的排除時 |
株式買取請求権の行使手続きと流れ
株式買取請求権を行使するには、法律で定められた手続きに従う必要があります。期限や方法を誤ると権利行使ができなくなる可能性もあるため、正確な手順を理解しておくことが重要です。ここでは、反対株主が買取請求権を行使する際の一般的な流れを解説します。
株主総会前の準備
株式買取請求権の行使は、会社から株主総会の招集通知を受け取った時点から始まります。買取請求権を行使するためには、まず株主総会に先立って「議案に反対する旨」を会社に通知しなければなりません。この手続きは非常に重要で、これを怠ると後の買取請求権行使が認められなくなります。
具体的な手順としては、以下のステップを踏む必要があります。
- 株主総会の招集通知と議案を確認する
- 議案に反対する場合、株主総会の前日までに書面で「反対の通知」を会社に提出する
- 通知が確実に届いたことを確認する(配達証明付き郵便の利用が推奨される)
この反対通知に法定の様式はありませんが、少なくとも「どの議案に反対するか」と「株主の情報(氏名、住所、保有株式数など)」を明記する必要があります。また、会社によっては独自の書式を用意している場合もあります。
株主総会での対応
反対通知を提出した後は、株主総会に出席して実際に反対票を投じるか、または議決権行使書で反対票を投じる必要があります。買取請求権を行使するためには、単に反対通知を出すだけでなく、実際の議決でも反対の意思表示をすることが法律上求められています。
株主総会に出席する場合は、議案が審議される際に明確に反対の意思表示を行いましょう。議決権行使書を提出する場合は、該当議案に対して「反対」の欄にマークするなど、明確に反対票を投じることが重要です。これらの手続きを適切に行わないと、後の買取請求権行使が認められない可能性があります。
買取請求の手続き
株主総会で議案が可決された後、買取請求を行う株主は定められた期間内に「買取請求書」を会社に提出する必要があります。買取請求の期限は原則として、効力発生前の20日前から効力発生日の前日とされていますが、組織再編の種類によっては異なる場合もあるため、招集通知や会社からの案内で確認しましょう。
買取請求書には以下の内容を記載します。
- 株主の氏名・住所
- 買取を請求する株式の数
- 株主総会の日付と議案の内容
- 株券が発行されている場合は株券の提出(または株券提出の猶予を求める旨)
買取請求書が会社に到達した時点で、株式買取請求の効力が生じます。この時点から、株主と会社との間で買取価格についての協議が始まることになります。
価格協議と裁判所への申立て
買取請求が行われると、株主と会社は株式の「公正な価格」について協議を行います。この協議が整えば、合意した価格で株式の買取が行われます。協議が整わない場合は、協議期間満了後30日以内に裁判所に対して「価格決定の申立て」を行うことができます。
買取請求に関する価格決定の裁判所への申立ては、株主と会社のどちらからでも行うことが可能です。申立てがあると、裁判所は第三者的な立場から「公正な価格」を決定します。この決定は両当事者を拘束し、決定された価格で買取が行われることになります。
裁判所が価格を決定する際には、以下のような要素が考慮されます。
- 会社の財務状況と資産価値
- 将来の収益予測
- 上場会社の場合は市場株価の動向
- 組織再編によるシナジー効果
- 業界の動向や類似企業の評価
裁判所の決定に不服がある場合は、即時抗告という形で上級裁判所に不服を申し立てることも可能です。
株式買取価格の決定方法と考慮要素
株式買取請求権の行使において最も重要かつ複雑な問題が、「公正な価格」の決定です。株主と会社の間でしばしば見解の相違が生じる部分でもあります。ここでは、買取価格がどのように決定されるか、その方法と考慮される要素について詳しく解説します。
「公正な価格」の基本的な考え方
会社法は買取価格を「公正な価格」と規定していますが、具体的な算定方法については法律上明確に定めていません。判例や実務では、企業価値が増加しない場合は「組織再編等がなかったと仮定した場合の株式の客観的価値(ナカリセバ価格)」、企業価値が増加した場合は「シナジー分配価格」が公正な価格とされています。この考え方は最高裁判所の判例でも示されています。
株式の客観的価値の算定方法としては、上場会社と非上場会社で異なるアプローチが取られる傾向があります。上場会社の場合は市場株価が基準となることが多いですが、非上場会社の場合は資産価値や収益価値などから算出されます。
上場会社の価格算定方法
上場会社の株式買取価格を算定する際は、一般的に市場株価が重要な基準となります。ただし、単純に買取請求時点の株価をそのまま採用するわけではなく、以下のような要素が考慮されます。
- 一定期間(通常1か月から6か月程度)の平均株価
- 組織再編等の公表前の市場株価
- 市場全体や業界の株価動向
- 特殊な要因による一時的な株価変動の排除
裁判例では、組織再編等の発表前の一定期間の平均株価を基準としつつ、シナジー効果の分配分としてプレミアムを加算するケースが多く見られます。実際の判例では、市場株価に対して15%~40%程度のプレミアムが認められたケースがあります。
非上場会社の価格算定方法
非上場会社の場合、市場株価という客観的な指標がないため、価格算定はより複雑になります。一般的には以下のような方法が用いられます。
- 純資産価額方式:会社の純資産を株式数で割った価格
- 類似会社比準方式:類似の上場会社の株価をもとに算出
- DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法:将来の予想キャッシュフローを現在価値に割り引いて算出
- 収益還元方式:過去の利益実績をもとに将来の収益力を評価
実務では、これらの方法を組み合わせて総合的に判断されることが多く、会社の業種や事業特性、財務状況などによって重視される方法が異なります。また、専門の評価機関による株価算定が重要な参考資料となります。
シナジー効果の分配
組織再編等によって生じるシナジー効果(相乗効果)をどう評価し、どのように分配するかは、買取価格決定の重要な要素です。シナジー効果とは、合併や事業統合などによって生じる追加的な企業価値の増加分を指します。
裁判例では、このシナジー効果の一部を反対株主にも公平に分配すべきとする考え方が採用されています。具体的な分配割合は個別の事案により異なりますが、通常は組織再編等の条件や当事会社間の交渉力、株主構成などを総合的に考慮して決定されます。
特にMBOや支配株主による完全子会社化などでは、少数株主に対するシナジー効果の公正な分配が重視される傾向にあります。これは、支配株主と少数株主の間の利益相反を考慮したものと言えるでしょう。
| 評価方法 | 適用場面 | 特徴・留意点 |
|---|---|---|
| 市場株価法 | 上場会社 | 一定期間の平均値を使用 |
| 時価純資産法 | 資産保有型の非上場会社 | 簿価ではなく時価評価が基本、含み益も考慮 |
| DCF法 | 将来成長が見込める会社 | 将来予測に基づくため不確実性が高い |
| 類似会社比準法 | 比較可能な上場会社がある場合 | 適切な類似会社の選定が重要 |
実務上の注意点と対応策
株式買取請求権の行使や対応には、法律上の手続きだけでなく、実務上考慮すべき多くの注意点があります。ここでは、株主側と会社側それぞれの立場から見た実務上の注意点と効果的な対応策について解説します。
株主側の注意点
株式買取請求権を行使しようとする株主は、以下の点に特に注意する必要があります。買取請求権の行使には厳格な期限や手続きがあり、一つでも手順を誤ると権利を失効してしまう可能性があるため、細心の注意が必要です。特に初めて行使する場合は、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。
- 反対通知の期限厳守(株主総会前までに会社に到達必要)
- 議決権行使での明確な反対票の投票
- 買取請求書提出の期限管理
- 必要書類の準備と正確な記載
- 株券発行会社の場合は株券の提出準備
また、買取価格について会社と協議する際には、自社株式の適正価値について事前に調査・検討しておくことが望ましいです。必要に応じて独自に株価算定を依頼することも検討すべきでしょう。裁判所に価格決定の申立てを行う場合は、弁護士への相談が推奨されます。
会社側の対応策
会社側としては、株式買取請求に適切に対応するための準備と体制整備が重要です。特に組織再編等を計画する際には、買取請求が行使される可能性を想定した対応が必要になります。
- 株主総会招集通知での買取請求手続きの明確な説明
- 反対通知や買取請求の受付体制の整備
- 適切な株価算定のための資料準備と専門家への依頼
- 買取資金の確保と資金計画の立案
- 買取請求対応のための社内体制の構築
特に中小企業においては、多数の株主から買取請求があった場合の資金負担が経営に与える影響を事前に想定しておくことが重要です。最悪のケースを想定した資金計画を立てておくことで、不測の事態を避けられます。
価格協議のポイント
買取価格の協議は、株主と会社の双方にとって最も重要かつデリケートなプロセスです。効果的な協議のためには以下のポイントに留意しましょう。
- 客観的なデータに基づく価格提示
- 外部の専門家による株価算定書の活用
- 類似事例の調査と参照
- 協議のタイムラインの明確化
- 裁判所申立ての可能性も視野に入れた交渉
協議にあたっては、感情的な対立を避け、客観的な事実と数字に基づいた建設的な話し合いを心がけることが重要です。双方が納得できる解決策を見つけることが、長期的には最良の結果につながります。
税務上の影響
株式買取請求権の行使には税務上の影響もあります。特に個人株主の場合、買取りによって得た金銭は株式の譲渡所得として課税されます。
譲渡所得の計算方法は、買取価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額となります。この所得に対しては、原則として申告分離課税が適用され、所得税・住民税合わせて約20%の税率が課されます。ただし、特定口座での取引や優遇税制の適用など、個別の状況によって税務処理が異なる場合があるため、必要に応じて税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
会社側においても、自己株式の取得として会計処理を行うとともに、税務上も適切な対応が必要です。特に非上場会社の場合、みなし配当課税の問題が生じる可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
株式買取請求権は、会社の重要な意思決定に反対する株主を保護するための重要な制度です。合併や事業譲渡、スクイーズアウトなど会社の根本的な変更が行われる際に、少数株主に「公正な価格」での投資回収機会を与えます。
この権利を行使するには、株主総会前の反対通知の提出、総会での反対票の投票、そして買取請求書の提出という一連の手続きを期限内に正確に行う必要があります。手続きを誤ると権利が失効するため、細心の注意が求められます。
買取協議が整わない場合は裁判所に価格決定を申し立てることも可能です。このような制度を理解し適切に活用することで、株主と会社の双方の利益のバランスを図りながら、企業価値の向上を目指すことが重要です。
会社の大きな変更を検討する際には、株式買取請求権の行使可能性も考慮した慎重な計画立案が求められます。M&Aや組織再編を検討している中小企業オーナーの方は、事前に専門家へ相談することをお勧めします。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。