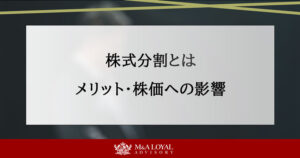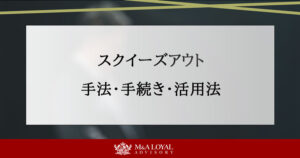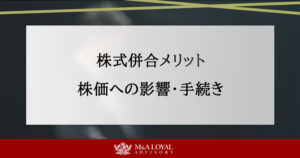株式併合とは?目的や手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
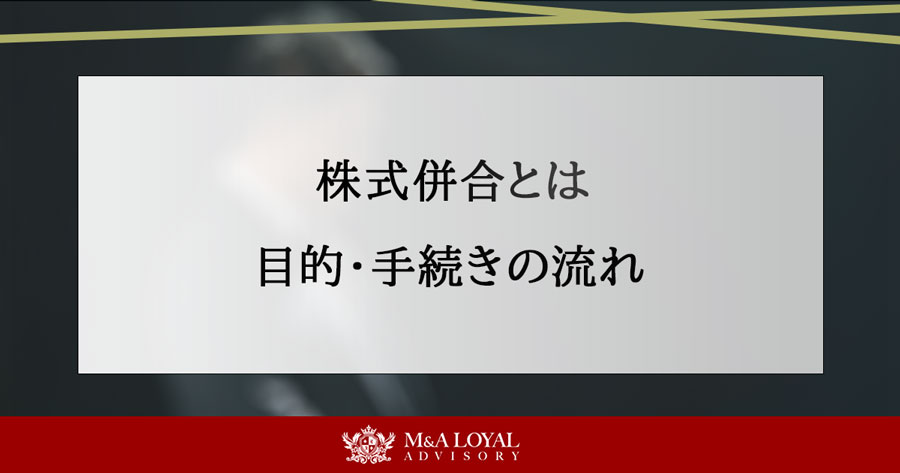
株式併合とは、複数の株式を1株にまとめることで発行済株式数を減少させる手法です。近年、経営効率化や管理コスト削減を目的として、多くの企業が株式併合を実施しています。
株式併合を実施することで、株主数の調整や株価の適正化、投資単位の最適化などの効果が期待できる一方で、少数株主の権利に重大な影響を与える可能性もあります。本記事では、株式併合の基本的な仕組みから目的、手続きの流れ、さらには注意点まで、中小企業のオーナーが知っておくべきポイントを詳しく解説します。
目次
株式併合とは何か
株式併合とは、複数の株式を1株にまとめることで、発行済株式数を減少させる手法のことを指します。この手法により、企業は株主構成の整理や経営効率化を図ることができます。
株式併合の基本的な仕組み
株式併合では、例えば4株を1株にまとめる「4対1」の併合を行うと、株主が保有する4,000株は1,000株に減少します。ただし、理論上、株式併合前後で株主が保有する株式の総額価値は変わらないとされています。これは、株式数が4分の1になる代わりに、1株当たりの価値が4倍になるためです。
株式併合は会社法第180条に基づき、株主総会の特別決議を経て実施されます。この手続きにより、企業は法的に有効な形で株式数の調整を行うことができます。
分割と併合の違い
株式併合と混同されやすいのが株式分割です。株式分割は1株を複数株に分割して株式数を増加させる手法で、株式併合とは逆の効果を持ちます。例えば、1株を2株に分割する場合、株主の保有株数は2倍になりますが、1株当たりの価値は半分になります。
株式併合は発行済株式数を減少させることで管理効率化を目指す一方、株式分割は株式の流動性向上や投資しやすい価格帯への調整を目的とします。どちらの手法も企業の資本政策において重要な選択肢となっています。
端数株の取り扱い
株式併合において重要な点は、端数株の処理です。併合比率によっては、株主が保有する株式数が割り切れない場合があり、1株未満の端数株が発生します。この端数株は、会社が適正な価格で買い取ることになります。
端数株の発生により、少数株主は議決権を失う可能性があるため、この点については特に慎重な検討が必要です。特に非上場企業の場合、株式の再取得が困難であることから、株主の権利に重大な影響を与える可能性があります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式併合の目的とメリット
企業が株式併合を実施する目的は多岐にわたりますが、主に経営効率化と財務戦略の観点から検討されます。ここでは、具体的な株式併合の目的とメリットについて詳しく解説します。
株式の管理コスト抑制
株式併合の最も重要な目的の一つが、管理コスト削減です。株主数の多い企業では、株主総会の運営、通知・配当手続き、名簿管理などで年間数百万円から数千万円のコストが発生します。
株式併合による株主数の減少により、管理コストを大幅に削減でき、特に中小企業の経営効率化に有効です。また、少数株主の権利行使に関する事務処理も簡素化されるため、経営陣は本業により集中できる環境を整えることができます。
さらに、株主総会における議事進行もスムーズになり、重要な経営判断を迅速に行える体制構築にも寄与します。これは特に、事業承継や組織再編を検討している企業にとって大きなメリットとなります。
株価の適正な水準への調整
株価が長期間にわたって低位で推移している企業では、投資家からの評価が低下し、資金調達や事業提携において不利な状況に陥る可能性があります。株式併合により投資単位を引き上げることで、株価を適正な水準に調整できます。
例えば、みずほフィナンシャルグループでは、投資単位調整を目的とした株式併合を実施し、機関投資家からの評価向上を図りました。この事例のように、株式併合は企業の投資魅力度向上にも寄与します。
適正な株価水準の維持は、企業の信用力向上や将来的な資金調達の円滑化にも直結するため、長期的な企業価値向上の観点からも重要な施策となります。
少数株主対策と経営の安定化
株主が分散している状況では、株主総会の運営や経営判断において様々なリスクが生じる可能性があります。特に、少数株主による権利行使が企業経営に支障をきたすケースも見られます。
株式併合により、1株未満の端数株を会社が買い取ることで、実質的なスクイーズアウト効果を得ることができます。これにより、経営陣は安定した企業運営を行える環境を整備できます。
ただし、この手法は少数株主の権利に重大な影響を与えるため、適正な手続きと公正な価格での買取りが不可欠です。会社法に定められた反対株主の株式買取請求権なども適切に保障する必要があります。
事業承継の円滑化
中小企業において事業承継を円滑に進めるために株式併合を活用するケースが増加しています。分散した株式を整理することで、後継者への株式移転や経営権の集約がより効率的に行えるようになります。
株式併合により株主構成をシンプルにすることで、事業承継時の複雑な手続きを軽減し、承継後の安定的な経営基盤を構築することが可能になります。これは特に、複数の親族や従業員が株式を保有している企業において有効な手法です。
株式併合の注意点とデメリット
株式併合には多くのメリットがある一方で、実施にあたっては慎重に検討すべき注意点やデメリットも存在します。特に株主の権利や企業の将来性に与える影響について理解しておくことが重要です。
株主の権利への重大な影響
株式併合の最も注意すべき点は、株主の権利に与える影響です。併合により1株未満の端数株が発生した場合、その株式は会社が強制的に買い取ることになり、該当する株主は数株分の議決権を失います。
特に非上場企業の株式の場合、一度手放した株式を再取得することは非常に困難であるため、実質的に株主としての地位を永久に失うリスクがあります。これは、従業員持株会や取引先が保有する少数株式において特に問題となる可能性があります。
また、端数株の買取価格の算定についても、株主との間で争いが生じる可能性があります。会社法では公正な価格での買取りが定められていますが、非上場企業の株式評価は複雑であり、株主が納得できる価格設定が困難な場合もあります。
投資単位の上昇による流動性低下
株式併合により投資単位が高額化することで、新規投資家の参入ハードルが上がる可能性があります。これは特に、個人投資家の投資機会を制限することにつながり、株式の流動性低下を招く恐れがあります。
東京証券取引所では、望ましい投資単位として50万円未満の範囲を示していますが、株式併合により投資単位がこの上限を超える場合、投資家層の縮小が懸念されます。流動性の低下は、将来的な株式売却や資金調達において不利な状況を生み出す可能性があります。
投資単位の調整は慎重に行う必要があり、企業の成長段階や将来の資金調達計画を十分に考慮した上で併合比率を決定することが重要です。
上場廃止リスクの検討
上場企業が株式併合を実施する場合、株主数の減少により上場維持基準を下回るリスクがあります。各証券取引所では、上場維持のための最低株主数が定められており、これを下回ると上場廃止となる可能性があります。
上場廃止は企業の信用力や資金調達能力に重大な影響を与えるため、株式併合の実施前に十分なシミュレーションを行い、上場維持基準への影響を慎重に検討する必要があります。必要に応じて、併合比率の調整や代替的な施策の検討も重要です。
手続きの複雑さとコスト
株式併合の手続きは法的に複雑であり、専門的な知識と経験が必要となります。取締役会決議から株主総会の開催、効力発生後の各種手続きまで、多岐にわたる作業が必要となり、相当な時間とコストを要します。
手続きに不備があると法的な効力が認められない可能性もあるため、弁護士や税理士などの専門家の助言を得ながら進めることが不可欠です。また、株主への説明責任も重要であり、十分な情報開示と丁寧な説明が求められます。
株式併合の手続きの流れ
株式併合を適切に実施するためには、会社法に定められた手続きを正確に履行する必要があります。手続きに不備があると法的効力が認められない可能性があるため、各段階での注意点を理解しておくことが重要です。
事前準備と取締役会決議
株式併合の第一段階は、取締役会における慎重な検討と決議です。まず、併合の目的や効果、株主への影響を詳細に分析し、実施の妥当性を判断します。この段階で、併合比率や効力発生日、対象となる株式の種類などの基本事項を決定します。
取締役会では、株主総会の招集決議も併せて行い、株主への通知方法や議事録の作成方法についても詳細に検討する必要があります。また、反対株主への対応や端数株の処理方法についても、この段階で明確にしておくことが重要です。
取締役会議事録は、後の手続きにおいて重要な証拠書類となるため、決議内容を正確かつ詳細に記録しておく必要があります。必要に応じて、法務担当者や外部の専門家による事前レビューを受けることも推奨されます。
株主総会の招集と特別決議
株式併合は会社の基本的な構造を変更する行為であるため、株主総会における特別決議が必要となります。特別決議には、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
株主総会の招集通知は、会社法の規定に従って適切な時期に発送する必要があります。通知には、併合の具体的な内容、理由、株主に与える影響、反対株主の権利などを詳細に記載しなければなりません。
株主総会では、株主からの質問に対して誠実かつ具体的に回答し、併合の必要性と合理性について十分に説明することが重要です。議事録の作成も法的要件の一つであり、決議の有効性を証明する重要な文書となります。
効力発生と事後手続き
株主総会での承認を得た後、指定された効力発生日に株式併合が実行されます。効力発生日以降は、併合比率に基づいて株式数が自動的に変更され、株主名簿の更新や新しい株券の発行(株券発行会社の場合)などの手続きが必要となります。
端数株が発生した株主に対しては、会社が適正な価格で買取りを行います。買取価格の算定には、企業価値評価や市場価格などを考慮した公正な手法を用いる必要があります。また、買取りに関する通知や支払い手続きも適切に実施しなければなりません。
効力発生後は、定款の変更登記や必要書類の備置きなどの法的手続きも完了させる必要があります。これらの手続きには期限が設けられているため、スケジュール管理を徹底することが重要です。
反対株主の株式買取請求への対応
会社法第182条の4では、株式併合に反対する株主に対して、公正な価格での株式買取請求権を認めています。この権利は株主の重要な保護措置であり、会社は適切に対応する義務があります。
買取価格の算定においては、企業の財務状況、将来の収益性、類似企業との比較などを総合的に考慮し、客観的で合理的な評価を行う必要があります。価格に関して株主との間で争いが生じた場合は、裁判所による価格決定手続きを経ることもあります。
反対株主への対応は、企業の信頼性や法的リスクの管理において重要な要素となるため、専門家の助言を得ながら適切に処理することが推奨されます。
株式併合の具体的事例
実際の企業による株式併合の事例を通じて、その目的や効果、注意点について具体的に理解することができます。ここでは、代表的な事例を取り上げて詳しく解説します。
佐渡汽船の大規模併合事例
2022年に実施された佐渡汽船の株式併合は、27万株を1株にまとめるという極めて大規模な併合として注目を集めました。この併合の主な目的は、債務超過約30億円という厳しい経営状況の中での経営再建とスクイーズアウトでした。
この事例では、大部分の少数株主が端数株主となり、実質的に株主から除外される結果となったため、少数株主保護の観点から様々な議論を呼びました。一方で、経営の安定化と再建への集中という目的は一定程度達成されたと評価されています。
佐渡汽船の事例は、経営危機にある企業が株式併合を活用する際の参考となる一方で、株主の権利保護の重要性についても重要な示唆を与えています。特に、公正な買取価格の算定や十分な情報開示の必要性が浮き彫りになりました。
双日の投資単位調整事例
2021年に実施された双日の株式併合は、東証の望ましい投資単位である5万円以上50万円未満の範囲に調整することを目的としていました。当時の株価307円では投資単位が30,700円と低すぎたため、併合により適正な水準への調整を図りました。
この事例では、機関投資家からの評価向上や株式の流動性改善などの効果が期待されました。実際に、併合後は投資家からの注目度が高まり、株価の安定化にも寄与したとされています。
双日の事例は、投資単位調整を主目的とした株式併合の成功例として、多くの企業が参考にしている事例です。特に、適切な併合比率の設定や市場への丁寧な説明が功を奏した点が評価されています。
中小企業における事業承継活用事例
中小企業においても、事業承継の円滑化を目的とした株式併合の活用が増加が見込まれます。ニデックによるTAKISAWAの完全子会社化の事例では、経営の意思決定を迅速化し、グループ一体での戦略を推進するために株式の非公開化が行われました。
この事例では、まず株式公開買い付け(TOB)によって市場の株式を買い集め、その後、株式併合を実施しました。これにより、TOBに応じなかった少数株主の株式を1株未満の端株(はかぶ)にして整理し、TAKISAWAを完全子会社としました。
少数株主の整理によって、株主総会の運営コスト削減や、迅速な意思決定が可能になるなど、経営効率化に大きく寄与しました。
このプロセスにおいて、少数株主との関係維持に細心の注意を払い、TOBにおける公正な買取価格(プレミアムを上乗せした価格)の提示と、手続きに関する十分な情報開示を行ったことが成功の要因となりました。この事例は、企業が株式併合を活用して経営改革を進める際の重要なポイントを示しています。
参考:ニデック株式会社|株式会社 TAKISAWA の株式併合の効力発生および、完全子会社化に関するお知らせ
会社法改正による影響事例
近年の会社法改正により、株式併合の手続きや要件に変更が加えられたことで、企業の対応にも変化が見られます。改正により、株主保護の仕組みが強化され、より慎重な手続きが求められるようになりました。
会社法改正の影響により、株式併合を検討する企業は、従来以上に株主への説明責任や公正な価格算定の重要性を認識するようになっています。これにより、専門家の助言を求める企業が増加し、より適切な手続きが行われる傾向にあります。
| 企業名 | 併合比率 | 主な目的 | 効果・結果 |
|---|---|---|---|
| 佐渡汽船 | 27万対1 | 経営再建・スクイーズアウト | 株主数大幅減少・経営安定化 |
| 双日 | 5対1 | 投資単位調整 | 機関投資家評価向上 |
| みずほFG | 10対1 | 投資単位最適化 | 流動性改善 |
まとめ
株式併合は、企業の経営効率化や財務戦略の実現において有効な手法ですが、株主の権利に重大な影響を与える可能性があるため、慎重な検討と適切な手続きが不可欠です。管理コスト削減や株価の適正化、少数株主整理などによるメリットがある一方で、株主の議決権消失や投資単位上昇による流動性低下(少数株主の強制的な排除)などのデメリットも存在します。
特に中小企業においては、事業承継の円滑化や経営の安定化を目的として株式併合を活用するケースが増加していますが、従業員や取引先との関係維持、公正な価格での端数株買取りなど、様々な配慮が必要となります。会社法に定められた手続きを正確に履行し、株主への十分な説明と情報開示を行うことで、法的リスクを最小限に抑えることができます。
株式併合の実施を検討される際は、その目的と効果を明確にした上で、専門家の助言を得ながら進めることをお勧めいたします。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&A・事業承継の仲介業者としてお客様の状況に応じた最適なソリューションをご提案いたします。M&Aや経営課題に関するご相談はお気軽にお問合せください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。