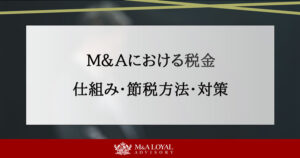累進課税制度とは?税率計算方法やメリット・デメリットを簡単に解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
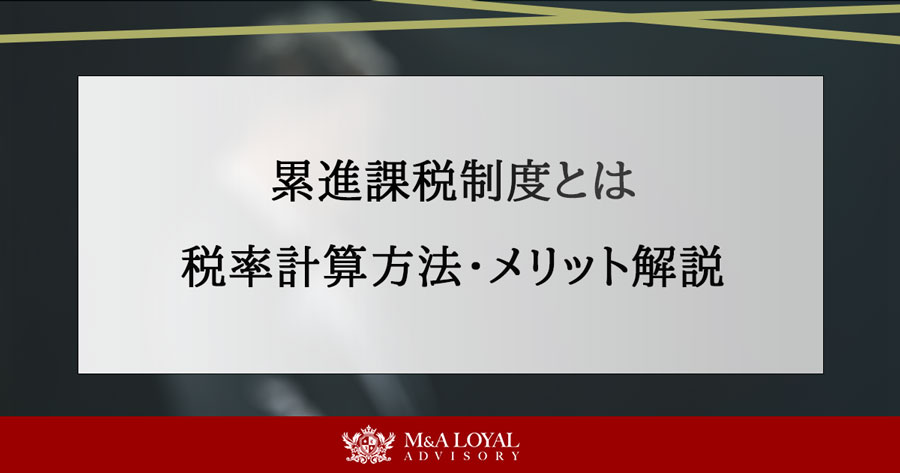
累進課税制度は、日本の税制において重要な役割を果たしている課税方式です。所得や資産の額に応じて税率が段階的に上昇するこの制度は、社会的公平性を保つ一方で、高所得者や資産家には重い税負担を課します。中小企業経営者の皆様にとって、この制度を理解することは事業戦略や資産形成において欠かせません。
事業が成長し所得が増加した時、事業承継を検討する時、M&Aを実行する時など、様々な場面で累進課税の影響を受けることになります。税率は最低5%から最高45%まで7段階に分かれており、所得の増加に伴って税負担も大きく変わります。本記事では、制度の詳しい仕組みから実践的な対策までわかりやすく説明します。
目次
累進課税制度とは何か|基本的な仕組みを理解する
累進課税制度は、課税対象となる所得や資産の金額が増えるほど、段階的に税率が高くなる課税方式です。この制度は、所得の多い人により多くの税負担を求めることで、社会全体の公平性と所得再分配を実現することを目的としています。
日本では所得税、相続税、贈与税において累進課税制度が採用されており、特に中小企業経営者や個人事業主にとっては、事業所得や譲渡所得に直接関わる重要な税制度です。
累進課税制度の定義と特徴
累進課税制度の最も重要な特徴は、「担税力に応じた課税」という考え方にあります。これは、所得が多い人ほど税金を負担する能力が高いという前提に基づいています。
具体的には、課税所得金額が一定の基準を超えるごとに税率が段階的に上昇する仕組みです。例えば、所得税では課税所得195万円未満の部分は5%、195万円以上330万円未満の部分は10%というように、所得が増えるほど高い税率が適用されます。
この制度により、低所得者の税負担を軽減しながら、高所得者により多くの税負担を求めることで、所得格差の是正と社会保障制度の財源確保を両立させています。
単純累進課税と超過累進課税の違い
累進課税制度には、単純累進課税と超過累進課税の2つの方式があります。両者の違いを理解することは、税負担の計算において非常に重要です。
単純累進課税は、課税対象額が一定の基準を超えた場合、その全額に対して高い税率を適用する方式です。一方、超過累進課税は、基準を超えた部分のみに高い税率を適用する方式です。
日本の所得税、相続税、贈与税では超過累進課税が採用されています。これにより、基準額を少し超えただけで税負担が急激に増加する「税率の崖」現象を避けることができます。
例えば、課税所得が330万円の場合、195万円未満の部分は5%、195万円以上330万円未満の部分は10%の税率が適用されるため、段階的で合理的な税負担となります。
比例税率や定額税との比較
累進課税制度の特徴をより理解するために、他の課税方式との比較を見てみましょう。
比例税率は、所得に関係なく一定の税率を適用する方式です。消費税(10%)がその代表例で、所得の多寡に関わらず同じ税率が適用されます。この方式は簡素で分かりやすい反面、所得再分配機能は持ちません。
定額税は、所得に関係なく一定額の税金を課す方式です。住民税の均等割(年額5,000円)がこれにあたります。この方式は最も単純ですが、低所得者により重い負担を強いる逆進性があります。
累進課税制度は、これらの課税方式と比べて所得再分配機能に優れており、社会全体の公平性を追求できる点で優れています。ただし、計算が複雑になり、高所得者の労働意欲に影響を与える可能性もあります。
中小企業経営者にとっては、事業所得の増加に伴う税負担の変化を予測し、適切な税務戦略を立てることが重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



累進課税制度の対象となる税金の種類
日本の税制において、累進課税制度が適用される税金は、所得税、相続税、贈与税の3つです。これらの税金は、いずれも個人の経済力や担税力に応じて税率が段階的に上昇する仕組みとなっており、中小企業経営者にとって特に重要な税制度です。
所得税における累進課税の仕組み
所得税は、個人の1年間の所得に対して課税される税金で、累進課税制度の代表的な例です。課税所得金額に応じて5%から45%まで7段階の税率が設定されています。
所得税の累進課税(総合課税)が適用される所得には、給与所得、事業所得、不動産所得などが含まれます。譲渡所得については、ゴルフ会員権の譲渡など一部のものは総合課税の対象となりますが、M&Aで重要な株式の譲渡所得や、土地・建物の譲渡所得は、他の所得と合算されない「分離課税」の対象であり、累進課税は適用されません。中小企業経営者にとって特に重要なのは、事業所得と役員報酬としての給与所得です。
事業所得の場合、売上から必要経費を差し引いた金額が課税所得となり、これに累進税率が適用されます。例えば、年間課税所得が500万円の場合、195万円未満の部分は5%、195万円以上330万円未満の部分は10%、330万円以上の部分は20%の税率が適用されます。
また、2013年から2037年までの期間については、復興特別所得税として所得税額の2.1%が上乗せされるため、実際の税負担はさらに増加します。
相続税の累進課税と税率構造
相続税は、被相続人から財産を相続した場合に課税される税金で、10%から55%までの8段階の累進税率が設定されています。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、相続財産がこの基礎控除額を超えた場合にのみ相続税が発生します。例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。
中小企業経営者にとって相続税は、事業承継において重要な検討要素です。会社の株式や事業用資産の評価額が高い場合、相続税の負担が事業承継の障害となる可能性があります。
相続税の計算は複雑で、まず相続財産全体から基礎控除を差し引いた課税遺産総額を各相続人が法定相続分に従って取得したものと仮定して税額を計算し、その後実際の相続割合に応じて各相続人の納税額を決定します。
贈与税の累進課税と計算方法
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に課税される税金で、年間110万円の基礎控除額を超えた部分に対して累進税率が適用されます。
贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。一般的に適用される暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税されます。
贈与税の税率には、一般税率と特例税率の2種類があります。特例税率は、18歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合に適用される優遇税率です。
中小企業経営者にとって贈与税は、事業承継対策として重要な役割を果たします。会社の株式を後継者に段階的に贈与することで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、贈与税は相続税よりも高い税率が設定されているため、贈与のタイミングや金額を慎重に検討する必要があります。年間110万円以内の贈与であれば贈与税は発生しないため、長期的な視点で計画的に実行することが重要です。
累進課税の計算方法と具体例
累進課税の計算は複雑に見えますが、基本的な仕組みを理解すれば実際の税負担を正確に把握できます。ここでは、所得税、相続税、贈与税の具体的な計算方法を、中小企業経営者にとって身近な例を使って解説します。
所得税の計算手順と税率表
所得税の計算は、以下の3つのステップで行われます。
まず、収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。次に、所得金額から各種所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)を差し引いて課税所得金額を求めます。最後に、課税所得金額に税率を適用して所得税額を計算します。
令和5年分の所得税率表は以下の通りです。
- 195万円未満:5%(控除額0円)
- 195万円以上330万円未満:10%(控除額97,500円)
- 330万円以上695万円未満:20%(控除額427,500円)
- 695万円以上900万円未満:23%(控除額636,000円)
- 900万円以上1,800万円未満:33%(控除額1,536,000円)
- 1,800万円以上4,000万円未満:40%(控除額2,796,000円)
- 4,000万円以上:45%(控除額4,796,000円)
例えば、課税所得が500万円の場合、「500万円×20%-427,500円=572,500円」となります。
復興特別所得税を含む実際の税負担
2013年から2037年までの25年間は、復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が上乗せされます。これにより、実際の税負担は計算した所得税額の約102.1%となります。
前述の課税所得500万円の例では、復興特別所得税を含む実際の税額は「572,500円×102.1%=584,519円」となります。
中小企業経営者の場合、事業所得に加えて役員報酬や不動産所得なども合算して総合課税される点に注意が必要です。特に法人成りを検討する際は、個人事業主として支払う所得税と法人税・役員報酬にかかる所得税の合計を比較することが重要です。
また、青色申告特別控除(最大65万円)や小規模企業共済等掛金控除を活用することで、課税所得を減らし、実効的な税負担を軽減できます。
相続税の計算方法と節税効果
相続税の計算は、以下の手順で行われます。
まず、相続財産の総額から基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を差し引き、課税遺産総額を計算します。次に、この課税遺産総額を法定相続分に従って各相続人が取得したものと仮定して、各相続人の法定相続分に応じた税額を計算します。
相続税の税率は10%から55%までの8段階で設定されており、法定相続分に応じた取得金額が1,000万円以下は10%、3,000万円以下は15%、5,000万円以下は20%と段階的に上昇します。
例えば、相続財産が8,000万円で法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は4,800万円となり、課税遺産総額は3,200万円です。配偶者の法定相続分1,600万円には15%の税率が適用され、子1人当たりの法定相続分800万円には10%の税率が適用されます。
相続税の節税効果として、配偶者の税額軽減制度(1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額まで非課税)や小規模宅地等の特例(事業用宅地400㎡まで80%減額)などがあります。
M&A時の税負担シミュレーション
中小企業のM&Aにおいて、個人株主が株式を譲渡する場合の税負担を考えてみましょう。
株式の譲渡所得は、原則として分離課税が適用され、譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。累進課税ではないため、どれだけ大きな譲渡益が発生しても税率は変わりません。
例えば、会社を1億円で売却し、取得費が1,000万円の場合、譲渡益は9,000万円となり、税額は約1,828万円(9,000万円×20.315%)となります。
ただし、役員退職金を併せて受け取る場合は、退職所得として累進課税が適用されます。退職所得は「(退職金-退職所得控除額)×1/2」で計算され、この金額が課税所得となります。
M&A時の税務戦略として、譲渡価格と退職金のバランスを最適化することで、全体の税負担を軽減できる可能性があります。また、事前の株式評価額引き下げ対策や、後継者への段階的な株式移転なども効果的です。
累進課税制度のメリット・デメリット
累進課税制度は、社会的公平性を重視する一方で、経済活動に対して複雑な影響を与えます。中小企業経営者にとって、この制度の長所と短所を正確に理解することは、効果的な税務戦略を立てる上で不可欠です。
累進課税制度の3つのメリット
累進課税制度には、以下の3つの重要なメリットがあります。
- 所得再分配機能による社会的公平性の実現:
高所得者により多くの税負担を求めることで、社会保障制度の財源を確保し、低所得者への支援を可能にします。社会全体の格差是正と安定した経済成長を促進する効果があります。
- 担税力に応じた公平な課税の実現:
同じ100万円の税負担でも、年収300万円の人と年収3,000万円の人では経済的影響が大きく異なります。各個人の支払い能力に応じた適切な税負担を実現できます。
- 経済の自動安定化機能:
景気が良い時期は高所得者が増え、累進税率により税収が増加。景気悪化時は所得が減り、低い税率が適用されるため税負担が軽減されます。経済変動を自動的に調整し、安定した社会運営に貢献します。
中小企業経営者にとっては、事業が軌道に乗る前の低収益期間は税負担が軽く、事業が成長して高収益となった際に社会貢献度の高い税負担となる仕組みは理にかなっています。
累進課税制度の3つのデメリット
累進課税制度には、以下の3つの主要なデメリットがあります。
- 労働意欲や投資意欲の減退:
所得が増えるほど税率が高くなるため、「頑張って稼いでも税金で大部分を持っていかれる」という心理的影響が生じる可能性があります。特に最高税率が45%に達する現在の制度では、この影響は無視できません。
- 国際競争力の低下と人材流出のリスク:
グローバル化が進む現代では、優秀な人材や企業が税率の低い国に移住・移転する可能性があります。これにより、長期的には税収減少や経済活力の低下を招く恐れがあります。
- 税収の不安定性と計算の複雑さ:
高所得者の所得変動により税収が大きく変動するため、安定した財政運営が困難になる場合があります。また、複雑な計算方法は納税者の理解を困難にし、適切な税務申告を阻害する可能性があります。
中小企業経営者が知っておくべきデメリット対策
中小企業経営者が累進課税制度のデメリットを軽減するための主要な対策は以下の通りです。
- 所得の平準化による税負担軽減:
事業所得が年によって大きく変動する場合、所得の集中年に高い税率が適用されます。好調な年には設備投資や研究開発投資を積極的に行い、将来の成長基盤を整えながら当期の所得を抑制します。
- 法人成りのタイミング検討:
個人事業主として高い累進税率を負担するよりも、法人税率の方が有利になる場合があります。特に所得が800万円を超える場合は、法人成りによる節税効果を詳しく検討する必要があります。
- 事業承継対策としての株式移転戦略:
株式の評価額が低い時期に後継者への贈与を実行し、将来の相続税負担を軽減します。年間110万円の贈与税基礎控除を活用した長期的な株式移転戦略も効果的です。
これらの対策を組み合わせることで、累進課税制度のデメリットを軽減しながら、適切な税負担で事業を継続・発展させることが可能になります。
事業承継・M&Aで累進課税が適用される場面
事業承継やM&Aにおいては、取引の形態や対象資産によって累進課税が適用される場面が異なります。中小企業経営者にとって、これらの場面を正確に理解し、適切な税務戦略を立てることは、事業承継やM&Aを成功させるための重要な要素です。
個人事業の事業譲渡における累進課税
個人事業主が事業を第三者に譲渡する場合、その税務上の取り扱いは非常に複雑です。譲渡対価は、譲渡する資産の種類に応じて所得区分が細かく分かれ、それぞれ異なる課税方式が適用されます。
具体的な所得区分は以下の通りです。
- 棚卸資産(商品・在庫など)の譲渡益:
「事業所得」として、他の事業所得と合算され、5%から45%の累進課税が適用されます。
- 営業権(のれん)や機械設備、車両などの譲渡益:
「譲渡所得(総合課税)」に分類されます。この所得も他の総合課税の所得と合算され、累進課税の対象となります。ただし、所有期間が5年を超える資産(長期譲渡)の場合、課税対象となる所得金額は2分の1に圧縮されます。
- 土地・建物の譲渡益:
「譲渡所得(分離課税)」となり、事業所得や給与所得など他の所得とは完全に分離して、所有期間に応じた所定の税率(長期譲渡で約20%、短期譲渡で約39%)で課税されます。
このように、譲渡対価を一体として捉えるのではなく、資産ごとに分解してそれぞれのルールで税額を計算する必要があり、将来的な事業売却を考える個人事業主にとって極めて重要な知識です。
例えば、個人事業主が営業権を含む事業全体を3,000万円で譲渡し、帳簿価額や譲渡費用を差し引いた譲渡益が2,000万円の場合、この金額は事業所得として他の所得と合算されます。既存の事業所得と合わせて課税所得が高額になると、最高税率45%が適用される可能性があります。
このような場合、譲渡時期を複数年に分散させることで、各年の税負担を軽減できる場合があります。また、事業承継税制の適用を検討することで、税負担の軽減や繰延が可能になる場合もあります。
役員退職金と累進課税の関係
M&Aや事業承継の際、経営者が会社から受け取る役員退職金は、退職所得として累進課税が適用されます。ただし、退職所得には特別な計算方法と控除制度があり、一般的な所得よりも優遇されています。
退職所得の計算方法は「(退職金-退職所得控除額)×1/2」となります。退職所得控除額は勤続年数によって決まり、勤続年数20年以下の部分は年40万円、20年を超える部分は年70万円で計算されます。
例えば、勤続30年で退職金3,000万円を受け取る場合、退職所得控除額は1,500万円(20年×40万円+10年×70万円)となり、退職所得は750万円((3,000万円-1,500万円)×1/2)となります。
この課税退職所得金額750万円に対して所得税の累進税率が適用されます。所得税額は「750万円 × 税率23% − 控除額63万6,000円」で計算され、108万9,000円となります。これに復興特別所得税(所得税額の2.1%)と住民税(課税退職所得金額の10%)を加えた実際の税負担額が決定します。退職所得の2分の1課税と退職所得控除により、実効税率は大幅に軽減されます。
M&Aの際は、株式譲渡価格と退職金のバランスを最適化することで、全体の税負担を最小化できる可能性があります。
相続・贈与による事業承継の累進課税
相続や贈与による事業承継では、承継される資産の種類と評価額によって、相続税や贈与税の累進課税が適用されます。
相続による事業承継の場合、会社の株式や事業用資産の評価額が相続財産となり、相続税の累進課税が適用されます。中小企業の株式は、純資産価額方式や類似業種比準価額方式により評価され、この評価額が高い場合は高い相続税率が適用されます。
生前贈与による事業承継では、贈与する株式の評価額に応じて贈与税の累進課税が適用されます。年間110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されませんが、まとまった株式を贈与する場合は高い税率が適用される可能性があります。
事業承継税制の特例措置を活用することで、一定の要件を満たす場合に相続税や贈与税の納税猶予や免除を受けることができます。この制度により、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる場合があります。
また、株式の評価額を事前に引き下げる対策として、退職金の支払いや不動産の購入などによる純資産額の圧縮、持株会社の設立による評価額の引き下げなどの方法があります。
これらの対策を組み合わせることで、事業承継時の累進課税による税負担を効果的に軽減し、円滑な事業承継を実現できます。
累進課税制度を踏まえた節税対策
累進課税制度では所得が高くなるほど税率が上昇するため、効果的な節税対策を実施することで税負担を大幅に軽減できる可能性があります。中小企業経営者にとって実践可能な節税対策を、具体的な方法と効果とともに解説します。
所得分散による税負担軽減策
所得分散は、累進課税制度の特性を活用した最も効果的な節税対策の一つです。一人に所得が集中すると高い税率が適用されるため、家族や複数年にわたって所得を分散させることで、全体の税負担を軽減できます。
家族への所得分散として、配偶者や子供を従業員として雇用し、適正な給与を支払う方法があります。この際、実際の労働実態に応じた適正な金額である必要があり、税務署の調査で否認されないよう注意が必要です。また、家族に対して事業用不動産の賃貸料を支払うことで、所得を分散させる方法もあります。
複数年にわたる所得分散では、収益の計上時期を調整することで各年の所得を平準化できます。例えば、大きな売上が見込まれる年に設備投資を行い、減価償却費によって所得を圧縮する方法があります。また、小規模企業共済への加入により、年間最大84万円の所得控除を受けながら、将来の退職資金を積み立てることができます。
確定拠出年金(iDeCo)の活用も有効です。個人事業主(第1号被保険者)の場合、国民年金基金等と合わせて年間最大81万6,000円(月額6万8,000円)の拠出が可能で、その掛金は全額所得控除の対象となります。これにより、高い税率が適用される年の所得を減らしながら、将来の年金資産を形成できます。
適切な売却タイミングの選択
事業譲渡や株式売却のタイミングは、税負担に大きな影響を与えます。他の所得が少ない年を選ぶことで、累進税率を低く抑えることができます。
個人事業の譲渡の場合、事業所得として累進課税が適用されるため、他の所得が少ない年に売却することで税負担を軽減できます。例えば、通常年間所得が1,000万円の経営者が、所得の少ない年に事業譲渡を行えば、譲渡益に適用される税率を下げることができます。
また、税制改正の動向を注視することも重要です。累進税率の変更や各種控除制度の改正により、売却タイミングによって税負担が変わる可能性があります。特に、事業承継税制の適用期限や要件変更に注意を払う必要があります。
役員退職金の支給時期も重要な検討事項です。退職所得は、給与所得や事業所得など他の所得と合算せず分離して税額を計算する点で優遇されています。その上で、勤続年数に応じた非常に大きな「退職所得控除」と、控除後の金額をさらに半分にする「2分の1課税」が適用されるため、他の所得に比べて税負担が大幅に軽減されます。また、複数年にわたって分割して支給することで、各年の税負担を軽減できる場合があります。
事業承継における生前贈与の活用
生前贈与は、相続時の累進課税による高い税負担を軽減する効果的な方法です。贈与税の基礎控除年110万円を活用し、長期間にわたって計画的に株式を移転することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。
具体的には、後継者に対して毎年110万円相当の株式を贈与することで、贈与税を負担することなく株式を移転できます。例えば、株式の評価額が1株1万円の場合、毎年110株を贈与できます。これを20年間続けることで、2,200株を無税で移転できます。
住宅取得等資金贈与の特例や教育資金贈与の特例などの特別制度を活用することで、基礎控除を超える贈与を行うことも可能です。これらの制度を適切に活用することで、より大きな金額を効率的に移転できます。
また、株式の評価額を事前に引き下げる対策も重要です。退職金の支給や不動産の購入により会社の純資産額を圧縮し、株式評価額を下げてから贈与を行うことで、より多くの株式を移転できます。
ただし、贈与税は相続税よりも高い税率が設定されているため、贈与する金額や時期を慎重に検討する必要があります。税理士等の専門家と相談しながら、最適な贈与戦略を立てることが重要です。
累進課税制度と確定申告の関係
確定申告は、累進課税制度による正確な税額計算を行うための重要な手続きです。年間の所得を正確に把握し、適切な税率を適用することで、公平な税負担を実現しています。中小企業経営者にとって、確定申告と累進課税の関係を理解することは、適切な税務申告を行う上で不可欠です。
確定申告での累進課税の適用方法
確定申告では、1年間のすべての所得を合算し、総所得金額を計算した後、各種所得控除を差し引いて課税所得金額を求めます。この課税所得金額に対して、累進税率を適用して所得税額を計算します。
具体的な計算手順は以下の通りです。まず、給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得などの総合課税対象所得を合計します。次に、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除を差し引きます。 なお、基礎控除額は2400万円以下の所得の場合は一律48万円です。
得られた課税所得金額に対して、5%から45%までの7段階の累進税率を適用し、所得税額を計算します。さらに、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算し、源泉徴収税額や予定納税額を差し引いて、最終的な申告税額を確定します。
中小企業経営者の場合、事業所得が主たる所得となることが多く、売上から必要経費を差し引いた所得金額が累進課税の対象となります。青色申告特別控除(最大65万円)や小規模企業共済等掛金控除などを活用することで、課税所得を圧縮し、累進税率による税負担を軽減できます。
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、どちらも所得税の精算を行う制度ですが、累進課税の適用において重要な違いがあります。
年末調整は、給与所得者を対象とした簡易的な税額計算制度で、給与所得のみを対象として累進課税を適用します。勤務先が従業員に代わって所得控除を適用し、源泉徴収税額との差額を精算します。ただし、年末調整では限られた所得控除しか適用できないため、医療費控除や雑損控除などは確定申告で申告する必要があります。
確定申告は、すべての所得を対象とした包括的な税額計算制度です。給与所得以外の所得がある場合や、年末調整で適用できない控除がある場合は、確定申告により正確な累進課税を適用します。
中小企業経営者の場合、役員報酬として給与所得を受けている場合でも、事業所得や不動産所得などの他の所得があることが多いため、確定申告が必要になります。これらの所得を合算して総合課税を適用することで、適切な累進税率による税負担を実現します。
確定申告が必要になる累進課税のケース
確定申告が必要になる主なケースを理解することで、適切な税務申告を行うことができます。
給与所得者であっても、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。例えば、会社員でありながら個人事業を営んでいる場合や、不動産賃貸収入がある場合などが該当します。これらの所得は総合課税の対象となり、給与所得と合算して累進課税が適用されます。
個人事業主や自営業者は、事業所得が48万円を超える場合に確定申告が必要です。事業所得は累進課税の対象となり、所得金額に応じて5%から45%の税率が適用されます。青色申告を選択することで、青色申告特別控除や欠損金の繰越控除などの特典を受けることができます。
また、年間の医療費が10万円を超える場合や、住宅ローン控除の適用を受ける場合、ふるさと納税の寄付金控除を受ける場合なども確定申告が必要です。これらの控除を適用することで、課税所得を減らし、累進課税による税負担を軽減できます。
譲渡所得や一時所得などの特別な所得がある場合も確定申告が必要です。ただし、株式の譲渡所得など一部の所得は分離課税が適用され、累進課税の対象外となります。
これらのケースを正確に把握し、適切な確定申告を行うことで、累進課税制度による公平な税負担を実現できます。
まとめ|累進課税制度を正しく理解して適切な税務対策を
累進課税制度は、所得や資産の額に応じて税率が段階的に上昇する仕組みで、日本では所得税、相続税、贈与税に適用されています。この制度は社会的公平性を保つ一方で、高所得者の税負担が重くなります。
中小企業経営者にとって重要なのは、事業承継やM&A時の税務影響を把握することです。個人事業譲渡は事業所得として累進課税が適用され、役員退職金は退職所得として優遇措置があります。
効果的な節税対策として、所得分散、適切な売却タイミング、計画的な生前贈与が挙げられます。小規模企業共済やiDeCoの活用により、税負担軽減と資産形成が両立できます。
税制改正により制度は変更される可能性があるため、税理士などの専門家と連携し、継続的な知識更新が重要です。 事業承継やM&Aに関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。