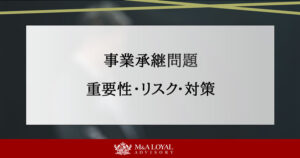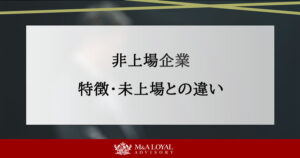自己株式とは?取得のメリットと手続の方法を分かりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
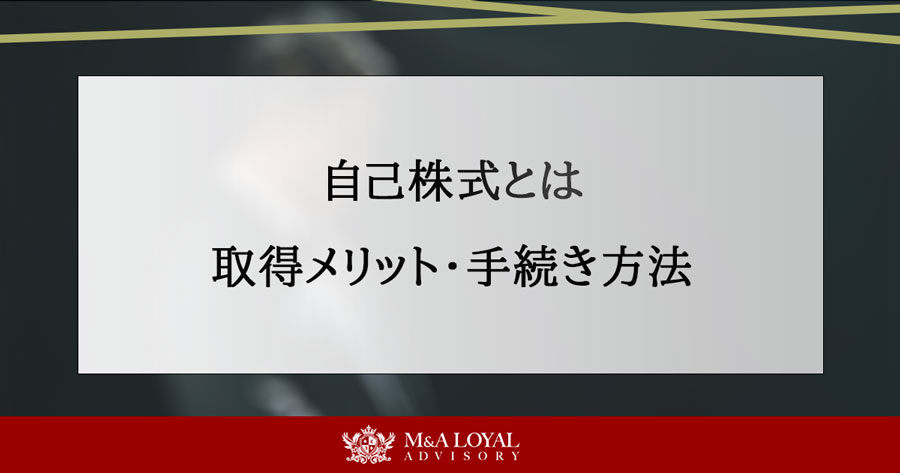
自己株式は、企業の戦略的経営判断において重要な手段です。M&Aの対価として活用したり、敵対的買収から会社を守ったり、事業承継を円滑に進めるために利用されています。しかし、自己株式の取得には複雑な法的手続きや税務上の注意点があり、適切な知識なしに実行すると思わぬリスクを招きます。 本記事では、自己株式の目的から手続きの方法まで分かりやすく解説します。
目次
自己株式の基本的な仕組みと法的位置づけ
自己株式とは、株式会社が自ら発行した株式を自社で保有することを指します。企業が市場などで流通している自社株を買い戻す行為により取得され、会社法155条に違反しない限り原則として取得が可能です。
定義と特徴
自己株式は議決権や配当請求権などの株主権を持たず、企業が自分に権利を行使する矛盾を避けるため、これらの権利は失効します。自己株式の取得は、資本政策や株主還元策として活用され、流通株式数の減少を通じて1株あたりの価値向上が期待されます。消却や売却などで処理されることが一般的で、法的制約を考慮した慎重な運用が必要です。
自己株式に関する法的背景と変遷
日本における自己株式の法的扱いは、時代とともに大きく変化してきました。明治期の商法では原則として禁止されていましたが、1938年の商法改正で一定の条件下で取得が認められるようになり、規制緩和が始まりました。
2001年の旧商法改正により、自己株式取得が本格的に合法化され、2006年の会社法施行により現在の制度が確立されました。現在では、企業は会社法155条に基づき自己株式の取得が禁止される一方、会社法156条以降の規定に従えば取得が認められる例外的制度が設けられています。
会社法では、自己株式の取得について財源規制や手続き規制を定めており、これらの規制は株主や債権者の利益保護を目的としています。財源規制により、自己株式の取得は「配当可能額」の範囲内で行われる必要があり、企業の資本維持や債権者に対する支払い能力を確保します。また、手続き規制により、株主総会や取締役会での承認が求められるほか、取得条件や方法について適切に開示することが必要です。
これらの規制は、企業の健全な資本政策を促進し、株主還元の一環として自己株式を活用する際の安全性を確保するために重要な役割を果たしています。
会社法における自己株式の位置づけ
会社法155条では、自己株式の取得について包括的な規定を設け、法律で禁止されていない限り、会社は自己の株式を取得できると定めています。
ただし、取得には一定の制限があります。分配可能額の範囲内でのみ取得が可能であり、この制限は会社の財政状態を健全に保つための重要な仕組みです。分配可能額は、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額で算定されます。具体的には、剰余金の額から自己株式の帳簿価額や準備金等の控除項目を差し引いた金額となります。
会社法では、株主平等の原則に基づき、特定の株主からのみ自己株式を取得する場合には株主総会の特別決議が必要とされています。これにより、不公平な取引を防止し、すべての株主の利益を保護しています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



自己株式取得の5つの主要目的とその活用方法
企業が自己株式を取得する目的は多岐にわたりますが、主要な5つの目的について詳しく解説します。それぞれの目的は、企業の戦略的な経営判断と密接に関連しており、適切に活用することで企業価値の向上につながります。
M&Aの対価としての活用
自己株式は、M&Aにおいて有効な対価手段として活用されています。株式交換や株式譲渡の際に、現金の代わりに自己株式を対価として使用することで、新株発行に伴うコストを削減し、既存株主の持株比率希薄化を防止できます。これにより、既存株主の利益を保護しつつ、企業買収を進めることが可能です。
さらに、自己株式を活用することで現金調達の負担を軽減し、財務の健全性を維持しながら大規模なM&Aを実行できるメリットがあります。ただし、自己株式を対価として使用する場合には、会社法に基づく手続きや株主総会での承認が必要となる場合があります。また、税務上の影響や財源規制にも留意する必要があります。
自己株式を対価とすることで、買収先企業の株主に対して統合後の企業価値上昇の恩恵を共有する機会を提供できます。これは友好的なM&Aを進める上で重要な要素です。ただし、自己株式の保有量には発行済株式数の10%を上限とする制約があるため、M&Aの規模によっては現金や新株発行など他の対価手段を併用する必要がある場合があります。
敵対的買収に対する防御策
自己株式の取得は、敵対的買収から会社を守る防御策の一つです。自己株式を取得することで、経営陣や友好的株主の持株比率を高め、買収者の影響力を抑えることが可能です。また、大量取得による株価上昇は買収コストを増大させ、買収意欲を削ぐ効果が期待されます。特に公開買付け(TOB)に対しては、自己株式の公開買付けを実施することで効果的な防御が可能です。
ただし、自己株式取得には法的制約があり、発行済株式数の10%を上限とする規制(会社法第113条)や株主総会での承認が必要です。また、防御策が株主価値の向上に資するものであるか慎重に検討し、経営陣の保身に偏らないよう配慮が求められます。他の防御策と組み合わせることで、より効果的な対応が可能です。
株価低迷の改善と価値向上策
自己株式の取得は、株価対策として広く活用されています。流通株式数が減少することで、1株あたりの利益(EPS)や1株あたりの純資産(BPS)が向上し、株価の上昇が期待できます。
市場での需要増加により、短期的な株価押し上げ効果も見込めます。特に株価が企業の本来価値を下回っている場合、自己株式取得は株主に対する効果的な還元策となります。配当と比較して、株主の選択により利益確定のタイミングを調整できる利点があります。
ただし、自己株式取得による株価上昇効果は一時的である場合が多く、根本的な企業価値向上の取り組みと併せて実施することが重要です。
事業承継における活用と後継者支援
非上場企業の事業承継において、自己株式は重要な役割を果たします。後継者が相続税や贈与税の納税資金を必要とする場合、会社による自己株式取得を通じて株式を現金化し、資金を確保することが可能です。これにより、後継者の財務負担を軽減すると同時に、他の相続人への配慮を行うことで、円滑な事業承継を実現できます。
特に、株式の評価額が高い企業では、自己株式取得による資金調達が事業承継成功の鍵となることがあります。ただし、自己株式取得には会社法に基づく手続きが必要であり、取締役会や株主総会での承認、さらに財源規制(配当可能額の範囲内)を遵守する必要があります。
また、事業承継後の経営体制を安定させるため、分散した株式を会社が集約し、後継者の経営権を確実に確保する手段としても自己株式取得は有効です。ただし、自己株式取得に伴う税務上の影響や、株式評価額の変動リスクについても慎重に検討することが求められます。
持株比率の戦略的調整
自己株式の取得は、特定株主の持株比率を調整する有効な手段です。会社法では、3%(株主提案権)、10%(解散請求権)、33.3%(特別決議阻止権)、50%(普通決議権)、66.6%(特別決議権)といった重要な閾値が定められており、特定株主の持株比率を33.3%未満に抑えれば特別決議を確実に可決できる体制を構築できます。また、50%以上の安定株主を確保することで経営の安定性を向上させることが可能です。
ただし、自己株式取得には発行済株式数の10%を上限とする規制や財源規制が伴い、慎重な運用が求められます。また、特定株主の影響力を抑えることが株主間の関係に影響を与える可能性があるため、計画を十分に検討することが重要です。市場環境や株価への影響も考慮しながら適切に進める必要があります。
自己株式取得のメリット・デメリットと注意点
自己株式の取得には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットやリスクも存在します。企業経営者は、これらの特徴を十分に理解した上で、自社の状況に応じた適切な判断を行う必要があります。
自己株式取得の主要なメリット
自己株式取得は、財務戦略の選択肢を広げる有効な手段です。買収防衛策として活用することで経営の独立性を維持し、株価上昇による株主還元が期待できます。ただし、株価の変動は市場環境に依存するため、必ずしも上昇が保証されるわけではありません。
事業承継では、相続税や贈与税の納税資金調達に役立ち、後継者の負担軽減と円滑な承継を支援します。また、M&Aでは、自己株式を対価として使用することで現金支出を抑え、戦略的な企業買収を実現できます。
ただし、自己株式取得には発行済株式数の10%を上限とする規制や財源規制があるため、法的条件を遵守することが求められます。税務上の取り扱いや株主間の関係への影響も慎重に検討する必要があります。
自己株式取得に伴うデメリットとリスク
自己株式取得の最も大きなデメリットは、資金繰りへの影響です。買い戻しには多額の現金が必要となるため、他の投資機会を逸する可能性や、運転資金不足のリスクが生じます。
処分手続きが煩雑であることも大きな負担となります。取締役会決議や株主総会決議などの法的手続きが必要で、迅速な対応が困難な場合があります。特に上場企業においては、金融商品取引法上の規制も考慮する必要があります。
税務上の負担増加も重要な懸念事項です。みなし配当課税や総合課税による税負担が生じる可能性があり、株主や会社双方にとって予期せぬ税務リスクをもたらすことがあります。これらのリスクを適切に評価し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
非上場企業と上場企業での違い
非上場企業と上場企業では、自己株式取得の目的や考慮事項が異なります。非上場企業では、株式の流動性が低いため、自己株式取得が株主にとって重要な現金化手段となります。ただし、適正な株価設定や公正な取引を行い、株主間の公平性を確保する必要があります。
一方、上場企業では、自己株式取得は株主還元や株価の安定化、投資家との関係強化を目的とします。また、市場環境や株価への影響を考慮した慎重な対応が求められます。
規制面では、上場企業は金融商品取引法の規制を受け、インサイダー取引規制や開示規制に対応する必要があります。一方、非上場企業にはこれらの規制は適用されませんが、特定株主を優遇せず公平性を確保することが重要です。
自己株式の4つの取得方法と具体的な手続き
自己株式の取得方法は、企業の上場・非上場の別や取得の目的によって選択肢が変わります。それぞれの方法には特徴的な手続きや規制があり、適切な方法を選択することで効率的な自己株式取得が可能になります。
市場取引による取得
市場取引による自己株式取得は、上場企業で最も一般的に利用される方法です。証券取引所を通じて自社株を購入するため、手続きが比較的簡単で、迅速な実行が可能です。取締役会決議により取得株式数の上限、取得価額の上限、取得期間を設定すれば実行できます。ただし、インサイダー取引規制や相場操縦規制を遵守し、適切なタイミングでの取得が重要です。
市場取引のメリットは、株主平等の原則が保たれることです。市場価格での取得となるため、特定の株主に有利な条件が生じることはありません。また、取得のタイミングや数量を柔軟に調整できるため、市場環境に応じた戦略的な取得が可能です。ただし、市場価格が急激に変動する場合には計画通りに取得できないリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
市場取引は最も一般的な方法ですが、公開買付け(TOB)や特定株主との合意による取得など、他の方法も場合によっては有効です。企業はそれぞれの方法のメリットとリスクを検討し、規制を遵守しながら適切に運用する必要があります。
公開買付け(TOB)による取得
公開買付け(TOB)は、主に上場企業で利用される取得方法ですが、非上場企業でも活用可能な手段です。あらかじめ取得期間、取得価格、取得予定株式数を公表し、不特定多数の株主から株式を取得する仕組みです。大量の株式を短期間で取得したい場合や、市場価格を上回る価格での取得を行いたい場合に有効です。
TOBは、敵対的買収への防御策としても利用され、市場に対する明確なメッセージを発信する手段となります。ただし、価格設定や条件によって市場や株主に与える影響を慎重に検討する必要があります。また、応募株式数が予想以上に集中した場合、資金不足のリスクがあるため、事前の資金計画が重要です。
TOBの実施には、金融商品取引法による規制が適用され、金融庁への届出書提出や公告、買付期間の設定(20営業日以上)などの手続きが必要です。これらの手続きには時間とコストがかかるため、実施の際には慎重な計画が求められます。
すべての株主からの取得(相対取引)
すべての株主から比例的に自己株式を取得する方法は、主に非上場企業で利用されます。市場を介さずに株主から直接買い取るため、非上場企業でも実行可能であり、株主総会の普通決議に基づいて実施されます。この方法では、すべての株主に平等な買取りの機会を提供し、取得比率を一定に保つことで持株比率を維持できます。
適正な株価設定は重要であり、税理士や公認会計士など専門家による評価を受けることで、公平性を確保し、税務上のリスクを回避できます。ただし、株主が売却に応じない場合や株価設定が不適切な場合にはトラブルが生じる可能性があるため、慎重な対応が求められます。また、会社法に基づき取得の目的や条件を明確にし、株主総会での説明や承認を経て適切な手続きを行うことが必要です。
特定株主からの取得
特定の株主からのみ自己株式を取得する方法は、株主平等の原則への配慮から慎重な手続きが求められます。会社法では、株主総会での特別決議が必要であり、取得対象となる株主以外の株主による3分の2以上の賛成が求められます。さらに、取得に反対する株主には、会社に対して自己の株式を同一条件で買い取るよう請求できる「買取請求権」が付与されます。この権利には期限が設定される場合があり、適切な対応が必要です。
この方法は、事業承継や株主整理において特に有効ですが、手続きの複雑さや他株主への配慮が重要です。取得の目的や条件を明確に説明し、公正な価格設定を行い、株主の理解を得ることが成功の鍵となります。また、買取請求権の行使により、予想以上の資金が必要になる可能性があるため、資金計画を十分に立てる必要があります。
自己株式取得の規制と会計・税務処理
自己株式の取得は、会社法をはじめとする各種法令による規制の対象となっています。また、適切な会計処理と税務処理を行うことで、財務報告の信頼性を確保し、税務リスクを回避することが可能になります。
会社法における財源規制と手続き規制
会社法では、自己株式の取得について厳格な財源規制を設けています。分配可能額の範囲内でのみ取得が可能であり、この制限により会社の財政状態の健全性を保護しています。
分配可能額は「その他資本剰余金+その他利益剰余金」で算定され、この金額を超える自己株式取得は認められません。これにより、債権者の利益を保護し、会社の支払い能力を維持する仕組みが確保されています。
ただし、一部の取得については財源規制の適用外となります。単元未満株式の買取請求、無償取得、他社事業譲受に伴う取得、吸収合併・吸収分割による承継などがこれに該当します。これらの例外規定により、必要な企業再編や株主対応が阻害されることを防いでいます。
取得方法における決議要件と財源規制の関係は以下の通りです。
| 取得方法 | 決議要件 | 財源規制 |
|---|---|---|
| 市場取引 | 取締役会決議 | 適用 |
| 公開買付け(TOB) | 取締役会決議 | 適用 |
| すべての株主から取得 | 株主総会普通決議 | 適用 |
| 特定株主から取得 | 株主総会特別決議 | 適用 |
自己株式の会計処理方法
自己株式の会計処理は、企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」に従って行われます。取得時には、取得原価で「自己株式」勘定に計上し、純資産の控除項目として表示します。基本的な仕訳は、借方に「自己株式(取得原価)」、貸方に「現金預金」を計上します。自己株式は資本取引として扱われるため、損益計算書には影響を与えません。
取得に伴う手数料や諸費用は、営業外費用として損益計算書に計上されますが、企業によって処理方法が異なる場合があります。また、自己株式を処分する際には、処分価額と帳簿価額の差額を資本剰余金または利益剰余金で調整し、原則として損益に計上しません。これにより、資本取引の性質が会計処理に反映されています。
さらに、自己株式を消却する場合は、資本金や資本準備金を減少させる形で処理され、純資産の構成に影響を与えます。適切な会計処理を行い、財務諸表に正確に反映することが求められます。
税務処理における注意点とリスク
税務上、自己株式の取得は原則として会社側に課税関係を生じませんが、時価の2分の1未満の価額で取得した場合には例外があります。このような場合、時価との差額が受贈益として法人税の課税対象となります。
株主側では、利益積立金額からの払戻しがある場合、その部分がみなし配当として総合課税の対象となります。これは、実質的に配当と同様の経済効果があるためです。ただし、市場取引による取得の場合は、みなし配当の規定は適用されません。
非上場企業では、株式の評価額算定が税務上重要になります。適正な価格での取得を行わなければ、税務調査において問題となる可能性があります。 また、事業承継税制の適用を受けている場合は、自己株式取得により適用要件に影響する可能性もあるため、事前の検討が必要です。
金融商品取引法上の規制
上場企業が自己株式を取得する場合、金融商品取引法上の各種規制に注意する必要があります。特に、インサイダー取引規制により、重要事実を知った状態での自己株式取得は禁止されています。
また、相場操縦規制により、株価を人為的に変動させる目的での取得は規制されています。 適切な取得計画の策定と、法令遵守体制の整備により、これらの規制違反を防止することが重要です。
大量の自己株式取得を行う場合は、適時開示規則に基づく開示も必要になります。投資家に対する適切な情報提供により、市場の透明性と公正性を確保することが求められています。
まとめ
自己株式は、M&Aの対価活用から敵対的買収防御、事業承継支援、株価対策まで、企業経営において多様な目的で活用できる重要な手段です。適切に活用することで、企業価値の向上と株主利益の最大化を同時に実現できます。
ただし、自己株式の取得には会社法上の財源規制や複雑な手続き、税務上のリスクが伴います。特に、資金繰りへの影響や法的手続きの煩雑さ、予期せぬ税負担などのデメリットを十分に理解した上で実行することが重要です。
成功する自己株式取得のためには、法務・税務・会計の各分野における専門知識が不可欠であり、適切な専門家のサポートを受けながら進めることをお勧めします。M&Aや事業承継における自己株式の戦略的活用をお考えの経営者の皆様は、ぜひ専門家にご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。