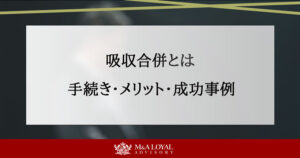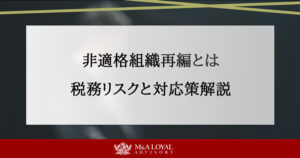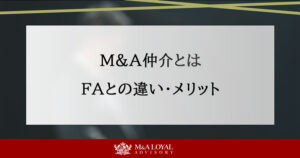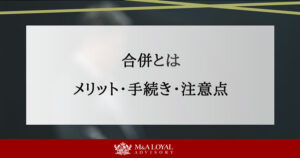新設合併とは?メリットや吸収合併との違い、流れを事例を交えて解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
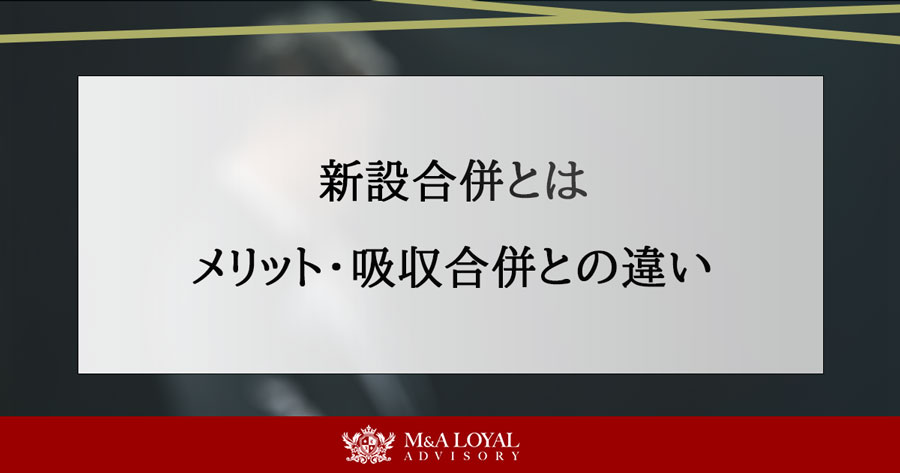
新設合併とは、2社以上の会社が合併する際に、既存の会社を消滅させ新しく会社を設立するM&A手法です。
同じ合併でも吸収合併とはどのような違いがあるでしょうか。また、他のM&A手法とはどのような違いがあるでしょうか。
本記事では、新設合併の特徴やメリット・デメリット、吸収合併との違い、手続き、事例などを詳しく解説します。
目次
新設合併とは
新設合併の基本的な仕組みや法律上の定義、合併と買収の違いについて解説します。
新設合併の定義・目的
新設合併は、M&Aの手法である「合併」のうちのひとつです。合併に関与する全ての会社が消滅し、新たに設立される会社に全ての権利義務を承継させる会社設立の手法です。
対等な立場での統合を図りたい場合や、新しいブランドや体制の基で経営を再スタートしたい場合に適しています。
合併には「吸収合併」と「新設合併」の2種類がありますが、新設合併は吸収合併と比較して手続きや費用の負担が大きく、実務上では新設合併が選択されることはほとんどありません。
新設合併の法律上の定義
新設合併については、会社法にて次のとおり定義されています。
「第二条(定義)二十八 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう」
会社法第2条は、会社法において使われる用語の定義を規定する条文で、他にもさまざまな用語が定義されています。
合併と買収の違い
合併と買収はどちらもM&Aの手法のひとつです。「合併」は企業同士がひとつに統合する手法であり、「買収」は企業の経営権を取得する形です。
なお、M&Aとは、資本提携のうち、経営権(支配権)の移動が伴うものを指し、広義では資本提携全般を含むこともあります。一方、資本の移動を伴わない提携は「業務提携」と呼ばれます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



新設合併と吸収合併の違い
新設合併と吸収合併の違いは次のとおりです。
- 消滅会社・存続会社
- 免許・許認可の承継
- 株主が受け取ることのできる対価の種類
それぞれ解説します。
消滅会社・存続会社について
新設合併では、関係する全ての会社が消滅し、新たに設立される会社がその権利義務を引き継ぎます。つまり、元の会社はいずれも法人格を失い、全く新しい法人が誕生するという特徴を持ちます。
一方、吸収合併では、一方の会社(存続会社)がそのまま法人格を維持し、他方の会社(消滅会社)の人材・技術・権利義務を全て引き継ぎます。存続会社はそのまま継続する一方で、消滅会社のみが法人格を失います。
このように、新設合併では全社が消滅するのに対し、吸収合併では存続会社が明確に存在し続ける点が大きな違いです。
免許・許認可の承継
新設合併と吸収合併では、免許・許認可や上場の取り扱いに明確な違いがあります。
新設合併では、関係会社全てが消滅し新会社を設立するため、これまでの免許・許認可は引き継がれません。
例えば、運送業の「一般貨物自動車運送事業許可」や、酒類販売・食品衛生に関する許可も、新会社として再取得が必要です。また、法人格が新たになるため、既存の上場も引き継げず、新会社として改めて上場申請を行う必要があります。
一方、吸収合併では、存続会社が法人格を維持するため、消滅会社の免許・許認可を基本的に承継できます。これにより、合併後も事業継続がスムーズに行えます。存続会社が上場企業であれば、引き続きその上場資格を維持できます。
このように、事業継続や上場維持の面では吸収合併の方が柔軟性が高いといえます。
株主が受け取ることのできる対価の種類
新設合併では、全ての会社が消滅し新会社が設立されるため、現金を対価とすると新会社の株主が存在しなくなるという問題が生じます。そのため、現金を対価とすることは認められておらず、原則として新会社の株式を対価として交付することが定められています。
一方、吸収合併では、消滅会社の株主に対して合併の対価として株式・社債・現金などを柔軟に選択できます。現金を対価とすることで、株主の意向に沿った対応がしやすくなります。
吸収合併における簡易合併と略式合併とは?
吸収合併には、株主総会の承認を省略できる「簡易合併」と「略式合併」の2つの特例制度があります。いずれも、条件を満たせば手続きを簡略化でき、合併をスムーズに進めることが可能です。
簡易合併は、存続会社が交付する合併対価が自社の純資産の5分の1以下である場合に、存続会社の株主総会を省略できる制度です。小規模な合併に適用され、支配関係の有無にかかわらず利用できます。
略式合併は、存続会社が消滅会社の議決権の90%以上を保有している場合に、消滅会社の株主総会を省略できる制度です。親子会社など、支配関係のある企業同士の合併で活用されます。
新設合併に似た他のM&A手法
新設合併に近い他のM&A手法についても解説します。
新設分割
新設分割も新たな会社を設立する組織再編の手法ですが、その目的や方向性は新設合併と全く異なります。
新設分割は、ひとつの会社が新たに設立した会社に対して、自社の一部または全部の事業・資産・負債を承継させる手続きです。つまり、1社から新たな会社を生み出す「分離型」の再編であり、特定事業の切り出しや分社化、将来的な上場準備などに活用されます。
新設合併は「複数の会社が1社になる」再編、新設分割は「1社が複数に分かれる」再編という点で、根本的な方向性が正反対であることが最大の違いです。
株式移転
株式移転は、1社または複数の会社が自社の全株式を新たに設立する親会社に移し、その傘下に入ることで完全子会社となる「持株会社型」の再編です。元の会社は存続したまま、企業グループとしての統合や再編を実現できます。段階的な再編や、各社の独立性を維持しながらの統合に適しています。
株式移転は「株式を通じて支配関係を構築する」再編であり、新設合併は「会社そのものを統合する」再編です。
新設合併のメリット
新設合併によるメリットは次のとおりです。
- 統合による規模拡大やシナジー効果が期待できる
- 対等合併の印象を与えられる
- 買収資金の準備が必要ない
- 事業承継問題の解決につながる
- 場合によっては節税にもなる
それぞれ詳しく解説します。
統合によるシナジー効果が期待できる
新設合併は、事業や経営機能をひとつの新しい企業に統合する手法であるため、それぞれの強みや経営資源を集約できます。業務の効率化やノウハウの共有、意思決定の一元化が可能となり、シナジー効果が大いに期待されます。
さらに、企業規模の拡大によって仕入れの共通化や大量生産が実現し、コスト削減や競争力の向上といったメリットも生まれます。販売ルートの拡充や営業エリアの拡大によって市場への影響力が増し、新規事業への参入など、さらなる成長機会が広がります。
対等合併の印象を与えられる
吸収合併は存続会社が明確なため、たとえ対等とされても上下関係が意識されやすく、関係者に不平等な印象を与えることがあります。
一方、新設合併は全ての会社が消滅し、新たな法人を設立するため、対等な立場での統合という印象を与えやすい点が特徴です。従業員にも受け入れられやすく、不満や抵抗感が生じにくいため、心機一転しやすい再編手法としても有効です。
買収資金の準備が必要ない
新設合併に限らず、合併は現金を使わずに実施できる点が大きなメリットです。新設合併や吸収合併では、株主への対価として株式や社債を活用できるため、資金調達が不要です。
十分な現金がない企業や、金融機関からの借り入れを避けたい企業にとって、資金負担の少ないM&A手法として有効です。
事業承継問題の解決につながる
新設合併は、事業承継の課題を解決する手段としても有効です。
特に日本では、中小企業の多くが後継者不足に直面しており、将来の事業継続に不安を抱えています。
新設合併を通じて他社と統合することで、経営資源を引き継ぎながら新たな法人として再出発でき、従業員や取引先との関係も維持しやすくなります。これにより、スムーズな事業承継が実現しやすくなります。
場合によっては節税にもなる
新設合併は、状況によっては節税効果も期待できます。
例えば、赤字事業を抱える会社と合併することで、その会社の繰越欠損金を活用できる場合があります。
これにより、合併後の会社が得た利益と相殺し、課税所得を抑えることができるため、結果的に法人税の負担を軽減できる可能性があります。
新設合併のデメリット
新設合併よりも吸収合併が多く行われていることからも分かるように、新設合併にはデメリットも多く存在します。
- 手続きや費用の負担が大きい
- 免許や許認可の引き継ぎができない
- 統合後の負担が大きい
- 対価に現金を選択できない
- 従業員の理解を得にくい可能性も
それぞれ詳しく解説します。
手続きや費用の負担が大きい
新設合併は、新たに会社を設立する必要があるため、吸収合併と比べて手続きが複雑で煩雑になりやすい傾向があります。
消滅会社の解散・清算登記に加え、就業規則や労務制度のすり合わせといった社内調整も多く、実務面での労力は相当なものとなります。
また、費用面でも大きな負担が伴います。定款認証や登録免許税、資本金の準備など、新会社設立に必要な最低限のコストだけでも20万〜30万円以上が見込まれ、専門家へ依頼すればさらに高額になります。
特に注意すべきは登録免許税です。新会社の資本金全体に対して0.15%が課税されるため、吸収合併に比べて課税対象が広がり、結果としてコストがかさむケースも多いです。
免許や許認可の引き継ぎができない
吸収合併では消滅会社の免許や許認可を存続会社が引き継ぐことが可能ですが、新設合併ではこれが認められていません。
新会社が新たに設立される扱いとなるため、事業に必要な免許や許認可は全て再取得が必要です。
場合によっては、許認可の再取得に加え、上場企業であれば上場の再申請が求められることもあり、手続きには相応の手間と時間を要します。
統合後の負担が大きい
統合後の負担が大きいことも、新設合併の大きなデメリットです。
吸収合併では存続会社の仕組みを引き継ぐことができますが、新設合併では統合後のシステムやルールをいちから整備する必要があります。加えて、異なる企業文化の調整も求められ、PMI(統合後の管理)の計画と実行が不可欠です。
準備が不十分だと、現場の混乱や人材流出のリスクが高まるため、合併前からの綿密な対応が重要です。
対価に現金を選択できない
新設合併では、株式や社債が主な対価となり、対価に現金を選ぶことができません。そのため、現金化を望む株主にとっては不利であり、特に未上場の新設会社の場合は、株式を売却することが難しくなります。
このような事情から、株主の反対により新設合併が頓挫するケースもあります。
従業員の理解を得にくい可能性も
新設合併では、社名・社風・ルールなどが大きく変わることが多く、職場環境や賃金体系の見直しが発生する場合もあります。
こうした変化に対して、従業員が不安や戸惑いを感じることがあり、反発や離職につながるリスクもあります。
新設合併の手続き・流れ
新設合併を実施するにあたっての全体的な流れや手続きは次のとおりです。
- 準備期間
- 取締役会の承認など
- 合併契約の締結
- 事前開示
- 債権者への催告など
- 株主への通知、株主総会特別決議
- 反対株主の買取請求手続き
- 合併効力発生
- 登記手続き
- 事後開示
それぞれを順番に解説します。
準備期間
まずは、消滅する会社が、債権者の確認や契約書の内容精査といった準備期間から始まります。
併せて、デューデリジェンスやバリュエーションの実施など、合併に必要な各種手続きも進める必要があります。
会社の設立手続きや債権者保護手続きには相応の時間を要するため、スケジュールには十分な余裕を持たせ、準備作業をできるだけ円滑に進めることが重要です。
取締役会の承認など
新設合併では、まず「新設合併契約書」を締結する必要があり、これが重要な初期段階です。
契約書には、次のような会社法で定められた必須項目を記載します(会社法第753条)。
- 消滅会社の商号・住所
- 新設会社の商号・目的・本店所在地・発行可能株式総数
- 新設会社の設立時の取締役氏名
- その他役員などの氏名あるいは名称
- 合併対価の内容と株式の割当方法
- 消滅する会社の株主などへ交付する対価の事項
- 消滅する会社の株主に対する株式割り当ての事項
- 新株予約権あるいは金銭に関する事項
契約締結後は、取締役会での承認決議を行い、合併条件に問題がないか確認した上で、正式に新設合併を進めていきます。
事前開示
新設合併を行う際、新設合併契約の内容や法務省令で決められている事項を記載あるいは記録した書面を本店に備え置く義務があります。
この事前開示書類は、株主が合併の内容を判断するための重要資料となるため「株主総会開催日の2週間前」または「通知・公告を行う日」のいずれか早い日までに準備しなければなりません。
記載内容には次の内容が含まれます。
- 新設会社の資本金・資本準備金
- 計算書類の概要
- 合併対価の相当性に関する事項
- 合併対価に関する参考情報
- 新設会社の債務履行見込みに関する事項
これらの情報は、株主への説明責任を果たす上で重要であり、法定の期限までに漏れなく整備しておくことが求められます。
債権者への催告など
消滅会社の債権者保護のための手続きも必須です。合併によって債権がリスクにさらされる可能性があるため、債権者に対して事前に通知・公告を行い、異議申立ての機会を与える必要があります。
具体的には、官報による公告と、会社が把握している債権者への個別催告を行います。債権者から異議があった場合は、弁済や担保の提供などの対応が求められます。
なお、定款で電子公告や日刊紙への公告が定められている場合は、官報と合わせた公告を行うことで個別催告を省略できるケースもあります。
株主への通知、株主総会特別決議
新設合併には、株主総会での特別決議が必要です。
株主総会の開催に際しては、原則として開催日の1週間前(公開会社は2週間前)までに招集通知を送る必要があります。通知方法は書面の他、株主の同意があれば電子的方法も可能です。なお、全株主の同意があれば通知は省略できます。
特別決議では、議決権の過半数が出席し、そのうち3分の2以上の賛成が必要です。この条件を満たさなければ、新設合併は実行できません。
また、合併効力発生日の20日前までに、新設合併を行う旨の通知または公告を行う必要があります。これらは招集通知や公告と併せて実施することも可能ですが、反対株主への対応も忘れずに行うことが重要です。
反対株主の買取請求手続き
消滅会社の株主が合併に反対する場合、自らが保有する株式について、会社に対して公正な金額での買取を請求できます(会社法806条)。
この制度は、合併によって不利益を被る恐れのある株主の権利を保護するために設けられています。
会社はこの請求に対し、新設会社の成立日から原則60日以内に、株価の決定と対価の支払いを行う義務があります。
新設合併の登記申請・合併効力発生
新設合併の効力は、新会社の設立登記日に発生します(会社法第754条)。この日に、消滅会社の権利義務は全て新設会社に承継され、新株予約権も効力を失います。
消滅会社の解散登記と新設会社の設立登記を同時に行う必要があり、効力発生日から2週間以内に登記申請を行うことが義務付けられています。
登記申請に必要な主な書類は次のとおりです。
- 新設合併契約書
- 変更登記申請書
- 債権者保護手続関係書類
- 合併に関する株主総会議事録
- 株券提供公告の証明書
- 資本金の計上証明書
- 被合併会社の登記事項証明書
- 株主の氏名・住所・議決権数の証明書
- 登録免許税に関する証明書
これらの必要書類を整えた上で適切に登記申請を行うことにより、新設合併の法的効力が正式に発生します。
事後開示
合併の効力発生日以後、遅滞なく所定の事項を記載した書面などを作成し、効力発生日から6カ月間、本店に備え置く義務があります。これにより、利害関係者が手続きを確認できるようにします。
備置すべき事後開示書類の主な内容は次のとおりです。
- 合併の効力発生日
- 消滅会社における法定手続きの状況
- 新設会社の変更登記日
- 承継した権利義務の概要
- 適格合併か非適格合併かの区分
この備置をもって、新設合併に関する一連の手続きが完了します。
適格合併と不適格合併とは?
会社合併は税法上の一定の要件を満たすことで次の合併に分けられます。
- 適格合併
- 非適格合併
それぞれについて解説します。
適格合併
適格新設合併とは、合併後も企業グループや事業の実質的な継続性が維持される場合に、一定の要件を満たすことで税務上の優遇措置を受けられる合併形態です。
要件を満たすと、資産は帳簿価額で引き継がれ、含み益への課税や繰越欠損金の消失が繰り延べられるという税務上のメリットがあります。
主にグループ内再編や業務提携の強化を目的とする合併で活用されます。
非適格合併
非適格合併は、適格合併の要件を満たさない合併で、資産を時価で評価して引き継ぐため、合併時点で含み益・含み損が課税対象となります。
非適格合併の方が有利となるケースもあり、M&Aなどで戦略的に選択されることがあります。ただし、含み益が課税対象になるなど、税務負担が増加するリスクもあるため、慎重な判断が必要です。
新設合併を成功させるためのポイント
新設合併を成功させるために抑えるべきポイントは次のとおりです。
- 事前のデューデリジェンスをしっかり行う
- 組織文化の統合と人材マネジメント
- 法務・税務の専門家の活用
事前のデューデリジェンスをしっかり行う
新設合併を成功させるには、事前のデューデリジェンス(詳細調査)が不可欠です。
デューデリジェンスとは、対象企業の財務・法務・税務などについて、専門家が多角的に調査・分析を行うプロセスです。
財務諸表の確認に加え、契約関係や潜在的な法的リスクの洗い出しも含まれており、合併後のトラブルや損失を未然に防ぐために重要な役割を果たします。
新設合併は、複数の企業が一体化して新たな法人を設立する形態であり、統合の成功は慎重な事前準備にかかっています。特に、合併相手の財務状況や経営方針、企業文化を十分に理解し、「本当にこの企業と合併して良いのか?」という視点で徹底的に検討することが重要です。
デューデリジェンスを基に、企業価値や株式価値を詳細に評価することで、公正な合併比率や新株の交付条件を適切に設定することが可能です。これにより、合併後の株主間で公平な権利分配が実現されるとともに、合併条件に関する不透明性が減少します。
その結果、合併比率や交付条件をめぐる紛争リスクを事前に回避することが可能となり、企業間の円滑な統合が促進されます。なお、デューデリジェンスの範囲には財務、法務、税務、人事、知的財産など多岐にわたる項目が含まれます。
リスクの見落としは後の混乱や損失に直結するため、戦略的適合性やデューデリジェンスの徹底が欠かせません。
組織文化の統合と人材マネジメント
新設合併を成功させるには、組織文化の統合と人材マネジメントも必要不可欠です。
異なる企業文化を持つ組織が一体となる新設合併では、従業員同士の摩擦を防ぐための文化的な融合が重要です。チームビルディングや対話の機会を設け、不安を軽減し、新しい環境に適応できるよう支援することが求められます。
法務・税務の専門家の活用
新設合併を成功させるには、法務・税務の専門家を活用しましょう。
合併には複雑な手続きや税務上のリスクが伴うため、弁護士や税理士の助言を受けることで、契約や手続きの不備を防ぎ、リスクを最小限に抑えられます。
専門家の支援があることで、合併のプロセスを円滑かつ安心して進められます。
新設合併に関する相談先
新設合併を検討する際の主な相談先は次のとおりです。
- 公認会計士・税理士
それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。
公認会計士・税理士
新設合併の相談先として公認会計士や税理士を選ぶと、企業価値の算定や財務調査、税務対策といった専門的な支援が受けられます。会計や財務の知識が豊富なため、リスクの見落としを防ぎつつ、手続きを円滑に進められる点が大きなメリットです。
特に既に顧問契約がある場合は、自社の状況を把握しているため相談がスムーズに行えます。
ただし、全ての会計士・税理士がM&Aに精通しているわけではなく、買い手・売り手の探索や法務面の支援などには対応できない場合がある点には注意が必要です。
M&A仲介会社
M&A仲介会社に相談することで、売り手と買い手の間に立ち、中立的な立場からM&Aの全工程をサポートしてもらえます。初期の相談から条件交渉、契約締結、クロージングまで一貫した支援が受けられるため、M&Aに不慣れな企業でも安心して進められる点が大きな特徴です。
M&A仲介会社独自のネットワークを活用してマッチング先を探せる強みがあり、業界動向や相場に精通しています。また、アドバイザリー形式で売り手・買い手いずれかに専属でサポートする形態もあります。
ただし、M&A仲介会社の報酬には費用がかかります。成功報酬は売却金額の5%前後が相場とされていますが、レーマン方式を採用している会社が多いです。
最低報酬額を定めている会社もあり、小規模なM&Aでも高額な費用が発生する可能性があることや、複数の買い手候補に情報を提供する過程で、情報漏えいのリスクが伴う点にも注意が必要です。
新設合併の事例8選
新設合併が行われた事例をいくつか紹介します。
三越
2003年9月、百貨店の三越は、名古屋三越・千葉三越・鹿児島三越・福岡三越の4つの連結子会社と新設合併を実施し、5社全てが解散・消滅し、新たに「三越」を設立しました。
当時は消費の低迷が長期化し、グループ各社の経営が厳しい状況にありました。そこで三越は、収益力の強化と財務基盤の安定化を図る抜本的な経営再編として、新設合併を選択しました。
この合併により、旧「三越」を含む5社の株式は上場廃止となりましたが、新会社は旧社名を引き継ぎ、主要五つの証券取引所へ上場申請を行い、合併直後に新規上場を果たしています。
JR東海リテイリング・プラス
2023年4月、JR東海はサービス向上を目的に、完全子会社の東海キヨスクとジェイアール東海パッセンジャーズを合併すると発表しました。
東海キヨスクは駅構内での小売業(飲食物・土産・書籍など)、ジェイアール東海パッセンジャーズは新幹線の車内販売や駅弁製造・飲食店運営を手がけており、合併によって駅構内事業を統合・効率化し、商品やサービスをワンストップで提供できる体制を目指します。
今後は、多様なニーズに応える商品展開に加え、地域性や食品製造の強みを生かして、駅の魅力向上を図る方針です。
野村不動産マスターファンド投資法人
2015年10月、野村不動産マスターファンド投資法人は、野村不動産オフィスファンド投資法人および野村不動産レジデンシャル投資法人と新設合併を行い、新・野村不動産マスターファンド投資法人として再スタートしました。
当時、REIT市場(不動産投資信託市場)は拡大期にあり、年金資金の活用や個人投資家の参入が進む中で、特化型REITから総合型REITへの転換が必要と判断されたことが、合併の大きな背景です。
この新設合併により、不動産ポートフォリオの規模拡大と安定化が実現し、オフィス資産を中核としつつ、野村不動産グループとのバリューチェーン強化による相互成長の体制が整いました。
富士ゼロックス
2010年1月、富士ゼロックスはグループ内の再編を目的に、新設合併を実施しました。新会社「富士ゼロックスマニュファクチュアリング」を設立し、富士ゼロックスイメージングマテリアルズ、鈴鹿富士ゼロックス、新潟富士ゼロックス製造、富士ゼロックス竹松工場の各拠点を統合しています。
この新設合併により、分散していた製造機能の集約や業務の効率化を図るとともに、優秀なエンジニアの補強によって技術力と生産力の強化を実現しました。
グループ内の完全子会社同士による再編であることから、税制上の適格合併に該当する可能性が高く、税務負担を抑えつつスムーズな統合が進められたと考えられます。
東洋製罐グループホールディングス
東洋製罐グループホールディングスは、2013年11月にタイにある子会社3社(Well Pack Innovation、Toyo Pack International、Toyo Seikan (Thailand))を新設合併し、新たな子会社を設立しました。
海外拠点を統合することで、現地の生産体制を集約し、コスト削減と品質管理の一元化を実現を目指したとみられます。
北越コーポレーション(旧北越紀州製紙)
北越コーポレーション(旧・北越紀州製紙)は、2016年7月1日にカナダの連結子会社Alpac Forest Products Inc.(AFPI)とその子会社であるAlberta Pacific Forest Industries Inc.(APFI)、Alpac Pulp Sales Inc.(APSI)の3社を現地法に基づく新設合併により統合し、新会社「Alberta Pacific Forest Industries Inc.」を設立しました。
この新設合併は、パルプの製造から販売までのビジネスプロセスを垂直統合し、市販パルプ事業における国際競争力の強化、事業効率の向上、コーポレートガバナンスの強化を目的としたものです。
中核であるAFPIは、カナダ・アルバータ州政府から付与された広大な森林資源を背景に、北米最大級の市販パルプ工場を運営しており、この統合によってグループ全体の競争力をさらに高める狙いがあります。
山之内製薬と藤沢薬品工業の新設合併
2005年4月、山之内製薬と藤沢薬品工業が合併し、アステラス製薬が発足しました。背景には、医薬品の開発費高騰と業界再編の加速があり、競争力強化を目的とした統合です。
合併比率は山之内製薬1に対し藤沢薬品0.71で、山之内に有利な条件でしたが、取締役は両社から均等に選出され、対等合併の形をとりました。
この合併は、国内製薬業界再編の先駆けとされています。
鹿児島みらい農業協同組合
鹿児島みらい農業協同組合(JA鹿児島みらい)は、2018年3月にJAグリーン鹿児島・JAかごしま中央・JA東部の3組合が新設合併して誕生しました。
農協の広域合併は、国の方針やJA全体の推進によって進められており、経営効率の向上やスケールメリットが期待できるため、今後も再編が進むと見られています。
ウェブライフ
2022年4月にデジタルステージは、ウェブライフジャパンおよびクリプトメリアと新設合併し、新会社「ウェブライフ」としてスタートしました。3社は元々同じ資本傘下にあり、それぞれがCMS、ECプラットフォーム、ウェブ制作・CG映像制作といった専門分野に特化して運営されていました。
今回の新設合併は、今後の発展や技術開発、クリエイティビティの追求を見据え、分散していた経営資源を統合し、効率化と事業拡大を図ることが目的です。
合併により、各社の強みを融合したことで、新たなサービスや価値あるユーザー体験の創出が期待されています。
新設合併に関するQ&A
最後に、新設合併に関するよくある質問とその回答を紹介します。
新設合併後の株式の扱いはどうなるか
新設合併後の株式の扱いでは、旧会社の株式は全て消滅し、新たに設立される会社が新株式を発行します。
この新株式は、合併前の各会社の株主に対し、持分に応じた割合で割り当てられ、株主は引き続き新会社の所有権を保有する形になります。
新設合併後は、通常、合併比率や新株割当条件が調整されることで、株主の経済的持分価値が合併前後で大きく変わらないよう配慮されます。
その結果、株主にとっての経済的価値や事業の継続性が保たれる仕組みとなっています。ただし、新設会社の設立に伴い、形式的には法人格が変更される点に留意が必要です。
新設合併における従業員の処遇はどうなるか
新設合併における従業員の処遇は、組織統合の成否を左右する重要な要素です。
合併により新会社が設立されると、従業員の配置転換や職務内容の変更が行われることがあります。これに伴い、新しいスキルを身につけるチャンスが生まれる一方で、環境の変化に不安を感じるケースも少なくありません。
そのため、従業員のモチベーションを保ち、不安を和らげるための丁寧な説明や支援策が欠かせません。処遇の透明性を確保し、納得感のある対応を行うことが、新設合併を円滑に進める鍵といえます。
新設合併と事業承継の関係とは
新設合併は、事業承継の一手段として活用されることがあります。
特に家族経営や中小企業では、次世代への円滑な事業承継を目的に、新設合併が検討されることがあります。複数の関係会社を統合し、新会社に一体化することで、経営体制を整理しやすくなるためです。
ただし、新設合併では旧株主が新会社の株主として残るため、経営権を完全に次世代に移したい場合には不向きな側面もあります。このため、一般的な事業承継では株式譲渡や事業譲渡など他の手法が選ばれることが多いです。
まとめ
新設合併は、企業の成長戦略の選択肢の一つです。このプロセスを通じて、新たな企業を設立し、それに複数の企業が合併することで、効率的な資源の統合や競争力の強化を図ることができます。この記事では、新設合併の特徴やメリット・デメリット、そして吸収合併との違いについて詳しく解説しました。
企業の将来ビジョンに最適な合併方法を選択し、計画を立てることで、ビジネスを新たなステージへと導くことができるでしょう。M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。