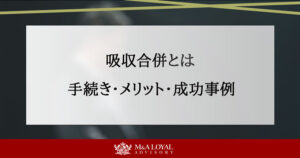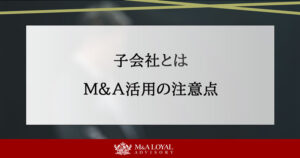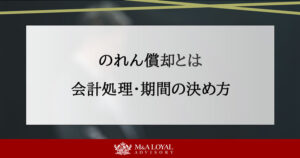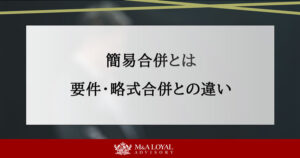吸収合併における会計処理・仕訳方法をケース別にM&A専門家が解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
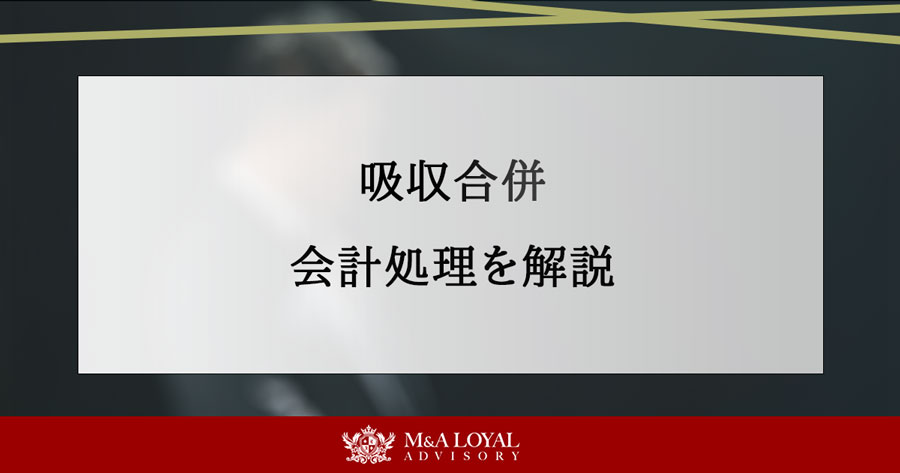
吸収合併は、企業の再編や成長戦略の鍵となる一方で、会計や税務の処理が非常に複雑です。特に、「取得」か「逆取得」かといった分類や、親子会社間・子会社同士・共同支配企業の合併など、ケースごとに会計処理や仕訳方法が大きく異なるため、実務では慎重な判断が求められます。
本記事では、吸収合併の基本から、パターン別の会計処理・仕訳例、そして見落としがちな税務上の注意点までを分かりやすく解説します。
目次
合併における仕訳とは
合併における仕訳に関する基本的な知識について解説します。
合併の仕訳は複雑になりやすい
合併は複数の会社を一つにまとめる組織再編の手法ですが、合併時の仕訳は、通常の取引とは異なり、複数の会社の資産や負債などを統合する必要があります。そのため、非常に複雑な処理になる点が特徴です。
なお、合併は「吸収合併」と「新設合併」に大別されますが、実務では吸収合併が主流です。
これは、新設合併が、全ての会社を解散させて新たに会社を設立するため、手続きが煩雑で税負担が増える傾向があるためです。また、新設合併では、新会社設立時の仕訳に準じるため、本記事では吸収合併に焦点を当てて解説します。
吸収合併とは
吸収合併とは、既存の会社が他の会社を吸収し、一つの会社となる合併形態です。吸収される会社(消滅会社)は解散し、その権利義務の全てが吸収する会社(存続会社)に引き継がれます。
実務においては、株主総会での承認や人事制度の検討、従業員の社会保険の手続きなど、多岐にわたる対応が必要です。会計処理もその一つであり、経理担当者は合併のポイントを理解した上で対応を進める必要があります。
会計処理においては、原則として「パーチェス法」が適用され、消滅会社の資産・負債は時価で評価されて存続会社の帳簿に反映されます。
パーチェス法とは
パーチェス法とは、M&Aなどの企業結合において、一方の企業が他方の企業を実質的に取得したとみなされる場合に適用される会計処理の方法です。
この方法の基本的な考え方は、買収する側(取得企業)が、買収される側(被取得企業)の資産や負債を、まるで自らが購入したかのように扱う点にあります。具体的には、買い手企業が支払った対価(株式や現金、負債)の合計額を「取得原価」として計上します。次に、売り手企業が保有する資産と負債を市場価格(公正価値)で評価し、これらを取得企業の帳簿に記録します。
そして、識別可能な資産・負債の時価純額と取得原価との差額を「のれん」として認識します。取得原価が時価純額を上回る場合は「正ののれん」、下回る場合は「負ののれん」とされます。
取得企業と被取得企業とは
合併における仕訳や会計処理を行う上で重要な概念が「取得企業」と「被取得企業」の区別です。
通常は存続会社が取得企業、消滅会社が被取得企業とされます。ただし、取得企業と被取得企業の判定は形式的な存続・消滅にかかわらず、次の要素を総合的に勘案して行われます。
- 総体としての株主が占める相対的な議決権比率の大きさ
- 最も大きな議決権比率を有する株主の存在
- 取締役などを選解任できる株主の存在
- 取締役会などの構成
- 株式の交換条件
なお、これらの基準に基づいて判定した結果、存続会社が会計上の被取得企業とみなされるケースは「逆取得」として会計処理されます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



吸収合併における会計上の分類
吸収合併における会計処理は、支配の移転有無に応じて「取得とみなされる吸収合併」と「共通支配下の取引」に分類できます。
取得とみなされる吸収合併
吸収合併において、実質的な支配関係の変動が生じる場合には「取得」として会計処理されます。
中でも、存続会社が支配権を取得する「通常取得」と、表面的な形式と異なり消滅会社側が実質的な支配権を握る「逆取得」という2つの形態に大別できます。
通常取得
「通常取得」とは、存続会社が取得企業となる一般的な合併の形です。消滅会社を被取得企業として資産や負債を引き継ぎ、その対価と純資産時価との差額をのれんとして計上します。
合併対価として新株の発行や、既存の株の引き渡しを行います。
逆取得
逆取得とは、法律上の存続会社が会計上は被取得企業として扱われ、法律上の消滅会社が実質的な取得企業となる、特殊な企業結合の形態です。
例えば、形式上はA社がB社を吸収合併しているにもかかわらず、合併後にB社側の株主がA社の議決権の過半数を保有し、支配権を握る場合、A社は会計上「被取得企業」、B社は「取得企業」として扱われます。これは、存続会社の支配が実質的に消滅会社側へ移転することを意味します。
このような逆取得が発生する典型的な例として、「逆さ合併」が挙げられます。逆さ合併とは、吸収合併において規模の小さい会社が存続会社となり、規模の大きい会社が消滅会社となるケースを指します。通常は大規模な企業が存続会社となるため、逆さ合併は例外的な形態とされます。
また、特別目的会社(SPC)との合併において、SPC(親会社)が消滅会社となる場合も、逆さ合併に該当します。こうした合併は、M&Aや再編スキームの一環として用いられることがありますが、実質的な支配関係の変動により逆取得として会計処理される点に注意が必要です。
共通支配下の取引
共通支配下の取引とは、企業結合の前後を通じて、関係当事会社がいずれも同一の支配主体によって継続的に支配されており、その支配が一時的でない場合に該当します。
吸収合併がこの要件を満たすときは、共通支配下の取引として会計処理されます。
親会社による子会社の吸収合併
親会社が子会社を吸収合併するケースは、グループ会社間の再編として行われることが多いです。
親会社が完全子会社(株式を100%保有している子会社)を吸収合併するケースでは、親会社は既に子会社株式を全て保有しているため、合併対価として新株を発行する必要がない「無対価合併」となることが一般的です。
一方、子会社に非支配株主が存在する場合は、その持分への対価として株式などを交付する必要があり、会計処理が異なります。
子会社同士の合併
子会社同士の合併も、通常は最終的に同一の親会社によって支配されているため、「共通支配下の取引」として扱われます。
この場合、合併前に最終決算を実施し、資産と負債の帳簿価額を確定します。
吸収合併における会計処理と仕訳パターン
吸収合併における会計処理と仕訳は、前述の会計上の分類に沿って、実務で特に重要となる次の四つのケースに分けて整理できます。
- 通常取得
- 逆取得
- 親会社による完全子会社の吸収合併
- 親会社による子会社の吸収合併(非支配株主が存在するケース)
これらの類型それぞれについて、存続会社・消滅会社・各株主の立場別に、会計処理のポイントと仕訳例を具体的に解説します。
通常取得
存続会社の会計処理と仕訳
存続会社(取得企業)の会計処理では、まず、支払った対価(新株発行や現金など)の時価を「取得対価」として算定します。次に、消滅会社(被取得企業)の資産・負債を、合併時点の時価で受け入れます。
最後に、引き継いだ純資産の時価と取得対価との差額を「のれん」または「負ののれん」として計上します。取得対価が純資産時価より多い場合は「のれん」(無形資産の価値)、少ない場合は「負ののれん」(将来リスクや安価での取得)とされます。
A社がB社を吸収合併し、B社の資産(現金2,000,000円、売掛金3,000,000円)および借入金(1,000,000円)を時価で引き継ぎ、対価として6,000,000円相当のA社株式を発行した場合、A社の仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金 | 2,000,000 | 借入金 | 1,000,000 |
| 売掛金 | 3,000,000 | 資本金 | 6,000,000 |
| のれん | 2,000,000 | ||
なお、対価として3,000,000円相当のA社株式を発行し、負ののれんが発生した場合の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金 | 2,000,000 | 借入金 | 1,000,000 |
| 売掛金 | 3,000,000 | 資本金 | 3,000,000 |
| 負ののれん | 1,000,000 | ||
消滅会社の会計処理と仕訳
消滅会社(被取得企業)は吸収合併により解散するため、合併前日を最終日として会計処理を行います。その際、時価評価ではなく、適正な会計処理によって算定された簿価で資産・負債を処理します。
また、最終的な帳簿残高をゼロにするため、全ての資産・負債・純資産を帳簿から消去する仕訳が必要です。
なお、合併対価として受け取った株式がある場合は、それを計上し、純資産との差額を「合併差益」または「合併差損」として処理します。
A社がB社を吸収合併し、B社の資産(現金・預金2,000,000円、売掛金3,000,000円)および借入金(1,000,000円)を時価で引き継ぐケースを考えます。このとき、対価として6,000,000円相当のA社株式が発行された場合、B社の仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 借入金 | 1,000,000 | 現金・預金 | 2,000,000 |
| A社株式 | 6,000,000 | 売掛金 | 3,000,000 |
| 合併差益 | 2,000,000 | ||
なお、対価として3,000,000円相当のA社株式が発行され、負ののれんが発生した場合の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 借入金 | 1,000,000 | 現金・預金 | 2,000,000 |
| A社株式 | 3,000,000 | 売掛金 | 3,000,000 |
| 合併差損 | 1,000,000 | ||
存続会社株主の会計処理と仕訳
存続会社(取得企業)の株主は、合併によって直接的な取引を行わないため、基本的に会計処理を行う必要はありません。仕訳も不要です。
ただし、合併により保有する存続会社の株式価値が変動する可能性はあります。その場合、株主は自身の保有する株式を時価評価し、その結果に基づいた処理が必要になることがあります。
評価差額は、株主における株式の保有区分(例えば、売買目的有価証券やその他有価証券など)に応じて会計処理が行われます。
消滅会社株主の会計処理と仕訳
消滅会社(被取得企業)の株主は、保有していた消滅会社の株式と引き換えに、存続会社の株式や現金などの合併対価を受け取ります。この取引は、株主にとって株式の譲渡とみなされ、税務上の適格合併か非適格合併かによって、課税額などが大きく異なります。
会計処理では、受け取った存続会社の株式を借方に、消滅する自社株式を貸方に記載します。受け取った対価が消滅会社株式の帳簿価額を上回る場合は「譲渡益」、下回る場合は「譲渡損」として計上します。
株式以外の対価(例えば現金)を受け取った場合は、「みなし配当」として認識されることもあります。
取得価額2,000,000円のB社株式に対し、時価2,500,000円のA社株式を受け取った場合(譲渡益が発生する場合)の仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| A社株式 | 2,500,000 | B社株式 | 2,000,000 |
| 譲渡益 | 500,000 | ||
取得価額2,000,000円のB社株式に対し、時価1,500,000円のA社株式を受け取った場合(譲渡損が発生する場合)の仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| A社株式 | 1,500,000 | B社株式 | 2,000,000 |
| 譲渡損 | 500,000 | ||
逆取得
存続会社の会計処理と仕訳
逆取得における存続会社は、会計上は被取得企業と見なされます。そのため、実質的な取得企業(消滅会社)の資産・負債を、合併直前の適正な帳簿価額で受け入れます。この場合、通常取得のような時価評価は行いません。
受け入れた純資産(資産から負債を差し引いた額)は、原則として資本金または資本剰余金として計上されます。もし純資産がマイナスで債務超過である場合は、その差額をその他利益剰余金として計上します。
存続会社A社が、消滅会社(実質的な取得企業)B社の資産・負債を簿価で受け入れるケースを考えます。B社の資産が5,000,000円(現金・預金2,000,000円、売掛金3,000,000円)、借入金(1,000,000円)の場合、A社の仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金・預金 | 2,000,000 | 借入金 | 1,000,000 |
| 売掛金 | 3,000,000 | 資本金 | 4,000,000 |
消滅会社の会計処理と仕訳
逆取得における消滅会社は、会計上は実質的な取得企業と見なされますが、この会社は合併によって解散するため、合併前日を最終日として通常の会計処理を行います。全ての資産・負債は存続会社に引き継がれ、帳簿上の残高をゼロにする仕訳が必要です。
具体的には、保有する資産を貸方に、負債と純資産(資本金や繰越利益剰余金など)を借方に記録し、帳簿を閉鎖します。
存続会社A社が、消滅会社(実質的な取得企業)B社の資産・負債を簿価で受け入れるケースを考えます。B社の資産が現金・預金2,000,000円、売掛金3,000,000円、借入金1,000,000円であった場合、B社の仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 借入金 | 1,000,000 | 現金・預金 | 2,000,000 |
| 資本金 | 4,000,000 | 売掛金 | 3,000,000 |
存続会社株主の会計処理と仕訳
逆取得における存続会社(会計上の被取得企業)の株主は、通常取得の場合と同様に、合併によって直接的な取引を行わないため、基本的に会計処理を行う必要はありません。仕訳も不要です。
消滅会社株主の会計処理と仕訳
逆取得の場合、消滅会社(会計上の取得企業)の株主は、存続会社が交付する株式(またはその他の対価)と交換されます。
この交換は、株主にとって株式の譲渡と見なされるため、通常取得の場合と同様に、譲渡損益が発生する可能性があります。受け取った対価と保有株式の簿価との差額が損益として認識されます。
取得価額2,000,000円のB社株式に対し、時価2,500,000円のA社株式を受け取った場合の仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| A社株式 | 2,500,000 | B社株式 | 2,000,000 |
| 譲渡益 | 500,000 | ||
親会社による完全子会社の吸収合併
存続会社の会計処理と仕訳
親会社は、吸収する完全子会社の資産・負債を、合併日前日時点の適正な帳簿価額で計上します。
この際、子会社株式の帳簿価額と、引き継いだ子会社の純資産(帳簿価額)との差額は、「抱合せ株式消滅差益」または「抱合せ株式消滅差損」として計上します。また、のれんは発生しません。
完全子会社が債務超過の場合でも吸収合併は可能で、その際の純資産のマイナス額は、特別損失や抱合せ株式消滅差損として計上されます。
親会社A社が完全子会社B社を吸収合併するにあたり、B社の資産9,000,000円(現金・預金5,000,000円、売掛金4,000,000円)および負債1,000,000円(借入金)を引き継ぐケースを考えます。このとき、A社のB社株式の帳簿価額が7,000,000円である場合、A社の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金・預金 | 5,000,000 | 借入金 | 1,000,000 |
| 売掛金 | 4,000,000 | B社株式 | 7,000,000 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 1,000,000 | ||
消滅会社の会計処理と仕訳
消滅会社である完全子会社は、吸収合併によって解散するため、合併の前日を最終日として会計処理を行います。その際、子会社の全ての資産や負債、および株主資本を帳簿から消去する仕訳が必要です。
具体的には、保有する資産を貸方に、負債と純資産(資本金や繰越利益剰余金など)を借方に記録します。これにより、子会社の会計帳簿上の残高は全てゼロになります。この処理は、他の吸収合併における消滅会社の仕訳と考え方は同様です。
親会社A社が完全子会社B社を吸収合併するにあたり、B社の資産9,000,000円(現金・預金5,000,000円、売掛金4,000,000円)および借入金1,000,000円(借入金)を引き継ぐケースを考えます。このとき、B社の資本金が6,000,000円である場合、B社の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 借入金 | 1,000,000 | 現金・預金 | 5,000,000 |
| 資本金 | 6,000,000 | 売掛金 | 4,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,000,000 | ||
存続会社株主の会計処理と仕訳
親会社が完全子会社を吸収合併する際、親会社の株主は合併に直接関与しないため、原則として個別の会計処理や仕訳は発生しません。
親会社の事業内容や財務状況が変化しても、株主自身の保有する親会社株式の価値変動は、直接的な仕訳として記録されることはありません。
消滅会社株主の会計処理と仕訳
完全子会社の株主は親会社のみであるため、親会社が完全子会社を吸収合併する場合、親会社が唯一の株主です。そのため、消滅会社の株主側での個別の会計処理や仕訳は発生しません。
親会社による子会社の吸収合併(非支配株主が存在するケース)
存続会社の会計処理と仕訳
親会社が子会社を吸収合併する場合、子会社の資産および負債は、合併日前日時点の帳簿価額で引き継がれます。この際、親会社が保有していた子会社株式に対応する部分と、非支配株主に対応する部分とを区分して処理する必要があります。
まず、子会社の純資産に含まれる株主資本は、合併時点における持株比率に基づいて、親会社持分相当額と非支配株主持分相当額に分けて算定されます。親会社持分に相当する金額と、親会社が保有していた子会社株式の帳簿価額との差額は、抱合せ株式消滅差益または差損として、特別利益または特別損失に計上されます。
一方、非支配株主持分に相当する純資産と、非支配株主に対して交付した合併対価(新株など)との差額については、その他資本剰余金として処理されます。
親会社A社が子会社B社を吸収合併するにあたり、B社の資産9,000,000円(現金5,000,000円、売掛金4,000,000円)および負債1,000,000円(借入金)を引き継ぐケースを考えます。A社は、B社株式の80%を4,000,000円で保有しており、残る20%の非支配株主持分に対しては、時価500,000円相当の新株を発行しました。この場合におけるA社の仕訳は、次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金・預金 | 5,000,000 | 諸負債 | 1,000,000 |
| 売掛金 | 4,000,000 | B社株式 | 4,000,000 |
| その他資本剰余金(非支配株主への交付対価) | 500,000 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | 3,500,000 | ||
消滅会社の会計処理と仕訳
消滅会社である子会社は、吸収合併によって解散するため、合併の前日をもって最終的な決算を行います。この際、子会社の資産や負債は、適正な帳簿価額に基づいて算定され、親会社に引き継がれます。
最終的な仕訳によって、子会社の全ての資産と負債が親会社に移転し、子会社の会計帳簿は閉じられ、帳簿残高は全てゼロになります。子会社の資本金や利益剰余金といった株主資本の項目も、この仕訳を通じて親会社に引き継がれます。
親会社A社が子会社B社を吸収合併するケースを考えます。B社の資産9,000,000円(現金5,000,000円、売掛金4,000,000円)および負債1,000,000円(借入金)を引き継ぐ場合、B社の仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 諸負債 | 1,000,000 | 現金・預金 | 5,000,000 |
| 資本金等 | 8,000,000 | 売掛金 | 4,000,000 |
存続会社株主の会計処理と仕訳
存続会社(親会社)の株主は、親会社が子会社を吸収合併する取引に直接関与しないため、原則として個別の会計処理や仕訳を行う必要はありません。
合併により、親会社の事業内容や財務状況が変化する可能性がありますが、株主自身の保有する親会社株式の価値が変動しても、その変動は個別株主の会計帳簿には直接反映されません。
消滅会社株主の会計処理と仕訳
消滅会社である子会社に非支配株主(親会社以外の株主)が存在する場合、これらの株主は、保有していた子会社株式と引き換えに、存続会社である親会社の株式などの合併対価を受け取ります。この取引は、非支配株主にとって子会社株式の譲渡と見なされるため、譲渡損益が発生する可能性があります。
会計処理においては、受け取った親会社株式を借方に、保有していた子会社株式の帳簿価額を貸方に記録します。受け取った対価が子会社株式の簿価を上回れば譲渡益、下回れば譲渡損とされます。
親会社A社が子会社B社を吸収合併し、B社の非支配株主が取得価額2,000,000円のB社株式に対し、A社株式(時価2,500,000円)を受け取った場合の仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| A社株式 | 2,500,000 | B社株式 | 2,000,000 |
| 譲渡益 | 500,000 | ||
吸収合併の会計・税務上のポイント
吸収合併の仕訳が完了しても、それだけで終わりではありません。会計処理と税務処理のずれや、法的な手続き漏れがあると、後から修正や追徴課税が発生するリスクがあります。ここでは、特に注意すべき点をいくつか紹介します。
のれん償却について
吸収合併で発生したのれんは、会計上、取得時から原則的に20年以内の一定期間で定期的に償却(費用化)していく必要があります。これは、のれんが無形固定資産として企業の将来の収益に貢献するという考えに基づいています。
なお、100万円ののれんを10年にわたって償却を行う場合、1年間の償却額は10万円です。仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| のれん償却 | 100,000円 | のれん | 100,000円 |
のれんの税務上の扱いについて
会計と税務では、のれんの取り扱いが異なる点に注意が必要です。会計上は「のれん」として処理されますが、税務上は一般的に「資産調整勘定」として扱われます。会計上の償却期間は最長20年ですが、税務上ののれんの償却期間は5年と定められています。
また、会計上ののれんは税効果会計の適用対象外ですが、税務上の資産調整勘定は税効果会計の適用対象となり、節税効果が発生します。
なお、負ののれんが発生した場合、税務上は原則として益金に算入され、特別利益として会計処理されます。
契約書・株主総会議事録・登記などの整理も必要
吸収合併は、経理部門だけで完結する手続きではありません。法務や総務など、関係部署との連携は不可欠です。
会計処理や税務処理を正確に行うためには、必要な法的書類を適切に作成し、整理しておく必要があります。具体的には、合併契約書や合併承認の株主総会議事録、合併登記の完了証明、税務署への各種届出などが含まれます。
これらの書類に不備があったり、手続きに漏れがあったりすると、合併そのものの有効性に影響を与えたり、後から追加で修正対応や追徴課税が発生したりするリスクがあります。各部門との連携を密にし、手続きの抜け漏れがないように徹底的な確認が求められます。
連結会計との整合性をよく確認する
親会社が連結決算を行っている場合、吸収合併は連結財務諸表に大きな影響を与えます。特に、子会社を吸収合併した際には、個別財務諸表上の処理だけでなく、連結会計上の処理も同時に考慮する必要があります。
具体的には、従来の連結財務諸表における資本連結の処理(投資と資本の相殺消去など)を見直し、新たな合併後の連結財務諸表に適切に反映させなければなりません。
連結財務諸表への影響を正確に把握し、適切な処理を行うためには、連結チームや監査法人との事前調整が非常に重要です。事前に十分な協議を行うことで、連結会計上の整合性を確保し、決算時の混乱や手戻りを防げます。
合併時の仕訳に関するQ&A
最後に、合併時の仕訳に関するよくある質問とその回答を紹介します。
適格合併と非適格合併とは
適格合併とは、法人税法上の要件を満たすことで、合併に伴う資産・負債の移転について課税が繰り延べられる合併形態です。
要件には、合併対価として金銭などを交付しないことや、被合併法人の事業が継続されること、従業員の大半が引き継がれることなどがあります。なお、支配関係の有無により求められる条件は異なります。
適格合併であれば譲渡益に課税されず、繰越欠損金の承継も認められます。
一方で、これらの要件を満たさない合併は非適格合併となり、資産は時価評価され、含み益に対して法人税が課税されます。また、被合併法人の欠損金は引き継がれず、税負担が重くなる傾向があります。
非適格合併時にはどんな税金がかかるか
非適格合併に該当する場合、合併によって移転する資産は帳簿価額ではなく時価で評価されます。そのため、含み益のある資産については、その差額に法人税が課税されます。また、被合併法人の繰越欠損金は承継できないため、税務上の損失が消滅し、合併後の節税効果が得られない点にも注意が必要です。
さらに、資本金が増加する場合には、その増加額に対して登録免許税が課税されます。加えて、移転資産に不動産が含まれる場合は不動産取得税が、課税資産の譲渡があれば消費税が発生する可能性もあります。
共同支配企業を形成した場合、仕訳や会計処理はどうなるか
共同支配企業の形成とは、複数の企業が対等な立場で共同出資し、新たな会社を一緒に運営・支配するようなケースです。
この場合、通常の合併のように「取得した」「取得された」という関係はなく、会計処理は帳簿価額ベースで行われます。つまり、各社が持っていた資産や負債は、帳簿上の価額でそのまま新会社に移されます。
また、新たな会社での資本処理も、出資内容に応じて資本金や資本剰余金として計上されるか、必要に応じて旧会社の資本構成を引き継ぐこともあります。
出資に対して受け取る株式も帳簿価額で評価されるため、譲渡益や譲渡損は発生しません。なお、取得対価には、議決権のある株式が用いられることが一般的です。
交付金合併とは何か
交付金合併とは、吸収合併の一種で、消滅会社の株主に対して対価として株式ではなく金銭(合併交付金)を交付する合併形態です。「キャッシュアウトマージャー」とも呼ばれます。
以前は、原則として存続会社の株式しか合併対価にできませんでした。しかし、2006年の会社法改正によって、現金による対価のみでの合併も可能となりました。
交付金合併のメリットとしては、存続会社の株主構成を維持したまま合併できる点が挙げられます。特に、経営権の移動を避けたい場合や、少数株主を整理して完全子会社化する局面などで用いられます。
簡易合併・略式合併とは何か
簡易合併と略式合併は、吸収合併における株主総会決議を省略できる制度であり、手続きの迅速化とコスト削減を目的とした制度です。
簡易合併は、存続会社が消滅会社に対して交付する合併対価の金額が、存続会社の純資産の5分の1以下である場合に適用され、存続会社の株主総会を省略できる制度です。
一方、略式合併は、消滅会社の株式を90%以上存続会社が保有している場合に、消滅会社の株主総会を省略できる制度です。 実務では両制度を併用するケースが多く見られます。
まとめ
本記事では、合併、特に吸収合併における仕訳と会計処理について詳しく解説しました。合併は企業の成長戦略として重要な手段であり、適切な会計処理と仕訳が求められます。吸収合併の会計上の分類は、多くの企業にとって複雑な領域であり、企業ごとの状況に応じた対応が必要です。各ケースにおける具体的な仕訳例を理解することで、実務における適用がスムーズになります。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。