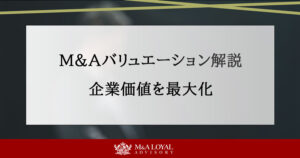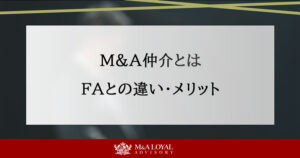M&A相場の完全ガイド|価格の計算方法や目安、手数料など徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
M&Aの相場はいくらでしょうか。企業の買収や売却を検討している経営者にとって、価格は大きな関心事の一つです。M&Aでは、財務状況や資産価値だけでなく、将来の成長性や業界の動向、経営戦略など、さまざまな要素が価格決定に影響を与えます。これらの複雑な要因を整理し、適正な譲渡価格を見極めることが、M&Aを成功させる鍵となります。本記事では、譲渡価格の目安や計算方法、手数料などM&Aにおける費用の相場について解説します。
目次
M&Aの相場価格はいくら?
相場とは、一般的に市場における時価、すなわちその時々の取引価格を指します。株式や債券、為替などと同様に、M&Aにおいても「相場」という言葉が使われることがあります。
M&Aの相場とは
M&Aの相場とは、いわゆる売却または買収にかかる平均的な費用の目安を指します。M&Aは企業の合併や買収を表す言葉であり、業界や規模によって価格は大きく異なります。例えば、個人事業であれば数十万~数百万、中小企業であれば数百万~数千万、大企業であれば数億円以上で取引されることもあります。そのため、一概にM&Aの相場を示すことは困難です。
しかし、売却または買収の際にどのくらいの価値がつくのかを算定することはできます。これを企業価値評価(バリュエーション)と言います。企業価値評価にはいくつかの手法があり、評価方法によって算出結果は異なるため、どの評価手法を用いるかも大切になります。また、最終的な取引価格はこうした評価に加えて、将来的な価値やリスクを基に買い手と売り手の交渉によって決定されます。
中小企業のM&Aの相場価格
前述したとおり、M&Aに明確な相場というものはありません。譲渡価格は企業の規模や財務状況、ブランド価値など複数の要因が絡み合って算出されるためです。ただし、目安となる価格を知ることはできます。
算定方法にはいくつかの手法がありますが、簡易的な算定方法に年買法という計算方法があります。年買法は、時価純資産に年間営業利益の2~5年分を加えて、企業価値を算出します。例えば、資産が8,000万円、負債が3,000万円、平均営業利益が5,000万円の場合の売却価格は次のようになります。
| 純資産の計算 純資産 = 資産 – 負債 = 8,000万円 – 3,000万円 = 5,000万円 売却価格の算出 年間営業利益の2年分を加えた場合:5,000万円 + (5,000万円 × 2) = 15,000万円 年間営業利益の5年分を加えた場合:5,000万円 + (5,000万円 × 5) = 30,000万円 |
したがって、年買法で計算した売却価格の相場は1億5,000万円から3億円となります。しかし、この計算では無形資産は除外されているため、さらに詳細な評価が必要となります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



M&Aの相場価格や目安を決める要素
M&Aの相場や目安となる価格を計算する際には、いくつかの要素が考慮されます。具体的には以下の項目を評価します。
- 財務状況
- 無形資産
- 市場・外部環境
- 買い手および売り手の状況
これらの要素を総合的に評価することで、企業の本質的な価値が見極められ、適正な譲渡価格を算定することができます。
財務状況
M&Aにおける企業の相場価格の決定要素の一つが、売り手企業の財務状況です。財務状況は、企業の健全性や成長性を示す指標となり、買い手が企業価値を評価する際の基準として使用されます。具体的には、売上高や利益率、資産負債のバランス、キャッシュフローの状況などが注目されます。
売上高や利益率が安定している企業は、将来の収益予測がしやすく、買い手にとって魅力的です。さらに、資産負債のバランスが健全であれば、財務リスクが低いと評価され、価格にプラスの影響を与えることがあります。キャッシュフローの状況も重要で、安定したキャッシュフローは企業の財務的な持続性を示します。
- 営業利益
営業利益とは、企業が営む事業で得た利益を示し、企業の収益性や経営効率を直接的に反映しています。企業が市場でどれだけの競争力を持ち、持続可能な成長を遂げられるかを判断する材料ともなります。そのため、この指標が高いほど、売り手にとって有利な価格交渉が可能になります。
ただし、営業利益だけに依存するのは危険です。営業利益の増減は、業界のトレンドや市場環境の変化に敏感に反応するため、その推移を慎重に分析すると同時に、他の財務指標や市場環境とのバランスを考慮し、全体的な企業の健全性を判断することが求められます。
- 純資産
純資産とは、企業の総資産から負債を引いたもので、企業の正味の価値を示します。純資産の金額が大きいほど企業価値も高く見積もられやすく、営業利益と並んで譲渡価格を算出する際の指標となります。特に中小企業では、純資産が企業の安定性や潜在的な成長力を示す指標となることが多く、買い手が投資の妥当性を判断する材料となります。
また、純資産は譲渡価格の下限を判断する基準としても使われます。ただし、貸借対照表上の簿価は過去の取得価格に基づくため、実際の価値を反映していないこともあり、時価評価による見直しが必要です。純資産だけに依存するのではなく、他の要素、例えば収益性や市場環境などとも併せて考慮することが大切です。
- 将来的な利益やキャッシュフロー
M&Aでは将来の利益やキャッシュフローも企業価値を評価する重要要素です。特に収益性や安定したキャッシュフローは、買い手にとって魅力的であり、取引価格を高めるポイントにもなります。純資産が「現在の価値」なら、将来利益は「これからの価値」として譲渡価格に大きく影響します。
特に、キャッシュフローがプラスであれば、買い手は企業が現状の収益を維持しつつ成長する可能性が高いと判断しやすくなります。逆に、負債が多い場合やキャッシュフローが不安定な場合、買い手はリスクを考慮し、譲渡価格を引き下げる要因となる可能性があります。
無形資産
M&Aの相場価格を決定する際、無形資産も重要な要素です。無形資産とは、目に見えない価値であり、譲渡価格を引き上げる要因となります。無形資産には、特許や商標などの知的財産権、ブランド価値、顧客リスト、ソフトウェア、ノウハウなどが含まれます。
これらの資産は、企業の競争力を高め、持続的な収益を生む源泉となり得ます。例えば、強力なブランドは消費者からの信頼を集め、顧客ロイヤルティを確保する手段として機能します。
また、特許や商標は競合他社による模倣を防ぎ、特定の市場での優位性を保つための武器となります。さらに、独自の技術やノウハウは、製品やサービスの差別化を図り、市場での競争を有利に進めることができます。
- 取引先や顧客リスト
M&Aの価格を算定する際には、取引先や顧客リストも大きな要素となります。買い手がM&Aを実行する目的の多くは、事業拡大や新規事業への参入です。このため、既に主要な取引先との長期的な契約や安定した供給チェーンを維持している場合は、買い手にとって非常に魅力的に映ります。
M&Aを通じて売り手の取引先や顧客リストを獲得することで、地域や市場の新規開拓にかかる手間を省くことができ、広告宣伝費などのコスト削減やスケールメリットを享受することが可能です。また、多くの取引先や顧客を抱えている場合やリピート率が高い場合は、安定した収益が見込めます。このように、同じ業界や事業規模であっても、取引先や顧客リストの質や数は譲渡価格に大きな影響を与えます。
- 経営者のビジョン(企業理念や経営方針など)
M&Aにおいて、企業の相場価格を評価する際には、財務状況や市場環境だけでなく、経営者のビジョンも重要です。経営者のビジョンは企業の方向性や長期的な成長戦略を示すものであり、これがM&Aの成否を左右することも少なくありません。
企業理念や経営方針が明確で一貫性があり、買い手企業との親和性が高い場合、企業の将来性や持続可能性が高いと判断され、より高い価値が見込まれることがあります。特に、企業理念が社会的な貢献や持続可能な取り組みを重視している場合、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資を考慮する投資家や企業から高く評価される可能性があります。
また、経営方針が柔軟で市場の変化に対応できるものである場合、将来的な成長ポテンシャルが高いと見られ、評価額にプラスの影響を与えることがあります。さらに、ビジョンが組織全体に浸透し、従業員がその実現に向けて積極的に取り組んでいる場合は、組織力としても評価され、競争力の一環として買い手にアピールすることが可能です。このように、経営者のビジョンがM&Aの相場価格に反映されることがあります。
- 優秀な従業員
M&Aにおいて、優秀な従業員の存在は企業価値に大きく影響します。人材は企業の成長や競争力を支える重要な資産であり、買収後の事業のスムーズな引き継ぎを促進します。特に専門的なスキルや経験を持つ従業員は、買収後の即戦力となります。そのため、譲渡価格を大きく押し上げる要因となります。
また、優れたリーダーシップを持つマネジメント層がいる場合、その企業は安定した業績を期待できるため、買い手にとっての魅力が増します。さらに、従業員の定着率が高い企業は、企業文化がしっかりと根付いている可能性があり、買収後の組織統合が円滑に進むことが期待されます。従業員のスキルセットや能力の多様性も企業の強みとなり得るため、M&Aにおける相場価格を高める要因となります。
- ブランド力・特許・技術力など
ブランド力や特許、技術力もM&Aにおける相場価格を決定する項目です。ブランド力は企業の市場における知名度や信頼性を示し、これが高いほど企業の価値が上昇しやすくなります。ブランドによる顧客の支持やロイヤリティは、企業の収益性を長期にわたって支える要素となるため、買い手にとっては非常に魅力的です。
次に、特許は企業が持つ独自の技術や製品を保護する法的権利であり、競争優位性を確保するための資産です。特許を多く保有している企業は、競合他社に対して優位に立つことができ、市場での独占的な地位を築くことができます。これにより、特許を持つ企業は買収の際に高い評価を受けることが多いです。
さらに、高度な技術力もM&Aの相場を大きく左右します。技術力が高い企業は、イノベーションを起こす能力を持ち、業界のリーダーシップを発揮することができます。このような企業は、新製品の開発や市場のトレンドに迅速に対応する力があるため、買い手にとっては将来の成長を期待できる魅力的な投資先となります。
しかし、これらの無形資産の評価は主観的な要素が多く含まれるため、専門的な知識や経験が必要となります。無形資産の価値を正確に把握するためには、専門のアドバイザーや評価機関の支援を受けることが推奨されます。
のれん代とコントロールプレミアム
特許・ブランド・ノウハウ・従業員の能力など無形資産や将来性への期待を金額化したものを「のれん(営業権)」と言います。M&Aは有形資産や営業利益等の目に見える価値にのれん代が加わって計算されます。交渉が激化したり期待値が高まったりすると、のれん代は上昇する傾向があります。
また、コントロールプレミアム(買収プレミアム)とは、M&Aにおいて企業の経営権を獲得するために、市場の株価に上乗せされる金額のことです。実際のM&A取引では、平時の市場株価に対しておおむね20〜40%程度が上乗せされるケースが一般的です。
市場・外部環境
M&Aの相場価格は、企業の内部的な要因だけでなく、市場や外部環境による影響も大きく受けます。市場の動向や経済全体の状況は、企業の評価に直接影響を与え、譲渡価格を左右します。例えば、全体的な経済成長率が高い時期には、企業の将来収益が期待され、M&A価格が上昇する傾向があります。逆に、不況時には企業価値が低く評価されることが多く、価格が下がることがあります。
また、業界特有のトレンドも重要です。成長が期待される業界やセクターでは、買い手の競争が激しくなり、相場価格が高騰することがあります。特に、技術革新が進む分野では、新技術や独自のノウハウを持つ企業が高く評価されることが多いです。
さらに、政治的な要因や規制の変化も考慮する必要があります。新たな法律や規制が導入されることで、業界全体の見通しが変わり、企業のリスクプロファイルが影響を受けることがあります。国際的な関係や貿易政策の変動も、特にグローバルに展開している企業にとっては重要な要素です。
買い手および売り手の状況
M&Aにおける売り手と買い手の戦略事情も譲渡価格や交渉プロセスに大きく影響します。例えば、買収後のシナジー効果や買い手・売り手の緊急度などが挙げられます。
- 買い手の状況
買い手の戦略や事業計画が売り手企業とのシナジーを生み出す可能性がある場合、買い手はより積極的に競争的な価格を提示することがあります。特に、買い手が新たな市場への進出や技術の獲得を目指している場合、売り手の持つ資源やノウハウは非常に価値あるものと見なされます。さらに、市場への参入を急ぐ場合には、契約を早めるために交渉価格を引き上げることもあります。
- 売り手の状況
M&Aの相場価格は、売り手の状況によっても左右されることがあります。例えば、売り手の経営者が高齢化している場合、後継者問題や健康上の理由から早急に契約を進めたいと考えることがあるでしょう。このような場合、通常よりも低めの価格での譲渡を決断するケースが見受けられます。また、売却益による資金調達を急ぐ場合も同様です。時間的な制約があると、売り手は市場の変化や新たな買い手との交渉機会を逃すことになるため、余裕をもった戦略と対策が大切になります。
- M&Aスキームの違い
M&Aの実行スキームも価格相場に影響を与えることがあります。M&Aスキームは、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割の4つに分類されます。それぞれのスキームには特有のメリットとデメリットがあり、これが譲渡価格の算定に直接的に関与します。
例えば、株式譲渡は企業全体を対象とするため、シンプルで手続きも比較的容易ですが、買い手は売り手の負債や義務も引き継ぐことになります。一方、事業譲渡は特定の事業を対象とし、買い手は選択的に資産や負債を取得できるため、買収リスクを軽減できる一方、手続きが複雑化しやすいです。
合併は、複数の企業が一つに統合されるため、シナジー効果が期待できる反面、それぞれの企業文化の統合が課題となります。会社分割では、特定の事業を別会社として切り出すことで、集中した経営資源の活用が可能となりますが、分割後の資本構成の調整が必要です。
M&Aスキームの違いは、法務、税務、財務の観点からも評価され、最終的な価格形成に寄与します。そのため、スキームの選択は戦略的な視点から慎重に行う必要があります。
- 支払い方法や仲介手数料
支払い方法やM&A仲介手数料は売り手と買い手の心理や交渉に直接影響を与えるため、相場価格の形成に深く関与しています。まず、M&Aの支払い方法には、現金、株式、アーンアウトなどがあります。
現金支払いは、売り手にとって即座に資金を得られるため、リスクが少なく、安心感があります。一方、株式での支払いは、将来の株価の変動に依存するため、売り手には不確実性が伴います。このリスクを避けるため、売り手は現金支払いを希望することが多く、その結果、現金支払いの条件が優遇されることがあります。
また、アーンアウトとは、買収後の業績に基づいて追加の支払いが行われる仕組みです。売り手は、業績が良ければ高い価格を得られる可能性がありますが、買い手にとっては将来の業績に依存するため、価格交渉では慎重さが求められます。
さらに、M&A仲介手数料も譲渡価格に影響を与える要因です。もし仲介手数料が高い場合、売り手はそのコストを考慮し、より高い譲渡価格を求める傾向があります。このように、価格の支払い方法や仲介手数料が最終的な取引価格に影響を与えることもあります。
M&Aの相場価格を算定する評価方法
M&Aの相場価格を決定する際の基準となる企業評価方法には「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」があり、これらの手法を組み合わせて、企業価値が算出されます。各手法には特徴があり、評価額の高低は企業の状況によって異なります。
- コストアプローチ:資産価値を基にした評価手法。資産が重要な業種では高く評価されるが、成長性を反映しない。
- マーケットアプローチ:類似取引を参考にした手法で、市場動向に応じて評価額が変動する。
- インカムアプローチ:将来利益やキャッシュフローを反映する。成長性が高い企業では評価額が高くなる傾向がある。
コストアプローチ
コストアプローチは、資産と負債の差(純資産)から企業価値を算出する手法で、「ストックアプローチ」とも呼ばれます。将来の収益ではなく、保有資産の価値に着目する点が特徴です。不動産や設備の多い企業、中小企業、将来予測が難しい企業に適しており、計算が簡単で透明性が高い点も利点です。
一方で、のれんを反映しにくく、成長企業の評価には不向きな場合があります。正確な時価評価には専門知識が必要です。コストアプローチには、次の2つの代表的な算出方法があります。
- 簿価純資産法
簿価純資産法は、貸借対照表に記載された帳簿上の資産から負債を差し引いた「簿価ベースの純資産額」を基に企業価値を評価する手法です。この純資産額を発行済株式総数で割ることで、1株あたりの株価の算出も可能です。
ただし、帳簿上の資産は取得時の価格に基づいているため、時価と乖離(かいり)しているケースが多く、現実の価値を正確に反映していない可能性があります。そのため、実務においてこの手法が単独で用いられるケースはほとんどありません。
- 時価純資産法(修正純資産法)
時価純資産法は、資産と負債を評価時点の時価に修正した上で企業価値を算出する手法です。「修正純資産法」とも呼ばれます。全資産を時価に換算し、そこから時価ベースの負債を差し引くことで、実質的な純資産価値を導き出します。
この手法は、企業の清算価値(全ての資産を換金して債務を返済した後に残る価値)に近い評価を行うものであり、場合によってはのれんなど将来利益を加味するケースもあります。そのため、後述する「年買法」と併用されることもあります。
- 年買法(年倍法)
年買法は、時価純資産に過去の営業利益の数年分を加えて企業価値を算出する簡易な手法です。コストアプローチの一種ではありますが、将来性も考慮するため、インカムアプローチの側面も持ちます。
年買法は小規模M&Aや個人間取引にも適しており、計算が簡単で過去の収益性を反映する評価手法です。将来予測に依存せず過去実績に基づくため、不透明な環境下でも使いやすい点が特長です。ただし、成長性や業績変動が大きい企業には適用が難しい場合があり、資産価値の反映は限定的です。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、株価やM&A事例などの市場データを基に企業価値を相対的に評価する手法です。上場企業や成長企業の評価に適しており、非上場企業でも類似上場企業を参考にできます。市場価格や類似取引を基に評価を行うため信頼性が高く、交渉時の根拠として用いられることが多いです。ただし、適切な比較対象がない場合や市場動向に左右される場合には、注意が必要です。
一方で、類似企業の選定が難しい小規模企業や独自性の高い企業には不向きな場合があります。また、市場環境の影響を受けやすい点が課題です。このため、他の評価手法(インカムアプローチやコストアプローチ)との併用が一般的です。マーケットアプローチには、主に次の3つの代表的な評価手法があります。
- 類似上場会社比較法(EBITDAマルチプル法)
類似上場会社比較法は、同業種・同規模で、成長性や収益性が類似する上場企業の株価や財務指標を基に、対象企業の価値を推定する手法です。市場の期待や成長性を反映しやすく、特に成長産業や上場企業の評価に適しています。中でも「EBITDAマルチプル法」は、減価償却や税効果などの会計上の差異を排除し、企業のキャッシュ創出力に着目して評価を行うため、実務で大変多く用いられています。
- 類似取引比較法
類似取引比較法は、過去に実施された類似のM&A取引事例を参考に、対象企業と共通点を持つ企業の売買価格や評価倍率(マルチプル)を用いて企業価値を推定する手法です。実例に基づいた評価が可能なため、交渉において説得力のある材料といえます。ただし、市場環境や交渉状況に大きく左右される点には留意が必要です。
- 市場株価法
市場株価法は、上場企業の過去1〜3カ月程度の平均株価を基に企業価値を評価する方法です。多くの市場参加者の判断を反映しているため、客観性の高い評価が可能です。ただし、この方法は経営権の移転やシナジー効果といったM&A特有の要素を考慮せず、「現状の企業価値」のみにとどまります。そのため、M&Aにおいては買収プレミアムや将来の付加価値を加味して最終価格が調整されることが一般的です。
インカムアプローチ
インカムアプローチは、将来の収益やキャッシュフローを基に企業価値を算出する手法で、成長企業や収益が見込まれる事業の評価に適しています。将来性やシナジーを反映でき、理論的かつ柔軟な評価が可能です。一方で、予測に主観が入りやすく、事業計画や割引率次第で評価が大きく変わる点が課題です。情報収集に手間がかかり、収益が見込めない企業には不向きです。代表的なインカムアプローチには、次の2つがあります。
- DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法
DCF法は、インカムアプローチの代表的手法で、将来のフリーキャッシュフローを割引率で現在価値に換算し、企業価値を算出します。通常は5〜10年分の予測にターミナルバリューを加え、成長性やリスク、シナジーも反映できます。ただし、前提に主観が入りやすく、割引率次第で評価額が大きく変わるため、慎重な検討が必要です。
- 配当還元法
配当還元法は、将来支払われる配当金を基に企業価値を評価する手法で、非上場企業や株主数の少ない企業で用いられることが多い方法です。ただし、配当額は企業の配当政策に左右されるため、将来の予測が困難である点が課題です。また、成長戦略を重視する企業では配当を抑えて投資に回すケースも多いため、安定配当が前提とならない大企業のM&Aでは、あまり利用されません。
M&Aの相場価格を高くする方法
M&Aにおいて相場価格を引き上げ、高い譲渡価格を実現するためには次の方法があります。
- 企業価値向上を図る
- 強みを明確に伝える
- 潜在的なリスクへの対策
- 業績の良いタイミングを逃さない
- 会社ごと売却する
それぞれについて解説します。
企業価値の向上を図る
相場価格を高める方法の一つが企業価値を向上させることです。企業価値を上げる方法には、収益性の向上や組織体制の整備、資産の整理等が挙げられます。収益性の向上では、コスト削減や売上の増加を図る施策を講じ、利益率を向上させることが重要です。例えば、新規市場への参入や製品ラインの拡大、既存顧客へのクロスセル戦略の強化などが考えられます。
次に、組織体制の整備も欠かせません。効率的な組織運営を実現するためには、人材の育成や適切な配置、明確な業務プロセスの構築が必要です。これにより、組織全体の生産性が向上し、買い手にとっての付加価値を提供できます。また、透明性のあるガバナンス体制も、信頼性を高める要素となります。
さらに、資産の整理も企業価値の向上に直結します。未使用または低収益の資産を売却することで、資産効率を改善し、キャッシュフローを強化することができます。バランスシートを最適化することで、企業の財務的な健全性を示すことができ、買い手に対するアピールポイントとなります。
強みを明確に伝える
M&Aにおける相場価格を引き上げるためには、企業の強みを効果的にアピールすることも大切です。強みの適切に評価し、伝えることは、企業の競争力を示し、買い手にとっての価値を明確にするための重要な要素です。具体的には、独自の技術や製品、特異な市場ポジション、顧客基盤、ブランド力などを強調することが考えられます。
また、強みのアピールには、定量的なデータを用いた説明が効果的です。売上高や利益率の推移、顧客満足度調査の結果など、具体的な数字を示すことで、買い手に対して信頼性と説得力を提供できます。
潜在的なリスクへの対策
M&Aの相場価格を高くするためには、潜在的なリスクの把握とその対策を講じることも重要です。リスク要因を事前に洗い出し、それに対する具体的な対応策を整備しておくことで、買い手が安心して取引に臨める状況を作り出せます。これには、法務やコンプライアンスの問題への対処、サプライチェーンの信頼性確保、さらには市場変動への対応策などが含まれます。
また、買い手とのコミュニケーションを円滑に進めるために、プロフェッショナルな仲介会社やアドバイザーを活用することも考慮すべきです。彼らの専門知識や経験を活かすことで、交渉過程をスムーズに進められ、結果として好条件での売却につながる可能性が高まります。
業績の良いタイミングを逃さない
M&Aを成功させ、相場価格を最大化するためには、業績の良いタイミングを見極めることが重要です。企業の業績が好調である時期は、買い手にとっても非常に魅力的に映ります。具体的には、売上高や利益率が上昇している時期、または業界全体の成長が見込まれるタイミングを狙うと良いでしょう。
このような時期にM&Aを実施することで、企業価値が高く評価される可能性が高まります。さらに、業績が良いときは、交渉において売り手が有利な立場に立ちやすく、より良い条件を引き出すことが可能です。
一方で業績が悪化していたり、負債を抱えている場合はリスクも高くなり、買い手が見つかりにくくなったり、価格が低く抑えられる可能性もあります。ただし、業績が好調であっても短期的な要因によるものである場合、買い手は取引に慎重になるため、売り手は業績が良い理由やその持続性をしっかりと説明できるように準備しておくことが大切です。
会社ごと売却する
M&Aの相場価格を最大化するためには、会社全体を売却することも有効な戦略となります。事業のみ売却は、特定の部門やプロジェクトに焦点を当てているため、買い手にとってはその事業のみに価値を見出すことになります。その結果、評価額もその事業の収益性や成長性に依存し、限定的なものとなることがあります。
一方で、会社全体を売却する場合、買い手は企業全体の資産、顧客基盤、ブランド力、そして無形資産を一括で取得できるため、総合的な企業価値を高く評価する可能性が高まります。さらに、企業全体の売却は、統合後のシナジー効果を見込むことができ、買い手にとってはより魅力的な提案となります。
例えば、既存の顧客基盤を活用してクロスセルを行ったり、新たな市場への参入を加速させたりすることが可能です。また、全社的なリソースの統合によるコスト削減も期待できます。このように、会社全体の売却は、買い手にとっての総合的な価値提案を強化し、結果として相場価格を引き上げる有効な手段となります。
M&Aの価格を決定する交渉手段
M&Aの交渉手段には、主に次の2つがあります。
- 個別交渉方式
- オークション方式
それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説します。
個別交渉方式
個別交渉方法は、M&Aの相手候補となる企業に対して取引条件を交渉し、双方が合意すれば取引が成立する方法です。合意に至らない場合は、別の相手候補を探して再度交渉を行います。この方法は柔軟な交渉が可能ですが、M&A交渉に関する専門知識が不足していると、希望価格での成立が難しくなったり、自社に不利な条件で契約を結んでしまったりするリスクがあります。そのため、M&Aの専門家である仲介会社やアドバイザーにサポートを依頼することが一般的です。
オークション(入札)方式
オークション方式は複数の買い手候補に条件提示を求め、最も有利な提案者と交渉を進める手法で、高値売却に効果的です。複数の買い手を競争させることで好条件を引き出すことが期待できる一方、選定プロセスが複雑で時間を要するため、短期決着には不向きな傾向があります。また、競争が成立しない場合やコストが増加するリスクも伴うほか、複数社に情報を開示するため情報漏えいリスクにも注意が必要です。
M&A仲介会社の手数料の相場
M&Aでは譲渡価格だけでなく、仲介会社への手数料も発生します。ここでは、M&A仲介会社の手数料の相場について触れていきます。仲介会社に支払う費用は次のとおりです。
- 相談料
- 着手金
- 中間報酬
- 成功報酬
なお、仲介会社によって着手金や中間報酬は無料など、必要な費用は異なります。
- 相談料
相談料とは、仲介会社に初回相談やアドバイスを受ける際に発生する料金のことです。この料金は、M&Aの概要説明や質疑応答などの初期対応に対する対価として請求されますが、多くの仲介会社では初回の相談を無料で提供しています。
初回相談では、目的や条件を伝えるだけでなく、仲介会社の対応力や実績も確認できます。一部の専門性が高い会社では有料で、相場は1回5,000〜1万円程度です。
- 着手金
着手金は、M&A仲介を正式依頼する際に支払う費用で、人件費や資料作成費が含まれます。相場は、案件の規模や依頼するアドバイザーによって異なるものの、一般的には100〜500万円程度です。また、近年は無料の仲介会社も増加しています。
ただし、大規模案件や専門性の高いアドバイザーを利用する場合、着手金が数百万円を超えることもあります。成功報酬が高めに設定されている場合もあるため、全体の費用構成の確認が重要です。着手金は不成立でも返金されないことが一般的です。
- 中間報酬
中間報酬は、基本合意書の締結時に支払う費用で、成功報酬の10~30%程度が相場とされています。この報酬は、M&Aプロセスの中間地点である基本合意の締結までの業務に対する対価として設定されており、M&Aが不成立となった場合でも返金されないことが一般的です。
- 成功報酬
成功報酬は、M&Aが成立した際に支払う報酬で、取引金額に基づいて計算されます。一般的にはレーマン方式が採用されており、取引金額に応じて次の料率が適用されます。一般的な成功報酬の相場は次のとおりです。
| ・取引金額が5億円以下の場合:5% ・取引金額が5~10億円以下の場合:4% ・取引金額が10~50億円以下の場合:3% ・取引金額が50~100億円以下の場合:2% ・取引金額が100億円超の場合:1% |
また、成功報酬に加えて月額報酬やデューデリジェンスの費用などの費用が発生する場合もあります。M&Aの規模が大きくなるほど、手続きが複雑化し、手数料も高くなる傾向があります。
M&A仲介会社を利用するメリット
M&A取引で仲介会社を利用するメリットは次のとおりです。
- 専門的な知識と経験の活用
- 買い手・売り手のマッチング
- 交渉・手続きの一括サポート
それぞれを詳しく解説します。
- 専門的な知識と経験の活用
M&Aは法務・税務・財務などの専門知識が必要な複雑なプロセスです。仲介会社を活用すれば、専門家の支援によりトラブルを避けて円滑に進められます。業界知識や客観的視点を持つ仲介会社は、適正な企業価値の算定を行い、双方が納得しやすい価格設定にもつながります。
- 買い手・売り手のマッチング
M&A仲介会社は、独自のネットワークを活用して、買い手企業や売り手企業の候補を幅広く探すことができます。また、業界や企業規模、経営方針などの条件に応じて最適な相手を選定できるため、スムーズかつ戦略的なマッチングが可能です。
- 交渉・手続きの一括サポート
M&Aでは条件交渉やスケジュール調整が不可欠です。仲介会社が第三者として介入することで、感情的対立を避けつつ円滑に合意形成しやすくなる傾向があります。また、資料作成やデューデリジェンス、契約確認など煩雑な手続きも一括でサポートしてくれるため、企業は本業に集中しながらM&Aを進められます。
M&A仲介会社を利用する際の注意点
M&A仲介会社を利用する際の注意点は次のとおりです。
- 手数料がかかる
- 仲介会社によって質に差がある
- 利益相反のリスクがある
- 情報は複数の仲介会社から集める
- 提示価格を鵜呑みにしない
- 手数料がかかる
M&A仲介会社に依頼すると、成功報酬などの一定の費用が発生します。特に中小企業の場合は、報酬割合が大きな負担となることもあります。M&A仲介会社によって料金体系は異なるため、事前に報酬の算出方法や、費用が発生するタイミングを十分に確認しておくことが重要です。
- 仲介会社によって質に差がある
M&A仲介会社には大小さまざまな規模があり、担当者の経験や業界知識にもばらつきがあります。知識や実績が不十分なM&A仲介会社に依頼してしまうと、適切な価格提示や買い手企業との交渉が期待できないリスクがあります。そのため、複数のM&A仲介会社に相談し、業界に精通した信頼性の高い会社を選ぶことが重要です。
- 利益相反のリスクがある
多くのM&A仲介会社は、売り手と買い手の双方を同時に担当する「両手仲介」の形式を採用しています。この場合、どちらの利益を優先すべきかが曖昧になりやすく、特に買い手企業寄りの提案がなされるリスクも否定できません。利益相反の可能性を意識した上で、冷静に交渉を進めることが求められます。
- 情報は複数の仲介会社から集める
仲介会社ごとに持っている業界知識や過去の取引実績は異なります。1社の意見や提示価格だけをうのみにするのではなく、複数の仲介会社に問い合わせて、情報を比較・検討することが客観的な判断につながります。
- 提示価格を鵜呑みにしない
仲介会社の中には、経営者の関心を引くために、「この価格で売れます」とやや高めの価格を提示する業者も存在します。しかし、その価格が必ずしも市場の実勢価格を反映しているとは限らず、後の交渉で大幅に下方修正されるケースも珍しくありません。提示された価格をうのみにせず、他の情報源と照らし合わせながら、冷静に判断することが大切です。
M&Aの成功事例
M&Aは近年活発に行われており、2024年のM&A件数(適時開示ベース)は前年比14%増の1,221件となり、2007年の1,169件を上回って17年ぶりに記録を更新しました。主なM&Aの成功事例は次のとおりです。
- サイバーエージェントによるニトロプラスの買収
- 日清紡ホールディングスによる日立国際電気の買収
- NTTによるNTTドコモの買収
それぞれ詳しく解説します。
サイバーエージェントによるニトロプラスの買収
2024年、サイバーエージェントはニトロプラスの株式72.5%を約167億円で取得し、連結子会社化しました。高いコンテンツ力を活用し、オリジナル作品によるユーザー増や収益性向上を狙った買収です。
日清紡ホールディングス株式会社による日立国際電気の買収
2023年、日清紡ホールディングスは、無線・映像機器を手がける日立国際電気の株式80%を約370億円で取得し、子会社化を決定しました(取得分は192億円)。DXの進展による通信需要の拡大を見据えたもので、日本無線との技術・販売面での補完強化が期待されています。
NTTによるNTTドコモの買収
2020年、NTTはNTTドコモの残り株式をTOBで取得し、完全子会社化を発表しました。買収総額は約4.3兆円で、国内最大規模のTOBとなりました。グループ資源を集約し、法人サービス強化や新たなライフスタイル支援を図る戦略です。
M&Aの相場価格に関するQ&A
最後に、M&Aの相場価格に関するよくある質問とその回答を紹介します。
休眠会社の相場価格はどのくらいか
そもそも「休眠会社」とは、現在は事業活動を行っていない企業を指します。便宜上、次の2種類に分類されます。
- 看板用休眠会社:過去の経歴が不明瞭だったり、預金口座に動きがあったりするなど、使用履歴に一定のリスクがある会社。
- 事業用休眠会社:経歴に問題はなく、単に長期間にわたって活動を停止している会社。
譲渡価格はあくまで交渉によって決まりますが、一般的な相場は次のとおりです。
- 資本金1,000万円以上の有限会社:約30万円程度
- 看板用休眠会社(株式会社):約30~50万円程度
- 事業用休眠会社(株式会社):約35~65万円程度
譲渡価格は登記情報や履歴、納税状況などにより変動します。
赤字でも売却可能か
赤字企業でも、条件次第で売却は可能です。M&Aでは将来性や事業価値が重視されるため、技術や顧客基盤に魅力があれば買い手が見つかることもあります。ただし、黒字企業に比べて譲渡価格は下がりやすく、売却の判断は早めが重要です。遅れると資産価値や信頼性が下がり、売却が困難になる恐れもあります。
買い手企業は、適正価格よりも安く買収すべきか
買収価格を安く抑えることは一見有利に見えますが、適正価格を大きく下回ると売り手の不信感を招きかねません。M&Aは人・事業・文化の引き継ぎを含む取引であり、双方が納得できる譲渡価格での合意が、統合後の協力関係や従業員の士気維持にもつながります。長期的成功のためには、譲渡価格よりも誠実な交渉と信頼構築が重要です。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
M&Aの相場について、正確な価格を把握するのは難しいかもしれませんが、この記事を通じて、どのような要素が価格に影響を与えるのか、どのようにしてその価格が決まるのかを理解する手助けとなったでしょう。財務状況や無形資産、市場の動向、そして企業の戦略など、さまざまな要因が絡み合い、最適な価格が形成されます。これらの要素をしっかりと把握し、適切な準備をすることで、M&Aを成功に導くことができます。
今後、M&Aを検討される方は、まずは自社の強みや成長性を明確にし、外部の専門家の意見を取り入れながら、最適な戦略を練ることが重要です。M&Aをご検討の際には、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の状況に応じた最適なプランをご提案し、貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。