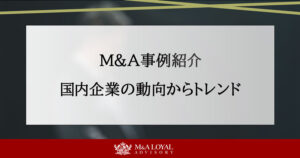神奈川県でM&A相談のおすすめは?動向や補助金、事例を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
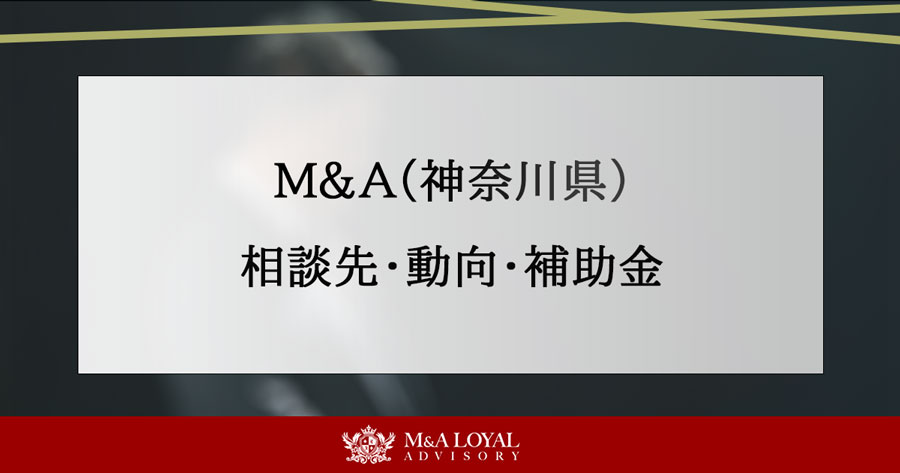
神奈川県でM&Aの相談をしたいが、どこに相談すれば良いか分からない…そんな不安をお持ちではありませんか? 実際に多くの経営者が同じ悩みを抱えており、信頼できる相談先を見極めることがM&A成功の第一歩です。
本記事では、神奈川県の経済・M&A動向や相談先、利用できる補助金制度、事例、成功のためのポイントまで詳しく解説しています。
目次
神奈川県の経済・M&A動向
まず、神奈川県の経済状況やM&Aの動向について紹介します。
神奈川県の経済状況
神奈川県の人口は2025年7月現在、9,222,299人であり、都道府県の総人口ランキングで第二位です。また、令和4年度の神奈川県の名目県内総生産は35兆1,594億円です。前年度と比較し0.6%減少し、実質成長率は+0.9%でした。
県民所得は29兆3,635億円で、前年度から1.1%減少し、一人当たり県民所得は318万円(同1.1%減)となりました。支出面では名目県民総所得は42兆4,222億円(同0.3%増)です。 米ドルに換算すると2,597億ドルに相当し、フィンランド(2,819億ドル)やポルトガル(2,552億ドル)のGDPに匹敵します。
神奈川県では、情報通信業や金融・保険業、サービス業などを含む第三次産業が中心となっており、全有業者に占める第三次産業の割合は79.0%と、全国平均の73.4%を上回り、東京都(84.6%)と沖縄県(81.7%)に次いで高水準です。
神奈川県のM&Aの数
令和3年度に神奈川県内に所在する企業が関与したM&A件数は、売却(譲渡)が192件、買収(譲受)が164件でした。 都道府県別では東京都が最多で、大阪府、愛知県が続き、神奈川県は第4位です。全国的にもM&A件数が多い地域であることが分かります。
神奈川県の休廃業件数
2024年に神奈川県内で休廃業・解散した企業(個人事業主含む)は4,416件で、前年から21.7%増加しました。休廃業・解散率は5.86%となり、東京都(7.71%)に次ぐ高い水準で、全国的にも上位に位置しています。
背景には、資産超過や黒字であった企業の休廃業割合の低下、高齢経営者の休廃業の増加(平均年齢72.8歳)、そしてエネルギー価格の高騰や後継者不足といった複合的な経営環境の悪化があるとみられます。
神奈川県の後継者不在率
2024年の神奈川県における後継者不在率は60.5%で、前年から3.1ポイント低下し、調査開始以来の過去最低となりました。減少は7年連続で、コロナ禍前の2019年と比べても11.9ポイント下がっており、改善傾向が明確に見られます。
この背景には、官民が連携した事業承継相談窓口の広がりや、支援メニューの多様化・強化によって、従来は支援の網が届きにくかった小規模事業者にも機会が提供されるようになったことがあります。加えて、自治体や地域金融機関による積極的な周知活動が、事業承継の重要性を広く浸透させたことも後押ししています。
一方、神奈川県の後継者不在率は全国平均(52.1%)より8.4ポイント高く、都道府県別では大分県(61.3%)に次ぐ8番目の高さとなっており、依然として高い水準にある状況です。
神奈川県の企業のM&A相談先
神奈川県の企業がM&Aを検討した際に、相談する団体や企業は次のとおりです。
- M&A仲介業者
- メインバンク
- 税理士事務所
- メインバンク以外の金融機関
- 公的機関
それぞれ相談先のメリットと注意点を解説します。
M&A仲介業者
専門性と案件情報の豊富さから、M&A仲介業者も多く利用されています。
神奈川県では、東京都内に本社を置く業者も含めさまざまM&A仲介会社を利用可能です。売り手・買い手双方の条件調整から契約、クロージングまでを一貫して支援でき、税務・法務との連携も整備されています。成功報酬型が多く、初期費用を抑えやすい点も魅力です。
一方で、仲介型は売り手・買い手双方を同時に支援するため、自社に有利な助言が得られにくい場合があります。成約優先で進行するリスクや報酬体系の不透明さを避けるため、事前の契約内容や担当者実績の確認が欠かせません。
神奈川県のM&A無料相談はM&Aロイヤルアドバイザリー
M&Aロイヤルアドバイザリーは、中小企業を中心とした多様な業界での成約実績を持つM&A仲介会社です。オーナー様のご決断に寄り添うコンサルタント、買手企業様とのマッチングを担当する提携支援部、会計士・税理士を中心としたコーポレートアドバイザリー部など、初期段階からご成約まで各プロセスの専門人材が分業体制でサポートするのが特徴です。
さらに完全成果報酬型であり、着手金や中間報酬は一切いただいておりません。相談料も無料のため、M&Aのセカンドオピニオンとしてご相談いただく経営者様も増えております。お気軽にご相談ください。
また、弊社では代表取締役社長・橋場 涼に直接相談ができる窓口を期間限定でご用意しております。事業承継に関するご質問であれば何でもご相談可能ですので、下記バナーよりお問い合わせください。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



メインバンク
神奈川県の企業がM&Aで最も多く相談する相談先は、日頃から取引のあるメインバンクです。
自社の財務状況や資金繰りを把握しているため、買収資金の融資や財務戦略に関する具体的な助言を受けやすい点が強みです。都市銀行や地方銀行、信用金庫など幅広い選択肢があり、ネットワークを活用した買い手・売り手マッチングも可能です。
例えば、横浜銀行ではM&A支援の対応力を高めるために、案件発掘・マッチング・クロージングの3チーム制を導入しました。その成果として、2024年度の成約件数は前年度比約34%増の47件に達し、体制の拡充が支援力と実効性の向上につながっていることが示されています。
一方で、多くの金融機関は案件規模の下限を設定しており、小規模案件は対象外となる場合があります。借入先ゆえに戦略を開示しにくい心理的負担や、成功報酬を含めたコストの高さも課題です。初回相談は無料でも、契約後は数千万円規模の費用が発生するケースがあります。
税理士事務所
次に多い相談先は税理士事務所です。
会計・税務の専門家として、財務デューデリジェンスや企業価値評価、節税戦略の立案に強みがあります。長年の顧問契約があれば財務状況を熟知しており、スムーズな初動が可能です。税制優遇措置の適用可否やスキーム選定など、高度なアドバイスも期待できます。
ただし、相手先探索や契約交渉は専門外であるため、M&A仲介業者や金融機関など他機関との連携が必要です。顧問契約内で対応できることもありますが、業務内容や時間単位で追加費用が発生するケースもあります。
メインバンク以外の金融機関
神奈川県では、メインバンク以外の地方銀行や信用金庫、信用組合などもM&A相談先として活用されています。
特定の業種や地域に強いネットワークを持つ場合があり、地元企業同士のマッチングや地域資源を生かした提案が可能です。複数行に相談することで、条件や選択肢の幅を広げられる利点もあります。
ただし、メインバンクと比べると自社の財務状況や事業内容の把握度が低く、情報収集や信用審査に時間がかかることがあります。また、取引関係が薄い場合は、支援範囲や熱量が限定的になる可能性もあります。
公的機関
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターや商工会議所などの公的機関も、M&Aの相談窓口として利用できます。
相談料が無料または低額で、事業承継に関する基本的な情報提供や専門家の紹介、補助金・制度の案内などを受けられる点がメリットです。中立的な立場から助言を得られる点も安心材料です。
一方で、公的機関は案件成約までを直接支援する機能は限定的であり、相手先探索や条件交渉は外部専門家への依頼が必要です。スピード感や高度な交渉力を求める場合は、民間の仲介業者や専門家と併用することが望まれます。
神奈川県でM&Aの相談ができる公的機関
神奈川県でM&Aに関する相談や支援を行っている主な公的機関は、次のとおりです。
- 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター
- 横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)
- 横浜商工会議所
- 神奈川県商工会連合会
- 神奈川県信用保証協会
- 神奈川県よろず支援拠点
- 神奈川県中小企業活性化協議会
それぞれの特徴を詳しく紹介します。
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターは、公益財団法人神奈川産業振興センター(KIP)が運営する公的な相談窓口です。産業競争力強化法に基づき、経済産業省関東経済産業局の委託を受けて設置されており、国の事業として中小企業の事業承継を支援しています。
神奈川県内の中小企業や小規模事業者を対象に、第三者承継(M&A)や親族・従業員承継に関する無料相談を行い、中立かつ秘密厳守で対応します。経験豊富なアドバイザーが企業の現状を踏まえた企業価値評価や承継方法の提案を行い、必要に応じて弁護士や公認会計士、税理士などの専門家と連携します。
また、既に他の支援機関や仲介業者に相談している場合でも、セカンドオピニオンとしての利用が可能で、経営者が納得できる承継・M&Aの実現を後押しします。
横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)
横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)は、中小企業支援法に基づき横浜市長から指定を受けた、市内唯一の「中小企業支援センター」です。公益財団法人として、中小企業の経営基盤の安定や強化、経営革新、新事業の創出や創業支援などを総合的かつ継続的に行い、横浜経済の活性化と地域社会の発展に貢献しています。
事業承継支援では、経営者や後継者向けの無料相談(窓口・訪問)や承継計画策定支援、さらに事業承継やM&Aに関するセミナーを実施しています。相談内容は、後継者への承継手順や株式・資産の移転方法、後継者不在時の事業譲渡、M&Aによる事業買収、後継者バンク登録、事業承継補助金申請など幅広く対応しています。
また、令和5年度には「事業承継助成金」を設け、企業概要書や事業承継計画書、株式評価算定書、企業価値評価書といった事業承継・M&Aに必要な書類の作成費用を最大20万円(費用の50%)助成しました。
さらに、横浜市および株式会社M&Aサクシードと協定を結び、後継者不在の企業に対してM&Aの検討や後継者候補の採用を支援する取り組みも推進しています。金融機関と連携しながら、円滑な事業承継の実現を後押しする体制を整えています。
横浜商工会議所
横浜商工会議所は、商工会議所法に基づき設立された地域総合経済団体であり、法人・個人・団体の会員とともに、横浜地域の商工業振興と発展のために幅広く活動しています。
M&Aや事業承継に関しては、経営相談窓口の一環として対応が可能です。特に、創業・経営革新に関する専門相談や法律相談、デジタル化・SDGs・事業継続計画(BCP)なども相談でき、実態に即した経営課題への助言が期待できます。
また、定期的に開催されるビジネスセミナーや交流イベントを通じて、ネットワークづくりの機会も得られます。
さらに、会員が利用しやすいよう貸会議室や会員交流会、各種共済・保険、販路拡大支援、検定試験などの支援サービスも提供しており、形にとらわれない多角的な支援環境が整っています。
神奈川県商工会連合会
神奈川県商工会連合会は、県内19商工会を会員とする団体であり、商工会の組織や事業についての指導・連絡、意見の取りまとめや行政庁への具申・建議などを通じて、商工会の健全な発達を図り、商工業の振興に寄与することを目的としています。
主な業務には、事業執行の総合調整や各種会議の運営、商工会の組織運営や職員人事・給与管理、経営指導員の認定、事業計画の立案・報告作成といった業務支援課の業務、商工会の支援環境整備や中小・小規模事業者の経営支援、情報化対策、青年部・女性部等の支援、小規模事業者持続化補助金や小規模企業支援強化事業の事務局業務などを担う地域振興課の業務があります。
また、小規模企業サポーターが企業を訪問し、支援施策の情報提供や経営課題のヒアリングを行い、必要に応じて専門家(コーディネーター)の派遣を支援しています。コーディネーターには中小企業診断士や税理士、弁護士、行政書士、社会保険労務士、IT専門家など150名以上が登録されており、1企業につき最大3回まで無料で支援を受けられます。
商工会には、地域に事業所を有し一定の条件を満たす事業者(法人・個人を問わず)が加入でき、会費は中小企業の場合で月額1,000円程度です。
神奈川県信用保証協会
中小企業・小規模事業者の事業資金調達を円滑にするために設立された公的な専門機関で、金融上の「公的な保証人」として機能しています。経営に真摯(しんし)に取り組み、将来の発展可能性を持つ事業者を対象に保証を行っており、県内の中小企業・小規模事業者の約4者に1者が利用しています。
信用保証制度は、中小企業・金融機関・信用保証協会が連携し、申し込みから融資までを支援する仕組みです。返済不能時には協会が代位弁済し、その後事業者が協会に返済します。さらに、原則として信用保証協会80%・金融機関20%でリスクを分担する責任共有制度も設けられています(一部保証制度は対象外)。
さらに、事業承継を支援するための保証制度も用意されています。例えば、一定の要件を満たすことで経営者保証を不要とする「事業承継特別保証」や「経営承継借換関連保証」、持株会社が事業会社の株式を集約化する際に利用できる「事業承継保証」などがあり、円滑な事業承継を後押しします。
加えて、事業承継に向けては専門家派遣制度があり、専門家による「事業承継診断」や「事業承継計画策定」の支援を無料で受けられる仕組みも整っています。
神奈川県よろず支援拠点
「よろず支援拠点」は、国(中小企業庁)が全国に設置している無料の経営相談所です。中小企業・小規模事業者の経営上の課題に対して、専門スタッフが解決策を提案し、成長を支援しています。
神奈川県よろず支援拠点もその一つで、県内の中小企業・小規模事業者に加え、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人など中小企業に類する団体や、創業予定の方まで幅広く利用可能です。売り上げ拡大や経営改善など、多様な相談に無料で対応し、事業者の発展をサポートしています。
神奈川県拠点では、経験豊富なチーフコーディネーターを中心に専門スタッフが相談に対応し、課題の本質を整理した上で解決策を提案します。その後のフォローアップや、必要に応じた他機関・専門家との連携まで一貫してサポートします。さらに、経営相談だけでなく、セミナーやイベントの開催にも積極的に取り組み、参加者にとって知識を深める場やネットワーキングの機会も提供しています。
なお、令和5年度の「よろず支援拠点」全体(全国全ての拠点)の実績としては、43万件以上の相談が寄せられ、相談者の9割超が満足と回答しています。
神奈川県中小企業活性化協議会
神奈川県中小企業活性化協議会は、産業競争力強化法に基づき設置された公正中立な公的機関で、公益財団法人神奈川産業振興センターが関東経済産業局からの委託を受けて運営しています。
中小企業の収益力改善、経営改善、事業再生、廃業・再チャレンジまで幅広い経営課題に対応する「駆け込み寺」として、秘密厳守で相談可能です。初期対応では無料面談を通じて課題を整理し、解決の方向性を助言します。必要に応じて、金融機関出身者や公認会計士、弁護士などによる「個別支援チーム」を組成し、再生計画の策定や実行フォロー、金融機関との調整などを支援します。
支援対象は神奈川県内の中小企業・個人事業者で、規模や業種を問わず利用できます(一部対象外業種あり)。
神奈川県で利用できるM&Aの補助金
神奈川県内の企業が活用できる主なM&A関連の補助金制度は、次のとおりです。
- 神奈川県事業承継補助金(県)
- 小規模事業者事業承継支援補助金(綾瀬市)
- 事業承継・M&A補助金(国)
それぞれの補助金制度について紹介します。なお、紹介している内容は2025年8月時点の情報です。最新情報や詳細は、各サイトにてご確認ください。
神奈川県事業承継補助金(神奈川県)
神奈川県事業承継補助金は、物価高騰や人手不足などの影響により、優れた経営資源を持ちながらも事業継続に課題を抱える中小企業の事業承継を促進し、経営資源や雇用の喪失を防ぐことを目的とした制度です。
令和7年度の補助金の詳細は次のとおりです。
補助対象者
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者
補助事業・補助率等
親族承継枠(株価算定支援):
- 親族への事業承継を目的とし、専門家等と連携する株価算定に係る取り組み
- 補助率:対象経費の2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)
- 補助上限:20万円
第三者承継枠(買い手支援 A):
- 第三者への事業承継に伴い、譲渡者において常時使用していた従業員を引き続き県内で雇用する取り組み(人件費に対する補助)
- 補助率:対象経費の2分の1以内(小規模事業者*は3分の2以内)
- 補助上限:100万円
第三者承継枠(買い手支援 B):
- 第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取り組み(デューデリジェンス費用等に対する補助)
- 補助率:対象経費の2分の1以内(小規模事業者*は3分の2以内)
- 補助上限:100万円
第三者承継枠(売り手支援):
- 第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取り組み(企業価値の算定費用等に対する補助)
- 補助率:対象経費の2分の1以内(小規模事業者*は3分の2以内)
- 補助上限:100万円
*小規模事業者の定義:
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員が5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員が20人以下
- 製造業その他:常時使用する従業員が20人以下
小規模事業者事業承継支援補助金(綾瀬市)
この補助金は、事業承継を検討する際に、事業承継に関する支援機関を活用して事業承継計画を策定する市内の小規模事業者に対し、補助金を交付する制度です。
対象者
- 商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定される小規模事業者
- 主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する「製造業」であること
- 以下の要件を全て満たすこと
- 市内で1年以上継続して事業を営んでいること
- 納期限到来済みの市税を完納していること
- 綾瀬市暴力団排除条例に該当しないこと
- 「あやせ工場スマートナビ」に企業情報を掲載済み、または交付決定までに掲載すること
- 外国人労働者を雇用している場合、日本語学習の機会や支援に努めること
- 「かながわSDGsパートナー」登録に向けた取り組みに努めること
- 除外条件:資本金の2分の1以上を大企業が所有、または役員の2分の1以上を大企業が占めている場合
対象経費
- 事業承継のための事業に必要な経費で、事業承継支援機関へ支払う費用
- 主な対象:
- 初期診断
- 課題分析
- 株価算定
- 事業承継計画の算定支援業務に係る委託料
- 補助金申請年度の3月31日までに事業が完了するものに限る
補助内容
- 経費の2分の1以内
- 上限20万円以内(消費税を除く、千円未満切り捨て)
事業承継・M&A補助金(国)
この補助金は、事業承継やM&Aを契機とした新規取り組みの推進や事業再編・統合に伴う経営資源の継承を支援し、中小企業の生産性向上と雇用維持を図ることを目的としています。
補助対象となる枠組み(支援内容に応じた四つの枠)
- 事業承継促進枠:5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している者を対象に、設備投資等に係る費用を補助
- 専門家活用枠:M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)を対象に、M&Aに係る専門家活用の費用を補助
- PMI(経営統合)推進枠:M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等に係るPMIの取り組みを行う事を対象に、PIMにおける専門家活用に係る費用や設備投資に係る費用を補助
- 廃業・再チャレンジ枠:事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)を対象に、再チャレンジを目的として既存事業を廃業するための費用を補助
補助率・補助上限額の目安
事業承継促進枠
- 補助率:1/2・2/3(中小企業者等のうち、小規模事業者に該当する場合は2/3)
- 補助上限:800万~1,000万円(一定の賃上げを実施する場合、補助上限を800万円から1,000万円に引き上げ)
専門家活用枠
- 補助率:
- 買手支援類型:1/3・1/2・2/3(100億企業要件を満たす場合:1,000万円以下の部分は1/2、1,000万円超の部分は1/3)
- 売手支援類型: 1/2・2/3(①赤字、②営業利益率の低下のいずれかに該当する場合)
- 補助上限:
- 買い手支援類型:600~800万円(800万円を上限に、DD費用を上乗せする場合200万円を加算)、2,000万円(100億企業要件を満たす場合)
- 売り手支援類型:600~800万円(800万円を上限に、DD費用を上乗せする場合200万円を加算)
PMI推進枠
- 補助率:
- PMI専門家活用類型:1/2
- 事業統合投資類型:1/2・2/3(中小企業者等のうち、小規模事業者に該当する場合は2/3)
- 補助上限:
- PMI専門家活用類型:150万円
- 事業統合投資類型:800万~1,000万円(一定の賃上げを実施する場合、補助上限を800万円から1,000万円に引き上げ)
廃業・再チャレンジ枠
- 補助率:2/3または1/2(事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用申請する場合は、各事業における事業費の補助率に従う)
- 補助上限:150万円(事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用申請する場合は、それぞれの補助上限に加算)
補助対象経費の例(枠に応じて異なる)
- FA・仲介手数料
- デューデリジェンス(DD)費用
- 表明保証保険料
- PMIに伴う専門家支援費用など
神奈川県のM&A事例
最近の神奈川県のM&Aの事例を紹介します。
安田倉庫株式会社 × エーザイ株式会社(現:安田ロジファーマ)
東京都港区に本社を置く安田倉庫株式会社は、エーザイ株式会社(本社:東京都文京区)の完全子会社であるエーザイ物流株式会社(本社:神奈川県厚木市)の全株式を取得し、2023年3月31日付で連結子会社化しました。
エーザイ物流は1991年の設立以来、医薬品物流を中心にエーザイグループ製品の安定供給を担い、さらにサードパーティ製品の取り扱いにも対応する専門ノウハウを蓄積してきました。今回のグループ化により、安田倉庫は医療用医薬品配送ネットワークと倉庫運営力を生かし、メディカル物流事業の拡充とサービス向上を図っています。
さらに、2023年10月1日付で商号を「安田ロジファーマ株式会社」へ改め、グループとしての一体感を高めるとともに、医薬品物流分野におけるブランド力と事業シナジーの強化を図っています。
参考:エーザイの子会社であるエーザイ物流を安田倉庫に譲渡する契約を締結
株式会社ロピアホールディングス × 株式会社スーパーバリュー
神奈川県川崎市に本社を置く株式会社ロピア・ホールディングスは、埼玉県などで食品スーパーや都市型スーパーセンターを展開する株式会社スーパーバリューに対し、2022年8月31日付で第三者割当増資を引き受け、出資比率を51.62%に引き上げて子会社化しました。さらに2023年2月には、追加で39億円を出資し、出資比率を66.60%へ拡大しています。
この出資拡大により、ロピア・ホールディングスはスーパーバリューへの財務・運営両面での支援体制を一層強化し、両社は物流センターの共同活用や店舗運営プロセスの最適化を推進しています。これらの施策により、商品の品質安定や作業効率の向上、従業員の生産性改善が進められています。
さらに、販売力を向上させるために商品ラインアップを一元化し、PB商品の導入によって販路を拡大しています。加えて、2023年2月期には販売費および一般管理費を前年同期比97.2%に抑えるなど、コスト削減の取り組みも進めています。
参考:日本経済新聞|スーパーバリュー、ロピアHDから39億円調達 再び増資
株式会社WOWOWコミュニケーションズ × 株式会社cinra
神奈川県横浜市に本社を置く株式会社WOWOWコミュニケーションズは、東京都千代田区に本社を置くインターネットメディア運営企業、株式会社cinraの全株式を取得し、2024年10月1日付で子会社化しました。株式譲渡契約の締結および譲渡実行はいずれも同日に行われています。
cinraは2003年創業のメディアカンパニーで、自社メディアの企画・運営の他、ウェブサイトの広告企画・制作、イベント企画、動画制作などを手掛けています。
この資本業務提携の狙いは、WOWOWが掲げる中期経営計画に沿って、中長期的な企業成長と新規事業創出を含む投資戦略を推進する一環であり、デジタルマーケティング分野での事業価値の最大化を見据えたものです。
WOWOWコミュニケーションズは、cinraのブランド構築力やメディア事業と、自社が展開するコンタクトセンター、データマーケティング、デジタルマーケティング事業を組み合わせ、一気通貫のサービス提供を進める方針です。
参考:WOWOW|連結子会社による株式取得(孫会社化)に関するお知らせ
北陸電気工事株式会社 × 株式会社日建
富山県富山市に本社を置く北陸電気工事株式会社は、神奈川県横浜市に本社を置く株式会社日建の株式取得および子会社化を目的とした株式譲渡契約を、2023年11月30日に開催した取締役会で決議しました。取得株式数は106,300株で、取得後は議決権の100%を所有する完全子会社となります。譲渡実行日は2023年12月5日です。
日建は1981年3月設立で、神奈川県横浜市を拠点に空調・給排水管などの管工事を主体に電気工事も手がける設備工事の事業者です。北陸電気工事は、地域に根ざして電気・管工事などの設備工事を手掛け、10月には中期経営計画「アクションプラン2024」を策定して、関東方面への商圏拡大を目指しています。そのため、今回の子会社化は、この計画の達成に寄与すると判断し、実行されました。
譲渡後の日建は、中期経営計画の中で関東への商圏拡大に向けた業容強化の一翼を担い、経営基盤の強化・展開の加速を図る方針です。また、取得による2024年3月期からの連結子会社化に関しては、その後の業績や影響について現在精査中で、今後も必要に応じて公表される予定です。
参考:北陸電気工事株式会社|株式取得(子会社化)に向けた株式譲渡契約締結のお知らせ
株式会社コメ兵ホールディングス × 株式会社アールケイエンタープライズ
愛知県名古屋市に本社を置く株式会社コメ兵ホールディングスは、神奈川県横浜市に本社を構える株式会社アールケイエンタープライズの株式を取得し、2024年10月23日付で子会社化しました。
アールケイエンタープライズは、1954年に横浜で創業した企業で、ハイブランド品のリユース事業を手がけています。小売・EC事業を展開し、国内市場にとどまらず海外にも販路を広げている点が特徴です。
今回のM&Aにより、コメ兵ホールディングスはアールケイエンタープライズの経営資源を取り込み、神奈川エリアを中心とした買取・小売の強化や、オークション事業拡大に伴う法人チャネルの拡充を図ります。さらに、相場変動が大きい時計商材における対応力を高めることで、ブランド・ファッション事業の成長スピードを加速させ、競争力の強化につなげる狙いです。両社のシナジーを最大限に生かし、中期経営計画の達成とグループ全体の企業価値向上を目指しています。
参考:株式会社コメ兵ホールディングス|株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
神奈川県でM&Aを成功させるポイント
売り手・買い手がそれぞれの立場でM&Aを成功に導くために、押さえておくべき重要なポイントは次のとおりです。
- 【共通】M&Aの目的と条件を整理する
- 【共通】信頼できる専門家をパートナーに選ぶ
- 【共通】関係者の理解と協力体制を築く
- 【売り手側】自社の現状を客観的に評価・改善する
- 【売り手側】情報開示と準備を万全に整える
- 【売り手側】売却のタイミングを見極め、早期に動く
- 【買い手側】リスク把握のための徹底調査を行う
- 【買い手側】高い相乗効果が期待できる相手を見つける
- 【買い手側】PMI(統合プロセス)を計画的に進める
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
【共通】M&Aの目的と条件を整理する
M&Aはゴールを誤ると期待した成果が得られません。
事業承継による存続やシェア拡大、新規事業への参入など、自社が何を優先すべきか明確にし、譲れない条件と柔軟に調整できる条件を切り分けることが重要です。
目的が明確であれば、交渉過程での判断軸もぶれにくくなり、結果として円滑な取引につながります。
【共通】信頼できる専門家をパートナーに選ぶ
法務・税務・財務に加えて、M&Aの実務経験を持つ専門家の関与が不可欠です。
神奈川県は全国的にもM&A件数が多い地域であり、地域に精通した専門家や仲介業者が多数存在します。
こうした専門家を早期に選定することで、買い手・売り手双方にとって公平で透明性のある取引を実現できる可能性が高まります。
【共通】関係者の理解と協力体制を築く
M&Aは経営者だけでなく、従業員や取引先、金融機関など多くの関係者に影響します。 早い段階から丁寧な説明と合意形成を図ることで、取引後の混乱や不安を最小限に抑えられます。
また、神奈川県のように産業集積が進んだ地域では、取引先や地域社会との関係性も重要視されるため、信頼関係を築く姿勢が成果に直結します。
【売り手側】自社の現状を客観的に評価・改善する
財務諸表だけでなく、組織体制や強み・弱みを第三者の視点で評価することが必要です。
神奈川県は製造業やサービス業など幅広い業種が集積しており、買い手にとっての魅力を高めるには、業界特性に応じた改善が効果的です。
現状把握のプロセスを通じて、自社がM&A市場でどのように見られているかを知ることもでき、戦略的な交渉に生かせます。
【売り手側】情報開示と準備を万全に整える
買い手は不透明な点があるとリスクを感じ、条件面で不利になることがあります。
財務・契約・労務・知的財産などの情報を整理し、タイムリーに開示できる体制を整えることで、取引の円滑化につながります。
適切な情報開示は、信頼構築や取引スピードの加速にも寄与し、結果として希望に沿った条件での成約を実現しやすいです。
【売り手側】売却のタイミングを見極め、早期に動く
業績が安定している時期に準備を始めることが、条件面で有利に働きます。
神奈川県は上場企業の数でも全国上位に位置しており、資本提携や事業譲渡の候補先が豊富です。
早めに準備を進めることで複数の候補から比較検討でき、より自社にとって望ましい相手を選べる余地が広がります。
【買い手側】リスク把握のための徹底調査を行う
買収後のリスクを抑えるためには、財務・法務・税務・人事など多方面の調査が不可欠です。
特に神奈川県では多様な規模・業種の企業が集中しているため、事業内容に応じて調査項目をカスタマイズすることが求められます。
徹底した調査は、統合後に顕在化しうる問題を事前に察知し、想定外のコストを回避する効果もあります。
【買い手側】高い相乗効果が期待できる相手を見つける
規模の拡大だけでなく、自社の強みと相手の強みを組み合わせて生まれる相乗効果を意識することが重要です。
神奈川県は首都圏の大市場に位置しており、販売チャネルの拡大や物流効率化など、地理的優位を生かしたシナジーも期待できます。
実際の効果を定量的に試算することが、適切なパートナー選びの指標となります。
【買い手側】PMI(統合プロセス)を計画的に進める
M&Aの成功は契約締結後の統合プロセスにかかっています。
人材の定着やシステム統合、企業文化の融合などを計画的に進めることで、想定した成果を実現できます。
PMIをおろそかにすると、せっかくのM&Aが逆に業績悪化を招くリスクもあるため、最初の段階から統合計画を策定することが不可欠です。
M&Aの相談に関するQ&A
最後に、神奈川県のM&Aに関するよくある質問とその回答を紹介します。
神奈川県のM&Aではどの業界が活発か
帝国データバンクの調査によると、神奈川県では大企業のM&A実施率が17.9%と全国平均(14.1%)を大きく上回っており、積極的な再編や成長戦略の一環としてM&Aを活用する動きが鮮明です。
一方、中小企業の実施率は8.3%で全国平均(8.5%)と同水準にあり、事業承継や経営基盤の強化を目的としたM&Aが一定程度進められています。
業界別にみると、金融業界(20.0%)が最も高く、次いで卸売業(12.8%)、サービス業(10.1%)と続きます。特に金融業では、グループ戦略や業界再編の影響から県内でもM&Aが多く行われており、存在感が際立っています。
神奈川県でM&Aをする際の注意点はあるか
神奈川県でM&Aを進める際は、悪質な買い手や仲介業者への警戒が必要であり、中小企業庁の登録制度を通じた信頼性の確認が欠かせません。
買い手が金額面を重視する一方、売り手は従業員の処遇を優先する傾向があるため、雇用や待遇の維持について十分な説明と合意形成を行うことが重要です。
また、県内ではM&Aの経験や準備が進んでいない企業も多く、早期の情報収集や専門機関への相談が成功の鍵といえます。
M&Aの基本的な流れを知りたい
一般的な流れは次のとおりです。
- 事前相談・経営状況の整理
- 企業価値評価
- 買い手・売り手候補の探索
- 条件交渉・基本合意
- デューデリジェンス(詳細調査)
- 最終契約・クロージング
神奈川県のM&Aの相場はどのくらいか
相場は業種・規模・収益性によって大きく異なります。小規模事業の場合は数百万円〜数千万円、中堅規模以上では数億円規模の取引も珍しくありません。
神奈川県は製造業やサービス業の案件が多く、地域内ネットワークを活用した成約が多い傾向です。
具体的な金額は企業価値評価(バリュエーション)によって算出されるため、早期に専門家へ査定を依頼することが推奨されます。
神奈川県でM&Aを検討してる際のおすすめの相談先はどこか
神奈川県では、公的機関から民間仲介業者まで幅広い相談先があります。
公的機関では「神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター」が無料で専門家相談を提供しています。
民間ではM&A仲介会社や金融機関(地銀・信用金庫)、税理士・公認会計士事務所などが実務支援を行います。初期段階では複数の相談先から意見を聞くことが推奨されます。
「M&A」と「事業譲渡」の違いは何か
M&Aとは、広く「企業の合併や買収などを含む経営統合の総称」を指します。狭義のM&Aでは、経営権や資本の移転を伴う「株式譲渡」や「合併」「会社分割」などが代表的な手法です。一方、広義のM&Aには資本移動を伴わない「資本提携」や「合弁会社設立」も含まれます。
事業譲渡は、企業の一部または全部の事業を譲渡する手法であり、「狭義のM&A」に含まれるケースが一般的です。譲渡されるものは、土地・設備・顧客・ノウハウなど、有形・無形を問わず事業に関連する資産・負債一式です。
一般的なM&Aのメリット・デメリットは何か
メリットには、売り手側では事業承継の実現や創業者利益の確保、従業員雇用の維持などがあります。買い手側では新規市場の獲得や既存事業とのシナジー効果、短期間での事業拡大が挙げられます。
デメリットとしては、条件交渉や契約締結までに時間がかかることや買収後の統合リスク、取引コストの負担などがあり、事前準備と専門家の関与が重要です。
M&AのサポートならM&Aロイヤルアドバイザリーへ
M&Aは会社の未来を左右する大きな決断です。適切な相談先を見つけることで、安心して進めることができます。神奈川県には、地元の経済状況に精通した専門家や公的機関がたくさんあり、初めての方でも心強い味方になってくれるでしょう。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、経験豊富なアドバイザーが、M&Aの検討からマッチング、実行、契約まで全面的にサポートいたします。相談は無料ですので、M&Aに関心をお持ちの中小企業の経営者様はお気軽にご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。