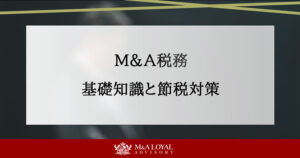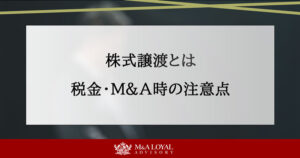M&Aにおける税金とは?税金の仕組み、節税方法・対策、注意点を詳しく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
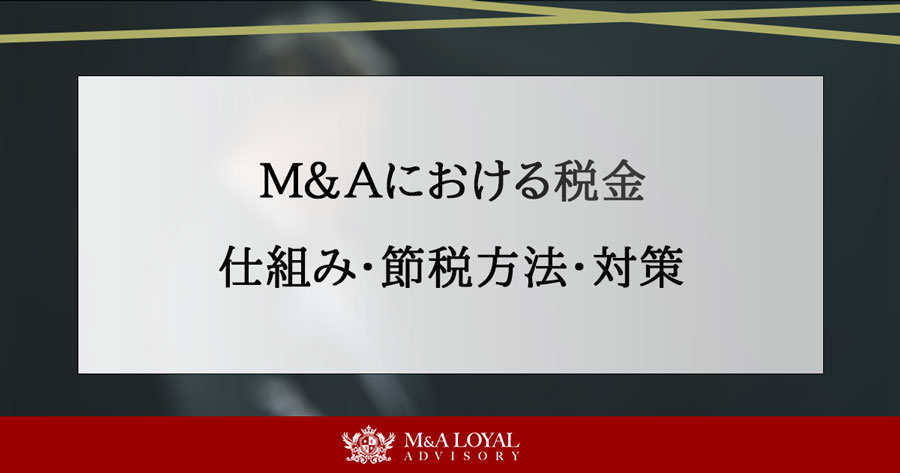
M&A(合併・買収)を行う際、税金は避けて通れない重要な要素です。取引の進行に伴い、企業や個人が負担する税金の種類やその計算方法、税務上の戦略は、M&Aの成否に大きな影響を与えることがあります。
そこでこの記事では、M&Aにおける税金の仕組みや、税金対策、個人と法人の違い、注意すべきリスクについて詳しく解説します。
また、SPA(株式譲渡契約書)を利用するM&Aにおける税務の特徴についても触れ、実務で役立つ情報をご提出。企業がどのように税金を最小化し、最適なM&A戦略を立てるべきかについてもご紹介します。
【安心の完全成果報酬型!M&Aについての無料相談フォームはこちら】
目次
M&Aにおける税金の基本
M&Aにおいて、税金は企業経営にとって重要な要素です。M&A取引を進める際に発生する税金は、売り手や買い手の税務戦略に大きな影響を与え、最終的には取引の成功に関わります。
そのため、M&Aを実施する企業は、適切な税務戦略を立て、最小限の税金負担で取引を行うことが求められます。
M&A取引での税金には、さまざまな種類があり、それぞれの税金の仕組みや課税方法を理解することが重要です。特に、企業や個人が負担する税金がどう計算されるか、どのタイミングで税金が発生するかを把握することで、取引後のリスクを減らすことができます。
M&Aにおける主な税金の種類
M&A取引において発生する代表的な税金は、以下の通りです。
■法人税
企業がM&Aを行う際には、譲渡した資産や株式に対して法人税が課税されます。特に、株式譲渡の場合、譲渡益に対して法人税が課税されます。
■消費税
事業譲渡の場合、譲渡対象の事業や資産の引き渡しに対して消費税が発生します。事業譲渡を行う際は、消費税の計算が重要なポイントとなります。
■所得税
個人が企業の株式を譲渡した場合、個人所得税が課税されます。特に、事業の承継に伴う譲渡は、税務上の考慮を十分に行う必要があります。
■譲渡所得税
株式の売買や資産譲渡において、譲渡所得税が発生します。この税金は、譲渡益に基づいて課税されるため、M&A後に税務申告を行う際に重要な要素です。
個人と法人のM&Aにおける税金
M&Aにおける税金は、個人と法人では大きく異なります。それぞれのケースにおいて、税金の取り扱いや負担が異なるため、理解しておくことが重要です。
以下では、個人と法人の税金の違いを詳しく解説します。
個人の株式譲渡にかかる税金(一律20.315%)
個人がM&Aを通じて株式を譲渡する場合、譲渡益に対して税金が課せられます。この税金は譲渡所得税として一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)が課税されます。
- 株式譲渡益の計算方法
株式譲渡益は、譲渡価格から取得費(購入時の株価)や譲渡費用(取引にかかる手数料など)を差し引いて計算されます。その差額に対して、上記の税率が適用されます。
■計算式:株式譲渡益=譲渡価格-取得費-譲渡費用
- 譲渡価格:株式を売却した金額
- 取得費:株式の購入時に支払った金額(購入代金や購入時の手数料など)
- 譲渡費用:売却時にかかった費用(M&A仲介手数料、弁護士費用、証券会社手数料など)
この計算で得られた譲渡益に対して、20.315%の税率を掛けて納税額を算出します。
■計算式:税金額=(譲渡価格−取得費−譲渡費用)×20.315%税金額=(譲渡価格−取得費−譲渡費用)×20.315%
■例:
- 譲渡価格:1,000万円
- 取得費:300万円
- 譲渡費用:50万円
(1,000万円−300万円−50万円)×0.20315=650万円
650万円×0.20315=132万475円
上場株式・非上場株式の違い
上場株式と非上場株式いずれも、計算方法や税率は基本的には同じですが、特定の条件下や評価方法、譲渡に関する特別なルールが適用されることがあります。また、非上場株式において取得費が不明な場合には、譲渡価格の5%を取得費とみなす特例があります。
税務申告の注意点
個人が株式譲渡を行った場合、確定申告を通じて税務申告を行う必要があります。税務署に正確な譲渡益を申告しない場合、ペナルティが課される場合もあるため、確定申告を行うことが重要です。
税務対策
株式譲渡による譲渡益を減少させるための対策として、取得価額を正確に算出したり、譲渡前に保有株式の評価額を見直したりする方法があります。また、損失が出た場合には、他の所得と相殺して税負担を軽減することも可能です。
法人の株式譲渡にかかる税金
法人が株式を譲渡した場合、譲渡益に対して法人税が課税されます。法人の場合、株式譲渡による譲渡益は企業の通常の所得(益金)として計上され、他の事業所得と合算して法人税等が課されます。
■法人税率
法人税率は企業の規模や所得金額によって異なります。
- 原則として法人税率は23.2%ですが、資本金1億円以下の中小法人については、所得金額のうち年800万円以下の部分に15%の軽減税率が適用されます。
- これらに加えて、法人住民税や事業税なども課税されるため、実効税率はさらに高くなります。
法人が株式譲渡益を得た場合、株式譲渡益は法人全体の課税所得に含まれ、その課税所得に対して法人税が課税されます。日本の法人税は基本的に一律の税率(例えば、23.2%)が適用されますが、地方税や事業税を加えると、実効税率が29%から42%程度に達する場合もあります。このため、株式譲渡益に関する税務処理は慎重に行う必要があります。
■法人譲渡益の計算方法
法人の株式譲渡益は、譲渡価格から取得費や譲渡にかかった費用を差し引いた金額(譲渡益)として計算されます。この譲渡益が他の所得と合算され、法人税等の課税対象となります。税務上、取引の記録や証拠書類を適切に管理しておくことが重要です。
- 譲渡益(利益)の計算
■計算式:譲渡益(利益)=譲渡価格 − 取得費 − 譲渡費用
- 譲渡価格:株式の売却金額
- 取得費:株式の購入金額
- 譲渡費用:売却にかかった手数料など
- 法人税額の計算
■計算式:税金額 = 譲渡益 × 法人税率(+住民税・事業税等)
- 法人税率は原則23.2%(中小法人の所得800万円以下は15%)
- 実際には、法人住民税や事業税も加算されますが、ここでは法人税のみで計算します
■税務申告の注意点
法人も毎事業年度ごとに確定申告が必要です。株式譲渡益を正確に計算し、決算書や法人税申告書に適切に反映させる必要があります。誤った申告を行うと、税務調査で追徴課税やペナルティを受ける場合があるため、正確な申告が求められます。
■法人の税務対策
法人の税務対策としては、譲渡益を適正に把握するために資産評価の見直しや、事業再編成の実施などが考えられます。また、法人の税務管理がしっかり行われていることは、M&Aや企業価値向上にも大きな影響を与えます。
※実際の税額計算は、他の所得や損益通算、繰越欠損金なども影響するため、詳細は税理士等の専門家にご相談ください。
【安心の完全成果報酬型!M&Aについての無料相談フォームはこちら】

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



M&Aにおける税金の対策
M&Aを行う企業にとって、税金対策は非常に重要な要素です。適切な税務戦略を講じることで、税負担を最小限に抑え、企業の成長を支えることができます。
以下では、M&Aを実施する際に考慮すべき税金対策について解説します。
税務上有利なM&Aの形態選び
M&Aを行う際には、取引の形態によって税金が大きく異なります。株式譲渡と事業譲渡は、それぞれ税務上の取り扱いが異なるため、どちらを選択するかが重要な決定要素となります。
- 株式譲渡のメリット
株式譲渡では、譲渡益に対して法人税が課税されることになりますが、取引後の企業統合がスムーズに進行するため、買い手と売り手の両方にとってメリットがあります。特に、譲渡後の資産や負債がそのまま引き継がれるため、事業再編が容易に進みます。
- 事業譲渡のメリット
事業譲渡は、譲渡する事業や資産に対して消費税が発生する可能性がありますが、負債を切り離せるため、買い手にとってはリスクを減らすことができます。特に、企業の不良資産を取り除くことができ、税務上の調整が柔軟に行える場合があります。
事前の税務調査とアドバイザーの活用
M&Aの実行前に、税務調査を行うことは非常に重要です。事前に税務調査を行い、どのような税務負担が発生するのかを把握することで、最適な税務戦略を選定することができます。
また、税理士やM&Aアドバイザーとの連携も大切です。専門家のアドバイスを受けることで、税務戦略を効果的に立て、最適なタイミングでの取引を進めることが可能です。
事前に税務面をクリアにしておくことで、M&A後の問題を未然に防ぎ、スムーズな取引を実現できるでしょう。
【安心の完全成果報酬型!M&Aについての無料相談フォームはこちら】
M&Aにおける税金のリスクと注意点
M&Aを行う際には税金面でのリスクもあります。適切な税務対策を講じていない場合、取引後に予期しない税負担が発生することがあり、そのリスクを避けるためには十分な事前準備と注意が必要です。
以下では、M&Aにおける税金のリスクとそれに対する注意点を解説します。
税務上の予期しない負担
M&Aにおいて、予期しない税務負担が発生することがあります。特に事業譲渡の場合、事業や資産の譲渡に対して消費税が発生するため、その計算が非常に重要です。
事業譲渡時に消費税を適切に計算していないと、想定以上の税負担を抱えることになり、企業にとって大きなリスクとなります。さらに、譲渡後に発覚した不適切な税務処理により、追加で税金を支払う羽目になる可能性もあります。
こうした問題を避けるためには、M&A実行前に税務面でのチェックを徹底し、必要な対策を取ることが不可欠です。
税金対策の失敗が引き起こす問題
M&Aにおける税金対策を誤ると、後々大きな問題を引き起こすことがあります。
例えば、譲渡所得税や法人税に関して、適切な税務戦略を立てていない場合、予想以上の税負担が企業に課せられることがあります。これにより、M&A取引後の経営に影響を与えることになり、事業計画が狂ってしまうことがあります。
また、税務申告の誤りやデューデリジェンス不足によって、取引後に追加の税金支払いを求められる場合もあります。
このような事態を避けるために、M&A実施前には税理士やアドバイザーと協力し、十分な事前調査を行っておくことが重要です。
【安心の完全成果報酬型!M&Aについての無料相談フォームはこちら】
節税方法とその実践
M&Aにおける税金対策は、税負担を最小限に抑えるための重要なステップ。税金が予想以上にかかることを避け、効率的に取引を進めるためには、節税方法を活用することが大切です。
以下では、M&Aにおける主な節税方法と、それらを実践するためのアプローチについて解説します。
M&Aにおける節税方法
M&Aにおける節税方法は、取引の形態や企業の状況によって異なりますが、いくつかの基本的な方法があります。
- 株式譲渡による節税
株式譲渡では、売却益に対して課税されますが、株式譲渡による所得は譲渡所得税として一律20.315%で課税されるため、税率が固定されています。これに対して、事業譲渡の場合は消費税が発生するなど、税負担が増える場合があります。したがって、株式譲渡を選択することが税金面で有利な場合があります。
- 事業譲渡を活用した節税
事業譲渡では、企業が持っている資産や負債を切り離すことができ、負担を軽減することができます。特に、負債や不良資産を切り離すことができる点で、事業譲渡が有利な場合があります。税金を抑えつつ、企業の負担を軽減したい場合には事業譲渡を選択する方法もあります。
- グループ間での資産譲渡
グループ会社間で資産や事業を譲渡する場合、一定の条件下で譲渡税が軽減されることがあります。グループ間取引を活用することで、税金負担を調整し、効果的な資産移転を行うことが可能です。
税金負担を軽減するための戦略的アプローチ
M&Aにおける税金負担を軽減するためには、戦略的なアプローチが求められます。税務対策を講じることで、税金を最小限に抑えつつ、取引の円滑な進行を実現することが可能です。
- 取引タイミングの選定
M&Aのタイミングを選定することも、税金負担を軽減するための戦略の一つです。例えば、企業の利益が大きくない時期や損失がある場合にM&Aを行うことで、税金の負担を減らすことができます。また、税制改正のタイミングを見越して取引を行うことも、税金の最適化に繋がります。
- 譲渡価格の設定
取引価格を設定する際には、税務面を考慮することが重要です。適切な評価方法を選び、譲渡価格を最適化することで、税負担を軽減することができます。また、譲渡価格に関連する補償条項や、後払いの条件を設定することで、税金の分散が可能です。
- 税務アドバイザーの活用
税金面での戦略的アプローチを行うためには、専門の税理士やアドバイザーを活用することが非常に重要です。税務の専門家と連携し、M&A前にしっかりと計画を立てることで、リスクを最小限に抑え、効率的な取引を実現することができます。
SPA(株式譲渡契約書)と税金
M&Aにおいて、SPA(株式譲渡契約書)は非常に重要な役割を果たしますが、税金との関係にも注意を払う必要があります。SPAの内容が、譲渡益に対する課税やその他の税務処理に直接的な影響を与えるため、税務面をしっかりと管理することが求められます。
SPAと税金の関係
SPAは、買い手と売り手が株式の譲渡条件について最終的に合意した契約書です。この契約に基づいて、譲渡価格や取引条件が決定され、株式の譲渡が実行されます。
税金においては、譲渡益が課税対象となりますが、譲渡価格の設定がそのまま税金計算に影響を与えるため、SPAで記載する内容は慎重に決めなければなりません。
また、譲渡価格や支払方法が税務上どのように扱われるかを事前に確認しておくことも重要です。特に、譲渡益をどのように計上するか、負債や資産の扱いがどのようになるかなど、税務面での確認が必要です。最終的には、SPAに記載された条件に従って譲渡益を計算し、税務申告を行う必要があります。
SPA締結後の税務処理
SPA締結後、買い手と売り手はそれぞれ税務申告を行う必要があります。
売り手は、株式譲渡による譲渡益を申告し、譲渡所得税を支払います。買い手側も、M&A後に取得した株式や資産に関連する税務処理を行う必要があります。
税務処理の重要なポイントとしては、売却益が適切に計算されているか、譲渡価格が市場価格に基づいて適切に設定されているかを確認することです。また、取引後に発生する可能性のある税務リスクや追加費用についても、SPAを通じて明確に定義しておくことが望ましいです。
これにより、税務上の問題を事前に解決し、M&A後の問題を避けることができます。
M&Aにおける税金対策の重要性
M&Aにおける税金は、企業にとって非常に重要な要素であり、税務面での対策を講じることが成功するM&Aのカギとなります。なお、個人と法人で税金の扱いが異なり、M&Aの形態によっても税務戦略が変わるため、事前に十分な調査と戦略が必要です。
そこで、SPA(株式譲渡契約書)を活用することで、譲渡益にかかる税金の取り扱いや責任分担を明確にし、適切に管理することができます。契約書には譲渡価格や資産の特定、税負担の分担に関する条項を含めることができるため、税務上のリスクを軽減する助けとなります。ただし、具体的な税務処理については専門家のアドバイスを受けることが重要です。
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社では、M&Aにおける総合的なアドバイザリーサービスを提供しています。
M&Aの実行前から税務戦略を立て、企業の成長を支援するための最適なアドバイスを行います。まずは無料相談をご活用いただき、専門家によるサポートをご検討されてみてはいかがでしょうか。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。