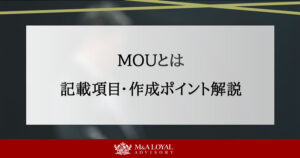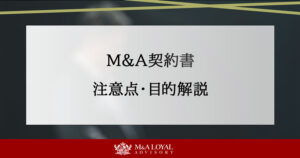M&Aの意向表明書とは?書き方や効力、基本合意書との違いを大公開
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
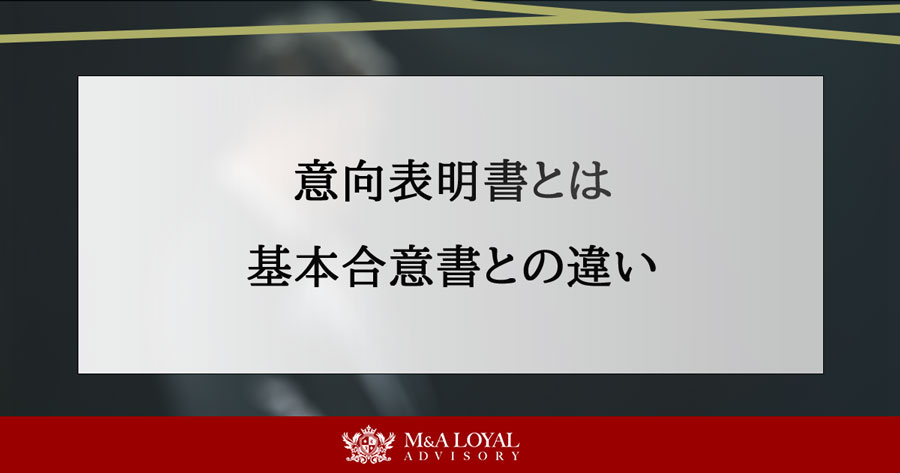
M&Aを検討する際、交渉の初期段階で重要となるものが「意向表明書」です。
これは買い手が取引の基本的な条件や意図を文書で明示するもので、交渉を円滑に進める上での重要な出発点です。法的拘束力は持たないことが一般的ですが、信頼関係の構築や意思確認の面で大きな役割を果たします。
本記事では、意向表明書の目的や基本合意書との違い、そして買い手・売り手それぞれにおけるポイントについて詳しく解説します。
目次
M&Aにおける意向表明書とは
まず、M&Aにおける意向表明書に関する基本的な知識について解説します。
取引の基本条件や双方の意向を文書化したもの
意向表明書(Letter of Intent、LOI)は、M&Aの初期段階で買い手が売り手に対して取引の意思と条件を示す文書です。双方の交渉を円滑に進めるための前提として、買収意向や想定スキームなどを簡潔に示すことで、M&A成約に向けた重要な起点として機能します。
買い手候補が複数いる場合、売り手は意向表明書を基に交渉対象を選定します。法定の様式はありませんが、買い手企業の概要やM&Aの目的、買収希望額、スケジュールなどが記載されます。
意向表明書に法的拘束力はあるか
意向表明書は通常、法的拘束力を持ちません。あくまで買い手の意向や大まかな条件を提示するものであり、売り手との契約的な合意を意味するものではないからです。
ただし、交渉の出発点として重要な意味を持ち、記載内容はその後のデューデリジェンスや基本合意書の土台になります。
実質的には交渉の誠意を示す書面であり、円滑なM&Aの進行に資する役割を果たします。
基本合意書との違い
意向表明書と基本合意書の違いは、作成時期や記載内容、法的拘束力の有無にあります。
基本合意書は条件交渉が進んだ後、双方で大枠の合意が形成された段階で交わされます。内容としては独占交渉権や秘密保持義務、価格の算出方法などが記載されます。
また、基本合意書は一部に法的拘束力を持たせることが多く、最終契約に向けた重要なステップと位置付けられます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



意向表明書の記載内容と書き方
意向表明書には、買い手の取引に対する意思や条件を明確に伝えるために、次の項目を記載することが一般的です。
- 企業概要
- 希望価格
- M&A実施の目的
- M&Aのスキーム
- M&A後の経営方針
- 従業員・役員の処遇
- 資金調達方法
- スケジュール
- デューデリジェンスの範囲や内容
- 独占交渉権
- 有効期限
- 法的拘束力がないことの明記
それぞれの詳しい内容や書き方について解説します。
企業概要
意向表明書の冒頭には、買い手企業の基本情報を明記します。
商号や代表者氏名、所在地、資本金、沿革、主な事業内容、財務状況、関連会社やグループの構成など、売り手企業に対して企業の信頼性や安定性を伝える情報が求められます。
事業の実績や業界内でのポジションなども記載することで、買い手としての実力や姿勢を示せます。
希望価格
譲受を希望する価格は、一定の価格帯(例:〇〇〜〇〇円)で記載することが一般的です。買収価格の算定根拠や価格修正の条件(例:デューデリジェンスの結果に応じて調整)なども併記しておくと、誠実な交渉姿勢を印象付けられます。
価格は売り手にとって最も重要な要素の一つです。そのため、過度な乖離(かいり)があると交渉が不成立となるリスクもあるため、慎重かつ丁寧な記述が必要です。
必要に応じて、会社案内やパンフレットなどを別途添付して、売り手が詳細を把握できるように配慮することも大切です。
M&A実施の目的
買い手が今回のM&Aを通じて何を達成したいのか、その背景や理由を明確に記載します。
例えば、事業の拡大や新規分野への参入、既存事業とのシナジー効果、競争力の強化などが該当します。売り手企業との関係性や相互補完性、統合後の展望についても触れることで、M&Aに対する誠実な姿勢と将来への期待を示せます。
売り手にとって納得感のある動機付けが記載されていることで、交渉を優位に進める要素となります。
M&Aのスキーム
M&Aの実施形態として、株式譲渡や事業譲渡、会社分割、合併など、どのスキームを想定しているかを記載します。
特に中小企業のM&Aでは、株式譲渡が多く活用されますが、買収対象の資産・事業の範囲、取得割合や譲受対象などを明示し、売り手との相互理解を促すことが重要です。
選定したスキームの理由についても簡潔に述べることで、スキームに対する戦略性や妥当性を伝えられます。
M&A後の経営方針
M&A成立後の経営方針を明示することで、売り手側の不安を和らげます。
経営戦略やブランドの存続、取引先との関係、シナジー効果の見込みなどを具体的に記載します。売り手企業の独自性を尊重しつつ、どのように企業価値を高めていくかのビジョンを示すことが重要です。
従業員・役員の処遇
M&A後の従業員や役員の処遇は、売り手にとって特に関心の高い項目です。
雇用契約の維持や待遇の継続、福利厚生の取り扱いなどについて明示することで、安心感を与えられます。
代表者が一定期間相談役などの立場で残る旨(キーマン条項)を記載するケースも一般的です。
資金調達方法
買収資金をどのように調達するのかについて、概要を明記します。自己資金や金融機関からの借り入れ、出資による調達など、調達方法の具体的な手段を示すことで、資金力や実行可能性を売り手に示せます。
資金調達の裏付けが明確であることは、買収の実現性を高める上で重要な要素です。必要に応じて、金融機関との調整状況や借入枠の有無なども記載します。
スケジュール
M&Aプロセスの想定スケジュールを記載します。例えば、基本合意書の締結やデューデリジェンスの実施、最終契約書の締結、クロージングの日程などを提示します。特に買い手が上場企業である場合は、適時開示義務に関するスケジュールも明確にしておく必要があります。
スケジュールの提示は、取引に対する準備状況や誠意を示す意味でも効果的です。
デューデリジェンスの範囲や内容
意向表明書の段階で、予定しているデューデリジェンスの範囲や調査対象について記載します。
デューデリジェンスとは、買収前に売り手企業の法務や財務、労務、コンプライアンスなどを調査し、事業に関わるリスクを把握するための監査です。
調査方法や専門家の活用予定なども明示し、売り手が事前準備しやすいよう配慮します。
独占交渉権
独占交渉権は、一定期間中、売り手が他の買い手候補と交渉を行わないよう求める条項で、買い手のリスクを軽減するために重要です。通常は基本合意書に記載されますが、意向表明書の段階で買い手が独占交渉を求めるケースも実務上よく見られます。
買い手はデューデリジェンスの実施にあたり、弁護士や会計士への依頼などで高額な費用を負担します。その過程で売り手が他社と交渉を進めれば、損失リスクが発生します。こうした事態を避けるため、買い手は意向表明書に独占交渉期間や延長の可否を明記し、排他性を確保します。
ただし、売り手の選択肢を制限する側面もあるため、相応の信頼関係や交渉の進展が前提です。
有効期限
意向表明書の効力がいつまで続くのか、有効期限を明示することで、売り手・買い手双方がスケジュール管理を適切に行えます。また、有効期限の設定は、売り手に対して決断を促す側面もあります。
例えば、フェーズごとの区切り(第一段階:基本合意まで、第二段階:最終契約まで)を設け、各段階の期限を明記することも効果的です。有効期限の経過に伴い失効する旨も記載することで、文書の曖昧性を排除できます。
法的拘束力がないことの明記
意向表明書は、買い手が取引への関心や基本的な条件を伝えるための文書であり、通常は法的拘束力を持ちません。この段階では契約は成立しておらず、買い手は意向表明書の提出後、デューデリジェンスを実施し、その結果を踏まえて基本合意書や最終契約書の締結を検討します。
ただし、文面によっては一部に拘束力があると解釈される可能性もあるため、「本書には法的拘束力を持たない」旨を明記することが重要です。
買い手側が意向表明書を作成する際のポイント
買い手側が意向表明書を作成する際のポイントとして、次の点が挙げられます。
- M&Aの目的とメリットを押し出す
- シナジー効果を織り込んだ価格を設定する
- 買収に対する熱意をアピールする
- 売り手の意向を確認・反映する
- 競合よりも良い条件を提示する
- 取引スケジュールの柔軟性を示す
- 組織・人材の統合戦略を提示する
それぞれについて解説します。
M&Aのメリットを押し出す
買い手は、意向表明書を通じてM&Aの目的はもちろん、自社と統合することによる売り手側のメリットを分かりやすく伝える必要があります。
単に「買いたい」と示すだけでなく、M&A後のビジョンや成長戦略、双方にとっての価値創出を明示することで、売り手にとっての納得感や信頼を生み出します。
具体的には、高いシナジー効果や市場拡大の見込み、事業基盤の強化などを根拠ある数値とともに提示し、売却後の企業の未来像を売り手が具体的にイメージできるようにします。買収金額だけでなく、非財務的な魅力も重要なアピール要素です。
シナジー効果を織り込んだ価格を設定する
買収価格の提示は、売り手の評価に直結する最重要項目です。特に、買収後に見込まれるシナジー効果を価格に織り込むことで、「高く評価している」という姿勢を示せます。
売り手は単に高値を提示する相手よりも、合理的かつ現実的に自社の価値を認めてくれる相手に好感を抱きやすい傾向があります。
算定根拠については、売り上げ拡大やコスト削減、技術統合などを通じた経済的効果を明示し、将来的な価値創出を前提とした金額であることを説明することが望まれます。金額提示と併せて、その妥当性を丁寧に伝える姿勢が求められます。
買収に対する熱意をアピールする
意向表明書は他社と比較される文書であるため、金額だけでは差別化が困難です。買収に対する熱意を明確に伝えることが、売り手企業との信頼関係構築に直結します。
具体的には、買収への思いや、M&A後の運営方針に対する責任感、経営陣からの直接のメッセージを記載するなどの工夫が効果的です。
フォーマットが定型であっても、補足資料やメッセージ欄などを活用し、売り手に対する真摯(しんし)な姿勢を表現することが重要です。他の買い手候補が多数いる場合こそ、明確な買収意欲の提示が、他候補との差別化につながります。
売り手の意向を確認・反映する
意向表明書は買い手側の文書であるとはいえ、売り手企業の意向を無視した内容では好印象を与えることはできません。面談や事前のヒアリングを通じて、売却理由や重視する条件、従業員の処遇など売り手の希望を把握し、それを文書内に適切に反映させることが大切です。
例えば、雇用の維持を望む売り手に対しては、従業員の処遇に関する具体的な方針を盛り込むことで、安心感を提供できます。売り手の視点に立った内容を盛り込むことにより、形式的な提案ではなく、信頼関係の構築を意識した誠実な表明書として評価されやすいです。
競合よりも良い条件を提示する
売却先の選定は、複数の買い手候補の中から比較検討されることが一般的です。そのため、競合よりも優れた条件を提示することが、意向表明書における重要な戦略です。
単に買収金額で勝負するのではなく、自社の信頼性や技術力、業界での実績などを生かし、売り手にとっての魅力を多角的に示すことが必要です。
また、M&A後の育成方針や従業員への配慮など、非金銭的な要素でも差別化を図れます。売り手企業が重視している基準を見極め、適切な条件提示を行うことで、「選ばれる買い手」としての地位を確立できます。
取引スケジュールの柔軟性を示す
売り手の事情に応じたスケジュール対応力も、買い手の評価ポイントです。例えば、「急ぎで譲渡を進めたい」「一定の移行期間を設けたい」といった要望に対して、柔軟に応じる意思があることを示せば、信頼性と協調性が伝わります。
意向表明書では、あらかじめ希望スケジュールを提示しつつ、「売り手様のご事情に応じ調整可能です」といった文言を添えることで、売り手にとって魅力的な買い手であることを印象付けられます。
組織・人材の統合戦略の提示
M&A後の統合を円滑に進めるためには、人材や組織文化への配慮が欠かせません。買収後のガバナンス体制やキーマンの処遇、文化融合の支援方針などを提示することで、「買収して終わり」ではなく、事業継続と成長を共に目指す姿勢が伝わります。
特に、売り手が従業員の雇用や企業文化を重視している場合は、統合後の組織設計や人材育成方針を明記することで大きな安心材料となります。
売り手側が意向表明書を確認する際のポイント
売り手側が意向表明書を確認する際のポイントとして、次の点が挙げられます。
- 専門家にアドバイスをもらう
- 価格を精査する
- 譲れない条件を明確にする
- 従業員の処遇と企業文化の維持を条件に入れる
- M&A後の事業継続性を確かめる
それぞれについて解説します。
専門家にアドバイスをもらう
意向表明書の内容を正確に評価し、交渉を有利に進めるためには、M&A仲介業者や弁護士、公認会計士などの専門家からのアドバイスが不可欠です。提示された価格や契約条件やデューデリジェンスの進め方などに潜むリスクを事前に把握することで、不要な譲歩を避けられます。
特に価格の算定根拠や将来的な条件変更のリスクに関しては、専門的知見がなければ判断が難しいため、外部の専門家に依頼することで、安心して判断できる体制を整えられます。
価格を精査する
提示された価格が妥当かどうかを慎重に精査することは、売り手にとって最重要の確認事項です。高額の提示があっても、独占交渉権獲得後にデューデリジェンスを理由に減額交渉を仕掛けてくるケースがあるため、事前に価格の根拠や評価方法を確認しておく必要があります。
具体的には、DCF法や類似企業比較法などの分析を通じ、企業価値と照らして実態と乖離(かいり)がないかを評価します。算定根拠が不透明な場合には、専門家の意見を仰いで適正価格の水準を把握しましょう。
譲れない条件を明確にする
売却交渉を進める前に、自社として「譲れない条件」と「交渉可能な条件」を明確にしておくことが大切です。
従業員の処遇や企業ブランドの維持、経営陣の役職・報酬、M&A後の経営方針など、売り手企業にとって重要な要素を明示的に整理することで、交渉中の判断軸が定まらない事態を防げます。
従業員の処遇と企業文化の維持を条件に入れる
従業員は企業の重要な資産であり、M&A後の処遇が不安定になることで、モチベーション低下や離職リスクが高まる恐れがあります。そのため、買い手側に対し、従業員の雇用継続や待遇維持の方針を事前に確認し、条件として文書化しておくことが望まれます。
また、企業文化の継承にも注意が必要です。買収後の統合過程で、価値観や行動様式のズレが発生すると組織の混乱を招くため、自社の文化をどう維持・融合させるかといった方針の擦り合わせを行うことが求められます。
M&A後の事業継続性を確かめる
売却後も自社事業が安定して継続されるかどうかは、従業員や顧客、取引先にとって重大な関心事項です。売り手としては、買い手が十分な資金力と運営体制を有しており、既存事業を維持・発展させる意欲があるかを見極めなければなりません。
事業継続に必要な資金計画や経営陣の配置、新規投資の有無などを買い手に確認し、将来の経営破綻や撤退リスクを回避できるようにしておく必要があります。
意向表明書作成を含むM&Aの基本的な流れ
意向表明書作成を含むM&Aの基本的な流れは次のとおりです。
- 初期の検討
- 専門家への相談
- 資料整理と準備
- 秘密保持契約の締結
- トップ面談
- 意向表明書の作成
- 提出・交渉
- 基本合意書の締結
- デューデリジェンス(DD)の実施
- 最終条件の調整と合意形成
- 最終契約書の締結とクロージング
それぞれの工程を分かりやすく解説します。
初期の検討
M&A交渉の最初の段階では、自社がM&Aを実施する目的や条件、譲受または譲渡の方針などを明確にします。買い手であれば、成長戦略の一環としてどのような企業を買収すべきかを検討し、売り手であれば、どのような買い手に引き継ぐべきかを整理します。
この段階での検討が不十分だと、交渉の途中で方針が変わってしまう原因となるため、目的・希望条件・譲れない点を社内で共有することが不可欠です。
専門家への相談
M&Aは法務や財務、税務などのさまざまな要素が絡むため、早期の段階でM&A仲介会社や弁護士、税理士などの専門家に相談することが推奨されます。専門家の助言により、案件の妥当性や最適な進め方を把握できます。
複数の専門家に相談することで、相性や知見を比較検討することも有益です。
資料整理と準備
買い手側は希望条件やM&Aの目的を文書にまとめ、売り手側は企業概要書(IM)、財務三表、ノンネームシート(簡易的な匿名情報資料)などを準備します。
特に売り手側は初期段階から資料を整えておくことで、買い手からのアプローチに迅速に対応できます。
秘密保持契約の締結
次に、売り手と買い手の間で秘密保持契約(NDA)を締結します。これにより、譲渡側が提供する財務情報や経営資料などの機密情報が外部に漏れるリスクを防ぎます。
秘密保持契約には、情報の取り扱い範囲や使用目的、第三者提供の禁止、違反時の責任などを盛り込み、取引の信頼性を高めることが求められます。
トップ面談
秘密保持契約締結後、買い手と売り手の経営陣によるトップ面談が実施されます。この面談では、財務データや契約条件だけでは伝わらない、経営者の価値観やビジョン、人柄などを相互に確認します。
M&Aは最終的に人と人との信頼で進む面があるため、双方が率直に意見を交わし、信頼関係を築けるかどうかが今後の交渉を左右します。ここで良好な関係が築ければ、意向表明書の提出に進みやすいです。
意向表明書の作成
トップ面談を経て、買い手側は意向表明書を作成します。
前述のとおり、法的拘束力は持たないことが一般的ですが、買い手側の本気度を示す資料として、売り手に対して大きな意味を持ちます。また、複数の買い手がいる場合には、売り手側の選定基準として機能します。
提出・交渉
売り手企業は意向表明書の内容を精査し、複数の買い手候補がいる場合には比較検討を行います。提示された条件(価格やスキーム、従業員の処遇など)を基に、優先交渉権を与える買い手を絞り込みます。
なお、検討期間は1〜2週間程度が一般的です。返答後は、意向表明書に基づいてより具体的な条件交渉に移行します。
基本合意書の締結
売り手が意向表明書の内容に納得し、一定の条件で交渉を進める意思を示した場合、買い手と売り手は基本合意書を締結します。
基本合意書には、今後のスケジュールやデューデリジェンスの範囲、独占交渉権の有無などが盛り込まれます。
デューデリジェンス(DD)の実施
買い手は、法務や財務、税務。労務、ITなどの各領域において、専門家と連携しながら詳細な調査を進めます。
この過程で問題点やリスクが発見されれば、取引条件が見直される可能性があるため、売り手には正確かつ透明性のある情報の提供が求められます。
最終条件の調整と合意形成
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な譲渡価格やスキーム、社員の処遇、クロージングの日程などについて、買い手と売り手の間で協議を行います。この段階では、双方が柔軟かつ戦略的に歩み寄る姿勢を持つことが重要です。
協議により合意された内容は、最終契約書に明記されます。
最終契約書の締結とクロージング
双方が最終契約書の内容を確認し、署名・押印を行うことで契約が正式に成立します。その後、資産や株式の引渡し、代金の支払いなどを経て、取引が完了しクロージングに至ります。
最終契約書には、表明保証や補償条項なども盛り込まれており、全ての内容に法的拘束力が生じます。
意向表明書の作成に関する相談先
意向表明書の作成・確認に関して、主な相談先は次のとおりです。
- M&A仲介会社
- 弁護士
- 税理士・公認会計士
- 銀行などの金融機関
- 商工会・商工会議所
それぞれについて解説します。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、M&Aの専門知識と豊富な実績を持つプロフェッショナル集団であり、初期相談から契約締結、アフターフォローまでを一貫して支援します。
M&Aに不慣れな企業であっても、手続き全般を包括的に任せられる点が強みです。業界や地域に特化したネットワークを活用し、売り手・買い手双方に最適なマッチングを実現します。
ただし、仲介会社によっては着手金や成功報酬などの報酬体系が異なるため、事前に契約条件をよく確認することが大切です。
弁護士
弁護士は、M&Aにおける法的リスクへの対応や契約書の作成・精査において欠かせない存在です。特に意向表明書における拘束力の明確化や秘密保持契約の整備、独占交渉条項の記載など、取引の初期段階から関与することで、将来的なトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
また、M&Aスキームの合法性や株主対応、労働法上の問題にも対処できるため、安心して交渉を進められます。
ただし、M&Aに精通した弁護士でなければ適切な助言が得られない場合があるため、M&A実務に特化した経験のある弁護士を選ぶことが重要です。
税理士・公認会計士
税理士や公認会計士は、M&Aに伴う財務・税務面の分析やスキーム設計を担います。特に株式・事業の評価や買収価格の妥当性検証、デューデリジェンスの実施、譲渡益課税の試算などを通じて、M&A後の財務リスクを最小限に抑える支援を行います。
普段から顧問契約をしている専門家であれば、自社の状況を理解しているため相談がスムーズです。
銀行などの金融機関
銀行や証券会社といった金融機関も、M&A支援サービスを提供しています。資金調達のアドバイスをはじめ、M&Aアドバイザリー部門を設置している大手銀行では、M&Aのマッチング支援に加え、企業価値の算定や評価にも対応しています。
また、取引関係のある銀行であれば、日頃からの信頼関係と企業理解を基にスムーズな相談が期待できます。ただし、対応スピードが遅い点や手数料の高さがネックとなる場合があります。
商工会・商工会議所
商工会・商工会議所は、公的機関として中小企業の経営支援を行っており、M&Aの初期相談にも対応しています。
会員であれば無料でアドバイスが受けられることもあり、費用を抑えて相談したい企業にとって有益な窓口です。地元企業とのネットワークがあり、地域内でのマッチングをサポートする機能も一部備えています。
ただし、M&A実務に関する専門的な支援や手続きの遂行には限界があるため、具体的な実行段階では外部の専門家との連携が必要です。あくまで初期相談や情報提供の窓口としての活用が現実的です。
事業承継・引き継ぎ支援センター
事業承継・引き継ぎ支援センターは、中小企業庁が設置する公的支援機関で、地域の事業承継・M&Aを無料で支援しています。
中小企業診断士やM&A専門家が在籍しており、売り手・買い手双方に対して中立的な立場からアドバイスを行う点が特徴です。地元企業とのネットワークやマッチング支援もあり、地方中小企業にとっては非常に頼れる存在です。
また、税理士・弁護士などの外部専門家とも連携しており、ワンストップで相談できる点も利便性が高いです。ただし、事業承継に特化しているため、大型M&Aや上場企業案件などには対応できない場合があります。
意向表明書のサンプル
M&Aの手法として「株式譲渡」を選んだ場合の意向表明書のサンプル書式を掲載します。
なお、実際に意向表明書を作成する際には、M&A仲介会社や弁護士、公認会計士などの専門家と相談しながら内容を検討することが重要です。誤解やトラブルを防ぐためにも、専門的な助言を受けた上で文案を作成することを強く推奨します。
〇〇年〇月〇日(提出日)
意向表明書
株式会社〇〇〇〇(売り手企業名) 御中
東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号
株式会社△△△△(買い手企業名)
代表取締役 〇〇 〇〇 印
拝啓 貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたびは、貴社の株式譲渡案件(以下「本件」といいます)につきまして、弊社に検討の機会を賜り、誠にありがとうございます。
弊社では、貴社よりご提供いただいた情報を基に社内で慎重に検討を進めてまいりました。その結果、弊社は貴社との取引に強い関心を有しており、下記のとおり意向を表明させていただきます。
なお、本書面の内容は、現時点における受領情報および公開情報に基づくものであり、今後の追加資料の開示やデューデリジェンス等の結果により、内容が変更となる可能性がある点をあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
1.弊社の概要
会社名:株式会社△△△△
所在地:東京都〇〇区〇〇〇〇
代表者名:代表取締役 〇〇 〇〇
事業内容:ウェブマーケティング、BtoC向けシステム開発 等
2.取引形態および希望譲渡価額
取引形態:株式譲渡(発行済株式100%の取得)
希望価格:〇億円〜〇億円(DCF法を参考に算出)
ただし、価格は今後の資料提供およびデューデリジェンスの結果により変動する可能性があります。
3.譲渡価額の算出方法
DCF法を採用し、貴社より受領した資料および市場情報等を基に試算しております。
4.本件を希望する目的
弊社はウェブ関連分野での事業拡大を進めており、貴社の有する高度な技術と人材を取り込むことで、両社の補完的な成長が可能であると判断しております。
5.従業員・役員の処遇について
従業員:全員を現行の雇用条件で引き続き雇用予定
役員:現任の取締役については、任期満了まで委任契約を継続予定
6.対価の支払方法および資金調達
支払方法:貴社指定の口座への銀行振込により一括支払い
資金調達:手元現預金および一部金融機関からの借り入れにより実施予定
7.想定スケジュール(目安)
・基本合意の締結:〇年〇月〇日
・デューデリジェンス実施:〇年〇月〜〇月
・最終契約締結:〇年〇月〇日
・クロージング実行:〇年〇月〇日
8.デューデリジェンスの範囲
財務・法務・税務・ビジネスの各領域について、弊社及び指定専門家が実施予定です。
費用は全額弊社負担といたします。
9.独占交渉権の希望
〇年〇月〇日までの間、弊社に対して独占的な交渉の機会を与えていただけますようお願い申し上げます。
10.本意向表明書の有効期限
以下のいずれか早い時点までとさせていただきます。
(1)基本合意契約の締結日
(2)最終契約の締結日
(3)本件の検討を中止した旨を通知した日
(4)〇年〇月〇日
11.秘密保持
本意向表明書の存在および記載内容については、相互に第三者に対して一切開示しないものとします。
12.法的拘束力の有無
本意向表明書は現時点の意向を示すものであり、法的拘束力は有しないものとします。
以上
M&Aにおける意向表明書に関するQ&A
最後に、M&Aにおける意向表明書に関するよくある質問とその回答を紹介します。
意向表明書を作成しないケースはあるか
意向表明書は原則として買い手側が売り手に対して提示するものですが、全てのM&Aにおいて必須というわけではありません。
例えば、既に信頼関係が構築されている関係者同士のM&Aや、親会社と子会社間で行われるグループ内再編など、交渉初期から基本合意に至るまでが迅速な場合には、意向表明書を省略してそのまま基本合意書や最終契約書に進むことがあります。
ただし、第三者間でのM&Aでは、意向の明文化が後の認識違いやトラブルを防ぐ意味でも重要であり、作成を省略する場合には慎重な判断が求められます。
ノンネームシートとは何か
ノンネームシートとは、M&A交渉の初期段階で、譲渡企業の詳細な情報を明かす前に、譲受候補企業へ概要を匿名で紹介するための資料です。
ノンネームシートは、意向表明書のやり取りが始まる前の段階で使用されます。企業名や特定の取引先名などの情報は記載されず、匿名性が保たれます。業種や所在地、売り上げ規模、従業員数、譲渡理由、希望するスキームなど、最低限の情報のみが盛り込まれます。
なお、詳細な情報の開示は、秘密保持契約の締結後に行われます。
キーマン条項とは何か
キーマン条項(ロックアップ)とは、M&Aの実行後も売却側の代表者や幹部などの中核人材が一定期間在籍し、事業の継続性や引き継ぎを担うことを約束する条項です。意向表明書においても、譲受側がこの条件を希望事項として提示することがあります。
事業運営の中心人物が急に退任すると、顧客離れや従業員の動揺を招く恐れがあるため、買収後の安定化を目的として合意されます。在任期間は1〜3年が一般的で、対象者のモチベーション維持のためにアーンアウト条項と併用されることもあります。
ロックアップ期間中は競業避止義務や他社関与の制限が設けられるケースも多く、意向表明書に記載する場合は、その拘束条件と対象人物の意向との整合性が重要です。
アーンアウト条項とは何か
アーンアウト条項とは、M&Aの契約において、取引完了後に対象事業が一定の業績目標を達成した場合、買い手が売り手に追加対価を支払うことを定めた規定です。基本的に前述のキーマン条項と併用されることが多いです。
対価の一部を成果に連動させることで、買収価格に対する認識の差を埋める役割を果たします。なお、評価指標には、売上高や営業利益などが用いられます。また、評価期間は通常3年以内に設定され、再売却リスクへの備えも契約上求められます。
売り手にとっては、売却後も経営に関与することで成果次第で報酬を得られるメリットがありますが、対価を一括で受け取れない点がデメリットです。一方、買い手側はリスク軽減につながり、不確実性の高い企業への買収で有効です。
まとめ
M&Aにおける意向表明書は、買い手が取引の意図や基本条件を示す重要な文書です。これにより、売り手との信頼関係を築き、交渉をスムーズに進めることが可能になります。
意向表明書は法的拘束力はありませんが、取引の方向性を明確にする役割を果たします。意向表明書の書き方や検討ポイントを理解し、それに基づいて準備を進めることで、M&Aプロセスを円滑に進めることができるでしょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。