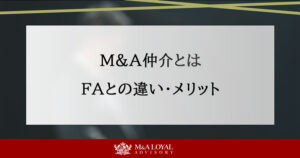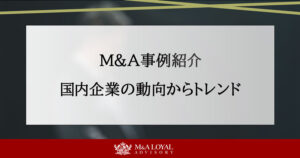北海道でM&Aを相談するならどこ?補助金や動向を事例と共に解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
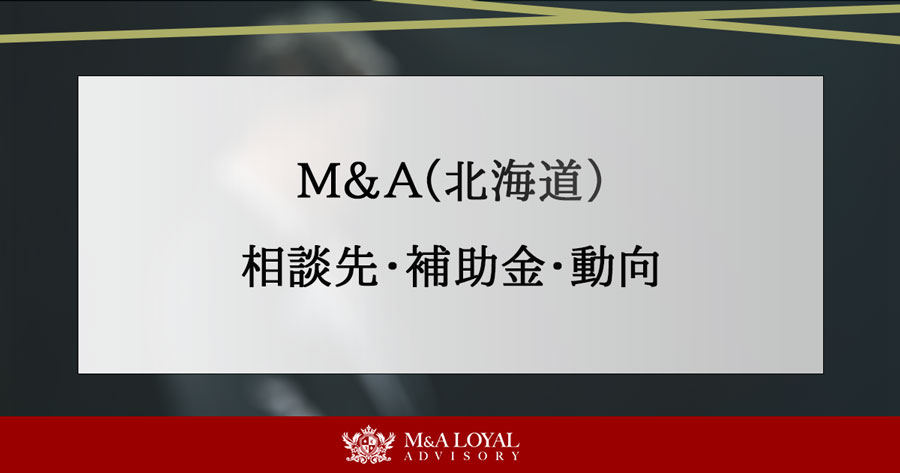
北海道でM&Aを検討しているが、どこに相談すれば良いか分からず困っていませんか。 後継者不足や事業承継の課題に直面する中で、信頼できる相談先を見つけられず不安を抱えている企業も多いでしょう。
本記事では、北海道の経済・M&A動向から相談先となる公的機関や仲介会社、さらに活用できる補助金制度や実際の事例まで幅広く紹介します。この記事を読めば、北海道でM&Aを成功させるための具体的な準備方法や相談窓口が理解でき、スムーズな事業承継・成長戦略につなげられます。
目次
北海道の経済・M&A動向
まず、北海道の経済状況やM&A動向について紹介します。
北海道の経済状況
令和2年の国勢調査結果によると、北海道の人口は5,224,614人です。都道府県の総人口ランキングで第八位です。
令和3年度(2021年度)の北海道の名目道内総生産は20兆5,409億円で、実質経済成長率は前年度比+2.3%となり、全国平均(+2.8%)に近い水準で回復しました。
産業構造をみると、第一次産業は3.9%と全国(1.0%)を大きく上回り、第二次産業は17.8%(全国26.5%)と低い水準にあります。一方で第三次産業は77.0%(全国71.9%)を占め、全国と比べて第一次産業と第三次産業の割合が高いです。
参考:令和2年国勢調査
北海道のM&Aの件数
令和3年度における北海道内企業のM&A件数は、売却(譲渡)が132件、買収(譲受)が114件でした。
M&A件数全国第1位の東京都では、売却(譲渡)が755件、買収(譲受)が893件を記録しました。北海道は全国第6位に位置しており、M&Aが比較的活発に行われている地域であることがうかがえます。
北海道の休廃業件数
2024年に北海道内で休廃業・解散した企業(個人事業主を含む)は過去最多の2,715件に達し、前年から20.6%増加しました。年間件数としては3年連続の増加です。
休廃業・解散に至った代表者の平均年齢は71.9歳で、前年から0.6歳上昇しました。年齢別では「70代」が44.0%と最も多く、次いで「80代以上」が23.0%を占めており、高齢化が進んでいることがうかがえます。
業種別では「建設業」が428件で最多となり、前年から9.7%増加しました。さらに「運輸・通信業」では36件と前年より71.4%増加するなど、一部業種で急増が見られ、全体の増加傾向を後押ししています。
2024年の休廃業・解散の増加背景には、コロナ禍での各種給付や支援策が縮小したことに加え、電気代や人件費の上昇、物価高による負担増が挙げられます。さらに、後継者不足や返済原資の確保が困難になったことから、やむなく休廃業を選択する企業も増えました。これら複合的な要因が、過去最多となる件数を押し上げたといえます。
北海道の後継者不在率
2024年の北海道における後継者不在率は65.7%で、前年から0.8ポイント低下し、調査開始以来の過去最低を更新しました。7年連続の改善となり、コロナ禍前の2019年(72.9%)と比べても7.2ポイント下がっています。
背景には、官民による事業承継支援策の拡充や、地域金融機関などの支援機関による積極的な取り組みによって、事業承継の重要性が経営者に浸透してきたことがあります。ただし、改善ペースは鈍化傾向にあり、特に「40代〜60代」や「80代以上」では不在率が悪化するなど課題も残っています。
また、北海道の後継者不在率は全国平均(52.1%)を大きく上回り、都道府県別では全国4番目の高さでした。依然として高い水準にあることから、世代交代の円滑化や「脱ファミリー化」への対応が今後の重要な焦点といえます。
参考:帝国データバンク|北海道「後継者不在率」動向調査(2024年)
北海道の企業のM&A相談先
北海道内の企業がM&Aを検討する際、主な相談先として多く選ばれている組織は次の機関です。
- M&A仲介業者
- メインバンク
- 税理士事務所
- 公的機関
- 公認会計士事務所
それぞれの特徴や留意すべき点を紹介します。なお、帝国データバンクによる本調査は複数回答形式で行われているため、各項目の割合を合計すると100%を超える場合があります。
M&A仲介業者
M&A仲介業者は、買い手と売り手の条件調整や契約支援を専門的に行う機関で、豊富な案件数とノウハウを持つ点が大きな強みです。北海道の調査では19.9%の企業が相談先として挙げており、一定の信頼を得ていることが分かります。
特に後継者不足に悩む中小企業にとって、幅広いネットワークを活用したマッチング力は有効です。ただし、手数料体系や支援範囲は業者ごとに異なるため、契約前に条件を確認することが重要です。
北海道のM&A無料相談はM&Aロイヤルアドバイザリー
M&Aロイヤルアドバイザリーは、中小企業を中心とした多様な業界での成約実績を持つM&A仲介会社です。オーナー様のご決断に寄り添うコンサルタント、買手企業様とのマッチングを担当する提携支援部、会計士・税理士を中心としたコーポレートアドバイザリー部など、初期段階からご成約まで各プロセスの専門人材が分業体制でサポートするのが特徴です。
当社は完全成果報酬型であり、着手金や中間報酬は一切いただいておりません。相談料も無料のため、M&Aのセカンドオピニオンとしてご相談いただく経営者様も増えております。お気軽にご相談ください。
また、弊社では代表取締役社長・橋場 涼に直接相談ができる窓口を期間限定でご用意しております。事業承継に関するご質問であれば何でもご相談可能ですので、下記バナーよりお問い合わせください。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



メインバンク
最も多く選ばれているのはメインバンクで、北海道の企業の54.9%が相談先として利用しています。
日頃から企業の財務状況や資金繰りを把握しているため、融資や財務戦略に関する助言を受けやすい点が強みです。一方で、案件規模に下限を設ける金融機関もあり、小規模案件では対象外となる可能性がある他、借入先という立場上、経営戦略情報を開示しにくい心理的なハードルも存在します。
北海道では、メインバンクのトップは北洋銀行で、道内企業2万3,696社が取引し、シェアは34.75%と最も高い比率を占めています。北洋銀行は日本M&Aセンターホールディングスと連携し、後継者不足に悩む道内企業と経営志望者をつなぐ「北海道サーチファンド」を設立しました。後継者不在企業と新たな経営者候補(サーチャー)をマッチングさせ、事業承継の円滑化を目指しています。
税理士事務所
次に多い相談先が税理士事務所で、北海道では32.0%の企業が相談先に選んでいます。会計・税務の専門家として、財務デューデリジェンスや企業価値評価、節税スキームの提案に強みがあります。
ただし、買い手探索や契約交渉は専門外となるため、M&A仲介業者や金融機関との連携が欠かせません。顧問契約の範囲を超える場合は追加費用が発生する点も注意が必要です。
公的機関
北海道の企業の17.3%が、公的機関をM&A相談先として活用しています。
中立的な立場からの助言に加え、補助金や制度の案内、専門家紹介など、初めてM&Aを検討する中小企業にとって安心できる環境が整っています。
ただし、相手先探索や契約交渉の支援は限定的で、スピード感を重視する場合には民間機関との併用が望まれます。
公認会計士事務所
公認会計士事務所を相談先に選んだ企業は13.3%でした。財務諸表監査や企業価値評価に精通しており、買い手に対する信頼性の確保や財務リスクの洗い出しに役立ちます。
一方で、契約交渉や買い手探索には対応できない場合が多く、他機関との併用が前提です。費用は業務単位や時間単位で発生するため、契約内容を事前に確認することが求められます。
北海道でM&Aの相談ができる公的機関
北海道でM&Aに関する相談や支援を行っている主な公的機関は、次のとおりです。
- 北海道事業承継・引継ぎ支援センター
- 北海道よろず支援拠点
- 商工会議所
- 商工会
- 北海道信用保証協会
- 北海道中小企業家同友会
- 中小企業基盤整備機構 北海道本部
それぞれの機関の特徴を詳しく紹介します。
北海道事業承継・引継ぎ支援センター
北海道事業承継・引継ぎ支援センターは、産業競争力強化法に基づき、経済産業省北海道経済産業局からの委託を受けて設立された公的な相談窓口です。道内の中小企業を対象に、親族内承継や従業員・役員承継(MBO)、第三者承継(M&A)まで幅広く支援しています。
センターの特徴は、事業承継に関わる手続きや課題解決をワンストップで対応できる点にあります。課題整理から事業承継計画の策定、国の支援制度の案内や金融機関・専門家との連携まで一貫してサポートが受けられます。経験豊富な専門家が常駐しており、秘密厳守かつ無料で安心して相談できる環境が整っています。
さらに、北海道内8カ所のサテライト(函館、旭川、帯広、釧路など)を拠点に、地域に密着した支援を展開しています。広大な道内の事業者が身近に相談できる体制を築き、行政や金融機関とも連携しながら、後継者不足や事業承継問題の解決を支援しています。
北海道よろず支援拠点
北海道よろず支援拠点は、国が全国に設置する無料の経営相談所として、(公財)北海道中小企業総合支援センターが経済産業省北海道経済産業局から委託を受け、2014年6月に開設されました。札幌本部に加え、函館・帯広・釧路・旭川・北見・室蘭の道内6カ所に拠点を設け、地域の中小企業・小規模事業者を幅広く支援しています。
北海道よろず支援拠点には、専任のチーフコーディネーターと約30名のコーディネーターが常駐し、売り上げ拡大や経営改善、資金繰り、労務・雇用、海外進出など多岐にわたる経営課題に対応します。特にIT活用による生産性向上や事業承継、人手不足、省力化、インボイス制度対応、省エネ対策といった政策的重点分野にも力を入れています。
相談は無料で回数制限もなく、対面のほか電話やオンラインでの利用も可能です。
商工会議所
商工会議所は、商工会議所法に基づき設立された唯一の地域総合経済団体であり、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。全国に515の会議所が設置され、125万社の会員が加盟しており、地域性・総合性・公共性・国際性という四つの特徴を持っています。
北海道には函館・札幌・旭川・帯広・北見・釧路などをはじめ、道内各地に商工会議所が設置されています。中小企業や地域産業を支えるネットワークとして機能し、経営相談や創業支援、事業承継に関する取り組みも幅広く展開しています。
札幌商工会議所は約2万社が加盟する道内最大の経済団体で、全国の政令指定都市の中でも会員数は東京・大阪に次いで3位を誇ります。経営相談や創業支援の他、事業承継・M&Aに関する相談窓口を設け、専門家による無料相談を実施しています。親族内承継から第三者承継まで幅広く対応し、課題整理や承継計画策定、法務・税務の専門家紹介を通じて、中小企業の円滑な承継を支援しています。
商工会
商工会とは、商工会法に基づき設立された特別認可法人で、主として町村における商工業の総合的な改善発達を図るとともに、地域社会全体の福祉向上に資することを目的とした地域経済団体です。小規模事業者の経営支援を行う「経営改善普及事業」や、地域活性化を目的とする「地域総合振興事業」などを展開し、経営指導員による相談対応や技術支援、税務・金融相談、創業支援など幅広い取り組みを行っています。
北海道には152の商工会が設立されており、石狩・渡島・桧山・後志・空知・上川・留萌・宗谷・オホーツク・胆振・日高・十勝・釧路・根室といった全道の主要地域を網羅しています。各地域の商工会では、M&Aを含む事業承継相談や経営課題へのアドバイスを通じて、中小企業や小規模事業者の持続的な発展を支援し、地域経済の安定と活性化に貢献しています。
北海道信用保証協会
北海道信用保証協会は、昭和24年に設立された公的機関で、北海道内の中小企業・小規模事業者の資金調達を支援しています。現在は道内約14万事業者のうち3分の1が利用しており、札幌本店の他、函館など道内9カ所に支店を展開しています。金融機関からの融資を受ける際に借入債務を保証することが主な業務ですが、近年は経営課題解決をサポートする「経営支援」にも力を入れています。
特に、事業承継に関しては「事業承継サポートデスク」を設置し、親族内承継やM&Aを含む第三者承継の相談に対応しています。経営改善計画の策定支援や専門家との連携、金融機関との調整などを通じて、中小企業の円滑な世代交代をサポートしています。
北海道中小企業家同友会
北海道中小企業家同友会は、1969年に設立された中小企業経営者による自主的な経済団体で、経営課題の共有や相互支援を通じて地域経済の発展に取り組んでいます。経営に関する勉強会や情報交換、金融・税制・労務・法律などの課題に対応する活動を行い、会員同士の交流やネットワーク形成を促進しています。
2022年4月には、事業承継を支援する相談窓口「つなげる」を開設しました。この窓口では、親族内承継や役員承継、第三者承継(M&A)といった幅広いケースに対応し、経験豊富な会員経営者が一次相談を担当します。初期相談は無料で受けられ、承継の方向性が見えてきた段階では専門家や公的機関と連携し、計画策定や税務・法務面の支援を行います。また、オンライン相談にも対応しており、道内全域から利用可能です。
中小企業基盤整備機構 北海道本部
中小企業基盤整備機構(通称:中小機構)は、国の中小企業政策を実施する中核的機関として設立された独立行政法人です。全国の中小企業・小規模事業者の成長を支えるために、創業支援や新事業展開、資金調達、販路開拓、人材育成、事業承継など、多岐にわたるサービスを提供しています。地域の自治体や金融機関、支援団体と連携しながら、中小企業が直面する課題の解決と経営基盤の強化を図ることを使命としています。
北海道本部は、北海道地域に根ざした中小企業支援の拠点として活動しています。地域の特性や企業ニーズに即した支援を行い、北海道の中小企業の自立的発展を後押ししています。創業や事業再編、事業承継といった経営の節目を支援するとともに、販路開拓や生産性向上、海外展開、DX・GX(デジタル化・脱炭素化)などの新しい挑戦にも幅広く対応しています。
北海道で利用できるM&A補助金・支援制度
北海道内の企業が活用できる主なM&A関連の補助金・支援制度を紹介します。
- 北のふるさと事業承継支援ファンド(過去実施分)
- 事業承継推進事業(苫小牧市)
- 事業承継・M&A補助金(国)
それぞれの補助金制度について紹介します。紹介している内容は2025年8月時点の情報です。最新情報や詳細は、各サイトにてご確認ください。なお、北のふるさと事業承継支援ファンドに関しては過去に実施された事例として紹介します。
北のふるさと事業承継支援ファンド(過去分)
「北のふるさと事業承継支援ファンド」(正式名称:北のふるさと事業承継支援ファンド投資事業有限責任組合)は、2017年に設立された官民連携ファンドです。北海道、道内六つの金融機関、そして公益財団法人北海道中小企業総合支援センターが出資・運営に参加し、地域経済と雇用を支える小規模企業の円滑な事業承継を目的に組成されました。
このファンドでは、経営者から株式を買い取り、その後親族外の後継者に譲渡する仕組みを採用し、後継者が株式の取得資金を準備するまでの一定期間、ファンドが株式を保有することで承継をサポートしました。投資対象は道内の小規模企業(法人)で、親族外承継や第二創業を含む事業承継案件に対応し、1社当たり最大3,000万円、最長10年間の投資が可能でした。
2018年3月には第1号投資先企業が決定するなど実績を残しましたが、本ファンドは2023年3月末をもって募集期間が終了しており、現在は新規の実施は行われていません。
事業承継推進事業(苫小牧市)
この事業は、市内の中小・小規模事業者および個人事業主が後継者不在によって廃業することを防ぐため、第三者承継を支援する制度です。
支援内容
- 市・金融機関・北海道事業承継・引継ぎ支援センターが連携し、事業承継の取り組みを支援
- 事業承継を完了した経営者に100万円を給付(予算上限になり次第終了)
対象者(次の全てを満たす者)
- 市内で事業を営む中小企業者等のうち、事業譲渡時に法人税の納税地が苫小牧市であった法人の経営者、または市内に住民登録のある個人事業主であったこと
- 譲受側が、①苫小牧市内に本社を有する法人、②市内に支店や営業所のある法人、③市内に住民登録のある個人事業主のいずれかで、第三者承継を完了していること(親族内承継、役員・従業員承継は対象外)
- 市内金融機関または北海道事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて事業承継を完了していること
- 第三者承継によって譲渡した事業が、市内で引き続き1年以上営まれること
- 市税を滞納していないこと(納税課との分割納付協議にて猶予中の者を含む)
- 事業承継後1年以内であること
対象外(いずれかに該当)
- 譲渡事業者または譲受事業者で、代表者または役員が暴力団等の排除条例に規定する暴力団・暴力団員・関係事業者等に該当する場合
- 公共法人(法人税法・別表第1に規定)に該当する場合
- 性風俗関連特殊営業および当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
- 宗教上の組織または団体
- 政治団体
- 親族内承継を行う者
- 役員または従業員への承継を行う者
- 事業の趣旨・目的に照らして市長が適当でないと判断する者
事業承継・M&A補助金(国)
この補助金は、事業承継やM&Aを契機とした新規取り組みの推進や事業再編・統合に伴う経営資源の継承を支援し、中小企業の生産性向上と雇用維持を図ることを目的としています。
補助対象となる枠組み(支援内容に応じた四つの枠)
- 事業承継促進枠:5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している者を対象に、設備投資等に係る費用を補助
- 専門家活用枠:M&Aにより経営資源を他者から引き継ぐ、あるいは他者に引き継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)を対象に、M&Aに係る専門家活用の費用を補助
- PMI(経営統合)推進枠:M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等に係るPMIの取り組みを行う事を対象に、PIMにおける専門家活用に係る費用や設備投資に係る費用を補助
- 廃業・再チャレンジ枠:事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)を対象に、再チャレンジを目的として既存事業を廃業するための費用を補助
補助率・補助上限額の目安
事業承継促進枠
- 補助率:1/2・2/3(中小企業者等のうち、小規模事業者に該当する場合は2/3)
- 補助上限:800万~1,000万円(一定の賃上げを実施する場合、補助上限を800万円から1,000万円に引き上げ)
専門家活用枠
- 補助率:
- 買手支援類型:1/3・1/2・2/3(100億企業要件を満たす場合:1,000万円以下の部分は1/2、1,000万円超の部分は1/3)
- 売手支援類型: 1/2・2/3(①赤字、②営業利益率の低下のいずれかに該当する場合)
- 補助上限:
- 買い手支援類型:600~800万円(800万円を上限に、DD費用を上乗せする場合200万円を加算)、2,000万円(100億企業要件を満たす場合)
- 売り手支援類型:600~800万円(800万円を上限に、DD費用を上乗せする場合200万円を加算)
PMI推進枠
- 補助率:
- PMI専門家活用類型:1/2
- 事業統合投資類型:1/2・2/3(中小企業者等のうち、小規模事業者に該当する場合は2/3)
- 補助上限:
- PMI専門家活用類型:150万円
- 事業統合投資類型:800万~1,000万円(一定の賃上げを実施する場合、補助上限を800万円から1,000万円に引き上げ)
廃業・再チャレンジ枠
- 補助率:2/3または1/2(事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用申請する場合は、各事業における事業費の補助率に従う)
- 150万円(事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用申請する場合は、それぞれの補助上限に加算)
補助対象経費の例(枠に応じて異なる)
- FA・仲介手数料
- デューデリジェンス(DD)費用
- 表明保証保険料
- PMIに伴う専門家支援費用など
参考:事業承継・M&A補助金
北海道のM&A事例
直近の北海道のM&Aの事例を紹介します。
北海道ジェイ・アール都市開発株式会社 × 合同会社BASE JAPAN
北海道ジェイ・アール都市開発株式会社は、2025年3月31日付で合同会社BASE JAPANの全出資持分を取得し、子会社化しました。BASE JAPANは2018年設立の宿泊事業者で、札幌・すすきののアパートメントホテル「THE BASE SAPPORO SUSUKINO」(全9室)を運営し、インバウンドやグループ客に人気があります。
本件は、JR北海道グループの「中期経営計画2026」で掲げる新規領域拡大やM&A活用の方針に沿った投資であり、無人ホテル「JRモバイルイン」など既存ノウハウとの相乗効果で、訪日需要の取込み強化を狙います。同グループにとって計画確定後のM&A第1号でもあり、将来ビジョン「未来2031」の実現に向けた事業拡大を進めます。
その後、2025年10月1日付で北海道ジェイ・アール都市開発を存続会社、BASE JAPANを消滅会社とする吸収合併を実施し、法人を集約して経営効率化を図ります。ホテルの名称は変更せず、運営を継続します。
参考:合同会社 BASE JAPAN の出資持分取得(子会社化)について
北海道中央バス株式会社 × ニセコバス株式会社
北海道中央バス株式会社は2024年9月13日、連結子会社のニセコバスを完全子会社化すると発表しました。ニセコバスが中央バス総業から自己株式を取得し、取得後に消却するスキームです。
北海道中央バスは旅客運送の他、不動産・ホテル・飲食・公衆浴場・旅行業を展開しています。ニセコバスは、旅客自動車運送事業を営んでいました。
本件の目的は、連結体制の下でグループ経営の自由度を高め、経営資源をグループ内で有効活用することです。
参考:連結子会社(ニセコバス株式会社)の完全子会社化に関するお知らせ
北海道新聞社 × 株式会社イー・シー
北海道新聞社は2025年5月27日、MICE(大規模国際会議・展示会)の運営会社株式会社イー・シー(東京・渋谷)の全株式を取得し、完全子会社化したと発表しました。取得額は非公表で、同社にとってM&Aは初の取り組みです。
イー・シーは2007年に札幌で創業し、政府主催の国際フォーラムや国際スポーツ大会の運営、会議通訳・同時通訳・翻訳を手がけ、札幌で「HAI北海道通訳アカデミー」を運営してきました。27日付で久松伸一氏が退任し、北海道新聞社アンビシャス・プロジェクト推進室の寺町誠志氏が社長に就任しました。従業員27人はそのまま引き継がれます。
北海道新聞社は、創刊以来培ってきた信頼・ネットワーク・イベント力と、イー・シーのMICE運営ノウハウを掛け合わせ、イベント・観光領域でのシナジー創出と事業領域の拡張を進め、地域経済・観光振興への貢献を目指す方針です。
株式会社COC × 株式会社たくみや
北海道コンフェクトグループの一社である株式会社COC(札幌市)は、2024年12月27日付で、土産用菓子の製造・販売を手掛ける株式会社たくみや(石川県小松市)の全株式を取得し、完全子会社化しました。これにより、たくみやは北海道コンフェクトグループに参入しました。
COCは洋菓子の販売に加え、新ブランド・新規事業の企画開発やバックオフィス機能を担います。たくみやは土産用菓子の製造・販売を展開しています。
グループ側は成長に向けて新ブランド開発・販売チャネル多様化・製造能力の増強を模索しており、たくみやも次世代商品の開発や製造拠点の有効活用を課題としていました。両社は協議の末、大きなシナジーが見込めるとしてグループ参入に合意し、今後はたくみやの事業基盤とグループの経営資源を掛け合わせ、より多くの皆さまに「まだ見ぬ、おいしい」を届けていく方針です。
参考: 株式会社COCによる株式会社たくみやの全株式取得のお知らせ
イオン北海道株式会社 × 株式会社西友
イオン北海道は2024年10月1日付で、西友の北海道事業から道内9店舗を承継しました。承継後は売場運営・システム・看板の切替などを行い、10~12月にかけて順次再オープンしました。ブランドはイオン(GMS/フード&ドラッグ)6店舗、マックスバリュ1店舗、ディスカウント業態「BiG」2店舗として再スタートしました。
背景には、2015年のダイエー9店舗承継、2020年のマックスバリュ北海道との経営統合で培った運営ノウハウを生かし、道内ネットワークをさらに拡大する狙いがあります。
参考:株式会社西友の北海道事業の承継に伴う9店舗の営業についてのお知らせ
北海道でM&Aを成功させるポイント
北海道でM&Aを成功させるには、地域特有の産業構造や社会的背景を踏まえた準備と対応が不可欠です。共通の基礎ポイントを押さえつつ、売り手・買い手それぞれの立場に応じた戦略を計画的に実行することが、成果を最大化する鍵です。
北海道でM&Aを成功させるための主なポイントは次のとおりです。
共通
- M&Aの目的と優先順位を明らかにする
- 地域に根ざした専門家・支援機関を頼る
- 従業員や取引先とともに歩む体制を築く
売り手側
- 自社の現状を客観的に棚卸しする
- 必要な情報を整理し、透明性を高める
- 売却の好機を見極めて動く
買い手側
- 徹底したデューデリジェンスでリスクを洗い出す
- 高い相乗効果を描ける相手を探す
- 統合後の姿を描き、計画的に進める
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
【共通】M&Aの目的と優先順位を明らかにする
M&Aを進める際の第一歩は、取引の目的と譲れない条件を具体的に整理することです。
最初に経営者自身が「何を優先すべきか」を明確化しておくことで、交渉の判断軸がぶれにくいです。売り手は「後継者問題の解消」や「従業員の雇用維持」、買い手は「新市場開拓」や「事業基盤強化」などを意識する必要があります。
目的が曖昧なままでは交渉が迷走し、結果として成約に至らないリスクが高まります。
【共通】地域に根ざした専門家・支援機関を頼る
財務・法務・税務など幅広い専門知識が必要となるため、仲介会社やアドバイザーの選定が成否を左右します。
北海道では、全国規模の仲介会社に加えて、農業・観光・物流といった地域産業に特化した専門家も多く存在します。さらに、サテライトオフィスを設けている公的機関や、オンラインで相談可能な公的支援機関も整備されており、地方の企業でも利用しやすい環境が整っています。
無料で相談できる場所も多いため、初期段階からこうした機関を積極的に活用することが望ましいです。地域事情に精通したパートナーを早期に確保することで、候補企業の発掘から交渉・成約までの精度が高まります。
【共通】従業員や取引先とともに歩む体制を築く
M&Aは経営者同士の合意にとどまらず、従業員や株主、主要取引先にまで影響を及ぼします。従って、早い段階から関係者との信頼関係を築き、安心感を与えることが不可欠です。
売り手は従業員に将来像を示して不安を和らげ、買い手は統合後のビジョンを丁寧に共有することが重要です。
関係者を置き去りにしたまま進めれば、不信感や離職といった深刻な問題につながりかねません。
【売り手側】自社の現状を客観的に棚卸しする
売却を検討する企業は、まず自社の財務状況や経営課題を客観的に整理する必要があります。
外部の専門家に診断を依頼すれば、自社では気付けなかった改善点が見つかるケースも少なくありません。
特に北海道は観光業や一次産業など地域依存度が高いため、外部視点で強み・弱みを把握することが企業価値の適正評価につながります。
【売り手側】必要な情報を整理し、透明性を高める
M&A交渉では、財務・契約・労務・知財など多方面の情報が求められます。
情報を早期に正確かつ一貫して整えておくことが、交渉のスムーズ化に直結します。整った情報開示は、買い手の信頼を獲得すると同時に、交渉スピードを加速させる効果があります。
逆に不透明な情報が残れば、条件面で不利になるリスクが高まります。
【売り手側】売却の好機を見極めて動く
売却のタイミングは企業価値を大きく左右します。
特に景気変動の大きい業界では、準備不足によるタイミングの遅れが致命的な機会損失につながります。
北海道では観光需要や一次産業の市況変動に左右されやすいため、業績が安定している時期に動くことが有利です。また、複数候補と比較できる状況を作ることで、条件面での優位性を確保できます。
【買い手側】徹底したデューデリジェンスでリスクを洗い出す
買い手は対象企業の財務・法務・人事などに加え、地域特有のリスクを調査対象に含めることが不可欠です。
一次産業の季節変動リスクや観光業の景気依存度、物流コストの高さなどは北海道特有の要素であり、軽視すると買収後に予期せぬ負担を招きかねません。
徹底したデューデリジェンスが、長期的な安定経営の土台となります。
【買い手側】高い相乗効果を描ける相手を探す
単なる規模拡大ではなく、自社の強みと相手の強みをどう組み合わせればシナジーを生み出せるかを見極めることが重要です。
シナジーの有無を事前に試算しておけば、買収後の具体的な成果をイメージしやすくいです。
北海道では観光と食品加工、農業と物流など、地域特性を生かした組み合わせが特に効果を発揮します。
【買い手側】統合後の姿を描き、計画的に進める
M&Aの本当の成否は、契約締結後の統合プロセスにかかっています。
従業員の定着や地域コミュニティとの関係維持が重要となる北海道では、統合後の経営方針や将来像を明確に示すことが不可欠です。
統合計画を具体的に描き、早期にPMIを実行することで、関係者の不安を和らげ、スムーズな移行を実現できます。
M&Aの相談に関するQ&A
最後に、北海道のM&Aに関するよくある質問とその回答を紹介します。
北海道のM&Aではどの業界が活発か
帝国データバンクの調査によると、北海道における過去5年間(2019〜2024年)のM&A実施率は9.9%でした。
規模別にみると、大企業の実施率は17.6%と高く、中小企業(8.3%)、小規模企業(8.0%)に比べて積極的にM&Aを活用していることが分かります。
業界別では、小売業が21.3%と最も高く、次いで金融業(15.4%)、不動産業(13.6%)が続きます。一方で、農・林・水産業では過去5年間にM&Aを実施した企業が確認されず、業界による取り組みの差も明らかです。
北海道でM&Aをする際の注意点はあるか
北海道でM&Aを進める際には、過半数の企業が「規制強化の必要がある」と考えている点を踏まえることが重要です。調査によると、全体の52.9%が規制強化を求めており、特に中小企業では54.1%と大企業(47.1%)を上回りました。
業界別では、金融業(61.5%)や製造業(60.8%)、小売業(59.6%)で規制強化を求める声が目立ちます。背景には、悪質なM&Aが発生した際に従業員の雇用や取引先への影響が大きく、社会的問題に発展しかねないという懸念があります。
北海道でM&Aの将来性はあるか
調査によると、北海道で「今後5年以内にM&Aに関わる可能性がある」と回答した企業は26.6%で、前回調査から低下しました。内訳は売り手15.7%、買い手7.2%、両方3.6%で、事業承継を背景とした動きが中心です。
規模別では大企業が42.4%と高く、中小・小規模企業を大きく上回りました。業界別では不動産業(40.9%)、小売業(40.4%)、金融業(30.8%)が目立ち、将来性のある分野として注目されます。
北海道の中小企業はどこにM&Aを相談すべきか
北海道の小規模事業者は、まず北海道事業承継・引継ぎ支援センターや各地の商工会議所、北海道中小企業家同友会といった公的・地域団体が有力な相談先です。
これらの機関は無料または低コストで利用でき、M&Aの初期段階から専門家による助言やサポートを受けられる点が大きな利点です。
さらに、自社の規模や業種に応じてマッチングを行うM&A仲介会社を活用することも有効です。具体的な相手先の探索や条件交渉の支援を得ることで、スムーズにM&Aを進めやすいです。
札幌以外でもM&Aは実施されているか
札幌以外でも、北海道内では十勝や旭川といった地域でM&Aが実施されています。
十勝では、昭和30年創業の畳屋を大手畳機械メーカー出身の起業家が承継した事例があります。音更町商工会の経営指導員が両者の思いをくみ取り、関係者との丁寧な調整を重ねることで、承継が実現しました。新社長は営業力を生かしながら新商品開発や補助金を活用し、事業拡大にもつなげています。
このように、札幌以外の地域でも商工会や支援機関が積極的に関与することで、地域に根差した中小企業の事業承継・M&Aが進められています。今後も十勝や旭川をはじめ、各地で同様の動きが広がることが期待されます。
M&Aの相談はどのタイミングで始めるべきか
M&Aを具体的に決断する前の段階から、選択肢の一つとして意識した時点で相談を始めることが望ましいといえます。
北海道には、北海道事業承継・引継ぎ支援センターや北海道よろず支援拠点など、無料で利用できる公的相談窓口が整備されており、初期段階から気軽に活用できます。
早めに専門家へ相談することで、自社の現状を客観的に整理し、必要な準備を前もって進められます。その結果、自社の希望条件に近い相手と出会える可能性が高まります。
M&AのサポートならM&Aロイヤルアドバイザリーへ
M&Aの相談を東京都で検討している場合、まず自社の目的や条件を明確にすることが大切です。市場の動向や競争環境は日々変化しており、信頼できる相談先を選ぶことが成功への第一歩となります。M&Aは複雑なプロセスですが、しっかりとした準備と専門家の支援があれば、安心して進められます。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、経験豊富なアドバイザーが、M&Aの検討からマッチング、実行、契約まで全面的にサポートいたします。相談は無料ですので、M&Aに関心をお持ちの中小企業の経営者様はお気軽にご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。