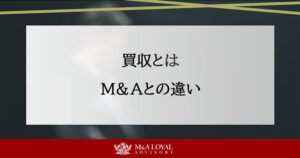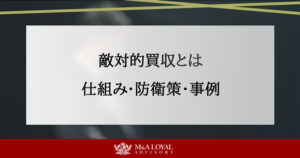友好的買収とは?目的やデメリット、敵対的買収との違い、事例を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
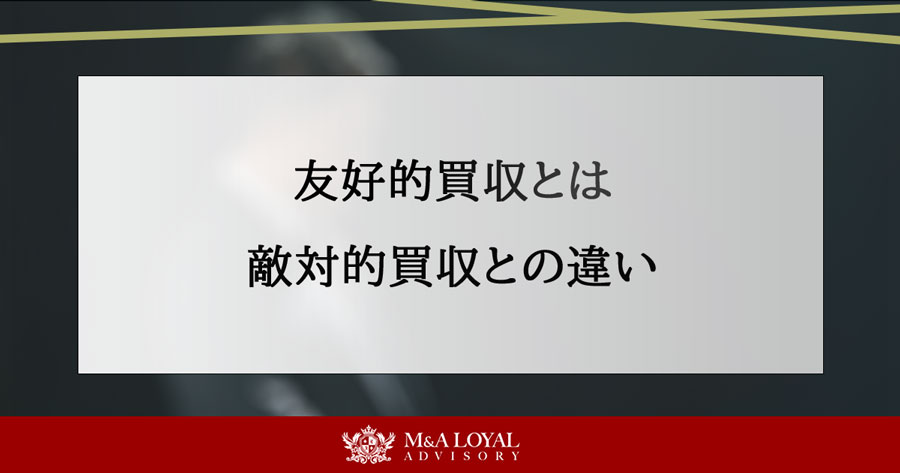
友好的買収は、M&Aの成功確率が高い王道戦略です。売り手企業の同意を得て実施されるため、円滑に進むケースが多く、統合後のシナジー創出やPMI(経営統合)の成功にもつながりやすいとされています。一方で、過剰な期待や買収価格の過大評価によるリスクも内包しています。
本記事では、友好的買収の概要や敵対的買収との違い、メリット・デメリット、手法や成功のポイント、代表的な事例まで詳しく解説します。
目次
友好的買収とは
まず、友好的買収に関する基本的な知識について解説します。
友好的買収とは同意を得て行う買収のこと
友好的買収とは、買収する企業(買い手側)と買収される企業(売り手側)が自主的かつ合意の上で実施されるM&Aの形態です。株式譲渡や第三者割当増資など、具体的な手法にかかわらず、対象企業の経営陣や株主と協議し、合意に至っていれば友好的買収と見なされます。買収後も両社が協力関係を維持し、シナジーの創出や利益の最大化を目指すことが特徴です。
ただし、形式的な合意があったとしても、実質的に売り手側が強制や圧力を受けていた場合、それは「友好的買収」とは見なされないことが一般的です。友好的買収は、双方が対等な立場で意図を共有し、長期的な利益を追求することが重要です。
例えば、企業間での技術力の補完や市場シェアの拡大を目的とした買収が成功した場合、両社の協力によって大きなシナジー効果を生むことが期待されます。一方で、買収後に経営方針の違いや文化の相違が問題となり、協力関係がうまく機能しないリスクもあります。
友好的買収を実現し成功に導くためには、事前の十分な協議と、買収後の統合プロセス(PMI: Post-Merger Integration)の適切な実行が重要です。
友好的買収と敵対的買収との違い
敵対的買収は、対象企業の経営陣や親会社などの同意を得ずに進められる買収のことです。主に株式公開買い付け(TOB)を通じて株主から株式を取得し、3分の1以上の株式を保有することで株主総会の特別決議を阻止したり、過半数を取得して経営権を掌握し子会社化を目指します。なお、TOB以外にも株式市場での買い集め(市場買付け)などが手段として用いられる場合もあります。
敵対的買収は、対象企業側の協力を得られないため、情報が制限されることや、買収後の統合が困難になるリスクがあります。また、買収に要するコストが高額になる点も課題です。特に、敵対的買収の対象となる企業は防衛策(ポイズンピルやホワイトナイトなど)を講じることが多いため、買収プロセスがさらに複雑化する可能性があります。
これらのリスクを伴うため、敵対的買収には慎重な計画と十分な資金力が求められます。
日本国内での買収の傾向
日本におけるM&Aの大半は、友好的買収によって実施されています。
この傾向の背景には、取引先や金融機関との信頼関係を重視する企業文化があり、合意に基づく買収でなければ取引関係や信用に悪影響を与える可能性があるためです。また、日本企業の多くは非上場であり、株式譲渡に制限があるケースも多いため、敵対的買収の余地は限られています。
2000年代には村上ファンドやライブドアによる敵対的買収が注目を集めたものの、成功例は多くありません。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



友好的買収のメリット
友好的買収のメリットとして、次の点が挙げられます。
- 敵対的買収よりも成功する可能性が高い
- 売り手企業との協力でシナジー効果が生まれやすい
- 経営統合(PMI)がスムーズに進みやすい
- 取引先や金融機関の心証悪化が防げる
それぞれについて解説します。
友好的買収は敵対的買収よりも成功する可能性が高い
友好的買収は、買収対象企業の同意と協力を得て行うため、敵対的買収に比べて成功率が高い点が大きなメリットです。合意の上で進めることで、買収価格の正確な算定や、デューデリジェンスなどの手続きもスムーズに行えます。
一方で敵対的買収は、対象企業の同意を得ずに行われるため、情報の提供が受けられなかったり、防衛策が講じられたりするため、買収が失敗に終わるリスクが高いです。
友好的買収は売り手企業との協力でシナジー効果が生まれやすい
友好的買収は、買い手企業と売り手企業が協力的な関係を築いた上で経営統合を進めるため、買収後にシナジー効果が期待される点が大きな特徴です。人材の確保やノウハウの共有が実現しやすく、統合によって単独で事業を行うよりも、売上拡大やコスト削減、新市場進出といった具体的な成果が期待されます。
例えば、大企業が中小企業を買収するケースでは、中小企業は大企業のブランド力や販売ネットワークを活用して事業を拡大しやすくなります。一方、大企業側は中小企業が持つ新しい技術や革新的なサービスを獲得し、自社の競争力を強化できるというメリットがあります。
ただし、友好的買収であっても経営統合が適切に行われなければ、文化や組織の違いが障害となり、シナジー効果が十分に発揮されないリスクもあります。成功のためには、事前の十分な計画と統合後の綿密な管理が必要です。
友好的買収は経営統合(PMI)がスムーズに進みやすい
友好的買収は、売り手企業と買い手企業の間であらかじめ信頼関係が築かれていることが多く、買収後の経営統合も円滑に進みやすい点がメリットです。
双方が協調し合う関係の下で統合が進められるため、業務フローの整備やシステムの統合、人事制度の調整なども合意形成が図りやすく、混乱が最小限に抑えられます。
逆に、敵対的買収では、経営陣や従業員が買収に否定的な姿勢を示すことが多く、買収後の統合段階であつれきが生じやすいです。特に、企業文化の違いや従業員の士気低下といった問題が起きると、想定していた統合効果が得られない可能性も高まります。
友好的買収は取引先や金融機関の心証悪化が防げる
友好的買収は、買収先の取引先や従業員、金融機関など関係者との信頼関係を維持しやすく、統合後の業務継続や人材流出防止にプラスに働きます。ただし、経営統合が適切に進まない場合、期待したシナジーが得られないリスクもあります。
一方、敵対的買収は、対象企業の意向に反して進められるため、取引先や金融機関、従業員などに悪い印象を与える可能性があります。その結果、信用低下や取引縮小、従業員の退職などの影響が生じる場合があります。
これらのリスクを踏まえ、買収後の統合計画を慎重に策定し、関係者への丁寧な説明を行うことが成功の鍵となります。
友好的買収のデメリット・リスク
友好的買収のデメリット・リスクとして、次の点が挙げられます。
- 株主が不利益を被る場合がある
- 思ったとおりのシナジー効果が得られない場合がある
- 交渉が長期化しやすい
- 買収後に想定外の支出が必要になる場合がある
それぞれを詳しく解説します。
友好的買収は株主が不利益を被る場合がある
友好的買収では、買い手と売り手の経営陣が主導して話を進めるため、一般株主の利益が軽視される恐れがあります。株主を重要な意思決定の当事者として捉え、利益を考慮することが不可欠です。
日本では株主の利益を明確に保護する法制度が十分に整備されておらず、経営陣や大株主が中心となって決定を進めた結果、少数株主に十分なプレミアムが提示されない事例もあります。
上場を視野に入れる企業や外部株主が存在する企業においては、株主の同意を得ずに買収を進めた場合、株主の反発によって買収が頓挫するリスクがあります。
友好的買収は思ったとおりのシナジー効果が得られない場合がある
たとえ友好的買収であっても、期待していたシナジー効果が得られないことがあります。
特に買収の完了を優先しすぎると、その後の経営統合が不十分になり、結果的に統合効果を発揮できずに終わるケースが見られます。経営統合は、シナジー効果を実現するための重要なプロセスであり、ここでの失敗は企業価値の毀損(きそん)につながることもあります。
経営統合をおろそかにした結果、業務の非効率や従業員の混乱が生じ、かえって業績が悪化したという事例も存在します。
友好的買収は交渉が長期化しやすい
友好的買収は、売り手企業との合意を前提とするため、交渉や調整に時間がかかりやすい傾向があります。両社の利害調整や、経営方針・人事体制のすり合わせといった統合準備に加え、法的手続きや独占禁止法の審査が必要となるケースではさらに時間を要します。
また、交渉期間中に市場環境が変化することもあり、株価の変動によっては買収価格の再調整が求められる場合もあります。こうした変動要因への対応も交渉の長期化につながります。
友好的買収は買収後に想定外の支出が必要になる場合がある
企業買収においては、表面上は健全に見える企業であっても、買収後に簿外債務や偶発債務、不正会計などが発覚するリスクがあります。こうした情報は帳簿に記載されておらず、買収前の調査で完全に把握するのは困難です。
加えて、商品のリコールや顧客への損害賠償といった対応が必要になる場合もあり、想定外の支出が発生する可能性があります。
友好的買収の手法
友好的買収の手法としては、次の方法があります。
- 株式譲渡
- 第三者割当増資
- 株式移転
- 株式交換
- 株式交付
- 事業譲渡
それぞれを分かりやすく解説します。
株式譲渡
株式譲渡とは、売り手企業が保有する株式を買い手企業に譲渡し、その対価として譲渡代金を受け取ることで経営権を移転するM&A手法です。法人格を維持したまま事業を承継できるため、手続きが比較的簡単であり、中小企業のM&Aで広く利用されています。後継者不在の解決策としても有効です。
株式譲渡では、従業員や取引先への影響が比較的小さいとされていますが、買い手企業による経営方針の変更や組織再編が行われる場合、影響が生じる可能性もあります。また、買い手は売り手企業の簿外債務だけでなく、過去の法的トラブルや税務リスクなども引き継ぐ可能性があるため、事前のデューデリジェンスが重要です。
株式譲渡は中小企業だけでなく、大企業間のM&Aでも活用されるケースがあり、柔軟性の高い手法として広く採用されています。
第三者割当増資
第三者割当増資とは、売り手企業が新たに発行した株式を買い手側が引き受けることで、資金提供と同時に経営権の一部を取得する手法です。買い手側は新株を引き受けることで議決権を獲得し、売り手企業の経営に参画します。この手法は、経営支援や資本提携を目的とする場合によく用いられ、段階的に経営統合を進めたいケースにも適しています。
また、第三者割当増資は、既存株主の持株比率が低下する(株式の希薄化)特性があります。このため、既存株主の利益が損なわれる可能性があり、条件によっては反発を招くこともあります。特に、新株発行の価格や割当先が不公平に見える場合、既存株主との間でトラブルが生じることがあります。そのため、第三者割当増資を実施する際は、既存株主への十分な説明と同意を得ることが不可欠です。
この手法は、買い手企業が段階的に議決権を獲得しながら売り手企業との関係を深めることができるため、長期的な戦略に基づく資本提携や経営統合に適した柔軟な手段となります。
株式移転
株式移転とは、既存の会社の全株式を新たに設立する完全親会社に移転し、その新会社を完全親会社とする企業再編の手法です。単独株式移転は1社でのグループ化に、共同株式移転は2社以上の経営統合に用いられます。
株式移転は、既存の法人格を維持したままグループ化できる点や、完全親会社が発行する新株を対価として用いる点が特徴です。このため、株式を活用した柔軟な資本構成の設計が可能です。
ただし、株主総会での特別決議(総議決権の過半数の出席およびその3分の2以上の賛成)や債権者保護手続きが必要であり、手続きが複雑で準備の負担が大きいことがデメリットです。また、株価算定や会計処理、持株比率の調整など、技術的な検討事項も多く発生します。
株式移転は主に企業再編やグループ経営の効率化を目的として活用され、戦略的な資本関係の構築に有効な手法とされています。
株式交換
株式交換とは、売り手企業の全株式を買い手企業が取得し、その対価として自社の株式を売り手企業の株主に交付する手法です。
対価が現金ではなく株式であるため、資金に余裕がない場合でも実行しやすいという利点があります。また、法人格を維持したまま経営統合を進められるため、ブランドや組織構造を一定程度保持した状態で段階的に統合を図れます。
一方で、株主の交換比率を正確に算定するための手続きには時間とコストがかかります。さらに、買い手企業の株式を交付することで株主構成に変化が生じるため、既存株主への影響も踏まえた慎重な対応が必要です。
株式交付
株式交付は、2021年の会社法改正によって導入された新しいM&A手法です。買い手企業が自社の株式を対価として売り手企業の株式を取得し、子会社化を進める制度です。
従来の株式交換が100%の完全子会社化を前提としていたのに対し、株式交付は過半数から100%まで柔軟に対応できるため、段階的な出資や資本提携の場面でも活用しやすくなっています。
この手法により、買い手企業は一定の出資比率で関与しつつ、将来的に完全子会社化へ移行する計画的な統合も可能です。資金を用意せずとも自社株を使って買収できる点も大きな特徴であり、戦略的なグループ再編の選択肢として注目されています。
事業譲渡
事業譲渡とは、企業が営む事業の一部または全部を他の企業に譲渡するM&A手法です。
譲渡対象の範囲を柔軟に設定できるため、売り手企業にとっては不要部門の整理や「選択と集中」の戦略に有効です。買い手企業にとっても、必要な資産や人材のみを取得でき、効率的な経営資源の獲得が可能です。
一方、事業譲渡は会社法上の組織再編行為には該当せず、譲渡対象ごとに個別契約が必要です。例えば資産や負債の移転、従業員や取引先との契約再締結、許認可の再取得など、煩雑な手続きが発生します。
友好的買収の成功のポイント
友好的買収の成功のポイントは次のとおりです。
- 買収の目的を明確にする
- 楽観的な経営戦略を立てない
- 企業価値を適正に評価する
- トップ面談を丁寧に行う
- 入念なデューデリジェンスを実施する
- 経営統合には細心の注意を払う
それぞれについて解説します。
買収の目的を明確にする
友好的買収を成功させるには、まず買収の目的を明確にすることが重要です。「なぜ買収が必要なのか」「どのような効果を期待するのか」を明確にした上で、買収対象企業の選定や手法の決定を進めなければ、期待した成果は得られません。
目的が曖昧なまま買収を進めると、シナジー効果を発揮できない誤った相手を選んでしまうリスクが高まります。
また、買収目的の明確化は、交渉や統合後の方針決定においても軸となるため、最初の段階で十分に検討しておく必要があります。
楽観的な経営戦略を立てない
友好的買収における失敗要因として、事前に策定された経営戦略が楽観的すぎることが挙げられます。買収は、企業が抱える課題を解決し、成長や事業拡大を目指すための手段であるため、現実的な視点に基づいた戦略の策定が必要です。
「買収すれば何とかなるだろう」といった楽観的な前提で買収を進めると、期待していたシナジー効果が得られず、損失に転じてしまう危険があります。
経営戦略を立てる際は、実行可能性の高い数値やデータを根拠として、事業環境やリスクも踏まえた上で具体的な施策を設計すべきです。
企業価値を適正に評価する
企業価値を適正に評価することは、友好的買収を成功に導く上で不可欠です。
財務諸表の数字や株価だけに依存した評価では、簿外債務や偶発負債、不正会計といったリスクを見落とす可能性があります。過大評価によって高値で買収してしまうと、買収後に思うような効果が得られなかった場合に財務負担が増し、経営を圧迫する恐れがあります。
企業価値を評価する際には、DCF法や類似企業比較法といった方法を用いて、財務状況や将来性、競争環境を多角的に分析する必要があります。
トップ面談を丁寧に行う
友好的買収では、買収前に設けられるトップ面談が極めて重要です。トップ面談とは、買い手企業と売り手企業の経営陣が直接対話し、買収の目的や条件、統合後の方針、リスク管理などを確認し合う場です。この面談を丁寧に実施することで、信頼関係を構築し、買収後のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。そのため、形式的な対話にとどめず、価値観やビジョンの共有を重視することが重要です。
トップ同士が相互理解を深め、一貫したメッセージを従業員や取引先に発信することで、買収への不安を軽減し、安心感を与えることができます。また、トップ間の信頼関係が構築されることで、買収価格や条件の交渉が円滑に進む可能性があり、結果としてコスト削減や時間短縮につながることも期待されます。
トップ面談は、単なる確認作業ではなく、双方の企業が共通の目標を持つための基盤を築く場であり、成功する友好的買収に欠かせないステップです。
入念なデューデリジェンスを実施する
デューデリジェンスは、友好的買収の成功を左右する重要な調査プロセスです。買収対象企業の財務状況や法務リスク、将来の業績見通しなどを多角的に調査することで、潜在的な問題を洗い出せます。
調査が不十分であると、買収後に簿外債務や契約リスク、不正会計などの重大な問題が発覚し、損失を被る恐れがあります。デューデリジェンスでは、調査対象や範囲をあらかじめ整理し、重要度の高い領域から優先的に確認することが大切です。
特に、資産や負債、知的財産、許認可、訴訟リスクなどについては丁寧な確認が必要です。慎重かつ計画的に調査を進めることで、買収後のリスクを最小限に抑えられます。
経営統合(PMI)には細心の注意を払う
経営統合は、買収後にシナジー効果を実現するために不可欠なプロセスです。買収が成功したとしても、統合に失敗すれば想定していた効果は得られず、企業価値が毀損するリスクがあります。
経営統合では、組織再編や人材配置、ブランドの統合、業務プロセスやITシステムの連携など、多くの要素を段階的に調整する必要があります。また、従業員の不安や反発を抑えるために、経営陣同士の連携や十分なコミュニケーション戦略も欠かせません。
経営統合における阻害要因を事前に洗い出し、丁寧に対処していくことが統合成功の鍵です。なお、統合計画は買収前から策定しておくことが望ましく、計画的かつ友好的な進行が求められます。
友好的買収の手順
友好的買収を実施する際の手順は次のとおりです。
- 買収先の検討と必要書類の準備
- トップ面談の実施
- 基本合意書の締結
- デューデリジェンスの実施
- 最終契約書の締結
- クロージング
それぞれを順番に解説します。
買収先の検討と必要書類の準備
友好的買収の最初のステップは、買収先の検討と必要書類の準備です。
買い手企業は、業種や地域、売り上げ規模などの希望条件をM&A仲介会社に伝え、それに基づいて候補企業の一覧が提示されます。この時点では、企業名を伏せたノンネームシートが用いられ、企業概要や売却理由などの基本情報が記載されています。興味を持った企業があれば、企業概要書(IM)などの詳細資料が開示されます。
一方、売り手企業はM&A仲介会社と契約を結び、資料作成や買収条件の整理を進めます。買い手と売り手がそれぞれの意図や条件を明確にした状態で情報を交換することで、信頼関係の構築が始まり、次の段階であるトップ面談へと進む準備が整います。
トップ面談の実施
買収先の候補が絞られた後、買い手企業と売り手企業の経営陣によるトップ面談が実施されます。面談では、社風や経営への思い、事業の方向性などについて相互理解を深めることが目的です。なお、面談は1回限りではなく、双方が納得できるまで複数回にわたって実施されることが一般的です。
トップ面談に進む前、または初期段階で秘密保持契約(NDA)が締結され、売り手企業は買い手企業に対して一定の情報を提供します。さらに、トップ面談後に買い手企業から情報開示の依頼があり、売り手側が詳細な情報を提供する場面もあります。
面談を経て、買い手企業が買収を正式に進めたいと判断した場合には、売り手企業に対して意向表明書(LOI: Letter of Intent)が提出されます。この意向表明書では、買収条件の大枠やデューデリジェンスを実施するための合意が示されます。その後、基本合意書の締結へと進み、買収プロセスが本格化します。
基本合意書の締結
トップ面談を経て買収に向けた意思が固まると、買い手と売り手の双方で「基本合意書」を締結します。
基本合意書には、買収対象(会社または事業)や買収価格、デューデリジェンスの実施予定、スケジュール、独占交渉権、秘密保持義務、善管注意義務などが記載されます。原則として法的拘束力はありませんが、独占交渉権や秘密保持義務などの条項には拘束力を持たせることもあります。
基本合意書の締結後は、買収条件の最終確認やリスクの精査を目的とするデューデリジェンスのフェーズに進みます。
デューデリジェンスの実施
デューデリジェンスは、最終合意の前に行う重要な調査プロセスです。買い手企業が弁護士や公認会計士などの専門家に依頼し、財務・法務・事業・ITなどの観点から買収対象企業の詳細な分析を行います。
この調査により、簿外債務や偶発債務、不正会計などのリスクを把握し、買収価格の妥当性や契約内容の見直しにつなげられます。
調査結果をふまえた条件調整が完了すれば、いよいよ最終契約書の締結に進みます。
最終契約書の締結
デューデリジェンスを経て、買収に必要な条件やリスクが明確になった段階で、最終契約書を締結します。最終契約書には、買収対象や買収価格、クロージング条件、表明保証、誓約事項、補償条項、損害賠償、競業避止義務などの具体的な内容が記載されます。
なお、最終契約書には法的拘束力があり、違反した場合には損害賠償などの法的責任を問われる可能性があります。
最終契約書の締結が完了すると、実際の買収手続きであるクロージングへと進みます。
クロージング
クロージングとは、最終合意書に基づいて、当事会社が合意内容を実際に履行するプロセスを指します。売り手企業にとっては、株式や資産の引き渡し・名義変更などの実務対応を、買い手企業にとっては買収対価の支払いなどを意味します。
通常、最終契約書の締結日からクロージングまでには一定の期間が設けられます。ただし、契約時点で必要な手続きが既に完了している場合や、契約後に確実に完了させる前提が整っている場合には、契約日と同時にクロージングを実施することもあります。
友好的買収の成功事例5選
国内企業による友好的買収の有名な成功事例をいくつか紹介します。
ヤフーによるZOZOの買収
2019年9月、ヤフー株式会社は株式会社ZOZOに対し、株式公開買い付け(TOB)を実施して子会社化を進めました。創業者の前澤友作氏が保有株の大半(約37%)を売却し、経営から退いたことから、両社合意による友好的な買収とされています。
ヤフーはEC事業の強化を目指しており、ZOZOも成長戦略の一環として強力なパートナーを求めていたため、両社の利害が一致しました。
買収後、前澤氏は代表取締役社長を辞任し、ZOZOの経営は新体制に移行しました。ただし、ZOZOのブランドや事業運営は維持され、ヤフーとのシナジーを活かしながら、引き続き事業が継続されています。経営陣にはヤフーからのメンバーが加わり、両社のリソースを統合した新たな成長戦略が進められています。
武田薬品工業株式会社によるシャイアー社の買収
2019年1月、武田薬品工業株式会社は、アイルランドの大手製薬企業であるシャイアー社を買収し、完全子会社化しました。買収金額は約6兆8,000億円にのぼり、日本企業によるM&Aとしては過去最大規模となりました。
本買収は、両社の得意分野を補完的に統合し、研究開発力と製品ポートフォリオの拡充を図ることで、グローバルな競争力を強化することを目的としていました。
買収後、武田薬品は世界の製薬企業の中で売上高トップ10に入り、世界的な製薬メーカーとしての地位を確立するに至っています。
三菱UFJフィナンシャル・グループによるアコムの買収
2008年、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、消費者金融大手のアコムを友好的TOB(株式公開買い付け)によって連結子会社化しました。MUFGはTOBにより議決権比率を40.03%に引き上げ、アコムの事業ノウハウを活用してクレジットカード事業の強化や新たなサービス展開を目指しました。
一方、アコムはMUFGの支援を受けて経営の安定性を高めるとともに、事業基盤の強化を実現しました。この買収は両社の合意に基づく友好的買収であり、アコムのブランドと事業は維持されながら、MUFGとの連携を通じたシナジー効果が追求されています。
ソフトバンクによるボーダフォン日本法人の買収
2006年、ソフトバンクは、英ボーダフォングループの日本法人であるボーダフォン株式会社を1兆7,500億円で買収しました。この買収は、ボーダフォングループ本社との事前合意を経て実施されたものであり、代表的な友好的買収と位置付けられています。
当時、ソフトバンクは新たに携帯電話事業へ進出する意向を持っており、既に構築されていたボーダフォンの顧客基盤と通信インフラを活用することで、短期間で市場に参入できました。
その後、ソフトバンクは携帯キャリアとして急成長し、国内第3位のシェアを誇る企業へと成長を遂げています。
フジテレビジョンによるニッポン放送の買収
2005年、フジテレビジョン(現フジ・メディア・ホールディングス)は、ニッポン放送を子会社化するためにTOB(株式公開買い付け)を実施しました。当時、ニッポン放送がフジテレビジョンの筆頭株主でありながら、規模が小さい「逆転構造」が問題視されており、この是正が目的でした。
しかし、ライブドアがニッポン放送の株式を大量取得し、経営権を狙った敵対的買収を仕掛けたことで事態は複雑化しました。これに対抗するため、ニッポン放送はフジテレビジョン向けの第三者割当増資を実施し、フジテレビジョンがその株式を引き受けることで保有割合を引き上げました。この結果、フジテレビジョンはニッポン放送を子会社化し、ライブドアの買収を阻止しました。
この事例は、敵対的買収と友好的買収が交錯するなかで、買収防衛策(第三者割当増資)の有効性が議論されたケースとして注目されました。
友好的買収の失敗事例5選
国内企業による友好的買収のうち、失敗したと評価されている事例をいくつか紹介します。
日本郵政による豪トール社の買収
2015年、日本郵政は国内郵便事業の成長鈍化に備え、海外物流展開の足がかりとしてオーストラリアの大手物流企業トール社を約6,200億円で買収しました。両社の協調によるグローバル戦略の加速を狙った友好的買収でしたが、結果は大きく期待を裏切る形となりました。
買収後、資源価格の下落による景気低迷や、トール社が過去のM&Aで抱えていた非効率な重複事業などが露呈し、業績は急速に悪化しました。日本郵政はこれらのリスクを十分に把握できておらず、2017年には約4,000億円の減損処理を行う事態に陥りました。
この失敗により黒字予想だった決算は赤字に転落し、株主や市場からの信頼を大きく失う結果となりました。
DeNAによるiemoおよびペロリの買収
2014年、株式会社DeNAは、キュレーションメディアを運営するiemo株式会社および株式会社ペロリを買収しました。この買収は、キュレーションメディア事業を強化し、新たな収益源を確保することを目的として行われました。
しかしその後、運営されていたキュレーションメディアの一部に、医師監修のない医療情報や著作権を侵害する可能性のあるコンテンツが掲載されていたことが判明しました。この問題により、計10サイトが閉鎖され、DeNAは企業イメージの毀損や減損損失を計上する結果となりました。
問題の背景には、買収前のデューデリジェンスにおけるコンプライアンス意識の見極めが不十分だったことが挙げられます。また、買収後のDeNA自身のコンテンツ監修体制や運営管理の不備も、事態を招いた要因といえます。この事例は、M&Aにおいて買収企業のデューデリジェンスと買収後のガバナンス体制の構築がいかに重要であるかを示すものとなりました。
丸紅による米ガビロンの買収
2013年、丸紅は米国の大手穀物商社ガビロン社を約2,700億円で買収しました。アジア市場における穀物需要の拡大を見据えた戦略的かつ友好的な買収とされ、グローバルな農業事業の基盤強化が期待されていました。
しかし、買収後には米中貿易摩擦の激化や国際的な穀物価格の下落といった外部環境の悪化に直面し、当初描いていた収益シナジーは実現しませんでした。その結果、のれんや固定資産に対する大規模な減損処理が続き、2020年3月期には丸紅として過去最大の赤字を計上するに至りました。
経営再建を図るなか、丸紅は2022年に同社の主要事業をオランダの農業商社バイテラへ売却し、約550億円の売却益を得て事業の整理を進めました。
キリンホールディングスによる伯スキンカリオールの買収
2011年、キリンホールディングス株式会社は、ブラジルの飲料大手スキンカリオール社を子会社化し、ブラジル市場への進出を図りました。当時、スキンカリオール社はビール事業で国内第2位のシェアを持ち、成長市場として期待されていたブラジルにおける戦略的買収でした。
しかし、買収後にブラジル経済が急速に低迷し、価格競争が激化しました。スキンカリオール社の業績は悪化し、赤字経営に転落しました。
キリン社は経営再建を試みたものの好転せず、2017年にはハイネケン・インターナショナルの子会社であるババリア社に売却しました。
東芝によるウエスチングハウスの買収
2006年、東芝はアメリカの大手原子力企業ウエスチングハウスを約6,600億円で買収し、原子力事業の強化とグローバル展開を目指しました。
しかし、2011年の東日本大震災を契機に世界的に原発の安全性への懸念が高まり、事業環境が一変しました。さらに、ウエスチングハウスの経営統合(PMI)に失敗しただけでなく、アメリカでの原発建設費の増大や経営の不透明性により、2017年には同社が経営破綻に至りました。
東芝は最大7,000億円規模の損失を計上し、粉飾決算も発覚しました。中核事業の売却にまで追い込まれ、企業の信頼性と業績が大きく揺らぎました。
友好的買収に関するQ&A
最後に、友好的買収に関するよくある質問とその回答を紹介します。
友好的買収と敵対的買収はどちらの方がコストがかかるか
一般的に、友好的買収の方がコストを抑えやすい傾向があります。
敵対的買収では、買収対象企業が非協力的な態度を取り、必要な情報開示が得られないことがあります。そのため、買収価格が過大になる恐れがあり、さらには買収防衛策の発動によって買収自体が長期化し、法的手続きや交渉コストが膨らみます。
一方、友好的買収では、対象企業と事前に合意があるため、デューデリジェンスや契約交渉などの重要手続きが円滑に進みます。買収後の経営統合も比較的スムーズであり、無用な対立を避けられることから、間接的なコストを低く抑えられる点が特徴です。
友好的買収では役員や従業員の処遇はどうなるか
友好的買収では、買収先の経営陣や従業員の処遇について事前に協議が行われ、統合後の方針が合意形成された上で実行されることが一般的です。特に経営陣については、買収後の経営体制に一定期間残留するケースが多く、経営統合を円滑に進める役割を担います。
従業員についても、雇用の継続性が比較的高く、労働環境に与える影響は抑えられます。ただし、組織再編や人件費削減が避けられない場合、希望退職の募集や配置転換が行われることもあります。
友好的TOBとは何か
TOB(株式公開買い付け)には、友好的TOBと敵対的TOBの2種類があります。
友好的TOBとは、買収を行う企業が、対象企業の経営陣や主要株主の了承を得た上で行うTOBのことを指します。グループ企業を完全子会社化する場合などに活用され、対象企業の協力を得ながら、合意に基づく形で株式の取得が進められます。このため、正確な企業価値評価が可能となり、デューデリジェンスも円滑に行える点が利点です。
反対に敵対的TOBは、経営陣の同意を得ずに株式を大量取得し、経営権を掌握しようとする手法です。敵対的買収では対抗措置が講じられることが多く、買収に失敗するリスクや余計なコストも発生します。
ホワイトナイトとは何か
ホワイトナイトとは、敵対的買収を仕掛けられた企業に対して、友好的に買収や資本参加を行う第三者企業を指します。白馬の騎士になぞらえてこう呼ばれ、対象企業の経営陣と協力し、敵対的買収からの防衛を目的とします。
一般に、ホワイトナイトは対象企業よりも規模や資金力に勝る企業であり、敵対的買収者よりも高い価格でTOBを行う「カウンターTOB」や、第三者割当増資の引き受けなどが主な手段とされます。
具体的な事例では、2006年に明星食品に対して米スティール・パートナーズが敵対的TOBを実施した際、日清食品がホワイトナイトとして友好的TOBを行い、買収防衛に成功しました。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
友好的買収はM&Aの成功確率が高いため、M&Aを検討している企業でもし友好的買収の機会があるなら、ぜひ前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
M&Aや経営課題に関して関心をお持ちの方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。