減価償却費は消費税の処理で変わる!税込・税抜で異なる3つの影響
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
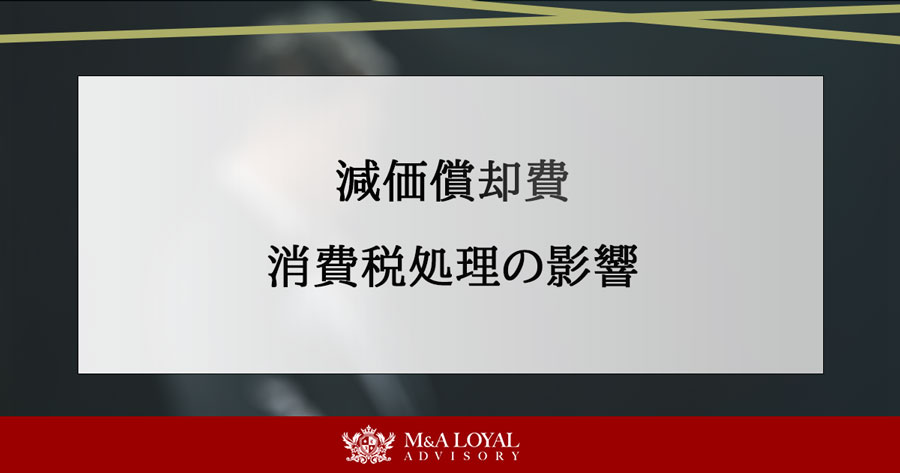
中小企業の経理担当者にとって、減価償却費の計算は日常業務の重要な要素です。しかし、消費税の処理方法が減価償却費に与える影響について、正確に理解している方は意外に少ないのが現状です。
税込経理と税抜経理の選択により、同じ資産を購入しても取得価額や償却方法が変わり、結果として企業の税負担や資金繰りに大きな差が生じることがあります。特に2023年10月のインボイス制度導入後は、従来の処理方法では対応できない新たな課題も発生しています。
本記事では、減価償却費と消費税の関係を体系的に解説し、中小企業が実践できる節税対策までご紹介します。
目次
減価償却費は消費税の処理方法で変わる!
減価償却費の計算は、消費税の経理処理方法によって大きく影響を受けます。税込経理と税抜経理では固定資産の取得価額の判定基準が異なるため、同じ資産を購入した場合でも減価償却の取扱いが変わってくるのです。
特に中小企業にとって重要な少額減価償却資産の判定においては、消費税の処理方法により「一括損金算入できるか」「減価償却が必要か」という決定的な違いが生じます。この違いを理解することで、より効果的な節税対策を実施できるでしょう。
消費税の税込経理と税抜経理の違い
消費税の会計処理方法には、税込経理方式と税抜経理方式の2つがあります。税込経理方式は、仕入れや売上を消費税も含めた総額で記帳する方法です。例えば、税抜き100万円の設備を購入した場合、消費税10万円を含めた110万円を機械装置として計上します。
一方、税抜経理方式では、本体価格と消費税を分けて記帳します。同じ設備の場合、機械装置100万円と仮払消費税10万円に分けて処理します。この処理方法の違いが、固定資産の取得価額に直接影響し、減価償却費の計算基礎となる金額を左右するのです。
取得価額の判定における消費税の扱い
固定資産の取得価額は、採用している消費税の経理方式により異なります。税込経理では消費税込みの金額、税抜経理では消費税抜きの金額が取得価額となります。この差は特に10万円や30万円といった税法上の判定基準付近で大きな影響を与えます。
具体的には、税抜き98,000円のパソコンを購入した場合を考えてみましょう。税抜経理では10万円未満となり消耗品費として一括損金算入できますが、税込経理では107,800円となり固定資産として減価償却が必要になります。このように消費税の処理方法により、同じ資産でも会計処理が大きく変わってくるのです。
免税事業者と課税事業者での違い
消費税の課税関係により、採用できる経理方式に制限があります。免税事業者は、法人税や所得税の計算上、税込経理方式を強制適用されます。たとえ日々の管理目的で税抜経理方式で記帳していたとしても、税務申告の際には税込金額に基づいて所得を計算し直す必要があります 。これは、免税事業者が消費税の申告義務を負わず、支払った消費税をコスト(取得価額や経費)の一部として扱うためです。
課税事業者は税込経理方式と税抜経理方式のいずれも選択できますが、一度選択した経理方式はすべての取引に適用する必要があります。取引ごとに経理方式を変更することはできないため、事業の実態に応じて適切な方式を慎重に選択することが重要です。免税事業者から課税事業者になる際は、経理方式の選択が新たに可能になるため、税務上の影響を十分に検討して決定しましょう。
参照:国税庁「No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理」

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



減価償却費に消費税が与える3つの重要な影響
消費税の処理方法は、減価償却費の計算や税務処理に大きな影響を与えます。特に中小企業においては、これらの影響を正しく理解することで効果的な節税対策や資金繰りの改善につなげることができるでしょう。
ここでは、消費税処理が減価償却費に与える3つの重要な影響について、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。これらの知識を活用することで、より戦略的な経営判断を行うことが可能になります。
少額資産の判定基準が変わる
消費税の処理方法により、10万円や30万円といった少額資産の判定基準が大きく変わります。最も影響が大きいのは、中小企業の少額減価償却資産の特例における30万円未満という判定です。
具体例として、税抜き280,000円のパソコンを購入した場合を考えてみましょう。税抜経理では取得価額が280,000円となり30万円未満のため、少額減価償却資産の特例を適用して購入年度に一括損金算入できます。しかし、税込経理では308,000円となり30万円を超えるため、通常の減価償却が必要になります。
判定基準の違いによる主な影響は以下の通りです。
- 税抜経理:30万円の壁を越えにくい
- 税込経理:消費税分だけ判定額が高くなる
- 10万円判定:より多くの資産で差が生じる
- 資金繰り:初年度の節税効果に大きな差
この違いは資金繰りや税務負担に直接影響します。税抜経理の場合は購入年度に全額を経費計上できるため、その年度の課税所得を280,000円分圧縮できます。一方、税込経理では数年間にわたって減価償却することになり、初年度の節税効果は限定的になってしまいます。
減価償却費の計算額が増減する
消費税の処理方法は、減価償却費として毎年計上される金額に影響します。税込経理を採用している場合、取得価額に消費税が含まれるため、税抜経理と比較して減価償却費が多く計上されます。
例えば、税抜き1,000,000円の機械装置(耐用年数5年、定額法)を購入した場合、税抜経理では年間200,000円の減価償却費となります。しかし、税込経理では取得価額が1,100,000円となるため、年間220,000円の減価償却費が計上されることになります。
減価償却費の計算における主な違いは以下の通りです。
- 税込経理:消費税分だけ償却費が増加
- 税抜経理:本体価格のみで償却費計算
- 年間差額:消費税率に比例した差が発生
- 最終的影響:処分時点で合計損益は同じ
この20,000円の差額は、毎年の税務計算や資金計画に影響を与えます。税込経理の方が短期的には多くの減価償却費を計上できますが、資産の処分や売却が完了した時点では、結果として両者の合計損益に差は生じません。重要なのは、どちらの方法が企業の事業計画や資金繰りに適しているかを判断することです。
費用計上のタイミングが遅れる
消費税処理の選択により、費用を計上できるタイミングに大きな差が生じることがあります。特に10万円前後の資産を購入する場合、この影響は顕著に現れます。
税抜き98,000円の事務用品を購入した場合、税抜経理では10万円未満となり購入年度に全額を消耗品費として損金算入できます。しかし、税込経理では107,800円となり10万円を超えるため、固定資産として計上し減価償却が必要になります。これにより、本来であれば即座に経費化できる支出が、数年間にわたって分割計上されることになります。
免税事業者は税込経理のみの採用となるため、このような費用計上のタイミングの遅れが生じやすくなります。特に設備投資を積極的に行う成長企業では、税込経理により短期的な税負担が増加する可能性があります。このため、課税事業者への転換を検討する際は、税抜経理の採用による節税効果も併せて評価することが重要です。
減価償却費と消費税を考慮した少額減価償却資産の活用法
少額減価償却資産の特例は、中小企業にとって非常に強力な節税制度です。しかし、消費税の処理方法や適用要件を正しく理解していなければ、せっかくの特例を活用できない可能性があります。
この特例を最大限活用するためには、30万円未満の判定基準を正確に把握し、年間300万円の上限を戦略的に使い分けることが重要です。特に中小企業のM&Aにおいては、これらの処理が企業価値評価に影響することもあるため、適切な理解と運用が求められます。
30万円未満の判定基準を正確に把握する
少額減価償却資産の特例における30万円未満の判定は、採用している消費税の経理方式により異なります。税込経理を採用している場合は税込価格で、税抜経理を採用している場合は税抜価格で判定するのが原則です。
実務において最も重要なのは、この判定基準を踏まえた設備投資の計画です。例えば、税抜280,000円のパソコンを購入する場合、税抜経理であれば特例の適用が可能ですが、税込経理では308,000円となり適用できません。このため、設備投資を検討する際は、購入予定額を事前に経理方式に基づいて確認することが重要です。
また、判定は資産の単位ごと(1台、1個、1セットなど)に行います。同じ種類のパソコンを複数台購入する場合でも、1台あたりの価格が30万円未満であれば、それぞれに特例を適用できます。ただし、機能的に一体として使用される設備については、全体で1つの資産として判定されるため注意が必要です。
中小企業の特例を最大限活用する
少額減価償却資産の特例を適用するためには、中小企業者等の要件を満たす必要があります。この特例の大きなメリットは、通常であれば数年間にわたって減価償却が必要な資産を、購入年度に一括で損金算入できることです。
特例を適用するためには、企業が以下の要件をすべて満たす必要があります。
【対象となる法人・個人事業主の要件】
- 青色申告を行っていること。
- 資本金または出資金の額が1億円以下であること。
- 常時使用する従業員の数が500人以下であること。
【適用除外となる条件】
- 大規模法人(資本金1億円超の法人等)に株式の1/2以上を所有されるなど、実質的に支配されている法人は対象外。
- 適用年度を含む過去3年間の所得金額の年平均額が15億円を超える法人も対象外。
- 令和4年4月1日以降に取得した資産のうち、貸付の用に供したもの(主要事業として行われるものを除く)は対象外。
【手続き上の要件】
- 取得した事業年度の決算で費用として経理(損金経理)すること。
- 確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付すること。
特に利益が多く出た事業年度においては、この特例を活用することで大幅な節税効果を得られます。実務上の注意点として、特例の適用には確定申告時に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の添付が必要です。また、損金経理が適用要件となっているため、決算書上で費用として計上することが必須です。資産として計上したままでは、たとえ税務申告で特例を主張しても適用を受けることができません。
年間300万円の上限を計画的に使う
少額減価償却資産の特例には、年間合計300万円という上限が設けられています。この上限を効果的に活用するためには、年間を通じた設備投資計画の策定が重要です。
実際の運用においては、事業年度の早い時期に上限に達してしまい、年度後半に購入した資産で特例を適用できないケースがあります。これを避けるためには、年間の設備投資予定を事前に把握し、優先順位を付けて特例を適用する資産を選択することが重要です。
特に注意すべきは、事業年度が12ヶ月に満たない場合の計算です。設立初年度や決算期変更により事業年度が短縮された場合、上限額は「300万円÷12×事業年度の月数」で計算されます。例えば、6ヶ月の事業年度であれば150万円が上限となります。また、他の特別償却制度や税額控除制度との重複適用はできないため、どの制度が最も有利かを慎重に検討する必要があります。
【償却資産税に関する重大な注意点】
法人税・所得税とは別に、地方税である「償却資産税」についても考慮が必要です。この特例を適用して損金算入した30万円未満の資産は、償却資産税の課税対象となります。
一方で、取得価額10万円未満で消耗品費として処理した資産や、20万円未満で「一括償却資産」として3年償却した資産は、償却資産税の対象外です。この違いは、特に10万円台の資産を取得する際に、どちらの処理が最終的に有利になるかの重要な判断材料となります。
減価償却費と消費税におけるインボイス制度の影響
2023年10月にスタートしたインボイス制度は、減価償却費の計算にも大きな影響を与えています。特に免税事業者から固定資産を取得する場合、従来とは異なる取扱いが必要となり、減価償却費の計算方法も変更されました。
この制度変更により、中小企業の固定資産管理はより複雑になりましたが、経過措置期間中は一定の配慮も設けられています。正しい理解と適切な対応により、税務リスクを回避し効率的な経営を維持することが可能です。
免税事業者からの仕入れで取得価額が変わる仕組み
インボイス制度導入後、適格請求書発行事業者以外(免税事業者等)からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除を行うことができません(経過措置期間除く)。これは固定資産の取得においても同様で、免税事業者から固定資産を購入した場合の消費税の取扱いが変更されています。
具体的には、税抜経理を採用している企業が免税事業者から固定資産を取得した場合、支払った消費税相当額のうち仕入税額控除の対象とならない部分の金額を、その資産の取得価額に加算しなければなりません。これにより、税抜経理であっても実質的に取得価額が膨らむことになります。
例えば、免税事業者から1,100万円で建物を購入した場合、従来であれば建物1,000万円、仮払消費税100万円として処理していました。
しかし、インボイス制度後は消費税相当額100万円全額を仮払消費税として処理することができません。仕入税額控除の対象となる金額のみを仮払消費税とし、残りは建物の取得価額に含める処理が必要になります。これにより、減価償却の対象となる固定資産の取得価額が増加し、毎年計上される減価償却費も増加することになります。
経過措置期間中の取得価額の計算方法
インボイス制度の急激な影響を緩和するため、一定期間に限り経過措置が設けられています。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間中は、免税事業者等からの課税仕入れについて消費税相当額の80%を仕入税額として控除することができます。
この経過措置を適用した場合の取得価額計算について具体例で説明します。免税事業者から1,320万円で建物を取得し、税抜経理を採用している場合を考えてみましょう。支払対価1,320万円のうち、消費税相当額は120万円(1,320万円×10/110)となります。
経過措置により仕入税額控除の対象となるのは120万円×80%=96万円です。したがって、仮払消費税として96万円を計上し、残りの24万円(120万円-96万円)は建物の取得価額に算入することになります。結果として、建物の取得価額は1,224万円(1,200万円+24万円)となり、この金額を基礎として減価償却費を計算することになります。
インボイス制度後の実務対応のポイント
インボイス制度に適切に対応するためには、まず取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認することが重要です。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索することで確認できます。固定資産のように高額な取引については、契約締結前に必ず確認しておくべきでしょう。
制度対応で重要な実務ポイントは以下の通りです。
- 取引先確認:適格請求書発行事業者の登録番号
- 帳簿管理:適格請求書と経過措置適用分の区分
- 台帳記載:控除対象外消費税の取得価額算入
- システム対応:会計ソフトの設定変更
- 専門家連携:税理士との情報共有強化
経理処理においては、適格請求書による仕入れと経過措置適用仕入れを明確に区分することが必要です。帳簿や証憑書類の管理方法も見直しが必要で、経過措置適用分については「80%控除対象」「免税事業者からの仕入」などの表示により区別することが求められます。
参照:政府広報オンライン「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」
減価償却費の消費税別処理における実務対応
減価償却費の処理において、消費税の経理方式による違いを正しく理解し、適切な仕訳と固定資産台帳への記載を行うことは、税務上の重要なポイントです。特に中小企業においては、経理担当者が正確な処理を行うことで、税務調査時のリスク軽減にもつながります。
ここでは、税込経理と税抜経理それぞれの具体的な処理方法について、実務で使える仕訳例と固定資産台帳への記載方法を詳しく解説します。これらの知識を身につけることで、日常の経理業務を効率的かつ正確に行うことができるでしょう。
税込経理での仕訳例と処理手順
税込経理方式では、固定資産の取得時から消費税を含めた金額で処理します。例えば、税抜価格1,000,000円の機械装置を現金で購入した場合、消費税100,000円を含めた1,100,000円で固定資産を計上します。
取得時の仕訳は、借方「機械装置1,100,000円」、貸方「現金1,100,000円」となります。この時点で、消費税を別途区分して計上する必要はありません。減価償却費の計算も、この1,100,000円を基礎として行います。耐用年数5年、定額法を適用する場合、年間の減価償却費は220,000円(1,100,000円÷5年)となります。
決算時には、借方「減価償却費220,000円」、貸方「機械装置減価償却累計額220,000円」の仕訳を行います。税込経理の場合、消費税の処理は決算時にまとめて行うため、減価償却費の計上時点では消費税を意識する必要がありません。ただし、決算時に消費税の申告額を確定した際は、租税公課として費用計上することになります。
税抜経理での仕訳例と処理手順
税抜経理方式では、固定資産の取得時から消費税を本体価格と区分して処理します。同じく税抜価格1,000,000円の機械装置を現金で購入した場合、取得時の仕訳は借方「機械装置1,000,000円」「仮払消費税等100,000円」、貸方「現金1,100,000円」となります。
この処理により、固定資産の取得価額は消費税を除いた1,000,000円となります。減価償却費の計算もこの1,000,000円を基礎として行うため、耐用年数5年、定額法適用の場合、年間の減価償却費は200,000円(1,000,000円÷5年)となります。税込経理と比較して年間20,000円少ない金額となる点が重要な違いです。
決算時の減価償却費計上仕訳は、借方「減価償却費200,000円」、貸方「機械装置減価償却累計額200,000円」となります。税抜経理では、消費税は取引の都度区分処理するため、減価償却費の計上においても消費税の影響を受けません。ただし、仮払消費税と仮受消費税の相殺により確定した納付税額は、決算時に適切に処理する必要があります。
固定資産台帳への記載方法
固定資産台帳への記載は、採用している消費税の経理方式に準じて行います。税込経理を採用している場合は、消費税込みの金額を取得価額として記載し、税抜経理の場合は消費税抜きの金額を取得価額として記載します。
税込経理の場合の記載例として、先述の機械装置では取得価額1,100,000円、耐用年数5年、償却方法定額法、年間償却額220,000円と記載します。備考欄には「税込経理方式適用」などと記載しておくと、後から確認する際に便利です。
税抜経理の場合は、取得価額1,000,000円、耐用年数5年、償却方法定額法、年間償却額200,000円と記載します。この場合も備考欄に「税抜経理方式適用、消費税等100,000円」などと記載しておくことで、取得時の詳細を明確にできます。
インボイス制度対応として、免税事業者からの取得については特別な記載が必要です。経過措置適用の場合、仕入税額控除できなかった消費税相当額は取得価額に算入するため、その内訳を明示しておくことが重要です。例えば「取得価額内訳:本体価格1,000,000円、控除対象外消費税相当額24,000円」などと記載することで、税務調査時の説明も円滑に行えます。
減価償却費と消費税処理で節税効果を最大化する方法
減価償却費と消費税の処理方法を戦略的に活用することで、中小企業は大きな節税効果を得ることができます。特に設備投資のタイミングや経理方式の選択は、長期的な資金繰りに大きな影響を与えるため、慎重な検討と計画的な実行が重要です。
ここでは、実際の企業経営で活用できる節税戦略について、具体的な方法論とその効果について詳しく解説します。これらの知識を活用することで、税務負担を適正化し、企業の成長資金を確保することが可能になります。
資金繰りを考慮して経理方式を選択する
消費税の経理方式選択は、単なる会計処理の問題ではなく、企業の資金繰りに直接影響する重要な経営判断です。税抜経理を選択した場合、少額減価償却資産に適用しやすくなり、初年度の費用計上額を増やすことができます。これは短期的なキャッシュフローの改善に大きく貢献します。
例えば、年間の設備投資額が500万円程度ある企業の場合、税抜経理を採用することで少額減価償却資産の特例適用件数が増え、初年度に損金算入できる金額が大幅に増加する可能性があります。この効果により、法人税の軽減と資金留保の両方を実現できます。
ただし、税抜経理は記帳作業が複雑になり、経理担当者の負担が増加する側面もあります。また、免税事業者から課税事業者になったばかりの企業では、税込経理の方が処理に慣れているケースが多いでしょう。このような場合は、記帳システムの整備や経理担当者の教育も含めて総合的に判断することが重要です。
設備投資のタイミングを戦略的に計画する
設備投資のタイミングは、減価償却費の計上時期と密接に関係するため、事業年度末との関係を考慮した戦略的な計画が必要です。特に少額減価償却資産の特例については、年間300万円の上限を効果的に活用するため、投資時期の分散が重要になります。
具体的な戦略として、利益が多く見込まれる事業年度には積極的に設備投資を行い、少額減価償却資産の特例を最大限活用することが有効です。逆に、利益が少ない年度や赤字が予想される年度には、特例の適用を翌年度に繰り延べることで、節税効果を最大化できます。
また、中小企業経営強化税制など他の優遇制度との併用も検討すべきです。ただし、少額減価償却資産の特例と他の特別償却制度は重複適用できないため、どの制度が最も有利かを慎重に比較検討する必要があります。税理士など専門家との連携により、企業の状況に最適な選択を行うことが重要です。
税務調査に備えて適切な書類を整備する
減価償却費と消費税に関する処理は、税務調査において重点的にチェックされる項目の一つです。特に少額減価償却資産の特例適用については、要件の充足や上限額の管理について詳細な確認が行われます。これに適切に対応するためには、日常的な書類整備が不可欠です。
税務調査対応で必要な書類は以下の通りです。
- 明細書:少額減価償却資産の取得価額明細書
- 証憑書類:請求書・契約書・領収書の保管
- 確認記録:取引先の適格請求書発行事業者登録
- 計算根拠:経過措置適用時の80%控除計算書
- 社内書類:経理方式選択の社内規程・決議録
インボイス制度対応として、取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認記録も重要です。経過措置適用の場合は、80%控除を適用した計算根拠を明確にし、固定資産台帳への記載も詳細に行う必要があります。
さらに、消費税の経理方式についても一貫性を保つことが重要です。原則として、期中で経理方式を変更することはできないため、選択した方式を確実に適用し、その根拠となる社内規程や決議録なども整備しておくべきです。これらの準備により、税務調査時に適切な説明ができ、企業の信頼性向上にもつながります。
まとめ|減価償却費と消費税の処理を正しく理解して節税につなげよう
減価償却費と消費税の処理方法は、中小企業の税務戦略において非常に重要な要素です。税込経理と税抜経理の選択により、少額減価償却資産の判定基準が変わり、費用計上のタイミングや節税効果に大きな影響を与えることがわかりました。
特に重要なのは、30万円未満の判定基準を正確に把握し、年間300万円の上限を計画的に活用することです。また、インボイス制度の導入により、免税事業者からの仕入れについては新たな処理が必要となっており、適切な対応が求められています。
これらの知識を実務に活用することで、適正な税務処理を行いながら効果的な節税を実現できます。中小企業のM&Aにおいても、これらの処理が企業価値評価に影響するため、正しい理解と適用が重要です。税理士などの専門家と連携しながら、自社に最適な消費税処理方法と減価償却戦略を構築していきましょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。














