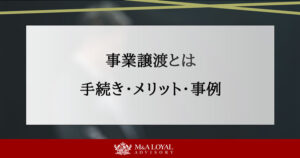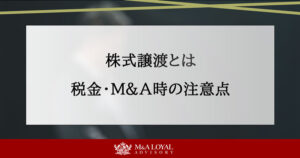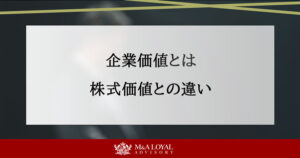会社譲渡とは?手続きや価格の決め方、税金、事業譲渡との違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
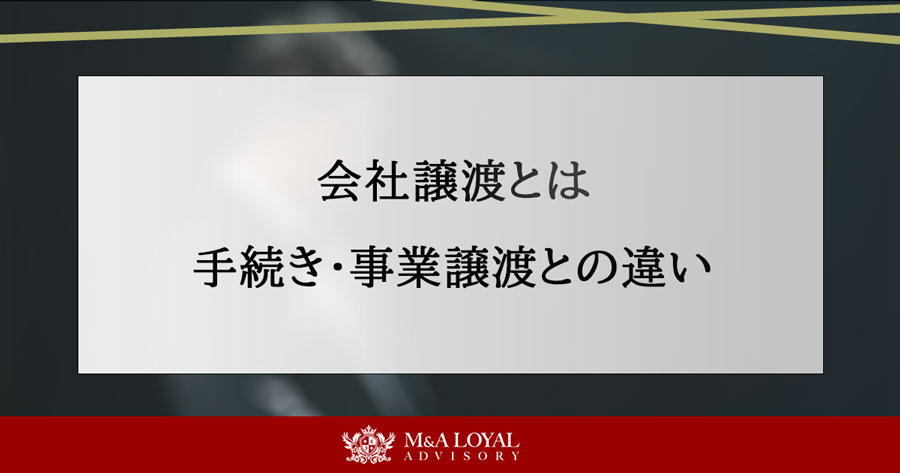
近年、後継者不足や資金問題の解決方法として会社譲渡を行う中小企業が増加していますが、どのような方法や手続きで行われるのでしょうか。
この記事では、会社譲渡に関する基本的な知識や実施するメリットやデメリットを解説します。
また、実際に会社譲渡を行う際の流れや手続きの内容、成功させるためのポイント、相場なども併せて解説します。
目次
会社譲渡とは
会社譲渡の定義や、どのような方法で譲渡が行われるかについて解説します。
会社譲渡の定義
会社譲渡とは、一般的には会社の経営権を第三者に譲り渡すことを指し、通常は株式の譲渡によって行われます。この場合、会社の事業・資産・負債・従業員などはそのまま会社に帰属し、株主が変わる形で経営権が移転します。経営者の引退や事業の方向転換、成長戦略の一環として活用されることが多いです。
なお、「企業譲渡」という言葉は日常的に「会社譲渡」と同義で使われることがありますが、法的には「事業譲渡」を指す場合もあります。株式譲渡と事業譲渡では、譲渡される対象や法的手続きが異なるため、正確な意味を理解することが重要です。
会社譲渡は「株式譲渡」と同じ意味で使われることが多い
会社を売却する方法には、大別して会社ごと売る「株式譲渡」と、事業のみを売る「事業譲渡」があります。一般的に「会社譲渡」といった場合は、株式譲渡を指すことがほとんどです。
株式譲渡とは、譲渡代金の支払いと引き換えに売り手が保有する株式を買い手に譲渡し、会社の支配権を移転するM&A手法です。株式譲渡では、売り手が保有する株式の全てを譲渡するケースもありますが、過半数の株式のみを譲渡する場合や一部の株式を譲渡する場合もあります。
株式譲渡は手続きが比較的簡単で、会社や事業をそのまま承継できるため、最も一般的で中小企業のM&Aでも広く使われています。
会社自体は存続するため、従業員や取引先への影響が少なく、後継者問題の解決策としても有効ですが、買い手は簿外債務などのリスクも引き継ぎます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式譲渡以外の会社譲渡の手段
株式譲渡以外の会社全体や会社の一部を売却する主な方法は次のとおりです。
- 事業譲渡
- 吸収合併
- 吸収分割
それぞれを解説します。
事業譲渡
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を他社に売却する取引で、法人格ごと
譲渡する株式譲渡とは異なる手法です。
売り手は不要な事業を切り離して整理でき、選択と集中を図ることができます。買い手にとっても、必要な資産や人材のみを選択的に取得できる点がメリットです。
一方、契約や資産移転を個別に行う必要があり、手続きは煩雑です。
吸収合併
吸収合併とは、買い手が売り手の全ての権利義務(資産・負債・契約など)を包括的に承継し、売り手が消滅する形の合併です。新会社を設立することなく既存の法人を残すため、他の合併形態に比べて手続きが比較的簡易であり、既存の組織体制を維持しやすいというメリットがあります。ただし、負債や契約の精査、人員調整などで手続きが複雑化する場合もあります。
この形態は、グループ企業の機能統合や、迅速な再編が求められる場合に多く用いられます。
吸収分割
吸収分割は、会社の事業の全部または一部を既存の他社に承継させる手法です。現金が対価となる事業譲渡と異なり、株式が対価となるケースが多いです。
好調な事業への集中や赤字部門の切り離し、他社との戦略的提携を目的とする場合に利用されます。また、包括的に事業を承継するため、契約や従業員関係もそのまま移行できる点がメリットです。
会社譲渡を判断する主なタイミング
一般的に会社譲渡を判断することの多いタイミングは次のとおりです。
- 早期退職(アーリーリタイア)を考えた
- 新しい事業・会社を起業したくなった
- 企業に将来性を感じなくなった
それぞれの具体的な背景について解説します。
早期退職(アーリーリタイア)を考えた
会社譲渡が行われる理由のひとつに、経営者自身の早期退職(アーリーリタイア)への希望があります。突然会社を閉鎖すれば、従業員の雇用や取引先との関係に大きな影響を与える恐れがありますが、第三者への譲渡であれば、会社の存続を図りながら自らの引退を実現できます。
また、譲渡によって得た資金を老後の生活資金として活用できます。
新しい事業・会社を起業したくなった
会社譲渡は、新たな事業や会社を起業したいという前向きな理由で行われることもあります。
株式譲渡や事業譲渡によって、資金調達とスムーズな経営移行の両方を実現できます。
企業に将来性を感じなくなった
会社譲渡の理由として、将来性への不安や業績の低迷が挙げられます。
会社や事業を第三者に譲渡することで、倒産を避けつつ譲渡益を得られる可能性があります。早期に判断すれば、負債や信用悪化のリスクを抑えながら出口戦略を描くことが可能です。ただし、譲渡益やリスク抑制には、譲渡対象の価値、交渉条件、譲渡タイミングなどが大きく影響します。
会社譲渡のメリット
会社譲渡によって得られるメリットは次のとおりです。
- 後継者問題の解決
- 売却・譲渡益を得られる
- 従業員の雇用確保・取引先との関係維持を実現しやすい
- 企業の存続・発展
- 個人保証や担保の解消
それぞれを詳しく解説します。
後継者問題の解決
会社譲渡の大きなメリットのひとつが、後継者問題の解決です。
近年では、経営者の高齢化や後継希望者の不足により、事業承継に悩む中小企業が増加しています。
帝国データバンクの『全国「後継者不在率」動向調査(2023年)』によると、後継者不在率は53.9%と、半数以上の企業が後継者不在という課題を抱えています。
売却・譲渡益を得られる
会社譲渡の大きなメリットのひとつは、株式の売却によって経営者が譲渡益を得られることです。
株式譲渡の場合、売却益は株主である経営者個人に直接帰属し、現金や株式などの形で対価を受け取ることが可能です。
このような利益は「創業者利益」とも呼ばれ、長年築いてきた会社の成果を資産として手にする機会となります。
従業員の雇用確保・取引先との関係維持
会社譲渡の大きなメリットとして、従業員の雇用確保と取引先との関係維持が挙げられます。特に中小企業では、後継者不在や経営難による廃業で従業員が職を失うリスクがありますが、会社譲渡により事業が継続されれば、雇用を守ることが可能です。
また、取引先や顧客との関係も維持され、買い手にとっては既存のネットワークを生かせる利点があります。これは新規開拓の負担軽減にもつながり、譲渡価格の上昇要因ともなります。
企業の存続・発展
M&Aによる会社譲渡によって大手グループの一員となれば、財務基盤の強化や新たな技術・販路の獲得が可能となり、再成長のチャンスが広がります。
加えて、新オーナーの経営資源を活用することで、社員のモチベーション向上や組織の活性化にもつながります。
個人保証や担保の見直し
会社譲渡や株式譲渡では、資産や負債、契約関係の引き継ぎ方法が異なります。特に、中小企業経営者にとって負担となる金融機関への個人保証は、事業譲渡や譲渡条件に応じて解消できる場合があります。
これにより、精神的・経済的な負担を軽減できる可能性がある点は大きなメリットです。
会社譲渡のデメリット・リスク
会社譲渡には次のようなデメリット・リスクが存在します。
- 旧経営者として拘束を受ける可能性
- 従業員や役員の処遇が交渉時と変わる可能性
- 多額の税金がかかる可能性
- 会社名が変わってしまう可能性
- 売却先が見つからない可能性
- 破談になる可能性
- 競業避止義務に注意
それぞれを詳しく解説します。
旧経営者として拘束を受ける可能性
会社譲渡を実施する際、旧経営者が一定期間会社に残ることを求められるケースがあります。この措置は「ロックアップ(キーマン条項)」と呼ばれ、買い手が事業を円滑に引き継ぐための対策です。
特に中小企業では、旧経営者が取引先や従業員との信頼関係維持に重要な役割を果たすため、数ヶ月から数年にわたって残留を求められることもあります。残留期間や役割は譲渡契約によって具体的に定められます。
また、売却対価が買収後の業績に応じて段階的に支払われる「アーンアウト」の形式になることもあります。
従業員や役員の処遇が交渉時と変わる可能性
会社譲渡後、役員や従業員の処遇について、交渉時に取り決めた内容が守られないリスクが存在します。
特に中小企業のM&Aでは、譲渡後に待遇や配置転換などが変更され、従業員の不満や離職につながるケースも見受けられます。
譲渡前の交渉段階で処遇条件を明確に取り決め、書面で合意しておくことが重要です。
会社名が変わってしまう可能性
会社譲渡後、買い手の意向によって、会社名が変更される可能性があります。これはブランド戦略やグループ内の名称統一などを目的とした経営判断によって行われるケースも多く見られます。
事前に社名変更の可能性を共有し、社内外に対する説明や告知を行った上で従業員へのフォローや取引先への案内など、アフターケアをしっかり行う必要があります。
多額の税金がかかる可能性
会社譲渡では、売却によって得た利益(譲渡益)に対して税金が課されます。
売却者が法人であれば法人税が、個人であれば所得税・住民税が課税対象となるため、実質的な手取り額が目減りする点には注意が必要です。
詳しい課税額やトラブルのリスクについては後述の「会社譲渡で課される税務」にて解説します。
売却先が見つからない可能性
会社譲渡(株式譲渡)は買い手がいて初めて成立する取引であり、希望する相手が見つからなければ譲渡自体が実現しません。
特に中小企業では、業績や将来性、人材構成などの条件によって買い手が見つかりにくく、最終的に廃業を選ばざるを得ないケースも存在します。
破談になる可能性
会社譲渡において、交渉が決裂するリスクもあります。
買い手との交渉が進んでいても、途中で簿外債務の発覚や機密情報の漏えいといった問題が明らかになると、信頼関係が損なわれ、最終的に破談となるケースがあります。
競業避止義務に注意
会社譲渡(特に事業譲渡)では、譲渡後に旧経営者が同様の事業を展開することを制限する「競業避止義務」が発生する場合があります。これは、譲渡の実効性を確保し、買い手の事業継続に支障が出ないようにするための法的枠組みです。
会社法第21条では、原則として売り手は、同一市町村およびその隣接地域内で20年間、同一事業を行ってはならないと定められています。
会社譲渡までの流れ
会社譲渡までの流れは次のとおりです。
- 会社譲渡の検討と準備
- M&A仲介会社と契約(ケースによる)
- 自社の価値算定
- 譲渡する企業の募集・決定
- 会社譲渡の手続き
- 会社譲渡の成立
- 会社譲渡の公表
- 会社の引き継ぎ
それぞれを順番に解説します。
会社譲渡の検討と準備
会社譲渡を進めるにあたっては、まず社内で「本当に譲渡が最善の選択肢であるか」を慎重に検討することが重要です。併せて、譲渡の方針や希望する実施時期、譲渡対象の範囲などを明確にしましょう。
検討の初期段階では、退職などの混乱を避けるため、信頼できる少数の関係者に限定し、情報管理を徹底することが重要です。
M&A仲介会社と契約
会社譲渡を検討する際は、信頼できるM&A仲介会社に相談し、契約を結びましょう。
譲渡手続きには財務・税務・法務などの専門的な知識が不可欠であり、自社のみで対応しようとするとリスクが高く、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
実績のあるM&A仲介会社をパートナーに選ぶことで、買い手の選定から条件交渉、契約書の作成まで一貫したサポートが受けられます。
自社の価値算定
会社譲渡を成功させるためには、まず自社の企業価値を正確に把握しておくことが重要です。譲渡金額の相場を理解せずに交渉を進めてしまうと、本来より低い価格で売却してしまうリスクが生じます。
企業価値の算定は専門的な知識と経験が求められるため、多くの場合はM&A仲介会社に依頼して行います。
譲渡する企業の募集・決定
自社の価値や譲渡相場を把握した後は、買い手の候補を選定します。
買い手は、経営権だけでなく、従業員や顧客、企業文化も引き継ぐ立場にあります。そのため、公式ホームページや公開資料を活用し、相手企業の実績や経営理念、人材活用方針などを慎重に確認しましょう。
買い手の候補が絞られた段階で、経営トップ同士による面談を行います。自社の強みや将来性をしっかり伝えるとともに、譲渡後の従業員の処遇や事業方針についての考えも確認しましょう。
会社譲渡の手続き
買い手候補との交渉や面談を経て、買い手が決定したら会社譲渡の手続きへと進みます。この段階では、具体的な契約条件の調整や書類の作成、必要な法的手続きなどが行われます。
会社譲渡の具体的な手続き方法については、次の項目で詳しく解説します。
会社譲渡の成立・公表
譲渡に関する手続きが全て完了すると、正式に会社譲渡が成立します。この時点で譲渡契約に基づく譲渡金額の受け渡しが行われ、経営権が買い手に移行します。
会社譲渡が成立した後は、その内容を社内外に適切な形で公表します。中小企業では従業員や取締役への丁寧な説明が中心となり、大企業の場合はマスコミや株主に対する正式な発表が求められます。
会社の引き継ぎ
会社譲渡が成立した後は、引き継ぎ作業を慎重かつ丁寧に進めることが重要です。経営権の移転だけでなく、取引先・顧客・従業員との関係や、業務フロー、財務・契約情報など、事業運営に必要なあらゆる情報を確実に引き継ぐ必要があります。
引き継ぎが不十分だと、従業員の離職や取引停止といった混乱を招き、買い手の経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
会社譲渡における手続き
会社譲渡における手続きは次のとおりです。
- 会社譲渡の承認請求
- 取締役会・株主総会の招集
- 会社譲渡契約
- 株主名簿の書き換え請求
- 株主名簿記載事項証明書の交付請求・交付
- 会社譲渡の完了
それぞれを順番に解説します。
会社譲渡の承認請求
株式譲渡制限会社の場合、株式の譲渡者は対象会社(今回売却する会社)に対して譲渡の承認請求を行います。所定の「株式譲渡承認請求書」に必要事項を記載し、対象会社に提出します。
中小企業では、経営者自身が株主である場合が多く、事前に承認が事実上得られているケースもあります。ただし、形式的であっても、会社の承認手続きは法律上必要です。
株式譲渡承認請求書とは、譲渡制限付き株式を譲渡する際、株式の譲渡者が対象会社に対して承認を求めるための書類です。譲渡株数や買い手の情報を記載します。
取締役会・株主総会の招集
承認請求を受けた対象会社は、株式譲渡の承認を審議します。
まず、取締役会設置会社では、取締役会が株式譲渡の承認について審議します。一方で、非設置会社の場合は、取締役が社内文書である「株主総会招集に関する取締役の決定書」を作成し、臨時株主総会の開催を正式に決定します。
その後、株主に対して「臨時株主総会招集通知」を送付します。この通知は、開催日時・場所・審議事項(株式譲渡の承認など)を株主に知らせるもので、法律上、原則として開催の1週間前までに送付しなければなりません。
臨時株主総会が開催されると、そこでの議事内容を記録した「臨時株主総会議事録」が作成されます。この議事録は、承認可否の決議内容を法的に明確化するための重要な文書です。
最終的に株式譲渡が承認された場合には、対象会社は株主の譲渡者に対し「株式譲渡承認通知書」を送付します。この通知書は、譲渡が正式に承認されたことを伝えるもので、承認請求から2週間以内に発行する必要があります。
株式譲渡契約
譲渡制限のある場合には株主総会での承認決議が必要となり、その後、株式の譲渡者と買い手の間で正式に「株式譲渡契約書」を締結します。この契約書には譲渡株数、金額、譲渡日、表明保証、競業避止義務など主要な条件が明記されます。
契約書はM&A仲介会社が提示する雛形をもとに、必要な修正を加えて最終的に確定されます。複雑な条件がある場合には、弁護士や専門家の関与が推奨されます。
株主名簿の書き換え請求
会社譲渡契約を締結した後は、譲渡後に株主名簿の名義を書き換えるための「株式名義書換請求書」を対象会社に提出し、「株主名簿」の書き換え請求を行う必要があります。
株式譲渡は、株式の譲渡者から買い手へ株式を移すだけでは法的に完結せず、対象会社が管理する株主名簿において名義が正式に書き換えられて初めて効力を持ちます。
株主名簿記載事項証明書の交付請求・交付
新株主となった買い手は、自身が株主であることを証明するため、「株主名簿記載事項証明書交付請求書」を対象会社に提出します。
対象会社は、株主名簿の記載内容に基づき「株主名簿記載事項証明書」を発行します。この証明書には、氏名や住所、保有株式数などが記載されており、新株主が正式に株主として登録されたことを証明する役割を持ちます。
会社譲渡の完了
以上の一連の手続きを全て完了すると、会社譲渡は正式に成立します。譲渡金額の決済や契約の履行、経営権の移転がこの時点で完了し、買い手が新たな株主としての権利を取得します。
会社譲渡で課される税金
会社譲渡によって課される税金は、個人株主か法人株主かによって異なります。
個人株主
個人が会社譲渡(株式譲渡)を行うと、譲渡益に対して所得税15%、住民税5%が課税されます。さらに、2037年までは復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されるため、合計で20.315%の税率が適用されます。
譲渡益は、譲渡金額から取得費や手数料などの譲渡費用を差し引いて算出します。取得費が不明な場合は、譲渡金額の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使用することができます。
法人株主
法人が株式を譲渡した場合、譲渡益に対して法人税が課税されます。個人と異なり、分離課税ではなく、通常の事業所得または営業外収益として課税対象となります。法人税率は法人の規模や所得に応じて異なります。中小法人の場合、所得800万円以下には15%、800万円を超える部分には23.2%の税率が適用されます。中小法人以外の場合、法人税率は一律23.2%です。
また、法人住民税や法人事業税、地方法人税も加わるため、実効税率は25〜35%程度となるのが一般的ですが、大法人で所得が非常に高い場合には、最大で40%を超えることもあります。
税務トラブルについて
譲渡益の過小申告や取得費の誤算、契約時期による課税タイミングのズレなどは、後に税務トラブルを引き起こす原因となります。
さらに、税金の申告や納付が遅れた場合には、延滞税や加算税が課されるリスクがあります。延滞税は納付遅延期間に応じて課され、加算税は過少申告や無申告、意図的な不正に対して課されます。これらのリスクを避けるため、適切な計算と申告が重要です。
また、株式譲渡が第三者間で行われる場合、市場価格に基づいた適正な評価が前提です(ただし、上場株式の場合。非上場株式の場合は市場価格が存在しないため、会社の純資産価額や収益力などをもとにした評価方法が用いられる)。一方、親子会社間や経営者間などの関係会社間取引では、税務署が時価調整や寄附金認定を行い、課税上の指摘を受けるリスクがあります。
会社譲渡の相
会社譲渡をする場合の相場について解説します。
会社譲渡の相場
会社の譲渡価格は譲渡・譲受の対象となる企業や事業の現時点における価値を金額として表したものであり、単一の基準によって決まるものではなく、買い手と売り手の交渉によって最終的に決定されることが一般的です。
そのため、明確な相場というものはありませんが、譲渡価格の決定要素や算出方法を組み合わせることで、一定の目安を知ることはできます。
価格決定の要素
会社の譲渡価格を決める際に考慮される要素について解説します。
財務状況
企業の財務状況は譲渡価格の重要な基準であり、資産から負債を引いた純資産が大きいほど企業価値が高まる傾向があります。ただし、企業価値は収益力や成長性なども総合的に考慮して評価されます。
また、将来の利益やキャッシュフローの安定性も重要な評価指標で、収益の見通しが明るい企業は、利益の複数年分で高く評価される傾向があります。
無形資産
企業の無形資産は譲渡価格に大きく影響します。顧客基盤、取引先との関係、ブランド力、特許、知的財産、技術力などが評価されます。
また、経営者のビジョンや優秀な従業員の存在も企業の魅力を高める要因です。赤字企業でも無形資産の価値が認められ、プラスの価格で譲渡されるケースがあります。
その他(市場環境・戦略・スキームなど)
譲渡価格は、財務や無形資産だけでなく、市場環境や当事者の事情、M&Aのスキーム(譲渡の方法)によっても大きく変動します。
市場価値や業界の成長性、競争状況も評価に影響を与え、買い手が大きなシナジー効果を見込んだ場合には、相場以上の価格が提示されることもあります。
また、株式譲渡か事業譲渡かといったスキームの違いも、手続きの負担やリスクの取り方に影響し、価格に反映されます。
価格算定方法
株式譲渡などのM&Aが実施される際、譲渡価格は主に「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」の三つを組み合わせて算出されます。
コストアプローチは、資産・負債から企業の純資産を算出し、主に中小企業や資産重視型に適用されます。
マーケットアプローチは、類似企業や過去のM&A事例を基に比較する手法で、市場の客観性が強みです。
インカムアプローチは、将来の収益やキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法で、成長企業に多く用いられます。
会社譲渡を成功させるポイント
会社譲渡を成功させるポイントは次のとおりです。
- 企業価値の向上
- 売却タイミング
- 専門家への相談
それぞれを解説します。
企業価値の向上
会社譲渡を成功させるためには、事前に企業価値の向上に取り組むことが極めて重要です。
まず、収益性の改善が基本です。業務効率の見直しやコスト削減により利益率を高めることで、営業利益の増加が期待でき、買い手からの評価が上がります。
次に、組織体制の強化が挙げられます。後継者の確保や人材育成に力を入れ、安定した経営体制を構築することで、買い手にとってリスクの少ない魅力的な企業となります。
さらに、資産整理も有効です。不要な設備や遊休不動産を処分して財務体質を健全化することで、資産の運用効率が向上し、企業の透明性と管理力がアピールできます。
売却のタイミング
企業の価値は業績に大きく影響されるため、業績が好調なタイミングでの売却は高値が期待でき、「いつ売るか」の判断が極めて重要です。
逆に、業績が下り坂になると売却条件が悪化しやすく、買い手探しや交渉が難しくなる恐れがあるため、売却時期の見極めがM&Aの成否を左右します。
専門家への相談
会社譲渡は法務・税務・財務といった専門知識が求められる複雑な取引です。
M&A仲介会社などの専門家は、これらの知識や実務経験を生かしてリスクを回避し、円滑な手続きを支援してくれます。
会社譲渡の際の相談先
会社譲渡を行う際の主な相談先は次のとおりです。
- M&A仲介会社
- 士業事務所
- 金融機関
それぞれの特徴について解説します。
M&A仲介会社
会社譲渡の場面では、M&A仲介会社の利用が最も一般的です。
M&A仲介会社に相談することで、譲渡プロセスを円滑に進められます。
企業の紹介から条件交渉、契約締結まで一貫してサポートしてくれるため、自社に合った買い手と出会える可能性が高まります。
士業事務所
税理士や弁護士といった士業事務所も、事業譲渡や売却の有力な相談先です。
税理士は企業価値評価や節税アドバイス、簿外債務の把握など、税務面を中心にM&Aの前後を幅広くサポートしてくれます。普段から付き合いのある税理士なら、気軽に相談できる点も利点です。
弁護士は契約書のリーガルチェックや法的リスクの助言に強く、安心して取引を進められます。
金融機関
金融機関は、会社譲渡の相談先として信頼性が高く、取引先銀行や地方銀行、信託銀行などは、日頃の関係性を生かして親身に対応してくれる傾向があります。また、豊富な取引先ネットワークを通じて、買収を希望する企業を効率的に紹介してもらえる可能性もあります。
さらに、金融機関を介することで手続きの信頼性が高まり、安心して会社譲渡を進められます。ただし、金融機関によっては大規模案件しか対応しない場合もあるため、事前の確認が必要です。
M&A仲介会社を利用する際のメリット・デメリット
会社譲渡においてM&A仲介会社を利用する場合のメリット・デメリットを解説します。また、利用の際の料金についても解説します。
メリット
M&A仲介会社を利用する最大のメリットは、法務・税務・財務に関する専門知識と豊富な実績を活用できる点です。
自社に合った買い手・売り手をマッチングしてくれるほか、価格交渉やスケジュール調整、契約書作成など煩雑な手続きも一括でサポートしてくれます。そのため、経営者は本業に集中しながら、安全かつスムーズに会社譲渡を進められます。
デメリット
M&A仲介会社の利用には、成功報酬をはじめとする費用負担が発生します。また、M&A仲介会社によって対応の質に差があり、経験や業界知識が乏しい会社に依頼すると価格設定や交渉が不利になることもあります。
さらに、売り手と買い手の双方を担当する「両手仲介」では、利益相反が生じるリスクがあります。提示された価格をうのみにせず、複数の仲介会社に相談して情報を比較・精査することが大切です。
M&A仲介会社を利用する際の料金
会社譲渡においてM&A仲介会社を利用する場合、発生する主な費用には「相談料」「着手金」「中間報酬」「成功報酬」の四つがあります。
相談料は初回相談時に発生する費用で、多くの仲介会社では無料とされていますが、一部では5000〜1万円程度の有料設定もあります。
着手金は正式に依頼する際に支払う費用で、人件費や資料作成費が含まれます。相場は、中小企業の場合は50万から200万円程度、大企業の場合は数百万円から数千万円程度です。不成立でも返金されないことが多いです。
中間報酬は基本合意書の締結時に支払う費用で、成功報酬の10〜30%が目安です。
成功報酬はM&A成立時に支払うメインの費用で、「レーマン方式」と呼ばれる取引金額に応じて段階的に料率が変わる計算方法が一般的です。
このほか、月額報酬などが別途発生する場合もあります。
会社譲渡の事例3選
ここ数年で行われた会社譲渡の例を紹介します。
タロスシステムズによるシンシアへの会社譲渡
2023年11月、コンタクトレンズ製造・販売を主力とするシンシア(東京都文京区)は、リユース業界向けPOSシステムを開発・提供するタロスシステムズ(千葉県千葉市)の株式51%を取得し、同社を連結子会社化しました。
シンシアは今回の買収を通じ、主力事業以外での収益源を確保し、事業ポートフォリオの多様化を図る狙いです。
タッグがタケエイに会社譲渡した事例
2023年10月、TREホールディングスの子会社であるタケエイ(東京都港区)は、株式会社タッグ(宮城県東松島市)の株式54.2%を取得し、同社を連結子会社化しました。
タッグは一般・産業廃棄物の収集運搬および中間処理を手がけており、タケエイが展開する廃棄物処理・再資源化事業との間で高いシナジー効果が見込まれます。
大久保鉄工所がMipoxに会社譲渡した事例
2023年10月、栃木県鹿沼市に本社を構えるMipox(マイポックス)は、同県宇都宮市に拠点を持つ大久保鉄工所の全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。
大久保鉄工所は部品の精密研磨加工を主業とする企業であり、Mipoxの中核事業である研磨フィルムや液体研磨剤の製造・販売、研磨装置開発などと親和性が高く、今回の買収によって受託研磨事業の領域拡大と多角化を図る狙いがあります。
会社譲渡に関するQ&A
最後に、会社譲渡に関するよくある質問とその回答を紹介します。
会社譲渡の相談はいつ始めるべきか
会社譲渡は、余裕を持って取り組むことが成功の鍵です。経営が安定しているうちに準備を始めることで、選択肢を広く持ち、希望に近い条件での譲渡が可能です。
逆に、急な体調悪化や引退によって時間的猶予がないと、交渉が不十分になったり、買い手との条件調整が難しくなるリスクがあります。
一般的には、売却や引退を考え始めた段階から3〜5年前に計画を立て、専門家へ相談することが理想的です。財務状況の整理や無形資産の強化、法務・税務の準備を行うための期間が必要です。
早めの準備が、経営者自身の納得いく承継と、事業の円滑な継続につながります。
赤字の会社でも売却できるか
赤字の会社でも条件次第で売却は可能です。M&Aでは事業価値や将来性が重視され、技術や顧客基盤が魅力的であれば買い手が見つかることがあります。
ただし、黒字企業に比べて譲渡価格は低くなる傾向があり、売却の判断を早めにすることが重要です。判断が遅れると資産価値や信頼性が低下し、売却が難しくなる恐れがあります。
休眠会社の譲渡価格はどのくらいか
休眠会社は、使用履歴にリスクがある「看板用休眠会社」と、長期間活動していない「事業用休眠会社」に分類されます。
譲渡価格は交渉によって異なるものの、資本金1000万円以上の有限会社で約30万円、株式会社では看板用が約30万円〜50万円、事業用が約35万円〜65万円程度が一般的な相場です。ただし、登記情報、履歴、納税状況などにより価格は変動します。
M&Aに関するご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
後継者不足や資金問題など、多くの中小企業が抱えている課題を解決する可能性がある「会社譲渡」。本記事でご興味をお持ちになりましたら、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。