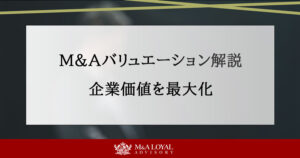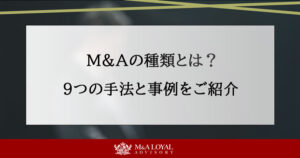簿価と時価の違いとは?計算方法やM&Aとの関係をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
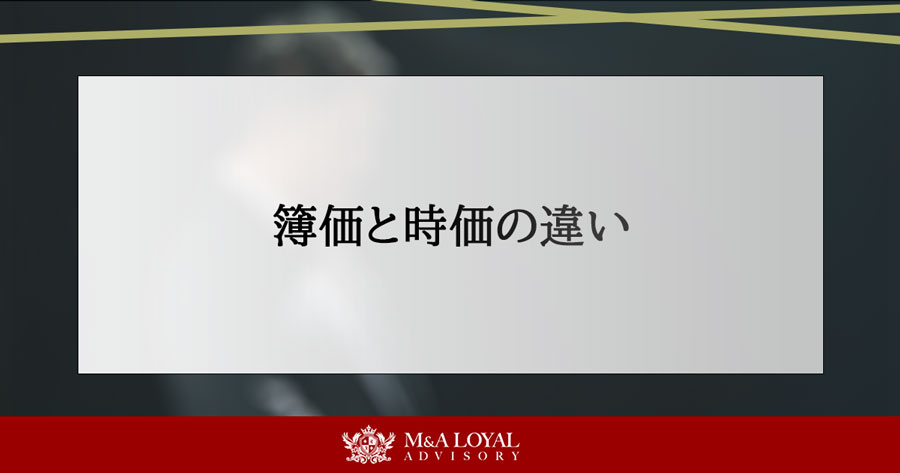
簿価と時価の違いを理解することは、企業経営や投資判断において非常に重要です。簿価とは、企業が資産を取得した際の原価を基にした帳簿上の価格であり、財務諸表に記載される基準となります。一方、時価は市場の現状を反映した価格であり、資産の現在の価値を示します。この違いを正確に把握することで、企業の真の財務状況を見極めることが可能となります。
特にM&Aの場面では、簿価と時価の違いを無視すると、企業価値の評価を誤り、適切な意思決定が困難になることがあります。本記事では、簿価と時価の違いを深掘りし、それぞれの計算方法と影響について詳しく解説します。
目次
簿価とは何か?基本的な仕組みと計算方法
簿価とは、企業の財務諸表に記載されている資産や負債の帳簿価格のことを指します。日本の会計制度では取得原価主義(資産を購入時の価格で記録し続ける方式)が採用されており、資産を取得した時点の価格で継続的に記録することが基本となっています。
簿価の定義と特徴
簿価は資産を取得した際の購入価格から減価償却費を差し引いた金額で算出され、市場の価格変動に関係なく一定の基準で計算されます。例えば、10年前に1億円で購入した土地は、現在の市場価格が2億円に上昇していても、簿価上は1億円のまま記載されています。この安定性が簿価の特徴であり、会計の継続性・比較可能性を保つ重要な役割を果たしています。
簿価の計算方法は資産の種類によって異なりますが、基本的には「取得原価-累計減価償却費-減損損失」で算出されます。この計算により、資産の帳簿上の価値を一貫した基準で把握することができます。
固定資産の簿価計算例
具体的な簿価計算方法を、建物を例に説明いたします。取得価格5,000万円の建物を耐用年数20年、定額法で減価償却する場合を考えてみましょう。
| 項目 | 金額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 取得原価 | 5,000万円 | – |
| 年間減価償却費 | 250万円 | 5,000万円÷20年 |
| 5年後の累計減価償却費 | 1,250万円 | 250万円×5年 |
| 5年後の簿価 | 3,750万円 | 5,000万円-1,250万円 |
このように簿価は取得時点の価格を基準とした機械的な計算により算出されるため、現在の市場価値とは大きく乖離する場合があります。特に不動産や株式などの資産では、この乖離が顕著に現れることが多く、M&Aにおいて重要な検討事項となります。
簿価純資産法による企業評価
簿価純資産法は、貸借対照表に記載されている資産から負債を差し引いて純資産を算出し、これを企業価値とする評価手法です。計算が簡単で客観性が高いという利点がありますが、M&A価格算定においては限界があります。
簿価純資産法は資産の現在価値を反映していないため、特に創業から年数が経過した企業や不動産を多く保有する企業では、実際の企業価値を大幅に過小評価してしまうリスクがあります。そのため、現在のM&A実務では簿価純資産法単独で企業価値を算定することは稀で、時価による修正が必要不可欠となっています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



時価とは何か?評価方法と算定基準
時価とは、現在の市場において成立するであろう適正な価格のことを指します。時価評価では、資産や負債の現在の市場価値を反映させることで、企業の実態により近い企業価値を把握することが可能になります。
時価の基本概念と重要性
時価は市場の需給関係や経済情勢を反映した現在の適正価格であり、M&Aにおいて買い手が実際に支払う価格の基準となる重要な指標です。簿価が過去の取得価格に基づく静的な数値であるのに対し、時価は現在の市場環境を反映した動的な価値評価といえます。
時価評価では、不動産については不動産鑑定士による鑑定評価、有価証券については市場価格や類似会社比較による評価、機械設備については専門業者による査定などが行われます。これらの専門的な評価手法により、資産の真の価値を把握することができます。
主要資産の時価評価方法
資産の種類別に、具体的な時価評価方法を整理いたします。それぞれの資産には適切な評価手法があり、専門知識が必要な場合も多くあります。
| 資産の種類 | 時価評価方法 | 評価のポイント |
|---|---|---|
| 土地・建物 | 不動産鑑定評価 | 立地条件、利用状況、収益性を総合評価 |
| 上場株式 | 市場価格(終値等) | 評価基準日の市場価格を採用 |
| 非上場株式 | 類似会社比較法、DCF法等 | 将来収益性や類似企業との比較 |
| 機械装置 | 専門業者査定、減価償却後再調達価格 | 稼働状況、技術的陳腐化を考慮 |
不動産時価査定では、固定資産税評価額や相続税評価額を参考にしつつ、実際の取引事例や収益性を踏まえた総合的な評価が重要となります。特に事業用不動産の場合は、単純な土地価格としての評価ではなく、事業継続性やアクセス性なども考慮した評価が必要です。
時価純資産法による企業価値算定
時価純資産法は、すべての資産と負債を時価で評価し直し、時価純資産を算出する手法です。この方法により、簿価純資産法の問題点を解決し、企業の実態により近い価値を把握できます。
時価純資産法では含み益や含み損が明確になるため、簿価では見えなかった企業の真の財務状況を把握することが可能になります。例えば、簿価1億円の土地が時価評価で3億円となった場合、2億円の含み益が存在することが判明し、これは企業価値の重要な構成要素となります。
ただし、時価評価には専門的な知識と相応の費用が必要となるため、評価の目的や重要性を考慮して実施の可否を判断することが重要です。M&Aにおいては、デューデリジェンス(買収前の詳細調査)の一環として詳細な時価評価が実施されることが一般的です。
簿価と時価の具体的な違いと影響
簿価と時価の違いは、企業の財務状況の理解やM&Aの価格算定において重要な影響を与えます。この違いを正しく理解することで、より適切な経営判断や価格交渉が可能になります。
帳簿価格と市場価格の乖離要因
簿価と時価の乖離は、取得時期の違い、市場環境の変化、資産の性質、会計基準の制約などが主な要因となります。特に長期間保有している不動産や株式では、この乖離が顕著に現れることが多く、企業価値評価において重要な検討事項となります。
例えば、バブル期前に取得した都心の不動産は、簿価では低い価格で計上されているものの、現在の時価では大幅に上昇している可能性があります。逆に、IT関連の機械設備などは技術進歩により時価が簿価を大幅に下回ることもあります。
含み益と含み損の企業価値への影響
含み益とは時価が簿価を上回る部分、含み損とは簿価が時価を上回る部分です。これらは簿価会計の財務諸表には直接現れませんが、企業の真の価値を判断する上で極めて重要な要素です。
| 項目 | 含み益の場合 | 含み損の場合 |
|---|---|---|
| 企業価値への影響 | プラス要因(価値向上) | マイナス要因(価値減少) |
| 売却時の税務 | 有価証券売却益として課税対象 | 売却損として損金算入可能 |
| M&A価格への影響 | 価格上昇要因 | 価格下落要因 |
| 計上タイミング | 売却実行時に実現 | 減損処理または売却時に実現 |
含み益や含み損の存在は、M&A後の事業運営や財務戦略に大きな影響を与えるため、買い手にとって重要な検討材料となります。特に含み損がある資産については、買収後の減損処理や売却によるスリム化など、具体的な対処方針を検討する必要があります。
会計基準と時価会計導入の影響
近年の会計基準改正により、時価会計の適用範囲が徐々に拡大されています。これにより、従来は取得原価主義で評価されていた資産についても、時価による評価が求められるケースが増加しています。
時価会計導入により財務諸表の透明性は向上しますが、市場価格の変動が直接損益に影響するため、業績の変動性が高まる可能性があります。特に金融商品や投資有価証券については、時価評価による影響が大きく、M&A価格算定においても重要な検討事項となります。
中小企業においても、上場企業への株式譲渡や大企業によるM&Aを検討する場合は、時価会計の影響を理解し、適切な資産評価を行うことが重要です。これにより、より正確な企業価値の把握と適切な価格交渉が可能になります。
M&Aにおける簿価と時価の重要性
M&Aにおいて簿価と時価の違いを理解することは、適切な企業価値評価と価格交渉の成功に直結する重要な要素です。買い手と売り手の双方にとって、正確な価値把握は公正な取引の基盤となります。
企業価値評価における時価の重要性
M&Aにおける企業価値評価では、簿価ベースの評価だけでは実際の企業価値を適切に反映できないため、時価による修正が不可欠となります。特に資産集約型の企業や創業から長期間経過した企業では、簿価と時価の乖離が大きく、時価評価の重要性がより高くなります。
例えば、製造業で古い工場用地を多数保有している企業の場合、簿価では低く評価されている土地が、現在の時価では大幅に上昇している可能性があります。この含み益を適切に評価することで、企業の真の価値を把握し、売却価格の向上につなげることができます。
デューデリジェンスと資産再評価
M&Aプロセスにおいて、買い手は詳細なデューデリジェンスを実施し、資産と負債の時価評価を行うことが一般的です。この過程で簿価では見えなかった価値や リスクが明らかになることが多くあります。
資産再評価により発見された含み益は売却価格の向上要因となる一方、含み損や偶発債務の発見は価格下落要因となるため、売り手側も事前の準備が重要です。特に不動産、有価証券、在庫資産については、専門的な評価が必要となることが多く、事前の価値把握が価格交渉を有利に進める鍵となります。
M&A価格算定手法と時価評価の関係
M&Aで用いられる主要な価格算定手法と、簿価・時価の関係を整理いたします。それぞれの手法において、時価情報の活用方法が異なることを理解することが重要です。
| 算定手法 | 簿価の活用 | 時価の活用 |
|---|---|---|
| 時価純資産法 | 修正の基準として使用 | すべての資産・負債を時価評価 |
| DCF法 | 初期投資額の参考 | 将来価値を現在価値に割引 |
| 類似会社比較法 | 財務指標の比較基準 | 市場価格ベースの倍率適用 |
中小企業のM&Aでは時価純資産法と年倍法が頻繁に使用されるため、正確な時価評価が適切な企業価値算定の前提条件となります。特に営業権(のれん)の算定においては、時価純資産を正確に把握することで、将来収益力に基づく適正な評価が可能になります。
税務上の取り扱いと注意点
M&Aにおける資産の時価評価は、税務上の取り扱いにも大きな影響を与えます。売却損益の計上タイミングや課税対象の範囲について、事前の検討が重要です。
資産の含み益が実現した場合、法人税の課税対象となるため、売却価格の検討においては税務コストも含めた総合的な判断が必要となります。また、グループ内再編や適格要件を満たすM&A手法の選択により、税務負担を軽減できる場合もあるため、税務専門家との連携が重要です。
実務における注意点と対策
簿価と時価の違いを実務で活用する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解し適切な対策を講じることで、M&Aを成功に導くことができます。
専門家による評価の必要性
時価評価には高度な専門知識が必要であり、不動産鑑定士、税理士、公認会計士など、各分野の専門家による適切な評価が不可欠です。特に複雑な資産構成を持つ企業や、特殊な業界の企業については、業界特有の評価ノウハウを持つ専門家の協力が重要となります。
評価の精度は最終的な売却価格に直接影響するため、コストを惜しまず適切な専門家を選定することが重要です。また、複数の専門家による評価を取得し、妥当性を検証することも効果的な手法です。
評価時点と価格変動リスク
時価評価は評価時点における価格であり、市場環境の変化により短期間で変動する可能性があります。特に株式や不動産などの市場性のある資産については、この変動リスクを考慮した評価が必要です。
M&Aプロセスが長期化する場合は、評価の更新や価格調整条項の設定など、価格変動リスクに対する適切な対策を講じることが重要です。また、市場環境が不安定な時期には、より保守的な評価を採用することも検討すべきです。
情報開示と透明性の確保
M&Aにおける価格交渉を円滑に進めるためには、資産の時価情報を適切に整理し、買い手に対して透明性の高い情報開示を行うことが重要です。これにより、信頼関係の構築と公正な価格での取引が可能になります。
| 開示項目 | 簿価情報 | 時価情報 |
|---|---|---|
| 不動産 | 取得価格、減価償却累計額 | 鑑定評価額、固定資産税評価額 |
| 有価証券 | 取得価格、評価損益 | 市場価格、類似取引価格 |
| 機械装置 | 取得価格、耐用年数 | 査定価格、稼働状況 |
| 在庫資産 | 簿価、評価減 | 正味売却価格、回転状況 |
適切な情報開示により買い手の理解が深まり、企業価値を正当に評価してもらえる可能性が高くなります。一方で、過度な情報開示は競合他社への情報流出リスクもあるため、秘密保持契約の締結など、適切なリスク管理も重要です。
継続的な価値向上への取り組み
M&Aの準備段階において、簿価と時価の乖離を分析することで、企業価値向上のための具体的な施策を検討することができます。これは売却価格の向上だけでなく、事業の持続的成長にも寄与します。
例えば、含み益のある不動産の有効活用や、時価が下落している資産の売却・入替など、戦略的な資産管理により企業価値の最大化を図ることが可能です。また、無形資産の価値向上や収益性の改善など、財務面以外の価値向上施策も重要な要素となります。
まとめ
簿価と時価の違いを正しく理解することは、M&Aや会社売却において適切な企業価値評価を行うための基礎となります。簿価は取得原価主義に基づく安定した評価基準である一方、時価は現在の市場価値を反映した動的な評価手法であり、それぞれに重要な役割があります。
M&Aにおいては時価評価による企業価値算定が不可欠であり、特に資産集約型企業や長期間事業を継続している企業では、簿価と時価の乖離が大きく、適切な時価評価が売却価格の向上に直結します。専門家による正確な評価と透明性の高い情報開示により、公正で円滑なM&A取引を実現することができます。
企業価値の最大化を図りつつ、適切なM&A戦略を検討されている経営者の皆様には、簿価と時価の違いを踏まえた総合的な企業価値評価をお勧めいたします。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、豊富な実績と専門知識を活かし、お客様の企業価値を最大限に引き出すサポートを提供しております。M&Aや経営課題に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。