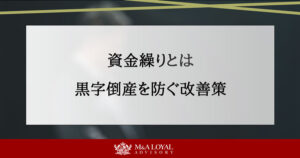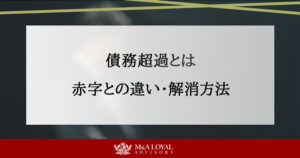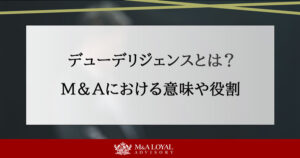貸倒損失とは?要件や計上基準、押さえるべきポイントを徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
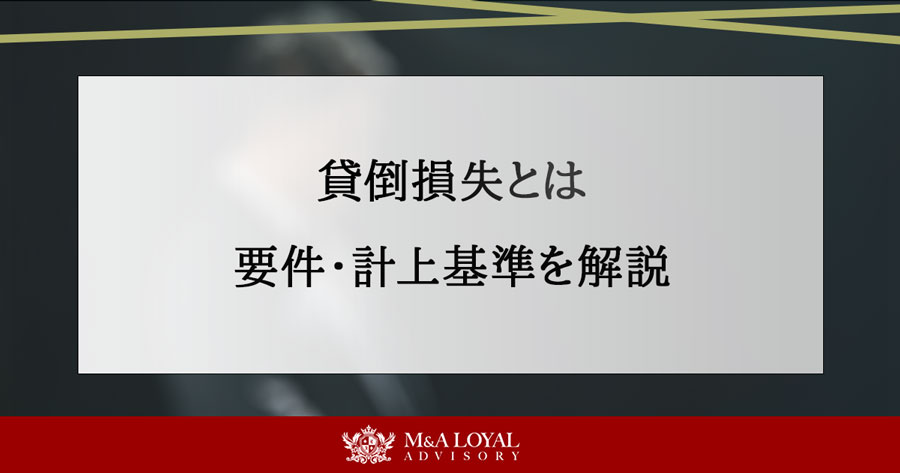
貸倒損失とは、企業が保有する売掛金や貸付金などの債権が回収不能となった場合に計上される損失のことを指します。企業経営において、こうした貸倒れのリスクは避けて通れない課題です。
貸倒損失を税務上適切に処理するには、国税庁が定める厳格な要件を満たす必要があります。要件を正しく理解せずに処理を行うと、税務調査で否認されるリスクや、本来損金算入できる損失を計上し損ねる可能性があります。
本記事では、貸倒損失の3つの要件と具体的な計上基準から、実務で必要となる税務処理、仕訳方法、証拠書類の整備まで、中小企業の経理担当者やM&A実務者が押さえるべきポイントを包括的に解説します。
目次
貸倒損失の要件を理解する前に知っておくべき基礎知識
貸倒損失は、企業経営において避けることが難しいリスクの一つです。特に中小企業では、取引先との密接な関係により、一社の倒産が経営に大きな影響を与える可能性があります。適切な貸倒損失の処理を行うためには、まず基本的な概念と実務上の注意点を理解しておくことが重要です。ここでは、貸倒損失の要件を学ぶ前提として必要な基礎知識について解説します。
中小企業で発生する貸倒損失の実態
中小企業における貸倒損失は、大企業に比べて一件当たりの影響度が大きい傾向にあります。
帝国データバンクの調査によると、2024年度の企業倒産件数は11年ぶりに1万件を超えました。特に、資材価格の高騰や深刻な人手不足を背景に、サービス業や建設業での倒産が急増しており、中小企業にとって貸倒リスクはより一層深刻な経営課題となっています。中小企業では取引先との結びつきが強く、一社あたりの依存度が高いことが多いため、一度の貸倒れが経営全体に深刻なダメージを与える恐れがあります。
貸倒損失の発生は、単に売掛金の回収不能にとどまらず、キャッシュフローの悪化により新規投資や人件費の支払いに影響を及ぼし、最終的には企業の成長サイクル自体を停滞させるリスクを抱えています。こうした連鎖的な影響を防ぐためには、日頃からの債権管理と適切な貸倒損失処理が不可欠となります。
貸倒損失と貸倒引当金の税務上の違い
貸倒損失と貸倒引当金は、どちらも債権の回収不能に関する会計処理ですが、税務上の取り扱いに重要な違いがあります。貸倒損失は実際に債権が回収不能になった場合に計上する実績に基づく処理であり、一定の要件を満たせば確実に損金算入が認められます。
一方、貸倒引当金は将来の貸倒れに備えて見積額を計上する予防的な処理です。
税務上、将来の貸倒れに備えて法定繰入率等を用いて一括で引当金を計上し損金算入することが認められるのは、原則として資本金1億円以下の中小法人等に限られます(ただし、資本金5億円以上の大法人との間に完全支配関係がある法人などは除かれます)。
貸倒損失が「確定した損失」として扱われるのに対し、貸倒引当金は「見積もりによる準備金」という性質の違いがあります。実務では、貸倒れの兆候を早期に察知し、適切なタイミングで引当金から損失への処理転換を行うことが重要になります。
※参照:国税庁「No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定」
M&A実施後に注意すべき債権管理のポイント
M&Aを実施した後の債権管理では、統合前後の債権の性質変化に特に注意が必要です。買収により新たに承継した債権については、売り手企業時代の債権管理体制や回収実績を詳細に把握し、買収後の管理方針を策定する必要があります。特に、既に回収困難な状況にある債権については、速やかに貸倒損失の要件該当性を検討することが求められます。
また、M&A後は取引先との関係性が変化する可能性があり、従来の信用供与条件の見直しが必要になることもあります。買収企業の信用力向上により取引条件が改善される一方で、統合過程での混乱により一時的に回収リスクが高まる場合もあります。M&A統合後の債権管理では、新たな管理体制の構築と既存債権の適切な評価・処理を並行して進めることが、財務健全性の維持につながります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



貸倒損失の要件:税務上認められる3つの計上基準
貸倒損失を税務上の損金として計上するには、国税庁が定める法人税基本通達9-6-1から9-6-3の厳格な要件を満たす必要があります。これらの要件は以下の3つに分類され、それぞれ異なる判定基準と損金算入のタイミングが定められています。
- 法律上の貸倒:裁判所決定等による債権の法的消滅
- 事実上の貸倒:債務者の資産状況から全額回収不能が明確
- 形式上の貸倒:取引停止1年経過等の形式的要件を満たす場合
適切な貸倒損失処理を行うためには、各要件の詳細な内容と実務上の注意点を正確に理解しておくことが重要です。
法律上の貸倒で債権が消滅する具体的なケース
法律上の貸倒(法人税基本通達9-6-1)は、法的手続きにより債権の全部または一部が切り捨てられた場合に適用されます。具体的には、会社更生法や民事再生法の規定により更生計画・再生計画の認可決定があった場合、特別清算に係る協定の認可決定があった場合、法令に基づかない債権者集会の協議決定や行政機関・金融機関等のあっせんによる合理的基準での切り捨てが該当します。
また、債務者の債務超過状態が相当期間継続し、弁済を受けることができない場合に書面で明らかにした債務免除額も法律上の貸倒として認められます。この場合の損金算入時期は、切り捨て事実が発生した事業年度となり、損金経理の要件は付されていないため、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求も可能です。
事実上の貸倒を判断する際の実務的な基準
事実上の貸倒(法人税基本通達9-6-2)は、債務者の資産状況や支払能力等から債権の全額回収が不可能であることが明らかになった場合に適用されます。重要なのは「全額が回収できない」ことが明らかである点で、一部でも回収可能な見込みがある場合は認められません。担保物がある場合は処分後でなければ損金経理はできず、保証人がいる場合は、その保証人に対して請求を行い、保証人からも回収できないことが明らかになった後でなければ、貸倒損失として処理することはできません。
実務では、債務者の破産手続終結決定時や事業停止により連絡が取れず資産もほぼない状況が確認された時点で事実上の貸倒として処理することが多くあります。この要件では損金経理が条件とされています。税務当局はこれを厳格な要件と解釈しており、回収不能が明らかになった事業年度に損金経理を失念した場合、原則として更正の請求は認められません。
ただし、損金経理は客観的な回収不能の事実を帳簿に反映させる行為に過ぎないとして、更正の請求を認めるべきだという学説や過去の裁決例も存在し、法的な争点となっています。しかし、税務調査でこの主張が認められることは極めて困難なため、実務上は必ず当該事業年度に損金経理を行うことが不可欠です。
形式上の貸倒で必要な1年間の取引停止要件
形式上の貸倒(法人税基本通達9-6-3)は、継続的取引を行っていた債務者に対する売掛債権について特例的に認められる処理です。対象は売掛金、未収請負金等の営業債権に限定され、貸付金等は含まれません。主な要件は、債務者との取引停止から1年以上経過した場合(ただし最後の弁済期・弁済時がより遅い場合はその時点から)と、同一地域の債務者に対する売掛債権総額が取立費用に満たない場合の2つです。
この処理では備忘価額(通常1円)を残して損金経理することが必要で、会社更生法等の手続中であっても要件を満たせば形式上の貸倒として処理できます。ただし、不動産取引のような一時的な取引は継続的取引に該当しないため適用対象外となります。
債務超過の継続期間3~5年の判断根拠
貸倒における債務超過の継続期間については、一般的に3~5年程度が相当期間とされています。この判断基準は、中小企業再生支援協議会での債務超過解消年数が5年以内とされていることや、金融検査マニュアルで概ね5年以内に正常先となる経営改善計画があれば債務者区分のランクアップが認められることを踏まえています。
ただし、災害による被害や取引先の倒産による不良債権が原因の債務超過では、より短期間でも相当期間として貸倒損失処理が認められる場合があります。
実務では、債務者の財産を時価評価によって算定し、弁済を受けることができない状態であることを客観的に証明することが重要です。 これは、債務免除が単なる資金援助(税務上の「寄附金」)ではなく、債権者にとって経済合理性のある経営判断であったことを示すためです。
例えば、債務者を倒産させるよりも債務免除を行う方が最終的な損失を圧縮できる、あるいは重要な取引関係を維持するために不可欠である、といった合理的な理由を取締役会議事録などで明確に記録し、客観的な証拠と共に保管しておくことが、寄附金認定リスクを回避する上で極めて重要となります。寄附金と認定されると損金算入が厳しく制限されるため、単に期間だけでなく債務超過の原因や程度も総合的に考慮し、寄附金課税のリスクを回避する必要があります。
貸倒損失の要件を満たした場合の税務処理と必要書類
貸倒損失の要件を満たした場合の適切な税務処理を行うには、損金算入時期の把握、必要書類の準備・保管、消費税の調整処理が重要になります。各要件によって処理方法や必要な証拠書類が異なるため、実務では要件ごとの違いを正確に理解し、適切なタイミングでの処理と書類整備を怠らないよう注意が必要です。
法律上の貸倒での損金算入時期と提出書類
法律上の貸倒では、切り捨て事実が発生した事業年度において損金算入が認められます。重要な特徴として損金経理の要件が付されていないため、会計上の処理を失念した場合でも法定申告期限から5年以内であれば更正の請求により損金算入が可能です。
必要書類については、以下のような証拠資料の保管が必要になります。
- 更生計画認可決定書:会社更生法適用時の必要書類
- 再生計画認可決定書:民事再生法適用時の証拠資料
- 債権者集会議事録:協議による切捨ての証明書類
- 債務免除通知書:書面による債務免除の記録
債務免除を行う場合は、書面による明確な意思表示が求められ、内容証明郵便等による送付が望ましいとされています。また、債務者の債務超過状態が相当期間継続していることを示すため、決算書や財産目録、登記簿謄本などの資料も併せて保管しておく必要があります。これらの書類は税務調査時の重要な証拠となるため、申告書提出期限から7年間の保存が義務付けられています。
事実上の貸倒での税務処理と証拠書類
事実上の貸倒では、債権の全額が回収不能であることが明らかになった事業年度において損金経理が要件となります。法律上の貸倒とは異なり、損金経理を行わなかった場合の更正の請求は困難であるため、回収不能が確定した事業年度での適切な会計処理が不可欠です。証拠書類としては、債務者の財産状況を示す決算書、破産手続終結決定書、事業停止の事実を示す資料、債権回収努力の記録などが重要になります。
担保物がある場合は処分後でなければ損金経理できないため、担保物処分の記録や処分価格の妥当性を示す資料も必要です。実務では債務者との連絡記録、内容証明郵便の送付記録、取引先からの情報収集記録なども保管し、債権回収に向けた合理的な努力を行ったことを客観的に示せるよう準備しておくことが重要です。
形式上の貸倒での損金経理と保管書類
形式上の貸倒では、売掛債権について備忘価額を控除した残額の損金経理が要件となります。対象は継続的取引による売掛金、未収請負金等に限定され、貸付金等は含まれません。必要書類には取引停止の事実を示す資料、最後の弁済日を証明する書類、1年経過の証明資料、督促状の送付記録などがあります。同一地域内の少額債権については取立費用の算定資料も必要です。
備忘価額(通常1円)を残した損金経理を行うことが形式要件となるため、会計処理では必ず備忘価額を計上する必要があります。継続的取引の証明として過去の取引履歴、契約書、請求書等の保管も重要で、一時的な取引(不動産売買等)は対象外となるため取引の性質を明確にしておく必要があります。
貸倒損失計上時の消費税控除手続き
貸倒損失が発生した場合、課税取引に係る債権であれば消費税額の控除が認められます。控除額は貸倒れとなった債権に含まれる消費税額で、貸倒れが生じた課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除します。
消費税控除の取り扱いは以下の通りです。
- 課税取引に係る債権:控除対象として処理可能
- 免税事業者期間の売上:控除対象外のため注意
- 不課税取引(貸付金等):消費税控除は適用不可
消費税申告書では「貸倒れにかかる消費税額」として別途集計し記載する必要があります。简易課税制度適用者も貸倒れに係る税額控除は可能で、過去の税率(3%、5%、8%等)で計上された債権については当時の税率で控除額を計算します。貸倒引当金計上時には消費税控除は認められず、実際に貸倒損失を計上した時点で控除が可能になります。なお、貸倒処理後に債権を回収した場合は、回収額に含まれる消費税相当額を「控除過大調整税額」として納付する必要があります。
貸倒損失の要件別にみる仕訳の実務処理
貸倒損失の仕訳処理は、該当する要件によって処理方法が異なります。法律上、事実上、形式上の各要件に応じた適切な会計処理を理解することで、税務上の問題を回避し、正確な財務報告が可能になります。ここでは各要件での具体的な仕訳例を示しながら、実務で注意すべきポイントについて詳しく解説します。
法律上の貸倒における裁判所決定後の仕訳
法律上の貸倒では、裁判所の決定や法的手続きにより債権の切り捨てが確定した時点で仕訳処理を行います。例えば、売掛金1,000万円について民事再生手続きにより70%が切り捨てられた場合、切り捨て額700万円を貸倒損失として計上します。仕訳は「借方:貸倒損失 7,000,000円/貸方:売掛金 7,000,000円」となり、残額300万円は継続して債権として管理します。
更生計画や再生計画では分割弁済が定められることが多いため、弁済予定額と切り捨て額を正確に区分することが重要です。債務免除を書面で行った場合も同様の処理となりますが、免除額の妥当性について債務者の財政状態との整合性を確認しておく必要があります。消費税については、課税取引に係る債権であれば切り捨て額に含まれる消費税相当額を控除対象とします。
事実上の貸倒で全額回収不能時の処理方法
事実上の貸倒では、債権の全額が回収不能であることが明らかになった時点で全額を貸倒損失として処理します。売掛金2,000万円が取引先の破産により全額回収不能となった場合、「借方:貸倒損失 20,000,000円/貸方:売掛金 20,000,000円」の仕訳を行います。貸倒引当金を設定していた場合は、引当金との相殺処理も必要になります。
担保物がある場合は処分後の処理となるため、担保物処分価額を売掛金から控除した残額が貸倒損失となります。例えば、担保物処分により300万円を回収した場合、貸倒損失は1,700万円となります。保証人がいる場合も保証人からの回収後でなければ貸倒損失として認められないため、保証債務の履行状況を適切に把握することが重要です。事実上の貸倒では損金経理が要件となるため、会計処理を失念しないよう注意が必要です。
形式上の貸倒における備忘価額1円の意味
形式上の貸倒では、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として処理することが要件となっています。備忘価額は通常1円とし、債権が完全に消滅したわけではないことを帳簿上明示する意味があります。売掛金3,000万円の形式上貸倒処理では、「借方:貸倒損失 29,999,999円/貸方:売掛金 29,999,999円」とし、1円を残して管理します。
備忘価額を残さずに全額を貸倒損失として処理した場合、形式上の貸倒として認められなくなる可能性があるため注意が必要です。同一地域の少額債権については、取立費用が債権額を上回る場合に備忘価額を控除した残額を損金経理できますが、この場合も1円の備忘価額を残すのが一般的です。形式上の貸倒は継続的取引の売掛債権のみが対象で、貸付金等は適用対象外となります。
償却債権取立益の計上が必要になるケース
過去に貸倒損失として処理した債権を後から回収した場合、その回収額を償却債権取立益として営業外収益に計上します。例えば、5年前に貸倒損失500万円として処理した債権について300万円を回収した場合、「借方:現金預金 3,000,000円/貸方:償却債権取立益 3,000,000円」の仕訳を行います。償却債権取立益は回収があった事業年度の収益として計上され、過去の貸倒損失を修正する処理ではありません。
部分回収の場合、回収額のうち元本部分と遅延損害金等の区分が問題となることがあります。税務上は回収額を元本の回収として取り扱うのが原則ですが、当事者間での取り決めがある場合はその内容に従います。
消費税については、回収した債権に消費税が含まれている場合、「控除過大調整税額」として納付する必要があります。なお、この計算は現在の税率ではなく、その債権が発生した当初の取引時点の税率に基づいて行う必要があるため注意が必要です。回収可能性が見込まれる債権については、償却債権取立益の計上に備えて適切な債権管理を継続することが重要です。
※参照:国税庁「No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算」
貸倒損失の要件を踏まえた中小企業のリスク管理
貸倒損失の適切な処理を行うためには、事前のリスク管理体制を構築することが重要です。中小企業では限られたリソースの中で効果的なリスク管理を実施する必要があり、M&A前後の統合プロセスにおいてはさらに注意深い債権管理が求められます。ここでは実務的な観点から、貸倒損失の要件を踏まえたリスク管理の具体的な方法について解説します。
M&A前後で強化すべき与信管理体制
M&A実施前後では、既存の与信管理体制を見直し、統合後の新しい事業体制に適応した管理システムを構築する必要があります。買収対象企業の債権については、デューデリジェンスの段階で回収可能性を詳細に調査し、問題のある債権については早期に貸倒損失の要件該当性を検討することが重要です。統合後は両社の与信管理基準を統一し、新たな与信限度額の設定や定期的な信用調査の実施体制を整備します。
- 統合前の債権精査と回収可能性評価の実施
- 与信管理基準の統一と与信限度額の再設定
- 定期的な信用調査体制の構築と情報共有システムの整備
M&A後の債権管理では、取引先との関係性の変化にも注意が必要です。買収により信用力が向上する場合もありますが、統合過程での混乱により一時的に取引条件が悪化する可能性もあるため、移行期間中は特に慎重な管理が求められます。
内容証明郵便による法的証拠の確保方法
債権回収努力の証拠を確保するために、内容証明郵便の活用は非常に有効です。支払遅延が発生した段階で内容証明郵便による督促状を送付することで、後に形式上の貸倒や事実上の貸倒として処理する際の重要な証拠となります。内容証明郵便では送付内容、送付日が公的に証明されるため、税務調査時にも有力な証拠資料として活用できます。
内容証明郵便の送付は消滅時効の完成猶予効果もあるため、権利保全の観点からも重要です。督促状には債権額、支払期日、支払方法を明記し、一定期間内に支払いがない場合の対応方針も記載しておきます。配達証明を併用することで、到達日時が明確になり、形式上の貸倒における1年経過の起算点を明確化できます。
売掛金保証サービスを活用した予防策
中小企業では債権回収リスクを軽減するため、売掛金保証サービスやファクタリングサービスの活用も効果的です。これらのサービスを利用することで、取引先の倒産リスクを第三者に転嫁し、安定したキャッシュフローを確保できます。M&A後の事業統合期間中など、リスク管理体制の整備が不十分な時期には特に有効な手段となります。
- 売掛金保証サービス:与信調査から回収まで一括代行
- ファクタリング:売掛債権の買取により即座に資金化
- 取引信用保険:倒産リスクに対する保険による補償
ただし、これらのサービス利用時にも手数料や保証料のコストを考慮し、自社の資金繰りと信用リスクのバランスを適切に評価することが重要です。サービス提供会社の信頼性や保証範囲についても十分に検討し、契約条件を慎重に確認する必要があります。
まとめ|貸倒損失の要件を正しく理解して税務リスクを回避しよう
貸倒損失の適切な処理は、中小企業の健全な財務管理において極めて重要です。法人税基本通達に定められた3つの要件を正確に理解し、適切な処理を行うことで税務リスクを回避できます。
法律上の貸倒では損金経理不要、事実上の貸倒では損金経理必須、形式上の貸倒では備忘価額を残した処理が求められます。実務では損金算入時期の把握と証拠書類の保管が重要で、M&A実施企業では統合前後の債権管理体制整備が特に必要です。適切な要件理解により、税務調査リスクを軽減し、持続的な企業成長の基盤を構築することが可能になります。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。