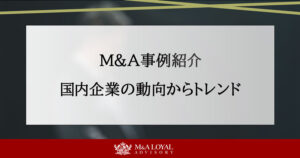労働者不足で経営危機?日本の現状や企業への影響、解決策を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
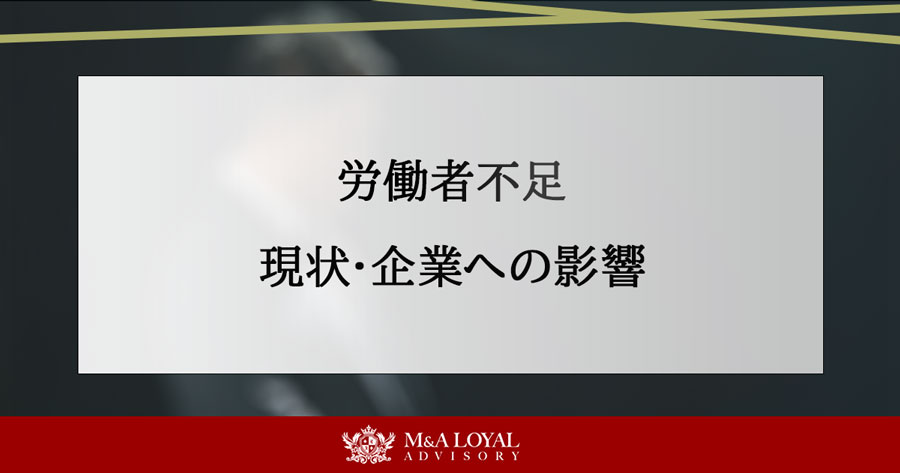
日本全体で深刻化する労働者不足は、もはや一過性の問題ではありません。2025年1月の調査では企業の半数以上が人手不足を感じており、人手不足倒産も過去最多を記録するなど、企業の存続そのものを脅かす構造的課題となっています。特に中小企業では大企業以上に労働者不足が深刻な状況にあり、売上機会の損失や既存社員への過重労働、技術継承の断絶など、経営の根幹を揺るがす影響が現れています。本記事では、労働者不足の実態と企業への具体的な影響を詳しく分析し、DX推進や多様な人材活用、M&A戦略など、中小企業が生き残るための実践的な解決策をご紹介します。
目次
労働者不足の深刻な現状と中小企業への影響
日本の労働者不足は、もはや一時的な現象ではありません。帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査」(2025年4月)によると、正社員が「不足」と感じている企業の割合は51.4%に達し、コロナ禍以降で最も高い水準を記録しています。この数値は、日本企業の半数以上が深刻な人材不足に直面していることを示しており、経営の根幹を揺るがす構造的な問題となっています。
2024年の最新データで見る深刻な労働者不足の実態
2024年の就業者数は6,781万人と過去最多を記録した一方で、企業の人手不足感は改善していません。総務省統計局の労働力調査によると、労働力人口は増加傾向にあるものの、企業が求める人材と求職者のスキルミスマッチが拡大しています。
特に注目すべきは人手不足倒産の急増です。帝国データバンクの調査によると、2024年の人手不足倒産は342件に達し、2年連続で過去最多を更新しました。これは調査開始以来最悪の記録であり、労働者不足が企業の存続そのものを脅かす事態に発展していることを物語っています。
内閣府・財務省の「法人企業景気予測調査」(2025年1~3月期調査)では、従業員数判断BSI(「不足気味」の企業割合-「過剰気味」の企業割合)において、大企業が28.3ポイントであるのに対し、中小企業は30.3ポイントと、依然として中小企業の方が深刻な人手不足に陥っていることが明確に示されています。
中小企業が直面する採用難と離職率の上昇
中小企業の人材確保は特に困難を極めています。日本商工会議所の調査(2024年7月)によると、中小企業の63.0%が「人手不足」と回答し、そのうち65.5%が事業運営に「深刻な影響」(「非常に深刻」または「深刻」)を受けている状況です。
大企業との採用格差も拡大しています。HR総研の調査によると、2024年卒採用において採用計画の8割以上を達成した企業の割合は、大企業(従業員1,001名以上)が76%だったのに対し、中小企業(従業員300名以下)では47%にとどまりました。この背景には賃金格差があり、中小企業が提示できる初任給や労働条件では、優秀な人材の確保が困難になっています。
さらに深刻なのは離職率の問題です。中小企業では一人当たりの業務負担が重く、長時間労働が常態化しやすい環境にあります。これにより既存従業員の疲弊が進み、離職が新たな人手不足を生むという悪循環に陥るケースが増加しています。
業界別に見る労働者不足の深刻度ランキング
2025年4月時点の帝国データバンクの調査によると、正社員の人手不足が最も深刻な業界は以下の通りです
(上位業種):
・情報サービス:69.9%
・メンテナンス・警備・検査:69.4%
・建設業:68.9%
これらの業界では、依然として7割近い企業が人手不足に直面しています。
建設業では、2024年4月から施行された時間外労働の上限規制(2024年問題)により、従来の働き方が制限され、さらなる人手不足が加速しています。これにより、労働集約型産業における人材確保は一層厳しさを増しているのが現実です。
労働者不足が加速する3つの根本原因
労働者不足は一朝一夕に生じた問題ではありません。日本社会が抱える構造的な課題が複合的に作用し、深刻な人材不足を引き起こしています。根本原因を理解することで、企業は適切な対策を立案し、持続可能な経営戦略を構築できるのです。
少子高齢化による生産年齢人口の急激な減少
日本の労働者不足の最大の要因は、少子高齢化による生産年齢人口(15~64歳)の減少です。生産年齢人口(15~64歳)は1995年の8,717万人をピークに減少に転じています。
さらに深刻なのは今後の見通しです。国立社会保障・人口問題研究所の最新の推計(令和5年推計)では、2070年には生産年齢人口が4,535万人まで減少すると予測されています。この急激な人口減少は「人口オーナス期」と呼ばれ、経済成長の重荷となる状況です。
高齢化も同時進行しており、2024年の高齢化率は29.3%に達しています。2070年には38.7%まで上昇し、1人の高齢者を1.3人の現役世代で支える「肩車社会」が到来します。労働力の供給者が減る一方で、社会保障や介護サービスへの需要は急増するという二重の負荷が、労働市場に深刻な影響を与えています。
若者の価値観の変化と転職市場の活性化
現代の若者の仕事に対する価値観は、従来世代と大きく異なります。パーソル総合研究所の調査によると、20代の若者は「働きやすさ」だけでなく「成長の機会」を重視する傾向が強まっています。単に快適な職場環境を求めるのではなく、自身のスキルや知識を高められる仕事を重視する傾向が顕著です。
転職に対する意識も変化しています。従来のように一つの会社で生涯働くという概念よりも、キャリアアップや自己実現のための転職を肯定的に捉える若者が増加しています。Z世代の多くは、本業と並行して副業やパラレルキャリアを志向し、一つの職場に固執しない柔軟な働き方を求めています。
ワークライフバランスへの意識も高く、長時間労働を前提とした従来の働き方に疑問を持つ若者が多数を占めます。マイナビの調査では、結婚後の働き方について「夫婦共働きが望ましい」と回答した学生の割合が上昇傾向にあり、特に男子学生では64.1%まで増加しています。
働き方改革がもたらす労働時間の制約
2019年から段階的に施行された働き方改革関連法により、企業の労働時間管理が厳格化されました。特に2024年4月から建設業、運輸業、医師に対しても時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」は、労働集約型産業に深刻な影響を与えています。
建設業では、従来は時間外労働の上限規制が適用されていませんでしたが、2024年4月以降は原則として月45時間、年360時間の上限が設けられました。これにより、従来の働き方では必要な労働時間を確保できなくなり、人手不足が一層深刻化しています。
運輸業においても同様の制約により、ドライバーの労働時間短縮が避けられなくなりました。宅配便の取扱量が急増するなか、ドライバー不足は既に深刻な状況にあり、2030年には8.6万人の需給ギャップが予測されています。
2024年問題が労働者不足に与える追加的影響
2024年問題は単なる労働時間の制約を超えて、産業構造全体に変革を迫っています。建設業では工期の延長や受注案件の選別が必要となり、運輸業では配送効率の向上や料金体系の見直しが急務となっています。
医療業界では、医師の働き方改革により、地方の病院や救急医療体制への影響が懸念されています。これまで長時間労働に依存していた医療現場では、限られた人員でサービス水準を維持するための抜本的な業務改革が求められています。
これらの制約により、従来の「人海戦術」から「効率性重視」への転換が迫られており、企業は生産性向上、DX導入、業務プロセスの見直しなど、根本的な経営改革に取り組まざるを得ない状況となっています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



労働者不足による中小企業経営への5つの深刻な影響
労働者不足は表面的な「人手が足りない」という問題を超えて、企業経営の根幹を揺るがす複合的な課題を引き起こします。中小企業においては、この影響がより深刻化する傾向があります。
売上機会の損失と事業縮小リスク
労働者不足の最も直接的な影響は、売上機会の損失です。人手不足により既存の業務を維持することが精一杯の状況では、新規受注を断らざるを得ない事態が頻発します。マンパワーグループの調査によると、人手不足企業の多くが「仕事の受注そのものを減らすか、断るしかない」状況に追い込まれています。
この問題は一時的な売上減少にとどまりません。仕事を断られた顧客は他社に発注せざるを得なくなり、一度他社に流れた仕事が戻る可能性はほとんどありません。継続的な受注機会の損失により、企業の市場シェアは徐々に侵食され、長期的な競争力低下につながります。
建設業や製造業では、特定の技術を持つ職人や専門技術者の不足により、これまで請け負っていた案件の継続が困難になるケースも多発しています。技術継承が進まない中で、ベテラン従業員の退職により企業固有の技術やノウハウが失われ、事業領域の縮小を余儀なくされる企業も少なくありません。
既存社員の過重労働とモチベーション低下
労働者不足により、既存従業員への業務負荷が急激に増加します。厚生労働省の調査では、人手不足が職場環境に与える影響として「残業時間の増加、休暇取得数の減少」が最多となっており、企業・労働者双方が最も深刻に感じている問題です。
従業員の離職により、離職しなかった既存従業員にその業務負荷が割り振られることで、一人当たりの業務量が大幅に増加します。これは「前向きに増えた仕事ではなく、誰かの退職のツケが回ってきただけ」という状況を生み、モチベーションの著しい低下を招きます。
過重労働の継続は、従業員の心身の健康に深刻な影響を与えます。
特に中小企業では、一人当たりの業務負担増加割合が高く、長時間労働が常態化しやすい傾向があります。この結果、従業員の働きがいや意欲が低下し、「残ったもの負け」状態となって、更なる人材流出を招くリスクが高まります。
賃金上昇圧力による収益性の悪化
人材獲得競争の激化により、中小企業にも賃金上昇圧力がかかっています。中小企業庁の調査によると、2024年度において36.9%の中小企業が「業績の改善が見られないが賃上げを実施予定」とする「防衛的賃上げ」を行っており、人材確保や定着率向上のための苦肉の策となっています。
しかし、中小企業の多くは賃上げの原資確保に苦慮している状況です。同調査では、賃上げの原資確保のための取組として「特に対応はしていない(収益を圧迫している)」と回答した企業が最も多く、人件費上昇が収益性を直撃している実態が明らかになっています。
大企業では初任給30万円時代と言われる中、賃上げ機運に追いつけない中小企業が増加しており、人材獲得においてますます不利な状況に置かれています。この結果、優秀な人材の確保が困難になり、事業継続に必要な人員を維持できない企業が増加しています。
技術・ノウハウの継承危機
労働者不足は、企業固有の技術やノウハウの継承にも深刻な影響を与えています。ベテラン社員の離職や定年退職により、長年培われた技術や業務ノウハウが若手に伝承されないまま失われる事態が多発しています。
製造業では特に深刻で、一人一人のスキルが高く評価される環境において、従業員の退職によりその従業員が担当していた業務が滞り、生産性が大きく低下する事例が報告されています。人材不足により新規採用を行っても、教育できる人材がいないという負の連鎖が起こっています。
技術継承の重要性は理解されているものの、人手不足により教育・研修の時間が十分に取れないことが問題となっています。厚生労働省の調査では、人手不足による企業への影響として「能力開発機会の減少」が上位に挙げられており、人材育成機能の低下が懸念されています。
このような状況が続くと、企業の競争力の源泉である技術力や専門性が失われ、長期的な事業継続が困難になる可能性があります。
競争力低下による市場シェアの喪失
労働者不足により企業の基本的な事業運営能力が低下すると、市場における競争力が著しく損なわれます。納期遅延、品質低下、サービス水準の悪化などが顕在化し、顧客満足度の低下を招きます。
人手不足により業務効率が低下すると、同業他社との競争において不利な状況に陥ります。十分な人員を確保している競合企業は、より迅速で高品質なサービスを提供できるため、市場シェアの移転が加速します。
また、イノベーションや新規事業開発への取り組みも困難になります。日常業務の維持に人員が割かれるため、将来への投資や競争力強化のための取り組みが後回しになり、中長期的な競争力の低下が避けられません。
労働者不足による倒産リスクと事業継続の限界
労働者不足の最終的な帰結として、企業の倒産リスクが急激に高まっています。人手不足倒産の主な原因は以下の通りです。
・従業員退職による業務継続困難
・採用難による必要人員の確保不能
・人件費高騰による収益圧迫
・後継者不在による事業承継失敗
帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年)」によると、特に2024年問題の影響を受けた建設業では99件、物流業では46件の人手不足倒産が発生し、両業種で全体の4割強を占めています。これらの業界では、働き方改革による労働時間制約と人手不足が重なり、事業継続そのものが困難になっているケースが多発しています。
黒字経営であっても人手不足により倒産に至るケースも増加しており、従来の財務指標だけでは測れないリスクが顕在化しています。事業の継続には適正な人員配置が不可欠であり、労働者不足は企業存続の根幹を脅かす経営課題となっているのが現実です。
労働者不足を乗り越える中小企業の実践的対策
深刻化する労働者不足に対して、中小企業は限られた資源の中で効果的な対策を講じる必要があります。単発的な施策ではなく、包括的なアプローチにより持続可能な人材確保・定着の仕組みを構築することが重要です。
DX推進による業務効率化と省人化
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、人手不足解消の最も有効な手段の一つです。人手で行っていた作業をデジタル化することで業務を自動化し、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
中小企業でも導入しやすいDX施策として、以下が挙げられます。
・クラウド型業務管理システムの導入
・RPAによる定型業務の自動化
・AIチャットボットによる顧客対応効率化
・電子決裁システムによるペーパーレス化
株式会社フジワラテクノアートの事例では、2019年より全社でDXを推進し、21個のITツール・システムを導入・活用しました。基幹システムの刷新により業務プロセスの可視化を実現し、仕入先への発注方法をFAX・郵送からオンラインに切り替えることで月400時間の工数削減を実現しています。
重要なのは、システム導入を目的とするのではなく、業務効率化による生産性向上を明確な目標として設定することです。また、従業員が自ら必要性を感じて学習できる環境づくりにより、DXの内製化を進めることで持続的な改善が可能になります。
多様な人材の活用(女性・シニア・外国人)
労働力人口の減少により、従来とは異なる人材層の活用が不可欠となっています。女性、シニア、外国人など多様な人材が活躍できる環境整備により、人材確保の選択肢を広げることができます。
女性の活用においては、ライフイベントとの両立を支援する制度整備が重要です。
・柔軟な勤務時間制度(フレックスタイム、時短勤務)
・リモートワーク環境の整備
・育児・介護支援制度の充実
・キャリア継続支援プログラム
シニア人材の活用では、豊富な経験と技術を活かせる環境づくりが求められます。定年延長や再雇用制度の導入、業務内容の工夫により身体的負担を軽減することで、高齢者が長期間働ける職場を実現できます。
外国人材の活用では、言語や文化の違いを受け入れる組織風土の醸成が重要です。日の丸交通株式会社では29か国116名の外国人が在籍し、多様な国籍や文化背景を持つ従業員が活躍できる環境を整備しています。
働き方改革による魅力的な職場づくり
若者世代の価値観変化に対応するため、働き方改革による魅力的な職場づくりが人材確保の鍵となります。ワークライフバランスの改善と成長機会の提供により、従業員の定着率向上を図ることができます。
効果的な働き方改革の施策
・時間外労働の削減と有給休暇取得促進
・多様なワークスタイルの導入
・成長支援制度の充実
・メンタルヘルスサポート体制の整備
株式会社メンバーズでは「みんなのキャリアと働き方改革」として、残業時間50%削減、年収20%アップ、女性管理職比率30%を目標に掲げ、全目標を達成しました。残業代減少への不安解消のためベースアップを実施し、顧客にも事前に理解・協力を求めることで、改革を成功に導いています。
また、従業員のエンゲージメント向上により離職率を低下させることも重要です。調査によると、エンゲージメントが高い企業ほど離職率が低下する傾向があることが確認されており、従業員が「この職場で長く働きたい」と思える環境づくりが効果的です。
アウトソーシングの戦略的活用
自社の核となる業務に集中するため、非中核業務のアウトソーシングを戦略的に活用することで、効率的な人材配置が可能になります。
アウトソーシング対象となる主な業務
・経理・給与計算等のバックオフィス業務
・清掃・警備等の管理業務
・コールセンター・顧客対応業務
・システム運用・保守業務
アウトソーシングにより、専門的な知識やノウハウを持つ外部パートナーのサービスを活用でき、業務品質の向上も期待できます。また、変動する業務量に対して柔軟に対応できるため、人件費の固定費化を避けることも可能です。
ただし、企業の核となる技術やノウハウは内製化を維持し、競争力の源泉を確保することが重要です。アウトソーシングの範囲を適切に設定することで、人材不足を補いながら企業価値を向上させることができます。
労働者不足対策にかかるコストと投資対効果
労働者不足対策には一定のコストが必要ですが、中長期的な投資対効果を考慮して取り組むことが重要です。人材確保・定着にかかるコストと、人手不足により生じる機会損失を比較検討する必要があります。
主要な対策コストとその効果
・DX投資:初期投資は大きいが、長期的な業務効率化効果
・人材育成:研修費用はかかるが、技術継承と定着率向上
・待遇改善:人件費増加だが、離職率低下と優秀人材確保
・働き方改革:制度整備コストだが、エンゲージメント向上
人手不足倒産のリスクを考慮すると、適切な人材投資は企業存続のための必須コストといえます。短期的な収益への影響を懸念するあまり、必要な投資を怠ることは、より大きな損失を招く可能性があります。
成功している企業の多くは、人材を「コスト」ではなく「投資」と捉え、長期的な視点で人材戦略を構築しています。限られた資源を効果的に活用し、段階的に改善を進めることで、持続的な人材確保・定着の仕組みを構築することが可能です。
労働者不足の根本的解決策としてのM&A戦略
従来の人材確保対策だけでは限界が見えるなか、M&Aは労働者不足の根本的解決策として注目を集めています。中小企業のM&Aは、単なる事業拡大の手段を超えて、人材リソースの確保と最適配分を実現する戦略的選択肢となっています。
経営統合による人材リソースの最適配分
M&Aの最大のメリットは、複数の企業が持つ人材リソースを統合し、最適な配分を実現できることです。個別企業では確保困難な専門人材や技術者を、統合により効率的に活用することが可能になります。
経営統合による人材リソースの最適化効果
・重複する管理部門の統合による効率化
・専門技術者の企業間異動による技術力向上
・営業人員の地域別配置最適化
・研修・教育体制の共有による人材育成効率化
特に中小企業では、一人の従業員が担う業務範囲が広く、特定分野の専門性を深めることが困難な場合があります。M&Aにより企業規模を拡大することで、従業員の専門性向上と効率的な役割分担が実現できます。
また、季節変動や案件の波動により一時的な人員過不足が生じる業界では、複数拠点間での人材融通により、全体として安定した人員配置が可能になります。これにより、繁忙期の外注コスト削減と閑散期の固定費圧縮を同時に実現できます。
規模の経済を活かした採用力の強化
企業規模の拡大により、採用力の大幅な向上を実現できます。大企業に比べて採用競争力に劣る中小企業が、M&Aにより規模を拡大することで、より魅力的な労働条件を提示できるようになります。
規模拡大による採用力強化の効果
・採用予算の拡大による多様な採用チャネルの活用
・福利厚生制度の充実による魅力度向上
・キャリアパスの多様化による成長機会の提供
・ブランド力向上による認知度アップ
統合により事業の安定性が向上すると、求職者にとって魅力的な職場として認識されやすくなります。また、複数の事業領域を持つことで、従業員のキャリア形成において多様な選択肢を提供でき、長期的な人材定着にもつながります。
さらに、採用活動のノウハウやネットワークを共有することで、これまでリーチできなかった人材層にアプローチすることも可能になります。各企業が培ってきた採用ルートを統合することで、より効率的で効果的な採用活動を展開できます。
事業承継と雇用維持の両立
高齢化する経営者にとって、事業承継は喫緊の課題です。2025年には経営者が70歳以上の中小企業が約245万社に増加し、その約半数の127万社で後継者が決まっていない状況です。このまま放置すれば、約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があります。
M&Aによる事業承継のメリット
・雇用維持による地域経済への貢献
・技術・ノウハウの継承と発展
・取引先関係の維持・強化
・従業員のキャリア継続支援
後継者不在による廃業を避けることで、その企業が持つ人材とノウハウを社会全体で有効活用できます。特に技術力や専門性の高い中小企業の場合、M&Aにより事業を継続することで、貴重な人的資源の散逸を防ぐことができます。
また、買収企業にとっても、即戦力となる人材と確立された事業基盤を同時に獲得できるため、新規事業展開や技術力強化を効率的に実現できます。従業員にとっては、より安定した経営基盤の下でキャリアを継続でき、成長機会の拡大も期待できます。
譲渡企業の従業員が持つ顧客との関係性や技術的ノウハウは、買収企業にとって貴重な無形資産となります。この人的資本を適切に活用することで、シナジー効果を最大化し、統合後の企業価値向上を実現できます。
M&A戦略の成功には、統合プロセスにおける人材のケアが重要です。文化の違いや不安感を解消し、統合メリットを従業員が実感できるような丁寧なコミュニケーションと制度設計が求められます。
労働者不足が構造的課題となる中、M&Aは単なる成長戦略を超えて、持続可能な事業運営を実現するための重要な選択肢となっています。適切なパートナー選定と統合プロセスの設計により、人材リソースの最適化と企業価値の向上を同時に実現することが可能です。
まとめ|労働者不足時代を生き抜く経営戦略とM&Aの可能性
日本の労働者不足は一時的な現象ではなく、少子高齢化や働き方の価値観変化により生じた構造的な課題です。
中小企業が労働者不足時代を生き抜くためには、従来の人材確保手法だけでなく、DX推進による業務効率化、多様な人材の活用、働き方改革による魅力的な職場づくりなど、包括的なアプローチが必要です。これらの施策により、限られた人材リソースを最大限に活用し、持続可能な経営基盤を構築することが可能になります。
特に注目すべきは、M&Aを活用した根本的な解決策です。経営統合による人材リソースの最適配分、規模の経済を活かした採用力強化、事業承継と雇用維持の両立により、個社では解決困難な人材課題を戦略的に解決できます。後継者不在による127万社の廃業リスクを考慮すると、M&Aは雇用維持と技術継承の重要な手段となります。
労働者不足は危機でもありますが、同時に企業変革の機会でもあります。人材を「コスト」ではなく「投資」と捉え、長期的な視点で戦略を構築する企業が、この困難な時代を乗り越え、持続的な成長を実現できるでしょう。M&Aを含む多様な選択肢を検討し、自社の状況に最適な戦略を策定することが、労働者不足時代における経営の成功の鍵となります。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。