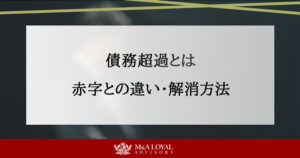詐害行為とは?取消権の時効と要件、該当ケースをわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
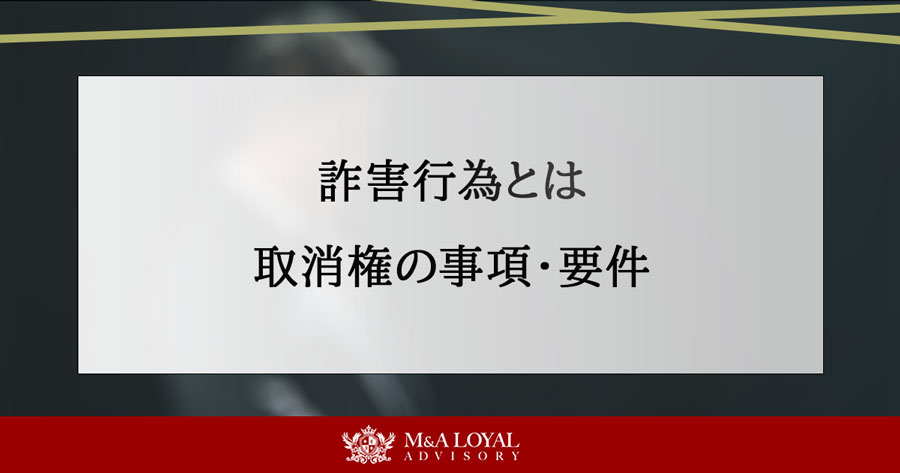
詐害行為とは、債務者が債権者を害する意図で財産を減少させる行為のことです。会社売却やM&Aの場面では、売り手企業が債務から逃れるために資産を安価で売却したり、関連会社に移転したりするケースが問題となります。このような行為は、M&A取引に重大な影響を与える可能性があり、債権者は民法424条に基づいて取消請求を行うことができます。
本記事では、詐害行為の定義や具体的なケース、取消権の要件や時効、防止策について詳しく解説し、M&A実務における注意点をわかりやすく説明します。
目次
詐害行為とは何か
詐害行為とは、債務者が債権者を害することを知りながら、自分の財産を減少させる行為を指します。この制度は、債権者の権利を保護するために民法に定められており、特にM&A取引において重要な法的概念となっています。
詐害行為の定義と法的根拠
詐害行為をした場合、債権者の債権回収が困難になります。そのため、民法424条では、一定の要件を満たす場合に債権者が取消請求を行うことができると定めています。
| 第424条【詐害行為取消請求】 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 |
詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全するための制度です。債務者が意図的に財産を減少させることで、債権者の利益を害することを防ぐことが目的となっています。
2017年民法改正のポイント
2017年の民法改正により、詐害行為に関する規定が見直されました。最も重要な変更点は、取消対象が「法律行為」(契約など法的効果を発生させる意思表示)だけでなく、事実行為(物理的な行為)も含まれるようになったことです。この改正により、法律行為以外の事実行為も詐害行為の対象となる可能性が生じ、M&A取引における詐害行為のリスクも拡大したといえます。
詐害行為の成立要件
詐害行為が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。まず、債務者に「害する意図(悪意)」があることが必要です。これは、債務者が自らの行為によって債権者を害することを認識していたことを意味します。
次に、受益者もその意図を知っていたことが要件となります。つまり、財産を譲り受けた第三者も、その譲渡が債権者を害することを知っていた必要があります。
さらに、債務者の「無資力(債務者が債務を返済できない状態であること)」も重要な要件です。
これらの要件がすべて満たされた場合、債権者は詐害行為取消請求を行うことができ、M&A取引においても重大な影響を与える可能性があります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



詐害行為に該当する具体的なケース
詐害行為に該当するケースは様々ありますが、M&A取引において特に注意が必要なものを具体的に見ていきましょう。これらのケースを理解することで、リスクを事前に回避することができます。
不動産の不当な譲渡
最も典型的な詐害行為のケースが、不動産の不当な譲渡です。債務者が市場価格を大幅に下回る金額で第三者へ不動産を譲渡する場合、詐害行為に該当する可能性が高くなります。
例えば、時価5,000万円の不動産を1,000万円で親族や関連会社に売却するような場合、債権者を害する意図があると判断される可能性があります。このような取引は、M&Aにおいても重要な注意点となります。
過剰な贈与による財産隠し
債務者が高額な無償贈与を行うことで財産を隠す行為も、詐害行為に該当します。特に、債務超過の状況で多額の贈与を行う場合は、詐害行為として認定される可能性が高くなります。
M&A取引では、売り手企業の経営者が取引前に個人的な贈与を行っていないか、詳細な調査が必要です。過去の贈与履歴を確認し、詐害行為のリスクを評価することが重要です。
主要資産の不当な安売り
会社の主要資産を不当に安く売却する行為も、詐害行為に該当する可能性があります。特に、M&A取引の直前に重要な資産を安価で処分する場合は、詐害行為として問題となることがあります。
製造設備や知的財産権など、事業に不可欠な資産を市場価格より大幅に安く売却することは、債権者の利益を害する行為として認定される可能性があります。
新設分割による会社分割
会社分割を利用した詐害行為が問題視されています。優良資産を新会社へ移転し、負債を旧会社に残すような分割は、詐害行為として問題となる可能性があります。
以下の表は、詐害行為に該当する可能性が高い会社分割の特徴をまとめたものです。
| 分割の特徴 | 詐害行為のリスク | 対策 |
|---|---|---|
| 優良資産のみ移転 | 高 | 適正な対価の設定 |
| 負債の一方的な残存 | 高 | 債権者への説明 |
| 関連会社への移転 | 中 | 第三者評価の実施 |
| 事業の合理的分割 | 低 | 適切な手続きの実施 |
債務超過企業の資産のみ譲渡
債務超過状態の企業が債務は引き継がずに、資産・事業のみを譲渡する場合も詐害行為に該当する可能性があります。このような取引は、M&A取引において特に注意が必要です。
債務超過企業との取引では、資産譲渡だけでなく、適切な債務の引き継ぎや債権者への配慮が必要になります。買い手企業は、このようなリスクを十分に検討した上で取引を進める必要があります。
詐害行為に該当しないケース
詐害行為に該当しないケースを理解することで、適法な取引と債権者を害する取引の区別を明確にすることができます。M&A取引において、これらのケースを参考にすることで、リスクを回避できます。
相当な対価での売却
適正な対価で資産を売却する場合は、詐害行為に該当しません。市場価格に基づいた適正な価格での取引であれば、債権者を害する意図がないと判断されます。
対価が適正であれば、たとえ資産が移転しても財産価値は維持されるため、債権者の利益を害することにはなりません。M&A取引では、第三者機関による適正な企業価値評価が重要です。
合理的な経営判断による資産処分
経営上の合理的な判断に基づく資産処分は、詐害行為に該当しません。事業の効率化や競争力向上のために行われる資産売却は、正当な経営行為として認められます。
以下のような場合は、合理的な経営判断として認められる可能性があります。
- 不採算事業の売却・撤退
- 経営資源の集中のための資産処分
- 市場環境の変化に対応した事業再編
- 効率化を目的とした設備更新
特定債権者への弁済
特定の債権者に対する弁済は、原則として詐害行為に該当しません。債務者が債権者に対して正当な債務を弁済することは、本来の義務を履行する行為だからです。
ただし、債務者と債権者が通謀して他の債権者を害する意図がある場合は、例外的に詐害行為として認定される可能性があります。M&A取引では、このような通謀の有無についても注意深く調査する必要があります。
相続放棄と財産分与
相続放棄は財産権の放棄ではなく身分行為として扱われるため、詐害行為には該当しません。また、離婚に伴う財産分与も身分行為として適法とされています。
ただし、財産分与について過大な分与が行われた場合は、その過大部分について詐害行為として認定される可能性があります。M&A取引では、売り手企業の経営者の個人的な財産移転についても注意を払う必要があります。
詐害行為取消請求の手続きと要件
詐害行為取消請求は、債権者が詐害行為を取り消すために行う法的手続きです。この制度の理解は、M&A取引におけるリスク管理において極めて重要です。
詐害行為取消請求の概要
詐害行為取消請求は、債務者の財産減少行為を取り消し、債務者の財産を回復させることを目的とした制度です。民法424条に規定されており、一定の要件を満たす場合に債権者が行使できます。
この請求が認められると、詐害行為は取り消され、移転された財産は債務者の元に戻ることになります。M&A取引では、このリスクを十分に考慮した契約条項の設定が必要です。
詐害行為取消権を行使する際の要件
詐害行為取消請求を行うためには、請求権者が以下の要件を満たす必要があります。まず、債権の発生が詐害行為より前であることが必要です。詐害行為後に発生した債権では、取消請求は認められません。
次に、金銭債権で強制執行が可能であることが要件となります。また、債務者が無資力であることも重要な要件です。さらに、債務者と受益者の悪意があることも必要です。
詐害行為取消権の手続きの流れ
詐害行為取消請求の手続きは、以下の流れで進行します。まず、証拠収集を行い、詐害行為の存在を立証するための資料を集めます。次に、弁護士に相談し、法的な検討を行います。
その後、裁判所に訴状を提出して訴訟を提起し、債務者に対して訴訟告知を行います。審理を経て判決が下されることになります。
詐害行為取消権の時効と注意点
詐害行為取消請求を行う際の重要な注意点として、必ず訴訟提起が必要であることが挙げられます。また、消滅時効についても注意が必要です。
消滅時効は、債権者が詐害行為を知った時から2年、詐害行為の時から10年となっています。さらに、債務者・受益者の悪意や無資力については、債権者側が立証責任を負うことも重要なポイントです。
詐害行為のリスクを防ぐための対策
M&A取引において詐害行為のリスクを防ぐためには、事前の十分な準備と適切な対策が不可欠です。以下に具体的な防止策を詳しく説明します。
デューデリジェンスの徹底
最も重要な対策は、デューデリジェンスの徹底です。財務・法務・事業内容について詳細な調査を行い、詐害行為の可能性を事前に検出することが必要です。
特に債務超過企業や財務状況が悪化している企業との取引では、過去の資産移転や債務処理について詳細な調査を行うことが重要です。専門家による第三者調査を活用することで、客観的な評価が可能になります。
契約内容の慎重な確認
M&A契約書において、表明保証条項を明確に規定することが重要です。売り手企業が詐害行為を行っていないことを明確に表明・保証させ、違反した場合の責任を明確にします。
また、補償条項やエスクロー(取引金額の決済を金融機関などの第三者に仲介してもらう)条項を設けることで、詐害行為が発覚した場合のリスク分担を明確にすることも効果的です。
記録の保管と専門家への相談
契約交渉から合意に至るまでの過程を詳細に記録し、保管することが重要です。これにより、取引の正当性を後から証明することができます。
さらに、弁護士・会計士・M&Aアドバイザーなどの専門家に相談し、法的リスクを事前に評価することが不可欠です。専門家の意見を取り入れることで、詐害行為のリスクを大幅に軽減できます。
適正価格での取引と情報開示
客観的な企業価値評価に基づく適正価格での取引を行うことは、詐害行為のリスクを回避する最も信頼性の高い方法です。特に、第三者評価や公正な市場基準を活用することで、取引の透明性と公正性を確保できます。これにより、債権者や利害関係者からの疑念を防ぎ、取引後の法的リスクを最小限に抑えることができます。
また、買い手企業に対する正確な情報開示を徹底し、隠蔽や虚偽表示がないことを確認することも重要です。透明性の高い取引を行うことで、詐害行為のリスクを最小限に抑えることができます。
まとめ
詐害行為とは、債務者が債権者を害する意図で財産を減少させる行為であり、M&A取引において重大なリスクとなる可能性があります。債権者は一定の要件を満たせば、民法424条に基づいて裁判所で取消請求を行うことができ、最悪の場合、成立したはずのM&A取引が無効となるリスクがあります。
特に債務超過企業との取引では、資産の不当な譲渡や会社分割による財産隠しなど、様々な形態の詐害行為に注意が必要です。これらのリスクを回避するためには、事前のデューデリジェンス徹底、適正価格での取引、専門家への相談などの対策が不可欠となります。
M&A取引における詐害行為のリスクを適切に管理し、安全で確実な取引を実現するためには、専門的な知識と経験が必要です。M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。