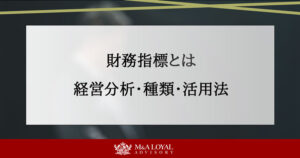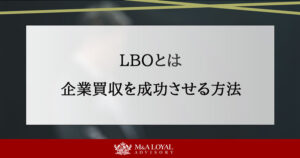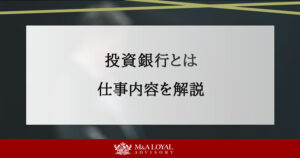コベナンツとは?メリット・デメリットや対応ポイントを徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
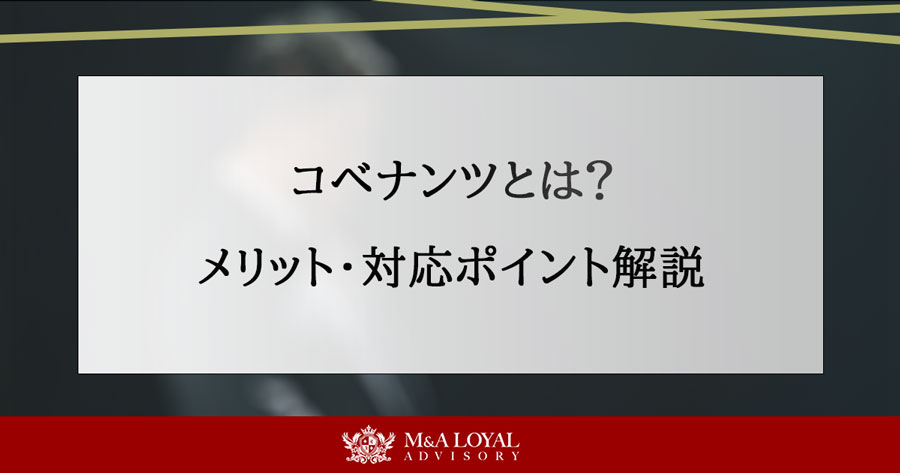
融資を受ける際に目にする「コベナンツ」という言葉。実はこれが融資契約の成否や企業経営の自由度に大きく影響する重要な要素なのです。
コベナンツとは、金融機関と企業の間で締結される融資契約に付随する特約条項のことで、企業の財務状況や経営活動に一定の制約を課すものです。
特に中小企業にとっては、このコベナンツの内容理解と適切な対応が、資金調達の成功と企業の持続的発展のカギを握ります。本記事では、コベナンツの基本から種類、メリット・デメリット、そして中小企業経営者が知っておくべき実践的な対応策まで、わかりやすく解説します。
財務制限条項や情報提供義務、事業承継時の注意点など、知っておくと役立つ知識を網羅的にご紹介します。
目次
コベナンツの基本|知っておくべき契約条項
中小企業の資金調達において、融資契約の条件は経営の自由度や将来の成長に大きな影響を与えます。特に「コベナンツ」と呼ばれる契約条項は、企業と金融機関の間の信頼関係を形作る基盤でもあります。
コベナンツの定義と基本的役割
コベナンツとは、金融機関(貸し手)が企業(借り手)に対して融資契約書で課す特約条項(義務)のことです。これらは借り手が「行うべきこと」や「行ってはならないこと」を明確に定め、融資の安全性を高める役割があります。
基本的に、コベナンツには以下のような役割があります。
- 貸し手のリスク低減:借り手の財務状況や経営行動に制約を設けリスクを抑制
- 早期警戒システム:財務状況悪化を早期に発見し、対応するための仕組み
- 健全経営の促進:財務指標の目標設定などを通じて財務規律を向上
コベナンツに違反した場合、新たな借入ができなくなるだけでなく、借入債務の期限の利益を喪失し、一括返済を求められるリスクもあります。
中小企業にとってのコベナンツの重要性
中小企業にとって、コベナンツは単なる制約ではなく、長期的な成長と安定した資金調達を実現するための重要な要素です。
まず、中小企業は大企業と比較して財務基盤が脆弱なことが多いため、コベナンツを通じた財務規律の確保が信頼獲得に繋がります。適切なコベナンツ設定は、金融機関との信頼関係構築に役立ち、長期的な融資関係の維持に貢献します。
- 経営の健全化促進:過剰な投資や無理な事業拡大を抑制
- 資金調達条件の改善:コベナンツ遵守の実績を積むことで有利な調達条件を獲得
- 事業承継やM&A時の円滑化:健全な財務状態の維持で大きな経営転換期の資金調達が容易になる
日本における中小企業融資とコベナンツの変遷
従来の日本における資金調達は、銀行融資に大きく依存し、特にメインバンクからの融資が中心でした。「メインバンク制」では、借り手が返済不能になった場合、主に不動産担保による回収が行われていました。
しかし、バブル崩壊後、金融環境は大きく変化し、企業は複数の金融機関と取引するようになりました。貸し手のリスク管理の観点から、不動産担保の価値よりも企業のキャッシュフローの健全性が重視されるようになり、明文化されたコベナンツの導入が進みました。
最近の動向としては、以下のような変化が見られます。
- 担保依存からキャッシュフロー重視への転換
- 多様な資金調達手段の広がり(社債発行やメザニンファイナンスなど)
- 情報開示の強化(金融庁による開示義務化)
- 中小企業向けコベナンツの普及

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



コベナンツの種類|主要な条項の解説
融資契約におけるコベナンツは、大きく「財務コベナンツ」「情報提供義務」「作為・不作為義務」の3つに分類できます。
財務コベナンツと重要な財務指標
財務コベナンツとは、あらかじめ遵守すべき財務指標を設定し、それを下回った場合に貸付人がローンの期限の利益を失わせることができる条項です。主要な財務指標は以下の通りです。
- レバレッジ・レシオ:
「有利子負債残高÷EBITDA」で計算される債務返済能力を示す指標 です。
- デット・サービス・カバレッジ・レシオ(DSCR):
「フリー・キャッシュフロー÷デット・サービス額」で算出され、元利金支払い能力を示します。ただし、不動産投資や不動産運営においては「NOI(正味稼働利益)÷デット・サービス額」で計算されることが一般的です。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ(ICR):
一般的には「(営業利益+受取利息+受取配当金)÷支払利息」で算出され、企業の利息支払い能力を表す重要な指標です 。フリー・キャッシュフローを用いた計算方法も存在しますが、契約内容によって定義が異なる場合があるため確認が必要です。
- 最低純資産額:企業が維持すべき純資産額の下限
レバレッジ・レシオは最も一般的な指標で、EBITDAとは「利息・税金・減価償却費控除前利益」を指し、企業の収益力を示すものです。ただし、EBITDAの具体的な計算方法は融資契約書等で個別に定義される場合があるため、契約内容を詳細に確認することが重要です。
情報提供義務と適切な開示方法
情報提供義務は、借入人の財務状態をモニタリングするために設けられる条項です。主な情報提供義務には以下があります。
- 財務諸表の提出:決算書(損益計算書、貸借対照表、CF計算書)の提出
- 事業計画書や資金繰り表の提出
- 重要事項の報告:経営に影響を与える事象の報告
- 税務申告書の写しの提出
これは金融機関が企業の状況変化を早期に察知し、必要な対応を取るための重要な手段です。適切な情報開示は金融機関との信頼関係強化にも役立ちます。
情報提供のポイント:
- 正確性:誤った情報提供は信頼関係を損なう
- 適時性:期限内の提出と重要事項の迅速な報告
- 一貫性:比較可能な形式での提出
- 透明性:問題も含めて隠さず開示
作為・不作為義務と経営への影響
作為義務(アファーマティブ・コベナンツ)と不作為義務(ネガティブ・コベナンツ)は、企業の経営判断に直接的な影響を与えます。
【作為義務の主な例】
- パリパス条項:他の債務と同等以上の優先順位で支払いを保証
- 事業維持条項:必要な事業許可の維持や主たる事業の継続
- 法令遵守義務
【不作為義務の主な例】
- 担保提供禁止:第三者への担保提供を制限
- 配当制限:過剰な配当や自己株取得を制限
- 投資制限:一定額以上の投資や新規事業参入を制限
- 資産処分制限:重要資産の処分やM&Aの制限
これらの義務は事業拡大や組織再編、配当政策に影響しますが、経営の安定性を高める効果もあります。
対応ポイント:
- 融資契約前に条項内容を理解し、事業計画への影響を考慮
- 例外条項の設定交渉
- 事前承認プロセスの確立
- 定期的な見直し交渉
コベナンツのメリットとデメリット
融資契約におけるコベナンツは、中小企業と金融機関の双方にメリットとデメリットをもたらします。これらを理解し、バランスよく活用することが重要です。
中小企業にとってのメリット
コベナンツは中小企業にとって様々なメリットがあります。
まず、財務管理の強化です。コベナンツで定められた財務基準を遵守するには日常的な財務管理が不可欠で、これにより問題の早期発見・対応が可能になります。特に財務管理にリソースが限られる中小企業では、このような外部からの規律づけが財務健全性の維持に役立ちます。
次に、市場や金融機関からの信頼構築があります。コベナンツを適切に遵守することで「約束を守る企業」という評価を得られ、それは取引先や投資家など他のステークホルダーからの信頼獲得にもつながります。
- 財務の透明性向上:定期的な財務報告による情報共有の促進
- 経営姿勢の評価:長期的視点での健全経営への姿勢が評価される
- 危機対応力の証明:厳しい環境下でもコベナンツを遵守する対応力の証明
さらに、有利な条件での資金調達が可能になります。継続的なコベナンツ遵守の実績を積み重ねることで、次回の融資交渉時により良い条件を引き出せる可能性が高まります。
金融機関側から見たメリット
金融機関がコベナンツを設定する主な目的は、融資に伴うリスク管理と貸付金の安全な回収の確保です。
最も重要なメリットは、リスク管理の強化です。コベナンツにより借り手の財務活動に一定の規制を加え、債務不履行リスクを低減できます。財務コベナンツを通じて借り手の財務状態を定期的にモニタリングし、問題を早期発見して対応することが可能になります。
- 財務状態悪化の早期把握:定期的な財務報告による異変の早期察知
- 過剰投資や無計画な事業拡大の抑制:経営判断への一定の制約
- 資産価値の保全:重要資産の処分制限により債権の担保価値を維持
また、借り手のガバナンス強化にも貢献します。ネガティブ・コベナンツを通じて、借り手に無計画な事業拡大や過剰な配当支払いを制限することで、長期的な企業ガバナンスの強化につながります。
デメリットとその対策方法
コベナンツには明らかなメリットがある一方で、中小企業と金融機関の双方にデメリットも存在します。
【中小企業側のデメリット】
最大のデメリットは、経営の自由度の制限です。コベナンツにより新規事業投資や事業活動拡大が制限され、特に成長段階の企業や事業転換を検討している企業にとって成長機会の喪失につながる可能性があります。
また、財務コベナンツ違反時のリスクや、管理コストの増加も無視できません。特に管理体制が十分でない中小企業では大きな負担となります。
【金融機関側のデメリット】
金融機関にとっても、管理コストの増大や過度な監視による借り手との関係悪化リスクがあります。
【効果的な対策方法】
- 契約前の十分な交渉:コベナンツの内容について事前に交渉し、自社の事業計画に影響が少ない条件となるよう努める
- ウェイバー制度の活用:一時的なコベナンツ違反が予想される場合、事前に金融機関と相談し、一定期間の適用免除を検討
- モニタリング体制の構築:定期的な自己チェック体制を確立し、違反リスクを早期発見
- 外部専門家の活用:会計士や財務アドバイザーなどの支援を受け、効率的な管理体制を構築
- 金融機関との良好な関係構築:日頃からのコミュニケーションを大切にし、問題発生時に柔軟な対応が得られる信頼関係を構築
資金調達手法別のコベナンツ対応
中小企業の資金調達方法は多様化しており、それぞれの方法によってコベナンツの内容や厳格さも異なります。資金調達手法の選択は、資金コストだけでなく経営の自由度にも影響するため、コベナンツの観点からも最適な手法を検討することが重要です。
通常の銀行融資における対応
一般的な銀行融資では比較的シンプルなコベナンツが設定されることが多く、銀行取引約定書に基づいた取引が基本となります。
一般的なコベナンツの特徴:
- 限定的な財務指標:純資産維持など基本的な財務安全性確保のためのシンプルな指標
- 目的限定の資金使途制限:設備資金であれば目的外使用の禁止など
- 基本的な情報開示:決算書類の提出や重要な変更の報告
- 追加担保提供の要請権限:財務状況悪化時に追加担保を求める権利
多くの場合、実際の運用は柔軟ですが、コベナンツの内容を事前に理解し違反しないよう管理することが重要です。
対応ポイント:
- 財務状況を定期的にモニタリングし、問題の兆候があれば早めに相談
- メインバンクとの信頼関係維持と密な情報共有
- 複数銀行の取引がある場合はコベナンツ条件の統一を交渉
- 資金使途の進捗状況の適切な報告
銀行融資のコベナンツは契約上の形式的制約というより、日常的なコミュニケーションツールとしての側面が強い点を理解し、信頼関係構築に努めることが重要です。
シンジケートローンの特徴と対応
シンジケートローンとは、複数の金融機関がシンジケート団(融資団)を組成し、一つの融資契約書に基づいて同一条件で融資を行う資金調達手法です。近年は中堅・中小企業でも活用されるケースが増えています。
シンジケートローンは通常、銀行取引約定書の適用対象外であり、より厳格なコベナンツが設定されます。
主な特徴:
- 詳細な財務コベナンツ:レバレッジ・レシオやDSCRなど複数の財務指標の遵守
- 定期的なモニタリング:四半期ごとなどでの財務状況報告
- 重要な経営判断の制限:大型投資や資産処分、追加借入などの制限
- シンジケート団による集団的意思決定:コベナンツ違反時の対応は全参加行の合意に基づく
対応ポイント:
- 契約前にアレンジャーと十分に交渉し、現実的なコベナンツを設定
- 財務指標の計算方法を明確に確認し、社内でのモニタリング体制を構築
- 契約書上の例外規定(キャーブアウト)の活用
- 重要事項の決議に必要な承認割合の確認
アレンジャーとなる金融機関との関係が特に重要であり、良好な関係構築がコベナンツ管理を円滑にする鍵となります。
M&A・LBOファイナンスの特殊条項
M&Aや事業承継の際に活用されるLBO(レバレッジド・バイアウト)ファイナンスでは、特に厳格なコベナンツが設定されます。LBOファイナンスは買収対象企業の資産や将来キャッシュフローを担保として買収資金を調達する方法です。
LBOファイナンスのコベナンツの特徴:
- 厳格なキャッシュフロー管理:DSCR(元利金支払能力)やICR(インタレスト・カバレッジ・レシオ)の基準設定
- 強力な資金流出制限:配当や役員報酬、関連会社への貸付制限
- 詳細な情報提供義務:月次での財務報告や事業計画の進捗報告
- キャッシュスイープ条項:余剰キャッシュフローによる強制期限前返済
- 厳格な追加借入制限
LBOファイナンスは、対象会社のキャッシュフローのみが返済原資となるノンリコースの融資であることが多いため、金融機関はリスク管理のために特に厳格なコベナンツを設定します。
対応ポイント:
- 買収後の事業計画を現実的に策定し、コベナンツ抵触リスクを検討
- 買収前のデューデリジェンスで対象会社の財務状況を精査
- コベナンツの緩和条件を事前に交渉
- 買収後の統合プロセスとコベナンツ管理責任者の明確化
- LBOファイナンス特有の用語や計算方法に詳しい外部アドバイザーの活用
中小企業向けLBOファイナンスでは、対象会社の規模や業種に応じた柔軟なコベナンツ設計が重要です。安定したキャッシュフローを生み出す事業であれば、現実的な条件を引き出せる可能性があります。
中小企業特有のコベナンツ対応ポイント
中小企業は大企業と比較して、経営資源の制約やオーナー経営者の存在など独自の特徴があります。そのため、コベナンツ対応にも中小企業ならではの視点と工夫が必要です。
オーナー経営者のための対策
中小企業の約7割がオーナー企業であり、会社の所有と経営が一体化しているため、コベナンツ対応において特有の課題があります。オーナー経営者と会社の財務が密接に関連している点が重要です。
コベナンツとの関連で注意すべきポイントは以下の通りです。
- 個人と法人の財務区分の明確化:会社の資金と個人の資金を明確に区分する
- 財務モニタリング体制:会社の財務状況を定期的にチェックする体制を整える
- 資金計画の綿密な策定:オーナー個人の生活設計も考慮した長期計画を立てる
- 適切な役員報酬設定:業績に応じた柔軟な役員報酬体系を検討する
特に「配当制限や役員報酬制限」などのネガティブ・コベナンツがある場合、オーナーの資金引出しに制限がかかる点に注意が必要です。また、コベナンツ管理を特定の人物に依存せず、複数の視点からの管理体制を構築することが理想的です。
事業承継時の重要条項と対応
中小企業にとって事業承継は企業存続にかかわる重要な局面であり、コベナンツに抵触するリスクが高まります。特に注意すべき条項は以下の通りです。
- 株式譲渡制限:オーナー保有株式の譲渡に関する制限
- 経営体制変更制限:取締役会や役員構成の変更制限
- 事業内容変更禁止:事業内容や組織再編に関する制限
- 重要資産譲渡禁止:重要資産の譲渡や処分を禁じる条項
対応ポイントとしては以下が重要です。
- 早期のコベナンツ確認:事業承継検討段階で融資契約内容を確認
- 金融機関との事前協議:事業承継計画を説明し、必要に応じて条件変更を交渉
- 段階的な事業承継の検討:コベナンツ抵触を避けるための段階的アプローチ
- 後継者の信用力強化:後継者の経験やスキルを示し、金融機関の信頼を獲得
現実的な財務指標の設定と交渉
中小企業にとって、コベナンツで設定される財務指標が現実的かつ持続可能であることは極めて重要です。不適切に厳しい指標は経営の自由度を制限し、成長機会の損失につながります。
財務コベナンツ交渉のポイント:
- 業種特性の考慮:業種に適した財務指標水準の設定を求める
- 季節変動の考慮:季節による変動がある場合、測定タイミングや基準値に柔軟性を持たせる
- 成長計画の共有:将来の投資計画を説明し、一時的な指標悪化への理解を求める
- 現実的なバッファ確保:予期せぬ環境変化に対応できる余裕を持たせる
中小企業は業績変動幅が大きい傾向があるため、複数指標の組み合わせや一時的な基準値緩和条件など、柔軟性のある対応を交渉することが重要です。効果的な交渉のためには、日頃から財務管理体制を整備し、適切な財務分析を行っておくことが不可欠です。
コベナンツ違反のリスクと対応策
コベナンツの重要性を理解し適切に対応するには、違反した場合のリスクと影響を把握しておくことが不可欠です。ここでは、コベナンツ違反による具体的な影響と、それを未然に防ぐための管理体制、そして万が一違反してしまった場合の信頼回復プロセスについて解説します。
違反による具体的な影響
コベナンツ違反が確認された場合、企業にはさまざまな影響が及びます。最も直接的な影響は、融資条件の変更や「期限の利益」の喪失です。
具体的な影響には以下のようなものがあります。
- 融資の一括返済要求:期限の利益を喪失し、融資残高の全額一括返済を求められる
- 金利の引き上げ:北日本銀行の例では、抵触1回で0.5%の金利引き上げとなる
- 追加担保の要求:担保不足と判断された場合、追加担保の提供を求められる
- 配当制限の強化:株主への配当が制限され、キャッシュの社外流出が厳しく制限される ・追加融資の拒絶:新規借入や融資枠の拡大が困難になる
これらの直接的な金融上の影響に加え、取引先への信用不安の波及や格付け低下、経営自由度の低下、経営者への心理的プレッシャーなど、二次的影響も考えられます。
ただし、実務上はコベナンツ違反が直ちに最悪のシナリオにつながるわけではありません。多くの金融機関は違反後直ちに一括返済を求めるのではなく、期限猶予や条項見直しなどの改善機会を与えるケースが一般的です。段階的な対応を行う金融機関も少なくありません。繰り返しの違反は信用力低下や将来の融資獲得困難化につながるため、注意が必要です。
違反を未然に防ぐ管理体制
コベナンツ違反を未然に防ぐには、適切なモニタリングと管理体制の構築が不可欠です。特に中小企業では限られたリソースの中で効率的な管理体制を整えることが課題です。
基本的なポイントは以下の通りです。
- 全社的な理解促進:経営者だけでなく、財務担当者や各部門責任者もコベナンツの内容と重要性を理解する
- 定期的なモニタリング:月次や四半期ごとに財務指標を確認し、基準値との乖離を把握
- 早期警告システム:財務指標が基準値に近づいた時点でアラートが出る仕組みを作る
- シミュレーション実施:事業計画策定時や重要な経営判断前に、コベナンツへの影響をシミュレーション
具体的な管理ツールとしては、コベナンツ管理表の作成、財務指標の自動計算システム、定期的なレビュー会議の実施、金融機関との定期的コミュニケーションなどが有効です。
中小企業では複雑なシステムや専任担当者を置くことが難しい場合も多いですが、外部専門家の活用や既存部門間の連携強化、クラウドツールの導入、全社的な意識向上などの工夫で効率的な管理が可能です。
特に重要なのは問題の早期発見と対応です。財務指標が悪化傾向にある場合は、金融機関への事前相談、事業計画見直し、一時的な対応策実施、ウェイバー(免除)交渉などの事前対応を検討しましょう。
違反後の信頼回復プロセス
万が一コベナンツに違反してしまった場合でも、適切に対応することで信頼関係を回復し、事業を継続することが可能です。
基本的な対応ステップは以下の通りです。
- 状況の正確な把握
・違反したコベナンツの内容と程度を正確に理解
・他のコベナンツへの影響も含めて総合的に状況把握
・違反の原因と背景を分析
- 金融機関への迅速な報告と説明
・違反確認時点で速やかに報告
・隠したり言い訳せず、事実を率直に説明
・違反原因と現在の財務状況について詳細に説明
- 改善計画の策定と提案
・具体的で実現可能な改善計画を策定
・短期的対応策と中長期的解決策を盛り込む
・数値目標と達成時期を明確にした計画を提示
- 誠実な交渉と関係構築
・金融機関の懸念に真摯に対応
・期限猶予や条件変更について建設的に交渉
・透明性の高い情報共有を約束し、信頼関係再構築
- 計画の着実な実行と報告
・合意した改善計画を確実に実行
・進捗状況を定期的に報告
・計画通りに進まない場合は早期に相談し修正
特に中小企業の場合、経営者の誠実な姿勢と改善への積極的取り組みが評価されることが多いです。隠したり責任転嫁せず、率直に状況を説明し解決に向けた姿勢を示すことが第一歩です。
具体的な改善策としては、コスト削減、資産見直し、収益力強化、運転資金最適化、資本政策などが考えられます。また、情報開示の充実、経営体制強化、外部アドバイザーの活用、コミュニケーション強化なども効果的です。
財務状態が改善されれば、融資条件が元に戻るケースも多いですが、繰り返しの違反は融資回収のリスクや将来の資金調達困難化につながるため、一度立て直したら再発防止に全力を挙げることが重要です。
最新動向を踏まえたコベナンツ対応
金融環境の変化に伴い、コベナンツを取り巻く状況も日々進化しています。中小企業の経営者は、最新の動向を理解し、適切に対応することで資金調達をより効果的に行うことができます。ここでは、コベナンツに関する最新の動向と対応策について解説します。
2025年開示拡充制度の影響
金融庁は、企業の財務情報の透明性を向上させるため、『企業内容等の開示に関する内閣府令』の改正を検討しており、2025年度から上場企業に対して銀行との間で締結している財務制限条項(コベナンツ)の開示を義務付けることが発表されています。(参照:日本経済新聞)
この制度変更は直接的には上場企業が対象ですが、中小企業にも以下の影響が考えられます。
- 金融機関側のコベナンツ設定の厳格化
- 業界標準的なコベナンツ条項の明確化
- 取引先や親会社が上場企業の場合、間接的な情報開示の可能性
中小企業にとっては、この開示拡充の流れを理解し、自社のコベナンツ条項の内容や交渉時の参考情報として活用することが重要です。また、将来の上場を検討している企業は、早い段階からコベナンツの内容と対応について戦略的に考える必要があります。
経済危機下の柔軟な運用と交渉
近年の経済危機や新型コロナウイルス感染症のような予期せぬ事態において、コベナンツの柔軟な運用が重要視されています。2020年には金融庁が「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一環として、金融機関に対して財務制限条項の柔軟な適用を要請しました。
こうした状況下での対応ポイントは以下の通りです。
- 経済環境の急変による業績悪化は一時的なものとして交渉
- 事前に金融機関とのコミュニケーションを密に取り、状況を共有
- 危機時の対応策と回復計画を具体的に提示
- 必要に応じてコベナンツの一時的な緩和や猶予を交渉
経済危機時には金融機関も借り手企業の存続を優先する傾向があり、コベナンツ違反に対しても機械的な対応ではなく、個別の状況に応じた柔軟な対応が期待できます。しかし、そのためには日頃からの信頼関係構築が不可欠です。
特殊金融取引における条項と特徴
近年、中小企業においても多様な金融取引が活用されるようになり、それぞれの取引特性に応じたコベナンツが設定されています。
特に注目すべき特殊金融取引とコベナンツの特徴は以下の通りです。
- プロジェクトファイナンス:
対象プロジェクトのキャッシュフローに焦点を当てたコベナンツが設定され、詳細なモニタリングが行われます。 - LBOファイナンス:
買収対象企業の資産や将来キャッシュフローを担保とした高レバレッジの融資であり、財務指標の厳格な管理が求められます。 - アセットファイナンス:
特定資産を担保とした融資で、その資産の価値維持や管理に関する条項が重視されます。
中小企業がこれらの特殊金融取引を利用する際は、通常の融資より複雑なコベナンツが設定される可能性が高いため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討することが重要です。財務面だけでなく、経営や事業の自由度にも影響するため、長期的な視点での判断が必要となります。
まとめ:コベナンツの理解と管理で資金調達力を高める
コベナンツは単なる制約ではなく、企業の健全な財務体質を維持するための重要な指針です。中小企業の経営者が融資契約に含まれるコベナンツを正しく理解し、積極的に管理することで、金融機関との信頼関係が強化され、より良い条件での資金調達が可能になります。特に財務指標の定期的なモニタリングと適切な開示を行い、問題が発生する前に対策を講じることが重要です。
また、事業承継やM&Aなどの重要な局面では、既存のコベナンツ条項の見直しも必要になります。コベナンツを「制約」ではなく「経営改善のツール」として活用し、持続的な成長のための資金調達力を高めていきましょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはぜひ一度、M&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。