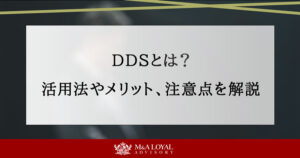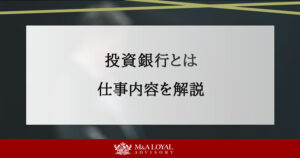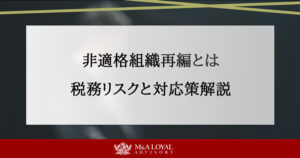資本性劣後ローンとは?メリット・デメリットから返済方法まで解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
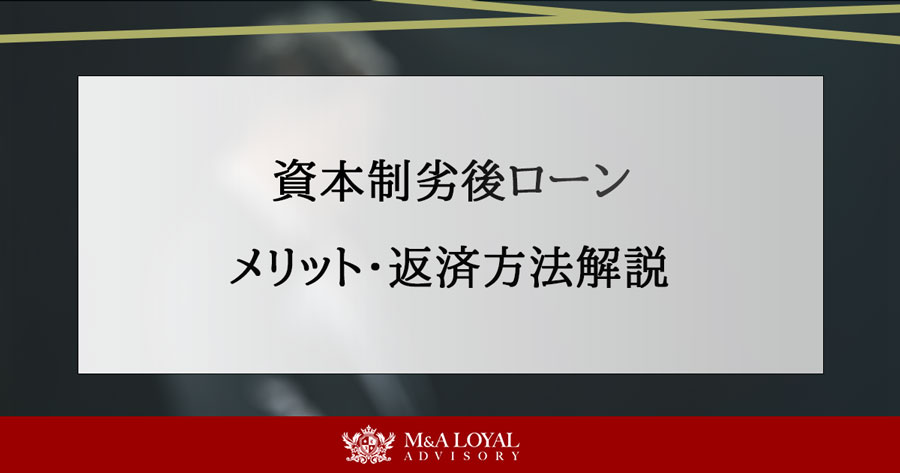
資本性劣後ローンをご存知でしょうか?借入金でありながら金融機関からは自己資本とみなされるという特殊な融資制度です。特に中小企業の財務体質強化や資金繰り改善に大きな効果を発揮します。
この記事では、資本性劣後ローンの基本的な仕組みから、「資本性」と呼ばれる理由、「劣後」の意味、期限一括返済の特徴、業績連動型金利の仕組みまで詳しく解説します。また、中小企業にとっての具体的なメリットや注意すべきデメリット、会計・税務上の取り扱い、効果的な活用シーン、そして日本政策金融公庫などへの申込方法まで網羅的に紹介します。
資金調達や財務改善にお悩みの経営者の方、ぜひ最後までお読みください。
目次
資本性劣後ローンとは?
資本性劣後ローンは、借入金でありながら金融機関からは自己資本とみなされるという特徴を持つ融資制度です。通常の融資では借入金が負債として計上されますが(これは資本性劣後ローンも会計上は同様です )、資本性劣後ローンでは金融機関の審査において自己資本として評価されるため、評価上の財務状況の改善効果が期待できます 。
主に日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などの政府系金融機関が取り扱っており 、中小企業の資金調達を支援する重要な制度となっています。
基本的な特徴と仕組み
資本性劣後ローンの基本的な特徴は以下の3点です。
- 期限一括返済方式:借入期間中は利息の支払いのみで、元金は期限到来時に一括返済
- 業績連動型金利設定:企業業績に応じて金利が変動し、業績不振時は低金利に設定
- 法的整理時の劣後性:万が一の法的倒産時には他の債務より返済順位が劣後
特に元金の返済が借入期間満了時まで不要である点は、毎月の資金繰りに余裕を持たせる効果があります。また、金融機関が企業を評価する際の自己資本比率の計算において、資本性劣後ローンの残高を資本に算入できるため、資金調達力の強化につながります。
「資本性」と呼ばれる理由
資本性劣後ローンが「資本性」と呼ばれるのは、借入金であるにもかかわらず、金融機関の評価において「自己資本」とみなされるからです。自己資本とは通常、株主から調達した資本金や企業活動で生み出された利益剰余金など、返済義務のない資金を指します。
企業の財務状況を評価する際に重要な指標の一つが自己資本比率です。自己資本比率が高いほど、企業の財務基盤は安定していると評価されます。資本性劣後ローンは、借入金でありながら資本として扱われるため、自己資本比率が向上し、金融機関からの評価が高まるという効果があります。
資本性劣後ローンの自己資本算入率は、返済期限までの残存期間によって変わります。残存期間が5年以上あれば100%を自己資本とみなすことができ、以降は1年ごとに20%ずつ自己資本算入率が減少していきます。
「劣後」の意味と法的位置づけ
「劣後」とは、返済の優先順位が他の債務よりも低いことを意味します。企業が万が一法的倒産に陥った場合、債権者への返済は法律で定められた優先順位に従って行われます。資本性劣後ローンは、この優先順位において最も低い位置に設定されています。
債務の返済優先順位は以下のようになっています。
- 財団債権:破産管財人の報酬など
- 優先的破産債権:税金、従業員給与など
- 一般的破産債権:通常の銀行借入金、買掛金など
- 劣後的破産債権:破産後の利息、延滞税など
- 約定劣後的破産債権:資本性劣後ローンなど
このように資本性劣後ローンは返済順位が最も低く設定されているため、万が一の倒産時には回収の可能性が低いという特性を持ちます。これは株式出資に近い性質であり、そのため金融機関の審査において資本として扱われる根拠になっています。
ただし、この返済順位の劣後性は、あくまで法的倒産手続きにおける取り扱いであり、私的整理の場合には異なる可能性がある点に留意が必要です 。
DDS(デッド・デッド・スワップ)との違い
資本性劣後ローンと似た制度にDDS(デッド・デッド・スワップ)があります。DDSとは、主に企業再生の場面で用いられる手法で、既存の借入金を劣後ローンに転換する制度ですが 、資本性劣後ローンとは以下の点で大きく異なります。
- DDSは既存債務の条件変更:既に借りている融資の返済条件を変更するもので、新たな借入はできない
- 資本性劣後ローンは新規融資:新たに資金を調達することができる「真水」の融資である
つまり、DDSは既存債務の性質を変えるだけで新たな資金は入ってきませんが、資本性劣後ローンは新規の融資なので実際に資金が手に入ります。財務改善と同時に資金調達を行いたい企業にとっては、資本性劣後ローンの方が有効な選択肢となるでしょう。
資本性劣後ローンは、特に財務基盤の強化が必要な中小企業や、大規模な設備投資を計画している企業、創業間もないスタートアップ企業など、通常の借入だけでは資金調達が難しい企業にとって、有効な選択肢となります。
資本性劣後ローンの詳細な仕組みと主な種類
資本性劣後ローンは、中小企業の資金調達における重要な選択肢として注目されています。ここでは、その仕組みや種類について詳しく解説します。
期限一括返済の仕組み
資本性劣後ローンの最大の特徴の一つが「期限一括返済」方式です。通常の融資では、借入後から毎月元金と利息を返済していくのが一般的ですが、資本性劣後ローンでは借入期間中は利息のみを支払い、元金は返済期限が来たときに一括で返済します。
例えば、10年の資本性劣後ローンを1億円借りた場合、10年間は毎月利息のみを支払い、10年後の期限到来時に1億円を一括返済する仕組みです。これにより期間中の資金繰りの負担が大幅に軽減されるため、事業拡大や業績回復に集中できるというメリットがあります。
借入期間は融資制度によって異なりますが、一般的には5年1ヶ月、7年、10年、15年、20年などの選択肢があります。期間を長く設定するほど自己資本としてみなされる期間も長くなるため、財務改善効果がより持続的になります。
なお、原則として融資実行から5年間は繰上返済ができないという制約があります。これは資本としての性質を担保するための条件であるため、借入の際には返済計画を慎重に立てる必要があります。
業績連動型金利設定の特徴
資本性劣後ローンのもう一つの重要な特徴が「業績連動型金利設定」です。金利は毎年、直近の決算内容に基づいて見直され、業績に応じて変動します 。具体的には、税引後当期純利益(最終的な利益)の状況によって金利が決まる仕組みになっています。
日本政策金融公庫「挑戦支援資本強化特別貸付」の金利設定例(2025年5月時点):
- 赤字(税引後当期純利益が0円未満)の場合:0.50%
- 黒字(税引後当期純利益が0円以上)の場合:返済期間に応じて3.25%~3.95%程度
特に注目すべきは、業績が悪化して赤字となった場合の金利が極めて低く設定されている点です 。これは企業が苦しい時期に金利負担を軽減し、業績回復を支援するための配慮です。一方で、業績が好調で利益が出ている場合は、貸し手のリスクを反映して通常の融資より高めの金利が設定される傾向にあります 。
主な提供金融機関
資本性劣後ローンを提供している主な金融機関は以下の通りです。
- 日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)
- 商工組合中央金庫(商工中金)
- 日本政策投資銀行(主に中堅・大企業向け、メザニンファイナンスの一環として)
特に中小企業向けの融資としては、日本政策金融公庫が中心的な役割を担っています。融資限度額は、現行の「挑戦支援資本強化特別貸付」において、 国民生活事業では7,200万円 、中小企業事業では15億円となっています 。いずれも別枠での融資となるため、通常の融資枠とは別に利用することが可能です。
民間の金融機関でも資本性劣後ローンを取り扱っている場合がありますが、一般的には公表されているプランは少なく、個別の相談ベースで対応しているケースが多いようです 。
新型コロナ対策版の特徴と条件
新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)は、日本政策金融公庫などから、コロナ禍における企業の資金繰り支援として提供されていましたが、既に新規申込を終了しています。
主な特徴:
- 業績に関わらず当初3年間は0.5%の低利率
- 無担保、無保証人での融資
- 資本性劣後ローンとして自己資本に計上可能
現在利用可能な資本性劣後ローンとしては、日本政策金融公庫の「挑戦支援資本強化特別貸付」(通常版)などがあります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



資本性劣後ローンの中小企業にとっての5つのメリット
資本性劣後ローンは中小企業にとって多くのメリットがあります。主な5つのメリットを簡潔に解説します。
金融機関格付けの向上効果
資本性劣後ローンの最大のメリットは、金融機関からの格付け向上効果です。通常の借入は負債として計上されますが、資本性劣後ローンは金融機関の評価では自己資本とみなされます。自己資本比率が向上することで、追加融資が受けやすくなり、既存融資の金利交渉も有利に進められます。債務超過企業の場合はそれを解消できることもあります。
例えば、自己資本比率20%の企業が資本性劣後ローンを利用すれば、金融機関からの評価上は自己資本比率が大幅に向上し、資金調達環境が改善します。
元金返済ゼロによる資金繰り改善
資本性劣後ローンは借入期間中の元金返済が不要で、利息のみの支払いで済みます。そのため、資金繰りに大きな余裕が生まれます。
この余剰資金を事業拡大や設備投資に回せるため、特に創業間もない企業や業績回復途上の企業には大きなメリットとなります。
赤字時における低金利のメリット
資本性劣後ローンは業績連動型の金利設定が特徴で、企業が赤字の場合は極めて低い金利(多くの場合0.5%程度)が適用されます。業績悪化時こそ資金繰りが厳しくなりますが、この仕組みにより金利負担が最小限に抑えられます。
無担保・無保証人で申請できる
資本性劣後ローンは原則として無担保・無保証人で申請できます。通常の融資では担保設定や経営者の個人保証を求められることが多いですが、資本性劣後ローンではそれらが不要です。
不動産などの担保資産を持たない企業でも申請でき、経営者の個人資産にリスクをかけずに資金調達ができるため、スタートアップ企業や事業拡大を目指す中小企業にとって大きなメリットとなります。
既存借入を借換えて返済負担を大幅に軽減できる
資本性劣後ローンは既存の借入金を借り換えることも可能です。複数の借入を一本化し、毎月の元金返済が不要になるため、返済負担を大幅に軽減できます。例えば、5,000万円の借入で毎月100万円の返済をしていた企業が資本性劣後ローンに借り換えれば、利息のみの数万円程度の支払いになります。
資本性劣後ローン利用時の注意点とデメリット
資本性劣後ローンには多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点やデメリットも存在します。融資を検討する際には、これらの点もしっかりと理解しておくことが重要です。
審査が厳しく事業計画書の作成が必須である
資本性劣後ローンは通常の融資と比較して審査のハードルが高く設定されています。融資する側からすると、元金返済が不要で一括返済のリスクが高いためです。審査では事業の将来性と実現可能性の高い事業計画が重視されます。
事業計画書には市場分析、売上・利益計画、資金計画、返済計画、リスク分析と対応策などを盛り込む必要があります。多くの場合、認定経営革新等支援機関の関与も必要となるため、申請準備には余裕をもったスケジュールを立てましょう。
黒字になると金利負担が大きく増加する
資本性劣後ローンの金利は業績連動型で、赤字時は低い金利(約0.5%)が適用されますが、黒字になると金利が大幅に上昇します。一般的には黒字の場合、金利は2.60%~4.65%程度となり、通常の融資と比較しても高めの水準です。
例えば1億円の資本性劣後ローンでは、赤字時の年間利息負担は約50万円ですが、黒字になると年間260万円~465万円に跳ね上がります。黒字化が見込まれる時期を予測し、金利上昇に備えた資金計画を立てておくことが重要です。
原則として5年間は繰上返済ができない
資本性劣後ローンは原則として、融資実行から5年間は繰上返済ができないという制約があります。これは資本性を担保するための条件です。
この制約により、予想以上に業績が回復・向上しても早期に返済できない、黒字化で金利負担が増大しても他の低金利融資への借換えができない、会社売却や事業承継を検討しても5年間は融資が残るといった不都合が生じる可能性があります。
満期時に一括返済が必要となるリスクがある
資本性劣後ローンは期限一括返済が原則であるため、満期時には借入元金を一括で返済する必要があります。例えば1億円の借入であれば、満期時に1億円を一度に返済する資金を用意しなければなりません。
これは多くの中小企業にとって大きな負担となる可能性があり、返済資金不足のリスク、急遽の借換え融資が必要になるリスク、満期が近づくと財務上の不安定要素と評価されるリスクなどがあります。
満期時の一括返済リスクに対処するためには、計画的な返済原資の積立て、キャッシュフローの改善・強化、複数の返済選択肢の検討、満期の1~2年前からの金融機関との相談などが大切です。借入時から満期時の返済を見据えた長期的な資金計画を立てておくことが経営の安定につながります。
資本性劣後ローンの会計・税務上の取り扱い
資本性劣後ローンは金融機関の評価においては「資本」とみなされる特殊な融資ですが、会計処理や税務上ではどのように扱われるのでしょうか。ここでは、資本性劣後ローンの会計・税務面での取り扱いについて解説します。
会計処理と勘定科目の選択
資本性劣後ローンは、金融機関の評価上は自己資本とみなされる特殊な性質を持ちますが、会計上は基本的に「借入金」として処理されます。つまり、貸借対照表の負債の部に計上する必要があります。
具体的な仕訳は以下のようになります。
【借入時の仕訳】 (借方)現金預金 ×××× (貸方)長期借入金 ××××
ただし、勘定科目の選択においては注意が必要です。通常の借入金と同様に「長期借入金」として処理することも可能ですが、資本性劣後ローンであることを明確にするために「資本性借入金」という勘定科目を使用することが推奨されています。
「資本性借入金」という勘定科目を使用することで、以下のようなメリットがあります。
- 金融機関が決算書を確認した際に、資本性劣後ローンの存在を認識しやすくなる
- 自己資本とみなされるべき借入金であることが明確になる
- 通常の借入金と区別することで、財務分析がしやすくなる
特に、金融機関が決算書だけを見た場合に、通常の長期借入金と資本性劣後ローンが区別できないと、正しい財務評価がなされない可能性があります。そのため、勘定科目を「資本性借入金」とすることで、金融機関による見落としを防ぐ効果が期待できます。
財務諸表に与える影響
資本性劣後ローンは会計上は負債として扱われるため、財務諸表には以下のような影響を与えます。
- 貸借対照表への影響
- 負債の部に「資本性借入金」などの科目で計上される
- 資産と負債の両方が同額増加するため、負債比率は上昇する
- 純資産(自己資本)には直接的な変化はない
- 損益計算書への影響
- 支払利息が増加する
- 業績連動型金利の場合、毎年金利負担が変動する可能性がある
- キャッシュフロー計算書への影響
- 借入時は財務活動によるキャッシュインフローとして計上
- 期間中の利息支払いは営業活動によるキャッシュアウトフローとして計上
- 満期時の一括返済は財務活動によるキャッシュアウトフローとして計上
財務分析を行う際、純粋な会計数値だけでは資本性劣後ローンの特性が反映されないため、財務指標の評価には注意が必要です。例えば自己資本比率を計算する場合、金融機関の評価と会計上の数値では差が生じることになります。
そのため、経営分析や事業計画を立てる際には、通常の会計数値とは別に、金融機関の評価を加味した「調整後自己資本比率」なども参考指標として算出することが有益です。
税務上の注意点
税務上、資本性劣後ローンは一般的な借入金と同様に扱われ、支払利息は損金(経費)として計上できます。しかし、いくつかの注意点があります。
- 金利の変動に関する注意点
- 業績連動型金利のため、利益状況によって支払利息が変動する
- 確定申告後に金利が確定するため、期中における利息の見積もりが必要となる場合がある
- 満期一括返済に関する注意点
- 期限到来時の一括返済のための資金積立は、税務上の損金にはならない
- 一括返済のために他の借入を行う場合、借換えとして適切に処理する必要がある
- 借換え時の注意点
- 既存借入の借換えとして資本性劣後ローンを利用する場合、適切な移行処理が必要
- 期限前弁済の可否や手数料などの条件を確認する
特に、資本性劣後ローンの業績連動型金利は、企業業績の変動に応じて金利も変動するため、税務計画を立てる際には注意が必要です。例えば、当初は赤字で低金利であっても、黒字転換によって金利負担が大幅に増加した場合、その分の利息支払いも増えることになります。
税務申告の際には、正確な利息計算を行い、適切に損金計上することが重要です。また、複数年にわたる長期の資本性劣後ローンを利用する場合は、将来の税務負担も考慮した計画を立てることをお勧めします。
資本性劣後ローンは会計・税務の観点からは通常の借入金と大きな違いはありませんが、その特殊性を考慮した処理や分析が求められます。不明点がある場合は、税理士や公認会計士などの専門家に相談することをお勧めします。
資本性劣後ローンが効果的な4つの活用シーン
資本性劣後ローンは様々な状況下の企業に対して効果的な資金調達手段となります。特に効果を発揮する4つの活用シーンについて見ていきましょう。
債務超過に陥った企業の財務体質を改善できる
債務超過とは、企業の負債総額が資産総額を上回っている状態です。債務超過の企業は金融機関からの追加融資が受けにくく、取引先からの信用も失いやすい問題を抱えています。
資本性劣後ローンは、金融機関の評価において自己資本とみなされるため、債務超過を解消するための有効な手段となります。例えば、資産1億円、負債1.2億円で2,000万円の債務超過に陥っている企業が3,000万円の資本性劣後ローンを利用した場合、金融機関の評価上は債務超過が解消されます。
メリットとしては、金融機関からの追加融資が受けやすくなる、取引先からの信用が回復する、上場企業の場合は上場廃止リスクを回避できるといった点が挙げられます。
大規模な設備投資資金を返済負担なく調達できる
大規模な設備投資を行う際、通常の借入だと毎月の返済負担が経営を圧迫するリスクがあります。資本性劣後ローンなら、借入期間中は利息のみの支払いで済むため、設備投資による収益が安定するまでの期間、資金繰りを安定させることができます。
例えば、5億円の製造設備を導入する場合、金利を仮に2%とすると、通常の10年融資では月々約480万円の返済が発生しますが、資本性劣後ローンなら月々の支払いは利息分のみ、赤字時なら21万円程度に抑えることができます。(実際の資本性劣後ローンの条件は、契約内容や金融機関、企業の信用状況などによって異なります。)
投資初期の返済負担を最小化できる、設備投資によるキャッシュフロー改善までの時間的猶予が得られる、業績に応じた金利設定により投資初期の赤字期間は金利負担も軽減されるといったメリットがあります。
初期投資の大きいスタートアップ企業の成長を支える
創業間もないスタートアップ企業や新規事業に取り組む企業は、収益が安定するまでに時間がかかるケースが多く、初期投資の資金調達が大きな課題となります。資本性劣後ローンは、このようなスタートアップフェーズの企業にとって有効な資金調達手段となります。
収益が安定するまでの期間、元金返済の負担がない、赤字期間は低金利で利息負担も最小限、無担保・無保証人での調達が可能といった点がスタートアップ企業に大きなメリットをもたらします。
日本政策金融公庫の「挑戦支援資本強化特例制度」は、特に技術・ノウハウに新規性がみられるスタートアップ企業を支援対象としており、革新的なビジネスモデルを持つ企業の資金調達機会を提供しています。
借入返済に苦しむ企業の資金繰りを大幅に改善できる
既存の借入金の返済負担が重く、資金繰りに苦しんでいる企業にとっても、資本性劣後ローンは有効な解決策となる場合があります。既存の借入金を資本性劣後ローンに借り換えることで、毎月の返済負担を大幅に軽減できる可能性があります。
例えば、複数の金融機関から総額1億円の借入があり、毎月の返済額が合計200万円に及ぶ企業が、この借入を資本性劣後ローンに借り換えた場合。
赤字時には元金返済が猶予されることがあるため、毎月の返済額は利息分のみとなり、仮に金利が年5%であれば月々の支払いは約42万円程度に減少する可能性があります。(ただし、資本性劣後ローンの金利や契約条件は金融機関や企業の状況によって異なります。)
毎月の返済負担が大幅に軽減され、創出された余剰資金を運転資金や事業改善に活用できるといった利点の他に、金融機関の評価上、自己資本とみなされるため財務体質も改善するといったメリットがあります。
ただし、単に返済を先送りするだけでなく、借換えによって生まれた資金的余裕を活かして、事業構造の改善や収益力の向上に取り組むことが重要です。資本性劣後ローンは企業の財務体質改善と事業再生のための戦略的な選択肢として活用しましょう。
資本性劣後ローンの申込方法と必要書類
資本性劣後ローンは通常の融資よりも審査が厳格なため、申込準備は入念に行う必要があります。ここでは、日本政策金融公庫を例に申込方法と必要書類について解説します。
日本政策金融公庫への申込手続き
日本政策金融公庫の資本性劣後ローンの申込手続きは、以下のステップで進めていきます。
- 事前相談:まずは公庫の窓口に相談。資本性劣後ローンの概要や対象要件の確認を行います。
- 事業計画書の作成:認定支援機関の支援を受けながら作成するのが望ましいです。
- 必要書類の準備と提出:後述する書類を揃えて提出します。
- 面談・審査:担当者との面談では事業内容や返済計画について詳しい質問があります。
- 審査結果の通知:審査期間は概ね2週間~1ヶ月程度です。
- 契約締結と融資実行:条件に合意したら契約を締結し、融資が実行されます。
事前に十分な準備を行い、明確な事業計画と返済見通しを示すことで、審査通過の可能性は高まります。
申請に必要な書類と事業計画書のポイント
資本性劣後ローンの申請には、以下の書類が必要です。
- 基本的な提出書類
・借入申込書(日本政策金融公庫所定の様式) 事業計画書
・会社案内、パンフレットなどの事業概要資料
・法人の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・決算書(直近3期分)、税務申告書
・試算表(直近月のもの)
・納税証明書 ・代表者の住民票または住民票記載事項証明書
- 資金使途に関する書類
・設備資金の場合:見積書、カタログなど
・運転資金の場合:資金繰り表、売上予測資料など
・借換資金の場合:既存借入金の返済予定表など
事業計画書作成のポイントは以下の通りです。
- 現状分析と課題の明確化:現在の経営状況や業界動向を客観的に分析します。
- 目標設定と実現戦略:実現可能な具体的目標と戦略を明記します。
- 数値計画:借入期間中の売上高、費用、利益の予測を示します。
- 資金計画と返済計画:一括返済の原資をどう確保するかが重要です。
- リスク分析と対応策:計画通りに進まない場合のリスク対応も記載します。
認定支援機関の役割と活用法
資本性劣後ローン申請には、認定支援機関の関与が求められるケースが増えています。認定支援機関とは、税理士、公認会計士、中小企業診断士など国が認定した支援機関です。
主な役割:
- 事業計画策定支援
- 資金調達のアドバイス
- 事業再生計画の策定
- 金融機関との交渉サポート
効果的な活用のポイント:
- 早期相談:資金繰りが厳しくなる前に相談することが重要です。
- 情報開示:財務状況や事業課題など、必要情報を積極的に開示しましょう。
- 継続的関係:計画策定だけでなく、実行段階でも定期的に相談することで、早期に課題に対応できます。
認定支援機関との連携は、資本性劣後ローンの審査通過だけでなく、その後の事業改善にも大きく貢献します。
まとめ|資本性劣後ローンを活用して財務体質を強化しよう
資本性劣後ローンは、借入でありながら金融機関からは自己資本とみなされる特殊な融資制度です。期限一括返済方式により借入期間中は元金返済が不要で、業績連動型金利により赤字時は金利負担も抑えられます。債務超過の解消や大規模設備投資、スタートアップ支援、借入返済負担の軽減など、様々な場面で効果を発揮します。
一方で審査が厳しく、黒字化すると金利が上昇し、原則5年間は繰上返済ができず、満期時には一括返済が必要という注意点もあります。適切な事業計画の策定と返済見通しが重要です。中小企業の財務体質強化と持続的成長を実現するためのツールとして、資本性劣後ローンを上手に活用しましょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。