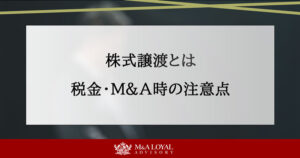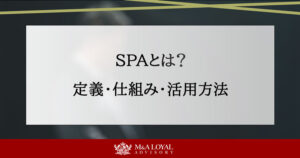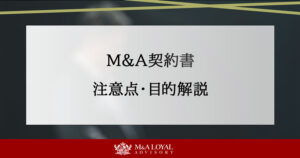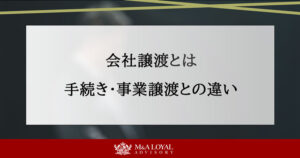株式譲渡の手続きを徹底解説|契約から税務まで全流れと注意点
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
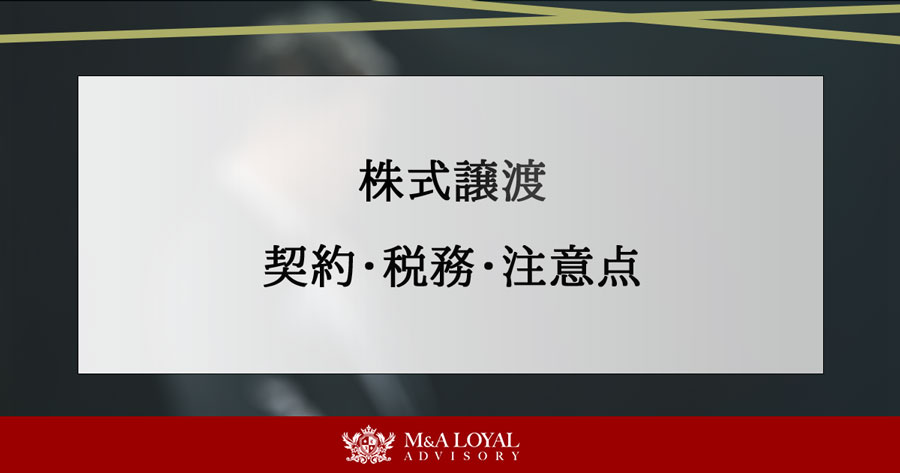
株式譲渡は、会社の経営権や出資比率を移転するうえで欠かせない重要な手続きです。特に、中小企業においては、親族や役員への承継、あるいは第三者へのM&Aを目的として実施されることが多く、法的・税務的な観点からも慎重な手続きが求められます。
しかし、実務では「株式譲渡契約書ってどこまで細かく書くべき?」「名義書換の手続きって会社でやるの?」「税金はどれくらいかかるの?」といった具体的な疑問が次々と浮かび、適切に処理できないままリスクを抱えてしまうケースも少なくありません。
本記事では、株式譲渡に関する基本知識から、手続きの流れ、契約書のポイント、税務処理、そして非上場企業ならではの注意点までを網羅的に解説します。経営者・財務担当者が安心して株式譲渡を進めるための実務ガイドとして、ぜひお役立てください。
目次
株式譲渡とは?その基本と種類
株式譲渡とは?定義と目的を押さえる
株式譲渡とは、株式会社の株主が自ら保有する株式を、他の個人や法人に対して譲渡することを指します。簡単にいえば「会社の所有権の一部を他者に引き渡す行為」であり、法律上は財産権の移転に該当します。
譲渡には「有償譲渡」と「無償譲渡」があり、金銭を対価として株式を引き渡す場合が有償、親族などに無償で引き継がせる場合が無償です。いずれの場合も、会社の所有構造が変わるため、会社経営に大きな影響を与える重要な行為となります。
株式譲渡が行われる主な目的
- 事業承継の一環として
- 経営者の高齢化により、親族(息子・娘・配偶者)や社内幹部(役員・従業員)に株式を引き継ぐケースが増えています。
- 第三者への会社売却(M&A)として
- 経営資源の集中や後継者不在を背景に、外部企業や投資家へ株式を売却する例も増加傾向です。
- 出資比率の再編や経営権調整として
- 株主構成を見直し、意思決定の円滑化を図るために株式譲渡が使われることもあります。
- 資金調達の手段として
- 個人資産の換金や経営者の資産形成のために、株式を第三者へ売却するケースもあります。
このように、株式譲渡は“経営権の移動”や“資本構成の再編”に直結するため、慎重かつ計画的な対応が必要です。
株式譲渡の2つの大別:譲渡制限株式と自由譲渡株式
株式譲渡の可否には、株式自体の性質(制限の有無)が大きく影響します。会社法上、株式会社が発行する株式は大きく以下の2種類に分けられます。
自由譲渡株式(上場企業に多い)
- 定款に譲渡制限がない株式は、株主の意思で自由に譲渡できます。
- 上場企業ではこの自由譲渡株式が基本で、株式市場を通じて売買されます。
- 第三者へ売却する際に、会社の承認を得る必要はありません。
譲渡制限株式(非上場企業に多い)
- 定款に「会社の承認が必要」と定められている株式は、譲渡制限株式となります。
- 中小企業や同族会社など、経営の安定性を重視する企業に多く見られます。
- 譲渡する際には、取締役会または株主総会の承認決議が必要です。
このような制限は、不適切な第三者が経営に関与することを防ぐ目的で設けられており、会社側にとってはガバナンス上の重要な仕組みです。
定款の確認が必須
譲渡制限があるかどうかは、会社の定款を確認すれば分かります。株式譲渡を検討する際には、まずは定款をチェックし、承認が必要かどうかを把握しておくことが非常に重要です。
M&A・事業承継との深い関係性
株式譲渡は、単なる所有権の移動にとどまらず、経営そのもののバトンタッチを意味します。そのため、M&Aや事業承継の場面では最も一般的かつスムーズな手法として広く活用されています。
株式譲渡によるM&A
- オーナー経営者が自社株式を第三者(同業他社・ファンド等)に譲渡することで、会社全体を売却する形になります。
- 「会社の法人格」や「許認可」「雇用契約」「事業資産」などがそのまま承継されるため、取引先や従業員への影響を最小限に抑えられる利点があります。
- 特に許認可業種(建設業・医療・介護など)では、株式譲渡によってライセンスを引き継ぐことが可能です。
株式譲渡による事業承継
- 親族(子・配偶者など)や社内の後継者(役員・従業員)へ株式を譲渡することで、会社の所有と経営を継続的に引き継げます。
- 「事業はそのまま、経営権だけが交代する」ため、事業継続性・従業員の雇用・取引の安定性を保つ点で有効です。
- 相続や贈与と絡む場合は、株式評価や税務対策も必要になります。
実務上よくある誤解と注意点
- 誤解①:「譲渡=すぐに経営権が移る」
→実際には、株主名簿の書換、株式譲渡契約書の締結、会社の承認など多段階の手続きが必要です。 - 誤解②:「自分の株式なんだから誰にでも譲渡できる」
→譲渡制限株式の場合は、会社の承認がなければ譲渡は無効となる可能性があります。 - 誤解③:「税金は売却益にしかかからない」
→贈与や相続との複合的なケースでは、贈与税・相続税・譲渡所得税のいずれか、あるいは複数が課税対象になります。
こうした誤解を防ぎ、適切な手続きを進めるには、早い段階で専門家のサポートを受けることが望ましいといえます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式譲渡の手続きフロー【全体像】
株式譲渡は一見シンプルな手続きに見えるかもしれませんが、実務上は複数のステップを慎重に踏む必要があります。特に非上場企業では、譲渡制限株式が多く、会社側の承認や法的な整合性を確保する手続きが不可欠となります。
この章では、株式譲渡の全体的な流れを5つの主要ステップに整理し、それぞれの実務的なポイントを詳しく解説していきます。
株主間での合意と基本条件の決定
最初のステップは、株主間で譲渡条件について明確な合意を形成することです。具体的には、「誰に」「いくらで」「いつ譲渡するか」を中心に、譲渡条件を詳細に詰めていきます。
譲渡の対象株式数や価格はもちろん、譲渡実行日、支払方法(現金一括・分割・預り金など)、売買後の議決権構成や役員体制への影響まで検討が必要です。特に非上場株式の場合、市場価格が存在しないため、純資産法や類似業種比準法などを用いて公正な評価を行い、その金額に基づいた交渉が求められます。評価に不安がある場合は、第三者である公認会計士や税理士に株価算定を依頼することが一般的です。
株式譲渡契約書の作成
株主間で条件が合意されたら、その内容を文書化するための株式譲渡契約書を作成します。契約書には、譲渡株式の種類・株数・譲渡価格・支払方法・譲渡実行日などの基本情報に加えて、譲渡対象株式が瑕疵のないものであることを確認する「表明保証」、譲渡後の義務や秘密保持、紛争時の解決手段(裁判所の管轄や準拠法)などを記載します。
株式譲渡契約書は、譲渡後にトラブルが生じた際の重要な証拠となるため、可能な限り弁護士や専門家のチェックを受けた上で作成することが推奨されます。とくにM&Aを目的とした譲渡の場合、買収監査(デューデリジェンス)の結果を踏まえた内容にする必要があります。
会社による承認手続き(譲渡制限株式の場合)
非上場会社で譲渡制限株式が存在する場合、株式の譲渡には会社の承認が必要となります。どの機関が承認権限を持つかは定款によって異なり、一般的には取締役会、または株主総会が承認機関とされています。
譲渡を希望する株主は、まず会社に対して譲渡承認請求書を提出します。その後、承認機関が審議を行い、譲渡を認めるか否かを決議します。決議結果は書面で通知され、正式な承認をもって、株式の譲渡が可能になります。なお、会社が承認しない場合は、会社自身が買い取りの相手先を指定する「会社買受制度」が適用されることもあります。
承認手続きの時期や内容については、譲渡を予定している株主と会社側で事前に十分なすり合わせを行い、誤解や遅延を防ぐことが肝要です。
名義書換と株主名簿の変更
会社の承認が得られたら、次に行うのが名義書換です。これは、会社が管理している株主名簿上の名義を、旧株主(譲渡人)から新株主(譲受人)へと変更する手続きです。
名義書換には、通常、株式譲渡契約書の写しや譲渡人・譲受人の署名押印のある書類、株券(発行されている場合)、株主名簿変更届などが必要となります。
名義書換が完了しなければ、譲受人は会社法上の株主として認められず、株主総会での議決権行使や配当受領などの権利行使ができません。譲渡契約の締結後は速やかに名義書換を行い、会社側にも正式な記録が残るようにすることが重要です。
税務申告と登記の要否
株式譲渡が完了すると、譲渡人は譲渡益が発生した場合に、税務上の申告が必要となります。具体的には、譲渡によって得た利益(譲渡所得)に対して、所得税と住民税が課されます。翌年の確定申告にて、譲渡収入や取得費用などを適切に計算し、申告を行わなければなりません。
一方で、譲受人には通常課税は発生しませんが、著しく低い価格での譲渡が行われた場合は、贈与とみなされて贈与税の対象になる可能性があります。また、親族間の譲渡や事業承継目的での譲渡では、相続税評価や資産移転計画にも注意が必要です。
なお、株式譲渡そのものについては、原則として登記義務はありません。ただし、株式譲渡を伴って役員変更や増資などが同時に行われた場合は、別途登記が必要となる場合があります。名義変更が社内の株主名簿に反映されていれば、通常の株式譲渡手続きとしては問題ありません。
このように、株式譲渡は複数の段階を経て進められ、それぞれに法的・実務的なポイントが存在します。ひとつでも手続きに不備があると、譲渡そのものが無効になったり、税務上の否認リスクを招いたりするため、慎重な対応が求められます。
株式譲渡契約書の作成ポイント
株式譲渡契約書は、株式譲渡に関する当事者間の合意を明文化した、法的に重要な契約書です。後々のトラブルを防ぐためにも、契約書の作成は形式的に済ませるのではなく、実務的・法的な観点からしっかりと整備する必要があります。本章では、株式譲渡契約書の基本構成から各条項の意味と注意点まで、実務に即した視点で詳しく解説します。
株式譲渡契約書の基本構成
株式譲渡契約書は、以下のような構成で作成されるのが一般的です。
- 表題・日付・当事者情報
→「株式譲渡契約書」という表題のもと、契約締結日と当事者(譲渡人・譲受人)の氏名または法人情報を記載します。 - 前文(背景説明)
→「当事者間で合意が成立したため、本契約を締結する」といった前提説明を簡潔に記載します。 - 契約条項(以下、主要条項を解説)
契約書に含めるべき主要条項と注意点
(1)譲渡対象株式とその数
譲渡する株式の種類・株数・発行会社名を明確に記載します。例えば「甲は、乙に対し、株式会社◯◯の普通株式○○株を譲渡する」といった記述が基本です。株式が複数種類ある場合(種類株式制度を採用している場合)は、種別も明記します。
(2)譲渡価格と支払方法
1株あたりの価格、合計譲渡金額、支払い期日、支払い方法(現金、銀行振込など)を明示します。価格決定の根拠(純資産価額方式や類似業種比準方式など)も契約書内に記載しておくと、税務上のトラブルを回避しやすくなります。
また、分割払いや条件付き支払い(アーンアウト)などを用いる場合は、条件とスケジュールを詳細に記載しておく必要があります。
(3)譲渡実行日と効力発生日
契約書の締結日と、実際に株式の譲渡効力が発生する日が異なる場合があります。たとえば「2025年10月1日をもって、乙に譲渡する」といったように、効力発生日を明確にしましょう。
この効力発生日は、株主名簿の名義変更時期や、議決権行使の基準日にも関わってくるため、非常に重要です。
(4)表明保証条項(Reps & Warranties)
譲渡人が譲渡する株式に関して、次のような事項が真実かつ正確であることを保証する条項です。
- 株式が譲渡人に正当に帰属していること
- 担保権や質権などが設定されていないこと
- 契約締結・履行に必要な権限を有していること
- 他に譲渡制限等の障害がないこと
この条項は、万が一後から瑕疵や権利トラブルが発覚した際の責任範囲を定めるための重要な条文です。
(5)誓約条項(Covenants)
譲渡人・譲受人双方が契約期間中または譲渡後に守るべき義務について定めます。よくある内容としては以下の通りです。
- 秘密保持義務(契約内容や会社情報の非公開)
- 競業避止義務(同業への参入制限)
- 引継業務への協力義務(従業員・取引先との引継)
これらの義務は、譲渡後の企業価値の維持や円滑な経営移行のために極めて重要です。
(6)解除条件と違約金
万が一、支払いの遅延や義務違反があった場合に、契約を解除できる条件と、解除に伴うペナルティ(違約金)についても定めておきましょう。譲渡人側が契約を履行しない場合、株式の譲渡が無効となるケースもあるため、法的責任の範囲を明確にすることが求められます。
(7)準拠法および裁判管轄
契約に関する紛争が生じた場合、どの国の法律を適用するか(通常は「日本法準拠」)や、裁判を行う裁判所(たとえば「東京地方裁判所」)を明記します。これにより、後々の紛争時に無用なトラブルを防ぐことができます。
実務でよくあるミスと対処法
曖昧な記載や抜け漏れ
たとえば「金額を未記載のまま押印してしまった」「支払期日の記載がない」といった形式的なミスが、後の紛争や未回収トラブルにつながることがあります。テンプレートを流用するだけでなく、個別案件に応じたカスタマイズが不可欠です。
署名・押印の不備
契約書の正本には、当事者全員の署名・押印が必要です。法人の場合は会社実印の押印と、代表者の氏名記載が求められます。PDF上の電子署名だけで済ませる場合もありますが、税務や裁判対応を見据えて原本を残しておくことが望ましいです。
事後に契約書を作成するケース
ときに「株式はすでに移転したが、契約書がない」という事後対応になることがあります。この場合、税務署に正当な譲渡を説明することが困難になったり、株主間のトラブルに発展する恐れがあります。契約書は必ず譲渡前に作成・締結しておくべきです。
株式譲渡契約書は、単なる売買契約書ではなく、将来の税務・法務・経営に直結する重要なドキュメントです。専門的な知見を活かして丁寧に設計し、トラブルの芽を事前に摘んでおくことが、安心・安全な株式譲渡の第一歩となります。
株式譲渡の税務と評価
株式譲渡において、税務と評価は最も専門的かつトラブルが発生しやすい領域です。特に非上場企業の株式では市場価格が存在しないため、適正な株価評価を行う必要があり、その結果が譲渡価格や課税額に大きな影響を与えます。本章では、譲渡時に発生する税金の種類とその計算方法、そして非上場株式の代表的な評価手法について詳しく解説します。
株式譲渡益にかかる税金(譲渡所得)
株式を売却して利益が出た場合、その譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。上場・非上場に関わらず、個人が株式を売却した際には、以下のような税金が発生します。
- 所得税:15.315%
- 住民税:5%
- 合計:20.315%(申告分離課税)
譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価額 −(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費:購入時の株式取得価格(贈与や相続の場合は評価額を基準)
- 譲渡費用:株価評価費用、専門家報酬、契約書作成費など
上場株式の場合は証券会社を通じて自動的に税金が徴収されますが、非上場株式の譲渡は、原則として確定申告が必要です。売却益があるにも関わらず申告しないと、税務署からの指摘や追徴課税の対象となります。
株式の評価方法(非上場株式の場合)
非上場株式の評価では、客観的かつ合理的な方法で株価を算定しなければなりません。特に譲渡人と譲受人が親族関係にある場合や、税務署の監視が入りやすいケースでは、適正な評価を怠ると贈与とみなされて追加課税を受ける恐れがあります。
国税庁が定める主な評価手法は以下の2つです。
(1)類似業種比準方式
上場企業の財務指標(売上高・利益・純資産等)と対象企業の指標を比較して評価する方法です。対象企業が事業規模・利益率の面で比較的安定している場合に適用されます。
- メリット:市場性に近い価格を算出できる
- デメリット:比較対象となる上場企業の選定が主観的になりがち
(2)純資産価額方式
対象企業の貸借対照表上の資産・負債を時価ベースで評価し、純資産の合計を株数で割って1株あたりの価値を算定する方法です。
- メリット:小規模企業や赤字企業にも適用可能
- デメリット:含み損益の調整や資産再評価の手間がかかる
実務ではこれら2つの方式を組み合わせて評価する併用方式や、中小企業特有のケースに応じて配当還元方式を用いることもあります。評価手法の選定や実行には、公認会計士や税理士の支援が必須といえるでしょう。
相続税・贈与税との関係と注意点
株式譲渡は税務上、単なる売買ではなく、場合によっては贈与や相続とみなされるケースがあります。とくに親族間で時価よりも著しく低い価格で株式を譲渡した場合、みなし贈与として贈与税の対象になる可能性があるため注意が必要です。
贈与とみなされるケース
- 無償で株式を譲渡した
- 時価評価が1株5万円なのに、1株1万円で譲渡した
- 譲受人が未成年または被扶養者で、対価能力がない
このような取引では、贈与税の申告が必要になります。また、税務署は実勢価格や株価評価レポートをもとに適正価格かどうかを判断しており、明確な根拠のない低価格取引は否認されることがあります。
相続との違い
一方、被相続人が亡くなった際に株式を相続する場合は、相続税の対象となります。このときの評価額は「相続開始時点での時価」であり、非上場株式では国税庁の定める評価方式に従って評価する必要があります。
相続税評価との整合性も重要
たとえば、株式譲渡時に評価を大幅に低く見積もっていた場合、後日相続が発生した際に税務署から整合性を問われ、評価の妥当性が否定される可能性もあります。そのため、株式譲渡と相続・贈与の評価方針は一貫しておくべきです。
税務調査リスクと回避策
非上場株式の譲渡には税務調査のリスクがつきものです。税務署は過去の申告データや類似会社の情報と照合し、異常値がある場合には調査を行うことがあります。以下のような状況では特に注意が必要です。
- 近親者への譲渡
- 譲渡価額が評価額より著しく安い
- 短期間に複数回の譲渡がある
- 評価根拠が曖昧、または存在しない
こうしたリスクを回避するためには、以下の対応が有効です。
- 税理士による事前の税務レビュー
- 株価評価レポートの第三者作成
- 譲渡契約書や承認書類などの適切な保管
- 贈与・相続との整合性の確保
とくに第三者評価書を添付した確定申告は、税務署に対する証明力が高く、税務調査を回避または有利に進めるための有効手段となります。
譲渡制限株式と手続きの注意点【非上場企業向け】
非上場企業の株式譲渡では、ほとんどのケースで「譲渡制限株式」が関係します。これは会社の定款により、株式の譲渡に一定の制限(=会社の承認)が課されている株式のことです。特に同族経営や中小企業では、外部の第三者による経営介入を防ぐために譲渡制限が設けられており、譲渡手続きには慎重な対応が求められます。
本章では、譲渡制限株式の基本知識から、手続き時に注意すべきポイント、そして実務上よくある落とし穴とその対策までを詳しく解説します。
譲渡制限株式とは何か
譲渡制限株式とは、株主が自由に株式を第三者に譲渡できないよう、会社の承認を必要とする株式のことです。これは会社法第107条第1項に基づく制度で、株式会社は定款で定めることにより、株式の譲渡に対して一定の制限を設けることが可能です。
たとえば、以下のような定款規定が典型です。
「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を得なければならない。」
このような条文がある場合、株主が保有する株式を譲渡するには、会社側の事前承認が必須となります。承認が得られない場合、譲渡の効力が発生しないか、会社に買受義務が発生する可能性があります。
定款と承認機関の確認
譲渡制限株式が存在する場合、最初に行うべきは定款の確認です。会社法では、承認機関を以下のいずれかから選ぶことができ、定款で明示する必要があります。
- 取締役会設置会社:取締役会
- 取締役会非設置会社:株主総会または代表取締役
承認機関が不明確な場合や、定款に記載がない場合は、承認が無効になる恐れがあります。株式譲渡を予定している会社の定款は必ず事前に確認し、必要があれば定款変更手続き(特別決議)も検討すべきです。
また、譲渡制限の範囲(全株式に適用されるのか、一部の種類株式のみか)も定款で明確に定められている必要があります。
承認手続きの実務と書式
譲渡制限株式の譲渡を行う場合、次のような手続きが必要になります。
- 譲渡承認請求書の提出(譲渡人 → 会社)
- 承認機関(取締役会・株主総会)での決議
- 承認通知書の交付(会社 → 譲渡人・譲受人)
- 名義書換手続きの実施
これらのステップはすべて書面で行うことが推奨されます。特に承認決議の議事録と通知書は、後日の証拠として保管しておくべきです。
書式例:譲渡承認請求書
株式会社○○御中
譲渡承認請求書
下記の株式を譲渡したく、会社の承認をお願い申し上げます。
譲渡株式数:○○株
譲渡価格:○○円
譲受人氏名:○○○○
住所:○○県○○市~
記入日:2025年○月○日
署名:譲渡人氏名+印
承認機関で否決された場合、会社側には一定期間内に買受人の指定や会社による買取を行う義務が課されるため、形式だけで拒否することはできません。
実務での注意点と落とし穴
譲渡制限株式の譲渡においては、次のような“落とし穴”が頻繁に見られます。
① 名義書換だけ行い、承認を取っていない
→これは法律上無効な譲渡となる可能性があります。株主名簿に記載されていても、承認手続きが抜けていれば株主権を行使できないケースがあります。
② 定款に承認機関が明記されていない
→「誰が承認すべきか」が不明確になると、承認手続き自体が無効とされるリスクがあります。
③ 親族間の譲渡で承認を省略してしまった
→たとえ親子間であっても、譲渡制限株式であれば会社の承認が必要です。形式上の手続きを怠ると、税務上も法務上も問題が発生します。
④ 取締役会の議事録が未作成または不備
→口頭で承認しただけでは法的に証明できません。少なくとも簡易な議事録と承認通知書は必須です。
承認拒否された場合の対応
会社が譲渡を承認しない場合、譲渡人は譲渡を強行できませんが、その代わりに会社に買受人を指定する義務が生じます(会社法第139条)。
- 指定された買受人が提示された譲渡価格で買い取る
- 会社自身がその株式を買い取る(自己株式取得)
一定期間内にこれが実施されなければ、譲渡は自動的に承認されたものとみなされる可能性があります。この制度は、株主の譲渡の自由をある程度保障するために設けられています。
譲渡制限株式は、会社の経営を守る盾であると同時に、株主の財産処分に対する制限でもあります。制度を正しく理解し、承認手続きを慎重に進めることが、トラブルのない株式譲渡の鍵となります。
株式譲渡トラブル事例と実務対策
株式譲渡は法的に定められた手続きを踏めば完了するものですが、実務ではさまざまなトラブルが起こる可能性があります。特に非上場企業の株式譲渡では、名義書換の未完了、契約内容の曖昧さ、税務処理の誤りなどが原因で、譲渡人・譲受人・会社の三者間に不信感や紛争が生じるケースが後を絶ちません。
名義書換の不備による株主権の問題
典型的なトラブルのひとつは、「名義書換の不備によって株主権が行使できない」というケースです。株式譲渡契約書は取り交わされ、譲渡人・譲受人間で金銭の授受も完了しているにもかかわらず、会社への名義書換手続きが行われていないことがあります。この場合、譲受人が株主として議決権を行使したり、配当を受けたりすることができず、法的な株主とは認められません。
税務処理の誤りとその影響
次に多いのは、「税務処理の誤りによって追徴課税を受ける」というトラブルです。非上場株式を譲渡する際、適正な価格評価をせず、親族間で時価よりも著しく安い価格で譲渡を行った場合、税務署から“みなし贈与”として否認される可能性があります。たとえば、評価額が1株あたり5万円であるにもかかわらず、1万円で譲渡したとすれば、その差額が贈与と見なされ、譲受人に対して贈与税が課されます。
契約書の曖昧さによるトラブル
「契約書が曖昧でトラブルに発展した」という事例も少なくありません。口頭での合意や簡素な書面のみで契約を済ませてしまい、譲渡価格や支払条件、譲渡日、表明保証の範囲などが不明確なまま譲渡が進められることがあります。このような場合、後から「約束した金額と違う」「支払いが遅れている」「株式に瑕疵があった」などの問題が発生した際に、いずれの主張が正しいかを証明する手段がなく、深刻な紛争に発展する恐れがあります。
譲渡制限株式での承認手続きの重要性
さらに見落とされがちなトラブルとして、「譲渡制限株式で承認手続きを怠った」事例があります。非上場企業では、株式の譲渡には会社の承認が必要な場合が大半です。それにもかかわらず、譲渡人・譲受人の間でのみ契約を結び、会社に報告も承認請求も行わないまま名義書換を進めてしまうと、その譲渡自体が法的に無効とされるリスクがあります。
株式譲渡に伴うトラブルは多岐にわたりますが、その多くは事前の備えと丁寧なプロセス管理によって未然に防ぐことができます。契約・承認・名義書換・税務といった各段階でのチェック体制を整え、専門家のサポートを得ながら慎重に進めることが、円滑な譲渡と信頼関係の維持につながります。
株式譲渡を成功させるための専門家活用術
株式譲渡における基本的な注意点
株式譲渡は、会社の所有権や経営権に直接関わる重大な手続きです。そのため、法的・税務的な整合性や契約内容の精緻さが求められ、経験の浅い当事者だけで進めようとすると、後々トラブルを引き起こす可能性が非常に高くなります。実際に、株式譲渡に関する紛争の多くは「契約書の不備」「税務処理のミス」「承認手続きの怠慢」といった基本的な確認不足が原因となっています。こうしたリスクを避け、安全かつ効率的に譲渡を完了させるためには、専門家の力を借りることが不可欠です。
専門家の役割と依頼のタイミング
この章では、株式譲渡に関わる専門家の種類とその役割、依頼のタイミング、そして費用感や選定のポイントまでを、実務的な視点から整理してご紹介します。まず、株式譲渡に関与する主な専門家としては、M&Aアドバイザー、公認会計士・税理士、弁護士の3つが挙げられます。それぞれの専門分野と担う役割は異なり、案件によっては複数の専門家が連携して対応にあたることが一般的です。
M&Aアドバイザーの役割
M&Aアドバイザーは、株式譲渡に関する交渉の窓口となり、売り手・買い手双方の調整役を担います。中小企業の事業承継や第三者への株式売却においては、まずこのアドバイザーが全体の進行管理を担い、スケジュールや条件面の調整を主導します。特に、候補先の選定や条件交渉、基本合意書(LOI)の取り交わしなど、交渉面における実務を得意としています。案件によっては、財務や法務の専門家と連携しながら、株式譲渡契約の設計・条件検討、クロージングの調整までを一括してサポートしてくれる場合もあります。経験豊富なアドバイザーに依頼することで、相手方との信頼構築がスムーズに進むだけでなく、全体像を見据えたアドバイスが得られる点が大きなメリットです。
公認会計士・税理士の役割
次に、公認会計士・税理士は、譲渡株式の価格評価および税務処理に関わる重要な専門家です。特に非上場株式の場合、客観的な市場価格が存在しないため、税務署に認められる適正な株価を算定する必要があります。この際、会計士や税理士は、会社の財務諸表や業績・資産内容をもとに、純資産価額方式や類似業種比準方式を用いて評価レポートを作成します。これが譲渡価格の根拠となり、税務調査時の立証資料として大きな意味を持ちます。また、譲渡益課税、贈与税・相続税の回避策、分割払い時の税務影響、役員退職金との兼ね合いなど、多面的な税務観点からのアドバイスが得られる点も重要です。特に親族間での譲渡や、持株会社を通じた株式移転を検討している場合には、早い段階で税理士に相談することが成功の鍵となります。
弁護士の役割
最後に、弁護士は、株式譲渡契約書の作成およびリーガルチェックを担います。契約書には、株式数や価格、支払条件だけでなく、表明保証、誓約義務、解除条項、紛争解決条項など、多くの法的リスクが関わります。経験の浅い当事者同士でテンプレートを使い回すだけでは、重要なリスクを見落とす可能性があります。特に、複数株主が関与する案件や、M&Aを目的とした外部企業への譲渡、または買い手にファンドや外国法人が含まれるような複雑なケースでは、契約リスクの洗い出しと調整交渉が不可欠です。弁護士に依頼することで、契約内容が法的に有効であることを担保し、万が一のトラブル時にも自社の立場を守ることができます。
依頼のタイミングと費用感
こうした専門家への依頼タイミングは、「譲渡を検討し始めた段階」からが理想です。特に、以下のような状況に該当する場合は、できるだけ早期に相談を始めましょう。
・初めて株式を譲渡する
・価格の妥当性に不安がある
・譲受人が親族・役員である
・会社に譲渡制限が設けられている
・契約書をどう作ればよいか分からない
・税金がどれだけ発生するか不明
上記の状況において、早い段階で相談しておくことで、必要な準備(定款の見直し、評価レポートの取得、社内決議のスケジュール調整など)を余裕を持って進めることができ、全体の進行が非常にスムーズになります。
費用については、専門家・企業ごとに異なりますが、目安として以下の通りです。
・M&Aアドバイザーは着手金50万円~、成功報酬は譲渡額の3~5%程度
・税理士・会計士は株価評価報酬10万円~30万円程度、顧問契約での月額対応もあり
・弁護士は契約書作成10万円~、法務アドバイザリーは月額契約またはタイムチャージ制
専門性や案件の規模に応じて金額は変動しますが、後々のトラブル防止や節税効果を考えれば、費用対効果は十分に見合う投資といえるでしょう。
株式譲渡は、法律・税務・交渉が交差する非常に繊細なプロセスです。信頼できる専門家と連携しながら進めることで、ミスを防ぎ、最適な形での譲渡が実現します。自社に合った体制を整え、安心して未来にバトンを渡すためにも、外部のプロフェッショナルを有効に活用しましょう。
まとめ|株式譲渡の手続きは正しい段取りと専門家選びがカギ
株式譲渡は、単なる所有権の移転にとどまらず、会社の経営権・資本構成・将来のビジョンに大きく影響を与える重要なプロセスです。とりわけ非上場企業の場合、市場価格のない株式をどのように評価し、誰に、どのような条件で譲渡するかによって、企業の安定性や後継体制が大きく左右されます。
本記事では、株式譲渡に関わる一連の流れ──定義や基本概念、手続きの各ステップ、契約書の注意点、税務と評価のポイント、譲渡制限株式の対応、トラブル事例、そして専門家の活用術──を網羅的に解説してきました。
重要なポイントは以下のとおりです。
- 株式譲渡は段階的に進めるべき法的プロセスであり、特に非上場株式では定款確認や承認手続きが不可欠であること
- 適切な株価評価と税務処理を怠ると、後から追徴課税やトラブルに発展するリスクが高いこと
- 契約書の曖昧さや名義書換の不備は、株主権や責任の所在をめぐる深刻な問題になり得ること
- M&Aアドバイザー・税理士・弁護士といった専門家の協力を得ることで、リスクを抑えながら安全に譲渡を進められること
特に、中小企業のオーナー経営者にとって、株式譲渡は「引退」や「世代交代」の節目にあたる人生と事業のターニングポイントです。だからこそ、法務・税務・感情のすべてに配慮した慎重な意思決定が求められます。
事前の段取りさえ間違えなければ、株式譲渡は経営の未来を切り拓くチャンスにもなります。逆に、基本的なルールや専門的な視点を軽視すれば、小さなミスが将来に大きな問題として残ることもあるでしょう。
譲渡を検討している段階であっても、早い段階から専門家に相談し、全体像を把握したうえで進めることで、譲渡プロセスは驚くほどスムーズになります。会社の未来、そして自分自身の将来設計のためにも、今こそ「正しい段取り」と「信頼できる専門家選び」が問われます。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。